\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

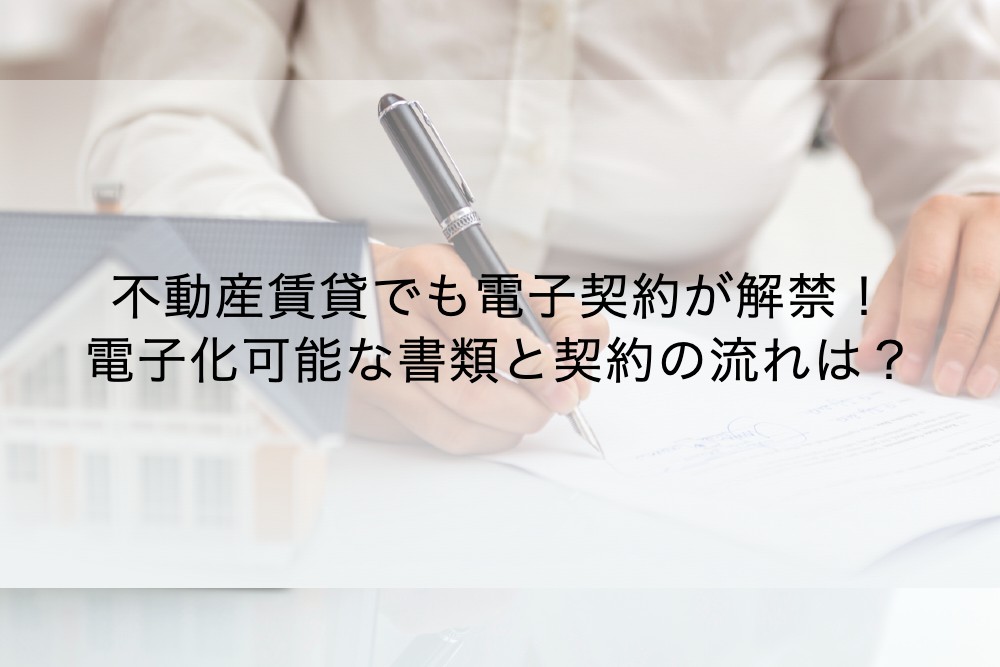
2022年5月、宅地建物取引業法(宅建業法)・借地借家法の改正法が施行されました。不動産賃貸の仲介業を営む方の中には、今回の法改正に注目している方も多いのではないでしょうか。電子契約の全面解禁によって、不動産業界の常識が大きく変わろうとしています。
ここでは、不動産賃貸における電子契約の基本や電子契約を導入する際のメリット、流れについて解説します。将来的に電子契約の導入を検討している方は、ぜひご一読ください。
電子契約とは、電子データで作成した契約書を用いて契約を締結することです。
そもそも契約時に契約書を作成する目的は、契約の合意内容を文書に記し、契約当事者がその内容に合意した旨をしっかりと記録に残すためです。万が一、トラブルが生じた場合、証拠として契約書が用いられます。
従って、電子データで作成した契約書は、紙媒体で作成した契約書と同等の証拠力が認められることが重要となります。そのための具体的な方法として、契約書が正式な文書である旨を証明するための「電子署名」や文書が改ざんされていない旨を証明するための「タイムスタンプ」などがあります。
不動産賃貸の取引においては、従来、宅建業法や借地借家法で各種書類の書面交付が義務付けられており、紙媒体での契約締結が一般的でした。しかし、2022年5月18日に施行された改正法によって、電子データで作成した契約も締結が可能になりました。
不動産賃貸で電子契約が解禁された背景には、「デジタル改革関連法」や「電子帳簿保存法」といった法律の改正や、お客さまのニーズの多様化が影響しています。
ここでは、各法改正の概要や不動産業界への影響、電子契約が解禁された背景について解説しましょう。
2021年5月19日に公布された「デジタル改革関連法」によって、行政や民間企業の手続きに必要だった押印の廃止、各種書面の交付に関する法律の見直しが行われました。このような改革が行われた理由の一つに、コロナ禍で日本のデジタル社会の遅れが顕在化したことが挙げられます。
コロナ禍の混乱の中で「押印や書類作成のために出社せざるを得ない」「お客さまからオンライン内見などの要望が増えた」といった経験をした方もいるのではないでしょうか。デジタル社会の遅れを認識した国や民間企業は、デジタル改革関連法の成立を機に、ITを活用した仕組みを構築しているところも多いです。
また、多様なサービスが混在する昨今の日本では、お客さま一人一人のニーズに合わせた対応が求められます。法改正の影響で、不動産賃貸における電子契約のニーズも徐々に広がるでしょう。
電子契約の導入には、一定のコストや労力を要します。どのサービスを利用するべきかお悩みの方には「電子印鑑GMOサイン」がおすすめです。「電子印鑑GMOサイン」は、不動産業界をはじめ350万社以上の事業者にご利用いただいている電子契約サービスです。
コストパフォーマンスの良さが強みであるため、導入コストを抑えたい方や電子契約サービスの導入がはじめての方に、ぜひご検討いただきたいサービスです。
国土交通省「不動産取引書時の書面が電子書面で提供できるようになります」
デジタル庁「デジタル改革のこれまでの経緯について」
厚生労働省「デジタル改革関連法の全体像(令和3年5月19日公布)」
電子帳簿保存法とは、従来、紙媒体での保存が義務付けられていた帳簿書類について、電子データでの保存を可能にすることなどを定めた法律です。電子帳簿保存法の対象となる書類は、契約書・請求書・領収書といった取引に関する書類です。
同法律では、2021年度に抜本的な改正が行われました。2022年1月1日以降は各種書類を電子データで保存する際の要件が緩和されたことにより業務負担が軽減され、多くの企業が対応しやすくなっています。例えば、これまでは電子データで帳簿書類を保存するために、税務署長の事前承認が必要でしたが、2022年1月1日以降は事前承認が不要になりました。
デジタル改革関連法による一般的な手続きのデジタル化に加えて、税務に関する帳簿書類の保存もデジタル化が進んでいます。帳簿書類の電子データ保存が普及するにつれて、電子契約を導入する企業も増えるでしょう。
国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」
国税庁「教えて!! 令和3年度改正 電子帳簿保存法」
国税庁「【経理のデジタル化】はじめませんか、電子帳簿保存・スキャナ保存」
不動産賃貸の仲介業者が注視すべき電子契約に関する法律は、主に「宅地建物取引業法(宅建業法)」と「借地借家法」です。従来、不動産賃貸の仲介業者が作成する以下の書類は、紙媒体での交付が前提でした。
また、契約締結前に行う重要事項説明は、対面で行うことが前提でした。しかし、2017年10月からは紙媒体での書面を交付した上で、オンラインによる説明が可能になりました。
そして、今回(2022年5月18日)に施行された改正法では、紙媒体での書面交付に代えて電磁的方法による電子書面交付が可能になっています。電磁的方法とは、PDFなどの電子データで作成した電子書面を電子メールやインターネット上でのアップロード、USBメモリなどで相手方に交付する方法です。
・法務省「借地借家法の改正について(掲載元)」
・e-Gov法令検索「宅地建物取引業法(第35条 第1項・8項・9項、第37条 第1項・4項・5項)」
・e-Gov法令検索「借地借家法(第22条、第38条 第1項・2項・3項・4項)」
今回の法改正は、不動産賃貸の重要書類に大きく関わりがあります。法改正によって電子化が可能になった重要書類の具体例は、以下の通りです。
| 書類 | 関連する法律(条項) |
|---|---|
| 定期建物賃貸借契約書 | 借地借家法(第38条 第2項) |
| 定期建物賃貸借契約の事前説明書 | 借地借家法(第38条 第4項) |
| 重要事項説明書 | 宅建業法(第35条 第8・9項) |
| 賃貸契約書 | 宅建業法(第37条 第5項) |
不動産賃貸の仲介業者が電子契約を導入する場合、仲介業者・お客さまの双方にメリットがあります。ここでは、電子契約を導入するメリットを解説しましょう。
不動産賃貸の仲介業者が電子契約を導入すると、お客さまの時間的負担を軽減できます。昨今、不動産ポータルサイトや不動産会社の公式サイトが充実しており、お客さまがインターネット上で部屋を探すケースが増えています。初回の来店時には、希望の物件が決まっているという方も多いのではないでしょうか。
また、現地を訪れずにオンライン内見のみで物件を決める方も一定数います。契約手続きに十分な時間を取れない方の中には、手続きのためだけに不動産会社を訪問することを煩わしく感じる方もいるでしょう。
電子契約を導入し、相談から契約締結までの手続きをオンラインで完結できれば、お客さまの時間的負担を軽減できます。
リクルート「2021年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)(p4、8(ページ下の数字))」
電子契約を導入すると、お客さまのコスト削減にもつながります。例えば、遠方にお住まいの方は片道の交通費のみでも、高額な費用となるでしょう。一度のみならず、内見や契約手続きのために複数回の訪問が必要であれば、お客さまの負担も大きくなります。
不動産賃貸の仲介業者が電子契約を導入することで、お客さまにかかる余計なコストを削減できます。
契約書を紙媒体で作成する場合、作成した電子データの出力や記名・押印といった事務作業が発生します。説明のみをオンラインで行うIT重説※の場合、遠方のお客さまへの書類を発送する手間もかかるでしょう。電子契約を導入すれば、書類作成にかかる全ての作業をオンラインで完結できます。
※IT重説のための書面の交付方法には、紙媒体の書面を事前送付する方法と電磁的方法で送付する方法があります
国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル(p28、29(各ページの下に記載されたページ数))」
契約書や請求書、見積書など、日々の業務では非常に多くの書類を作成します。そのような書類は一定期間の保管が義務付けられているため、全てを合わせると膨大な量になってしまいます。
「確認したい書類が見当たらず、時間を無駄にしてしまった」という経験がある方もいるのではないでしょうか。電子契約を導入すれば、オンライン上での保管が可能になります。ファイル名に日付・ユーザー名・書類名などを記載しておけば、書類を検索する手間を削減できるでしょう。
また、契約書などの書類を電子データで保管する場合、物理的なスペースが必要ない点もメリットです。
紙媒体での契約書に伴う事務作業の負担や管理の煩わしさから解放されるためには、電子契約サービスの導入が必要不可欠です。「電子印鑑GMOサイン」を導入して、業務効率化・コスト削減を目指してはいかがでしょうか。
不動産賃貸における電子契約の締結は、以下の事前準備を行った上で実施します。
電子契約の流れは以下5つのステップです。
STEP1:重要事項説明書・契約書のアップロード
STEP2:不動産賃貸業者による電子署名
STEP3:IT重説の実施
STEP4:入居者による電子署名
STEP5:契約の電子データをサーバーに保管
電子契約を締結する際の書類を電磁的方法で交付する場合、以下の要件を満たす必要があります。
国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」 p7、8、10、12、15(各ページの下に記載されたページ数)
政府が掲げるデジタル社会の推進によって、今後も電子契約を導入する企業は増えるでしょう。社会の変化に対応できるように、早めの準備をおすすめします。
電子契約の導入は、企業の業務効率化・コスト削減への近道です。導入によって社員が働きやすい環境づくりや自社の収益性UPを期待できる点は、大きな魅力といえるでしょう。
また、電子契約の導入はお客さまにとっても、スピーディーな契約締結が可能になる、交通費を節約できるといったメリットがあります。
「電子印鑑GMOサイン」では、セキュリティ対策が重要な不動産取引に適したプランをご用意しています。コストパフォーマンスの良いサービスとして多くの事業者にご利用いただいているため、導入を検討している方はお気軽にご相談ください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
