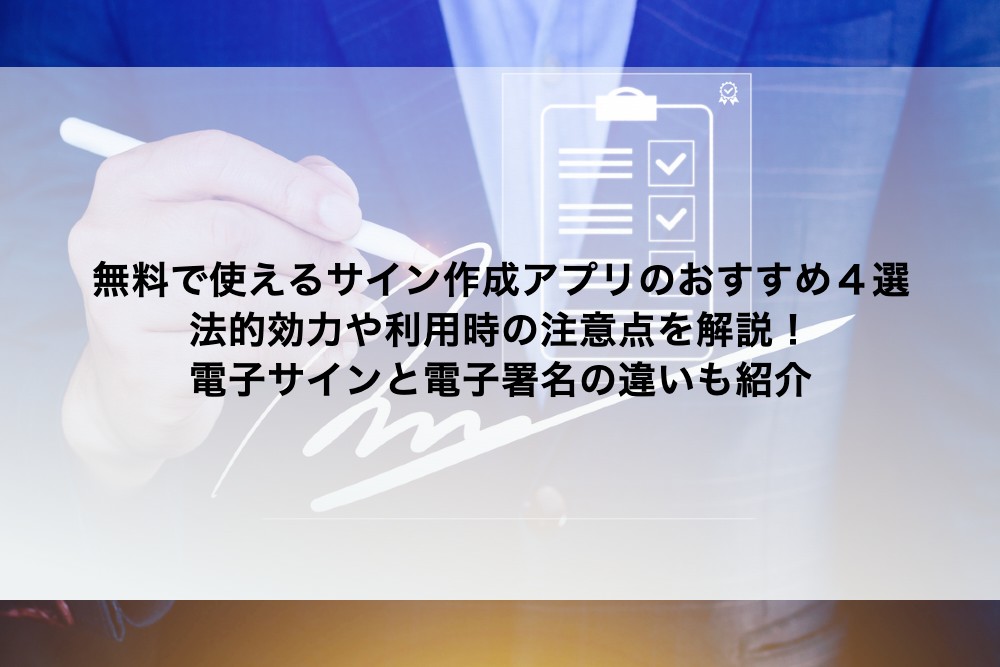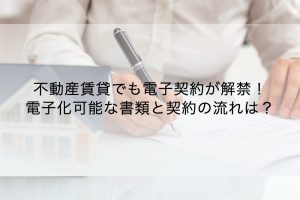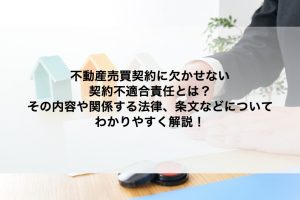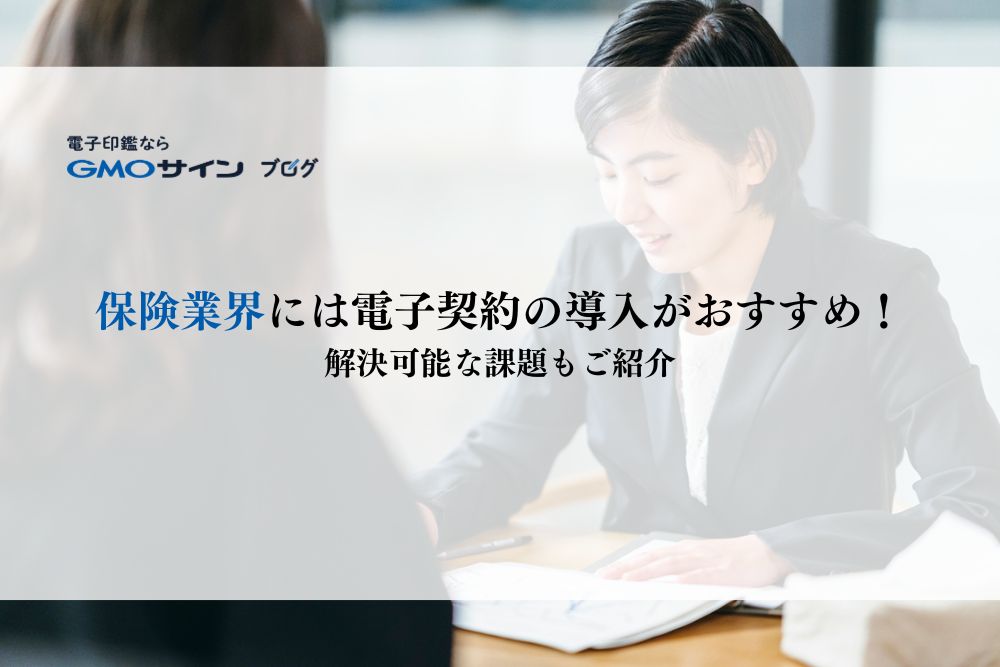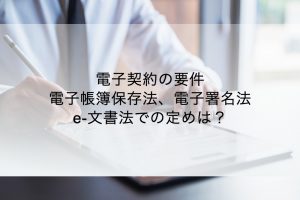2024年11月30日までのお申し込み限定で、GMOサインの「無料プラン」をご利用中の方が有料プラン「契約印&実印プラン」へプランアップしていただくと、お申し込み月を含めた2カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスですので、この機会をお見逃しなく!
コロナ禍によって、テレワークが推奨される中、「ハンコを押すために出社しなければならない」ということが大きく報道され、政府も企業もデジタル化が急務であると認識されるに至りました。
特に契約については、契約内容について証拠として保全する必要性があることから、これまでは書面で行われることがほとんどで、電子化の対応は遅れていました。そこで、今回は、電子契約をする場合の注意点と書面契約との違いなどについて解説します。
電子契約とは、契約について電子的な方法で管理するものです。契約内容をテキストエディターなどで作成して、PDF化し、それをメールなどで相手に送付して相互で確認し、合意が得られたら、電子署名するという流れが一般的です。
署名された電子契約は、サーバーやクラウドストレージで保管、管理されます。電子契約と書面契約との大きな違いは、電子契約には印紙が不要ということです。印紙税法は、契約の種類や金額によって税額が異なりますが、一般的に契約金額が大きくなればなるほど高額になります。印紙税は、電子契約には必要がないため電子契約にすると印紙税分のコスト削減ができます。
また、書面契約では、紙代、印刷代、郵送費などのコストが発生します。それに対し、電子契約は、パソコンの電気代と通信費は発生するかもしれませんが、仕事中はパソコンの電源を入れているのが通常ですし、ネット環境も常時接続しているでしょうから、実質的にコストはかかりません。ただ、電子署名に関しては、電子署名サービスを利用することになるので、そのサービスの利用料は発生します。
電子契約の代表的なメリットは、以下の通りです。
書面の契約書の場合、2通の契約書を郵送して、相手の記名・押印をしてもらい、1通を返信してもらう必要があります。つまり、早くても数日が必要なわけです。それに対し、電子契約は電子署名するだけなので、最短だと数秒で契約を締結することも可能です。
書面契約で必要な印紙が、電子契約では不要です。たとえば、企業が締結する大型契約ともなると、万単位の印紙税がかかります。この印紙税を支払わなくて良い点は大きなメリットでしょう。
書面契約の場合、ファイルなどに綴って保管しなければなりません。どこに何があるかを管理するために目録を作成するなどの手間もかかります。それに対し電子契約はサーバーやクラウドストレージで管理されるため、保管のスペースが必要なく、管理の手間もかかりません。また、ファイル名を適切に設定すれば検索も容易なので、契約書を確認したい場合でもすぐに探すことができます。
書面契約は、紙代、印刷代、郵送費などのコストが発生します。電子契約の場合には、電子署名サービスの利用料金以外は、ほとんどコストがかかりません。
契約書を紙で作る場合には、印刷して、製本、記名・押印するなど、事務的な労力がかかります。それに対して、電子契約は、パソコン画面の操作だけで処理が可能なので、労力が軽減されます。
契約書のような重要な書類は自宅に郵送するわけにはいきません。代表印なども会社にあるため、契約書に押印する場合、会社に出社する必要があります。一方、電子契約であれば自宅でも署名できますので、テレワークでも速やかに契約を締結できます。

メリットの多い電子契約ですが、メリットばかりではありません。導入にあたっては必ず注意点も把握しておきましょう。
電子契約を導入する場合、ワークフローの変更が必要になる場合があります。たとえば、これまでは、営業部門などで契約書を起案したら、法務部あるいは顧問弁護士などがリーガルチェックして、営業部門に戻し、上司の決裁を受けるという流れだとします。これが、電子契約になると、決済の手続きをどうするかなど、ワークフローの確認や必要に応じたワークフローの見直しが必要になります。また、契約に関する規定などがある場合、規定の改正も必要になります。
契約は相手があるものなので、一方の当事者が電子契約で行いたいと言っても相手から応じてもらえなければ成立しません。電子契約自体は、パソコンが使える環境なら決して難しいものではありませんが、契約の相手方は高齢者やパソコンをもっていない人もいるかもしれません。また、取引先の都合もあるので、電子契約を導入する場合には取引先にあらかじめ同意を得る必要があります。
契約をするのに本来書面は必要ないので、ほとんどのものは電子契約にできます。一方で、不動産に関する契約の一部(定期借地契約など)では、書面での作成が法令で義務付けられているため、電子化できません。ただし、これらも法律が改正されて、相手方の承諾が得られれば、電子化が認められることになりました。不動産に関する契約などは2022年5月までに施行される予定です。個別の法令によって規制がある場合があります。
ほとんどのものは電子契約できますが、たとえば、所得税法では契約書を保存しておく義務がありますが、電子帳簿保存法で、電磁的記録による方法でも保存することが認められています。
また、e-文書法は、国税関係だけでなく、多くの法定文書を電子化することを認めるものですが、「パソコンやプリンターで可読できるもの」などの一定の要件が課されています。
数多くの電子契約サービスがリリースされているため、自社の目的に合ったものを選ぶことが重要です。ここでは、電子契約サービスの選び方をお伝えします。
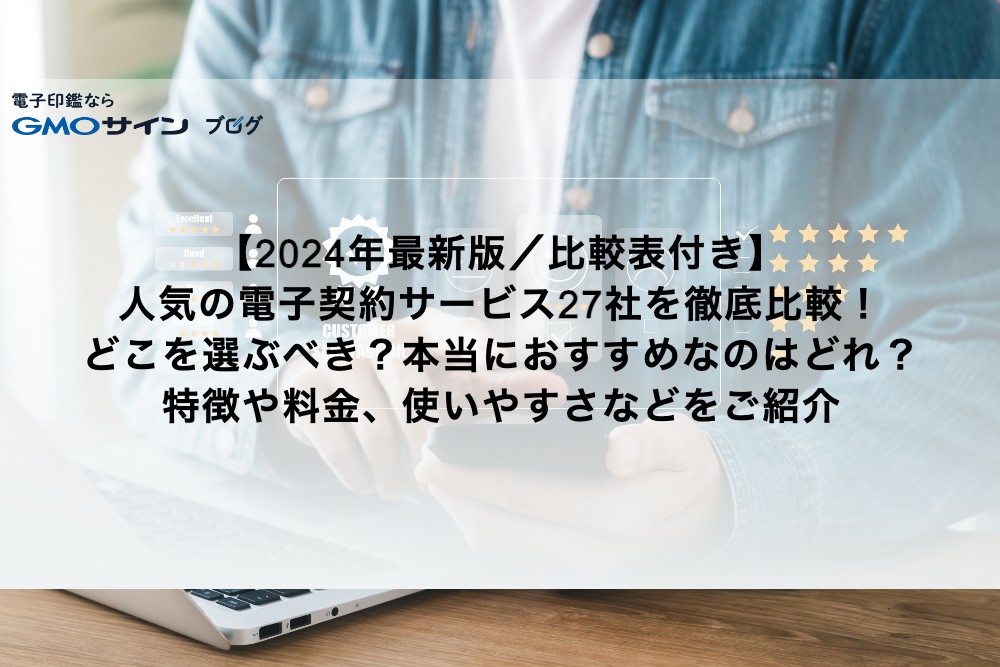
電子契約サービスは、月額利用料という形で料金が発生することが一般的なので、長期的な視点に立ってコストが高いかどうか判断する必要があります。もっとも、安いだけで、使い勝手が悪かったり、セキュリティが不十分だったりということでは困ります。求める機能と金額が見合っているかを確認しましょう。
電子契約が使いにくいと誰も使わなくなるので、使いやすいかどうかは重要なポイントです。
契約内容というものは機密事項が多く含まれているため、万が一にも外部に情報が漏れるようなことがあってはなりません。セキュリティ対策がしっかりしている事業者を選びましょう。
電子署名の方法には、「立会人型」と「当事者型」があります。電子契約サービスを選ぶ場合には、サービス会社が、立会人型なのか、当事者型なのか、あるいは、その両方を用意しているのかを確認してください。立会人型は簡便な点がメリットですが、なりすましのリスクがあります。一方、当事者型は立会人型に比べ信頼性が高いですが、手間や費用がかかることがあります。

電子契約を行う場合、相手に電子契約サービスを利用することについて同意を得なければなりません。相手先企業が使っている電子契約サービスであればスムーズに話が進むので、利用企業が多いサービスを選んだ方が、承諾してもらえる可能性が高まるでしょう。利用企業が多いということは、多くの企業で検討されて導入されているということなので、それだけ信頼できるともいえるでしょう。
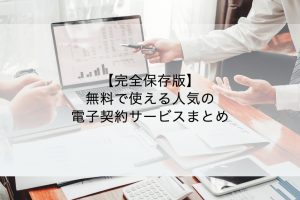
電子契約をする上での注意点、電子契約と書面契約の違い、電子契約のメリットなどを解説しました。一部、電子契約が認められない契約書もありますが、法律も電子化できるよう変わってきており、将来的には全て電子契約することができる時代もくるのではないかと思われます。
電子契約を導入していない企業は、これを機会に電子契約の導入について検討してみてはいかがでしょうか。「電子印鑑GMOサイン」は、導入企業数が40万社を突破し、導入実績数は国内No.1です。GMOサインは、立会人型・当事者型のどちらも選択でき、用途に合わせて使い分けることができます。セキュリティ対策もトップレベルなため、安心して利用できるでしょう。
2024年11月30日までのお申し込み限定で、GMOサインの「無料プラン」をご利用中の方が有料プラン「契約印&実印プラン」へプランアップしていただくと、お申し込み月を含めた2カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスですので、この機会をお見逃しなく!
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
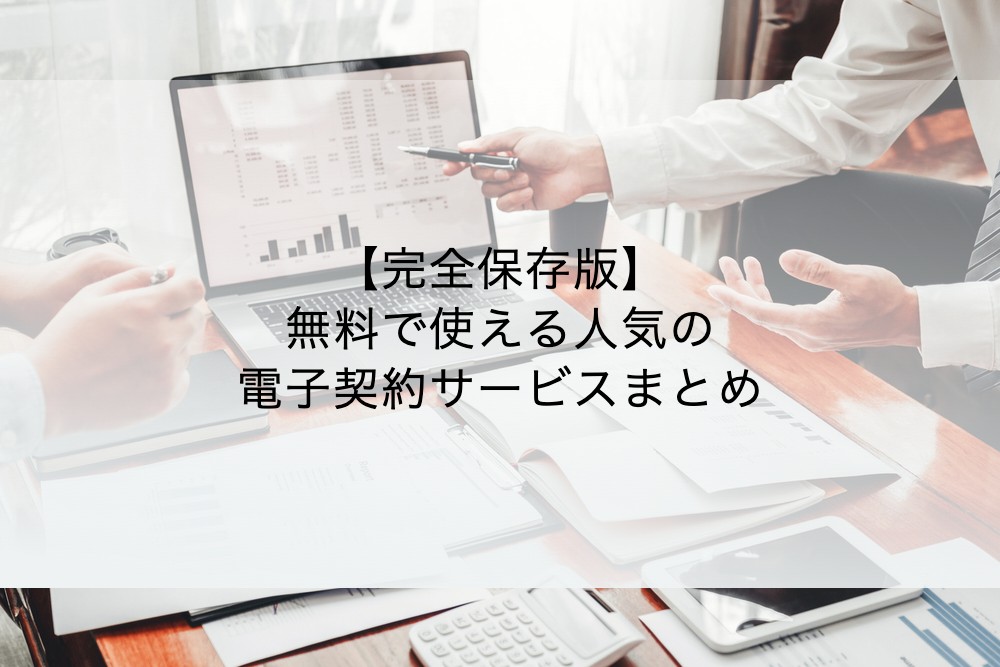
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
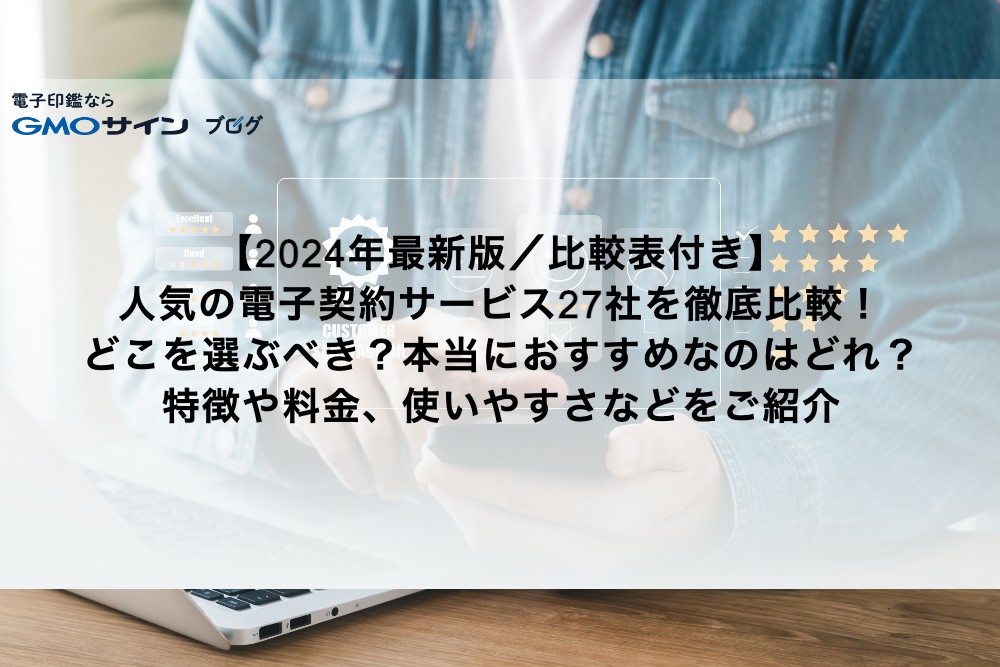
\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。