\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

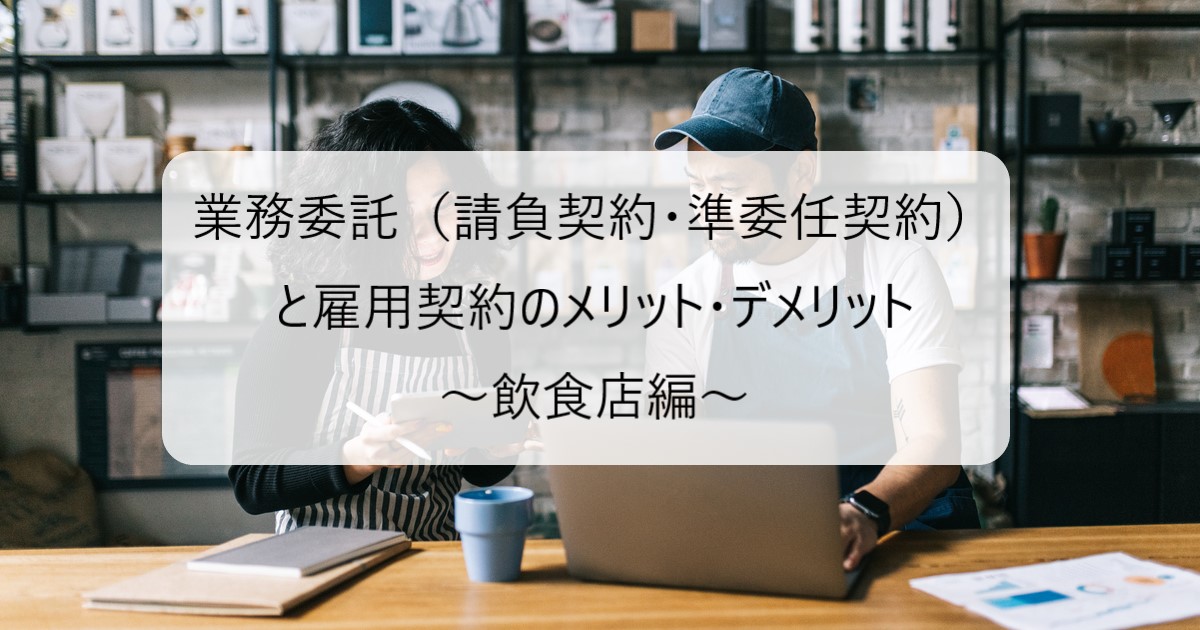
飲食店を経営している個人や企業にとって、事業の効率化などを求め「自分の経営しているレストランにおいてシェフ等と契約し、その店舗運営すべてを任せたい」などというニーズは世間では意外と高いようです。
このような場合、レストラン経営者であるオーナーとシェフ等との間の法律関係はどうなるのでしょうか?
このようなケースを一般的には「業務委託」などといいますが、法律上、雇用契約か業務委託契約のどちらに該当するのかの判断は、意外に難しいのです。しかし、どちらに該当するかによって法律で定められた義務やメリット・デメリットが異なるため、よく理解しておく必要があります。
今回は飲食業において人材を確保する際の契約形態として、雇用契約や業務委託契約などによる違いやメリット・デメリットについて解説します。
飲食店を開業するなどに際してオーナーが現場での働き手を直接雇うのか、それとも業務委託するのかによって当事者間の法律関係は大きく異なることになります。
このような場合における当事者の法律関係は、大きく次の2つに分けることができます。
・雇用契約
・いわゆる「業務委託契約」
それぞれに関して、少し詳しく見ていきましょう。
民法第623条では、雇用契約について、以下のように定めています。
民法第623条(雇用)
「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」
すなわち、雇用契約の成立要件は、
①労働者が使用者に使用されて労働すること
②使用者がその対価として賃金を支払うこと
となります。
オーナーと現場での働き手との間において上記要件を満たす合意が成立した場合には、両当事者間には雇用契約が成立することになります。そのため、当事者間の法律関係を判断する際には、雇用契約に関する法律の規定を確認することになります。
また、労働基準法や最低賃金法など企業(雇用者)と労働者との関係を規定する各種法律が適用されます。
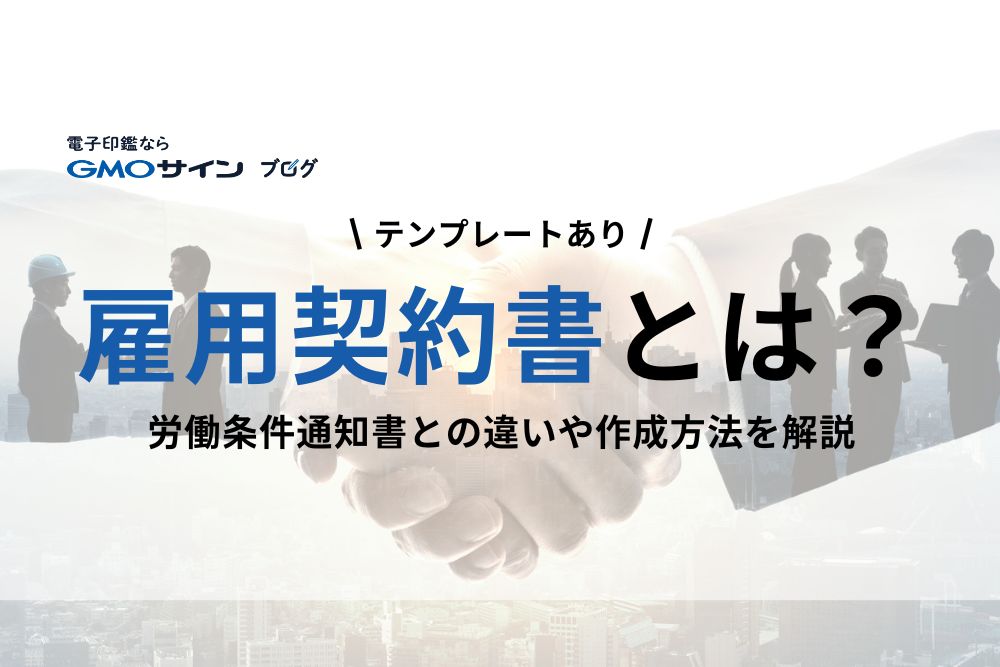
所有している物件において飲食業を開業する場合において、経営や実際の店舗の営業一切をオーナーが他者に任せる手法があります。このような方法を一般的にはよく「業務委託」などと呼びます。
飲食店において、その業務を他者に委託するケースとしては、以下のようなケースが考えられます。
①委託者であるオーナーが運営する店舗における現場仕事(調理・接客など)の委託
②経営上の専門知識に基づく指導的業務(各種コンサルタント・マネージャーなど)の委託
③店舗丸ごと一軒の経営・運営の委託
④一定の成果物(ホームページの制作・メニューの改良や新規開発など)作成の委託
上記のようなケースでは、オーナーは飲食店の現場での働き手を直接雇用するのではなく、その業務を受託する他社(受託者)との間でいわゆる「業務委託契約」を締結することになります。
本記事では、ここまで「業務委託」という言葉を便宜上用いてきましたが、実はこれは法的根拠に基づいた言葉ではありません。
つまり、「業務委託契約」そのものの規定がある条文は存在しないのです。
「業務委託契約」は、その契約内容によって以下の2つのどちらかに分類されることになります。
①「請負契約」(民法第632条)
②「委任(準委任)契約」(民法第643条、656条)

上記のように、飲食業のオーナーと働き手側の間の契約には雇用契約と業務委託契約の2パターンがあります。
しかし、どちらに該当するかの法律的な判断基準は意外と複雑なので注意が必要です。
例えば、雇用契約であるか、業務委託契約であるかはその内容で決まります。契約書上の名目を「業務委託契約書」としたとしても、その内容次第では雇用契約として扱われるので注意が必要です。
契約が雇用契約となるのか、それもといわゆる業務委託契約となるのかに関しては(非常に専門的な内容となるため本記事では詳細は割愛しますが)大まかに言って以下の3つの条件を満たしている場合には雇用契約ではなく、業務委託契約(請負契約または準委任契約)と判断される可能性が高いと考えてよいでしょう。
①委託者であるオーナー以外の業務を行うことができる
②オーナーの指示・依頼に関して受託者に許諾の自由がある
③就業規則や労働条件に拘束されない
業務委託契約と判断される場合、オーナーから委託を受けた者(受託者)は「労働者」ではなく「個人事業主」となります。このため、雇用関係を規律する法律である「労働基準法」などの適用から除外されることになります。
ちなみに、以前、某有名牛丼チェーン店が残業代など未払い賃金に関して労働者側から訴えを提起され、裁判で当事者の法律関係が争われたたケースがありました。この訴訟において牛丼チェーン店側は従業員との法律関係を「業務委託」であると主張しました。当事者の法律関係が業務委託であれば、牛丼チェーン店側には残業代などの支払い義務が法的に発生しないからです。しかし、裁判所はこの主張を認めず、当事者間の法律関係を「雇用契約」と判断し、牛丼チェーン店側に未払い賃金の支払い義務の存在を認めています。
実際、チェーン店において「②オーナーの指示・依頼に関して受託者に許諾の自由がある」というのは、少し考えにくいですよね。
このように当事者間の法律関係が雇用契約となるのか、いわゆる業務委託契約となるのかの判断に関しては、契約書のタイトルや契約内容で決まるのではなく、実態から判断されます。
民法は第632条において、請負契約について以下のように定めています。
民法第632条(請負)
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」
業務委託契約の内容が、一定の成果物に対して報酬を支払うことを目的としている場合には民法第632条~第642条で定められている「請負契約」の規定が適用されることになります。
例えば、「指定のレシピのケーキ100個を期日までに指定場所に納品する」というような場合が請負契約の典型例です。
この場合、請負人(業務の受託者)は契約の目的物の完成まで報酬の支払いを請求することができないこととされています。
なお、請負人は成果物に対して責任を持ち、納品後であっても損害が発生した場合には一定の損害賠償責任が課せられることもあります。
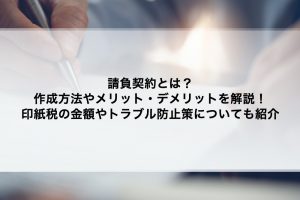
オーナーなど委託者が他者(受託者)に対して一定の行為を行うことを任せる契約のことを「委任契約」といいます。
民法上の委任契約では、その委任内容は「法律行為」とされています。「法律行為」とは、契約など法律上債権・債務を発生させるような行為のことを言います。
そして、飲食業の実際の業務は法律行為ではないため、飲食業の現場仕事を任せるような契約は「準委任契約」とされます。
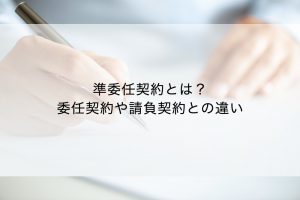
業務委託の性質が準委任契約とされる場合には、契約によって定められた業務内容を受託者が執行することによって報酬請求権が発生することになります。(同法第648条)
なお、準委任契約は請負契約とは違って、受託側(受任者)が成果物の結果に対して責任を負う必要はありません。
つまり「料理を作ること」はお願いできても、「料理の出来」や「時間内で仕上げて欲しい数量」などを確約してもらえるわけではないのです。「指定レシピのケーキ100個の制作」を準委任契約で依頼した際にケーキが80個しか完成しなくても依頼側がクレームすることはできません。準委任契約は店舗運営のコンサルティングやレシピへのアドバイス契約などには向きますが、調理の契約などは請負契約のほうが合っているでしょう。
なお、法律行為の詳細に関しては以下の記事を参照してください。
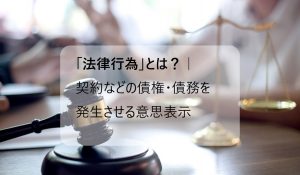
飲食店経営の都合上、ごく短期間だけ現場での働き手を必要とするケースもあるでしょう。従業員が急に休んでしまったためピンチヒッターとして「1日だけ」「数時間だけ」などという、ごく短期間の働き手との間の法律関係は、通常の場合には雇用契約となるでしょう。
そのようなケースでは、労働期間が短いことから賃金など細かい労働条件を不明確にしがちです。
しかし、そのような短期間の労働者との関係も立派な契約ですので、勤務させる以上、労働条件はあいまいにしてはいけません。
たとえ短期のパート・アルバイトであっても人を雇う際には、雇用契約書を作成することをお勧めします。賃金など労働条件を明示することによって、のちの「言った言わない」のトラブルを未然に防止することができるでしょう。
また、労働者を雇用した場合には、各種労働条件を明記した「労働条件通知書」の交付が必要とされています(労働基準法第15条)。
労働条件通知書のテンプレートは厚生労働省のウェブサイトにありますが、法改正により労働者の希望があればeメールやLINEのようなSNSでの交付、電子契約サービスの利用も可能になりました。
飲食店においては、スポットでの依頼やお試し雇用のケースも数多くあると思いますが、電子化すれば管理もしやすくなります。積極的に活用しましょう。
【参考】一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)(厚生労働省)
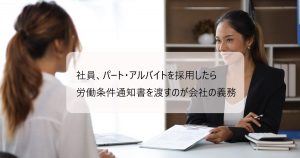
いわゆる業務委託契約ではなく、雇用契約の形態を採用した場合には主として以下のようなメリット・デメリット が考えられます。
法律関係がシンプルであり、現場で働く従業員のすべてが雇用主であるオーナーの指揮命令に服する義務があるため、業務に関するオーナーの意向を反映させることが容易です。
オーナーと労働者との関係が直接的であるため、飲食業の経営を続けることによって業務上有益なノウハウを蓄積できる可能性が高くなります。
業務委託と異なり、オーナー側で人材を確保する必要があるため、人手の確保に要する各種コストの負担が必要となります。
労働基準法、労働契約法や最低賃金法など各種の法律の規制を受けるため、労働者に対して細かい管理が必要となります。
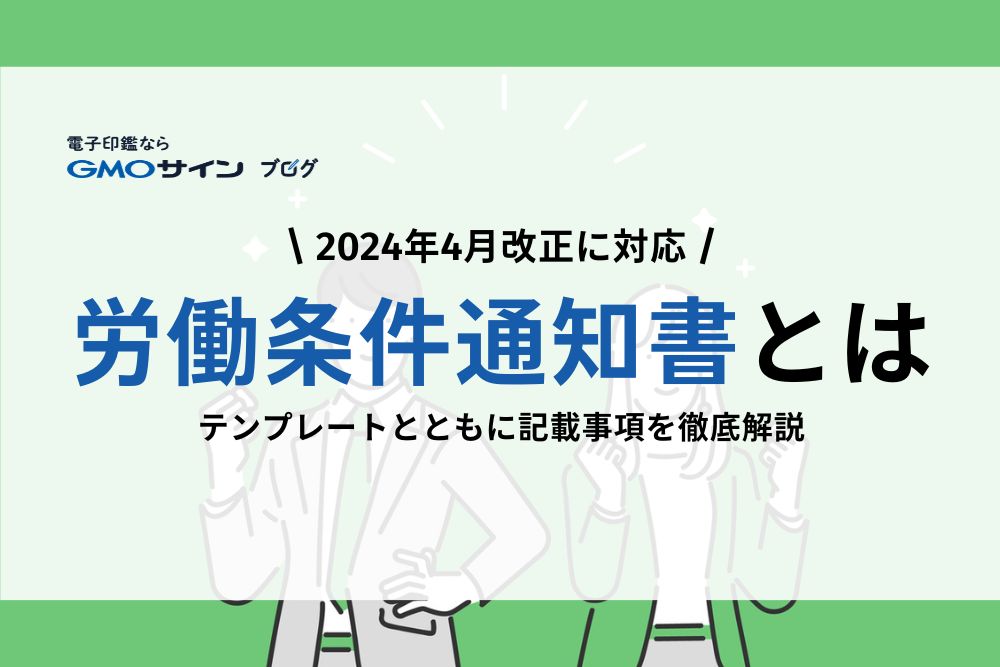
当事者の法律関係が雇用契約ではなく業務委託(請負契約または準委任契約)の形態を採用した場合には、主として以下のようなメリット・デメリットが考えられます。
飲食業を開業する場合、まったくノウハウがない状態から経営を軌道に乗せることは至難の業と言えます。一説によると、飲食業は開店後2年以内に50%の店舗が閉店に追い込まれるといわれています。そのような厳しい業界において、開店当初から専門的ノウハウやスキルを活用することは不可欠です。
店舗の運営ごと委託するような場合、現場での働き手などは、すべて業務の受託者が用意してくれるため、オーナーが人材確保のために動く必要がありません。人手不足が叫ばれる昨今の日本において、必要な人材を確保することは意外と苦労の多いものです。業務委託することで、そのような手間暇をカットすることができます。
店舗を長く経営しても、オーナー側には営業に関するノウハウやスキルが蓄積しにくい傾向があります。
受託者側は、業務を受託するかどうかを決定する裁量があります。そのため業務に関する独立性が広く認められるため店舗の経営などに関してオーナーの意向を反映しにくくなる可能性があります。
飲食業における雇用や業務委託には、いくつかの契約形態が存在します。オーナー企業が雇用主となり従業員を直接雇う雇用契約。いわゆる業務委託をすることによって店舗の運営や調理・接客などを外部に委託する準委任契約や請負契約など、それぞれには特徴があります。
各契約形態のメリットとデメリットを十分理解したうえで、自社にとって最適な方法を選択するとよいでしょう。
また、業務委託の場合でも契約書を取り交わすことはトラブル回避の面から極めて重要ですが、雇用契約の場合は労働条件通知書の交付が必須です。法改正でデジタルの活用も認められるようになりましたので、積極的に利用して業務の負担を減らしましょう。
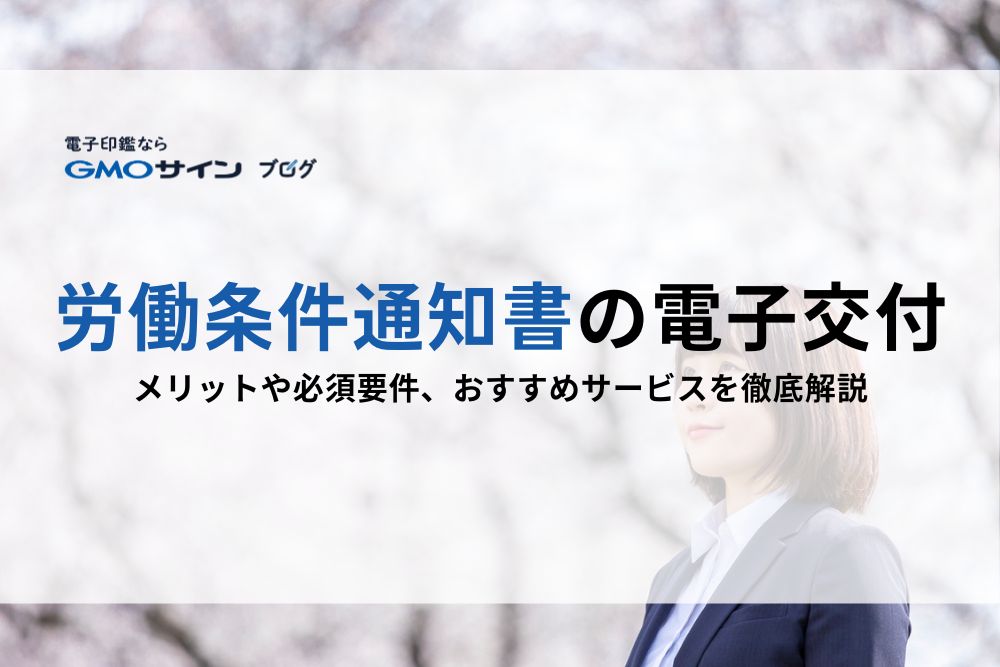
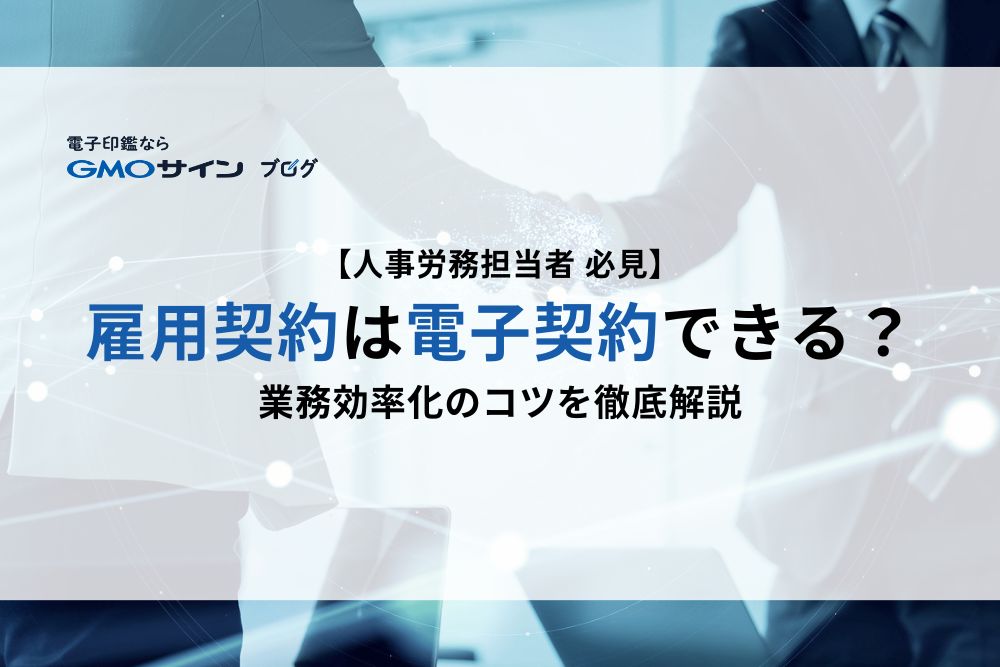
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
