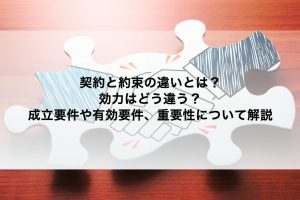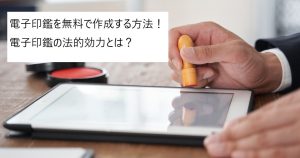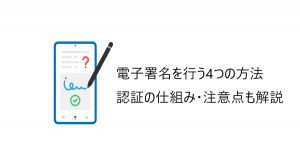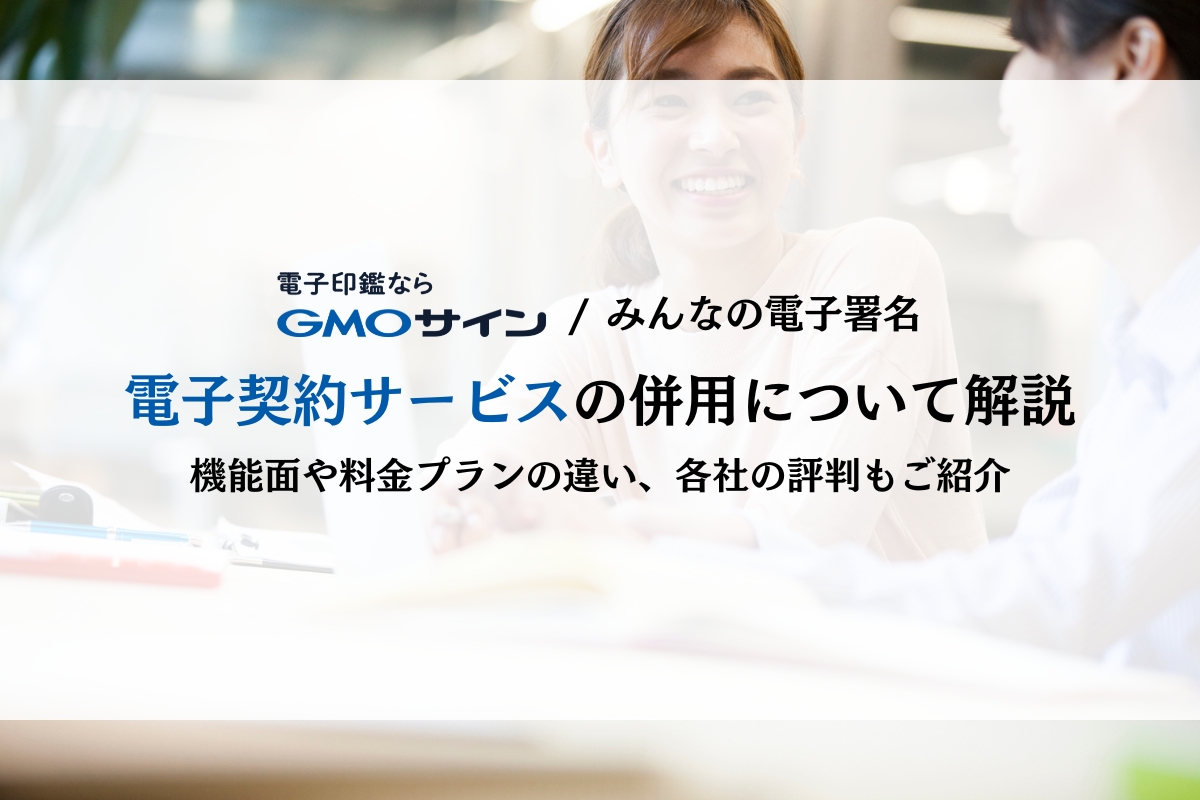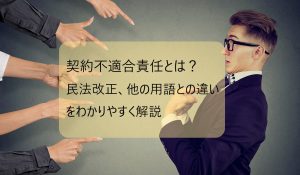\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

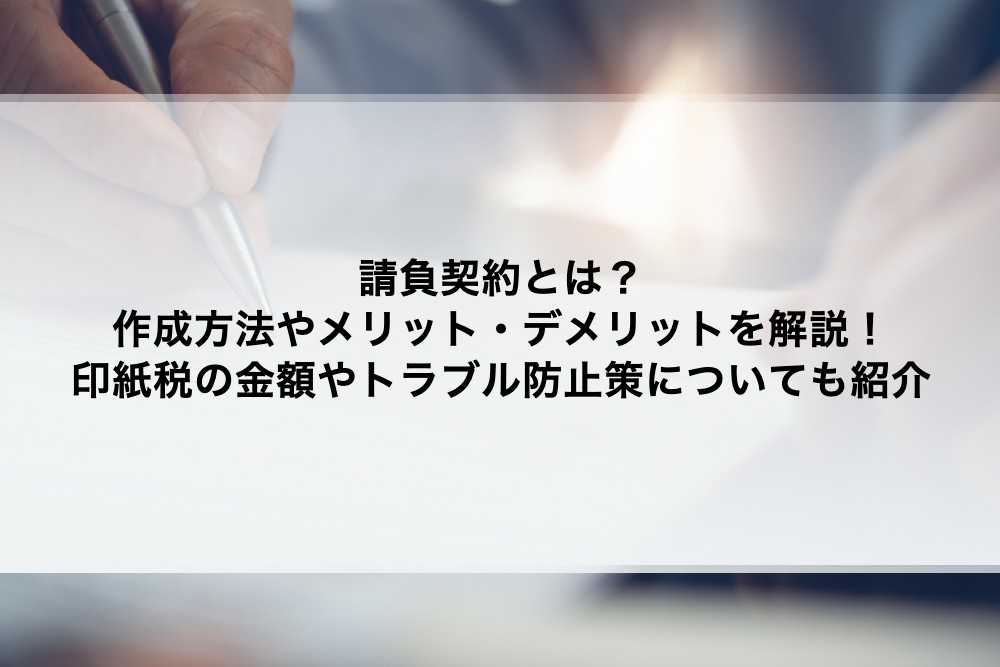
法人や個人が、他の法人もしくは個人に仕事を依頼する際には「請負契約」という契約を結ぶことがあります。この請負契約とはどのようなものなのでしょうか?
この記事では請負契約の意味や他の契約との違い、締結するメリットやデメリット、注意点についてご説明します。請負契約書のテンプレートもご用意しましたので、ぜひご活用ください。
請負契約とは、当事者の一方が相手方に対して仕事を完成させることを約束し、もう一方がその仕事の対価として報酬を支払う契約です。請負人(受注者)には仕事を完成させる義務が生じ、注文者には代金を支払う債務が生じます。
例えば、家を建てる際には、施主はハウスメーカーや工務店などの住宅会社と工事請負契約を締結します。住宅会社は請負契約を結んだ以上、「家を建てる」という仕事を完遂しなければなりません。家を完成させて引き渡して、はじめて住宅会社は施主から代金を受け取ることができるのです。
仕事を外部に発注する際に締結する契約には、請負契約の他にもさまざまな形態があります。ここからは請負契約と他の契約形態との違いについて見ていきましょう。
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。法律行為とは、意思表示によって一定の法律上の効果を発生させる行為のことをいい、契約の締結や解除、遺言書作成、訴訟、会社の設立などが挙げられます。例えば、弁護士に訴訟の代理依頼する場合が挙げられます。
請負契約においては、受注者に仕事を完成させる義務が生じますが、委任契約ではそれがありません。弁護士に訴訟代理を依頼し、敗訴した場合であっても一定の報酬は生じます。委任契約においては、受任者は注意義務を尽して事務処理を行う義務を負うにすぎないためです。
準委任契約とは、当事者の一方が事実行為(法律行為以外の行為)を相手方に委任し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。事実行為に当てはまるものは非常に幅広く、例えば、医師による診察や治療、介護事業者が提供する介護サービス、コンサルタントが行うコンサルティングサービスなどが挙げられます。
これも委任契約と同様に、仕事を完成させる義務が生じないところが請負契約との大きな違いです。医師に治療を依頼して病気が完治しなかったとしても、債務不履行にはなりません。
以上のように、請負契約は成果物の完成を約束する契約であるのに対し、委任契約・準委任契約は行為をすることを約束する契約であるという点で異なります。
業務委託契約とは、一方の当事者が業務を依頼し、相手方がそれを承諾することで成立する契約です。請負契約・委任契約・準委任契約全て、この業務委託というくくりに入ります。
前述のように、仕事の完遂を約束するのであれば請負契約、法律行為を行うのであれば委任契約、事実行為を行うのであれば準委任契約というように、目的に応じて適切な契約の形態を選択します。
契約形態が請負契約であっても、契約書の表題を「業務委託契約書」とすることもあります。
派遣契約とは、派遣会社が雇用している労働者を相手方に派遣して労働させる契約のことを指します。請負契約との大きな違いは「相手方の指揮命令下にあるかどうか」ということにあります。
派遣元と派遣先との派遣契約に基づいて派遣先に派遣された労働者は、派遣先の指揮命令下に入ります。労働者は派遣先の労働時間や休日といった就業規則や職場のルールに従って仕事をしなければなりません。業務内容や仕事の進め方なども派遣先が指示することが可能です。
一方で、請負契約は発注者の指揮命令下に入ることはありません。受注者は自分の裁量で仕事を進めて成果物を完成させます。また、請負契約では受注者自らが業務を行いますが、派遣契約は契約を締結した受注者(=派遣会社)が労働者を派遣して業務を行わせるというのも大きな違いです。
請負契約を締結する際には発注者側・受注者側ともに良い点と注意すべき点があります。ここからはそれぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
発注者側のメリットとして挙げられるのが、コストを抑えられる点です。例えば、雇用契約を締結して従業員を雇うとなると人件費や保険料、教育費、採用費などのコストがかかります。また、特に正規雇用の場合は仕事量が減ったとしても簡単に解雇することはできません。一方で、請負契約の場合は、必要なときに外部の専門スキルがある会社や人材に仕事を依頼することが可能で、報酬のみを支払えばよく上記の費用がかからないのでコストを削減することができます。
一方で、仕事の質が安定しないことがデメリットです。前述のように、請負契約は相手方を指揮命令下に置くことができず、詳細な指示が難しくなります。どうしても仕事の質は相手方のスキルや知識に左右されがちです。また、仕事を外部に出すことで、自社にノウハウが蓄積されないのもデメリットといえます。
受注者側のメリットとしては、自分の裁量で業務を進められることです。仕事のやり方から労働時間、休日にいたるまで制限を受けないので、自由な働き方が可能です。近年、正社員や派遣社員として企業に雇用されるのではなく、クライアントと請負契約を結ぶフリーランスという働き方を選択される方も増えてきています。
一方で、結果がシビアに求められるというのが厳しい点です。仕事の質が悪ければ次回からの契約が打ち切られてしまう可能性もあります。正社員と異なり、保障がないのもデメリットです。社会保険料も自分で負担しなければならず、仕事量が減った場合はやはり契約を打ち切られて失業してしまう可能性もあります。請負契約を締結して実態は派遣労働者のように働かせる「偽装請負」の被害に遭うリスクもあるというのもデメリットです。これについて、詳しくは後述します。
請負契約書も他の契約書と同様に発注者を「甲」、受注者を「乙」というように置き換えて作成します。また契約の目的や契約内容、報酬額や支払条件、契約解除、秘密保持、再委託、損害賠償などの項目を記載します。
請負契約書は印紙税法上の「課税文書」(2号文書)にあたり、契約金額が明記されている場合は、それに応じた印紙税額分の収入印紙を購入して契約書に添付しなければなりません。契約金額ごとの印紙税額を下表にまとめました。
出典:(参考)国税庁「請負に関する契約書」
記載された契約金額 税額 1万円未満のもの(※) 非課税 1万円以上100万円以下のもの 200円 100万円を超え200万円以下のもの 400円 200万円を超え300万円以下のもの 1,000円 300万円を超え500万円以下のもの 2,000円 500万円を超え1,000万円以下のもの 1万円 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円 5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円 1億円を超え5億円以下のもの 10万円 5億円を超え10億円以下のもの 20万円 10億円を超え50億円以下のもの 40万円 50億円を超えるもの 60万円 (※)契約金額の記載のないもの 200円
請負契約では発注者・受注者双方の認識の相違などから、さまざまなトラブルが発生するリスクがあります。ありがちなのが業務の内容や範囲についてのトラブルです。発注者側にとっては、期待した仕事をやってくれない、受注者側にとっては契約範囲外の仕事をさせられたというトラブルがよくあります。
何をいつまでに行うのか?どの範囲まで行うのか?どのような状態になったら完成といえるのか?を具体的に契約書に盛り込みましょう。
金銭関係もトラブルの種となります。
報酬はいくらなのか?消費税や経費の扱いはどうするのか?支払日はいつか?どのように支払うのか?をしっかりと明記しておくことが大切です。
これ以外にも不測の事態に備えて契約解除ができる条件や損害賠償請求、協議事項についても盛り込んでおくことで、トラブルの防止につながります。
仮に請負契約違反をしてしまった場合、刑事上あるいは民事上の大きな代償を支払うことになるかもしれません。ここからは発注者側・受注者側でよくある請負契約違反のケースと、それに対するペナルティについて見ていきましょう。
発注者側によくありがちな請負契約違反として偽装請負があります。偽装請負とは、請負契約を締結したのにもかかわらず、自らの指揮命令下に受注者を置いて恣意的に労働させることを指し、労働者の権利を侵害する行為として大きな社会問題となっています。
例えば、請負契約を締結した発注者に細かく業務について指示をしたり労働時間や休日を指定したりする行為(代表型)、受注者側が責任者を置かせて労働者をその指揮命令下で働かせる行為(形式だけの責任者型)、請負契約を締結した受注者が別の業者に再委託してその業者が労働者を発注者や受注者の指揮命令下で働かせる行為(使用者不明型)、労働者を斡旋された企業が派遣元ではなく労働者個人と請負契約を結んで指揮命令下で働かせる行為(一人請負型)などがあります。
偽装請負に該当する行為があった場合、行政指導や改善命令、勧告、企業名の公表などのペナルティが科せられます。また、職業安定法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が科せられる場合もあります。
受注者側によくありがちな請負契約違反として、債務不履行が挙げられます。債務とはある者が他の者に対して一定の行為をすること、あるいはしないことを内容とした義務のことです。請負契約を締結した場合、受注者側には「仕事を完成させる」という債務が生じることになります。
受注者側が途中で仕事を放棄したり、求められた品質に合致しない成果物を納品しなかったりした場合、債務不履行に該当することがあります。この場合、発注者は受注者に対して履行の追完請求や報酬の減額請求、契約解除請求ができます。
仮に受注者の債務不履行によって発注者が損害を被った場合、受注者は民事訴訟を起こされ損害賠償請求がなされる可能性があります。
請負契約を選択することで発注者側・受注者側ともにさまざまなメリットを得られる反面、トラブルが発生するリスクもあるため、それを見越して請負契約書を作成する必要があります。ぜひ、今回の記事を参考に作成してみましょう。
また、書面での請負契約締結は、契約書が相手方に郵送で届くまでの時間や印紙代などのコストがかかってしまいます。そこで、電子契約がおすすめです。パソコンやスマートフォンでスムーズに契約が締結できるため、時間や手間がかかりません。電子契約であれば印紙が不要なのでコストも削減できます。
電子印鑑GMOサインは、請負契約の締結にも対応可能です。最短1分で契約が締結でき、コストも年間80%削減できたという実績があります。導入実績は260万件以上で、自治体や大手企業でも導入されています。電子契約を導入してペーパーレス化で業務効率改善やコストダウンを実現しませんか?
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。