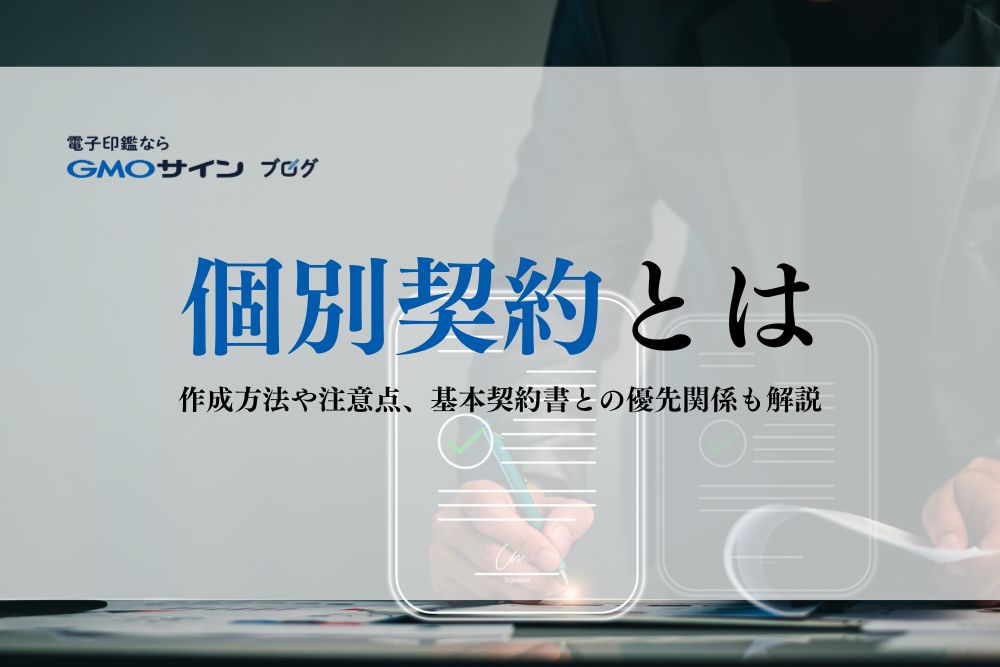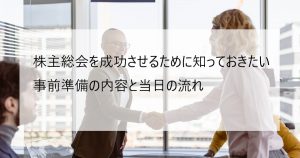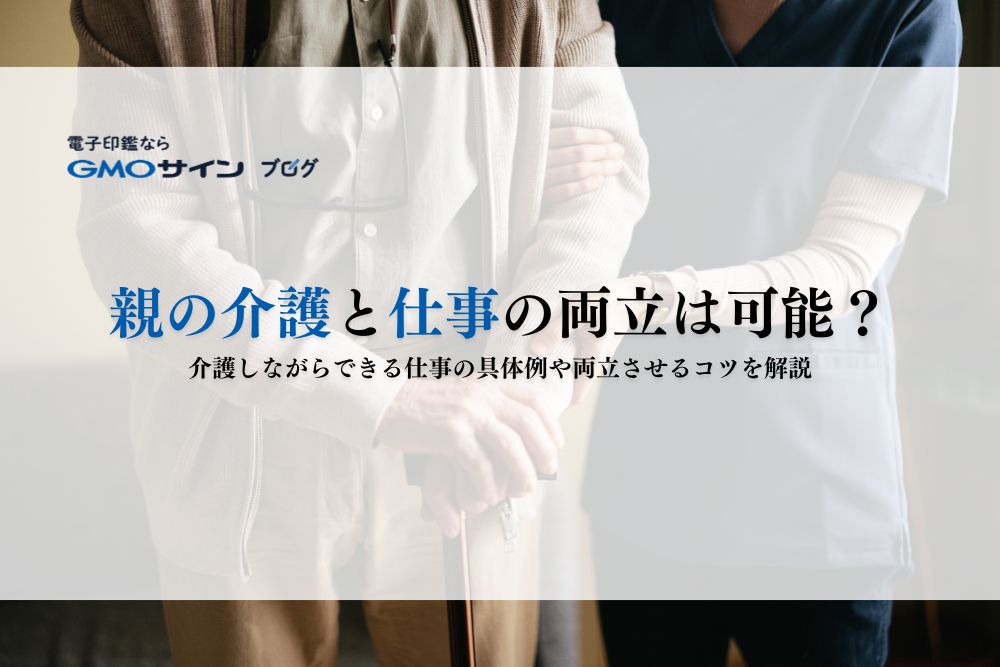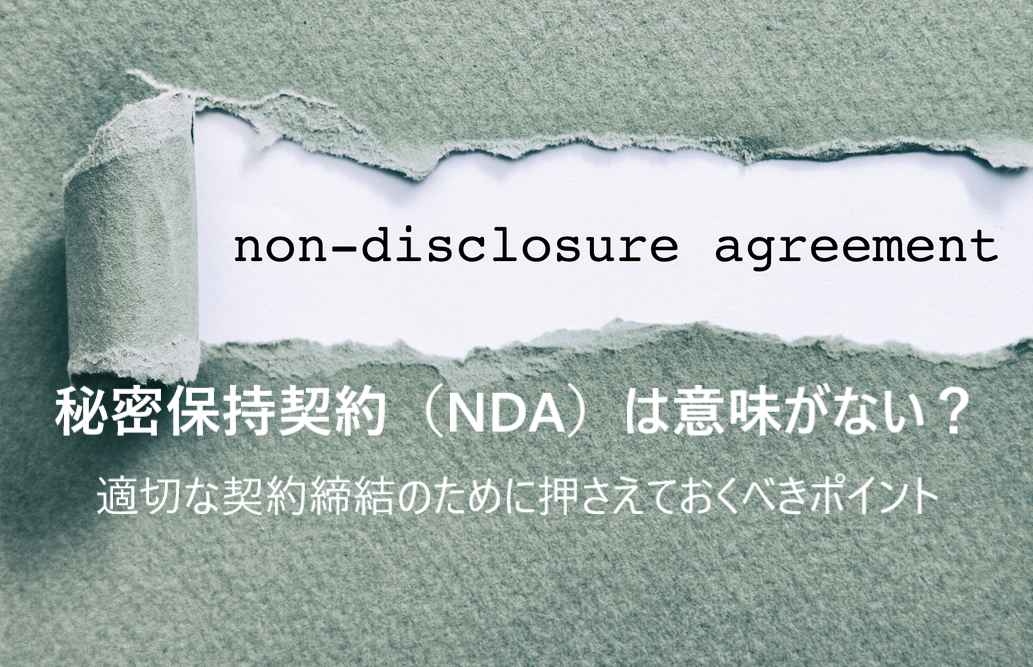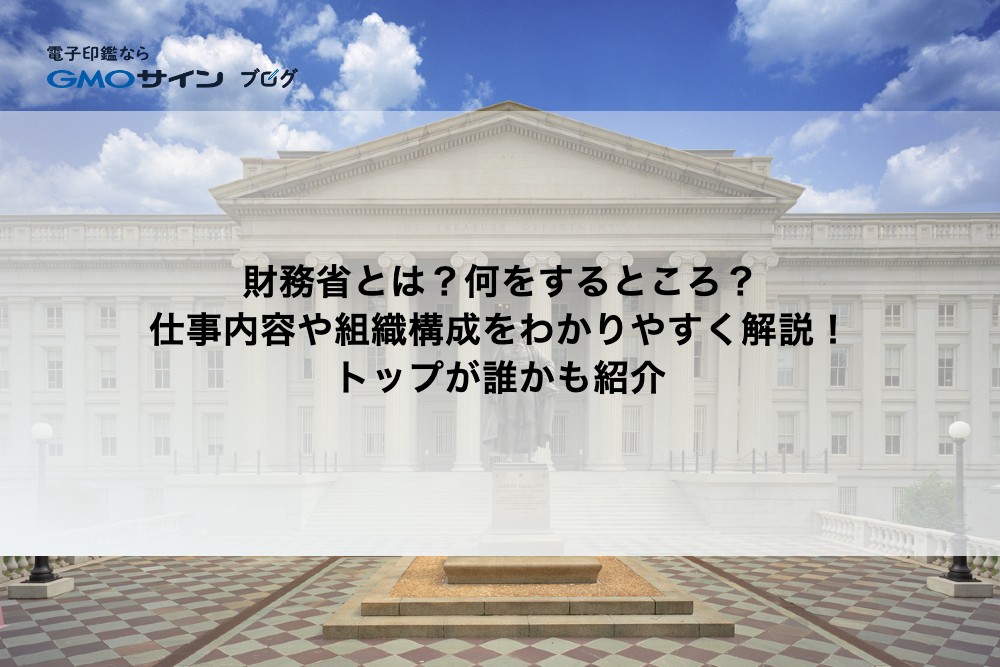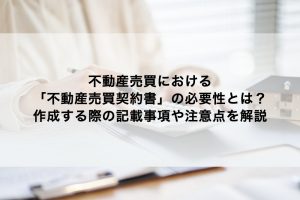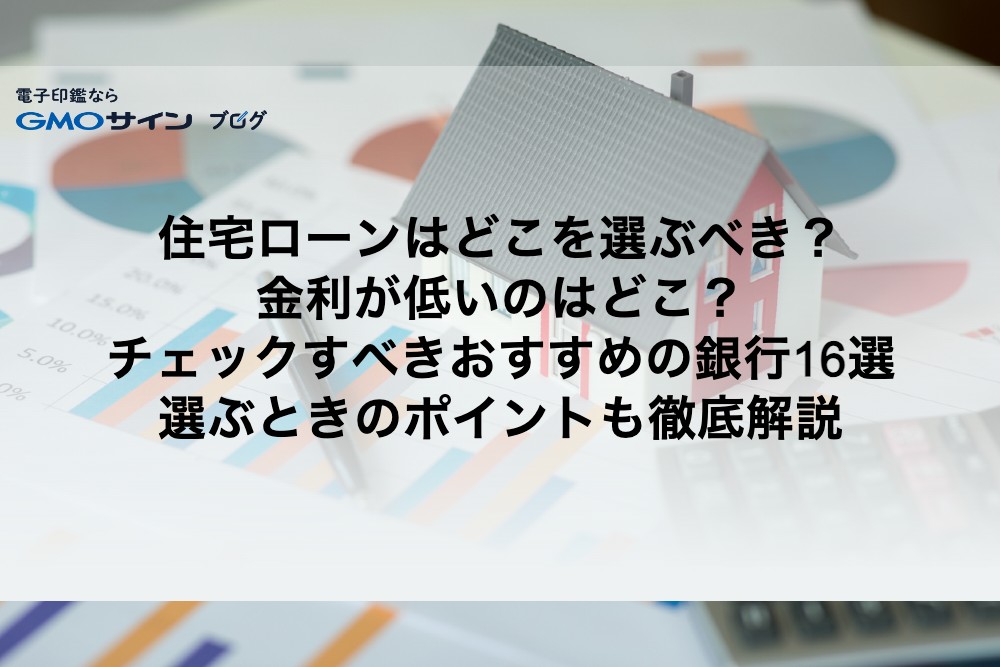\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /


商標権は企業がビジネスを行う上で非常に重要な役割を果たしています。バッグやスニーカーから、飲料、家電、飲食店にいたるまで、あらゆるものにそのブランドを認識できるロゴやマークがついていますが、ブランドを運営する企業は、商標権があるからこそ、安定的な利益を確保できるのです。
そして、このような商標権を持つ企業は、他社と商標使用許諾契約を締結することで、他社に自社の商標を使用させることもできます。商標権を持つ側にとっても、使用させてもらう側にとってもメリットが大きく、幅広く利用されている契約です。ただ、トラブル防止のため、商標使用許諾契約書を作成する際には必要な事項を漏れなく盛り込むことが重要です。
本記事では、商標使用許諾契約について、契約書に記載すべき条件や注意点などを中心に解説していきます。
商標というのは、他社の商品やサービスと区別する目的で使用されるロゴやマークなどのことです。商品やサービスの名称やキャラクター、音声なども商標に含まれます。
ロゴやマークなどを作成するのみでは、商標権という法的な権利は発生しません。商標権を得るには商標登録が必要です。商標登録をすることで、商標権を得ていることを一般に周知できます。
商標権を得ているロゴやマークなどは、他社が無断で使用することはできません。そして、消費者は商標を見ることで、どこの企業の商品なのか一目で分かり、安心して購入できます。

ロゴやマークなどの商標登録を行った場合に、商標権として行使できる権利は次の2種類です。
専用権というのは商標を登録者のみが使用できることです。ただし、指定商品または指定役務に限られます。役務というのはサービスのことです。商標登録を行う際に、対象とする商品や役務を指定します。
他社では同じ種類の商品やサービスに対して、商標登録済みのロゴやマークなどは使用できません。
禁止権は商標登録済みのロゴやマークなどを他社から無断で使用された場合に、排除できる権利のことです。具体的には、差止請求を行うことなどが挙げられます。商標の無断使用により損害が発生した場合には、損害賠償請求を行うことも可能です。
ただし、禁止権に関しても専用権と同様に、指定商品または指定役務に限られます。
このように、自社の商品やサービスの認知のために用いられる商標ですが、商標使用許諾契約を結ぶことで、他社に商標を使用させ、その対価に使用料を受け取ることも可能です。
商標使用許諾契約とは、自社で保有している商標を他社に使用させる際に締結する契約のことです。主に対象となる商標と関連のある商品やサービスを提供する場合などに用いられます。すでに一定の認知度を得ている商標を表示して宣伝することで、消費者に安心感を与えるのが目的です。
たとえば、知名度の低い中小企業でも、ブランド力の高い大企業と商標使用許諾契約を締結することで、ビジネスを有利に進められると想定できます。
商標使用許諾契約において、商標を所有していて使用権を与える側をライセンサー、商標の使用権を与えられる側をライセンシーと呼びます。
このような商標使用許諾契約において、ライセンサーはライセンシーに商標の使用料を支払うのが一般的です。ライセンサーとなる大企業にとっては、使用料収入を得られるメリットがあります。
商標ライセンスは次の2種類に分けられます。商標使用許諾契約を締結する際には、どちらの種類なのかを明記しておくことが重要です。では、それぞれの商標ライセンスについて見ていきましょう。
専用使用権というのは、対象となる商標に関してライセンシーが独占的に使用できるライセンスのことです。独占的であるため、ライセンサーは同じ商標に関して複数社に対して専用使用権を与えることはできません。また、他社に専用使用権を設定すると、ライセンサーも、対象の商標を使用できなくなります。法的効力が非常に強力だと捉えておくといいでしょう。
商標使用許諾契約を締結するだけでは、専用使用権を設定することはできません。特許庁で手続きを行い、登録する必要があります。
通常使用権というのは、対象となる商標に関して、他の企業も使用できるライセンスのことです。専用使用権とは異なり独占的に使用することはできません。ライセンサーは、複数の企業と商標使用許諾契約を締結して通常使用権を与えることができます。ライセンサーもこれまで通り自社の商標を使用可能です。
通常使用権を付与する場合には、専用使用権を付与する場合と違って、特許庁での登録手続きは必要ありません。商標使用許諾契約を締結すれば法的な効果が生じます。
商標使用許諾契約を作成する際には、トラブル防止のため、条件を明確に記載しておくことが大切です。では、具体的にどのような事項を記載しておくべきなのか見ていきましょう。
企業によっては、複数の商標を保有していることもあるでしょう。商品やサービスごとに異なるロゴを使用していることはよくあります。また、同じ商品やサービスに対して、複数のロゴやキャラクターを使用しているケースも見られます。そのような場合に、どの商標の使用を許諾しているのか明確に記載しておきましょう。
商標使用許諾契約では、対象となる商標に関して無制限に使用が許諾されるわけではありません。特定の商品やサービスの販促の際に限定して使用が許諾されます。
そのため、商標使用を許諾する具体的な範囲を、明確に記載しておかなければなりません。対象となる商品やサービスの他に、地域や店舗などに関しても明確に記載しておくことで、トラブルの防止につながります。
ロイヤリティというのは、商標使用権の対価としてライセンシーがライセンサーに対して支払う使用料のことです。ライセンス料と呼ばれることもあります。ロイヤリティの決め方は主に次の3種類です。また、ロイヤリティを無償にすることも可能です。では、それぞれの決め方について見ていきましょう。
ランニング・ロイヤリティは対象商品やサービスの売上金額によってロイヤリティの金額が変動する決め方です。出来高払方式とも呼ばれ、一定期間ごとに売上金額や数量などにライセンス料率を乗じて算出されます。ライセンス料率はあらかじめ決めておく必要があり、通常使用権なら1~3%程度、専用使用権なら10%程度が相場です。
例えば、対象商品の売上が1,000万円でライセンス料率が3%なら、ロイヤリティは30万円と算出されます。
ランニング・ロイヤリティを採用している場合には、売上が伸びるほどライセンサーにとって有利です。逆にあまり売上が伸びない場合には、ライセンシーの負担が軽くなります。
ランプサム・ペイメントは、売上金額などの実績値とは無関係にロイヤリティの金額を一定額に決める方式です。固定額払方式とも呼ばれています。
ライセンサーにとっては、売上状況にかかわらず一定金額を確保できるのがメリットです。ライセンシーにとっては、売上が好調な場合には有利ですが、不調な場合も同じ金額を支払う必要があり不利な面もあります。
イニシャル・ペイメント+ランニング・ロイヤリティは、固定額ロイヤリティと売上比例のロイヤリティを組み合わせる方法です。
ライセンス料率も固定額の部分もやや低めに設定します。売上が好調なほどライセンサーにとって有利ですが、ランニング・ロイヤリティほどではありません。また、売上が不調なときのライセンシーの負担はランプサム・ペイメントと比べると抑えられます。
ロイヤリティが無償という設定は、主にラインセンサーとライセンシーが親会社と子会社の関係の場合などに行われます。
無償とはいっても、別法人である以上は商標使用許諾契約が必要です。
ロイヤリティが無償という点以外に関しては、通常の商標使用許諾契約と変わらず、条件などを明確に規定しなければなりません。
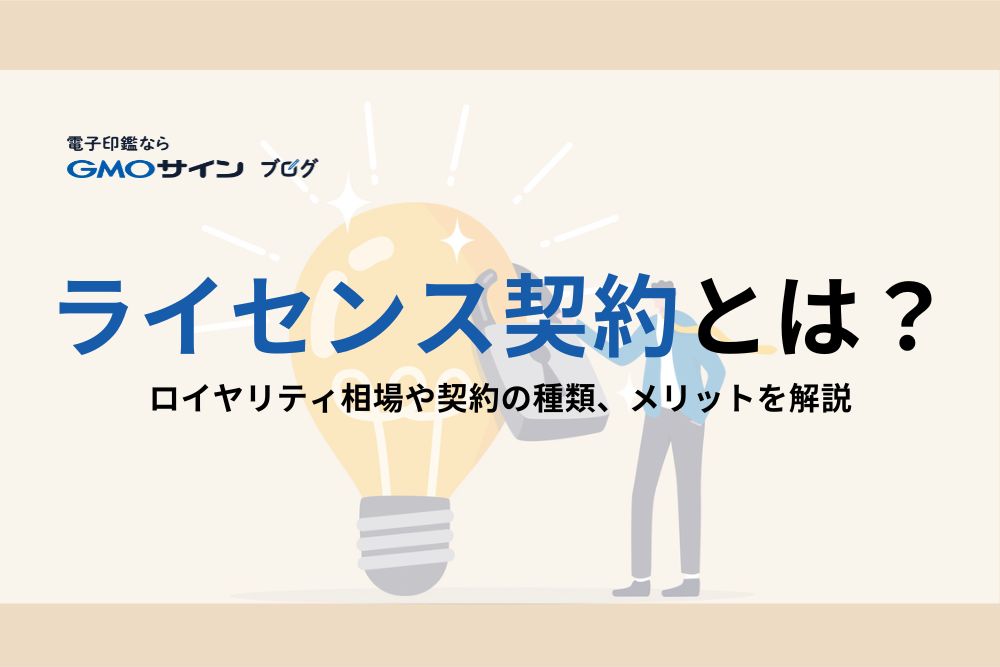
遵守事項というのは、ライセンシーが商標を使用する際のルールのことです。商標を使用するといった場合には、さまざまな使用方法が想定されます。商標の使用方法によっては、ライセンサーにとって不都合が生じる場合もあるでしょう。そのため、商標使用許諾契約において、遵守事項を明確に定めておくことが大切です。
例えば、商標を表示する箇所や大きさ、色などが挙げられます。表示位置や色などが変わると、イメージも変わる可能性があるため、表示方法を定めておきましょう。特殊なフォントを使用している場合には、フォントに関する指定も必要です。
また、品質の良くない商品に商標を使用すると、ブランドイメージの低下につながるおそれもあるでしょう。そのため、商標そのものだけでなく、商標を使用する商品に関して遵守事項を定めることも可能です。品質管理基準を定めておくことで、ライセンサーのブランドイメージを守れます。それとあわせて、ブランドイメージを毀損する行為を禁止する旨の規定も設けておきましょう。
商標使用許諾契約を締結する際には、あらかじめ契約期間を定めておきます。契約期間が満了すると更新されない限りは契約が終了する仕組みです。ただし、更新を前提としているケースもあるため、更新に関することを商標使用許諾契約に盛り込んでおきましょう。
また、契約期間満了まで何も問題なく経過するとは限りません。ライセンサーかライセンシーのどちらかの状況が変化して、解約の必要性が生じる場合もあります。そのため、契約の解約についても定めておかなければなりません。通常は解約を申し入れる側が相手側に対して違約金を支払うことで契約期間満了前に解約できます。違約金の金額について明記しておけば、実際に解約の必要性が生じた場合に、両者ともにスムーズに対応できるでしょう。中途解約を認めないという取り決めを行うことも可能です。
契約の解約とは別に解除というものもあります。一定の解除事由が生じた場合に契約をはじめからなかったことにできるというものです。ただし、具体的な解除事由は商標使用許諾契約で定めておく必要があります。一般的に、重大な契約違反に該当する行為や破産などの事実が確認された場合を解除事由として定めるケースが多いでしょう。
ライセンシーが不正な目的で商標を使用した場合には、トラブルに発展する可能性があります。そのため、商標使用許諾契約において、不正利用を禁止する旨の規定を設けておきましょう。また、実際に不正使用が確認された場合の対応も明記しておくのが望ましいです。主に契約解除や損害賠償請求などが行われます。
クオリティーコントロール条項は、商標を用いて宣伝する商品やサービスに関して一定の品質を担保するための規定です。品質の低い商品やサービスで商標が使用されることを防止し、ライセンサーのブランドイメージの維持に役立てられます。
ライセンサーは、ライセンシーの商品やサービスについて品質確認を行い、商品であれば販売する前の段階で、検査などが行えます。定期的な立入検査なども可能です。具体的な方法に関して、商標使用許諾契約に明記しておく必要があります。
商標使用許諾契約を締結する際には、次のような点に注意が必要です。
ライセンシーが商標使用許諾契約に基づいて商標を使用する場合、第三者からクレームを受けることがあります。クレームへの対応はライセンサーとライセンシーのどちらにとっても重要です。また、実際に対応する際には時間や労力などのリソースを消費するため、どちらが対応するかどうか明確に定めておく必要があります。クレームへの対処方法を定めていないと、対応が遅れてしまう可能性があるため注意しましょう。
一般的にはライセンシーが対応すると定めるケースが多いようです。対応にかかる費用も多くの場合で、ライセンシーが負担します。
契約締結などの業務に関わる法務担当者は、商標使用許諾契約の内容を十分に理解しているでしょう。しかし、他部署の社員は契約や法律に関する専門的な知識がないことが多く、意図せず契約違反に該当する行為を行ってしまうこともあるかもしれません。
そのようなトラブルを防止するため、他部署の社員も商標使用許諾契約の内容を理解できるようにしておくことが大切です。具体的には、社内で研修会を実施したり、商標使用に関するガイドラインを作成したりしておきましょう。
大半の契約書には収入印紙を貼付する必要があります。そのため、商標使用許諾契約書を作成する際にも、収入印紙を準備しようとする人が多いかもしれません。しかし、商標使用許諾契約書は収入印紙の貼付が不要な文書です。誤って貼付してしまわないように注意しましょう。
ただし、商標権を譲渡する際に作成する「無形財産権の譲渡に関する契約書」には収入印紙の貼付が必要です。商標使用許諾契約書とよく似ているため、間違えないようにしましょう。
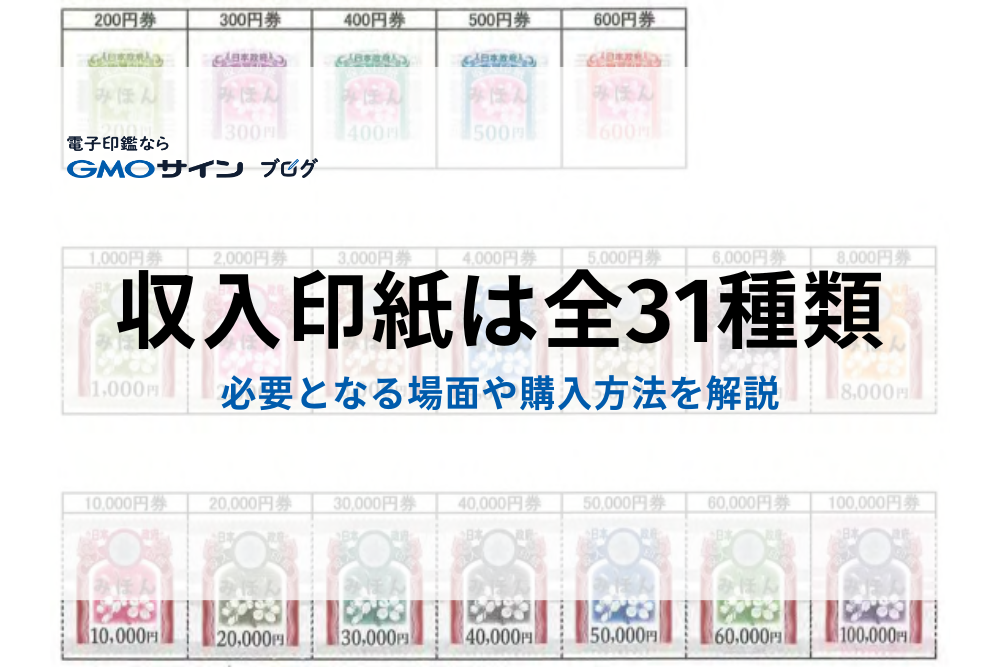
商標使用許諾契約を締結する際は、電子契約を利用するのがおすすめです。
商標使用許諾契約を締結する際に、紙の契約書を作成するのは手間がかかります。2部作成してライセンサーとライセンシーのそれぞれで、同じものを保管しておかなければなりません。さらに、記名や押印などが必要なため郵送が必要ですし、製本するのに手間やコストもかかるでしょう。
その点、電子契約であれば署名や押印が不要なため、郵送も不要です。製本の手間やコストかかりません。お互いに離れた場所にいても、相手にデータを送信すれば内容を確認できます。相手は、電子署名を付与して送信するだけです。電子署名を行うことで真正性を確保できて、タイムスタンプを利用することで、改ざんも防止できます。電子契約が完了した後は、記載内容の確認も簡単に行えて便利です。
商標使用許諾契約を締結するのであれば、ぜひ電子契約の導入を検討してみましょう。

商標使用許諾契約は、商標登録済みのロゴやマークなどを他社に使用させたり、使用させてもらったりする際に締結する契約です。商標権の保有者をライセンサーといい、商標権を使用させてもらう側をライセンシーといいます。
通常はロイヤリティの支払いが行われますが、無償に設定することも可能です。ロイヤリティに関することや、契約の更新・解約・解除などは重要度が高いため、漏れなく明記しておきましょう。その他、商標の使用ルールを規定する遵守事項やクオリティーコントロール条項なども重要です。明確に条件を設定しておくことがトラブル防止につながります。
そして、契約締結後は、社内で商標を扱う可能性のある社員に契約内容や商標の使用方法などを十分に周知しましょう。ガイドラインを作成したり研修会を実施したりなど、契約違反がないように注意しながら運用していきましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。