\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

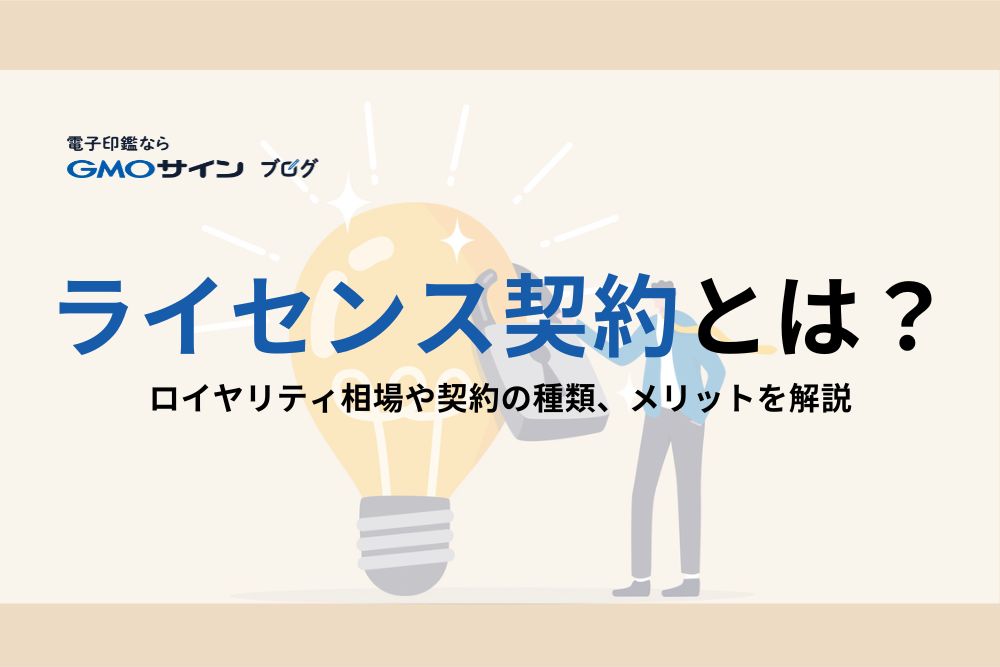
ライセンス契約とは、知的財産権を提供するライセンサーが利用する相手方のライセンシーに対し、ライセンスの対象となる特許権や著作権、その他ノウハウ等について、実施権、利用権、使用権などを許諾する契約です。多くの知的財産権が存在するため、ライセンス契約の種類や記載事項も多岐にわたります。
そこで本記事では、ライセンス契約のロイヤリティや契約の種類、メリット、記載事項、契約の流れなどについてわかりやすく解説します。記事後半ではOEM契約との違いについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ライセンス契約とは、特許(ライセンス)などの知的財産の使用について、所有者と結ぶ契約を意味します。また特許だけでなく、商標権や著作権、または技術・設計などのノウハウも知的財産の対象となります。
ライセンサー(知的財産権を提供する側)とライセンシー(利用する側)との間で使用期間、使用内容などを定めて契約することで、ライセンサーにロイヤリティ(使用許諾に対する対価)が支払われます。
つまり、ライセンサーはライセンスによる収入を獲得し、一方ライセンシーは他社の技術やブランドを利用して利益を上げられるのです。
ライセンサーのメリットは、自社の特許や意匠、著作物などの使用を他社に許諾することによって、ライセンス料として収入を得られることです。
また自社に技術力や設備があまりない場合でも、ライセンシーのブランドや広告などによって自社ブランドの人気が上がる可能性があります。
一方、ライセンシーは、技術やブランドを導入することで効率的にビジネスを展開できるため、新しい顧客をつかめばライセンス料を上回る利益を得られる可能性もあります。自社で開発しようとしていた技術について他社がすでに特許権を得ていた場合などでも、ライセンシーになれば事業が継続できるようになります。
ライセンサーのデメリットは、ライセンシーが商品を企画する際に毎回確認をとる必要がある点や、ライセンスの対象物に対して在庫確認や調整を行う点が挙げられます。
またライセンサーが保有する対象物と、ライセンシーが対象物を使用して開発する商品のブランドイメージが異なっていた場合、お互いのブランドのイメージが壊れてしまうケースが考えられます。さらにライセンス契約を行う場合には、時間がかかって交渉がまとまらないケースも考えられるでしょう。
デメリットを回避するためにはライセンス契約に関する専門的な知識が必要であるため、知的財産および交渉や契約の専門家である弁護士や弁理士に依頼すると良いでしょう。
ライセンス契約におけるロイヤリティの一般的な相場は、3~5%です。ただし、専門性が高い知的財産権物の場合は10%前後となるケースもあります。
ロイヤリティには法令による定めはなく、金額や支払い方法などはライセンサーとライセンシーの合意によって自由に決められます。
またロイヤリティは、特許の分野や契約方法によって異なりますが、ほかにも特許が関連する製品の市場価値などもロイヤリティを左右する要素となります。
ライセンス契約の主な種類は、以下のとおりです。
それぞれの内容について詳しく解説します。
特許ライセンス契約とは、特許を取得している人(ライセンサー)に対し、特許権を使いたい人(ライセンシー)が特許権者から許諾を受け、契約を結ぶことです。特許権によって保護される技術や発明の実施を許諾する契約です。専門的かつ高度な技術的発想が対象となります。
商標ライセンス契約とは、商標権によって保護される登録商標の使用を許諾する契約です。商標を使用する独占的な権利を持つ商標権者(ライセンサー)が、他者や企業にその商標の使用を許諾します。また、許諾した相手(ライセンシー)に対して、その商標権を行使しないことを約束します。ライセンサーは、商標を使用させる代わりに、ライセンシーから対価を受け取ります。具体的には、商品に使われるロゴマークや新サービスの名称などが対象となります。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
引用元:特許庁「商標制度の概要」

意匠ライセンス契約とは、意匠権によって保護されるデザインの利用を許諾する契約です。意匠権とは、物品のデザインを保護する権利のことです。最近は物だけでなく画像、建築物、内装なども意匠権が認められるようになってきています。インテリアやファッション系のデザイン、電子機器の形や画面のデザインなども意匠登録できます。
意匠法の保護対象となる「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。
引用元:特許庁「意匠制度の概要」
また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。
著作権ライセンス契約とは、著作権によって保護される創作物の利用を許諾する契約です。著作権法によれば、著作物には小説などの文章、音楽、舞踊、絵画などさまざまな分野が含まれます。著作権は、基本的に受注者、つまり手を動かして作成した人が持つ権利です。ライター、プログラマー、作曲家あるいはイラストレーターなどの著作者が著作権を持つのが原則です。
そのため、仕事の発注者は著作権を譲渡してもらうか、著作権のライセンス契約を締結することになります。ただし、ライセンス契約の場合は、譲渡と違い、権利は受注者(著作者)に存在します。
(著作物の例示)
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
著作権ライセンス契約の主な具体例には、以下の2つが挙げられます。
それぞれの契約について詳しく解説します。
ソフトウェアライセンス契約とは、ソフトウェアの著作権者が相手方に対して、当該ソフトウェアの使用を許諾する契約です。契約に基づいてソフトウェアの使用を、他社(他者)に許諾します。販売元のソフトウェアメーカーがライセンサーとなり、ソフトウェアの購入者がライセンシーとなるのです。ソフトウェアの購入者には、ライセンスが与えられ、契約の範囲内でソフトウェアを使用できます。
なお、あくまでも使用の許諾であって、著作権を譲渡する契約ではありません。市販のOSやパッケージソフトの場合、ライセンス契約書(使用許諾契約書)が添付されており、その契約に同意することでライセンスを得ます。
ソフトウェアライセンス契約では、著作権者がライセンサーとなり、ライセンシーに対して著作権で保護されている行為(複製など)を許諾し、その代わりに使用許諾料を受け取る仕組みになっています。そのためソフトウェアの複製などを行う際には、原則として著作権者の許諾が必要です。
キャラクターライセンス契約とは、アニメや漫画などに関するキャラクターコンテンツのライセンサーがライセンシーに対して当該キャラクターコンテンツの使用を認める代わりにロイヤリティをもらう契約です。
販売する商品にキャラクターを印刷したり、キャラクターをインターネット配信したりする場合にキャラクターライセンス契約が締結されます。
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部・本社・本店)が、フランチャイジー(個々の店)に商標を利用する権利などを付与する契約です。商標の使用を許諾するとともに、事業経営に関する指導援助の対価として、加盟金やロイヤリティなどをフランチャイザーに支払います。コンビニや飲食店チェーンなどをイメージするとわかりやすいでしょう。
ライセンス契約には、通常実施権設定契約と専用実施権設定契約の2種類があります。
それぞれのライセンス契約についてわかりやすく解説します。
通常実施権設定契約とは、特許や意匠、著作物などを利用できる権利です。
ただし専用実施権設定契約と異なり、対象物の利用を独占できません。そのため、知的財産権の無断使用等に対して差止請求等を行えない点には注意が必要です。ライセンサーがライセンシーに対して通常実施権を与えた場合、ライセンサー自身も対象物を引き続き使用できます。また通常実施権は、複数のライセンシーに与えることも可能です。
なお通常実施権は、以下の2つに分けられます。
それぞれ詳しく解説します。
独占的通常実施権とは、特許権者(特許の所有者)がライセンサーに対して、第三者に実施権を許諾してはいけない特約を付した通常実施権です。独占的に利用することで成果が期待できる場合に用いられるケースが多いです。
非独占的通常実施権とは、複数の会社が特許を扱える形式の通常実施権です。それぞれの会社にある設備や人員を利用して、相互的に協力することで結果が出やすい場合に使われやすいです。
専用実施権設定契約とは、発明内容の公開を条件として一定期間ライセンシーが独占的に対象物を利用できる契約です。この契約では、原則として出願日から20年間、特許権者は特許発明を独占的に実施できます。専門実施権契約を行う場合には、ライセンシーを特許庁が管理する特許原簿に設定登録します。
また発明して特許権を取得したものの、自らそれを実施して利益を上げることができない場合は、第三者に専用実施権または通常実施権を設定してライセンス料を得られる点が特許権者にとってのメリットと言えます。
なお、一般的に通常実施権よりも専用実施権の方がライセンス料は高額になります。
クロスライセンス契約とは、ライセンス契約の当事者間で互いに特許、意匠、著作物などの使用を許諾し合う契約です。つまりクロスライセンス契約では、当事者はそれぞれライセンサーかつライセンシーになると言えます。主に電機メーカーが、周辺機器の品揃えの充実や販路の拡大を図る場合に用いられます。
たとえば、A社がXという特許を持っていてB社がYという特許を持っている場合、A社はB社に特許Xを許諾し、B社はA社に特許Yを相互に許諾するという手法です。いわばトレード契約であり、使用料が発生しないケースもありますが、権利の強さによってどちらかに使用料が発生するケースもあります。
サブライセンス契約とは、他社から許諾を受けた特許や意匠、著作物などの使用をさらに第三者へ許諾する契約です。
主に子会社や関連会社に対して、特許物の製造や販売を委託する場合に用いられます。
たとえば、A社が持っているライセンスを、B社に許諾してライセンス契約を締結します。B社には、CとDという子会社があります。C社とD社でもA社の技術やサービスを使えるようにするには、通常、C社とD社各々がA社と契約を結ばなければなりません。しかし、A社とB社がライセンス契約を結ぶ際に、サブライセンスを認めていれば、B社の子会社であるC社とD社は、直接A社とライセンス契約しなくてもA社の持つライセンスを使用できます。
ライセンス契約では、主に以下の条項を記載します。
ライセンス契約は高額な契約になるケースが多いので、契約内容には細心の注意を払いましょう。
ライセンス契約は、「準備」「交渉」「締結」の3段階で行われます。
それぞれのステップについてわかりやすく解説します。
まずは、利用したい特許情報の問い合わせ先に連絡します。具体的には開放特許情報データベース(https://plidb.inpit.go.jp/)にアクセスして、「登録者情報」から利用したい開放特許情報について調べて登録者へ連絡します。
その特許を用いてどのような商品やサービスを開発したいのか登録者へ説明するとともに、ライセンス料の支払い方法などについても交渉します。
登録者からの了解を得られたら、ライセンス契約を締結します。契約書を作成し、双方が署名・捺印をした時点で契約が成立したとみなされます。
事業化にあたっては、他の権利に抵触する可能性やその他の規制などに注意しましょう。
このとき秘密保持に関する条項も定めておくことが重要です。
具体的にはライセンスに関する秘密情報の漏えいを防ぐために、以下の条項を契約書に記載しておきましょう。
基本的に契約は、当事者同士の合意があれば成立します。そのため、他者の状況や事例などは関係なく、両者が合意をすれば契約を締結できます。ただし、企業の大きさ、立場などを利用して特許や知的財産権と関係ない部分で独占的な契約を結ばせる、あるいは有利な地位を濫用するような契約は、独占禁止法で禁止されているため、避けなければなりません。あくまでも知的財産の許諾という範疇でお互いが合意することが大切です。
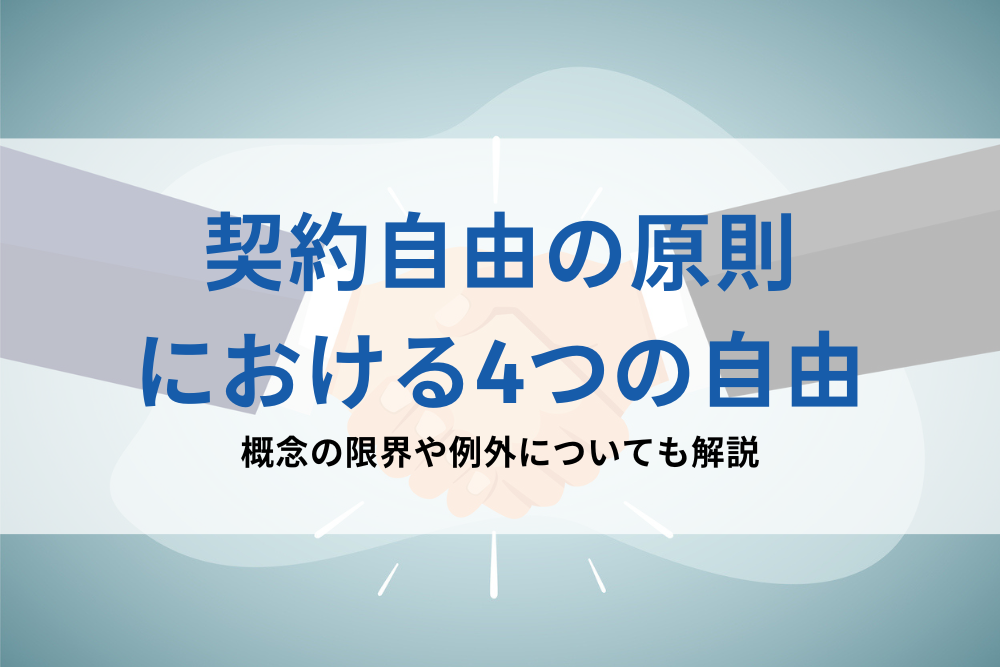
契約の中に含めなければいけない基本的な注意事項の1つ目は、許諾の対象となる範囲を明確にすることです。特許権などをライセンスする場合、契約を結ぶライセンシーはビジネスのどの部分について特許権を使用して良いか、あらかじめ範囲を決めておく必要があります。
あらゆる行為に対し、特許権を使用して良いと漠然とした雰囲気で契約すると、後で「この製品に対して許諾したつもりだったのに、まったく関係ないものにも使われている……」と、意図と違う結果になりかねないため気をつけてください。
契約書の中で許諾範囲を明確にすべきです。対象製品・対象サービスをきちんと定義すること、そして「どういった行為に許諾するか」、つまり製造なのか販売なのか、どのような行為に対して許諾するのかを明確にすることが必要となります。
基本的な注意事項の2つ目は、独占的なライセンスか非独占的なライセンスかを明確にすることです。独占的許諾の場合は専用実施権、複数の企業に許諾する場合は通常実施権と呼ばれます。
独占的なライセンスであれば、ライセンシーにとってメリットが大きいため、それだけ高い対価が得られるでしょう。ただし、その反面、ライセンシーのビジネスが思うように発展しない、市場を開拓できない、といった問題が起きた際に想定より低いライセンス料しか得られないだけでなく、他社にライセンスできない結果になります。そのため、独占的ライセンスにするかどうかは、ライセンシーの能力や市場の規模なども見て十分に考える必要があります。
3つ目はライセンス許諾の期間を明確にすることです。特許権は出願から最大で20年権利が認められるため、権利がなくなるまで許諾することも可能です。しかし、あまりにも長期間の設定では、ライセンシーがそれだけ長くビジネスを続けられるか、といった問題が生じます。そのため、相手の能力、ビジネスプランなどを慎重に検討し、決定する必要があるでしょう。
4つ目の注意事項は許諾する地域の範囲を決めることです。地域ごとにサービスを許諾する場合は注意が必要です。たとえば、地域Aでは企業1に許諾し、地域Bでは企業2に許諾するというプランの場合、それぞれ「この地域の中で、このサービスの提供について許諾する」と、地域をきちんと定義する必要があります。国内はもちろん海外について権利を持っている場合も同じです。中国では企業A、アメリカでは企業Bというように国やエリアごとに分けて契約する場合、それぞれ別の契約で地域を明確にし、その根拠となる権利も明確にしたうえでライセンスを許諾します。
ここで挙げたのは4つの基本的な注意事項だけですが、実際にライセンス契約を交わす際には、そこに紐づけする重要な事項が数多くあります。たとえば、
といったことは、ライセンス契約における重要事項です。
「OEM」とは、「Original Equipment Manufacturing」の略称で、委託者のブランドで商品を生産することを意味します。一般的に、自社ブランドの商品の製造を他社(受託者)に委託する契約をOEM契約と呼びます。
たとえば、化粧品やスマホのアクセサリー、キャンプ用品などを自社のブランドで販売する場合、自社で企画し、製造は製造設備を持つメーカーに委託するケースがOEMです。
OEM契約はあくまでも製造に関する契約であり、販売や宣伝は含まれません。販売や宣伝を行うのは、メーカー(OEM)ではなく、委託した事業者です。ライセンス契約は、他の企業が開発した技術やノウハウ、商品、サービスなどに対しライセンス料(使用料)を払って商品を製造したり、サービスや商標を使用したりすることです。そのため、ライセンス契約とOEM契約は異なります。
OEMのメリットは、製造コストを下げられることです。他社の製造ラインを使用することで開発費用を抑えられ、販売に必要な最小限の製品供給を受けることで、在庫リスクを最小限にできます。
ただし、OEM契約を結ぶ場合は、他社(他者)の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。デザインが意匠権侵害になる、不正競争防止法違反になる、というケースも見られるため注意しましょう。

ライセンス契約は、主に通常実施権設定契約と専用実施権設定契約に分けられます。しかし、特許を利用する目的によってはクロスライセンス契約やサブライセンス契約などより便利な契約があることを本記事でご説明しました。
自社がどのような形態でライセンス契約を結ぶべきなのかは、目的によって異なります。そのためライセンス契約を締結する前には目的を明確にしてベストな形式で契約を結ぶために、さまざまな契約形態があることを知り、それぞれのメリットやデメリットを把握してベストな形式で契約を結びましょう!
ライセンス契約では、当事者間で交渉を何度も重ねたり遠方で契約を結んだりするなど手間や時間がかかるケースが多いです。
そこで便利なのが、スピーディに契約を締結できる電子契約です。
電子契約ツールには、以下のメリットが挙げられます。
またオンラインで契約を交わすため、電子媒体で契約書を保管できます。紙媒体では紛失などの恐れがありますので、管理面でも有用だと言えます。
ライセンス契約を検討している方におすすめしたい電子契約ツールは、電子印鑑GMOサインです。
電子サインだけでなく、電子証明書を利用した電子署名という方法でも契約を締結できるため、特に厳格な管理が求められるライセンス契約に向いています。
電子印鑑GMOサインを使って、スピーディかつ厳格にライセンス契約を締結してみてはいかがでしょうか。
\ 月額料金&送信料ずっとゼロ /
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
