\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

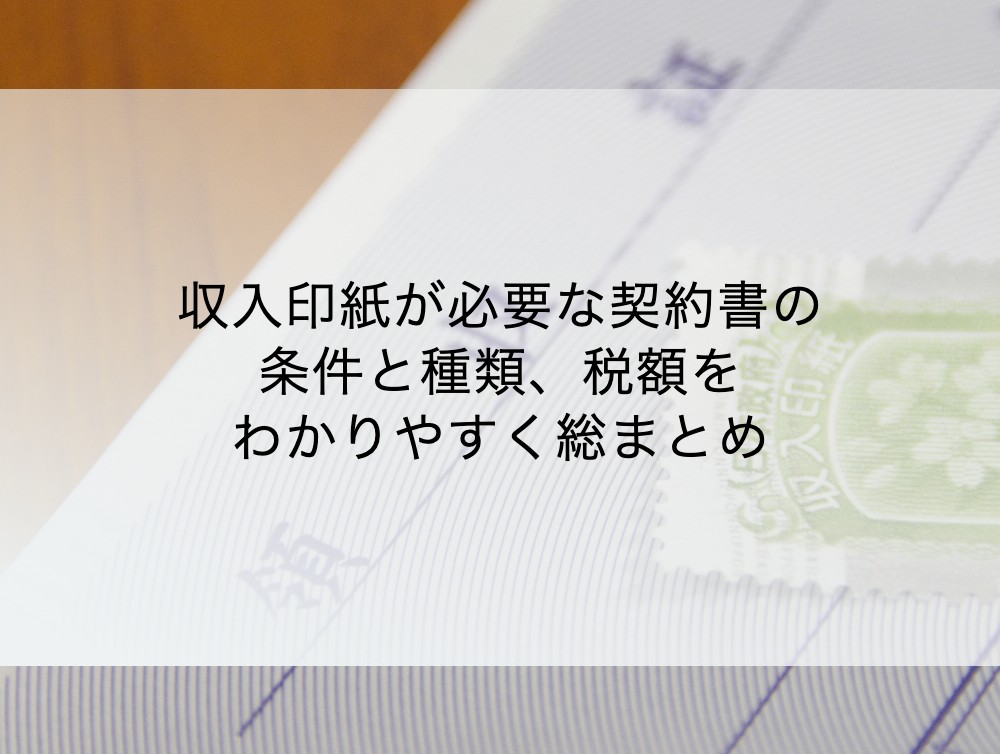
ビジネスや不動産投資、マイホーム購入など、重要な取引では契約書を作成しますが、契約書には収入印紙の貼付が必要となることが多くあります。
収入印紙は税金の納付を示す大事な証書であり、印紙が貼付されていないと大きなトラブルにつながります。
今回は、契約書における収入印紙の役割、必要な価格金額などについてご説明します。国税庁のホームページも出典としてご紹介しますので、そちらもあわせて必ずチェックしてください。
また、収入印紙について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


収入印紙は、あらゆる注文書、契約書、領収書、受取書などに貼付しなければならないわけではありません。
貼付対象となる書類は印紙税法に規定されており、その規定に外れるもの、あるいは非課税であると明示されているものは課税対象でないため、貼付の必要はありません。まずは収入印紙の定義と、貼付すべき契約書の条件についてご説明します。
収入印紙とは、印紙税の課税対象に該当する書面(「課税文書」といいます)に貼り付ける切手のような証票のことです。
印紙税は給料から天引きされる、あるいはコンビニエンスストア等に支払用紙を持ち込んで支払う、というものではなく、「収入印紙を購入し、課税文書に貼り付け、消印をすることで支払う(正確には支払ったことが証明できる)税金」です。
消印がないと、収入印紙を使い回していないことを証明できず、すなわち印紙税を納付したという証明にならないので注意が必要です。

収入印紙は、郵便局、法務局、コンビニエンスストアなどで購入できます。日本のどこでも入手しやすいもので、一般的な郵便切手とほぼ同サイズのものです。
課税文書に該当する書面は、印紙税法で定められた課税事項が記載されている文書です。全部で20種類あり、「第XX号文書」の形で呼ばれています。例えば、不動産売買契約書は「第1号文書」のひとつです。
こうした文書は、当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書でなければいけませんが、この目的で作成された契約書か否かは記載内容から判断されます。そのため、仮に契約書のタイトルが「不動産売買契約書」でなく「覚書」であっても、記載内容が印紙税法における「不動産売買に関する契約書」に該当すれば、印紙が必要な契約書(課税文書)として扱われますので、注意が必要です。
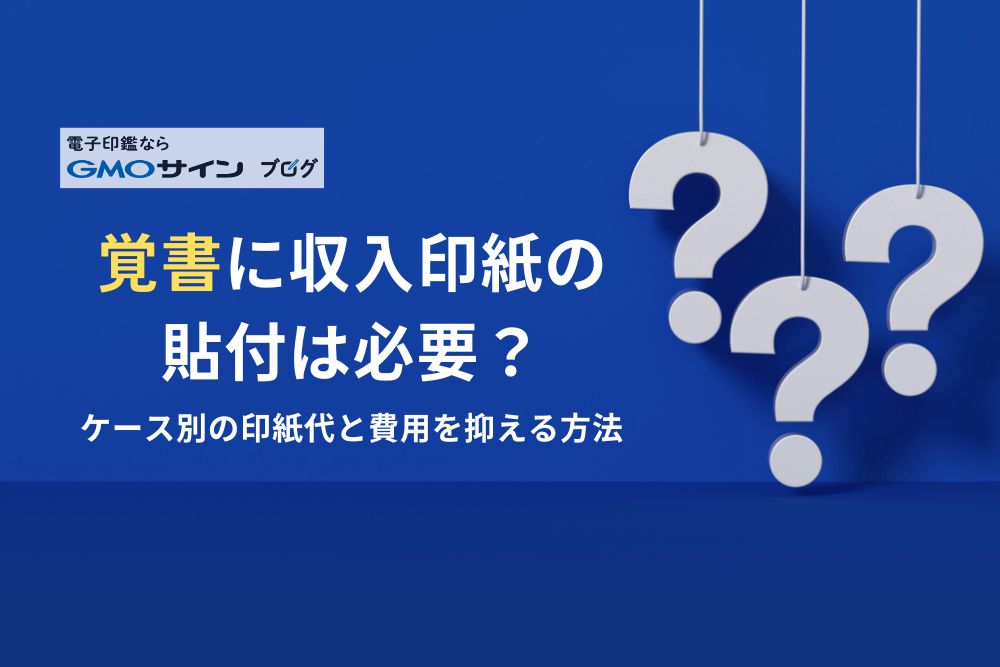
なお、契約内容が印紙税法の課税文書に該当しても、契約書に記載されている金額によって「非課税文書」となる場合があります。
例えば、レシートや領収書などの「金銭又は有価証券の受取書」について、受取金額が5万円未満のものは非課税です。そのため、私たちがスーパーやコンビニエンスストアで行う日常的な買い物のレシートに、収入印紙を貼付する必要がないのです。
【出典】国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
税抜金額5万円以上のものであっても、クレジットカードを利用して購入した領収書も収入印紙の貼付は不要です。クレジットカードによる取引は現金あるいは有価証券のやり取りが存在しない、「信用取引」にあたります。
国税庁は「クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭または有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、(中略)この領収書には印紙を貼付する必要はありません」という見解を示しています。
ただし、印紙税が不要になる条件として、領収書に「クレジットカードで支払った」という記載が必要です。
【参考】「クレジット販売の場合の領収書」
コンビニでコーヒーを買う、八百屋さんで野菜を買うといった単発契約の場合は印紙税が不要です。また、相手が不特定な場合、あるいは継続的な取引であっても3ヵ月以内で更新の定めがないものに関しても対象外となります。一方で、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書といった特定の相手との間で、継続的に生じる取引を前提の契約書は後述する7号文書にあたります。
印紙税は書面に対してかかる税金です。電子契約なら紙の契約書はありませんので、課税文書の作成にあたらないとされ、電子契約への収入印紙は不要となります。
国税庁は、課税対象となる文書の「現物の交付がなされない以上(中略)印紙税の課税原因は発生しない」と見解を示しています。ただし、プリントアウトして印鑑を押す場合、収入印紙が必要となる場合があるのでよく確認が必要です。
【出典】国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」別紙1-3
どんな契約で電子契約サービスが使えるのか?対象となる文書や契約類型の詳細についてはこちらの記事をご参照ください。
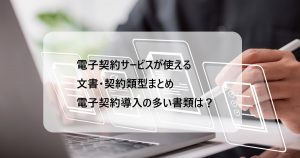
電子契約が使える文書・契約類型において書面による契約から電子契約に置き換えた場合、印紙税が不要になる分、契約にかかるコストを抑えることができます。
電子契約の導入による収入印紙税の削減など、費用対効果についてシミュレーションページより具体的にご確認いただけます。こちらもぜひご参考ください。
また、電子印鑑GMOサインの料金プランは下記のページに掲載しております。お試し用の無料プランもございますので、使い勝手やコスト削減、業務効率改善効果を検証した上で導入いただくことが可能です。

収入印紙の貼付対象となる契約書には、いくつか種類があります。また、その種類に応じて課税金額(購入・貼付すべき収入印紙の金額)も異なります。
ここでは、主な課税文書と税額についてご紹介します。
第1号文書には、先に挙げた不動産売買契約書を含めて4種類の契約書が規定されています。印紙税額は、記載された金額により異なります。
例えば、契約書に記載の金額が1万円未満であれば非課税ですが、1万円以上10万円以下だと200円、10万円を超え50万円以下だと400円などと定められています。
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などがこれにあたります。
なお、ここでいう無体財産権とは「特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権」のことであり、例えば「著作権の譲渡契約」は課税文書に該当します。
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などがあたり、建物賃貸借契約書は該当しません。
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。利息は、印紙税額を決定する記載金額には含まれません。
運送契約書、貨物運送引受書などが含まれます。乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。したがって、新幹線や飛行機などの高額なチケットであっても収入印紙を貼付する必要はありません。
ただし、令和6年(2024年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります。
【出典】国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
第2号文書は、「請負に関する契約書」の1種類だけです。ここでいう請負とは、請負人が相手方に対し仕事の完成を約束し、注文者が報酬を支払う契約形態を指します。
第2号文書には、工事請負契約書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書などがあります。第1号文書と同様、契約金額に応じて印紙税額も異なります。
ただし、令和6年(2024年)3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減措置が適用されます。
【出典】国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
第5号文書は、「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」です。ただし、会社法または、保険業法に規定する合併契約を証する文書か、会社法に規定する吸収分割契約または、新設分割計画を証する文書に限ります。
印紙税額は、一律で4万円です。
【出典】国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
第7号文書は、「継続的取引の基本となる契約書」です。売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などが挙げられます。
契約期間が3カ月以内で、更新の定めのないものは除きます。ただし、第7号文書には該当しなくても、第1号文書や第2号文書に該当する可能性もあるため注意が必要です。
印紙税額は、一律で4,000円です。
【出典】国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
スクロールできます【出典】国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
号 文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき) 1
*不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
*地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
*消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
*運送に関する契約書(傭船契約書を含む)
運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円
※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。
(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)2 *請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています
(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)3 *約束手形または為替手形
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本または謄本は非課税です。記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの記載された契約金額が
・10万円未満:非課税
・10万円以上:200円4 *株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
・500万円以下:200円
・500万円を超え1千万円以下:1千円
・1千万円を超え5千万円以下:2千円
・5千万円を超え1億円以下:1万円
・1億円を超えるもの:2万円
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
スクロールできます【出典】国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
号 文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき) 5 *合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書
(注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。4万円 6 *定款
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。4万円
(非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)7
*継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など4千円 8 *預金証書、貯金証書
200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)9 *倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
200円 10 *保険証券 200円 11 *信用状 200円 12 *信託行為に関する契約書 (注) 信託証書を含みます。
200円 13 *債務の保証に関する契約書 (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)14 *金銭または有価証券の寄託に関する契約書 200円 15 *債権譲渡または債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が
・1万円未満:非課税
・1万円以上:200円
・契約金額の記載のないもの:200円16 *配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が
・3千円未満:非課税
・3千円以上:200円
・配当金額の記載のないもの:200円17 *売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など記載された受取金額が
・5万円未満:非課税
・5万円以上100万円以下:200円
・100万円を超え200万円以下:400円
・200万円を超え300万円以下:600円
・300万円を超え500万円以下:1千円
・500万円を超え1千万円以下:2千円
・1千万円を超え2千万円以下:4千円
・2千万円を超え3千万円以下:6千円
・3千万円を超え5千万円以下:1万円
・5千万円を超え1億円以下:2万円
・1億円を超え2億円以下:4万円
・2億円を超え3億円以下:6万円
・3億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:15万円
・10億円を超えるもの:20万円
・受取金額の記載のないもの:200円
非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの*売上代金以外の金銭または有価証券の受取書 (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が
・5万円未満:非課税
・5万円以上:200円
・受取金額の記載のないもの:200円
非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの18 *預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 ・1年ごとに200円
非課税文書:
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳19 *消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円 20 *判取帳
1年ごとに4千円

税金や法律に関わることであるため、実務で収入印紙を使う際、「これはどう考えればいいの?」と疑問に思うことが多く出てきます。
最後に、よくある質問と回答を見ていきましょう。
契約には2者以上が関わりますが、収入印紙の代金は原則として課税文書を作成した者が負担することになっています。ただし、2通を作成して双方が1通ずつ保管する契約書の場合、2通とも収入印紙が必要なため、双方が連帯して1通ずつ印紙代を負担することが一般的です。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ当事者間で決めておくようにしましょう。
収入印紙の貼付位置は、左上の余白部分であることが一般的です。貼り付けた後には、契約書に押印した印鑑もしくは署名で消印を行います。
印紙税法は、一度貼付した印紙の再使用を防ぐため、契約書に貼付した収入印紙と契約書の両方に印影がかかるように契約者の押印または署名をすることを定めています。消印を行わなかった場合、契約書に貼付した印紙の額と同じ額を過怠税(かたいぜい)として徴収されますので、注意が必要です。
収入印紙の貼付をもって納税となるわけですから、課税文書となる契約書で収入印紙を貼らなかった場合は、脱税とみなされてしまいます。
税務署に課税文書に印紙が貼付されていない旨を指摘された場合、過怠税として本来納付すべき金額の3倍が課せられます。本来納付すべき印紙税に加えて、印紙税の2倍の過怠税を払わなければいけません。貼り忘れのないよう、注意してください。

今回のご説明内容は2021年7月時点の印紙税法に基づいており、その内容は今後、変更される可能性があります。
収入印紙の貼付ミスは脱税とされ、過怠税の徴収や企業のブランド力の毀損(きそん)につながってしまいます。ぜひ国税庁のホームページやニュースをチェックし、ミスのないよう気をつけましょう。
また、収入印紙のコストについて削減・改善したい場合には電子契約の導入もおすすめです。詳細について、電子印鑑GMOサインでは無料でご参加いただける入門セミナーなど毎月開催していますので、ぜひご利用ください。


電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
