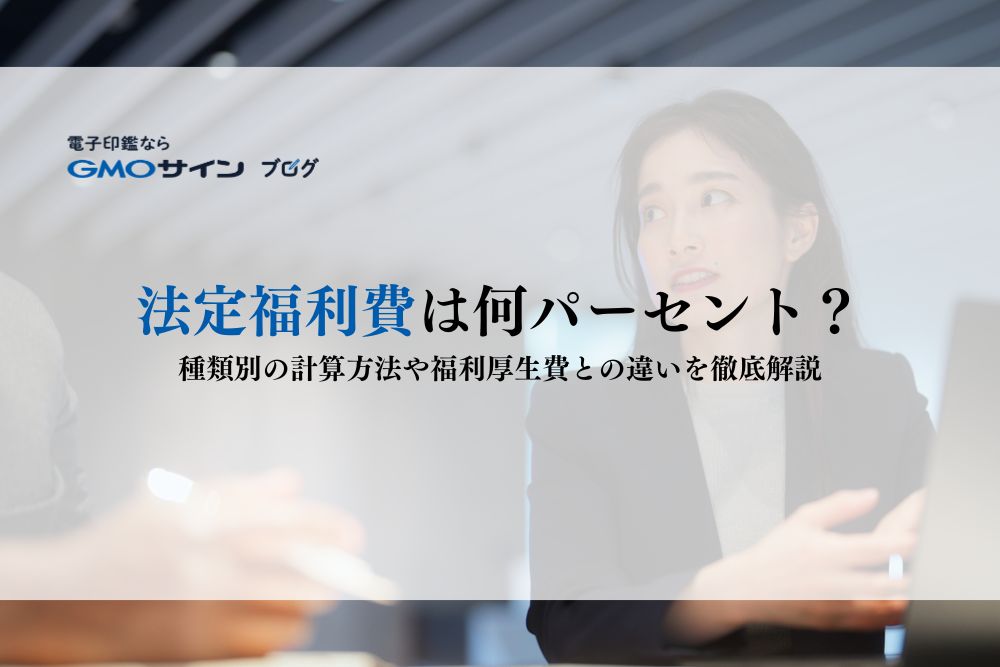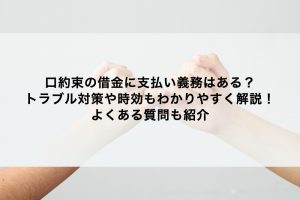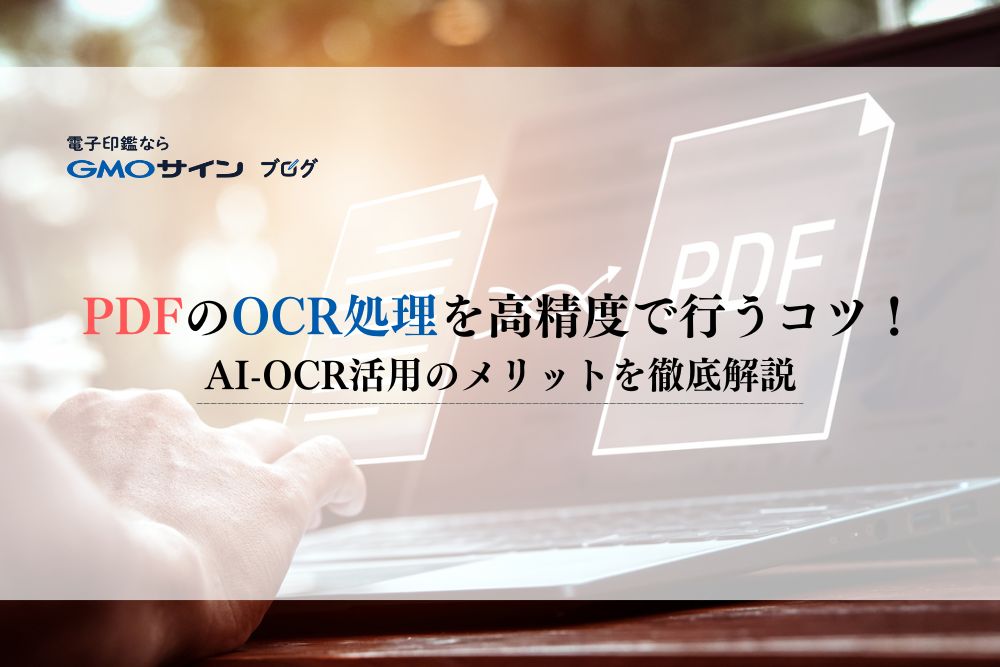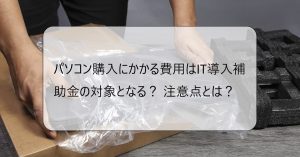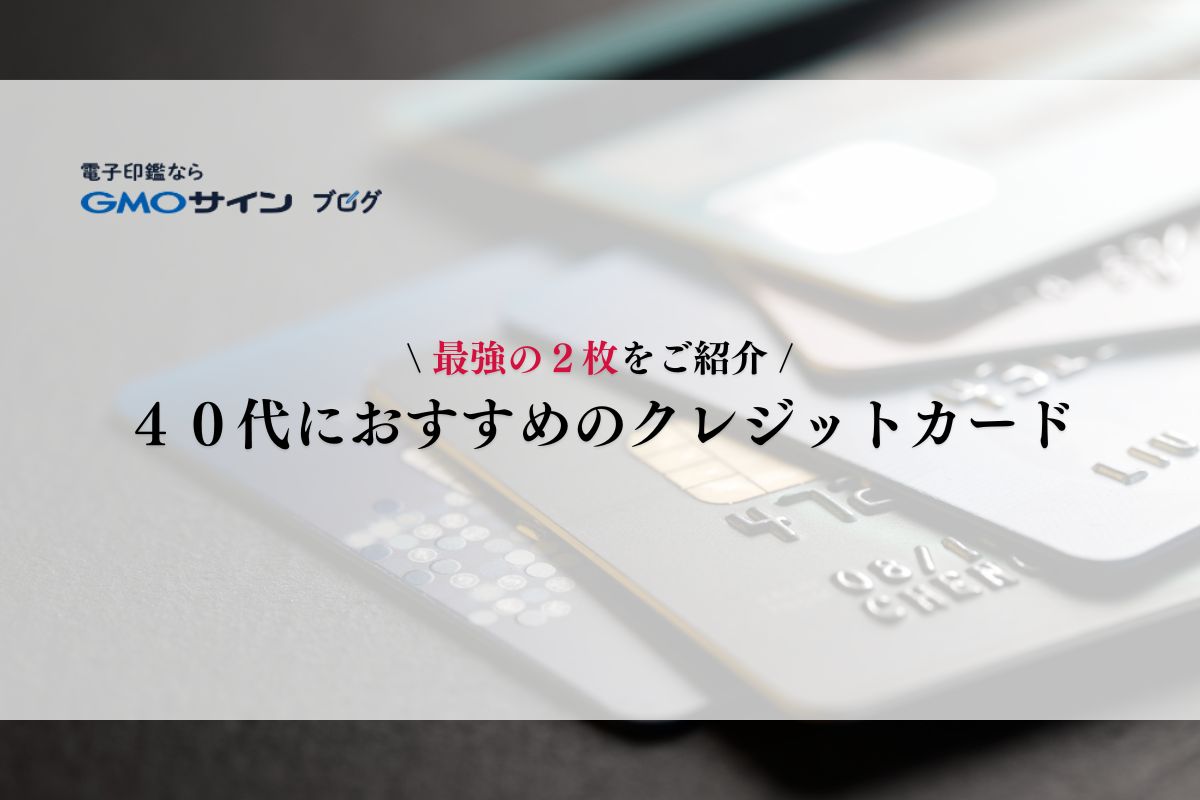契約書の「目的条項」は、契約の冒頭に位置づけられ、当事者間で交わす取引の趣旨や背景、意図を明文化する重要な条項です。
一見すると形式的に思われがちですが、契約内容の解釈やトラブル発生時の判断材料としても機能するため、曖昧な記載はリスクにつながります。特に業務委託契約や秘密保持契約では、目的条項の記載が契約全体の有効性や実効性を左右するケースもあり、企業法務において非常に重要な条項です。
本記事では、目的条項の役割や必要性、契約別の記載例、作成時のポイントまでを徹底解説。実務にすぐ活かせる知識として整理しました。
契約書の目的条項とは?
契約書における目的条項とは、当事者間で交わす取引の目的や内容、背景などを記載する条項です。
契約書の冒頭に位置づけられ、「第1条(目的)」として記載されるケースが一般的です。たとえば「本契約は、〇〇を目的とする」などの形式で、契約の全体像を簡潔に示します。
目的条項は、直接的に権利義務を規定するものではないため、軽視されがちですが、契約の意図や背景に関する共通認識を形成するために不可欠な要素です。とくに契約内容の解釈や争点が生じた際、目的条項は重要な参考情報となります。

契約書における目的条項の役割
目的条項は、契約の主旨や背景を明確にすることで、当事者間の認識を一致させる役割を果たします。
ここでは、契約書における目的条項の役割についてみていきましょう。
契約の主旨を明確にする
契約書における目的条項は、取引の目的や内容を当事者間で明確に共有するために存在します。
契約書の記載が不明確な場合や債務不履行の場合には、その解釈の拠り所として目的条項が参照される場合があるため、非常に重要です。とくに秘密保持契約では、目的条項に基づき「目的外使用」が制限されるため、内容が契約の有効性や制限範囲に直結します。
契約条件を適切に解釈できるようにする
契約書に不明確な表現が含まれている場合、裁判や行政判断においては「契約の解釈」が求められます。この際に重視されるのが、当事者の真意や契約の背景を示す目的条項です。
たとえば、民法では「取引上の社会通念に照らして契約の内容に適合していない場合」に契約不適合責任が問われますが、この「社会通念に照らす」判断基準として、契約書内の目的条項が用いられます。
契約当事者が「どのような目的で契約を結び、何を達成したかったのか」が明文化されていることで、契約全体の解釈に一貫性を持たせやすくなります。
曖昧な目的条項が招くリスク
目的条項は形式的な条文と見なされがちですが、その記載が曖昧だと、契約解釈の基準として機能せず、解釈のずれや争いを招く原因になります。
とくに契約文言にあいまいな表現が含まれている場合、目的条項の不備が重大なリスクにつながることがあるため注意が必要です。
契約内容の解釈の違いを巡る紛争
前述のとおり、契約に曖昧さがある場合、目的条項が契約全体の趣旨を示す手がかりとなります。
そのため目的条項自体が曖昧だったり、テンプレートの流用によって実情と合っていない場合、かえって紛争を引き起こす原因になりかねません。
以下にトラブルの具体例をまとめましたので、参考にしてください。
具体例1:業務委託契約の場合(納品期限をめぐるトラブル)
契約書には「業務完了後、速やかに納品する」とのみ記載されていたが、発注側は「3営業日以内」、受託側は「1週間以内」と解釈。
目的条項に「本業務は〇月のキャンペーン運用に必要な制作物を完成させるためのものである」と記載していれば、納品期限を共通認識とすることが可能です。
具体例2:秘密保持契約の場合(秘密情報の範囲をめぐる対立)
目的条項に「今後の協業に向けた情報交換」とのみ記載されていたが、後に開示した営業戦略資料が「契約の目的外」として利用されていた。
目的条項で「新製品開発に関する事業提携の検討」と明記されていれば、使用範囲の逸脱を主張できる場合があります。
債務不履行責任のリスク
契約書の目的条項は、債務不履行責任の判断にも影響を及ぼす重要な要素です。
たとえば請負契約では、成果物が種類・品質・数量の面で「契約の内容」に適合しているかどうかが争点となりますが、その判断にあたり、契約の目的が明記されていれば「どのような状態であれば目的が達成されたといえるか」が明確になります。
ソフトウェア開発契約であれば「業務効率の向上を目的とする」と明示されていれば、実際に開発された成果物が効率向上に寄与しなければ、債務不履行と判断される可能性があるのです。
このように、目的条項の内容は、契約の成果が妥当か否かを判断する基準として機能します。
目的条項に記載すべき要素
契約書の目的条項を作成する際は、「なぜこの契約を結ぶのか」「誰が何をして何を達成するのか」を簡潔に記載する必要があります。
取引の背景や契約の動機、対象業務の範囲、最終的な目的などを論理的に整理することで、契約内容の理解が深まり、トラブル予防にもつながります。形式に沿いつつも、実務に即した情報を盛り込みましょう。
目的条項に記載すべき主な要素は、以下の通りです。
- 契約締結の背景・動機(業務効率化のため、新事業の検討に向けてなど)
- 契約の目的(最終的に達成したい成果や方向性)
- 契約の対象(業務範囲や製品、情報など)
- 手段・方法(何をどうするかの概要)
- 当事者間の関係性・役割分担(特に委託・請負など)
【契約別】目的条項の記載例
契約の種類によって、目的条項に求められる記載内容や重点は異なります。
ここでは、実務でよく使われる契約類型ごとに、どのような情報を目的条項に盛り込むべきかを具体的に解説します。
条文例もあわせて紹介するので、作成時の参考にしてください。
業務委託契約の目的条項の記載例
業務委託契約とは、企業が自社業務の一部を外部の事業者に委託する際に締結する契約です。Web制作、営業支援、経理代行、SNS運用、ライティング業務など、専門性や効率性を重視する場面で活用されます。
目的条項では、「何の業務を、何のために委託するか」を明確に記載することで、業務範囲や成果物への期待が当事者間で共有され、認識のズレを防ぐことが可能です。
また契約不適合責任や納期遅延など、後のトラブルの回避にもつながります。
目的条項の記載例1:Web制作業務の場合
第〇条(目的)
本契約は、委託者が自社商品のプロモーション活動の一環として、受託者に対しランディングページのデザインおよびコーディング業務(以下「本業務」という)を委託し、本業務の遂行に関する条件を定めることを目的とする。
目的条項の記載例2:営業支援業務の場合
第〇条(目的)
本契約は、委託者が新規顧客の獲得を目的として、受託者に対し見込み顧客リストの作成およびアポイント獲得業務(以下「本業務」という)を委託し、当該業務の内容および履行条件を明確にすることを目的とする。

秘密保持契約の目的条項の記載例
秘密保持契約(NDA)は、当事者間で機密情報を共有する際に、その情報の漏洩や目的外利用を防ぐために締結されます。
初期段階の業務提携やM&Aの検討では、まだ具体的な契約が成立していないにもかかわらず、経営情報やノウハウの共有が必要となるため、目的条項において「何のために情報を開示するのか」を明示しておくことが極めて重要です。
目的条項が曖昧だと、「この情報は契約の目的に含まれていたか」「使用目的に反しているか」といった解釈を巡るトラブルの原因となりかねません。
以下に、シーンごとの具体例を示しますので参考にしてください。
記載例1:業務提携の検討に関する秘密保持契約
第〇条(目的)
本契約は、甲および乙が新規事業領域における業務提携の可能性について検討するにあたり、両者が相互に開示する営業情報、技術資料その他の秘密情報の管理および使用範囲を定めることを目的とする。
記載例2:M&Aに関連する秘密保持契約
第〇条(目的)
本契約は、甲が乙の株式取得を含む企業買収の実施可能性について検討するに際し、乙から開示される財務資料、顧客情報等の秘密情報について、その管理および取扱条件を明確にすることを目的とする。

売買取引基本契約の目的条項の記載例
売買取引基本契約とは、同じ取引先との間で継続的に商品や製品を売買する場合に、個別取引ごとに条件を繰り返し取り決める手間を省くため、共通のルールを事前に取り決めておく契約です。
目的条項では、どのような商品を、どのような形で取引していくのか、当事者の関係性や取引の性質を明確にすることが求められます。
また、不動産のように一度きりの売買であっても、目的条項において取引対象の性質や目的を明記しておくことで、契約不適合責任を巡るトラブルを未然に防ぐ効果が期待できるでしょう。
記載例1:継続的な商品売買契約の場合
第〇条(目的)
本契約は、乙が製造・販売する電子部品を、甲が継続的に仕入れ・使用することを前提に、両者の基本的な売買取引条件および当該取引に伴う権利義務関係を明確に定めることを目的とする。
記載例2:不動産売買契約の場合
第〇条(目的)
本契約は、甲が所有する東京都新宿区内の事業用建物(以下「本物件」という)を、乙が自社オフィス移転のために購入することを目的とし、当該売買契約に関する諸条件を定めるものである。

良い目的条項の書き方のポイント
目的条項は、ただ契約の背景を説明するだけではなく、契約全体の「前提」を明確にする重要な要素です。
ここからは、良い目的条項の書き方のポイントを解説していきます。
5W1Hを徹底する
目的条項を明確に記載するためには、「5W1H」の観点を意識することが非常に効果的です。契約文は簡潔さが求められる一方で、抽象的な表現にとどまると、後の解釈に差が出てトラブルを招く恐れがあります。
5W1Hを用いて内容を整理することで、契約の目的が一目で理解でき、他条項との整合性も取りやすくなります。
| 観点 | 意味 | 目的条項での表現例 |
| Who(誰が) | 契約当事者(甲・乙など) | 「委託者である甲と受託者である乙は…」 |
| What(何を) | 契約の対象となる業務や物品 | 「〇〇業務の実施」「〇〇商品の販売」 |
| Why(なぜ) | 契約締結の動機・背景 | 「業務効率化のため」「市場拡大を目的として」 |
| When(いつ) | 履行時期・契約期間 | 「〇年〇月〇日から開始する」「契約期間中」 |
| Where(どこで) | 業務遂行や納品の場所 | 「甲の事業所にて」「クラウド上で共有」 |
| How much(いくらで) | 対価や報酬、価格設定など | 「報酬は金〇円とする」「定価に基づき算出」 |
解釈が分かれないように具体的かつ簡潔に記載する
目的条項は、契約の対象となる商品やサービスの内容、取引の範囲などを端的かつ明確に記載することが重要です。
業務内容が多岐にわたる場合や、独自の用語・ルールがある場合は、具体的な業務範囲や期待される成果の記述がトラブル予防につながります。
なお、秘密保持契約では情報の利用が「契約の目的」内に限られることが多く、目的条項が使用範囲の判断基準となるため重要です。
目的条項を作成・レビューする際の注意点
目的条項は形式的に見えがちですが、契約全体の理解や他条項の運用に大きく関わる重要な要素です。
ここからは目的条項をレビューする際の注意点について解説していきます。
契約締結の動機や取引経緯が記載されているか
目的条項は、契約内容に疑義が生じた際に当事者の意図を補完する重要な手がかりになり得ます。
とくに契約不適合責任が問われる場面では、契約締結時の動機や背景が重視されるため、「なぜこの契約を結んだのか」「どのような成果を期待していたのか」が明確であることが重要です。
「業務効率化のため」や「新規市場への参入を視野に」などの文言が記載されていれば、成果物が目的に適合しているかどうかの判断基準となります。
提供すべきサービス・商品が明確か
目的条項では、契約に基づいて提供されるサービスや成果物の「性質」や「範囲」を明示することも欠かせません。抽象的な表現にとどまると、納品物の内容や品質をめぐって解釈が分かれ、トラブルの火種となることがあります。
たとえば、業務委託契約で「マーケティング支援」とだけ記載していた場合、具体的に何を提供するのか(資料作成、広告運用、戦略提案など)が当事者間でずれる可能性があります。一方で、「SNS運用方針の立案およびレポート作成業務」と記載すれば、業務の内容と範囲が明確になり、後の解釈のぶれを防げます。
契約書全体に合った内容となっているか
目的条項は契約の背景や全体の方向性を示すものであり、他の条項との整合性が求められます。
内容が抽象的すぎたり、実態とずれていると、契約の解釈に混乱を招き、権利義務の範囲が不明確になるおそれがあります。
記載は簡潔で構いませんが、以下のような点が明確になっているかを確認しましょう。
- どのような商品・サービスが取引対象なのか
- 当事者間で発生する主要な権利義務は何か(例:販売・購入、委託・受託など)
- 継続的な取引であるかどうか
- 特許のライセンスなど、特有の事情がある場合はその旨
目的条項を疎かにしないことが、契約トラブルを防ぐ第一歩
契約書の目的条項は、一見すると形式的な条文に思えるかもしれませんが、実は契約全体の理解や運用に深く関わる重要なパートです。
契約の背景や意図、業務範囲などを明記することで、当事者間の認識を共有でき、解釈のズレやトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。特に、秘密保持義務や契約不適合責任など、目的の解釈が実務や法的判断に影響するケースでは、目的条項の記載が判断基準として参照されることもあります。
本記事で紹介したように、契約の種類や内容に応じて適切な要素を盛り込み、契約書全体との整合性を意識した記載を心がけましょう。目的条項を丁寧に設計することが、契約の信頼性と実効性を高めるための第一歩となります。