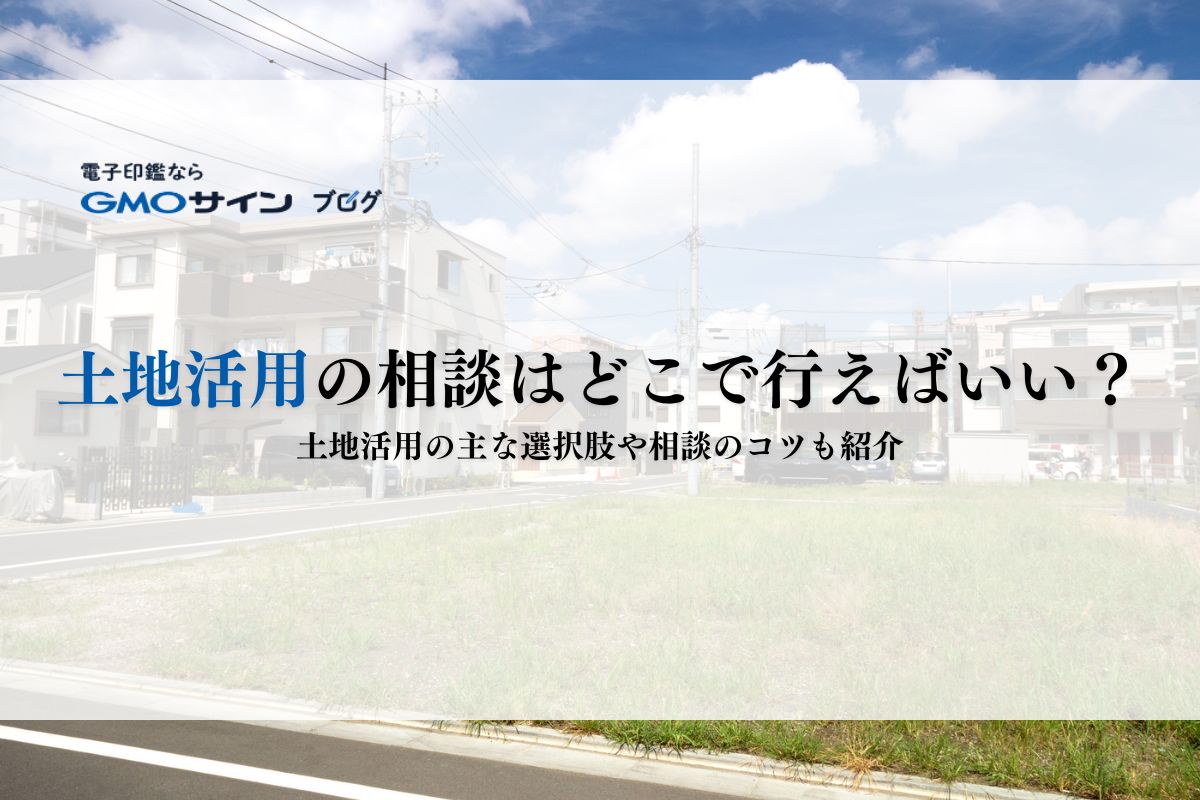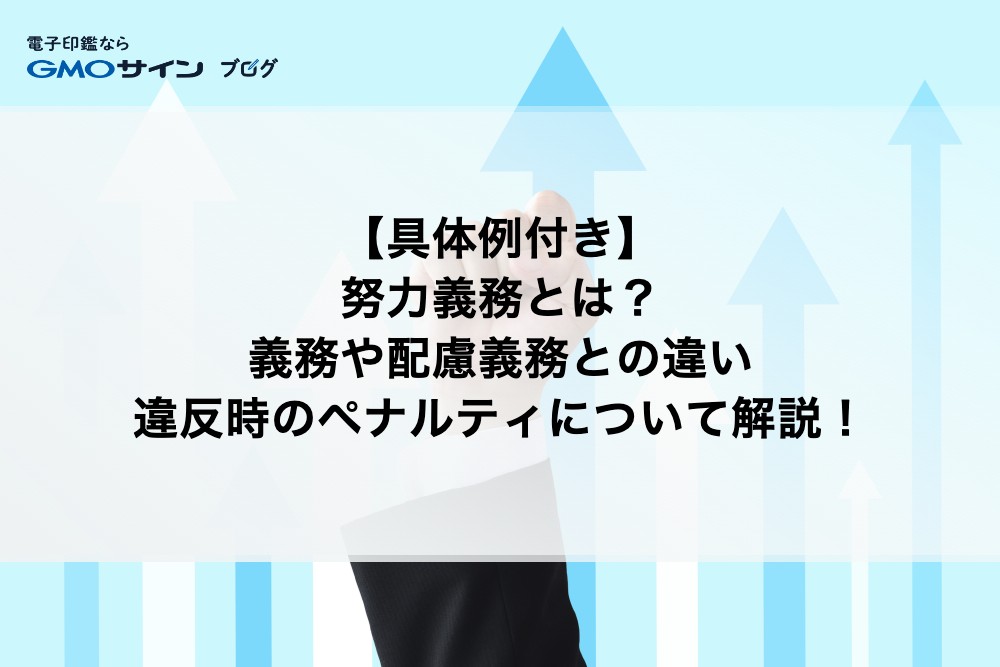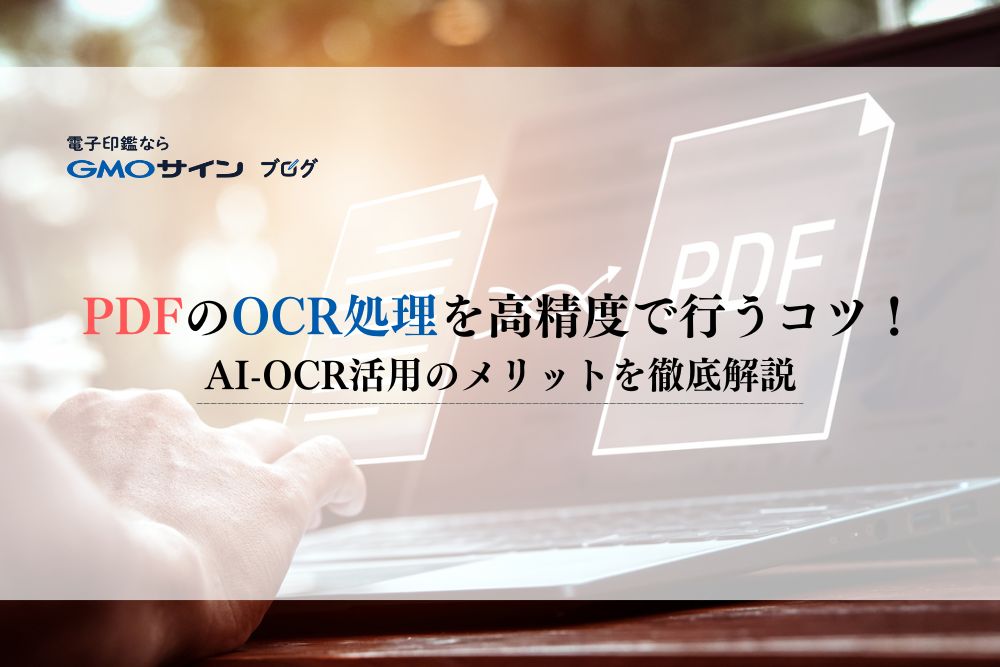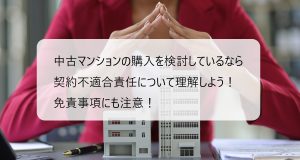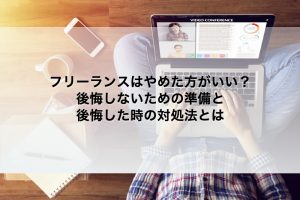\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

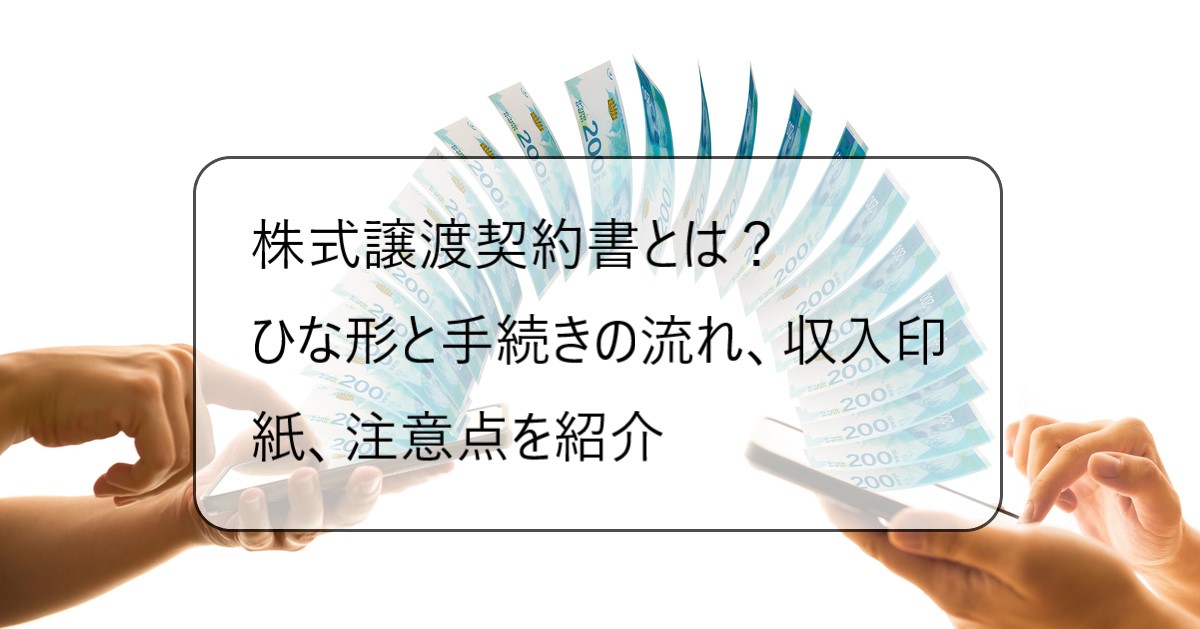
株式譲渡を行う際には、株式譲渡契約書の作成が推奨されます。株式譲渡契約書とは、株式譲渡に関する事柄を定めた契約書のことで、株主の氏名・会社情報・譲渡価額・対価の支払い方法などが記載されています。
株式譲渡は、会社の経営権が移転する場合や譲渡代金が高額に及ぶ場合があり極めて重要な取引であるため、契約書は不備のないよう慎重に作成しなければなりません。
そこで今回は、株式譲渡契約書の定義・ひな形(テンプレート)をご紹介します。株式譲渡契約書に必要な記載事項や貼付が求められる収入印紙の金額についても解説しますので、株式譲渡契約をスムーズに締結するためにも、ぜひ本記事をご参考ください。
株式譲渡契約書(Stock Purchase Agreement、略称:SPA)とは、企業の株式を売買する際に使用される文書のことです。この契約書の作成にあたって、売り手と買い手の間で株式の売買に関するすべての条件と事項を定めることで、双方の権利・義務を明確にできます。
株式譲渡契約書は、株式の売買における双方の合意事項を正確に記録するために必要な書類です。文書化することで、後々のトラブルを防ぎ、双方が安心して取引を進められるようになります。
株式の譲渡とは、株式を他人に譲る意思をもって譲ることです。この株式譲渡の一種として、株式売買があります。
株式売買とは、株式譲渡の対価として一定の金銭を受け取ることです。つまり、株式譲渡の中でも、譲渡する株式の対価として、特に金銭を受け取る場合を株式売買といいます。ちなみに、対価のない株式譲渡は、株式贈与と定義されます。
株式譲渡契約の手続きは、事業者間での株式の売買を円滑に進めるための重要なプロセスです。以下に、株式譲渡契約手続きの大まかな流れをまとめました。
売り手と買い手双方の意向を確認し、大まかな条件を整理
譲渡に関する詳細な条件を明記した契約書の草案を作成
売り手の財務状況や法的問題を詳細に調査
双方が契約書の内容に合意したら、最終的な契約書を作成
契約書に署名・捺印し、正式に契約を締結
契約に基づき、株式の引渡しを実行
譲渡後、必要に応じて商業登記の変更手続きを行う
株式譲渡に伴う税金の申告や支払いの手続きを行う
株式譲渡契約に必要な手続きは契約の内容や双方の合意により異なるため、法律の専門家と密に連携し、適切な手続きを遂行することが重要です。
本章では、有償・無償の取引に分けて、株式譲渡契約書のひな形(テンプレート)の一例を順番に紹介します。
ここで紹介するひな形は一般的な内容を反映しておりますが、具体的な取引の内容や法律上の要件に応じて、専門の法律家からサポートを受けながら作成することをおすすめします。
【株式譲渡契約書】
売り手: [売り手の氏名または会社名、住所]
買い手: [買い手の氏名または会社名、住所]
・第1条(譲渡する株式)
売り手は、買い手に対し、[会社名]の普通株式[譲渡株式数]株を、本契約に基づき譲渡する。
・第2条(譲渡価格)
譲渡する株式の価格は、[金額]円とする。
買い手は、上記金額を売り手指定の銀行口座に[支払い期限]までに支払うものとする。
・第3条(株式の引渡し)
売り手は、買い手から譲渡価格の全額を受領した後、[引渡し日]に譲渡する株式を買い手に引き渡す。
・第4条(保証)
売り手は、以下の事項を保証する。
売り手は、譲渡する株式を自由に譲渡できる権利を有している。
譲渡する株式には、第三者の権利が存在しない。
・第5条(協議解決および管轄裁判所)
本契約書に定めのない事項および本契約書の解釈に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
本契約に関連する紛争が生じた場合、[管轄裁判所]を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約書は、売り手と買い手が署名または記名・捺印の上、各1通ずつ保有する。
[作成日]
売り手: [署名または記名・捺印]
買い手: [署名または記名・捺印]
【株式譲渡契約書(無償)】
譲渡人: [譲渡人の氏名または会社名、住所]
譲受人: [譲受人の氏名または会社名、住所]
・第1条(譲渡する株式)
譲渡人は、譲受人に対し、[会社名]の普通株式[譲渡株式数]株を、無償で譲渡する。
・第2条(株式の引渡し)
譲渡人は、[引渡し日]に譲渡する株式を譲受人に引き渡す。
・第3条(保証)
譲渡人は、以下の事項を保証する。
譲渡人は、譲渡する株式を自由に譲渡できる権利を有している。
譲渡する株式には、第三者の権利が存在しない。
・第4条(協議解決および管轄裁判所)
本契約書に定めのない事項および本契約書の解釈に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
本契約に関連する紛争が生じた場合、[管轄裁判所]を専属的合意管轄裁判所とします。
本契約書は、譲渡人と譲受人が署名または記名・捺印の上、各1通ずつ保有する。
[作成日]
譲渡人: [署名または記名・捺印]
譲受人: [署名または記名・捺印]
本章では、株式譲渡契約書に記載する事項のうち、代表的な7つの項目をピックアップし、順番に解説します。
株式譲渡の内容は、株式譲渡契約書の中で最も基本的な事項です。一般的には、下記の内容を定めます。
●株式の銘柄
●株式の種類
●株式数
●譲渡の対価
●譲渡実行日
株式を売り手から買い手へ正式に移すことを、クロージングと呼びます。クロージングの段階は株式譲渡の最終手続きであり、以下のような重要な事項をきちんと定める必要があります。
●譲渡対価の支払方法
●株式の移転
そのほか、株券不発行会社の場合の手続きとして、株式の移転後に株主名簿への新しい所有者の記載が求められます。
株式の移転と代金の支払いには、特定の条件を設けるのが基本です。この条件を前提条件と呼び、売り手と買い手それぞれが負うべき義務が発生します。
例えば、売り手が株式の所有権を持っていること、買い手が約束された方法で支払いを行うことなどが、代表的な前提条件です。
相手方が一つでもこれらの前提条件を満たしていない場合、株式譲渡の実行義務は発生しません。これは、契約が無効となる保護措置の一つです。しかし、場合によっては、ある当事者が任意で相手方の前提条件を免除することも可能です。
株式譲渡契約書では、売主と買主が自分自身や対象となる会社に関する重要な事項が真実かつ正確であると保証することが求められます。これを「表明保証」といいます。
例として、売主が売り渡しをする株式の所有権を持っている、会社の財務状況が正確に報告されているなど、重要な情報に誤りがないことを確約するものです。
通常、売主側の表明保証を特に重視し、詳細に定めることが一般的です。これは、買主が購入する前に、会社に隠れた問題がないかをしっかり確認するための手段となっています。
株式譲渡契約では、売主と買主が取引の前後で守るべきルールや義務が設定されます。以下に、代表的な例を挙げて説明します。
●取引の前に守るべき義務:売主の競業避止義務、売主の財産の流出防止義務
●取引の後に守るべき義務:買主の雇用維持義務
株式譲渡契約の締結後、クロージング前に株式譲渡契約を解除できる事由を記載します。例えば、以下のような事項です。
●契約違反と評価できる事実があったこと
●譲渡実行前提条件が不足していること
●重大な表明保証違反や遵守事項違反があったこと
ここまでに紹介した事項のほか、秘密保持に関する条項や反社会的勢力の排除に関する条項、損害賠償に関する条項などを定めることもあります。
株式譲渡契約書は、基本的には印紙税の対象ではないため、通常は収入印紙を貼る必要がありません。
しかし、特定の状況下での例外があります。具体的には、株式の買い手が売り手に対して代金を前払いし、契約書が「受取書」の役割も果たしている場合です。このような場合、一定の金額の収入印紙を契約書に貼る必要が生じます。
下表に、株式譲渡契約書に貼付する収入印紙の金額をまとめました。
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 30,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
株式譲渡契約を締結する際には、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。本章では、2つの注意点をピックアップし、順番に解説します。
株式譲渡契約書を含めて、法人の取引に関する契約書の保管期間は通常7年間です。契約書のみならず、帳簿書類や取引で作成・受領した書類も7年間保管しなければなりません。
なお、欠損金の繰越控除の適用を受けている場合、欠損金が生じた事業年度における契約書の保管期間は10年間となるため注意しましょう。
一方で、個人間の株式譲渡契約の場合、法律上の定めは特にありませんが、確定申告に契約書を使用した場合であれば、5年間保管しなければなりません。
個人間の取引についても、株式譲渡契約書を作成する法的な義務はありません。とはいえ、契約の内容を明らかにし、後々のトラブルを回避するためにも、契約書は必ず作成しておくことをおすすめします。
最後に、株式譲渡契約書についてよくある疑問と回答をまとめました。
契約書の保管方法には、紙やマイクロフィルム、電子データによる保管があります。各方法で異なるメリット・デメリットがあるため、自社に適した方法を採用しましょう。
| 保管方法 | 主なメリット | 主なデメリット |
| 紙 | 特別なシステムが不要で誰でも管理可能 | 保管スペースが必要 探すのに時間がかかる |
| マイクロフィルム | 長期保存できる | 電子データよりも、 広い保管スペースが求められる |
| 電子データ | 保管コストを削減できる 検索の手間を削減できる | 電子契約サービスを導入する場合、 導入コスト・維持費が必要 |
主に以下のような目的で創業者(経営者)は会社の株式を譲渡します。
●家族に株式を分け与えたい
●従業員に株式を分け与えたい
●外部の協力者に株式を分け与えたい
●会社の事業を第三者に売却したい
株式譲渡契約書とは、企業の株式を売買する際に使用される文書のことです。売り手と買い手の間で株式の売買に関するすべての条件と事項を定めるため、双方の権利・義務を明確にできます。
ひな形や記載事項、手続きの流れを活用し、株式譲渡契約書をスムーズに作成しましょう。
なお、最近では株式譲渡契約書の保管方法として、電子データで保管する動きが進んでいます。電子データで契約書を保管することで、保管コストを削減できたり、検索の手間を削減できたりするほか、電子契約を導入する場合は収入印紙代を節約できるメリットもあります。
電子契約の導入をご検討でしたら、電子契約サービス電子印鑑GMOサインの利用がおすすめです。電子印鑑GMOサインは、株式譲渡契約書のほか、発注書・受注書・領収書・検収書など相手方の署名を必要としない書類に電子署名を行えます。
無料プランと有料プランを用意しておりますので、まずは無料プランから試しに導入してみてはいかがでしょうか。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。