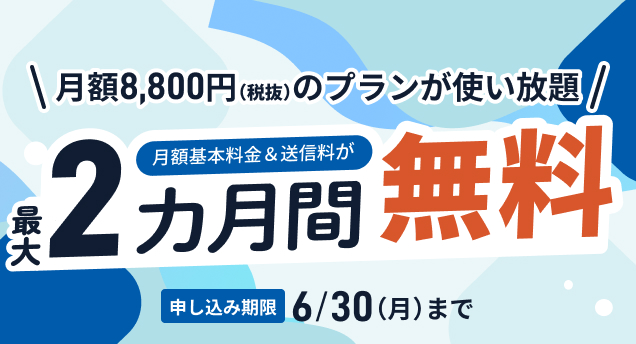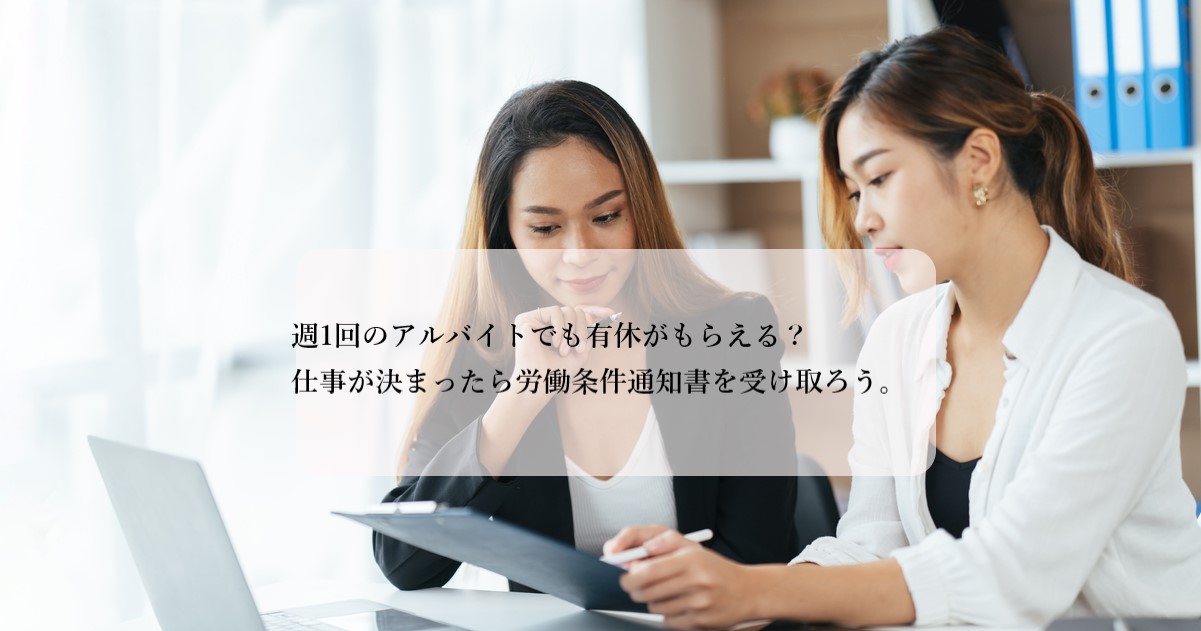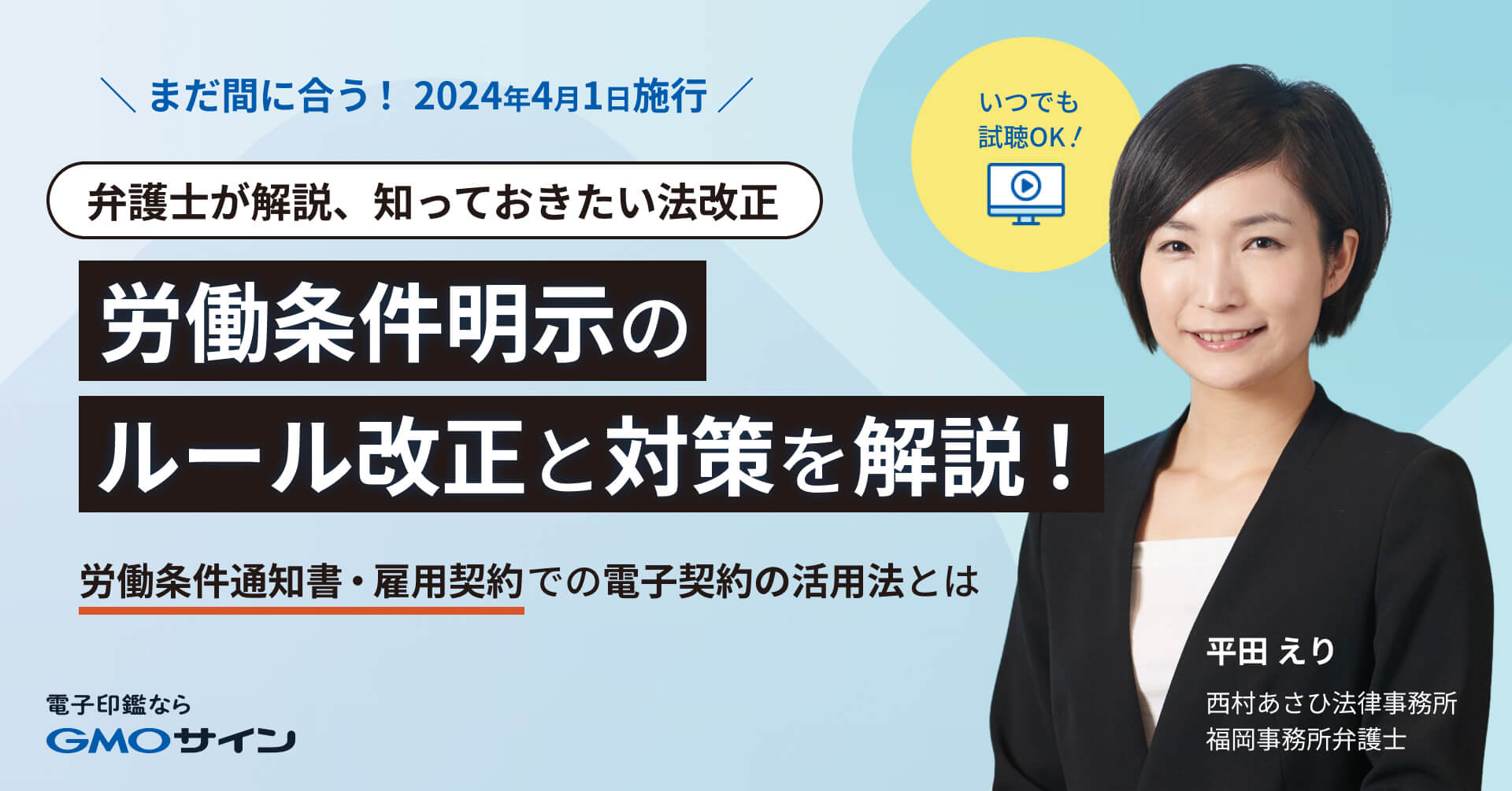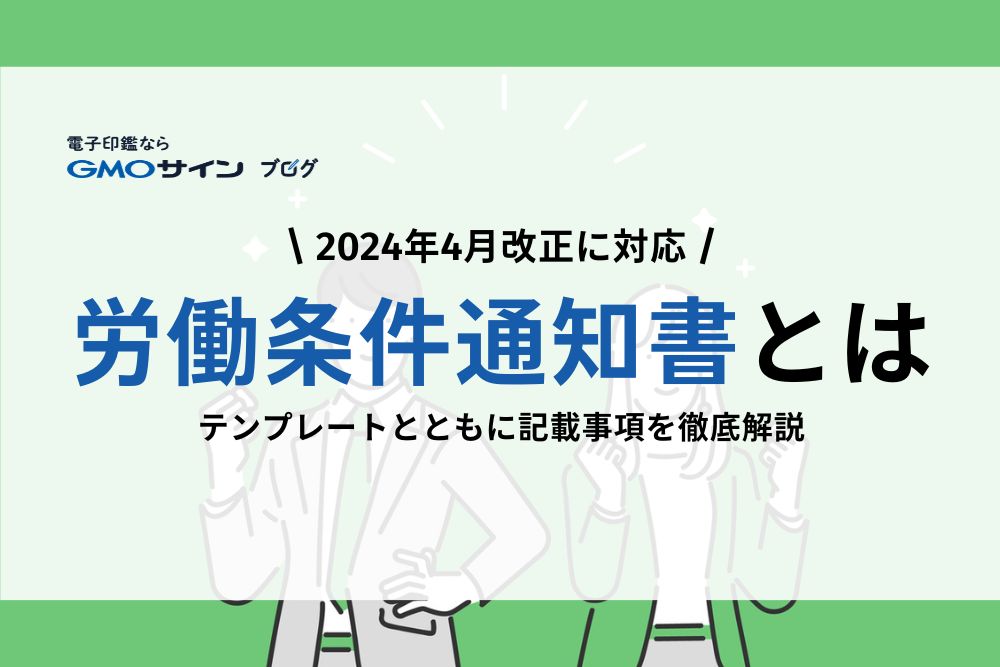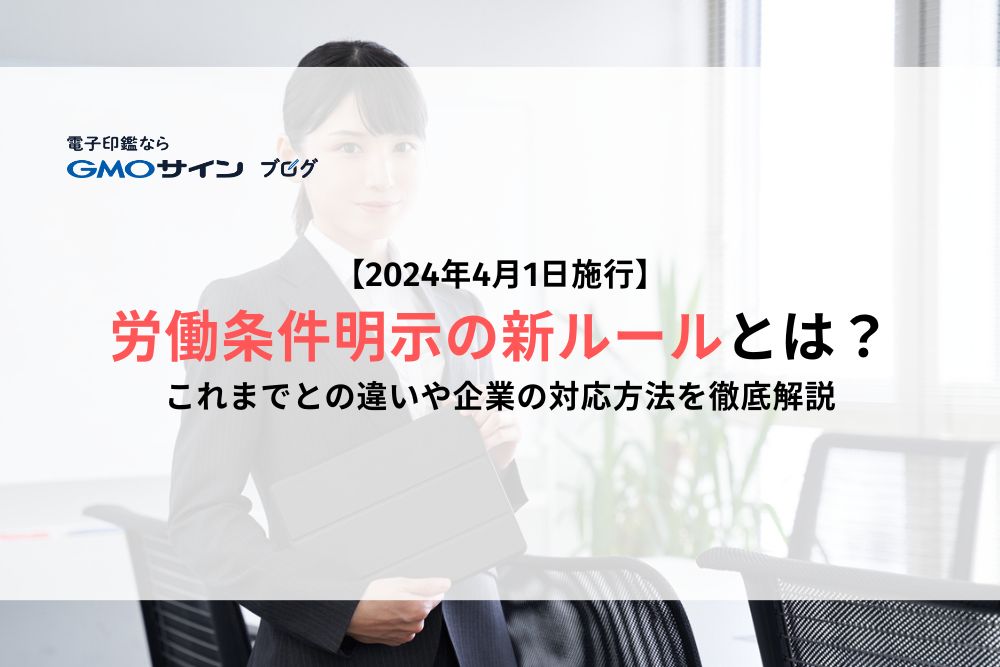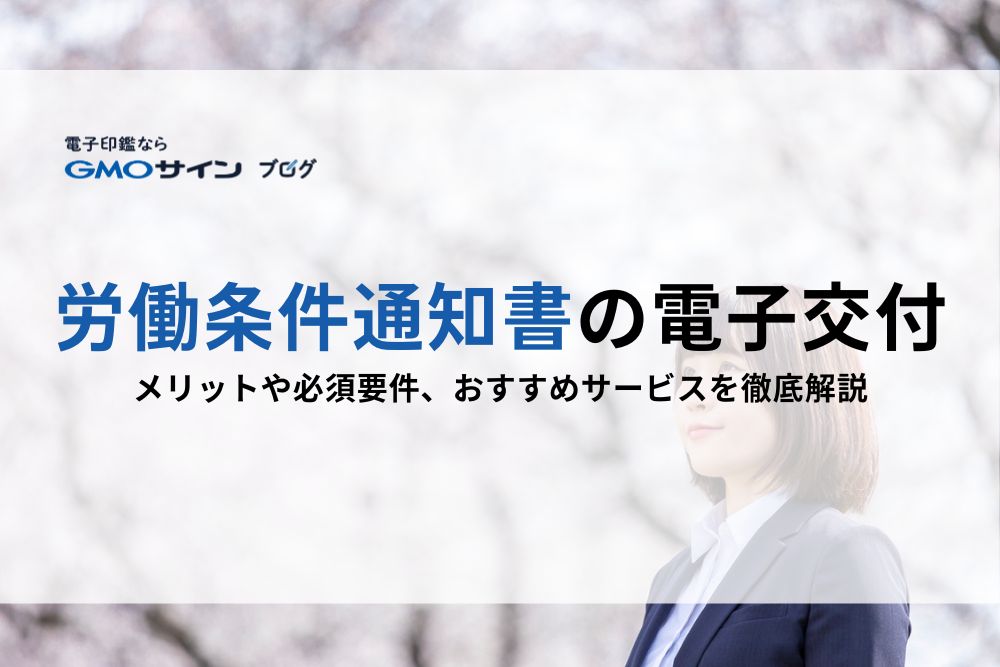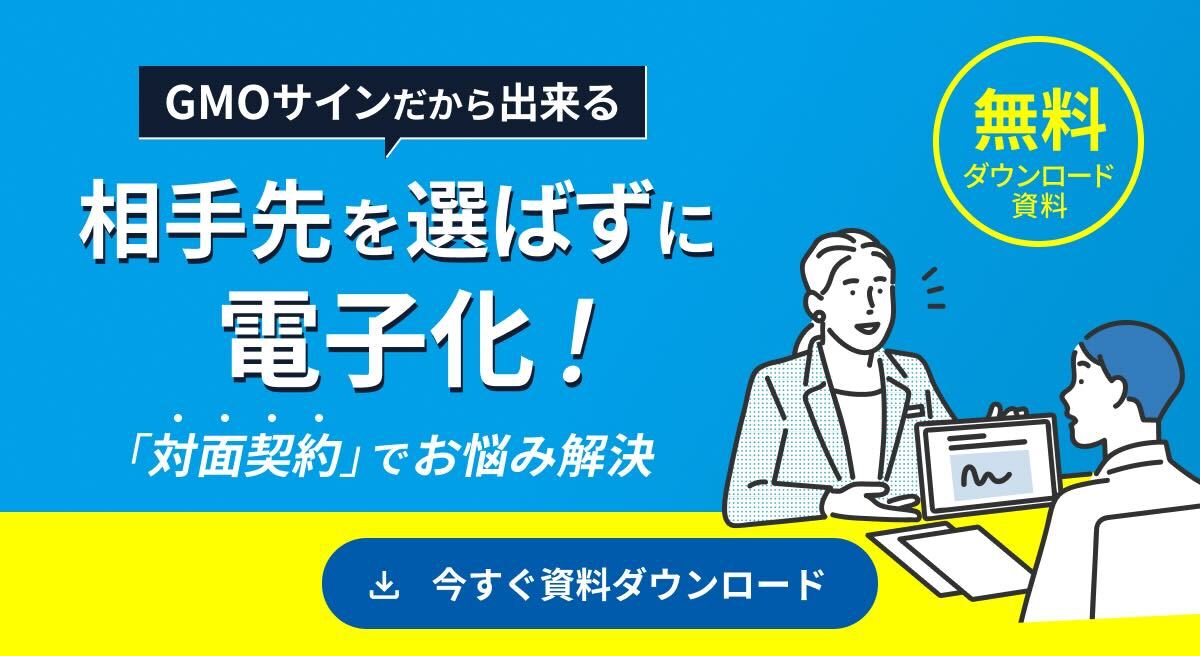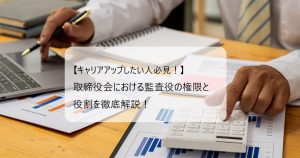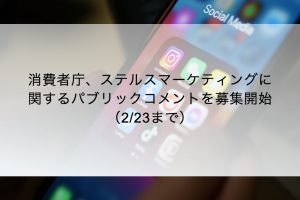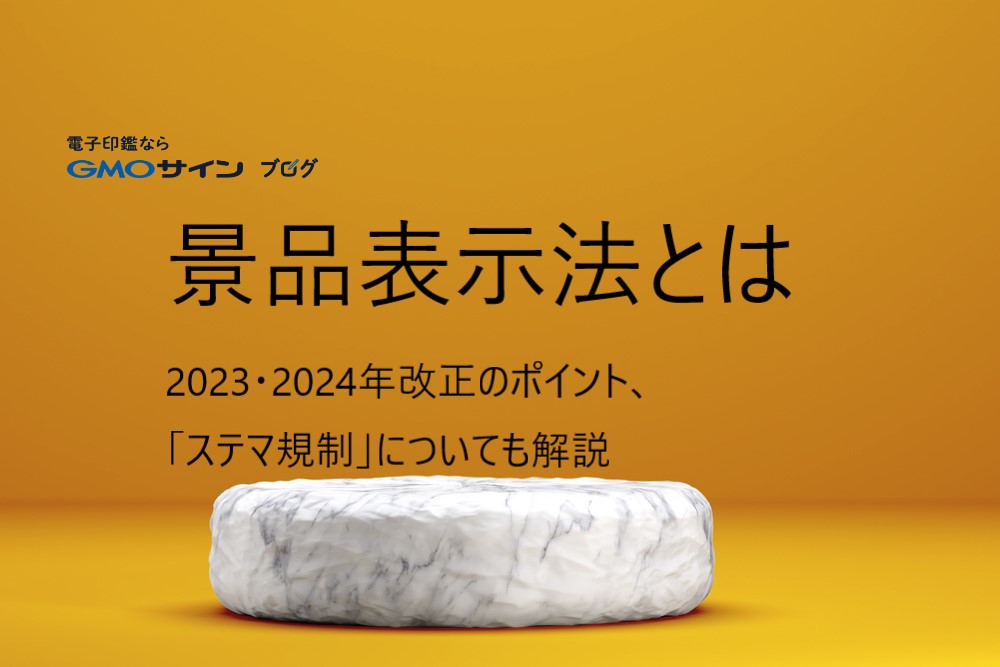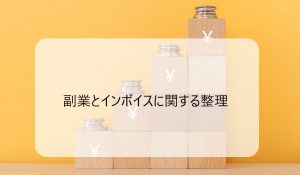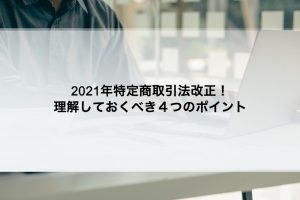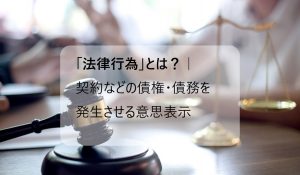春です。新生活の始まる時期です。会社に新しい方が入社してきたという方、ご家族がパートやアルバイトを始めたという方も多いのではないでしょうか。
採用するにあたって、雇う側は「労働条件通知書」の交付が必要ですが、働く側の皆さんはすでに受け取りましたか?そこには週1回のパートタイムやアルバイトでも有給休暇(有休)がもらえると書いてあるようです。本当でしょうか。
本記事では、労働条件通知書について雇われて働く方々の立場に基づいて解説いたします。
【セミナー無料配信中】労働条件明示のルール改正について弁護士が深掘り解説
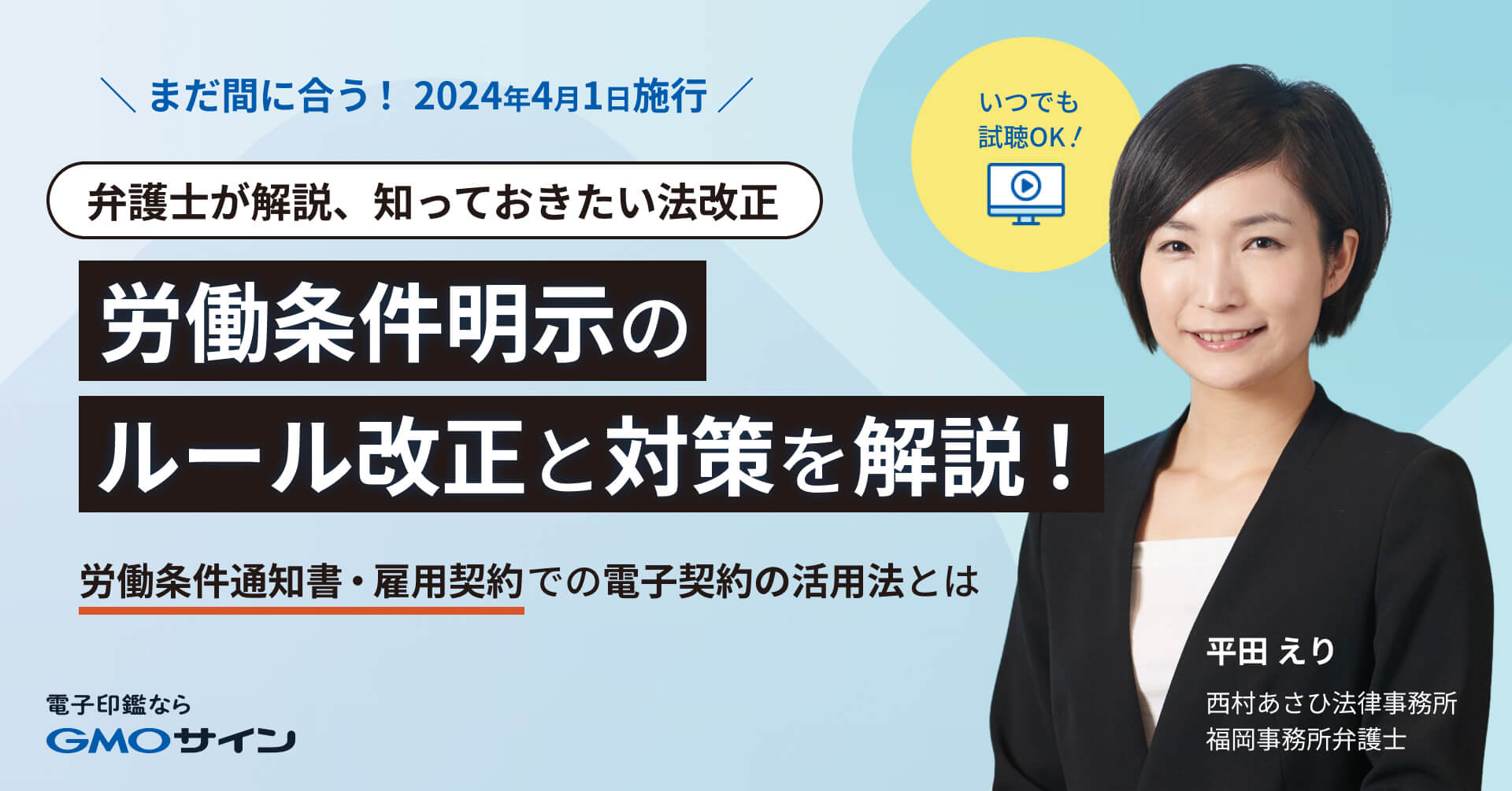
目次
労働条件通知書とは?
(1)雇う側が労働者に渡すことが法律で義務づけられている書類
パートやアルバイトをする際は、勤務先と労働契約を締結することになります。労働契約とは、労働者が雇用主の指揮命令の下で働いて、賃金をもらう約束のことです。
労働契約そのものは口頭でも成立しますが、雇用主は、採用に際して賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に示さなければなりません。そのうち一定の事項については、書面の交付により、労働者に明示しなければならないと法律で定められています(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条第4項)。
なお、書面での交付が大前提ですが、労働者が希望する場合は、EメールやLINEなどのSNSのメッセージ機能、ウェブメールサービスといったデジタル上での明示も可能です。
出力して書面を作成できるものに限られますが、労働者の個人的な事情によらず、一般的に出⼒可能な状態であれば問題ありません。なお、第三者に閲覧させることを目的としている労働者の方のブログや個人のホームページへの書き込みは認められません。
あわせて読みたい
労働条件通知書とは?テンプレートとともに記載事項を徹底解説【2024年4月改正によって新たに追加される...
企業が労働者を雇用する際には、就業場所や業務内容、賃金など労働条件について記した労働条件通知書を必ず交付しなければいけません。労働条件通知書の基本的な書き方...
(2)労働条件通知書に記載する事項
雇用主が労働条件通知書に記載しなければならない事項は以下の通りです。
- 労働契約の期間に関すること
- 期間の定めのある労働契約の場合、更新の有無・更新の基準に関すること
- 就業の場所及び従事する業務に関すること
- 労働時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制勤務の就業時転換に関すること
- 賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締め切り及び支払いの時期に関すること
- 退職に関すること(解雇事由を含む)
- 昇給・退職手当・賞与の有無(パートタイム・有期雇用労働者)
- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(パートタイム・有期雇用労働者)
このほか、以下の事項を制度として設けている場合には労働条件通知書に記載しておく必要があります。
- 退職金に関する事項
- 臨時に支払われる賃金等に関する事項
- 労働者に負担させるべきものに関する事項
- 安全・衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰・制裁(懲戒)に関する事項
- 休職に関する事項
あわせて読みたい
【2024年4月改正】労働条件明示の新ルールを徹底解説 | これまでとの違いや企業の対応方法、新ルールに...
「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正により、労働条件通知書のルールが2024年4月から変更されます。これまでは問題なかっ...
(3)労働条件通知書のフォーマットは厚生労働省のウェブサイトにある
厚生労働省が公開している労働条件通知書のフォーマットを確認してみましょう。実際に受け取るものと若干異なる部分があるかもしれませんが、フォーマットを埋めると記載義務事項がすべて記載される仕組みになっています。
厚生労働省が作成した労働条件通知書の書式(一般労働者用;常用、有期雇用型)の例をぜひ参考にしてください。
【参考】厚生労働省作成の労働条件通知書のフォーマット
労働条件通知書はいつ受け取れるのか?
雇用主が労働条件通知書を渡すタイミングは、労働基準法第15条で「労働契約締結時」と定められています。
内定ではなく即時採用・入社の場合は入社時に受け取りますが、内定期間がある場合は、内定の時点で労働契約が成立すると考え、雇用主は内定通知書とともに労働条件通知書を明示する必要があります。
なお、労働条件通知書を紙またはデジタル(eメールやLINE、SNSのメッセンジャー機能など)のどちらで受け取るかは、働く側から雇用主に希望することができます。
あわせて読みたい
労働条件通知書の電子交付についてメリットとおすすめサービスを解説
2019年4月から労働条件通知書の電子化(電子交付)が可能となりました。そこで本記事では、労働条件通知書を電子化するメリットやデメリット、電子化に必要な3つの要件...
労働条件通知書がもらえないときは?
労働契約や雇用契約のなかに労働条件通知書に記載しなければならない事項がすでに含まれている場合があります。しかし、特段の契約書や電子契約もなく、労働条件通知書が雇用主から受け取れないときは、こちらから勇気をもって話してみましょう。厚生労働省のフォーマットを印刷して書いてもらい、雇用側の責任者の署名やハンコをもらう、というのもひとつの方法です。
それでも労働条件通知書がもらえないときは、その勤務先が少し約束にルーズである可能性があります。労働基準関係法令の違反だからです(雇用主は最高で30万円以下の罰⾦となる場合があります。)
万一、勤務期間中に雇い主とトラブルとなってしまったときに、労働条件通知書がないとそもそも条件や契約内容があいまいになってしまうというリスクも生まれます。十分に注意してください。
まとめ|週1回のアルバイトでも有休がもらえるのは本当?
労働条件通知書は、雇用主がパートタイム勤務やアルバイトの方に対しても渡さなければならない書類であることにつき解説いたしました。
働く側にとっても、労働条件通知書が手元にあれば勤務を開始した後も自分の労働条件を書面で確認できるため、納得・安心して働くことができます。必ず勤務開始日までに受け取り、内容を確認しましょう。なお、労働条件通知書は、紙でなく電子データやeメール、SNSのメッセンジャー機能での受け取りも可能です。希望する方は雇用主に相談してみましょう。
さて、週1回勤務のアルバイト勤務でも有給休暇(有休)が行使できるのかという文頭での話ですが、労働基準法第39条に定められた2つの条件を満たせば最低1日は有給休暇を取得することができます。
2つの条件とは、以下になります。
①半年間継続して雇われていること、
②全労働日(週1回×半年)の8割以上を出勤していること
- 連帯保証人が個人の場合の極度額
- 譲渡に関する規定
- 賃借人の原状回復及び収去の義務
- 敷金に関する規定
週1回の出勤日の付与日数は1日が最小なので、半年以上勤務すると最低でも1日の有給休暇を取得できることになります。このようなことも労働条件通知書に記載される内容ですので、労働契約時によく内容を確認しましょう。
【参考】厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)
電子印鑑GMOサインは、労働条件通知書の保存や管理に便利な電子契約サービスです。
受け取り側がお試しフリープランで保管が可能になりますので、もし電子契約ツールを利用して労働条件通知書を受け取る場合などに備えて、この機会にアカウント作成をしてみてください。
労働条件通知書の電子化と今後の課題
社員、パート・アルバイトを採用したら労働条件通知書を渡すのが会社の義務 | 助成金の申請にも活かそう
【対面契約とは?3つの特徴】
①紙の契約書と同様に、その場でサインが可能。メールアドレスが不要に!
②タブレットを使い目の前で契約を締結するため、契約相手先の準備がいらない
③フリーメールアドレスよりも本人性担保が高い状態で締結!
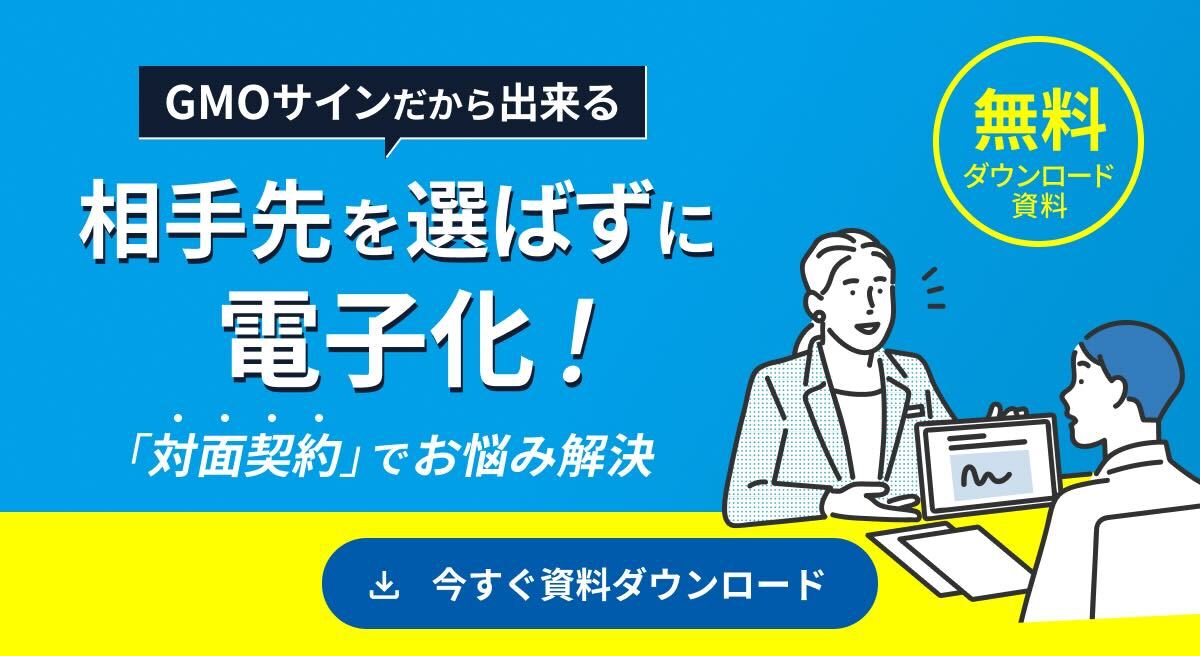
GMOサイン対面契約なら、
相手方のご状況に依存せず様々なシーンで電子契約が可能になります。