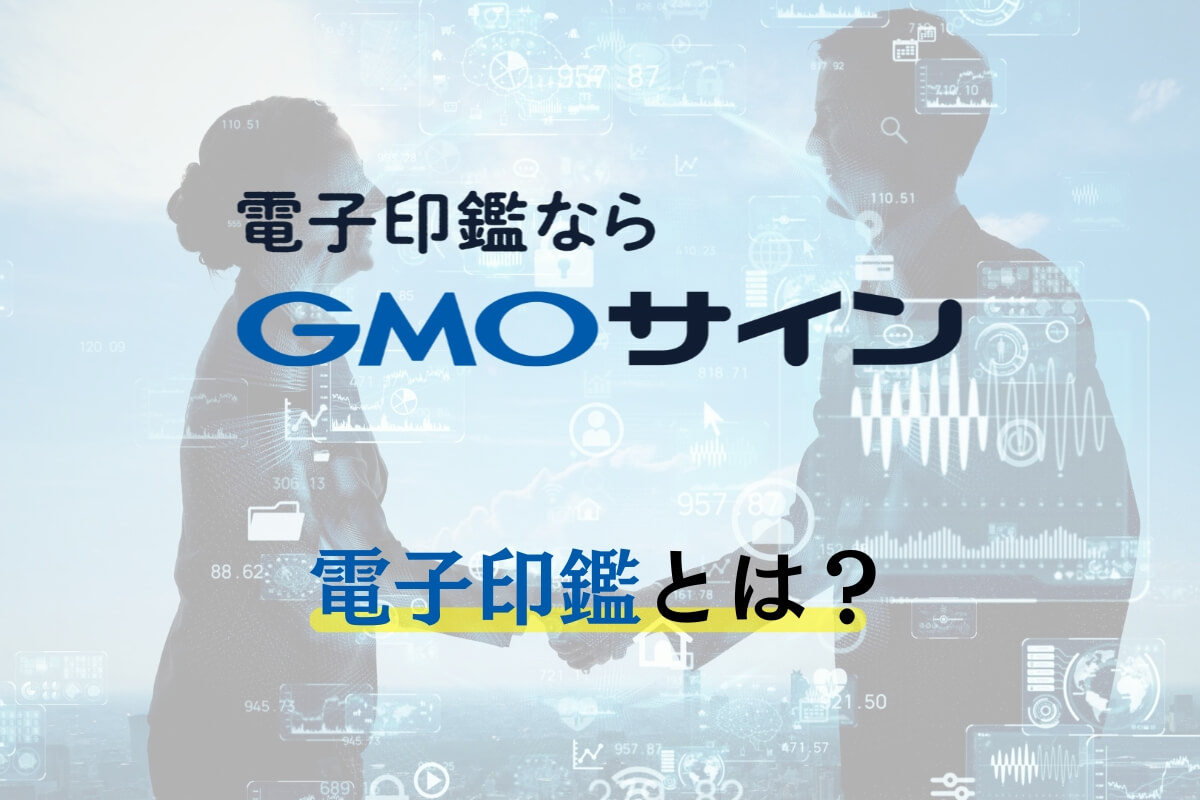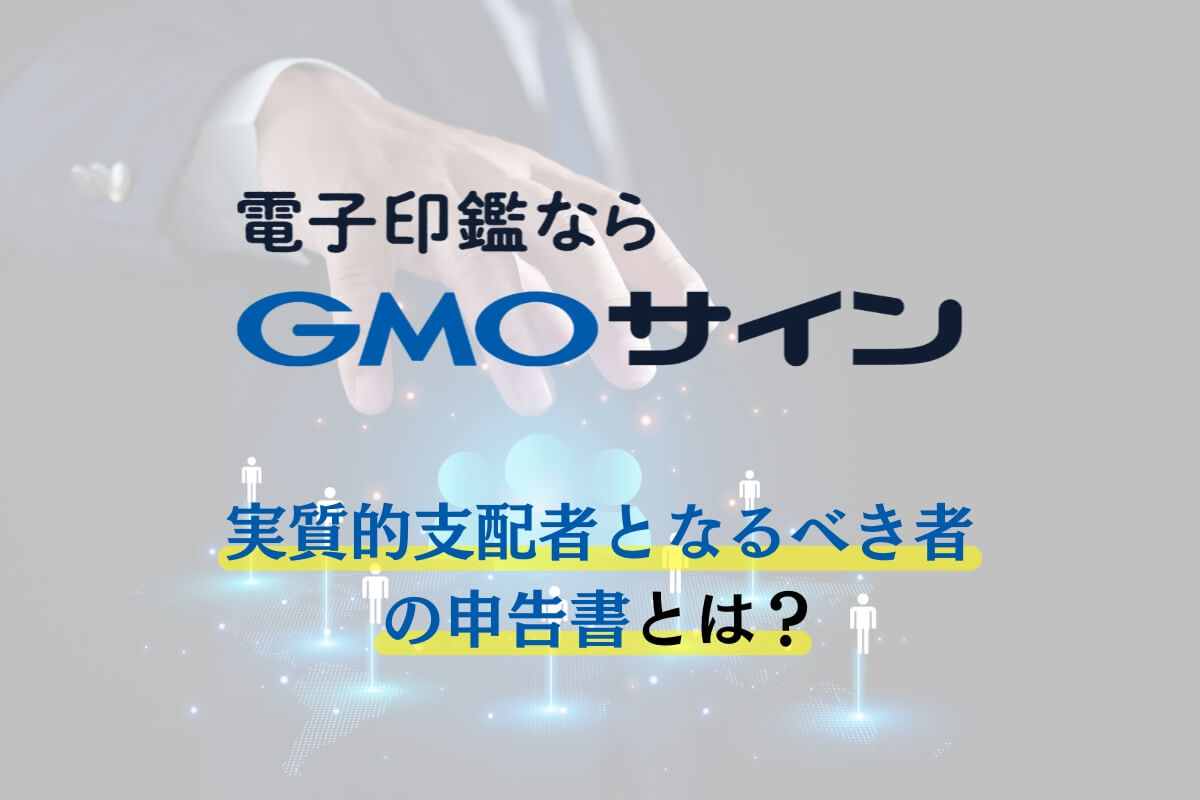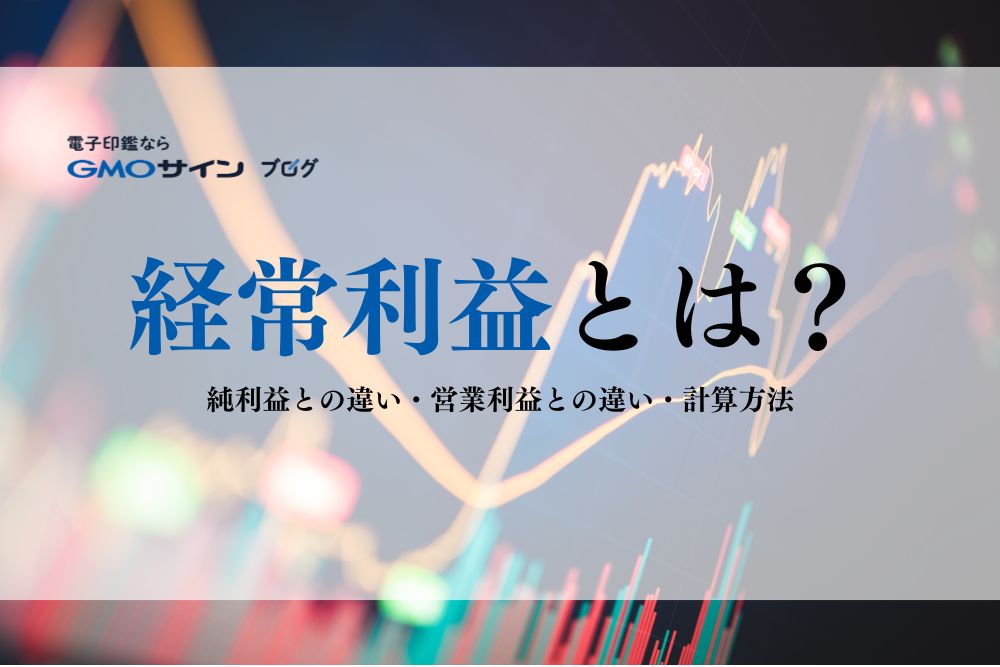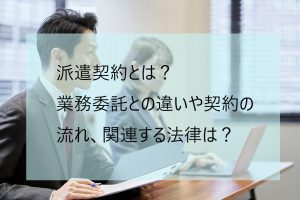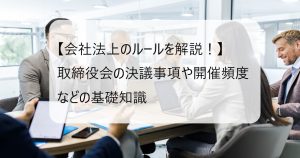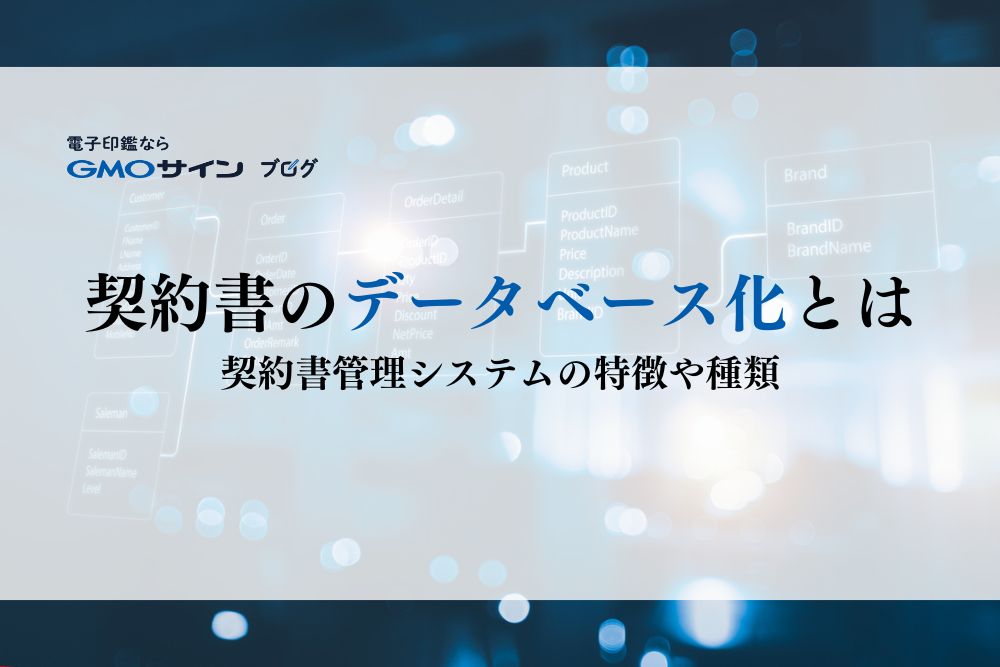ふるさと納税による控除は、配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などとは異なり、年末調整では受けられないことにご留意ください。
各種控除を年末調整により対応していて確定申告する必要がない給与所得者は、ワンストップ特例を利用できるため、手間がかかりません。なお、ワンストップ特例の場合、所得税からは控除されず、住民税のみから控除される仕組みです。
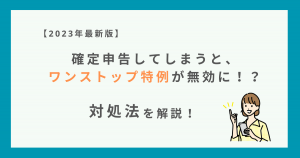
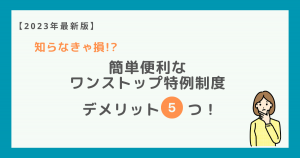
この記事では、ワンストップ特例を利用してふるさと納税の控除を受けて住民税を減らす方法を詳しく解説します。確定申告が不要な給与所得者(会社員・公務員など)の方は、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自身で自由に選択した自治体に対して寄付(ふるさと納税)を実施した場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分に関して、所得税と住民税から控除される制度です(上限あり)。
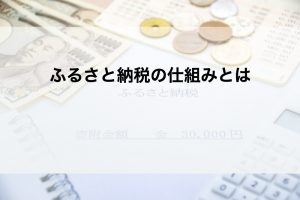
以下、所得額および住民税から控除される金額の計算方法を紹介します。
所得税から控除される金額の計算方法
所得税からの控除額は、以下の式で算出されます。
所得税の税率は、課税所得の増加に応じて上昇する仕組みです。また、控除対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限とされています。
住民税から控除される金額の計算方法
住民税からの控除には基本分と特例分があり、基本分に関しては以下の式で金額が算出されます。なお、控除の対象とされるふるさと納税額は、総所得金額の30%が上限です。
特例分に関しては、以下の式で金額が算出されます(特例分の金額が、住民税所得割額の2割を超えない場合)。
なお、特例分(上の式で算出された金額)が住民税所得割額の2割を超える場合は、以下の式で算出されることにご留意ください。
この場合、所得税からの控除、および、基本分・特例分を合計しても「ふるさと納税額-2,000円」の全額が控除されず、実質負担額が2,000円を超えます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)を把握するための方法
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税および住民税から控除されるふるさと納税額の目安を知りたい場合は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されている表をご覧ください。家族構成別・年収別に、年間上限額の目安を把握できます。
不明な点がある場合は、税務署や各自治体のふるさと納税担当部署に相談しましょう。
ふるさと納税による控除は年末調整では受けられない
配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは、年末調整で受けることが可能です。しかし、ふるさと納税による控除は、年末調整では受けられません。ふるさと納税による控除を受けたい場合は、以下のいずれかの方法を選択しましょう。
・確定申告
・ふるさと納税ワンストップ特例制度
各方法に関して詳しく説明します。
確定申告でふるさと納税の控除を受ける方法
以下は、給与所得者が確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合の流れです。
- ふるさと納税する
- 自治体から送付される「受領書」を保管しておく
- 確定申告書を作成し、ふるさと納税した翌年の3月15日までに所轄の税務署に提出する(受領書を添付する)
- ふるさと納税した年の所得税から控除を受けられる(源泉徴収によって納めすぎている所得税がある場合は還付を受けられる)
- ふるさと納税した翌年度分の住民税が減額される形で住民税からの控除を受けられる
後述するワンストップ特例制度の対象ではない場合は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度でふるさと納税の控除を受ける方法
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告しなくても控除を受けられる仕組みで、以下の条件を満たす場合に利用できます。
・確定申告が不要な給与所得者である
・ふるさと納税先(自治体)の数が5つ以内である
以下は、ワンストップ特例制度でふるさと納税の控除を受ける流れです。
- ふるさと納税する
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄付先の自治体に提出する(翌年の1月10日必着)
- 所得税からの控除は実施されず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税した翌年度の住民税の減額という形で控除される
なお、ふるさと納税先が6つ以上の場合や、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などを受けるために確定申告する場合は、ワンストップ特例制度を利用できません。その場合は、所轄の税務署に確定申告して控除を受けましょう。
ふるさと納税による控除額は年末調整ではなく住民税決定通知書で確認しよう
ふるさと納税による控除額は、住民税決定通知書でチェックすることが可能です。
控除額を確認したい場合は、住民税決定通知書の摘要欄を見ましょう。摘要欄の寄附金税額控除額が、ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額であれば、正しく控除されています。
万が一、金額が整合しない場合は、自治体にお問い合わせください。
ふるさと納税するメリット
以下は、ふるさと納税の主なメリットです。
それぞれに関して詳しく説明します。
好きな自治体を応援して所得税や住民税の負担を軽減できる
物価の高騰が続く昨今、
なるべく多くのお金を手元に残したい(税金の負担を少なくしたい)
とお考えの方も多いでしょう。
国や自治体に納める所得税・住民税の額が減少するため、その分、生活費や貯蓄に回せる金額が増えます。
なお、「ふるさと」という単語が含まれていますが、寄付先の自治体に制限はありません。生まれ育った自治体以外にも、ふるさと納税(寄付)が可能です。好きな自治体を応援しながら税金の負担を軽減できることが、ふるさと納税という制度の魅力です。
ふるさと納税先の自治体から返礼品をもらえる
ふるさと納税すると、寄付先の自治体から返礼品をもらえる場合があります。受け取れる返礼品の種類は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式サイトで詳細を確認しましょう。
また、さまざまな企業が、ふるさと納税用のポータルサイトを開設しています。フリーワードを入力したり、ジャンル、カテゴリーで絞り込んだりして、自分に合った返礼品を探せる仕組みが提供されているので、ぜひ活用ください。
なお、ふるさと納税の返礼品として受け取った物品の経済的価値は、一時所得とみなされます。ただし、一時所得に関しては、年間で50万円を超えない限り、課税されません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば手間がかからない
上述したように、ふるさと納税による控除は、年末調整では受けられません。給与所得者の場合、確定申告の経験がない方も多いため、確定申告書の作成に手間取る可能性があります。
手間をかけずに控除を受けたいのであれば、ワンストップ特例を利用するために、ふるさと納税先(寄付先)の自治体数を5以下にしておきましょう。6以上の自治体にふるさと納税するとワンストップ特例制度の対象外とされ、確定申告しなければいけないことにご留意ください。
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税する場合は、以下の点に注意しましょう。
・ふるさと納税額(寄付金額)の全額が控除されるわけではない
・返礼品の価値はふるさと納税額(寄付金額)を大幅に下回る
・医療費控除や住宅ローン控除なども受ける場合、控除しきれない可能性がある
それぞれ詳しく説明します。

ふるさと納税額(寄付金額)の全額が控除されるわけではない
ふるさと納税しても、寄付金額の全額が控除されるわけではありません。上述した目安額(上限額)までの寄付金額であれば、ふるさと納税額から2,000円(実質負担額)を差し引いた金額まで控除を受けられますが、上限額を超えると実質負担額が増加します。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されている表を参照したり、エクセルなどで使えるシートを活用したりして、実質負担額が2,000円を超えないように寄付額を調整しましょう。
また、さまざまな企業が運営しているふるさと納税用ポータルサイトで、「シミュレーション機能」が提供されている場合があります。シミュレーション機能で試算したうえで、ふるさと納税額を決めることもご検討ください。
返礼品の価値はふるさと納税額(寄付金額)を大幅に下回る
以前は、ふるさと納税した方に対して、高額な返礼品を送付する自治体も存在しました。しかし、「自治体を応援する」という制度の主旨から乖離していることが問題視され、2025年5月時点では以下に示す制限が課されています。
・返礼品は自治体の地場産品で、調達費が寄付額の30%以下であること
・返礼品の調達費や送料、仲介サイトに支払う仲介手数料、決済手数料、広報の費用、事務費用などを合計した総費用が寄付額の50%以下であること
上記規制により、現在では、自治体によっては寄付額に見合う価値がある返礼品が提供されない場合もあることを認識しておきましょう。
医療費控除や住宅ローン控除なども受ける場合、控除しきれない可能性がある
ただし、他の控除を受けると、課税所得額が減るため、ふるさと納税の控除限度額(寄付額から2,000円を差し引いた金額全額が控除されるふるさと納税額)も減少します。
そのため、無計画にふるさと納税すると、寄付額から2,000円を差し引いた金額を控除しきれず、実質負担額が2,000円を超える可能性があります。他の控除も受けるのであれば、その点も加味して事前にシミュレーションを実施しましょう。
なお、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受けるために確定申告する場合、ワンストップ特例制度を利用できないことにご留意ください。
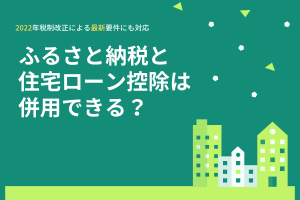
ふるさと納税による控除は年末調整ではなく確定申告かワンストップ特例で受けよう
昨今、物価高で生活コストが上昇していますが、ふるさと納税を実施して控除を受けることにより、所得税や住民税の負担を軽減することもご検討ください。
ただし、ふるさと納税による控除は、年末調整では受けられません。控除を受けたい場合は、自身で確定申告書を作成して所轄の税務署に提出するか、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しましょう。
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者(会社員・公務員など)で、ふるさと納税先(寄付先)の自治体が5つ以下の場合に利用できます。
確定申告する手間をかけずに所得税・住民税からの控除を受けられるため、ワンストップ特例の対象とされる条件を満たす場合は、ぜひ活用ください。
~あなたの寄付を支える自治体のDXと電子契約~
今や多くの方が利用する「ふるさと納税」。スマートフォンで簡単に申請できたり、魅力的な返礼品がすぐに見つかったりと、年々便利になっていると感じませんか?
実はその裏側では、私たちが快適にふるさと納税を利用できるよう、全国の自治体が業務のデジタル化(DX)を進めることで、サービスを支えています。今回は、その知られざる舞台裏と、そこで活躍する「電子契約」についてご紹介します。
ふるさと納税が人気になるにつれて、自治体の業務は増え続けています。寄付の受付や管理はもちろん、返礼品を提供してくれる地域の事業者とのやり取りもその一つです。特に、事業者との間では、商品の内容や発送、個人情報の取り扱いなど、多くの約束事を記した「契約書」を取り交わす必要があります。
これらの契約をすべて紙で行うと、印刷・郵送・保管といった手間やコストがかかり、職員の方々の大きな負担となっていました。
そこで今、多くの自治体が導入しているのが、ふるさと納税の業務をまとめて効率化する「管理システム」です。
中でも、全国1,300以上の自治体(※)で導入されているシェアNo.1のふるさと納税管理システムが、株式会社Workthyの提供する「ふるさと納税do」です。
※2024年7月時点

そして「ふるさと納税do」は、契約業務を効率化するため、当社の「電子印鑑GMOサイン」と連携しています。これにより、自治体と事業者は、オンラインでスピーディーかつ安全に契約を締結できるようになりました。
自治体の業務が効率化されると、どうなるでしょうか。
職員の方々は、これまで契約事務などにかけていた時間を、より魅力的な返礼品を開拓したり、地域のPR活動を企画したりといった、より創造的な業務に使えるようになります。
今回は、ふるさと納税の裏側を支える自治体のDXと、そこで活用される「電子印鑑GMOサイン」についてご紹介しました。
GMOサインは、このように自治体の業務をサポートするだけでなく、企業のビジネスシーンから個人の暮らしの中まで、あらゆる場面での「契約」をより安心・便利に変えていきます。契約の電子化にご興味のある方は、ぜひ公式サイトもご覧ください。