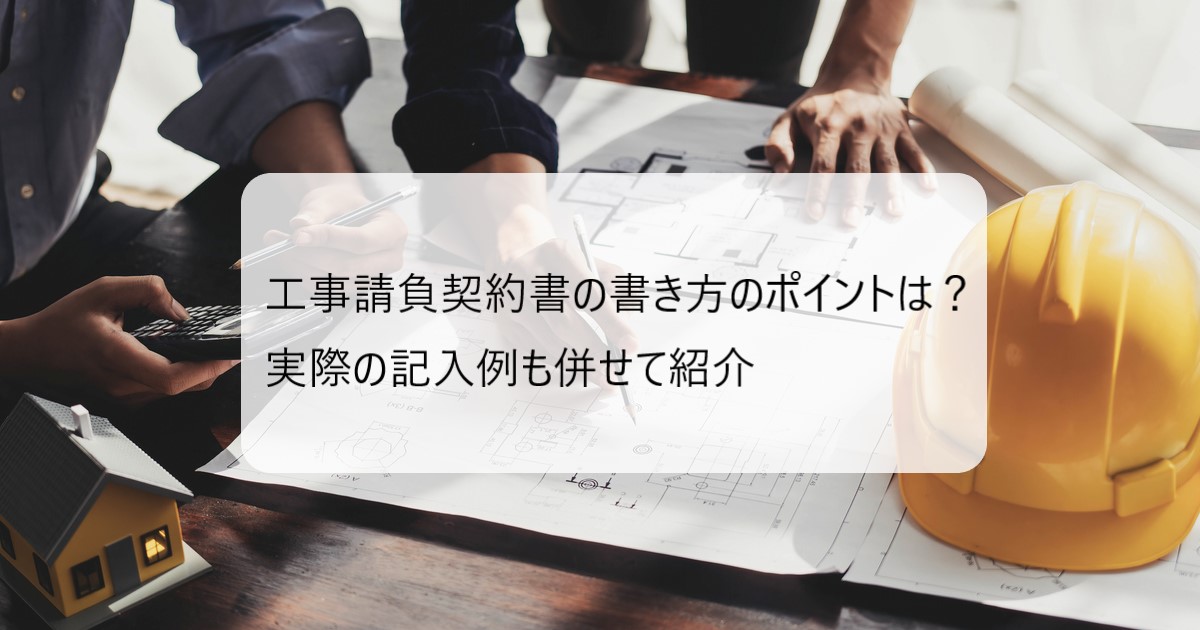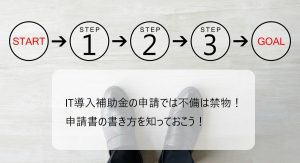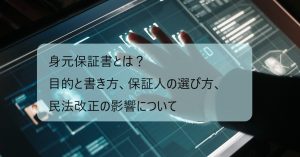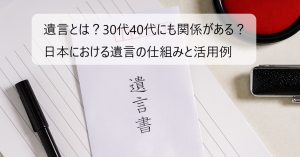\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

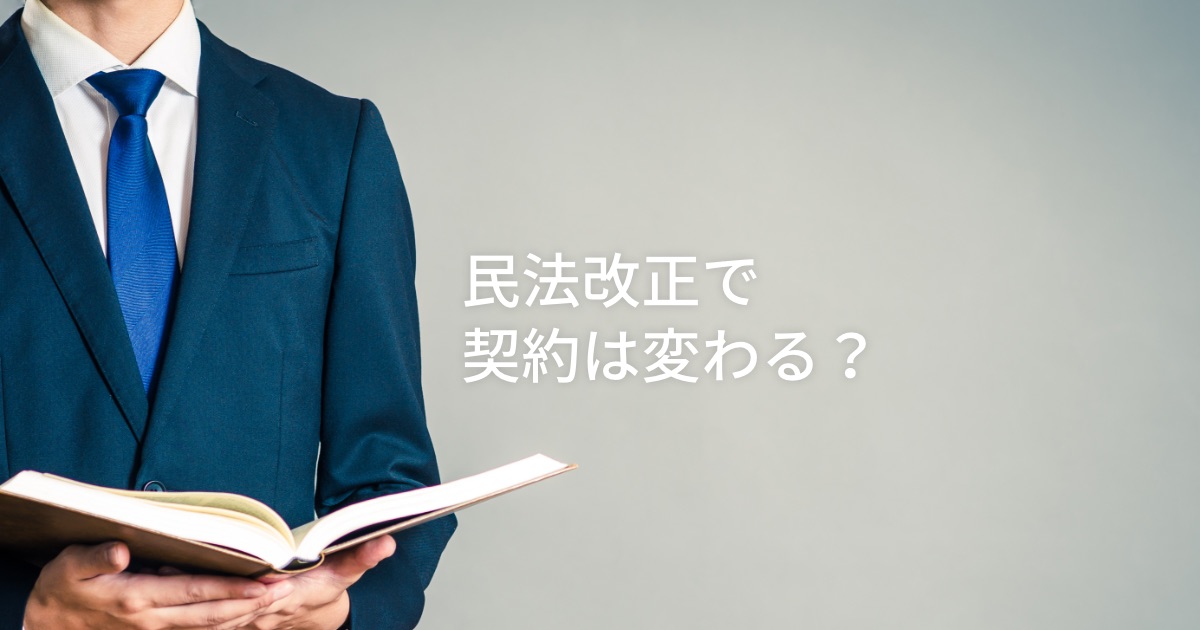
2020年4月、新民法が施行されました。民法は市民社会を取り仕切る原理・原則のルールを定めた法律です。約120年ぶりに大改正された新民法では、多くの制度が改変・新設されました。
今回は、新設された第522条(契約の成立と方式)の要点を確認し、今後の契約について考えてみましょう。
2020年に行われた民法改正は、約120年ぶりに抜本的な見直しがなされたため、大改正とも呼ばれています。これまでの民法は個別の条文に対して小規模な改正がなされることはたびたびありましたが、今回の改正では大きな見直しがされています。
すでに判例で確立されている決まりごとや、現代社会において当たり前となっているような商習慣を条文に盛り込み、明文化されたのです。ただし、大きな改正が行われたといっても、その背後にある基礎・基本の重要性が揺らぐことはありません。
契約の成立に必要な要素は何か というのは、民法の根本にもかかわる奥の深い問題です。こうした点についても、今回の民法改正では見直しが行われました。
契約の考え方は、第522条(契約の成立と方式)で規定されています。この条文は新民法で新設された条文で、契約の成立プロセスを定めるものです。
新設された第522条の条文を実際に見ていきましょう。
民法第522条(契約の成立と方式)
- 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
ポイントは、以下の3点です。
民法522条に示されるような内容は、現代社会における取引の常識と比べてみても、特に違和感なく受け入れることのできるものでしょう。
民法上、契約は口約束でも成立するとされています。今回の民法改正においても、口約束によって契約が成立するという点は変わっていません(法令上、書面による契約が必要な場合を除く)。しかしながら、民法第522条で、契約の形式や手続きよりも申込みと承諾の有無を優先すると明記されたことで、今後の契約業務にどのような影響を与えるのでしょうか。
日本では従来、契約成立の証拠を残すために契約書の作成や捺印が用いられて来ました。これは万一の争いに備え、申込みや承諾の事実を裏付けるための慣習でしたが、この考え方は今後も継続するべきです。
また、契約の証拠を残すことができれば、形式や手続き方法は自由とも考えられます。つまりこれからのビジネスシーンでは、従来からの書面契約に変わって電子契約への移行が受け入れられやすい社会になりつつあるのではないでしょうか。
将来にわたって争いの余地を残さないリスクマネージメントをいかに継続するか。その方法を実務に導入することが求められます。
今回は民法の大改正によって、ビジネスの基礎となる契約の考え方の変化について整理しました。大改正といってもその内容は、120年の間に積み重なってきた商習慣などを取り入れたものです。特に契約に関する規定の理解では、大改正という言葉に焦る必要はありません。深く正確な理解をもとに、改正された民法に合わせて実務のあるべき姿を考えることが大切です。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。