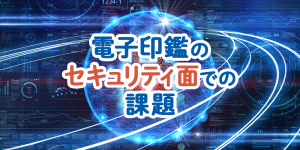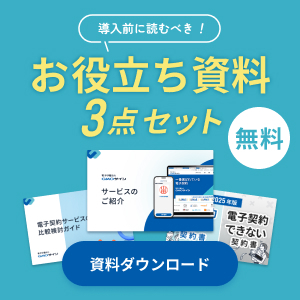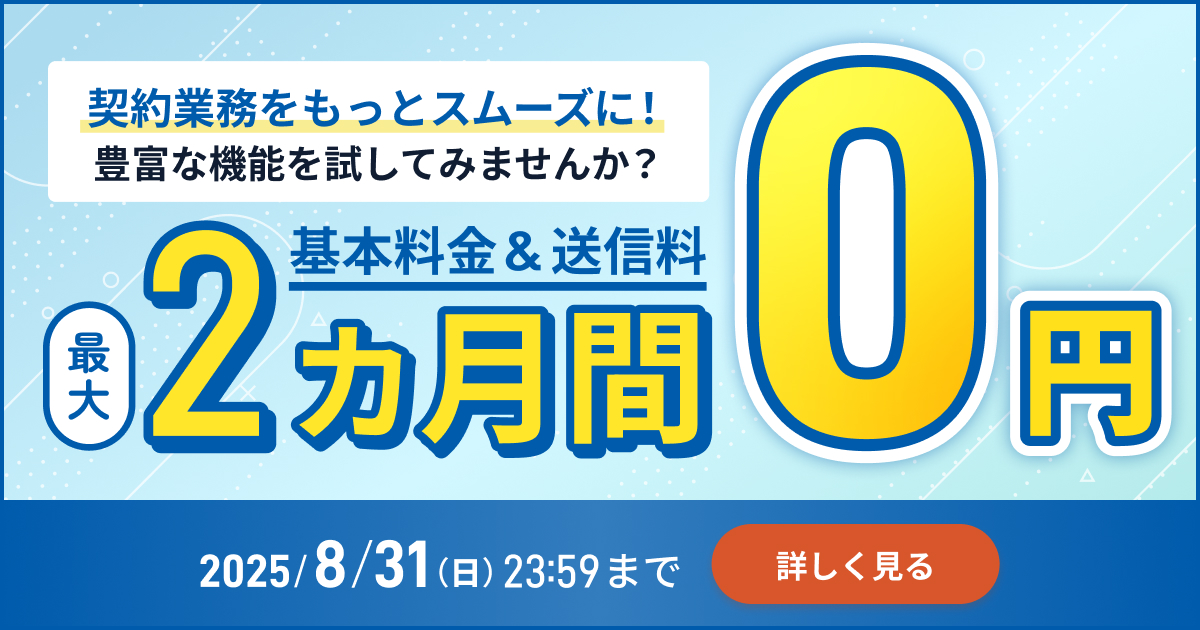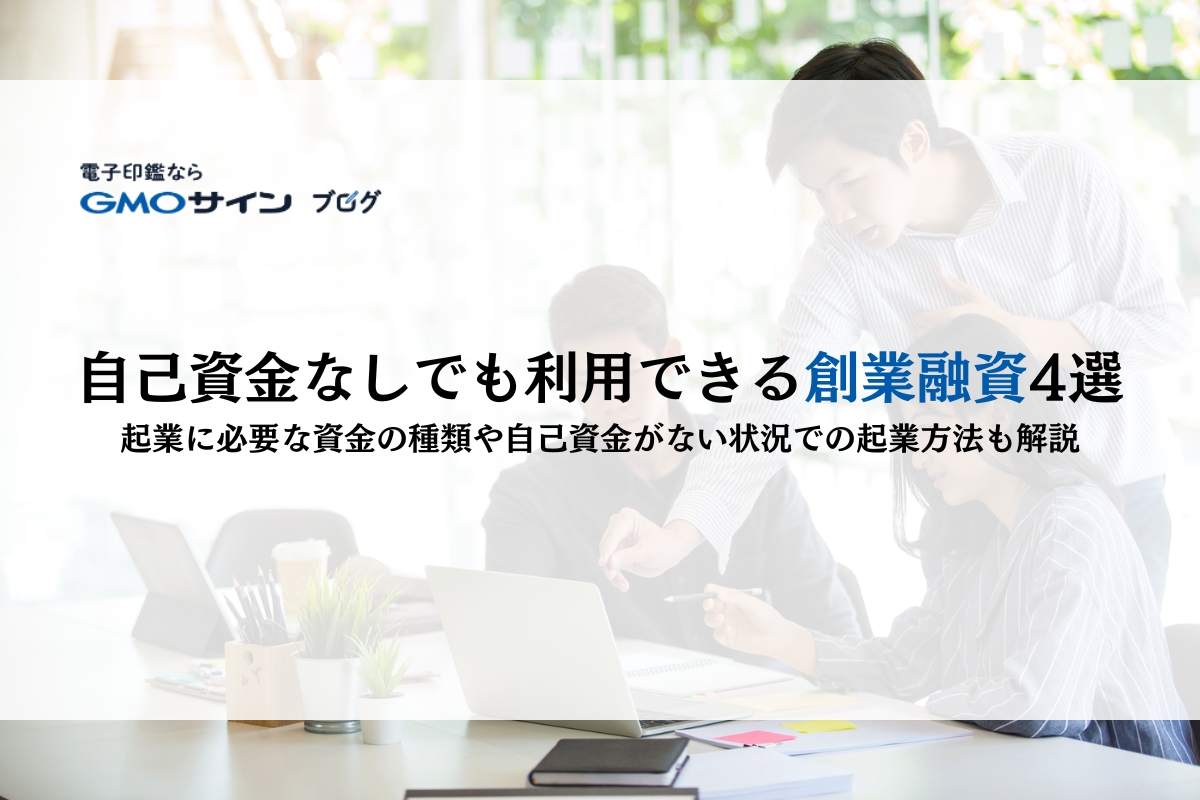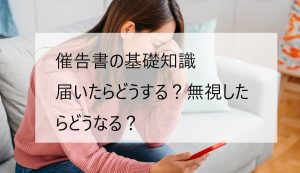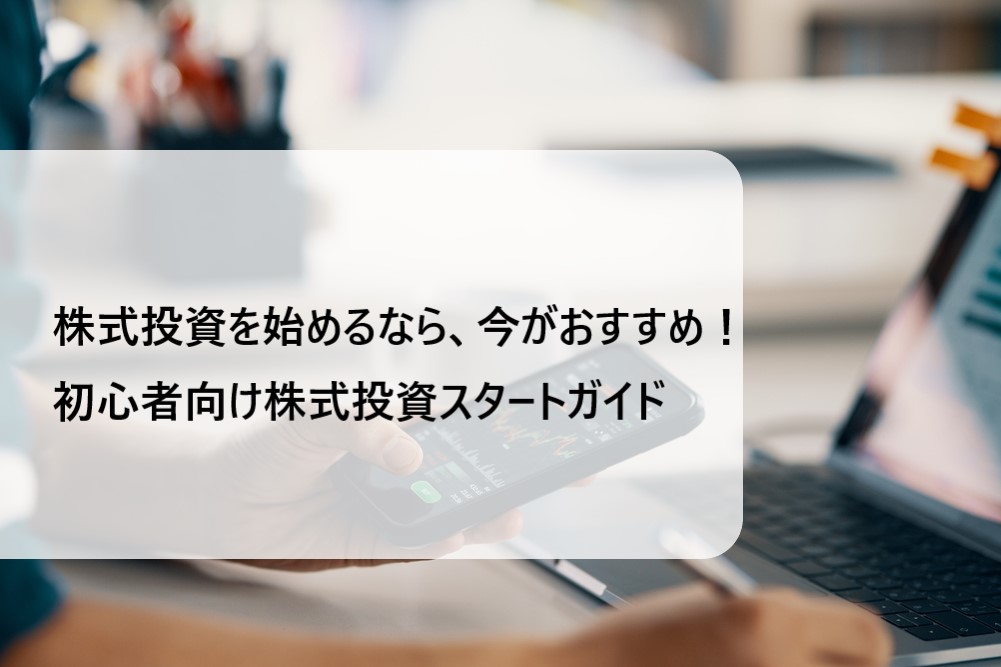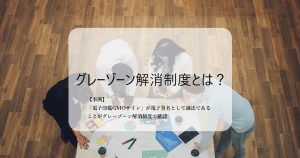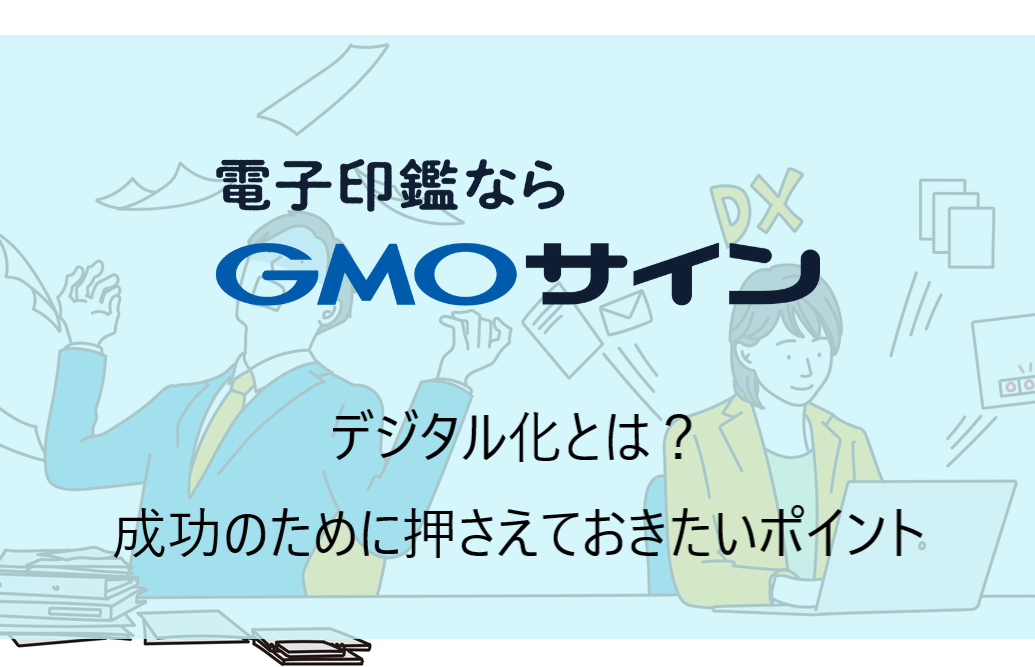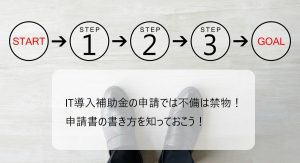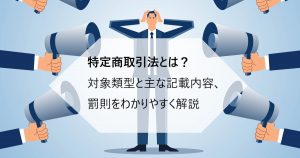CSR(企業の社会的責任)とは何か?注目される理由や導入するメリット、似た用語との違いについても解説

昨今ではCSRという言葉を耳にする機会が多くなりましたが、具体的な意味をご存じでない方もいるでしょう。また類似した用語も多いので、混同されるケースも多いです。
本記事では、CSRの概要や注目されている理由、似た用語との違いについて詳しく解説します。導入するメリットや注意点などもお伝えしますので、ぜひご覧ください。
CSRとは
CSRとはCorporate Social Responsibilityの略称であり、「企業の社会的責任」という意味です。企業の社会的責任とは、企業が経済活動を行うにあたって、社会貢献するために果たすべき責任を指します。企業が行う経済活動は特徴や業界などによって様々ですので、果たすべき責任はそれぞれ異なります。
また従業員や投資家、消費者などステークホルダーの観点からも配慮する必要があります。なぜなら企業は主に役員などの経営陣が方針を決定しますが、CSRを遵守するためには自社の経済活動に関するあらゆる人間の利害を考慮しなければ、社会に貢献しているとは言えないからです。
さらに近年では、環境保護から課題を見つけるアプローチも注目されています。資源の保護や持続可能な経済活動を実現するために、CSRを導入する企業も増えているのです。
このようにCSRを果たすには、様々な視点から検討する必要があります。そのため自ら課題を発見して、自分たちにとってのCSRとは何かを考えてから行動する必要があると言えるでしょう。
日本でCSRが注目されている理由
近年では、日本でCSRという言葉がしばしば使われるようになりました。その背景には、企業が起こす不祥事や経済のグローバル化、資源の保護が関係していると言われています。
ある企業における社会的な不祥事が発覚すると、消費者はその企業だけでなく属する業界にも不信感を抱く傾向が見られます。このような状況において企業が社会的な信用を獲得するためには、CSRを果たさなければならないという機運が国内で高まりつつあるのです。
また経済のグローバル化も関係しています。現在の日本では大企業以外にも国外で活動する企業が増加しており、ビジネスを行うにはそれぞれの国におけるCSRを意識するようになっているのです。
さらに資源の保護目的もあるとされています。日本では外国から資源を輸入して製品を作る企業が多いですが、経済を持続するために資源を適切に使う必要性が高まっています。
似た用語との違いを解説
CSRと類似している用語が世の中で広く使われています。その中でも、サステナビリティやSDGs、コンプライアンスは混同されがちですので、それぞれの違いについて解説します。
サステナビリティとの違い
サステナビリティとは「持続可能性」と訳され、現在の社会的機能や自然環境を継続するために必要な活動を指します。
企業活動などの社会的機能では資源を使って製品やサービスなどを提供しますが、サステナビリティによって資源の消費を抑制したり、新しい資源を生産したりするなどの活動を行います。つまり、サステナビリティは企業が健全に社会活動を行うための概念であり、CSRの一環という位置づけと言えるでしょう。
SDGsとの違い
SDGsとは、「持続可能な開発のための目標」と訳されます。2015年9月国に国連総会で採択された概念であり、地球環境を保全してより良い世界を作り上げていくための指標となっています。
SDGsは普遍的な目標が盛り込まれた概念ですが、一方CSRはそれぞれの企業が果たすべき社会的役割を示すための概念と言えます。そのためSDGsはどの企業や組織にも共通する目標であるのに対し、CSRは各企業の事情に合わせて課題やソリューションを見出して解決することを目指す指標である点が異なります。
コンプライアンスとの違い
コンプライアンスとは、「社会的規範の遵守」という意味です。コンプライアンスは社会が求めているルールを守って社会的責任を果たす概念ですので、企業が行うCSRのアプローチの一環という位置づけと言えるでしょう。
CSRを実践するメリット
CSRには、主に以下のメリットが挙げられます。
・社会的信頼の向上
・優秀な人材採用が期待できる
・コンプライアンスへの意識向上
それぞれ詳しく解説します。
社会的信頼の向上
CSRに取り組むことで、自社が適切な社会活動や環境保全に取り組んでいることをアピールできます。そのため、取引先や株主、消費者の信用を得ることができ、間接的に業績向上に貢献できる可能性があります。
またCSRへの意識徹底を進めることで、健全な企業体質の醸成も期待できるので、社会的に貢献する会社に成長できるでしょう。
優秀な人材採用が期待できる
CSRの徹底で社会的信用が得られれば、業績アップや企業基盤の安定につながります。そのため、優秀な人材が集まることが期待できるでしょう。
また企業経営が安定すれば、従業員の待遇改善も可能です。給料アップや手厚い福利厚生、より働きやすい職場環境の構築などが進めば、離職者の抑制も見込めます。
コンプライアンスへの意識向上
CSRの一環にはコンプライアンスが挙げられますので、企業全体で法令を遵守する意識の向上が期待できます。不祥事を未然に防ぐには企業の体質が重要ですので、従業員を含めた全体的な取り組みは有効と言えるでしょう。
CSRにおける注意点
CSRにはメリットがありますが、以下のような注意点も考えられます。
・コストや手間がかかる
・逆に人材が不足する可能性もある
それぞれ詳しく解説します。
コストや手間がかかる
CSRを導入するには、随時発生する課題の発見と解決が欠かせないため、企業によってはかなりのコストや手間がかかる可能性があります。そのため、かなりの予算や人手が必要となる可能性に注意しなければなりません。
逆に人材が不足する可能性もある
CSRを導入すると優秀な人材の採用を期待できますが、逆に人材が不足する可能性もあります。なぜなら少子化によって労働人口の減少が進んでいる日本では、人材不足に困っている企業も少なくありません。そのような場合には、CSRによってリソースが割かれてしまい、他の業務で人材を確保することが難しくなってしまうケースが考えられます。
CSRを実践するための7つの原則
CSRは世界各国で実施されており、その基本となる国際規格としてISO26000が定められています。ISO26000とは、2010年11月に国際標準化機構(ISO)から発行された社会的責任に関するガイダンスであり組織が社会的責任を果たす指針となっています。
ISO26000には以下の7つの原則が示されており、CSRを実践する上での重要な枠組みとして活用されています。
・説明責任
・透明性
・倫理的な行動
・ステークホルダーの利害の尊重
・法の支配の尊重
・国際行動規範の尊重
・人権の尊重
それぞれ詳しく解説します。
説明責任
企業では経済活動を含むあらゆる活動で、社会に対して影響をもたらします。その影響に関して詳しく説明を行い、責任を負うことが求められます。
透明性
意思決定では、透明性を確保する必要があります。具体的には、経営陣がどのようなプロセスを経て意思決定したかを明確にして、第三者が確認できる仕組みを作ることが求められます。
倫理的行動
企業のすべての活動は、倫理に基づいて行われければなりません。公平や誠実をモットーにした活動を心がけましょう。
ステークホルダーへの配慮
株主や取引先、顧客に配慮するだけでなく、従業員への配慮も求められています。CSRでは、社内外に関するあらゆるステークホルダーに対する心遣いが必要なのです。
法律の尊重
自国の法令だけでなく、外国で活動を行う場合にはその国の法令を遵守しなければなりません。昨今ではグローバル化が進んでいますので、重要な原則と言えます。
国際行動規範の尊重
企業が国際的に活動する場合には法令を遵守するだけでなく、規範や慣習を尊重することも求められています。
人権の尊重
人権は人間に等しく与えられている普遍的な権利であることを認識し、尊重した上で活動を行わなければなりません。
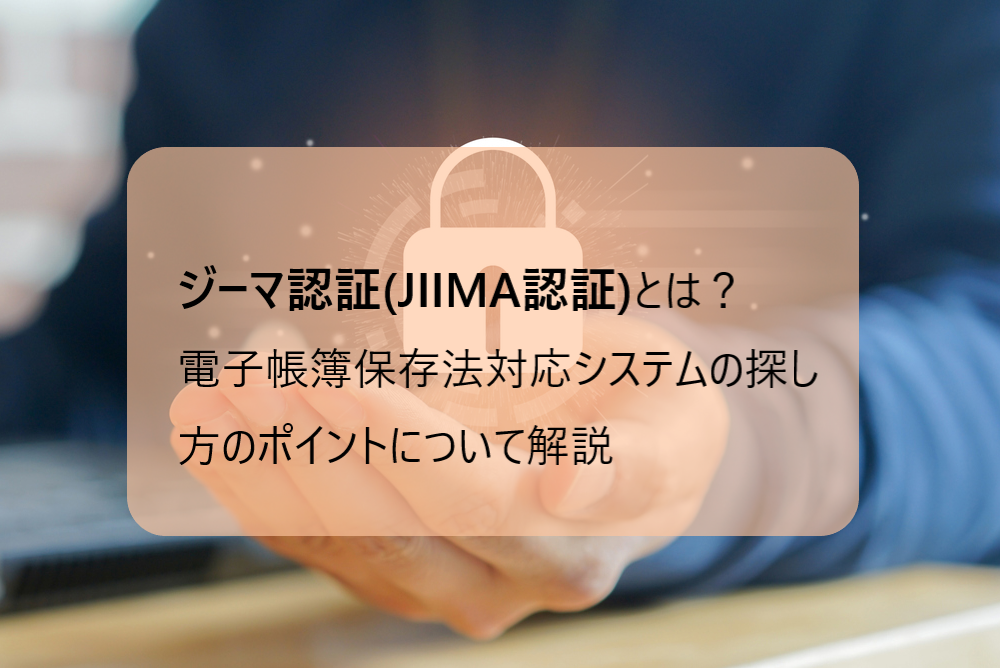
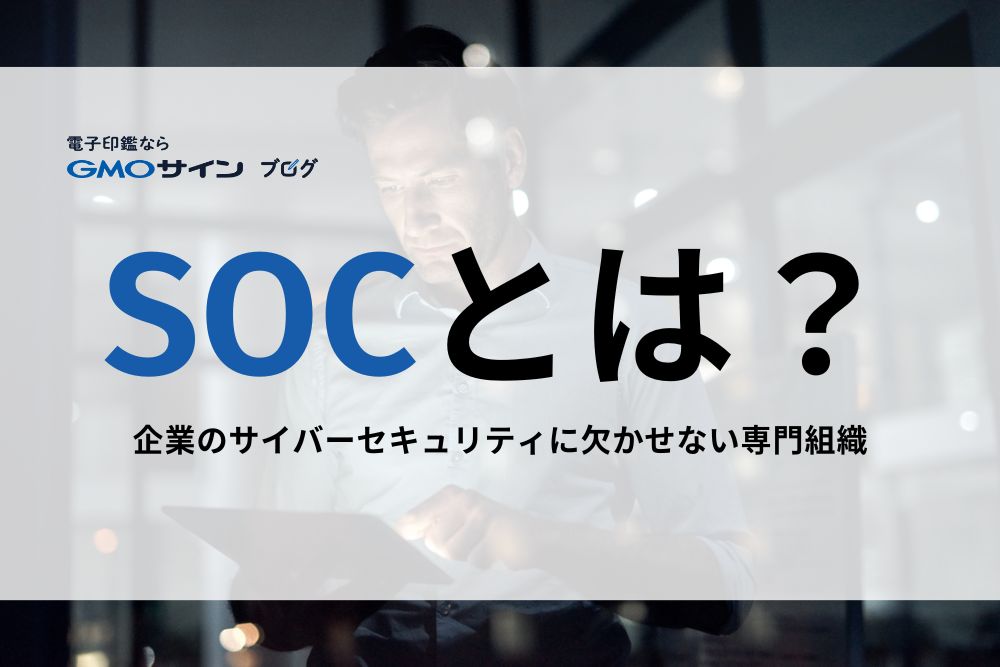
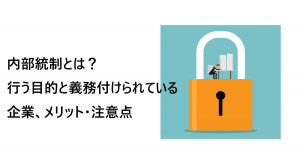

自社でCSRを導入するには
社会的責任が求められている現代では、CSRは企業が経済活動を行う重要な指針として役立ちます。実践すれば社会的信用の向上などのメリットを得られますが、コストや手間がかかるといった点を意識する必要もあります。
導入する場合には7つの原則を意識して自社の特徴や業界に合った活動に具体化し、すべての従業員に周知することから始めましょう。