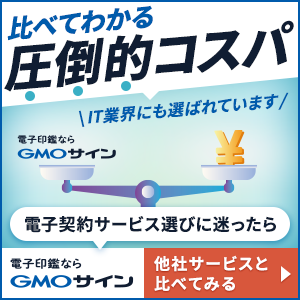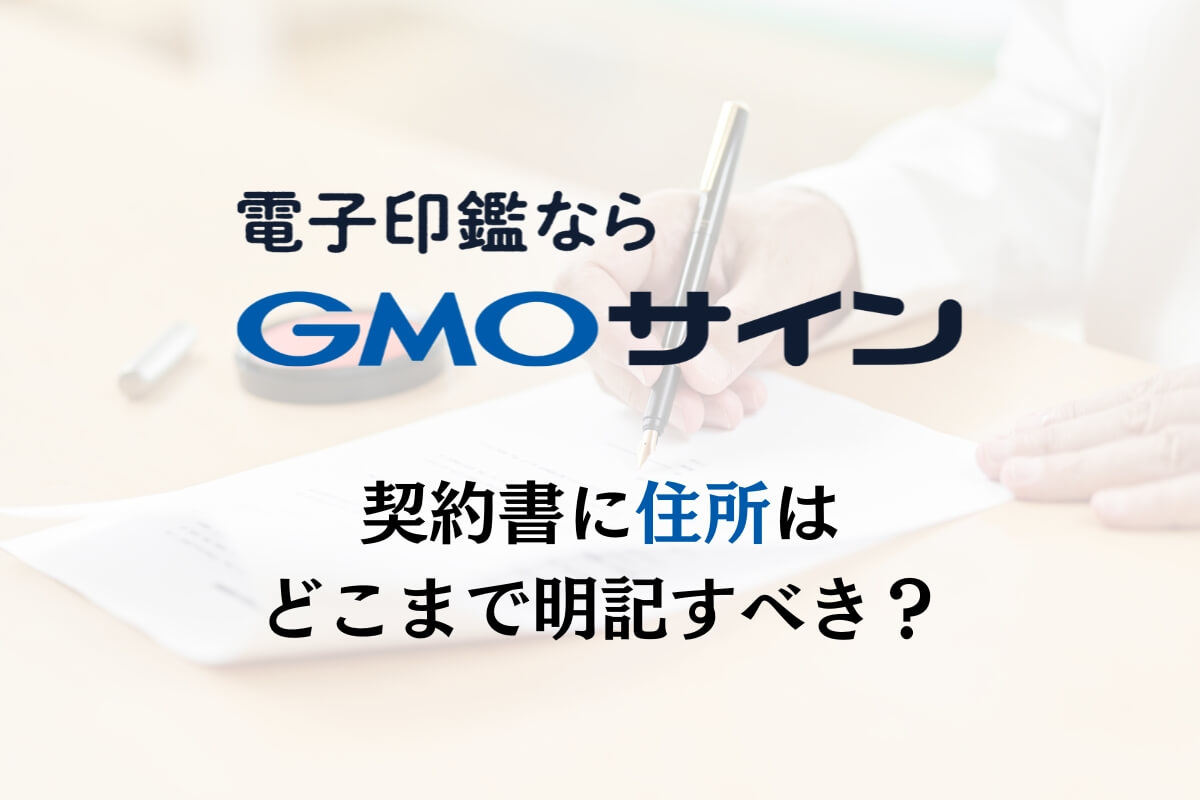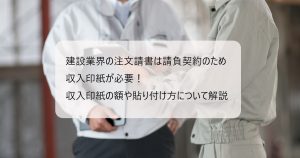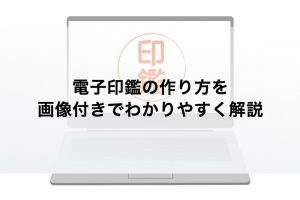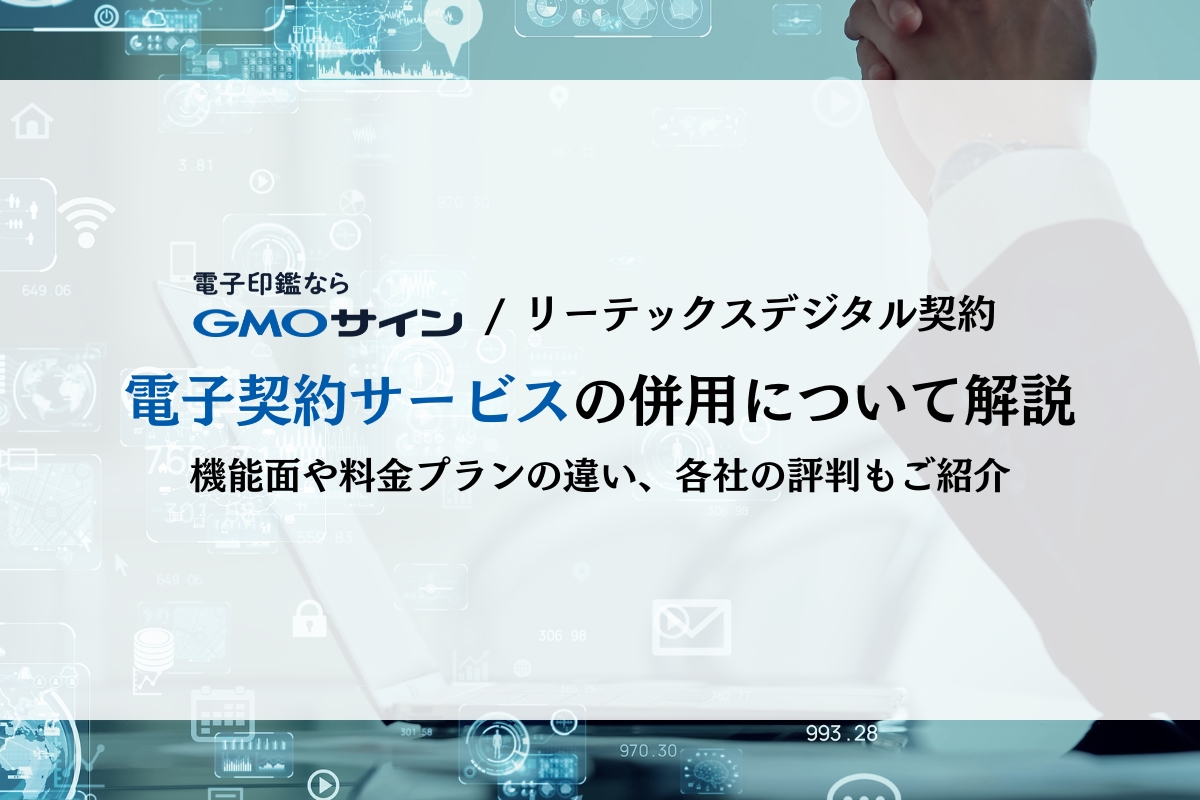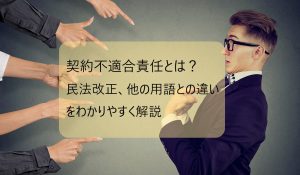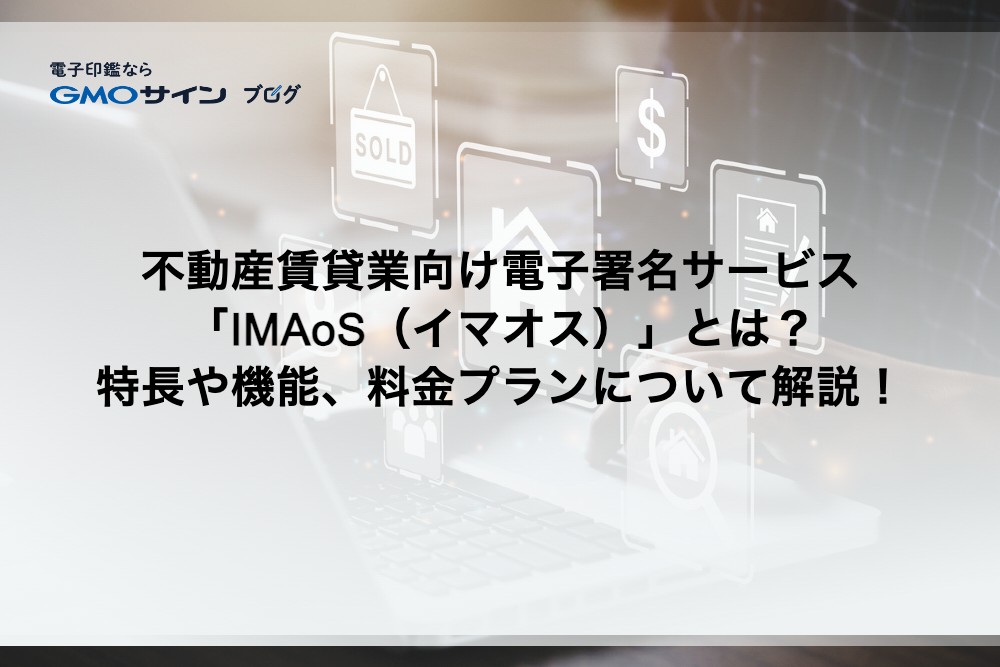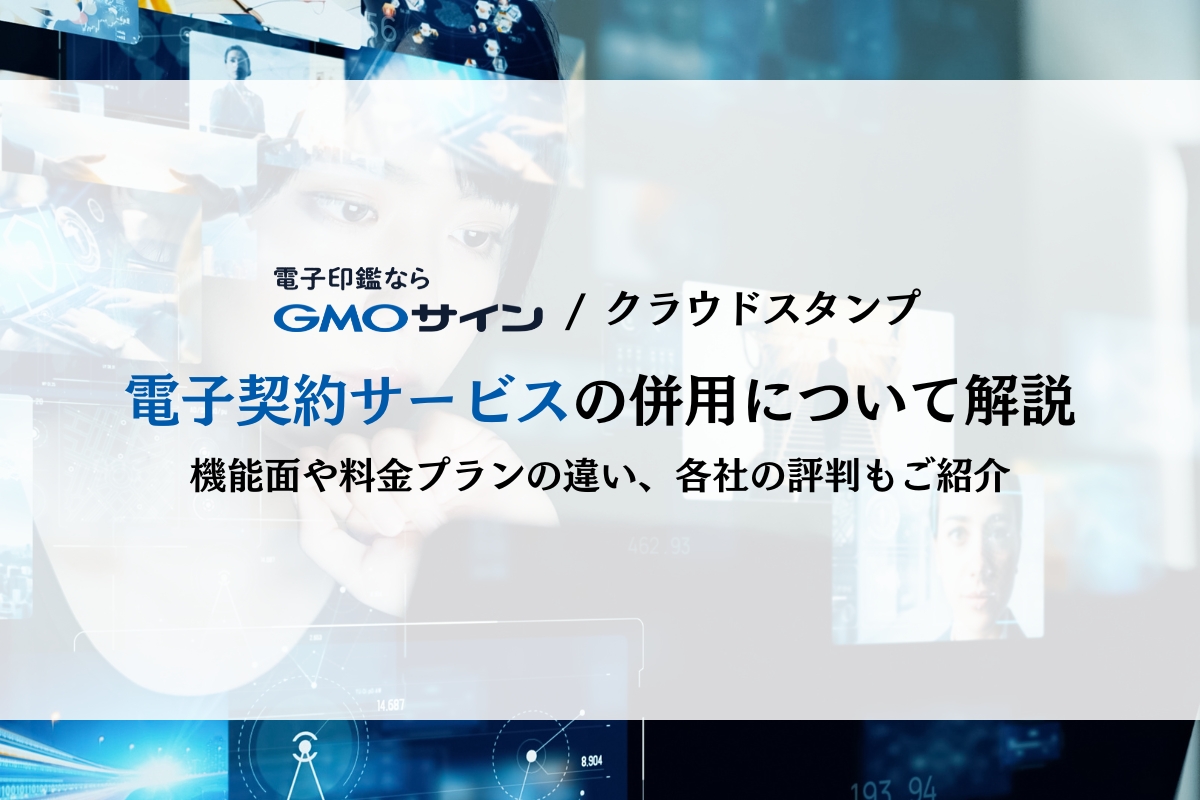送付状は単に書類を送るだけでなく、相手に対する敬意を示し、確認と記録のための証拠を提供する重要なツールです。
本記事では、送付状の必要性を理解し、適切に作成するための基本的なガイドラインを解説します。簡潔で明瞭な表現や適切な挨拶文の使用、それに伴うマナーやエチケットについて、具体的なポイントを紹介します。
送付状の役割とその記載内容
書類送付の際に使用する送付状ですが、契約書に添える場合、その役割とは何でしょうか。また、送付状にはどのような情報を盛り込むべきなのでしょうか。
送付物の明確化
送付状の最大の役割は、何を送ったのかを明確に伝えることです。送付状があれば、受け取った人がパッと見ただけで、「あ、これは契約書だな」と一目で理解することができます。
そのため、送付状は目次のような役割を果たし、書類の整理や確認作業をスムーズに進める助けとなります。
挨拶
挨拶は単なる言葉のやりとりを超えて、相手への敬意を示す大切な役割を果たします。
何も言わずに物を手渡される場面と、丁寧な挨拶とともに物を手渡される場面を想像すると、どちらが好ましいかは一目瞭然でしょう。後者の方が敬意を感じ、より良い印象を持つはずです。
同様に、送付状に一言添えることで、相手への敬意を示すだけでなく、相手に良い印象を与えることもできます。
こちらの要望を伝える伝達ツール
送付状は、単なる挨拶だけでなく、相手方への具体的な要望を伝えるツールとしても活用されます。
たとえば、契約書に署名して返送してもらいたい場合、「契約書をご確認いただき、問題がなければサインをいただき、返送してください」と記載します。具体的な要望を記載することで、具体的なアクションを依頼することが可能です。
このように、送付状は相手との円滑なコミュニケーションを促進し、ビジネスをスムーズに進めるための重要な役割を果たします。
送付状に記載すべき情報
書類を送付する際、送付状に記載すべき基本的な項目とその意義について詳しく見ていきましょう。
日付の記載:タイムスタンプとしての役割
送付状には、送付した日付を記載します。この日付は書類の送付履歴としての役割を果たすのです。書類の整理や管理、また、何か問題が生じた際に参照する重要な情報となります。
書類がいつ送られたのかを把握することで、遅延や紛失がないか確認することも可能です。
送付先と差出人:誰から誰に対する書類なのかを明確化
送付状には、送付先と差出人の会社名、担当者名を明記します。これにより、受け取る側が誰からどの書類を受け取ったのかを即座に認識できるわけです。
また、差出人が誰であるかを明示することで、何か問題が生じた際にはその人へ迅速に連絡が取れるというメリットもあります。
タイトル:送付内容の予告
送付状のタイトルは、送る書類の内容を一言で伝える役割があります。「契約書送付の件」のように具体的に書くことで、受け取った人はすぐに何が送られてきたのかを理解できるでしょう。
これにより、書類の優先度を判断したり、受け取った書類を適切に処理したりする手がかりにもなります。
挨拶文:コミュニケーションの窓口
挨拶文は送付状の中でも特に大切な要素です。それは、挨拶文がビジネスの世界におけるコミュニケーションの窓口となるからです。
挨拶文には頭語と結語があります。頭語は挨拶文の最初に記載される表現で、相手に対する敬意を示します。日本のビジネス文書では拝啓や拝呈などが一般的です。
これに続けて、時候の挨拶を入れます。「拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」のように具体的に書くと、親しみや敬意を伝えることができるでしょう。
結語は本文の終わりに記載され、敬具や拝具などが一般的によく用いられています。ここでも、相手に対する敬意を示す言葉を選ぶことが重要です。
結語の直前には感謝の言葉や、具体的な要望などを書くことが一般的です。たとえば、「今後とも一層のご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。敬具」といった書き方があります。
送付内容:詳細な説明
送付する書類の詳細な内容を明記します。本文の結びの挨拶のあとに「記」と中央に書き、その下に送付書類名と部数を箇条書きで記載し、最後に右下に「以上」と書くのが丁寧な形式です。
記
- 〇〇契約書 2通
- 会社案内 1部
以上
このように記載することで、受け取る側が書類の内容と数量を正確に確認できます。
備考欄
送付状の最後には備考欄を設けます。送付する書類に関する追加情報や要望などを記載するためです。たとえば、「契約書にサインをして、同封の返信用封筒に入れて返送してください」など、受け取る側に対する具体的な指示を記載することがあります。
送付する書類に特別な取り扱いを要求する場合や、そのほか受け取る側に知らせるべき重要な情報がある場合にも活用されます。
送付状作成のキーポイント
送付状の作成は、一見すると単純なように見えるかもしれません。しかし、実はその効果的な使用法と作成方法にはいくつかのキーポイントが存在します。以下でその主要なポイントを詳しく解説します。
PC作成(横書き)が一般的
現在のビジネスシーンでは、送付状はPCで作成し、A4用紙に横書きで印刷するのが一般的です。手書きである必要はありません。読みやすく、修正も容易なため、特別な理由がない限りPCでの作成をおすすめします。
手書きの場合は縦書きで
お礼状を兼ねるなど、特に丁寧な印象を与えたい場合は、手書きで作成することもあります。その際は、より丁寧な形式とされる縦書きで書くのが一般的です。
情報の端的な伝達
送付状は、その本質的な目的として、書類の送付を通知する役割を果たします。このため、情報は必要最小限に抑え、簡潔に書くことが重要です。
送付状は、差出人から受取人へのシンプルなメッセージの伝達手段であり、それ以上に情報過多となると、その本質的な機能を損なってしまいます。
適切な敬語の使用
送付状の目的は、情報を明確に伝達することです。
過度な敬語を使用すると、情報の伝達が曖昧になり、理解が難しくなる可能性があります。したがって、適度な敬語を用いて、文章をわかりやすく書くことが大切です。
書類の配列
送付状に記載した内容と同じ順番で書類を配列することで、受取人が書類を探す手間を省くことができます。これは、送付状が書類の目次としての役割を果たすことを考えると理解できるでしょう。
契約書の郵送に適した方法
契約書は「信書」に該当するため、法律上、日本郵便のサービス(ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットを除く)または国が許可した信書便事業者を利用して送付する必要があります。ここでは、契約書の送付によく利用される日本郵便のサービスについて解説します。
特定記録郵便
特定記録郵便は、郵便物の引き受けと配達状況(郵便受けへの投函まで)をインターネット上で確認できるサービスです。受取人の受領印は不要ですが、「いつ配達されたか」という記録が残るため、送付した事実を客観的に証明したい場合に適しています。
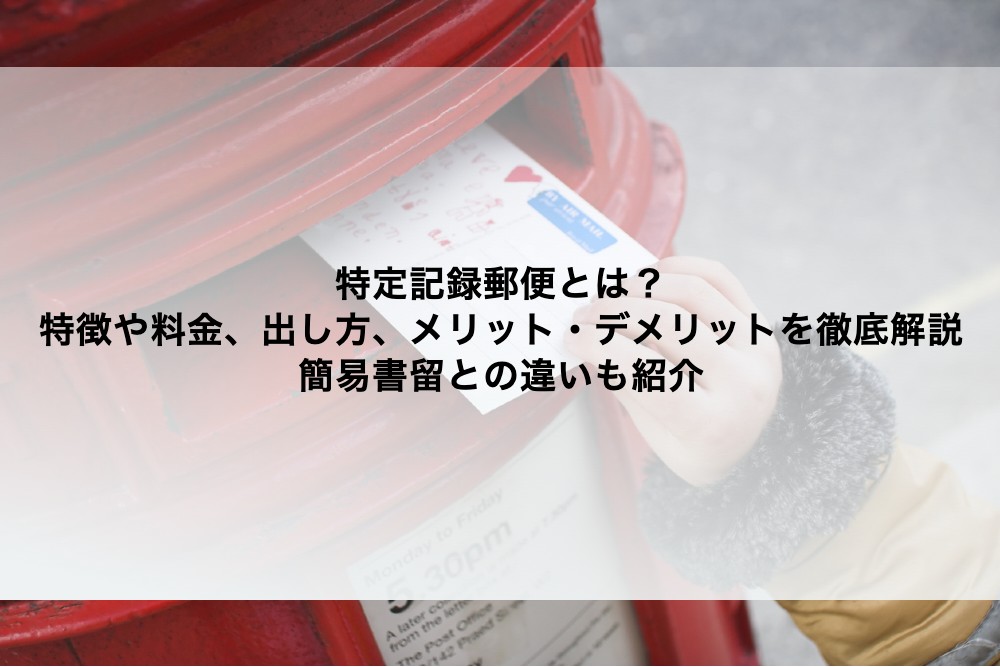
簡易書留
簡易書留は、引き受けから配達までの過程を記録・追跡でき、配達時には受取人へ対面で手渡し、受領印(または署名)をもらうサービスです。万一の場合の損害賠償額は、原則として5万円までとなります。確実に相手の手元に届けたい場合に最も推奨される方法の一つです。

レターパック
レターパックは、A4サイズの書類を全国一律料金で送ることができるサービスです。追跡サービスも付いています。
- レターパックプラス(赤色): 配達先へ対面で手渡し、受領印(または署名)が必要です。簡易書留と同様に、確実に届けたい場合に適しています。
- レターパックライト(青色): 郵便受けへの投函で配達完了となります。
契約書のような重要書類では、対面手渡しで受け取りが確認できる簡易書留またはレターパックプラスの利用がより安全と言えるでしょう。
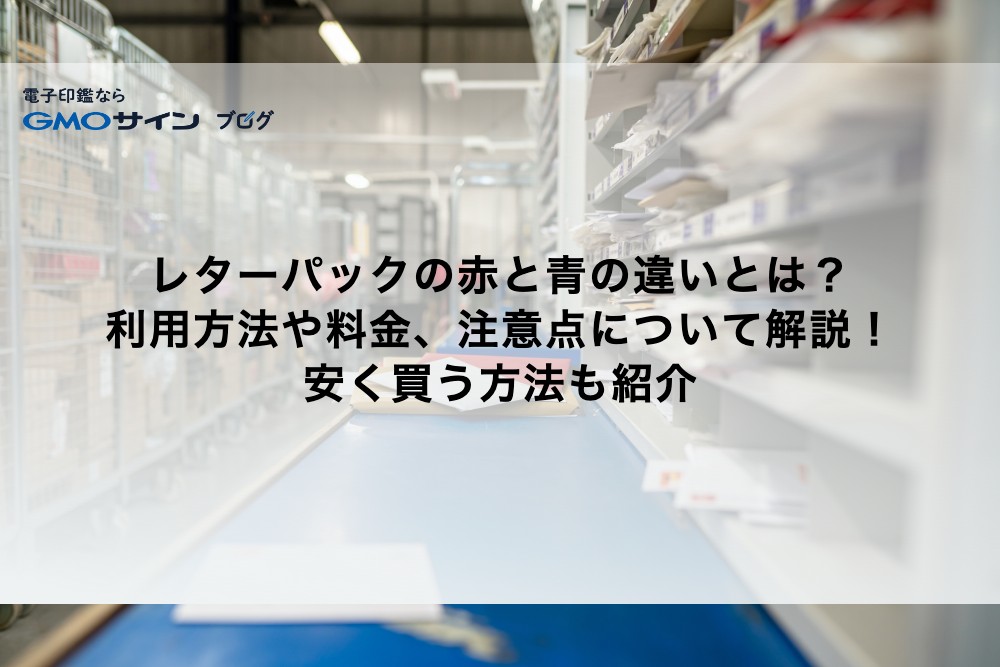
契約書送付のマナー
契約書は法的な意味を持つ重要な文書であり、その送付には特定のマナーが求められます。
文書保護:クリアファイルに入れて送る
契約書は法的な意義を持つ重要な文書であるため、折ったりせずにそのままの状態で送ることが求められます。そのため、クリアファイルなどの保護材に入れて送ることが一般的です。
これにより、書類が汚れたり、損傷したりするのを防ぐだけでなく、受け取った人が書類を見やすくなります。
プライバシー保護:透けない封筒を使用する
契約書の内容は重要な情報を含んでいるため、その内容を他人に知られることは避けるべきです。そのため、透けない封筒を使用して情報漏洩を防ぎます。
返送手続きの簡略化:返信用封筒の同封
契約書に署名捺印をして返送してもらう場合、返信用の封筒を同封するとよいでしょう。これにより、受取人の手間を省き、返送作業をスムーズに進めることが可能になります。
契約書と送付状に関するよくある質問
契約書に送付状は必要?
契約書を送付する際には、送付状を添付するのが一般的に推奨されます。
- 挨拶と内容物の明示
- 送付の目的の伝達
- ていねいな印象
- 確認事項の伝達
法的に必須というわけではありませんが、送付状には上記のような役割があり、ビジネスマナーとして重要とされています。
契約書を郵送する際に避けるべきことは?
契約書を郵送する際に避けるべきこととして、以下のようなものが挙げられます。
- 普通郵便のみで送付する(追跡・補償なし)
- 送付状を同封しない
- 封筒の宛名や差出人の記載が不正確・不十分
- 契約書を直接封筒に入れる
- 契約書の折り方が雑、または不適切な折り方
- 返信用封筒を同封しない(相手に返送を依頼する場合)
- 送付期限ギリギリに送る、事前の連絡なしに送る
これらは紛失リスクや証拠能力の確保、ビジネスマナーの観点から問題となる可能性があります。しかし、契約の効力そのものに影響するわけではありません。
契約書は折って送ってもいいですか?
契約書を折って送っても、法的効力の面からは問題ありません。A4サイズの契約書を長形3号の封筒に入れる場合は、封筒のサイズにあわせて折ることが一般的です。
もし、契約書を折らずに送りたい場合は、A4サイズの書類がそのまま入る「角形2号」などの大きめの封筒を使用しましょう。
\\ こちらの記事もおすすめ //

ビジネスパートナーとの関係を円滑にする契約書送付状
契約書に添える送付状は、ビジネスプロセスの一部として見過ごすことのできない重要な要素です。適切な送付状は相手への敬意を示し、コミュニケーションを円滑にし、かつ、紛失や誤解を防ぐ役割を果たします。
また、送付方法やマナーに気をつけることで、相手との信頼関係を深めることにもつながるでしょう。本記事の内容を参考に、相手に対する配慮と尊重を示す効果的な契約書送付状を作成してください。
契約書の送付・管理をもっと手軽で安全に!電子契約という選択肢
ここまで、契約書に同封する送付状の書き方や郵送のマナーについて解説してきました。これらは重要なビジネスマナーですが、一連の作業には印刷、封入、郵送といった手間や、切手代・封筒代などのコストがかかるのも事実です。また、郵送中の紛失リスクもゼロではありません。
電子契約なら送付状も郵送も不要に
電子契約サービスを利用すれば、作成した契約書データをクラウド上で相手方に送信し、オンラインで署名(電子署名)をもらうことができます。
- コスト・手間の削減:印刷、製本、封入、郵送といった物理的な作業が一切不要になります。郵送費や印紙税(※課税文書の場合)もかかりません。
- スピードアップ:郵送にかかる往復の時間がなくなるため、契約締結までのリードタイムを数日から数分に短縮できます。
- セキュリティ強化と管理の効率化:郵送中の紛失や情報漏洩のリスクがありません。締結後の契約書はクラウド上で安全に保管され、検索も簡単です。
送付状に記載していた挨拶や依頼事項は、電子契約の送信時にメッセージとして添えることができ、これまでの丁寧なコミュニケーションを維持したまま、業務を大幅に効率化できます。
はじめるなら「GMOサイン」
電子印鑑GMOサインは、導入企業数350万社以上の実績を持つ電子契約サービスです。立会人型電子署名を月に5件まで無料で利用できるお試しフリープランでも十分な機能が揃っています。
まずは無料プランから、契約業務の新しい形を体験してみませんか。