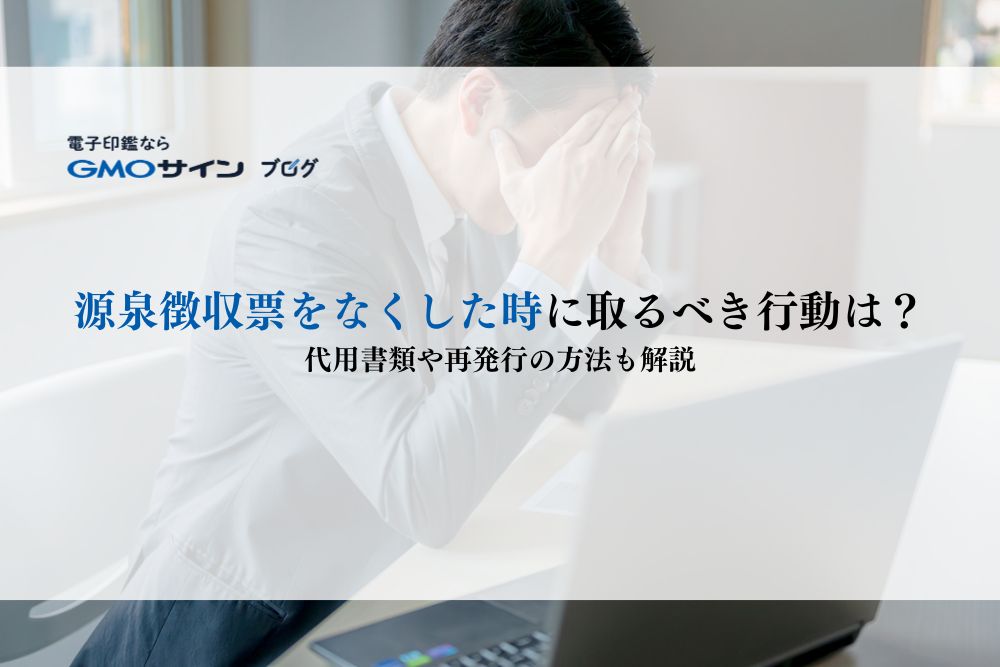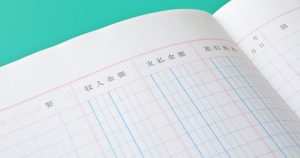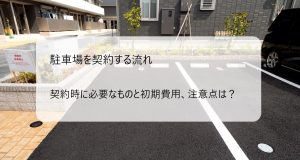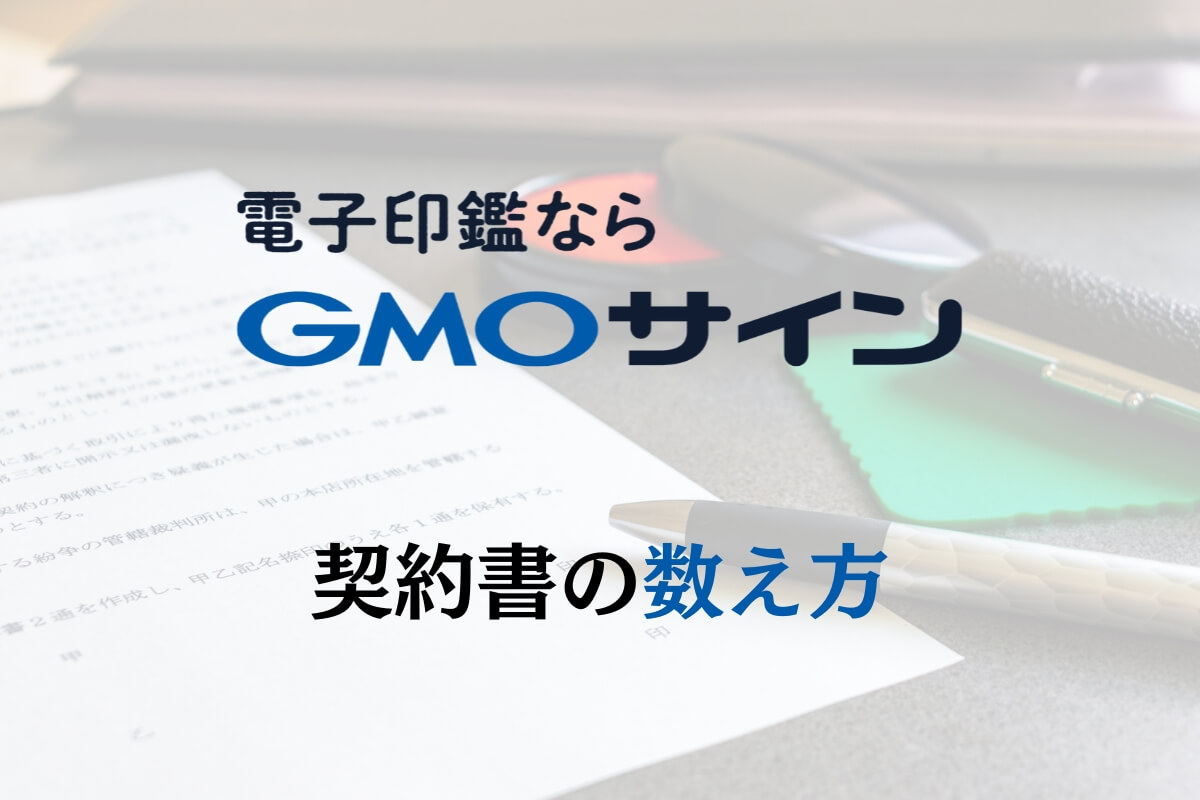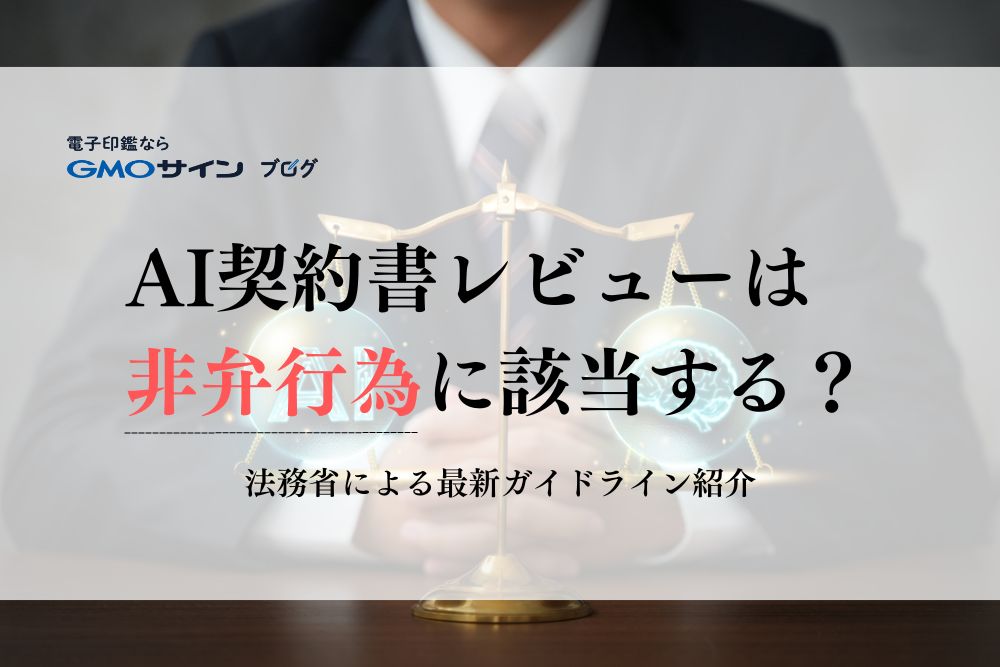商標登録は、企業のブランドイメージや利益を守るために必要な作業です。会社名やロゴマーク、キャッチコピーなど、目印になり得るものはすべて重要な商標として扱われるので、権利保護や利益確保のために登録をしておきたい人も多いでしょう。
この記事では、商標登録の内容や商標権を取得するメリットなどを詳しく解説します。具体的な手順についてもわかりやすく紹介するので、商標登録がどのようなものなのか知りたい方やこれから登録をしたい方はぜひ参考にしてみてください。
商標登録とは?
私たちの身近には、さまざまな製品やサービスがあふれています。製品やサービスは、その開発元である会社が他社と区別するために、特徴的な文字や図形などを付与していることが多いです。これらの文字や図形などは商標と呼ばれます。
製品やサービスに付いているロゴマークや製品に付けたキャッチコピー、会社名そのものなど目印になり得るものはすべて商標に当てはまります。この商標を自社のものであると主張するための法的な仕組みが商標権です。
商標権を取得すべき理由
企業は商標を使ってビジネスを展開します。しかし、有名になってくるとその商標を利用して不当に利益を得ようとする第三者が現れます。また、悪意がなくとも偶然同じような商標が作られてしまい、ユーザーが自社の商標と混同する事態にも陥りかねません。
このような事態に陥っては、自社に十分な利益が見込めず、逸失利益による損害も出しかねません。こうした問題を防ぐために、商標登録を行って商標権を取得する必要があるのです。
商標登録がされていないサービスに対して、意図的に外部の人間が商標登録を行うケースもあります。これによって商標を生み出したはずの本人がその商標を使用できず、かえって商標権侵害で訴えられたケースもあります。自分が作り上げた大切な製品やサービスの正当な権利を主張するためにも、商標登録を早急に進める必要があるのです。
商標権を取得するメリット
商標権を取得することにはさまざまなメリットがあります。取得には手続きが必要ですが、自社が抱える大切な商標であるならば早急に取得を目指しましょう。
類似の製品やサービスの利用を制限できる
商標権を取得すれば、登録した商標について、ビジネスにおける独占的な利用権が発生します。類似製品やサービスの利用も制限できるため、他社が無断で商標をそのまま、もしくは模倣したビジネスを展開した場合はその利用を停止させる差止請求が可能です。また、場合によっては損害賠償請求も可能になります。
商標が持つブランドイメージ向上
商標登録を済ませておけば、自社独自の製品やサービスであることを正当に主張可能です。
製品やサービスの評価が高まるに連れて、商標が持つブランドイメージも強まります。そのマークを見れば、一目で会社名が出てくるような企業は数多くあるでしょう。このような企業は、自社の商標をしっかりと守ったからこそ、高い認知度を得られたわけです。
商標ライセンス料を徴収できる
商標が有名になってくると、その商標を使って製品やサービスを展開させて欲しいと打診してくる企業も出てきます。そうしたケースでは、商標利用を認める商標ライセンス契約を交わすことが可能です。
ライセンス契約によって、使用料を徴収できるため、自社にとって重要な利益となります。また、その商標を他社に譲ってもよい場合は譲渡という形で商標を売却することも可能です。企業利益のために最適な選択を選びましょう。
商標登録は先願主義
商標登録は先願主義、つまり早い者勝ちとなっています。そのため、いくら自分達が作り上げた商標であっても、すでに類似したものが商標登録されている場合の利用は認められません。先願主義を悪用されることで、未登録商標を取得され、不当に商標権を主張される事態に陥る可能性もあります。
手続き時の事前調査によって類似の商標が登録されていれば仕方ありません。しかし、商標を本格的にビジネスで利用する場合は、早急に調査のうえ登録可能であれば手続きに進みましょう。
商標登録のやり方
商標登録の手続きは、いくつかの段階に分けられます。すべての段階をクリアできれば無事登録になるため、手順と手順ごとの注意点について押さえておきましょう。
事前調査
手続きを進めるうえで最初に行うべきは、事前調査です。類似の商標がすでに登録されており出願できない状況ではないか、そして以降の審査で合格するレベルの商標であるかを確認します。
まずは類似の商標登録がないかを商標データベースより確認しましょう。自身の商標そのものはもちろん、文字や図形の特徴などから類似の商標登録の有無についても調べて、登録にふさわしいものであるかを調査します。
次に、登録予定の商標に何かしらの特徴があり、ありふれたものでないかも確認します。商標は類似したものだけではなく、あまりに特徴がないものも審査に通りません。インターネットなどで登録予定の商標の分野について調べて、自身の商標が特徴的かを判断しましょう。
特許庁へ出願
事前調査で問題がない場合は、商標登録願を作成します。特許庁のサイトよりテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入します。ここで、あらかじめ商標についての区分を決めることが必要です。
商標登録出願時には、対象の商標がどの区分に該当するかを指定する必要があります。指定した区分で商標登録が認められた場合、その区分内においては商標の独占権がありますが、ほかの区分では独占権が認められません。
商標が複数の区分にまたがる場合は、願書も複数の区分を指定して出願しなければならないため注意しましょう。
特許庁による審査
出願届を提出後は、特許庁による審査に進みます。ここでの審査は大きく方式審査と実体審査に分けられます。
方式審査では、出願書類の内容不備や印紙代の金額など形式上の審査が行われます。その後、商標登録を認めてもよいか、権利の詳細な内容について精査される実体審査が行われます。
実体審査は、商標法で定められた多くの審査項目に基づく審査です。事前調査でも確認した類似商標や特徴の有無などを厳しくチェックされます。この審査で登録に相応しくないと判断された場合は、特許庁から拒絶理由通知が送付されます。
登録査定
審査に通過した場合には、登録査定に進みます。査定といってもここでは登録に関する手続きを進めるのみです。
商標登録
審査の合格通知が送達されてから30日以内に登録料を特許庁へ納付することで、正式に商標登録が完了します。期限内で登録料の納付が完了しなかった場合、出願が取り下げられるため注意しましょう。
登録料の納付後、1カ月前後で特許庁から登録証が届きます。登録証には登録された権利の詳細や登録番号について記載されているため、大切に保管しておきましょう。
商標権の存続期間は10年
商標権は、一度登録すれば永続的に効力を持つわけではありません。存続期間は10年となっており、この期間を過ぎてしまうと効力を失います。しかし、手続きを行うことで、さらに10年の期間商標権を更新可能です。
存続期間終了の6カ月前から、存続期間最終日の間に更新手続きを行わなければならないため、手続きを忘れて失効しないように気をつけましょう。10年以上商標を利用してビジネスを続ける場合は、必ず更新を行いましょう。
商標登録は外部へ依頼するのがおすすめ
商標登録の申請や必要書類の準備は自身でも可能です。しかし、通常業務と並行して事前調査などを進めるのがたいへんな人も多いでしょう。その場合は商標登録の手続きを外部へ依頼するのもおすすめです。
商標登録は、商標をはじめとした知的財産権の専門家である弁理士に依頼するとよいでしょう。その場合は、商標登録費用にくわえて依頼料も発生するため、自社の予算も考慮したうえで検討してください。
商標を利用していなければ取り消し請求のリスクも
商標登録はしたものの、その商標がしばらく(継続して3年が目安)利用されていない場合は、不使用取消審判の請求がなされて登録商標が無効化されるケースもあります。
不使用取消審判は、ライセンス契約や譲渡での利益を得る目的で、商標登録を繰り返す第三者に対して有効な対処法ではあります。しかし、自身の商標の場合でも類似商標を持っている会社から請求が来ないとも限りません。
商標登録に関するよくある質問
商標登録にかかる費用はいくら?
商標登録でかかる費用の総額は、指定する区分数や登録時印紙代の納付方法によって異なります。
【印紙代の分割納付時】
| 区分数 | 出願時印紙代 | 登録時印紙代 | 総額 |
| 1 | 12,000円 | 17,200円 | 29,200円 |
| 2 | 20,600円 | 34,400円 | 55,000円 |
| 3 | 29,200円 | 51,600円 | 80,800円 |
【印紙代の一括納付時】
| 区分数 | 出願時印紙代 | 登録時印紙代 | 総額 |
| 1 | 12,000円 | 32,900円 | 44,900円 |
| 2 | 20,600円 | 65,800円 | 86,400円 |
| 3 | 29,200円 | 98,700円 | 127,900円 |
弁理士に依頼する場合は、上記の金額にくわえて手数料や謝金が必要です。事務所によって具体的な金額は異なりますが、日本弁理士会のアンケートによると1区分指定の場合は最も多いケースとして手数料が5万~8万円、謝金が4万~6万円ほどかかります。
商標登録は早い者勝ち?
商標登録は、原則として先に出願したものが権利を得られます。同一または類似の商標がすでに出願・登録されている場合、あとで出願された商標は登録できないので注意しましょう。
商標登録ができないものはある?
以下の項目に該当する場合は商標登録ができません。
引用:出願しても登録にならない商標|特許庁
- 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
- 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
- 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
出願をする際は、自社の商標が上記に当てはまっていないか確認しましょう。確実に登録を行いたい場合は、弁理士に商標調査を依頼することがおすすめです。
商標登録で自社の利益を適切に守ろう
商標登録は、自社の作り上げた製品やサービスを守り、利益を得るための大切な制度です。商標を使ったビジネスを続けるためにも、入念な事前調査を行ったうえで早急に登録手続きを進めましょう。
商標登録は、先願主義であるため、少しでも後れをとるとその商標が使えない可能性も十分にあり得ます。その状態で商標を利用してしまうと、商標権侵害として損害賠償請求を提起されるリスクもあるため、気をつけなければなりません。取得後も存続期間については注意し、期限が迫ってきたら更新手続きを忘れずに行いましょう。