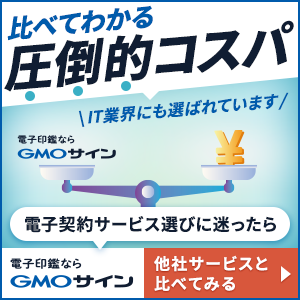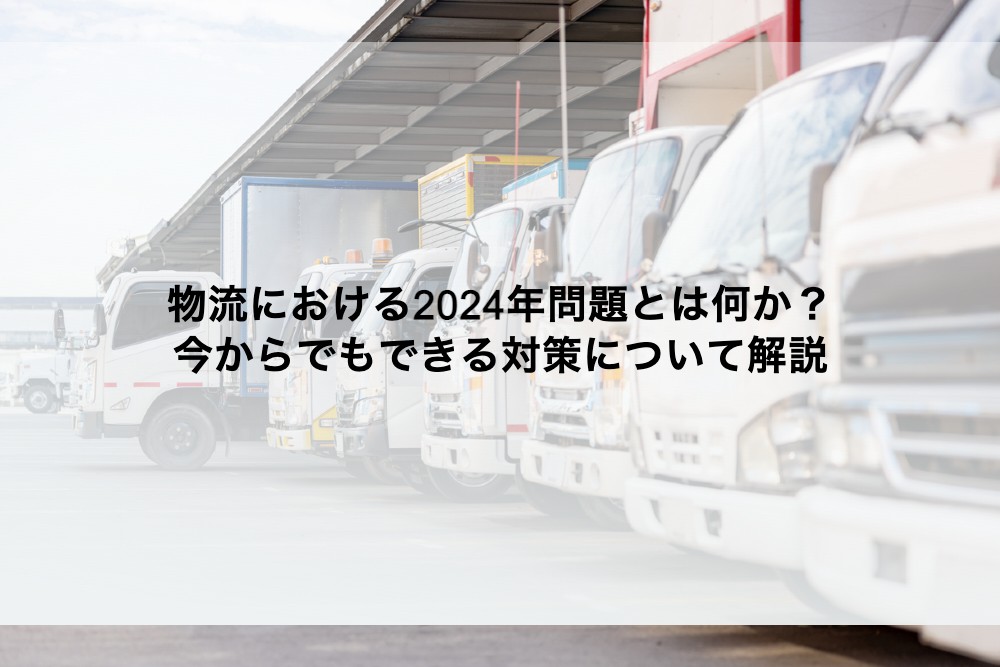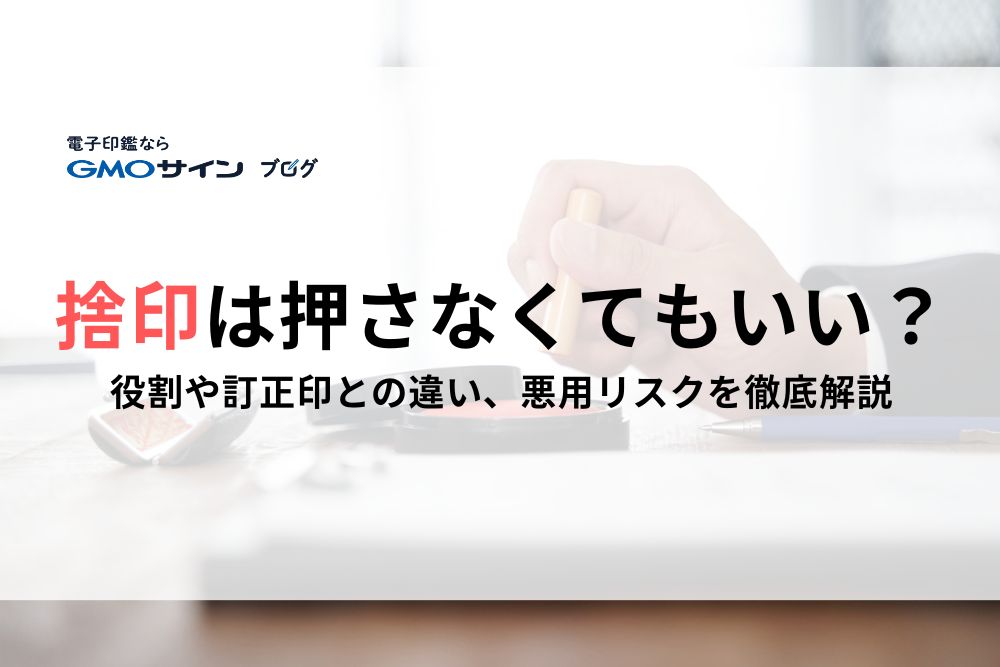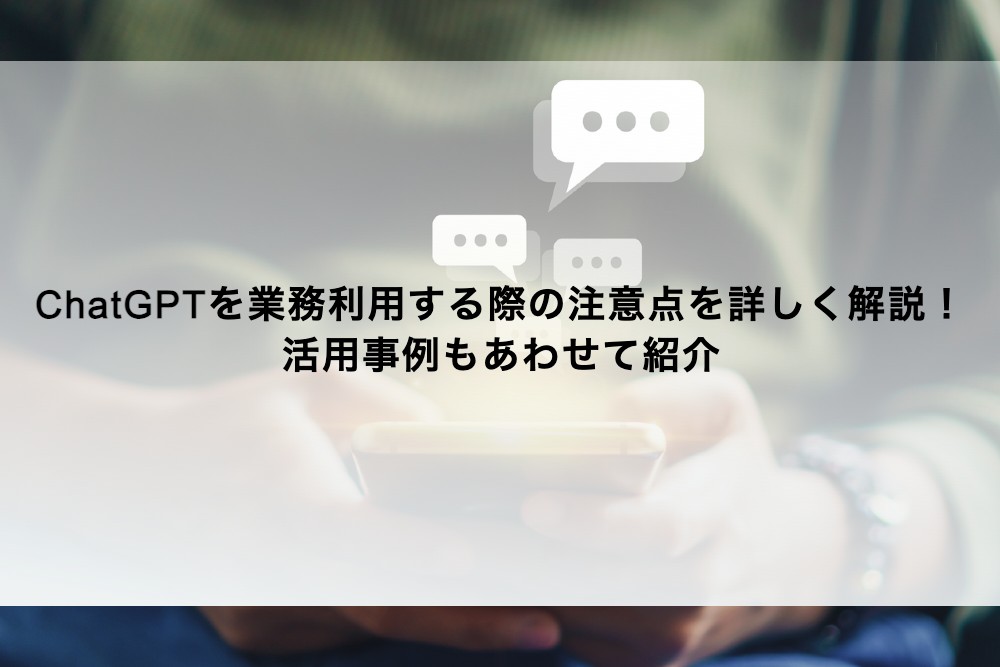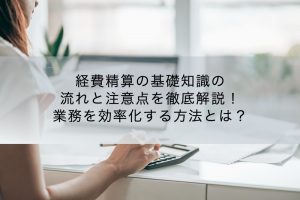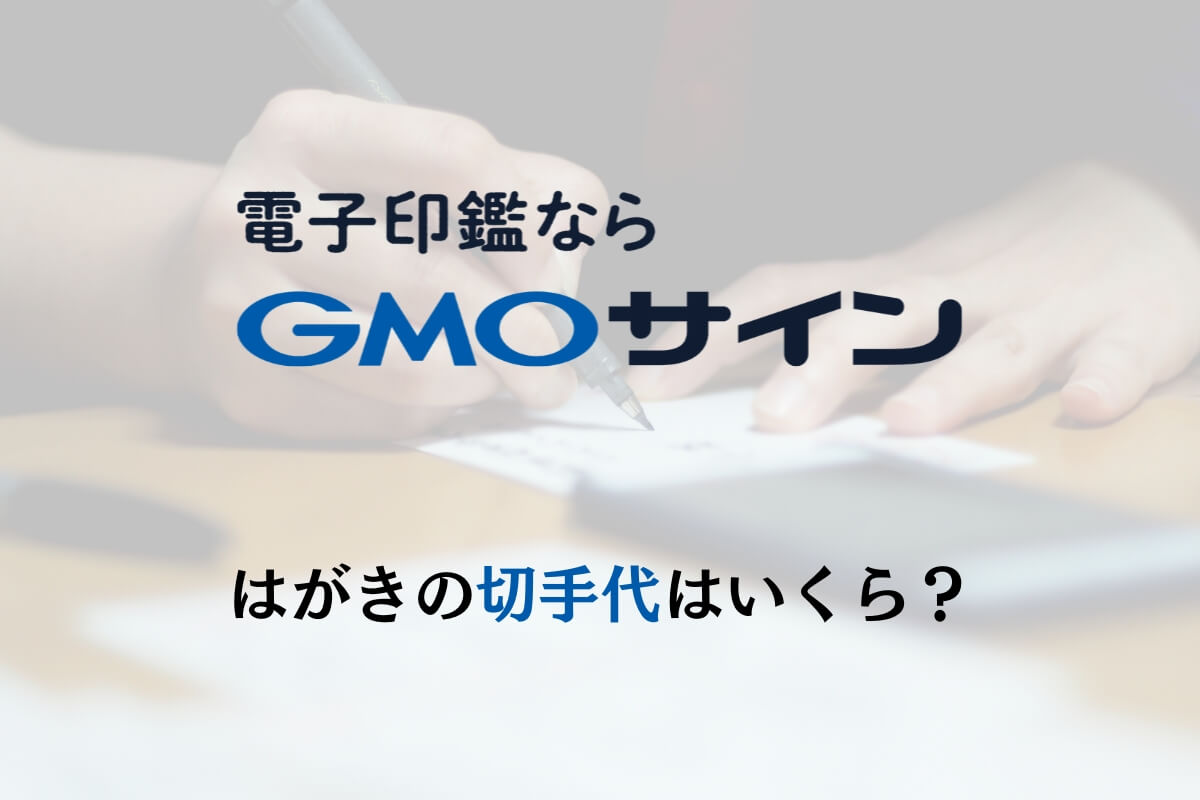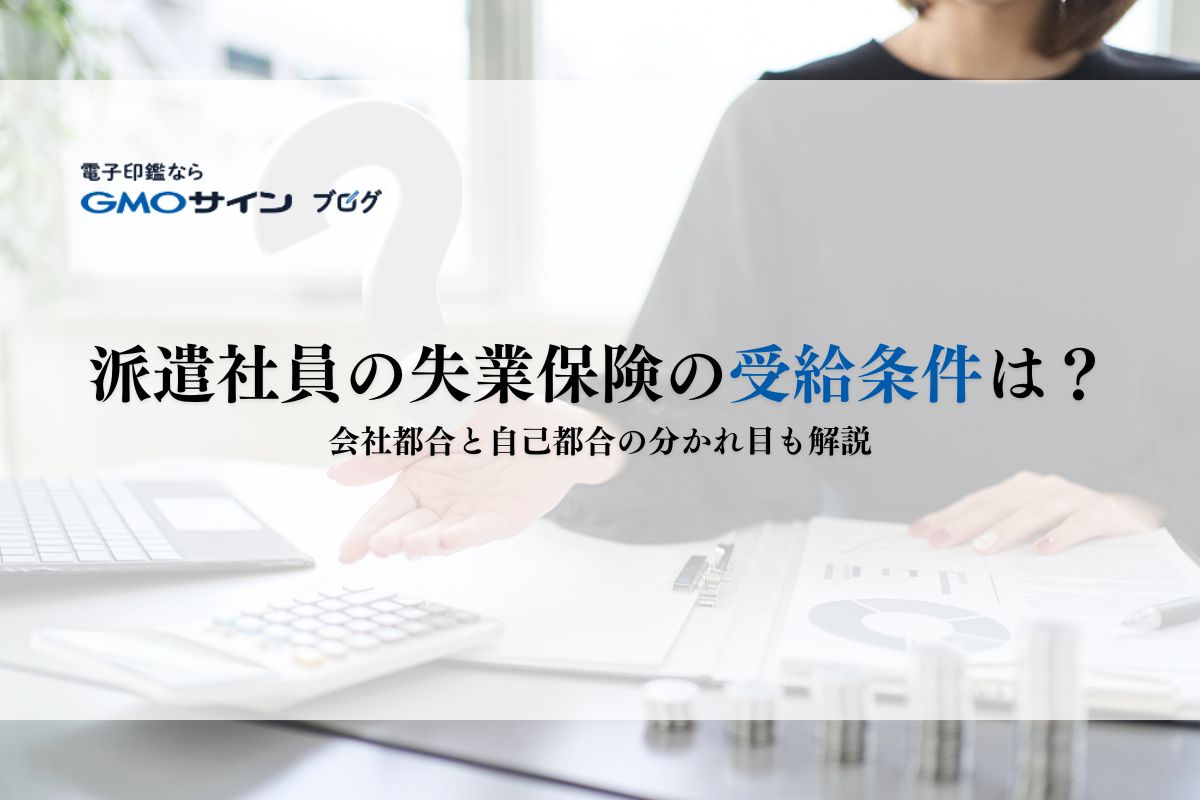2025年の公益通報者保護法改正で、どのような対応が求められる?
内部通報体制の構築や運用について、具体的に何から始めればよい?
この記事では、2025年施行の公益通報者保護法改正について、事業者が押さえるべき重要ポイントと実務対応をわかりやすく解説します。
- 公益通報制度の基本概念と改正の背景
- 令和7年改正における4つの主要変更点
- 企業規模別の体制整備義務と具体的要件
- 違反時の罰則内容と企業への影響
- 実務で必要な対応フローと準備事項
改正内容への対応に不備があると、企業が行政指導や刑事罰の対象となり、社会的信用失墜のリスクを負う可能性があるため、注意が必要です。本記事を参考にして改正内容を把握し、必要な対応を進めましょう。
公益通報とは?種類と条件
企業活動における不正を早期に発見し、是正するためには公益通報者保護法の正しい理解が不可欠です。まずは、制度の基本を解説します。
公益通報制度の目的
公益通報制度は、企業や行政機関における法令違反を内部から発見・是正するために設けられました。企業内部で不正が行われた際、いち早く察知できるのは現場で働く従業員です。しかし、不正を指摘したことで解雇されたり、職場で不利益な扱いを受けたりするリスクがあれば、多くの人は声を挙げることをためらってしまうでしょう。
不正行為が放置されれば、製品の欠陥による消費者被害や環境汚染、不正会計による株主への損害など深刻な事態へと発展しかねません。公益通報者保護法は正当な通報をした労働者などを不利益な取扱いから保護することで、安心して不正が指摘できる環境を整え、問題の早期発見と是正につなげることを目指しています。
公益通報の対象となる事実・種類
公益通報の対象となるのは刑法や労働基準法、消費者契約法など法令違反や社会的に重大な不正行為です。どのような法律が対象になるかは政令で具体的に定められており、その数は刑法や食品表示法、金融商品取引法など約500本にものぼります。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
- 食品メーカーによる産地や賞味期限の偽装
- 自動車メーカーによるリコール隠し
- 工場からの基準値を超える有害物質の排出
- 不正な会計処理による粉飾決算
- 顧客情報のずさんな管理と漏えい
一方で、社内における人間関係のトラブルや上司への不満、法律違反にあたらない社内ルール違反などは、原則として保護対象となりません。セクシャルハラスメントやパワーハラスメントも基本的に対象外です。
公益通報の成立条件
公益通報が成立し、公益通報者保護法による保護を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 通報者は正社員やアルバイトなどの労働者
- 通報内容が法令違反や不正行為に該当する
- 通報の目的が不正の目的ではない
- 法律で定められた通報先へ通報する
それぞれ解説します。
要件① 通報者は正社員やアルバイトなどの労働者
通報者は、企業の労働者が対象です。正社員や契約社員だけでなく、アルバイトやパートも含まれます。なお2022年の改正では、退職から1年以内の退職者・役員・取引先労働者などが追加され、現役社員に限定されていた保護を大幅に広げました。
要件② 通報内容が法令違反や不正行為に該当する
通報の内容が行政罰や刑事罰の対象となる法令違反に該当していること、かつ真実相当性(通報者が合理的な根拠を持っていること)が認められることが必要です。
要件③ 通報の目的が不正の目的ではない
通報対象事実が存在しないことを知りながら虚偽の通報をする、通報を盾に金銭や物品を要求するなど、通報の目的が個人的な恨みや嫌がらせ、あるいは単なる好奇心など公益の保護とは関係のない動機の場合は対象となりません。
要件④ 法律で定められた通報先へ通報する
公益通報が保護されるためには、適切な通報先への通報が求められます。おもな通報先は以下の3つです。
- 事業者内部:内部通報窓口など
- 行政機関:厚生労働省や消費者庁など
- その他の外部機関:報道機関や消費者団体など
これらの要件を満たすことで、通報者は法的な保護を受けられます。
【参考】消費者庁:公益通報ハンドブック
公益通報者保護法改正の背景と施行スケジュール
法律は、社会の変化に対応して姿を変えていきます。公益通報者保護法も2004年の制定から年月を経て、より実効性のある制度へと大きな見直しが行われました。ここでは、どのような経緯で改正されてきたのか、2025年改正の背景や施行時期について解説します。
制度の沿革と改正の背景
公益通報者保護法は2004年に制定され、2006年から施行された制度です。しかし、当初の法律では通報者の保護が十分とはいえず、多くの課題を抱えていました。
たとえば、勇気を出して内部告発した従業員が報復として解雇されたり、閑職に追いやられたりする事例が相次いだのです。これでは従業員が萎縮してしまい、不正の早期発見という制度本来の目的を達成できません。
2025年の改正では、より実効性の高い運用体制の整備や、企業規模に応じた義務付けの明確化が盛り込まれています。
2025年改正の施行はいつから?
公益通報者保護法は2025年6月4日に改正法が成立し、公布日(6月11日)から1年6カ月以内に施行される予定です。今回の改正は、通報者の保護強化と企業の対応義務の拡充をおもな目的としています。
施行日に向け、企業は社内体制の見直しや新たな対応ルールの策定、担当者への研修などを段階的に進める必要があるでしょう。
令和7年改正の4つの主要ポイント
2025年に改正された公益通報者保護法では、従来の制度を大幅に見直す内容が盛り込まれています。ここでは、特に重要な4つのポイントを解説します。
公益通報者の範囲拡大
1つ目のポイントとして、公益通報者として保護される対象が、大きく拡大されたことが挙げられます。従来は企業の従業員や役員が中心でしたが、フリーランスや業務委託先の個人など、企業と直接雇用関係にない者も新たに保護の対象となります。また、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスも対象です。
今回の改正により、企業の枠組みを超えた多様な働き方をする人が違法行為や不正を発見した際に、安心して通報できる環境が整えられます。現代の労働環境に即した保護範囲の拡大は、内部通報制度の実効性を高め、社会全体のコンプライアンス向上にも寄与するものです。事業者側も新たな対象者への対応や教育が求められるため、体制整備の見直しが不可欠となります。
公益通報の対象拡大・阻害要因への対処
通報対象となる違法行為の範囲が広がり、企業による内部通報体制の不備そのものが通報対象となりました。従来は刑事罰や過料が科される法律違反が対象でしたが、企業が通報対応従事者の指定を怠る行為も公益通報の対象に含まれるようになったのです。なお300人以下の事業者は努力義務のため、体制不備だけでは通報対象となりません。
通報者が安心して声を上げられるよう、企業は通報窓口の運用における公平性と透明性を確保する必要があるでしょう。
体制整備の義務化と刑罰規定の新設
2020年の改正(2022年6月1日施行)により、常時使用する労働者が300人を超える事業者では、公益通報対応業務従事者の指定と内部通報フローの整備がすでに法定義務となっています。今回の2025年改正では、義務の実効性を高めるために以下を新設しました。
- 勧告に従わない場合の命令権
- 命令違反時に個人・法人とも30万円以下の罰金を科す刑事罰
- 報告徴収に加えた立入検査権限
内部通報体制の未整備そのものは、命令・検査を経ても是正しない場合に30万円以下の罰金(両罰規定、拘禁刑なし) が適用されます。
不利益取扱いの抑止・救済強化
通報者が通報を理由に解雇や降格、懲戒などの不利益な取扱いを受けることを防ぐため、改正法では不利益取扱いの抑止と救済措置が一層強化されました。具体的には、公益通報から1年以内に行われた解雇や懲戒については、通報を理由としたものと推定される規定が新設され、企業側に立証責任が課されます。
- 行為者個人に6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 法人に3,000万円以下の罰金
通報を理由とした不利益取扱いをした個人や法人に対しては、直罰や重い罰則が科されることとなり、通報者保護の実効性が大幅に高まったといえるでしょう。
改正に伴い事業者に課される新たな責務
公益通報者保護法が事業者に求める新たな責務について解説します。改正のポイントを理解し、実効性のある内部通報制度を構築しましょう。
内部通報体制の構築義務(300人超は義務、300人以下は努力義務)
従業員数が300人を超える事業者は、内部通報体制の整備を構築する義務があります。具体的には通報者が安心して内部通報できる環境を確保し、企業自らが不正行為の早期発見・是正に努めることを求めるものです。
従業員数300人以下の事業者の場合は努力義務ですが、企業規模にかかわらず内部通報制度を整備することで、コンプライアンス意識の向上とリスク低減につながるでしょう。
通報窓口・担当者の選定と独立性の確保
事業者は、公益通報に対応するための体制を整備する義務も負います。具体的には通報窓口および公益通報対応業務従事者の任命を行う必要があります。通報窓口の設置と担当者の選定は、通報者が不安なく相談できる体制づくりの要です。
不正の通報先が人事部門や経営層に近い部署である場合、通報の公平性や通報者の安全が確保されにくくなるでしょう。通報内容の公平な調査とふさわしい対応のため、担当者は経営層から独立した立場で選任し、利害関係者の関与を避けることが求められます。
是正措置の実施と運用体制の整備
是正措置の実施と運用体制の整備は、改正公益通報者保護法において企業に強く求められる重要な責務です。公益通報を受けた場合、企業はその内容について迅速かつ公正な調査を実施し、法令違反や不正行為が判明した場合には具体的な是正措置を講じなければなりません。
是正措置には、不正行為の停止や再発防止策の策定、関係者への指導・教育の徹底などが含まれます。これらを通して、内部統制の強化と組織の健全性維持を図りましょう。
従事者への教育・守秘義務の徹底
通報対応業務に携わる担当者には、法令や社内規程の正確な理解と実務に即した対応力が求められます。そのため、企業は定期的に研修や勉強会を実施して通報制度の目的や流れ、通報者保護の考え方、調査手順などを体系的に教育することが不可欠です。
また従事者が通報対応の過程で得た情報を不用意に漏えいしないよう、具体的なケーススタディを交えた実践的な研修も効果的です。守秘義務違反が発生した場合、企業だけでなく個人にも行政指導や罰則が科される可能性があるため、全担当者が高い倫理観を持って業務にあたることが求められます。
通報者への不利益取扱いの禁止と損害賠償責任の免除
通報者が公益通報してから1年以内に解雇や懲戒処分を受けた場合、それが通報を理由としたものであると推定される立証責任の転換が導入されました。従来は通報者側が不利益取扱いの因果関係を証明する必要がありましたが、改正後は企業側が通報を理由としたものでないことを立証しなければなりません。
また通報者に対する解雇や懲戒などの不利益取扱いが行われた場合、これを抑止するための刑事罰も導入されました。
- 行為者個人に6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 法人に3,000万円以下の罰金
違反した個人に対しては拘禁刑や罰金が、法人に対しては最大3,000万円以下の罰金が科されるなど、罰則が大幅に強化されています。
通報後の適切な対応と紛争予防策
通報を受けた企業は迅速かつ公正に事実関係を調査し、必要に応じて是正措置を講じなければなりません。調査の過程では通報者や関係者のプライバシー保護を徹底し、通報内容の秘密保持を厳格に守ることが義務付けられています。
適切な対応によって、通報後に生じる誤解やトラブルを最小限に抑え、組織内での紛争を未然に防げるでしょう。通報者への不利益取扱い防止や、通報内容の漏えいを防止するための教育・研修も強化されており、違反があった場合には刑事罰や行政指導が科される可能性があります。
公益通報者保護法に違反したらどうなる?
公益通報者保護法に違反した場合、企業や個人がどのような行政的・刑事的な措置を受けるかについて解説します。想定されるリスクを理解し、未然に防止する体制づくりに活用してください。
報告・助言・指導・公表の対象となる場合がある
企業が法令に基づく通報対応体制を整備していない、または不適切な運用をしている場合、行政機関による報告徴収や助言、指導の対象となります。たとえば従業員300人超の事業者が通報担当者を指定していない場合、厚生労働省や各所管官庁が具体的な是正を求める指導をすることが可能です。
また重大な違反があったにもかかわらず改善されない場合は、消費者庁が企業名などを公表する運用が検討されています。企業にとっては社会的信頼の低下を招くリスクがあるため、形式的な体制ではなく実効性のある通報制度の運用が求められるでしょう。
刑事罰・罰則が課される場合がある
公益通報者保護法では、違反行為の内容によって刑事罰や罰則が異なります。
- 体制未整備の場合
- 公益通報者に対して報復行為を行った場合
それぞれの違いを理解しておきましょう。
体制未整備に対する行政措置と罰金
常時300人超の労働者を抱える事業者が内部通報体制を整えず、監督当局の勧告にも応じない場合は命令が発出されます。それでも是正しなければ、個人・法人とも30万円以下の罰金が適用され、命令違反企業として公表される可能性があります。
300人以下の企業は努力義務ですが、取引先から体制整備を求められるケースも多いため、早期にルール準拠のフローを導入しておくとリスクヘッジになるでしょう。
報復行為に対する刑事罰
公益通報を理由に従業員を解雇・減給したり、降格や配置転換で不利益を与えたりすると、行為者個人には最長6カ月の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には最高3,000万円の罰金が科されます。
通報者報復は刑事事件化しやすく、判決と同時に企業名が報道されるケースも多いです。そのため、単なる法令順守だけでなく役員から現場まで報復禁止を明文化し、教育の徹底を図ることが不可欠です。
企業の実務における具体的な対応フロー
2025年に改正された公益通報者保護法に対応するために、企業が取るべき具体的な対応手順を5つのステップでまとめました。形だけでなく運用面においても実効性を確保し、従業員が安心して通報できる環境づくりを進めていきましょう。
内部通報対応規程の見直し
まずは、既存の内部通報規程の再点検と見直しをしましょう。2025年改正では、通報対象の範囲拡大や対応体制の義務化など多くの実務的変化が生じており、これらに準拠したルール整備が不可欠です。
新たに義務化された事項や通報者の保護範囲の拡大、調査手順の明確化など、法改正の要点を反映した規程へとアップデートしましょう。
体制構築・マニュアル整備
通報窓口の設置とともに、社内外の関係者が迷わず対応できるよう運用マニュアルの整備が必須です。
特に、常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が300人を超える事業者は体制構築が義務であり、担当部署の明確化や調査・報告・是正までの一連の流れを標準化する必要があります。
マニュアルには通報受付から初期対応、調査手順や報告様式などを具体的に記載し、関係者の判断や行動に一貫性を持たせましょう。トラブル発生時の対応や、通報者との信頼関係の維持についてもルール化することで現場対応の質を高められます。
通報対応者の選定と教育(または外部窓口の検討・整備)
通報対応のために、公益通報対応業務従事者を任命する必要があります。法的にも定められた役割であり、通報受付から調査、改善措置までを一貫して担い、守秘義務や中立性が求められる立場です。
対応者には守秘義務の研修を定期的に実施し、通報者の個人情報や通報内容が漏えいしない体制を整備します。ヒアリング手法や調査の進め方などをまとめたマニュアルを整備しておくことで、対応のばらつきを防げるでしょう。
社内通知
制度の実効性を高めるために、改正内容や通報制度の意義を全従業員に周知しましょう。新しい規程や通報の流れ、保護の仕組みを明示するだけでなく「なぜ通報制度が必要なのか」「どのような時に活用するべきか」といった制度の背景もあわせて説明することで、制度への理解を深められます。
あわせて通報が組織の健全性維持に資するものであることを繰り返し発信し、通報しやすい職場風土の醸成にも努めてください。
実施状況のモニタリング・継続的改善
制度の定着には、導入後のモニタリングと継続的な改善が欠かせません。定期的に通報件数や対応状況、再発防止策の実施率などを検証し、必要に応じて規程やマニュアルをアップデートしましょう。
通報が適切に処理されているか、通報者が不利益を受けていないかなど、第三者的な視点を取り入れたチェック体制の構築も効果的です。法令を守ることにとどまらず、組織の透明性向上や従業員の信頼獲得といった観点から、内部通報制度を企業価値向上やリスクマネジメントの要として位置づけることが求められます。
公益通報者保護法の改正に関するよくあるQ&A
公益通報は努力義務?
公益通報自体は、従業員や関係者にとって義務ではなく、努力義務でもありません。通報するか否かはあくまで本人の自由意思に委ねられており、通報しなかったからといって法的責任が生じることはありません。
ただし、企業としては不正を早期に把握する手段として内部通報制度を機能させることが求められており、従業員が安心して通報できる環境整備が強く期待されています。
通報者には法的な保護が用意されているため、通報に対する誤解を払拭して制度の信頼性を高めることが大切です。
従業員数が300人を超える事業者における公益通報窓口の設置は義務?
公益通報窓口の設置は義務です。300人超事業者に対する内部通報体制の整備義務は、すでに2022年6月1日施行の2020年改正法でスタートしています。さらに2025年の改正では、この義務の実効性を担保するために監督権限(命令・立入検査)と命令違反時の罰則が追加されました。
- 体制未整備(命令違反時):個人・法人とも30万円以下の罰金
- 報復行為(解雇・減給など):個人6カ月以下の拘禁刑/30万円以下の罰金、法人3,000万円以下の罰金
300 人超の企業は体制を整えるだけでなく、勧告・命令への対応も視野に入れた運用体制を構築する必要があります。

従業員数300人以下の事業者がやるべきことは?
窓口設置や体制整備は義務ではありませんが、法令違反の予防や従業員の安心感向上のためも可能な範囲で通報制度の導入が望ましいといえます。
たとえば簡易的な通報窓口の設置や、通報者保護の方針を明文化するだけでも組織の透明性と信頼性の向上につながります。法的義務がない場合でも、社会的責任を果たす観点から積極的に対応していきましょう。
改正内容を把握して必要な対応を進めよう
2025年の公益通報者保護法改正は、企業にとって制度の形だけ整える時代から、通報が実際に機能する仕組みを作る段階への転換を意味します。
この記事を参考に改正法のポイントを正しく理解し、早い段階で自社の制度設計と運用の見直しを進めていきましょう。
内部通報制度の運用を効率化・高度化する電子契約の活用
公益通報者保護法の改正に対応した内部通報制度を適切に運用するには、規程の整備や周知、通報記録の厳格な管理など、多くの事務手続きが伴います。これらのプロセスに電子契約サービスを導入することで、コンプライアンス体制をより強固なものにできます。
活用例1:規程改定時の同意取得・管理
内部通報規程を改定した際は、全従業員への周知と内容を理解したことの確認が必要です。電子印鑑GMOサインのような電子契約サービスを使えば、従業員一人ひとりへの説明・同意取得手続きをオンラインで完結できます。誰がいつ同意したかの記録が一元管理でき、担当者の負担を大幅に削減します。
活用例2:調査記録や関係者とのやり取りの信頼性確保
通報内容の調査記録やヒアリングの議事録は、その後の是正措置の根拠となる重要な証拠です。これらの文書に電子署名とタイムスタンプを付与することで、「いつ」「誰が」「どのような内容」の文書を作成したかを法的に証明し、改ざんを防ぎます。これにより、調査プロセスの客観性と信頼性を飛躍的に高めることができます。
活用例3:外部専門家(弁護士など)との契約締結
外部の法律事務所などを通報窓口として委託する場合、委託契約や秘密保持契約の締結が必要です。電子契約サービスを利用すれば、契約手続きを迅速かつ安全に進めることができ、ペーパーレス化によるコスト削減と管理効率の向上にも繋がります。
免責事項(本記事のご利用にあたって)
本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。