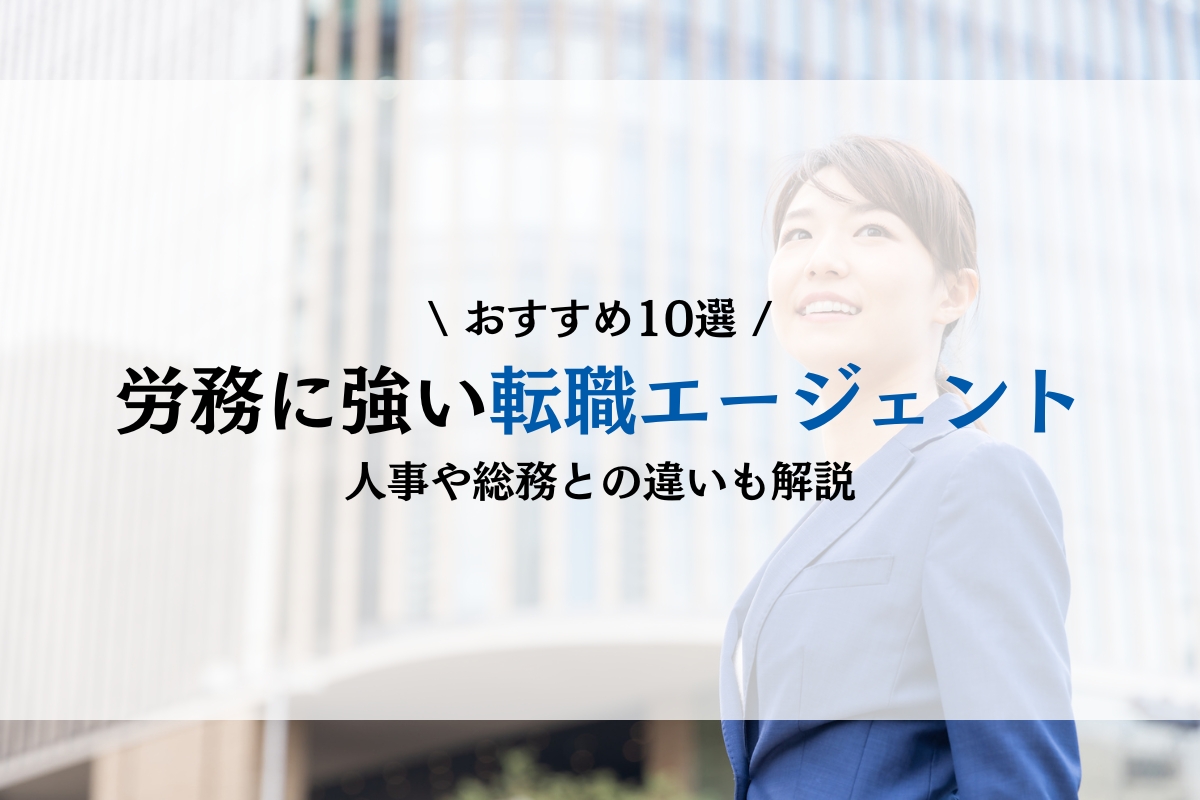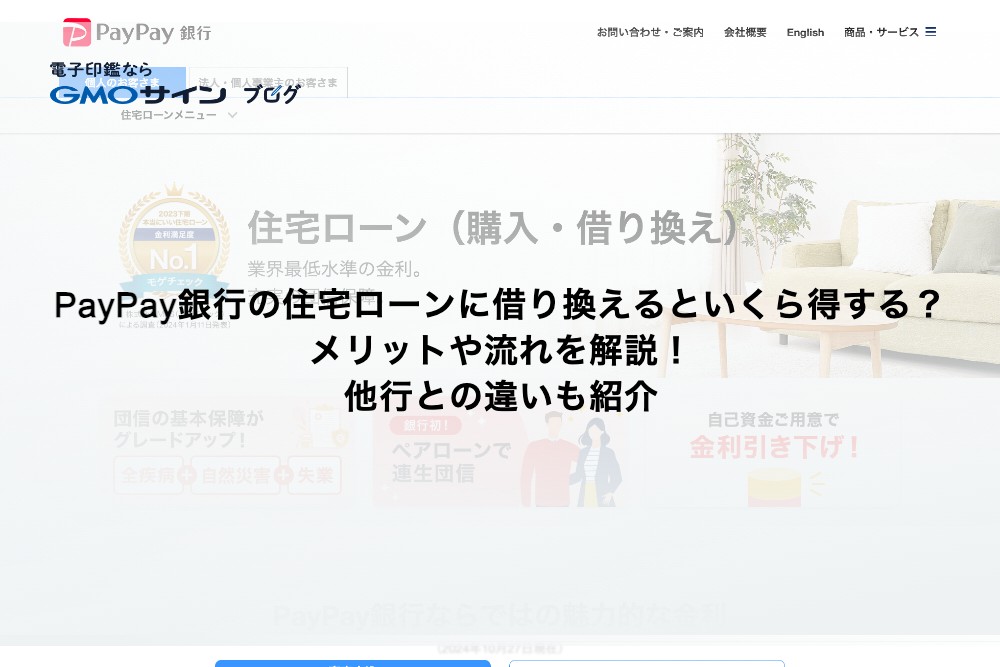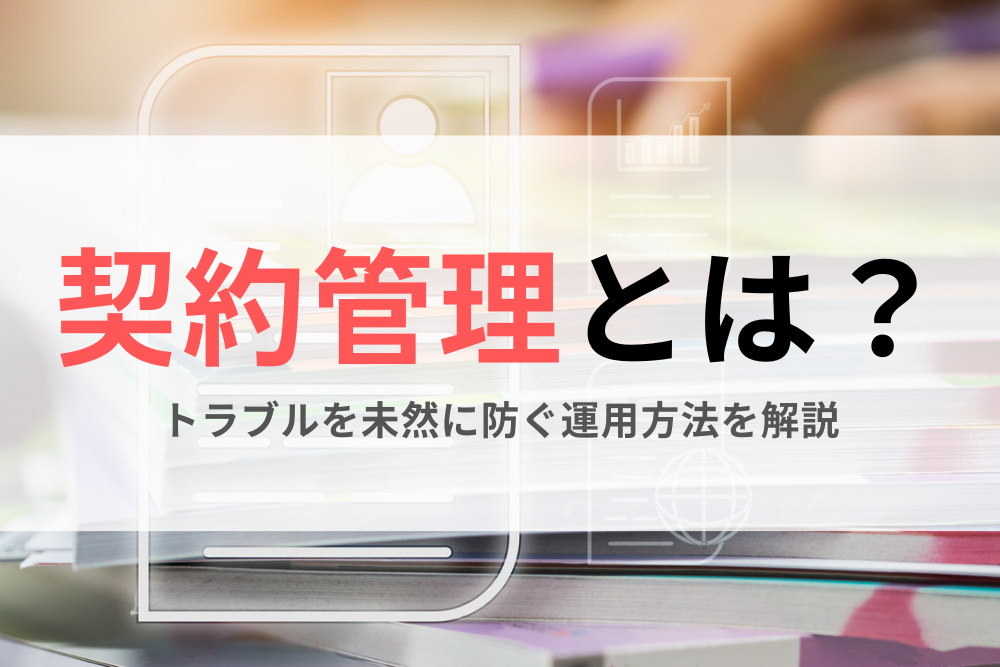\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /


売買契約書は、売主と買主が商品やサービス、不動産などの売買取引を行う際に取り交わす重要な文書です。取引内容や条件を明確に記載することで、取引をスムーズに進められるだけでなく、トラブルやリスクの回避にもつながります。
本記事では、売買契約書の基本から、雛形や記載項目、作成時の注意点をわかりやすく解説します。売買契約書の作成にかかる手間やコストを抑える方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
売買契約書とは、商品やサービスの売買において、売主と買主が合意した取引条件を文書にまとめたものです。民法522条では、売買契約は口頭での約束でも成立するとされていますが、契約書を取り交わしておくことで後々のトラブル予防やリスク軽減につながります。
たとえば、以下のようなトラブルが発生した場合でも、契約書が証拠となり、スムーズな解決に役立ちます。
また、地震や台風、火災など不可抗力による損害が発生するケースも考えられます。損害が発生した場合に、売主と買主のどちらが損害の補償責任を負うのかを明確にし、損害補償の範囲をあらかじめ取り決めておくことで、双方が安心して取引を進められるでしょう。
売買契約書は、取引する対象や契約の形態によって主に以下の3種類に分けられます。
それぞれの契約書の特徴や活用される場面を詳しく解説します。
不動産の売買に関連する契約書は、土地や建物を売買する際に、売主と買主の間で取り交わす書面です。取引内容によって契約書の種類は異なりますが、よく使われるものは以下の通りです。
| 土地・建物に関連する売買 | 借地権・抵当権付きの不動産の売買 |
|---|---|
| ・不動産売買契約書 ・土地建物売買契約書 ・土地売買契約書 ・建物売買契約書 ・農地売買契約書 ・区分所有建物売買契約書 | ・借地権付建物売買契約書 ・借地権付底地売買契約書 ・抵当権付売買契約書 |
不動産の売買契約においても、法律上は契約書を作成しなくても口頭で成立します。しかし、不動産は高額かつ重要な資産であるため、トラブル防止の観点から契約書を作成するのが一般的です。通常は、売買の仲介を行う不動産会社が契約書を作成し、内容に問題がなければ売買契約が締結されます。
商品やサービスの売買に関連する契約書は、企業間や個人間で物品の売買を行う際に締結する文書です。一般的に「物品売買契約書」と呼ばれ、主に以下の場面で使用されます。
物品売買契約書には、取引対象となる商品やサービスの名称、製造番号などの詳細を明記し、当事者間の認識違いによるトラブルを防ぐ役割があります。
契約内容は、原則として当事者同士の合意によって自由に決められます。商法や民法の規定と異なる内容で契約する場合は、後のトラブルを防ぐためにも、具体的な内容を契約書に記載しておきましょう。
特定の相手と複数回にわたる継続的な売買取引を行う場合、毎回同じ契約を締結するのは売主・買主双方にとって大きな負担になります。そこで、共通の取引条件をあらかじめ定めた売買契約書である「継続的売買取引基本契約書」を取り交わすのが一般的です。継続的売買取引基本契約書には、具体的に以下の文書があります。
基本契約の締結により、日常的な取引に関する契約手続きの手間やコストの負担が軽減されます。さらに、売主は販路の安定確保、買主は仕入れ先の確保につながるメリットがあります。契約内容と異なる条件で取引を行う場合のみ、個別契約を締結する進め方です。
ここからは、売買契約書の書き方を紹介します。売買契約書を作成する際は、取引内容や条件を正確かつ具体的な記載が重要です。記載漏れを防ぐためにも、売買契約書の主な記載項目・内容や雛形を参考にして作成してみてください。
売買契約書には、取引する商品や代金、納入の期日や場所、支払い期日などを記載します。主な記載項目・内容は以下のとおりです。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 当事者の表示 | 売主・買主の氏名(名称)と売買契約である旨 |
| 売買の目的物 | 商品名や数量など取引対象の情報 |
| 引き渡し | 引き渡しの期日・場所・方法・費用負担(運送費や保管費用など売主・買主どちらが支払うか) |
| 代金と支払方法 | 金額、支払期限、支払方法 |
| 所有権移転時期 | 所有権が移るタイミング |
| 検査 | 検査方法や検査期間 |
| 遅延損害金 | 支払い遅延時の遅延損害金の利率 |
| 契約不適合 | 不具合や仕様違いがあった場合の対応 |
| 危険負担 | 自然災害や火災など不可抗力による損失時の責任範囲や代金支払いの取り決め |
| 保証 | 品質保証の基準 |
| 契約解除 | 契約違反や破産した場合は契約解除できる旨 |
| 損害賠償 | 賠償範囲や内容 |
| 協議事項 | 契約書に記載のない事項は協議で解決する旨 |
| 合意管轄 | トラブルが発生して裁判を行う場合、どの裁判所が管轄か |
特に引き渡しの期日や場所、所有権の移転時期、支払期限・方法などはトラブルが起こりやすいポイントです。あいまいな表現を避け、具体的に記載しましょう。
売買契約書には代表的な雛形があります。ここでは、売買契約書のなかでも特によく使用される「不動産売買契約書」「機械売買契約書」の2つを紹介します。
雛形は一般的な記載項目・内容をまとめたものであるため、基本的な契約条件を網羅しています。ただし、実際の取引内容や条件は案件ごとに異なります。作成の際は必ず当事者間で合意した内容にあわせて、条項の追加・削除・修正を行いましょう。
土地と建物を売買するときに用いる不動産売買契約書は、不動産会社が契約書を作成するケースが一般的です。自分で作成する必要がある場合には、以下の雛形を参考にしてください。
不動産売買契約書
売主(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)は、本日、末尾記載の不動産(以下「本物件」という。)について、以下のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(売買物件)
本物件の表示は、以下のとおりとする。
第2条(売買代金)
本物件の売買代金は、金______円也とする。
第3条(手付金)
1.乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付金として金______円也を支払う。
2.手付金は、売買代金の一部に充当する。
第4条(売買代金の支払)
乙は甲に対し、売買代金から手付金を控除した残代金金______円也を、令和__年__月__日限り、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。
第5条(所有権移転及び引渡し)
1.甲は乙に対し、本物件の所有権を、乙が前条の売買代金全額を支払った時に移転する。
2.甲は乙に対し、本物件を、前項の売買代金全額の受領と同時に、現状有姿のまま引き渡すものとする。
3.所有権移転登記手続は、司法書士に委任し、その費用は乙の負担とする。
第6条(公租公課の負担)
本物件に関する公租公課は、引渡日を基準として、引渡日の前日までの分を甲の負担とし、引渡日以降の分を乙の負担とする。
第7条(契約不適合責任)
1.本物件に契約の内容に適合しない点(以下「契約不適合」という。)があった場合、乙は甲に対し、引渡日から3ヶ月以内に限り、修補を請求することができる。
2.前項にかかわらず、本物件の隠れたる契約不適合については、乙は甲に対し、引渡日から2年以内に限り、損害賠償を請求することができる。ただし、甲がその契約不適合を知りながら乙に告げなかった場合はこの限りではない。
3.本条の定めは、買主が宅地建物取引業者である場合には適用しない。
第8条(契約の解除)
1.甲又は乙が本契約に定める義務の履行を怠った場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、なお履行がないときは、本契約を解除することができる。
2.前項による解除の場合、違反者は相手方に対し、売買代金の20%相当額の違約金を支払うものとする。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
令和__年__月__日
売主(甲):
住所:
氏名: 印
買主(乙):
住所:
氏名: 印
高額な機械類や設備を売買する場合は、機械売買契約書を取り交わします。契約書を作成する際は、以下の雛形を活用してみてください。
機械売買契約書
売主(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)は、本日、以下の機械(以下「本機械」という。)について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(売買物件)
本機械の表示は、以下のとおりとする。
第2条(売買代金)
本機械の売買代金は、金______円也(消費税込み/別途消費税)とする。
第3条(代金の支払)
乙は甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。
第4条(引渡し)
1.甲は乙に対し、本機械を、乙が前条の売買代金全額を支払った後、速やかに、下記の場所において、現状有姿のまま引き渡すものとする。
* 引渡場所:
2.引渡しに要する費用(運搬費、梱包費など)は、___の負担とする。
第5条(所有権の移転)
本機械の所有権は、乙が売買代金全額を甲に支払い、甲が本機械を乙に引き渡した時に、甲から乙に移転する。
第6条(危険負担)
本機械の引渡し前に、甲及び乙いずれの責にも帰すことができない事由により、本機械が滅失又は毀損したときは、その損害は甲の負担とする。この場合、乙は本契約を解除することができる。引渡し後は、乙の負担とする。
第7条(契約不適合責任)
1.乙は、本機械の引渡しを受けた後、速やかに本機械の検査を行うものとする。
2.本機械に、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない点(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、乙は甲に対し、引渡しの日から__日間(または別途定める期間)に限り、______(例:修補の請求、代替物の引渡し請求、代金の減額請求など)を請求することができる。
3.前項の期間内に乙からの通知がない場合、本機械は契約に適合したものとみなす。
4.本条は、甲が契約不適合を知りながら乙に告げなかった場合には適用しない。
第8条(契約の解除)
甲又は乙が本契約に定める義務の履行を怠った場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、なお履行がないときは、本契約を解除することができる。この場合、違反者は相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
令和__年__月__日
売主(甲):
住所:
氏名(名称): 印
買主(乙):
住所:
氏名(名称): 印
ここからは、売買契約書を作成・締結する際に押さえておきたい注意点を解説します。契約内容によっては、後のトラブルや損害につながるおそれがあるため、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。
注意しておきたいポイントをそれぞれ詳しく解説します。
売買契約書を作成する際は、取引にともなうリスクを十分に考慮し、取引条件を具体的かつ漏れのない記載が必要です。たとえば、商品名や数量、価格、納期、支払い期限などの取引条件があいまいなままだと、納品ミスや代金回収の遅れといったトラブルに発展するリスクがあります。
また、万が一トラブルが起きた場合に備えて、売主・買主それぞれの責任範囲や対応方法まで取り決めておきましょう。ルールが明確であれば、双方が納得したうえでスムーズに取引が進めやすくなります。
あいまいな表現がないか丁寧に確認することも重要です。表現次第では、相手方と解釈が異なり、後の誤解やトラブルにつながるおそれがあります。売買契約書の内容に不安がある場合は、専門家である弁護士にチェックを依頼することも検討しましょう。
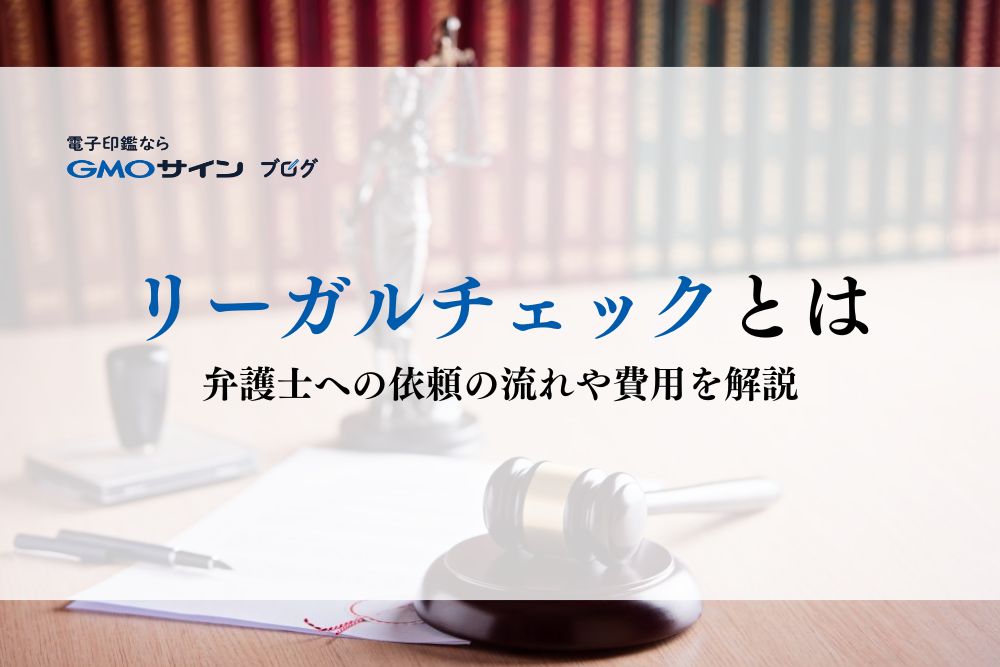
売買契約書を作成する際や締結前には、一方の当事者に不利益な内容が含まれていないか、慎重に確認します。内容によっては、どちらか一方に過度な負担がかかり、トラブルに発展する可能性があります。
特に注意したいのが、売買にかかる費用や税金負担の取り決めです。たとえば、以下のような内容が契約に含まれていないか、細かな点までチェックしましょう。
また、相手方の義務が一方的に軽く設定されていないかも、見落とさないように確認します。契約内容が公平な内容となるよう必要に応じて修正を依頼することで、将来的なトラブル防止につながります。
売買契約書を作成する際は、契約不適合責任に関する対応を十分に検討して記載しましょう。契約不適合責任とは、引き渡した商品や物件が、契約で定めた種類・品質・数量に適合しない場合に売主が負う責任のことです。たとえば、部品Aを注文したにもかかわらず、誤って部品Bが納品された場合などが該当します。
契約不適合責任は、2020年の民法改正によって従来の「瑕疵担保責任」から名称と内容が改められたものです。従来の瑕疵担保責任は「隠れた欠陥」が責任の対象でしたが、契約不適合責任では「契約内容に適合しないすべてのケース」が対象です。そのため、買主が取引時点で不具合や欠陥を知っていた場合でも、契約内容と異なる場合は売主の責任となる可能性があります。
売主として責任を負いきれないものについては、容認事項として漏れなく記載しておくか、特約として契約不適合責任の対象とならないことを明記しておきましょう。
売買契約書は、契約書の内容によって印紙税がかかるケースがあります。特に不動産や高額な取引では、印紙税額も大きくなるため注意が必要です。
ここからは、収入印紙の貼付が必要な場合と不要な場合に分けてそれぞれ詳しく解説します。
売買契約書のうち、以下の譲渡に関する契約書は課税文書である「第1号文書」に該当するため、収入印紙の貼付が必要です。
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業、地上権、賃借権
売買契約書に記載された契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。第1号文書に該当する売買契約書にかかる印紙税額は以下のとおりです。
| 記載の契約金額(1通または1冊につき) | 印紙税額 | 軽減税率が適用された印紙税額(※) |
|---|---|---|
| 10万円以下・契約金額の記載がないもの | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
※不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された売買契約書は印紙税の軽減税率が適用されます。
また、継続的な取引に関連する売買契約書については、取引期間が3カ月を超える場合は第7号文書に該当する課税文書のため、1通につき4,000円の収入印紙が必要です。

課税文書に該当する場合でも、以下のようなケースでは収入印紙の貼付は不要です。
電子契約の場合は、不動産売買契約書や鉱業権譲渡契約書など、本来は印紙税の課税対象となる契約でも印紙税はかかりません。これは、印紙税法上における「課税文書」は紙で作成された契約書のみが対象とされているためです。
印紙税の課税対象かどうかを見極めるためには、国税庁が公表する印紙税額一覧表や印紙税法を確認して判断できます。判断に迷う場合は、誤った対応を避けるためにも税理士や専門家への相談をおすすめします。

売買契約書に収入印紙の貼付が漏れていたとしても、契約自体が無効になることはありません。しかし、印紙税の貼付が漏れていた場合「納付漏れ」と判断されて「過怠税(ペナルティ)」が課される可能性があります。
印紙税の納付漏れと判断されると、本来支払うべき印紙税額に加え、その2倍の金額が追加されます。結果として、合計で3倍の過怠税を請求されるため注意しましょう。なお、自主的に申告した場合は、過怠税の額が1.1倍に軽減されます。
また、契約書に記載された取引金額に応じて、正しい金額の収入印紙を貼付する必要があります。もし貼付した収入印紙の金額が不足していた場合も、納付漏れとみなされるため、印紙税額を事前に確認しておくことが大切です。
売買契約書にかかる印紙税の負担を軽減したい場合は、電子契約の活用がおすすめです。紙の契約書では、契約金額に応じて収入印紙の貼付が必要となり、1件あたり数百円から数十万円の費用が発生する場合があります。一方、電子契約であれば印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙は不要です。その結果、取引ごとに発生する印紙税のコストを抑えられます。
また、電子契約であれば、印紙税法上の「課税文書」には該当しないため、収入印紙の貼付漏れによる過怠税のリスクもありません。印刷や製本、郵送などの手間やコストも削減でき、業務効率化と経費削減の両面で効果が期待できます。近年では、不動産売買をはじめとする高額取引でも電子契約が活用され、契約手続きの迅速化にもつながっています。
なお、電子契約を導入する際は、法的効力を確保するためにも、電子署名法に対応したクラウド型の電子契約サービスを選びましょう。電子署名と認定タイムスタンプが付与されるサービスを活用すれば、紙の契約書と同じ効力を持つ契約がオンラインで完結します。

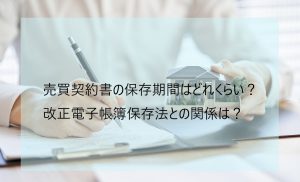
売買契約書は、商品やサービス、不動産などの売買取引を行う際に、取引条件を明確にし、トラブルを防ぐために欠かせない重要な書類です。作成する際は、雛形や記載項目を参考にしながら、記載漏れがないように仕上げましょう。特に取引条件は、具体的かつ明確に記載し、当事者双方に不利益が生じないよう注意が必要です。
また、売買契約書は内容によって印紙税がかかる場合があります。特に不動産の売買や高額な契約では、収入印紙が高額になるため注意しましょう。一方、電子契約を活用すれば印紙税が不要となり、印刷・郵送の手間やコストの削減にもつながります。
電子印鑑GMOサインは、印紙税を節約できるだけでなく、業務効率化も図れるクラウド型の電子契約サービスです。売買契約書の作成や確認は関係者が多く関わるため、スムーズな進行が求められます。契約内容のチェックから締結までを効率化できる契約レビューオプションの活用もぜひ検討してみてください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)