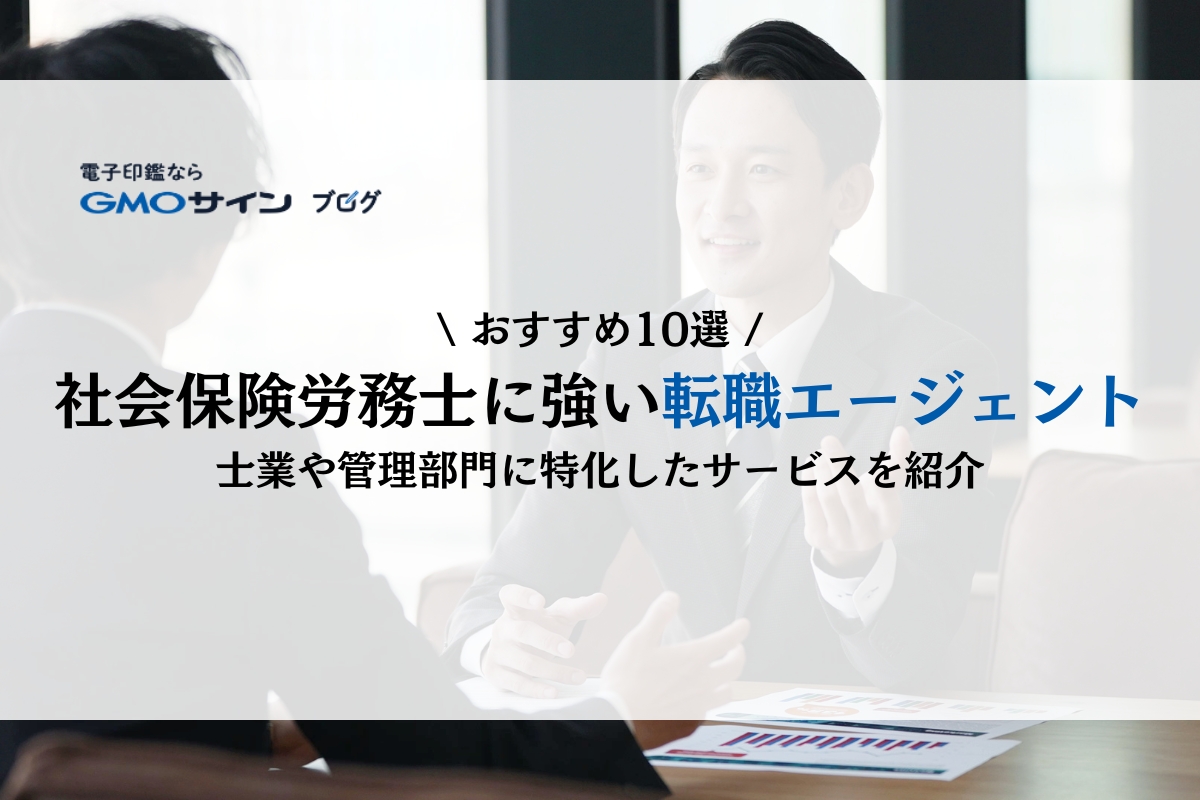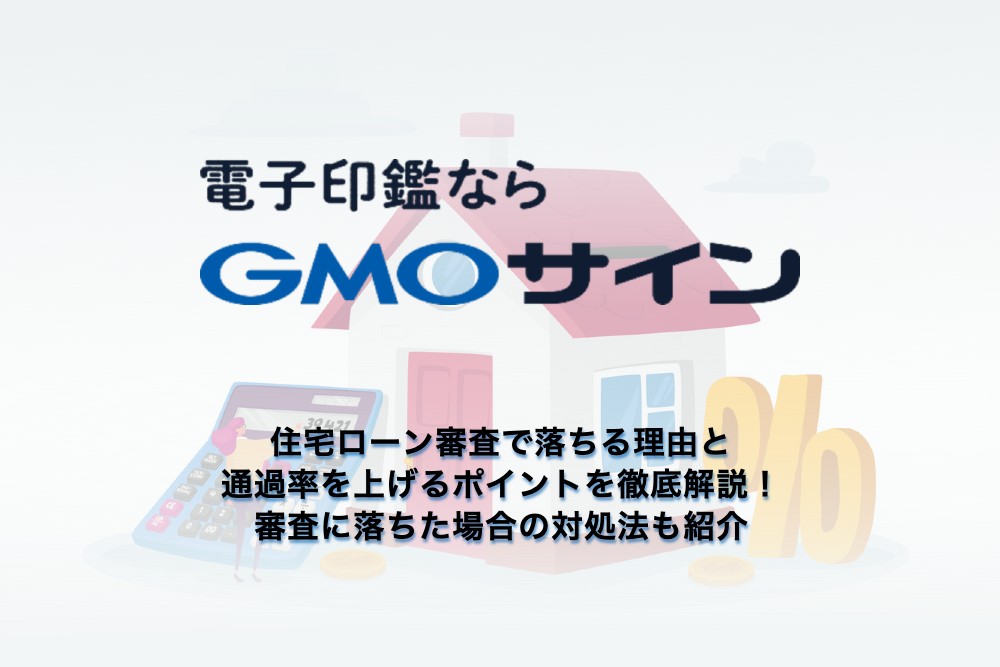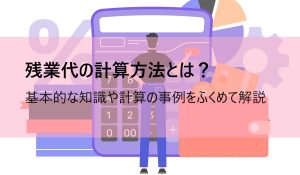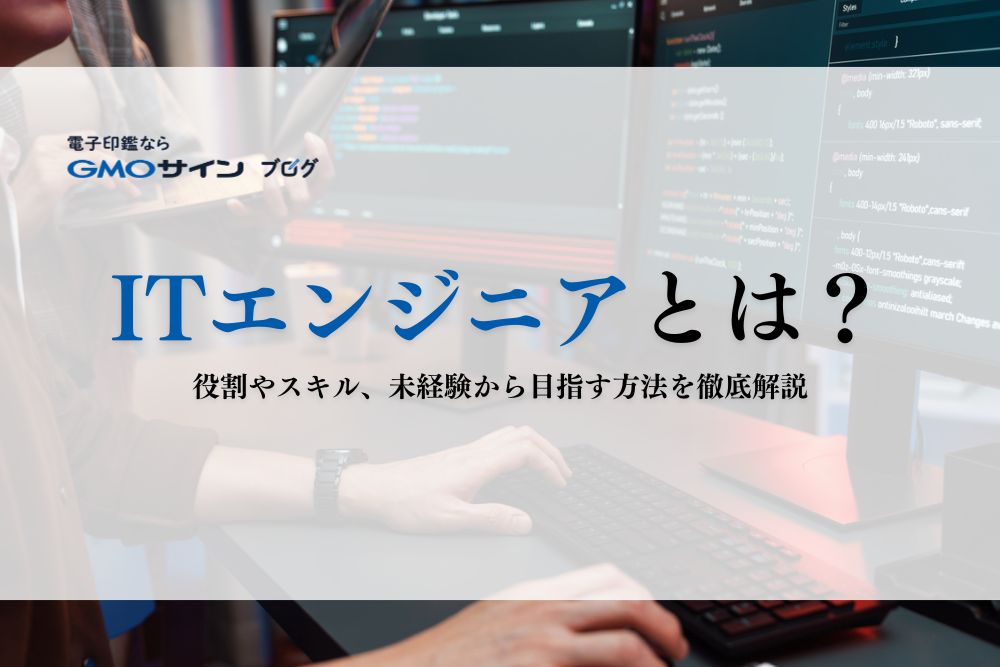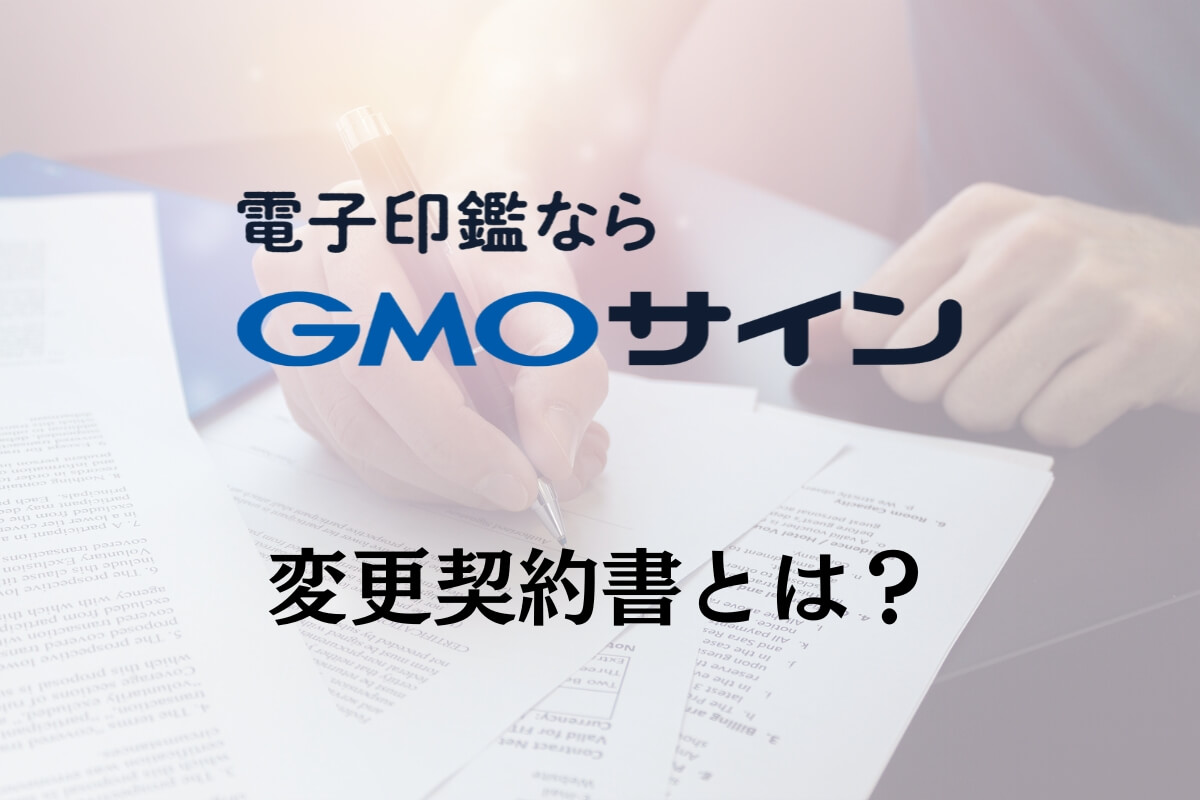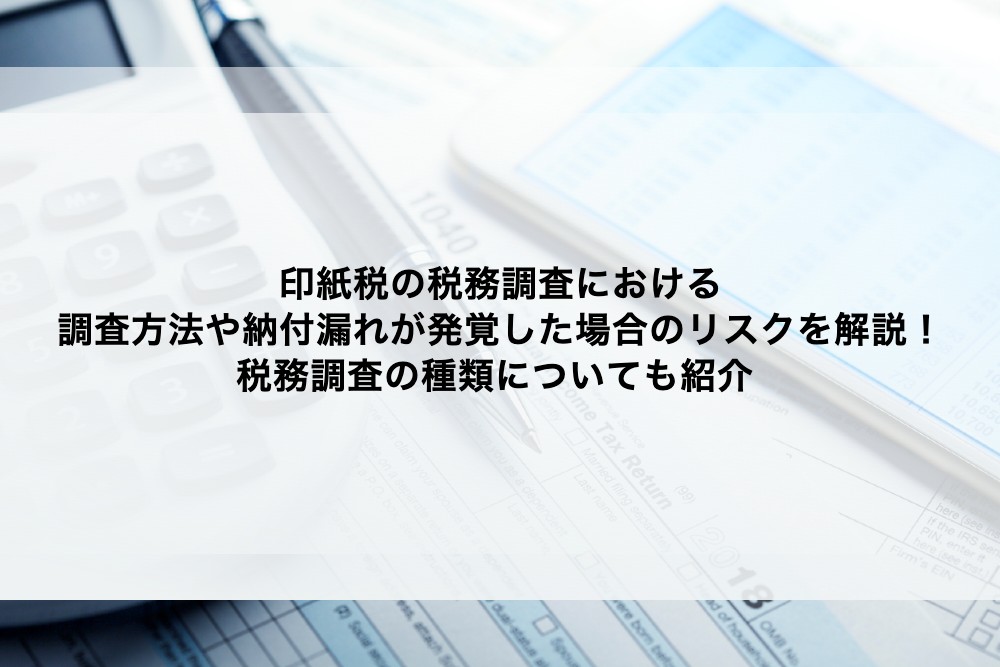\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

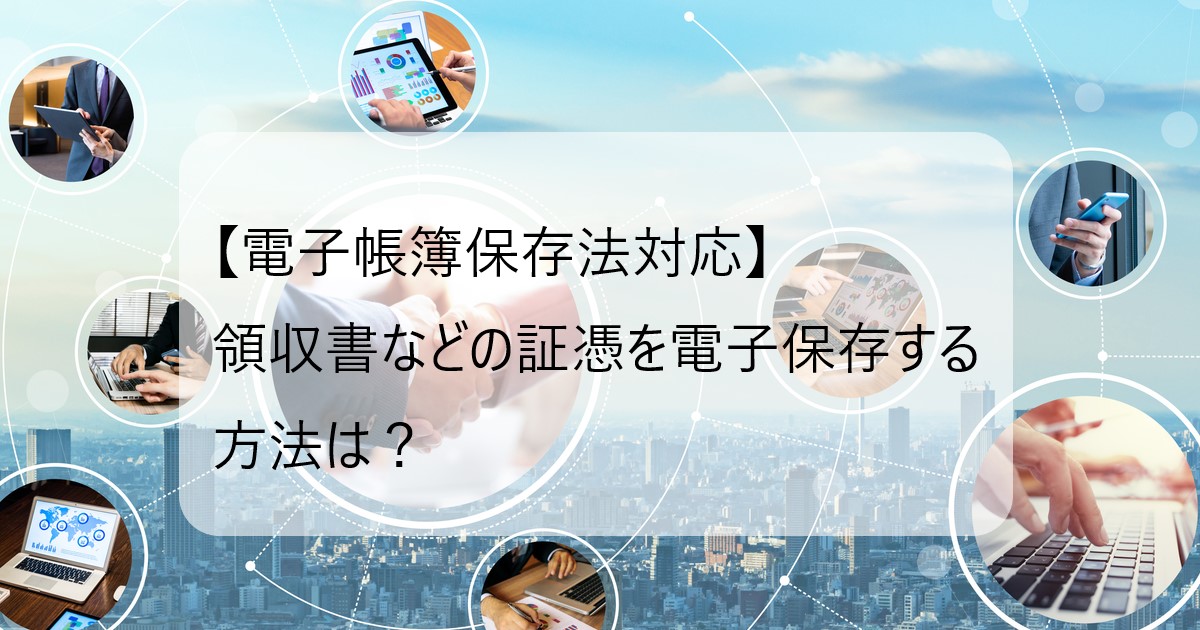
業務の中で日々増えていく証憑に、管理の手が回らずお困りではないでしょうか。社内外で取引があったことを証明できる証憑は、経理業務を中心にさまざまなケースで取り扱いがされるため、気づけば膨大な量を抱えています。
企業の証憑管理をスムーズにする方法に、紙媒体から電子保存への移行が考えられます。企業の電子化が成功すれば、証憑をすべて電子データとして一括管理でき、コスト削減が可能です。
とはいえ、証憑の電子化には、国税書類を電子保存する際の要件を定める電子帳簿保存法への理解が避けて通れません。そのためこの記事では、電子帳簿保存法に従いながら、証憑を電子保存する方法について解説していきます。
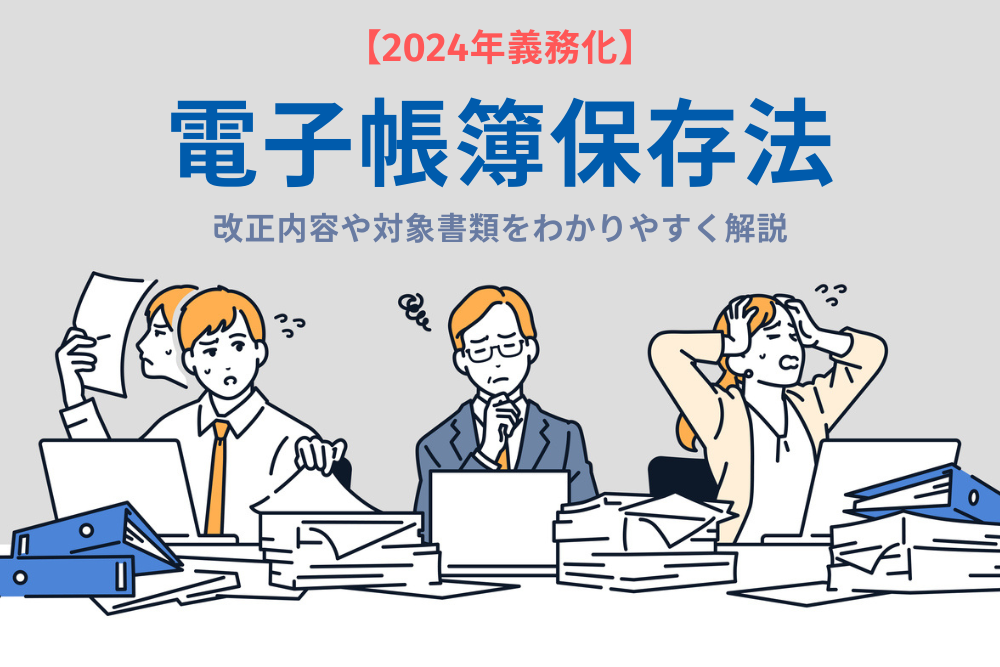
証憑(ショウヒョウ)とは、取引がたしかにされたことを証明する書類です。売買契約書や請求書などの社外向け書類のみならず、雇用契約書や給与明細のような社内向け書類も証憑に含まれます。
証憑は、トラブル発生時に有効性を発揮するため、多くのビジネスシーンで重要視されています。証憑を交わしていれば、取引先と食い違いによる問題が起きた際も、記載内容に従うことによる解決が期待できます。
ビジネスの現場で取り交わされる証憑には、いくつかの種類があります。
具体的には、以下のような種類が挙げられます。
入金伝票や売掛金台帳のことを指す帳票との違いは、書面の作成時期です。帳票はやり取りが完了したのちに作成するのに対し、証憑は取引開始のタイミングで作成します。
電子帳簿保存法とは、紙での保存が義務付けられていた書面を、電子データでも保存ができるよう定めた法律です。電子帳簿保存法は2022年1月に改正が行われ、証憑の保存要件がより簡素化されました。この章では、電子帳簿保存法を遵守しつつ、証憑の電子保存を行う2種類の方法について触れていきます。証憑はさまざまな種類があるため、領収書を例にあげて解説します。
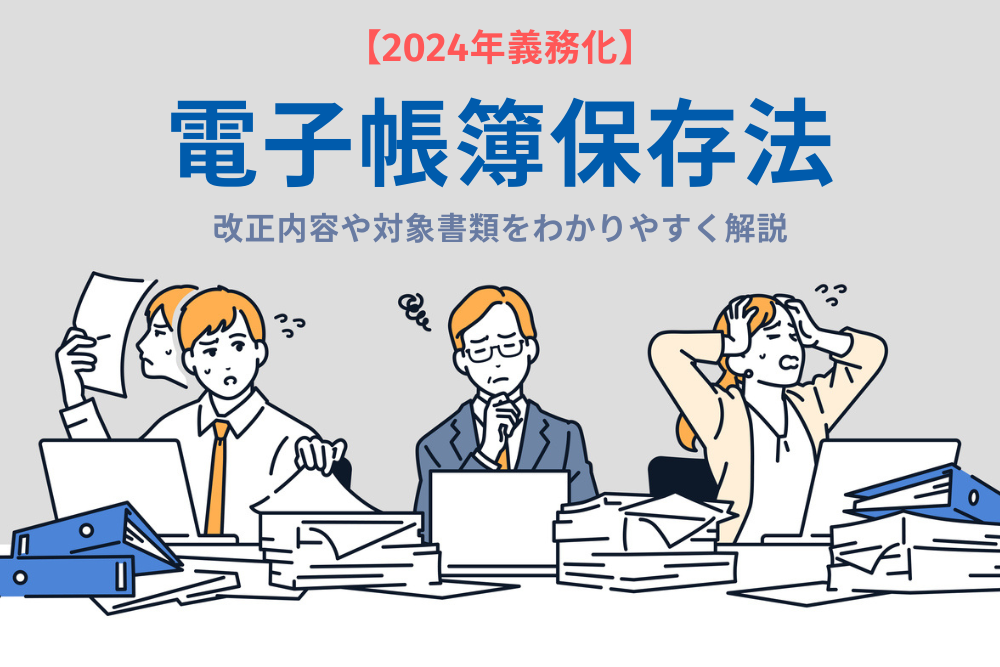
電磁的記録とは、パソコンで作成を行った電子的なデータのことを指します。領収書をデータで受け取った場合は、紙ではなく電子データでの保存が必要になります。
ただ領収書をPDFスキャンして保存しておくだけでは、電磁的記録による保存ができていると言えません。なぜなら、証憑である領収書は、電子帳簿保存法で定められた要件に沿って保存する必要があるからです。
電磁的記録による保存には、主に以下のような要件があります。
電子帳簿保存法の改正により、電磁的記録による保存要件の緩和が進んでいます。
たとえば、改正前は、電磁的記録による保存に税務署長の承認が必要でした。しかし、企業の事務負担軽減の観点から、現在では事前承認が不要になっています。
さらに、電子データ検索システムの設置にも緩和が施されています。改正前は、帳簿の種類に応じた複雑な検索ができるシステムの導入が求められていました。しかし、改正後は取引年月日や取引金額、取引先の3つのみが検索要件の記録項目とされました。また、税務職員による電磁的記録の提示又は提出の要求(ダウンロードの求め)に応じることが可能であれば、範囲指定や組み合わせ要件も不要となっています。
電磁的記録による保存はさまざまな要件が必要になりますが、電子帳簿保存法の改正により企業の証憑電子化が簡素化されています。
領収書をデータで受け取った場合は電磁的記録による保存が必要な一方で、紙で発行・受領した領収書は、スキャナ保存が必要です。スキャナとは、紙の書類を読み取り、パソコンやタブレットなどの電子媒体で閲覧できるようにデータ化をする機械です。
スキャナ保存についても要件が定められており、重要書類と一般書類とで要件に違いがあります。重要書類は、企業の経営に直結するような書類を指し、領収書も該当します。一般書類は、見積書や注文書のような、経営に直結しない書類のことです。
証憑の電子保存をすれば、業務の効率化やコスト削減など、紙での保存では得られなかったさまざまなメリットが獲得できます。ここでは、証憑を電子保存するメリットについて解説します。
証憑を電子保存すれば、紙での保存にかかっていたコストの削減が期待できます。
電子保存化で主に削減できるコストは、以下の通りです。
ほかにも、書面を郵送・廃棄するための人的コストの削減も可能です。
証憑の確認が必要となった場合でも、検索機能を使えば、すぐに電子保存したデータを発見可能です。帳簿書類を紙で保管していた場合、日々増えていく書類のなかから、手間をかけて探し出さなくてはなりません。
さらに、電子データはクラウド上に保存がされる性質上、オフィスの外からでもアクセスが可能です。どこからでも証憑の管理や閲覧ができれば、経理業務の効率化が期待できます。
証憑は保管期限が7年と定められており、紙で保存を続けた場合、保管スペースの圧迫が考えられます。企業内の証憑をすべて電子データにすれば、保管場所の確保について考える必要はありません。
電子データをクラウド上に保存すれば、組織内で証憑の共有がかんたんに行えるようになります。そのため、契約の進捗確認や文書管理がデータ上で可能になり、ガバナンス強化が期待できます。
紙で証憑を保管する場合は、さまざまな状況での紛失リスクが考えられます。持ち出し時だけでなく、盗難や火災が原因でも紛失の可能性があります。電子化をしておけば、物理的に書面が無くなる心配がありません。
また、紙保存の場合、悪意ある第三者により署名や押印が改ざんされる可能性があります。電子化した証憑であれば、契約を行った本人であると証明する電子署名の活用で、改ざんを防止できます。さらに、契約に改ざんが行われ ていないことを証明できるタイムスタンプを付与できるのも、電子契約でリスク低減ができる理由です。
証憑を電子保存する際には、いくつかの注意点が存在します。電子帳簿保存法の改正をきっかけにした注意点ばかりのため、電子化を推進するにあたっては理解が必要です。
スキャナ保存が行われた国税関係書類の改ざんや隠蔽が判明した場合には、ペナルティとして重加算税が通常より 10%加重されます。重加算税とは、申告内容が適正でない場合に課されるものです。
不正行為に対するペナルティは、2021年1月の電子帳簿保存法の改正で制定されました。改正により電子保存が簡素化されたと同時に、適正な取り組みを推進するための措置として整備されています。
電子帳簿保存法の改正により、電子取引の保存方法が、データ保存のみに限定されました。電子取引とは、電子上でやり取りをしたデータすべてを指します。主に以下のようなケースが、電子取引に該当します。
電子取引の紙保存が廃止になったことで、今まで紙保存をしていた企業は、電子保存に移行をしなければなりません。電子取引のデータ保存義務化は、2024年1月から開始されます。
証憑を電子保存する場合の保存期間は、確定申告書提出期限の翌日から7年間と義務付けられています。例外として、欠損金の繰越控除が発生する場合は10年間保存が必要になります。
紙の証憑を電子データにするため、スキャナ保存した場合の原本については、保存期間が設けられていません。そのため、電子保存が完了したら原本はすぐに廃棄可能です。
証憑の電子保存は、電子帳簿保存法に則り改ざん防止措置を講じる必要があります。以下の要件のなかで、1つでも要件を満たしていれば問題ありません。
訂正削除の防止に関する事務処理規程は、適用範囲や運用体制などを詳細に定める必要があります。タイムスタンプや改ざん防止システムの導入ができない場合は、国税庁が提供しているサンプルを参照して規程の作成をしましょう。
証憑の電子化を進めたい企業にとって、課題となるのは電子文書の信頼性の担保です。データのやり取りをした以降も、改ざんされずに保管できている証明ができなくては、証憑としての役割が保てません。
署名エンジンは、文書が電子上に存在し、以降変更がされていないことを証明するタイムスタンプを付与できる機能を有しています。この章では、署名エンジンについて詳しく解説をします。
署名エンジンとは、書類の真正性を保障することができる署名システムのことです。財務諸表や医療データ、卒業証明書、指示書、さらには遺言書など、各種文書の信ぴょう性を担保した状態で電子化し、保存することができます。
この機能により、たとえば、請求書発行システムや雇用管理システム、施工管理システムなど、自社で提供しているサービスに信ぴょう性を持たせる機能を追加することができるため、自社サービスの付加価値を向上させられます。
電子印鑑GMOサインを提供するGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社は署名エンジンを提供しております。
たとえば、電子文書発行システムではタイムスタンプの付与ができないケースがありますが、署名エンジンを組み込むことで、電子文書に証拠力を持たせることが可能となります。
署名エンジンを導入すれば、さまざまな既存システムに、電子文書の信頼性を付与できます。たとえば、以下のようなシステムへの組み込みが考えられます。
現在企業に浸透しているシステムを崩さずに電子化を促進し、サービスの向上が実現可能です。
さらに、署名エンジンの導入・開発支援もメリットとして挙げられます。システムの動作検証はもちろん、社員への理解を得るための勉強会開催の支援も行います。導入から開発までの細かなプロセスすべてをサポートするため、スムーズなシステム導入が可能です。
証憑の電子化を促進して企業の価値を高めたい方は、まずはお問い合わせください。
社内外の取引を証拠付ける役割となる証憑は、電子化により適切に管理をしなければなりません。ただ保管するだけでなく、タイムスタンプの付与や、本人の署名を電子的に証明する電子署名を施す必要があります。
企業のペーパーレス化を後押しする形で改正が続けられてきた電子帳簿保存法は、証憑の電子化にも対応できるようになっています。
企業は電子帳簿保存法についての理解を深め、電子帳簿保存法の義務化に向けて準備を進めましょう。
GMOサイン署名エンジンは、既存の文書発行システムへ電子帳簿保存法に対応できる仕組みの組み込みが可能です。電子文書の信頼性や有効性を担保し、企業の電子化を推進したい方は、下記のページよりお気軽にお問い合わせください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
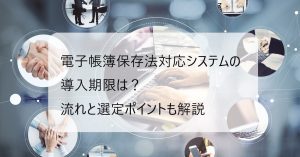 【2024年義務化】導入検討するなら今!電子帳簿保存法対応システムの導入期限は?流れと選定ポイントも解説
【2024年義務化】導入検討するなら今!電子帳簿保存法対応システムの導入期限は?流れと選定ポイントも解説
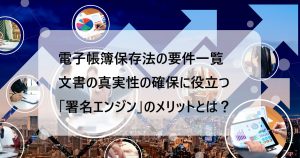 【最新版改正に対応】電子帳簿保存法の要件一覧|文書の真実性の確保に役立つ「署名エンジン」のメリットとは?
【最新版改正に対応】電子帳簿保存法の要件一覧|文書の真実性の確保に役立つ「署名エンジン」のメリットとは?
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。