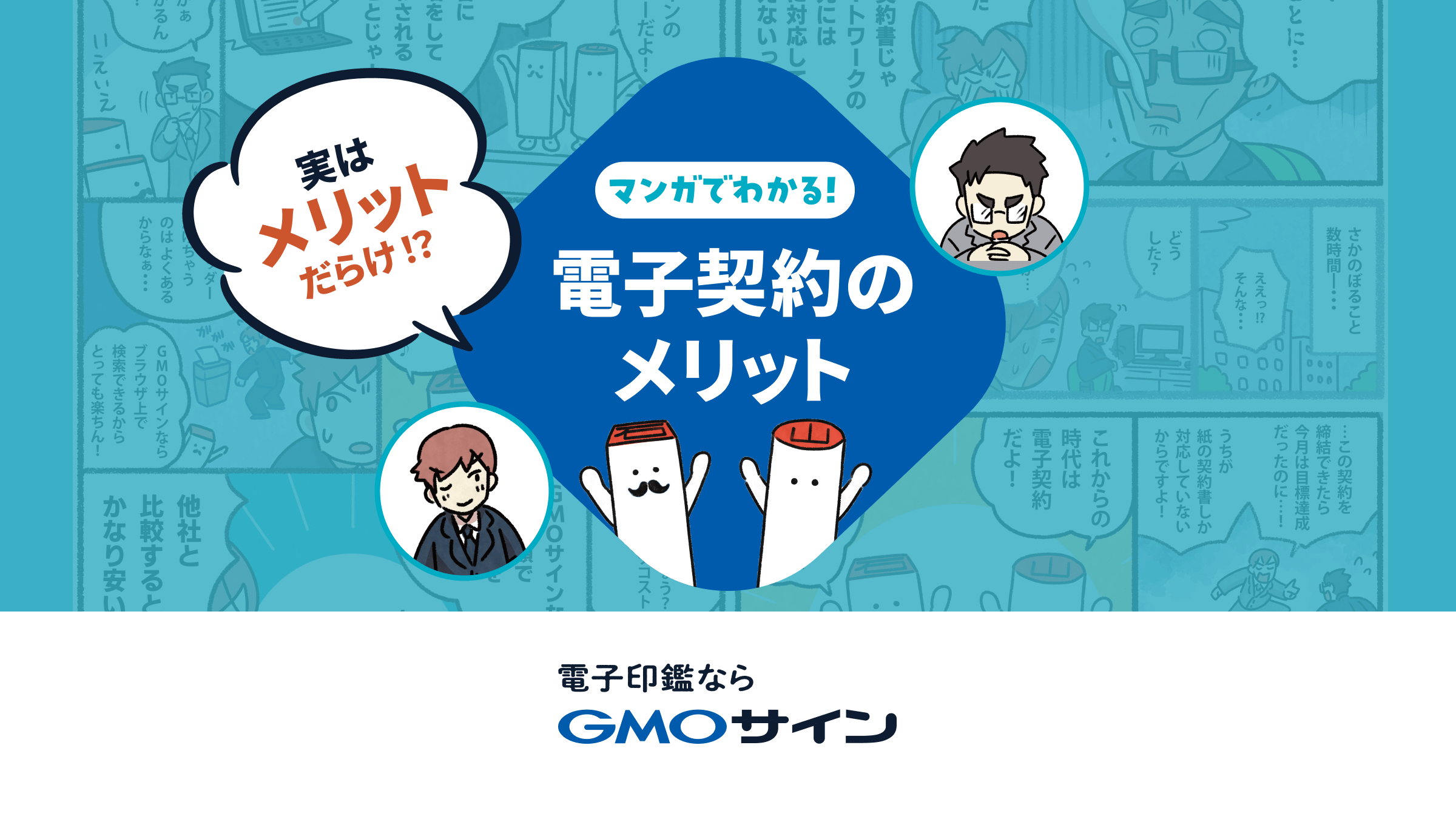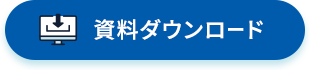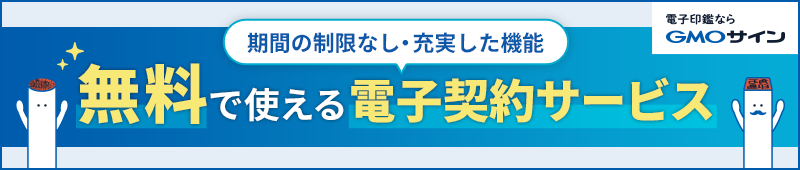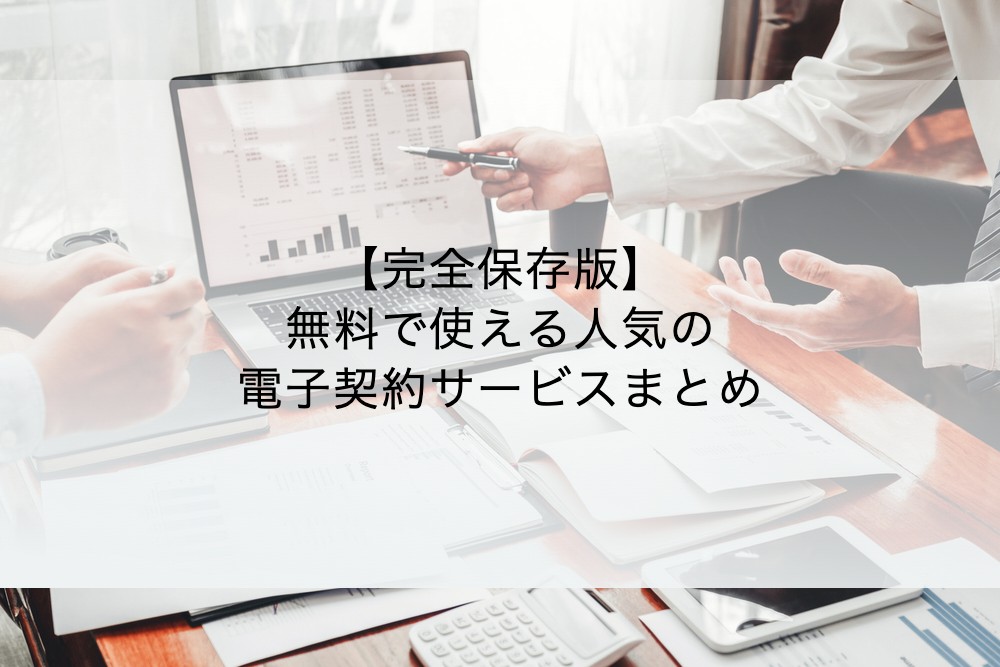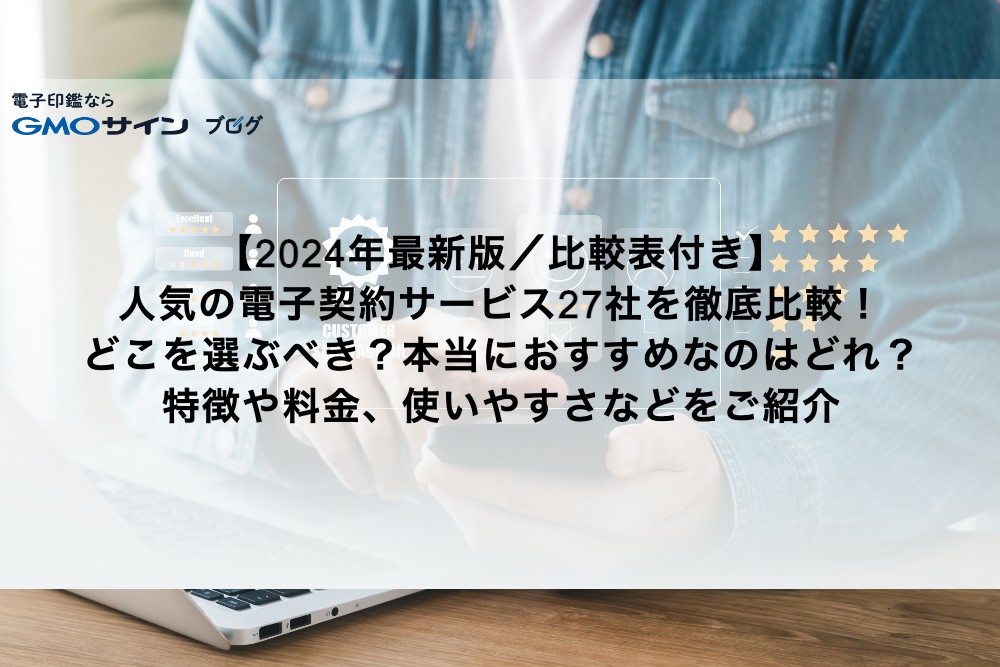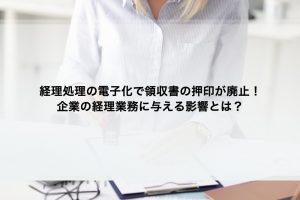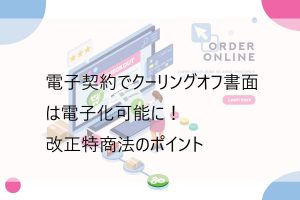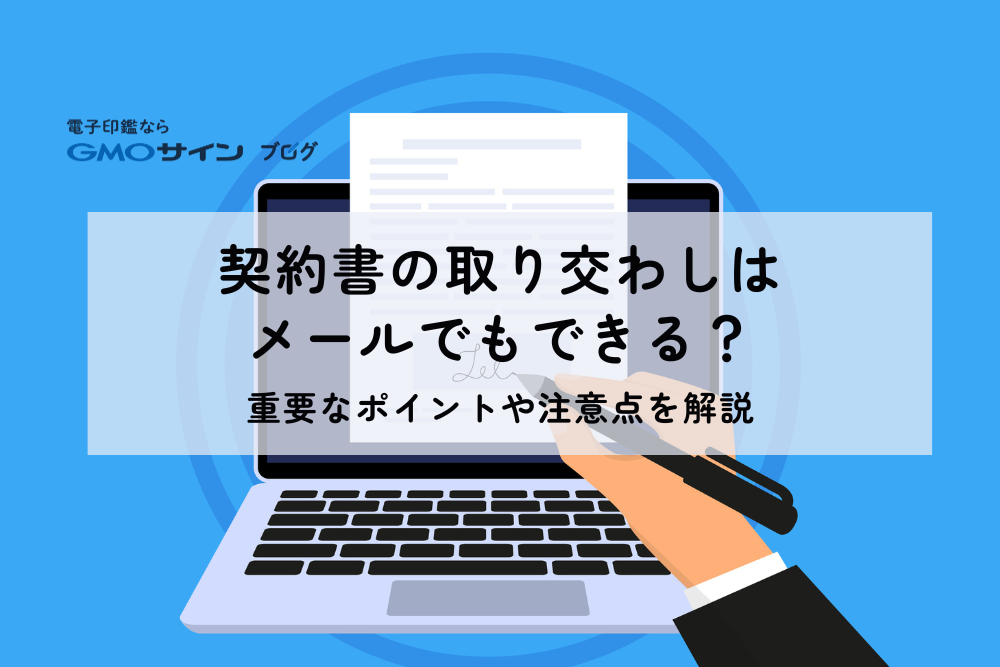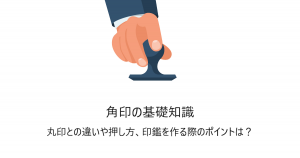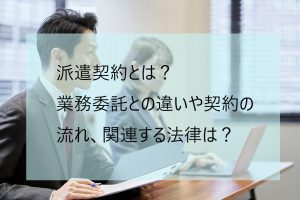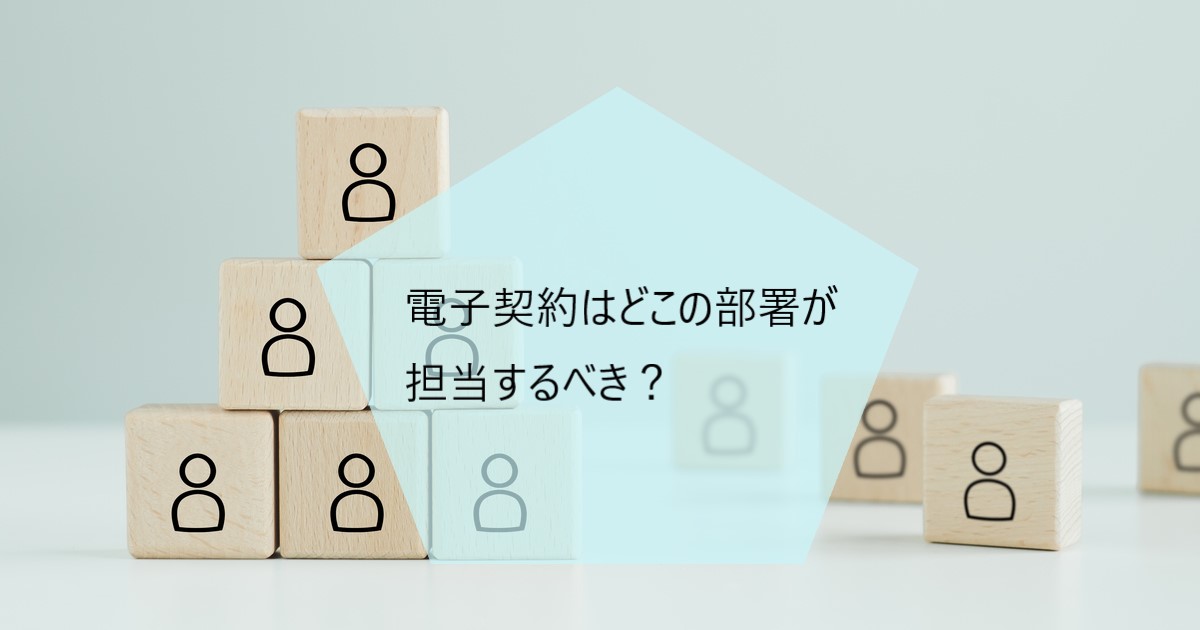【経理の基礎知識】 請求書に角印が必要な理由

管理業務では、前任者のやり方を引き継ぐケースが多いでしょう。しかし、改めて一つひとつの業務を精査すると、「これは何のためにやっているのだろう?」と、本当に必要な業務なのか、判断できないものもあるのではないでしょうか。
このように形骸化しがちな業務の一例として、請求書への押印が挙げられます。企業が取引先に対して請求書を発行する場合、角印(印影が四角の印)を押すのが一般的です。しかし、この角印、何のために押しているのか、実のところ理解していない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、いつも何となく押しているであろう、角印の謎に迫っていきましょう。
請求書の角印は法律上必須ではない
請求書発行の際、紙の請求書をプリントアウトして、そこに角印を押すというのが、これまで一般的にビジネス上で行われてきた慣習です。しかし、法律上、取引先への請求時に、紙の請求書や角印が必須かというと、実はそうではありません。
紙の請求書がなくても、印鑑が丸印であっても、法的に問題はなく、請求の可否に限っていえば、必要なのは相手方に支払いの義務があるという事実だけなのです。
請求書の社印はトラブルの予防には役立つ
では、請求書に角印を押すことは、何のために必要なのでしょうか。これは、請求書を受け取る側に対して、信頼性を高めるためであるといえます。
つまり、角印が押されていれば、第三者による成りすましや、偽造が行われたものではないと確認ができるため、後々の契約トラブルを軽減することができると考えられてきました。請求書に押す角印は、いわゆる会社の「認印(みとめいん)」とも考えられ、会社が発行した正式な書類であると証明する効果も見込んでいました。

また、ひょっとすると、業務にあたる担当者にとっても、会社の印を押すというステップをひとつ挟むことで、仕事に対する責任感が高まるといった副次的効果も見込んでいたのかもしれません。
電子化した請求書に角印は必要?
今後、場所や時間に囚われない働き方である「テレワーク」の普及によって、角印が持つ意味は、形を変えていくことが予想されます。
というのも、わざわざ紙に請求書を印刷し、角印を押し、郵送したり手渡ししたりする物理的なコストや手間を減らすべく、電子データによるやり取りが盛んになっていくことが予想されるからです。事実、2020年には新型コロナウイルス感染拡大にともない、緊急事態宣言が出され、テレワークが急速に普及しました。
しかし、従来のように紙の契約書で諸々の契約を締結している企業が多かったため、押印のために契約担当者が出社を余儀なくされるケースも少なくなく、「テレワークの意味がない」「効率が悪い」という声が相次ぎ、電子契約や電子データでのやりとりが急速に普及しました。

現在では、請求書を電子データで作成することも、一般的なものとなってきています。請求書を受け取る立場からみれば、電子データで送られる請求書が偽造されたものでないかどうか注意する必要があるでしょう。
電子化された請求書に角印の印影があったとしても、請求書が偽造されたものでないことを証明することはできません。この点を踏まえると、請求書のファイル形式は、修正が容易ではないPDFなどが望ましいといえます。角印を押す機会は電子化とともに減っていくでしょう。参考記事として、電子印鑑の導入と知っておくべきポイントでも解説しています。
なお、受け取った請求書の保管に際しては、「電子帳簿保存法」の規定が及びます。紙からデジタルデータに置き換わる過程においては、こうした関連法規が示す要件に準拠しなければなりません。
電子帳簿保存法と請求書の関係
電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。その名の通り、電子計算機(パソコンなど)で国税関係帳簿書類を作成する際の保存について定められた法律です。
国税関係帳簿書類とは仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿や、領収書、見積書といった証憑(しょうひょう)書類などを指します。請求書もこれに含まれるので、電子データでの作成・保存が可能となるわけです。
電子帳簿保存法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。対象となる書類や保存方法についてもご説明しています。

まとめ
請求書の角印は、書類の偽造・改ざんを防ぐビジネス上の慣習の一つとして、長く用いられてきました。
IT技術が進歩した今日では、電子契約や電子データを用いるビジネスも増えました。今後は電子署名などの技術を用いて偽造・改ざんを防止していくことになるでしょう。
角印を押した請求書が電子データに置き換わる過程では、関連法規が改正されるといった動きもあります。こうしたハンコ事情の変化は、今後もますます注目されるところでしょう。