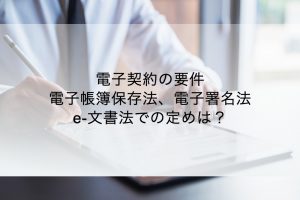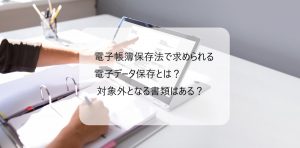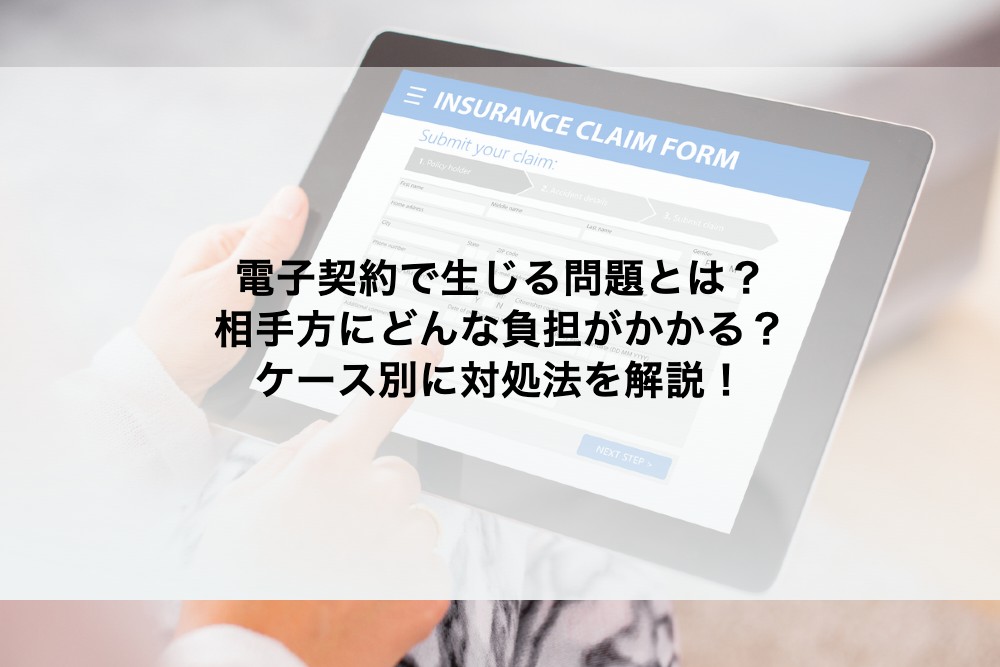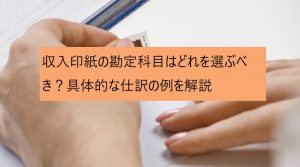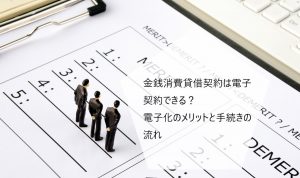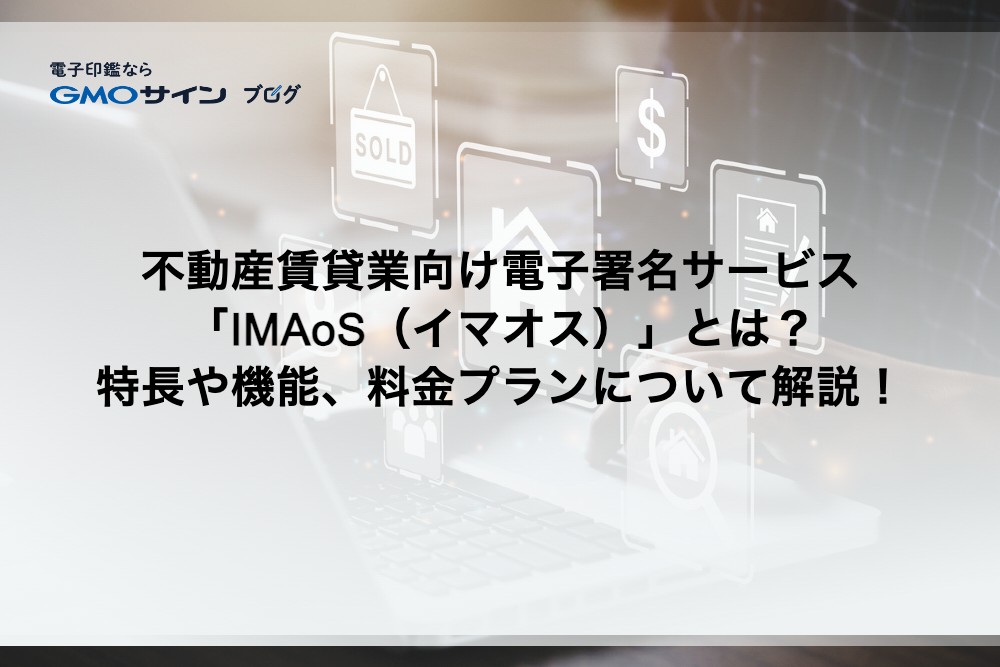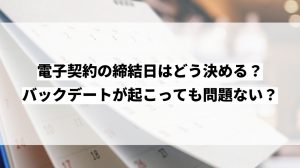契約書は郵便法上「信書」に区分され、送り方が法律で限定されています。宅配便やメール便で送ってしまうと、違法となりかねません。
企業では社内全体への正しい知識の周知徹底が必要です。誤った方法で送付するとコンプライアンス違反となり、対外的信用を損なうおそれがあります。
本記事では、総務省のガイドラインに基づいた「信書」の定義から、契約書の送り方や違反リスク、送付サービスの違いまで解説します。また、代替手段として電子契約を導入する効果やメリットも紹介します。
「信書」とは?総務省の定義をわかりやすく解説
総務省のHPに掲示されている「信書のガイドライン」にて以下のように定義されています。
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
引用:信書のガイドライン
郵便法第4条及び信書便法第2条にも規定されており、3つの要素すべてを満たす必要があります。
- 特定の受取人
- 差出人が意思表示や事実通知を受ける者として特に定めた者
- 送り先が明確に特定されている
- 差出人の意思表示・事実通知
- 差出人の考えや思いを表示
- 事実を通知
- 具体的な意思や事実を相手方に伝える目的があることが必要
- 文書
- 文字、記号、符号等の知覚による認識できる情報が記録された物
- 文書の記載手段は手書きまたは印字された物
- 記載する素材に関しては物理的な形があり、人の知覚によって認識される物
主な信書は
- 書状(手紙)
- 請求書
- 領収書
- 納品書
- 申告書
- 招待状
- 許可書
- 契約書
- 証明書
- ダイレクトメール など
が該当する書類です。
信書に該当しない書類としては、
- 書籍
- 新聞
- 株券
- 小切手
- 商品券
- 乗車券
- クレジットカード
- キャッシュカード
- 会員カード など
が挙げられます。
企業の担当者は法令遵守の前提として信書の定義を理解しておく必要があるでしょう。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
② 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
③ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
④ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
(定義)
第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
二 国内において信書便物が差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
二 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
三 その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。
契約書が「信書」に該当する理由
契約書は信書に必要な3つの要素をすべて満たすため、法律上明確に「信書」に該当します。
契約書に関する3つの要素は、以下のとおりです。
| 要素 | 内容 | 具体例 |
| 特定の受取人 | ・特定の取引相手に対しての書類 ・当事者の特定情報が記載される | ・売主と買主、貸主と借主など ・氏名や商号 |
| 意思表示・事実通知 | ・当事者間の合意内容を明示 ・権利や義務の発生を表示 | ・売買意思や貸借合意、業務委託依頼などの意思表示 ・契約条件、代金、期限などの条件表示 |
| 文書 | ・印字または手書き ・契約内容が記録された物理的な物 | ・印刷された契約書 ・手書き契約書 ・印鑑が押された書面 ・手書きのサインがある書面 |
信書である契約書の送り方
信書に該当する契約書の送り方には法的な制約があり、郵便法に基づいて適切に選択する必要があります。仮に違反した場合の罰則や企業リスクについても正しく理解しておきましょう。
郵送が原則
信書である契約書の送付は、原則として郵送です。日本郵便株式会社が提供する郵便サービスは、郵便法に基づいて信書の送達を行う唯一の一般的なサービスです。ただし、国が定めた特定信書便事業者というものがあり、特定信書便事業者も特定信書の送達が可能です。
具体的なサービスは、
- 普通郵便
- 書留郵便
- 特定記録郵便
- 配達証明郵便
- レターパック
- スマートレター
- 飛脚特定信書便 など
郵送以外で送付した際の罰則内容
信書は郵便以外の方法で送付した場合、郵便法第4条と郵便法第76条により重い罰則が科されます。具体的には以下のとおりです。
- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 配送を行った事業者だけでなく、配送を依頼した側も対象
信書の取り扱いには、厳格なルールが定められています。違反した際には、違法として企業のコンプライアンス上の重大な問題になるため、関係者への周知が重要です。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
② 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
違反した場合の企業が受けるリスク
信書の送り方に違反した際、企業が受けるリスクは多くあります。法的リスクとしては、前述の罰則です。しかし、それにとどまらず取引先からの信頼失墜、社会的な信用低下を招く可能性があります。
また、上場企業の場合は内部統制の不備として株主や投資家からの評価に影響する可能性もあります。
信書である契約書を送れるサービスと送れないサービスの違い
信書である契約書の送り方は限定されています。しかし、意図せずに送付できてしまう方法があるため、注意が必要です。適切な送り方を理解するため、それぞれの内容を見ていきましょう。
信書である契約書を送付できるサービス
信書である契約書を送付する選択肢は、郵便サービスと特定信書便の2種類あります。郵便と特定信書便の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 郵便サービス | 特定信書便 |
| 根拠法令 | 郵便法 | 民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法) |
| 事業者 | 日本郵便株式会社 | 総務大臣の許可を得た民間事業者(特定信書便事業者) |
| 特徴 | 幅広い選択肢があり、重要度や緊急性に応じて使い分けが可能 | 事業者ごとの特定条件下でのみ信書送達が可能 |
各種郵便サービスの中でもレターパックは、契約書送付に適したサービスです。A4サイズ・4kg以内の書類を全国一律料金で送付でき、追跡サービスも利用可能ですから、契約書送付に用いられることが多いです。
また、書留(一般書留、簡易書留)や配達証明郵便は、より安全性を重視したい場合に選ぶケースが一般的です。追跡番号から郵送物の所在を確認でき、郵便物が破損したり届かなかったりした場合に賠償されるメリットがあります。
特定信書便の民間事業者は「特定信書便事業者」として登録されており、一部の宅配事業者やバイク運送業者などが該当します。一般的な宅配便サービスとは異なり、特定の条件下でのみ信書の送達が可能です。
信書である契約書を送付できないサービス
一般的な宅配便サービスは、「荷物」の送達を目的としており、信書の送付はできません。法的根拠としても郵便法第4条にて信書の送達は、郵便事業者に限定されており、一般の運送事業者による信書の取り扱いが禁止されています。
同様にメール便についても「荷物」として扱われるサービスであり、契約書を送付できません。料金が安く便利なサービスですが、契約書のような信書には利用できないため注意が必要です。
郵送の手間・リスクを解決する「電子契約」という選択肢
契約書を郵送で送る場合、郵便法の制約により郵便サービスしか使えず、時間とコストがかかります。さらに郵送中の紛失や配達遅延のリスクもあります。
これらの問題を解決するうえで効果的な代替手段が、電子契約です。ここでは電子契約により解決する郵送時の課題や導入のメリットなどを解説します。
電子契約が解決する郵送の課題
電子契約は物理的な文書ではないため、信書に関する法律の規制対象外です。定められた送付方法の制約を受けることなく、インターネットを通じて契約書を送付して締結できます。主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 電子契約 | 郵送 |
| 送付方法 | メールやクラウドなど | 郵便と特定信書便のみ |
| 送付期間 | 即時 | 一般的に1日〜7日 |
| 送付コスト | 月額料金 | 切手代・封筒代・人件費 |
| 紛失リスク | なし | あり |
| 配達遅延 | なし | あり |
| 追跡機能 | 履歴管理 | 限定的 |
電子契約の法的有効性
電子署名法に基づく法的効力により、電子契約は従来の書面契約と同等の法的効力を持ちます。
適切な電子署名が付与された電子契約は、民事訴訟法における証拠能力も認められており、裁判での有効性についても問題ありません。
導入メリットの具体例
郵送の課題解決以外にも電子契約を導入するメリットは、多くあります。
- 印紙税の削減によるコスト削減効果
- 電子契約では印紙税が不要
- 高額な契約ほど印紙税がかかるため、規模の大きい企業ほど削減効果あり
- 業務効率化
- 印刷、製本、押印、郵送準備などの物理的な作業が不要
- 担当者の業務負荷が大幅に軽減
- 契約書の保管スペースや管理コストが削減
- セキュリティ強化
- 電子署名とタイムスタンプによる証明機能
- なりすましや改ざんを防止
- クラウド上での暗号化保存により、紛失や盗難のリスクも解消
- 環境負荷の軽減
- ペーパーレス化により紙の使用量を削減し、環境への配慮が可能
企業経営に大きな効果をもたらすでしょう。
電子契約導入の検討ポイント
電子契約サービスを導入する際には、電子署名法に準拠した機能などを総合的に評価して選択することが重要です。
- 電子署名機能の有無
- タイムスタンプ機能
- セキュリティレベル
- 使いやすさ
- サポート体制
- 料金体系

契約書の信書扱いを回避できる電子契約で効率化を
契約書は信書に該当し、適切な送り方を選ぶ必要があります。契約書の送付には、郵便法の制約や違反時の重い罰則、企業が負うリスクなどの理解が欠かせません。
「電子印鑑GMOサイン」は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営する電子契約サービスです。350万社以上の事業者にご利用いただいている国内でもトップクラスの実績があります。
テンプレート機能や一括送信といった便利な機能や選べる署名タイプ、充実したセキュリティ対策が特長の電子契約システムです。
同⽔準の他社サービスと比べ、使用料がリーズナブルであるため、はじめての電子契約にもおすすめです。また月に5件まで利用できる「お試しフリープラン」も用意していますので、ぜひ一度お試しください。