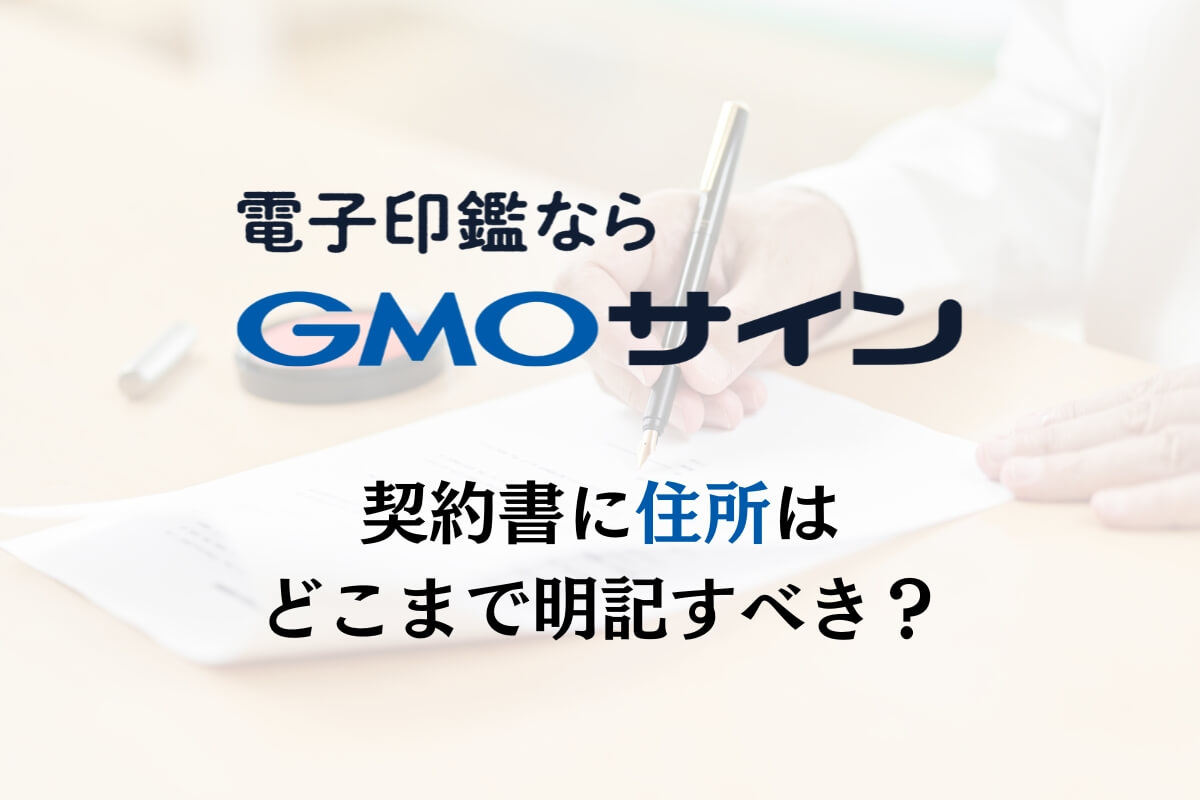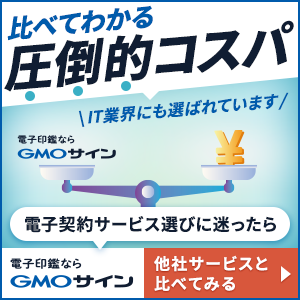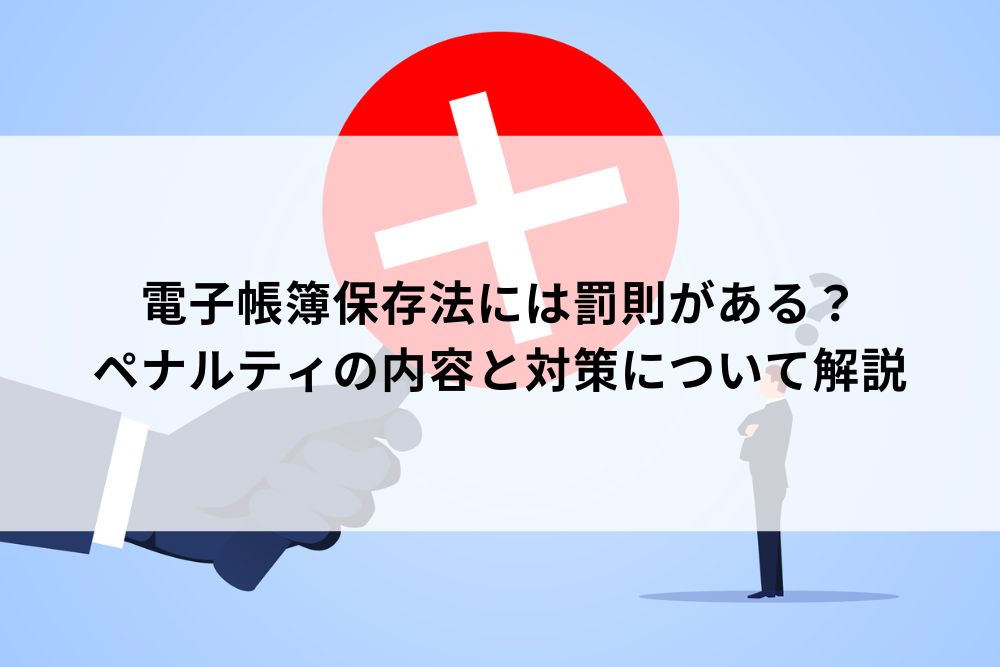契約書を交わす際、署名捺印欄に設けられた住所欄に「どこまで書けばいいのか」「住民票通りに書くべきか」と迷った経験はありませんか。
結論から言うと、契約書に住所の記載は原則として必要です。住所は、契約の相手方が誰であるかを法的に証明し、万一のトラブルの際に重要な役割を果たすためです。
この記事では、契約書に住所を記載する法的な理由から、個人・法人別の正しい書き方、住所変更や間違いがあった場合の対処法までをわかりやすく解説します。
契約書に住所の記載が不可欠な2つの法的理由
契約書を作成するにあたって、住所の記載をどうするかについては、大半の企業で住所を記入するように求められています。というのも、住所が記載されていないと、当事者の特定が後々難しくなる可能性があるためです。
したがって、基本的に契約書には住所を記載するものだと考えておいたほうがよいでしょう。
理由1:契約当事者を法的に特定するため
契約書における住所の最も重要な役割は、契約当事者を一意に特定することです。
個人の氏名や企業名だけでは、同姓同名や類似商号の他者・他社と混同されるリスクがあります。「こんな契約は知らない」といった否認を防ぐためにも、氏名・名称と住所をセットで記載し、「誰が」契約を結んだのかを明確にする必要があります。
理由2:訴訟など法的手続きで必要となるため
万が一、契約に関してトラブルが発生し訴訟に発展した場合、裁判所に提出する訴状には当事者の住所を記載することが民事訴訟法で定められています。
第百三十三条
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
出典:民事訴訟法|e-Gov法令検索
契約書に正確な住所が記載されていれば、速やかに訴訟手続きを進めることができます。
もし相手の住所が不明な場合、「公示送達」という特別な手続きが必要となり、時間も手間もかかってしまいます。将来的なリスクを回避するためにも、契約締結の段階で正確な住所を確認しておくことが極めて重要です。
\\ こちらの記事もおすすめ //
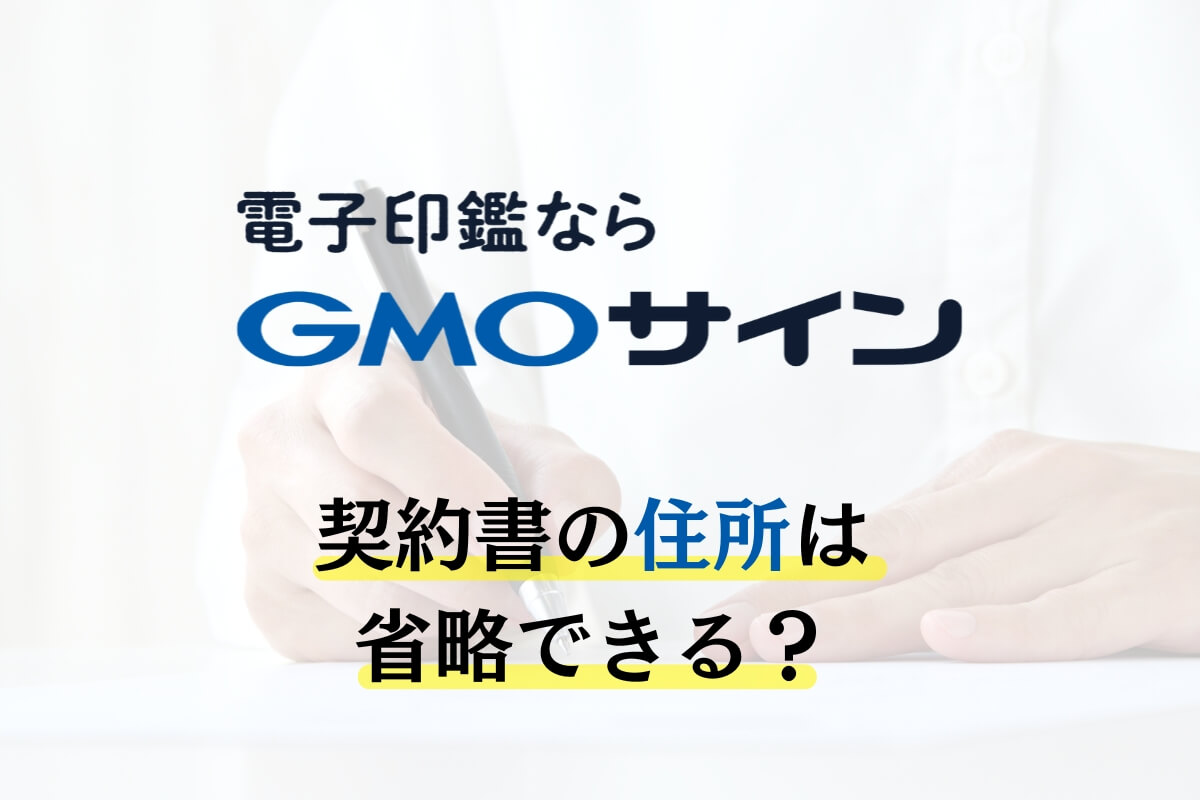
【ケース別】契約書の正しい住所の書き方と注意点
相手を特定するためにも、契約書には住所を記載するのが一般的ですが、どの住所を記載すればよいのでしょうか。ここでは、契約の当事者が企業の場合と個人の場合に分けてみていきます。
個人の場合:原則として「住民票の住所」を記載
個人事業主(フリーランス)や個人として契約する場合、住民票に記載されている正式な住所を省略せずに記載するのが原則です。
- 番地の書き方
-
「1-2-3」のようなハイフン表記でも問題ありませんが、より正確性を期すなら「一丁目2番3号」のように住民票の表記に合わせましょう。
- マンション・アパート名
-
必ず建物名と部屋番号まで正確に記載してください。(例:〇〇マンション101号室)
バーチャルオフィスや私書箱の住所は、居住実態がないため当事者の特定が困難になる可能性があります。そのため、契約相手としてはリスクが高いと判断されるケースも少なくありません。もし相手方がこれらの住所を提示した場合は、別途、住民票上の住所を確認させてもらうなどの対応を検討すべきです。
法人の場合:必ず「登記簿謄本(登記事項証明書)の所在地」を記載
法人として契約する場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)に記載されている本店所在地を正確に記載するのが鉄則です。
なお、本社と支社など、複数の拠点を有しているところもあるでしょう。この場合、特別な事情がない限り、登記されている本社所在地の住所を記入することになります。
契約書に住所を記載する目的として、契約当事者の特定があります。この場合、公的な登記情報をベースにしたほうがその目的にマッチします。登記されている商号と住所が一致すれば、会社の特定も可能なためです。
また、何らかの事情で登記されている住所と実際に活動している場所が一致しないケースもあるでしょう。その場合、会社の特定ができなくなってしまう恐れがあります。
契約書の住所を変更した場合
契約書に記載されている住所から引越しをして別の住所になった場合、再度契約書を作り直す必要はありません。契約書に記載されている旧住所でも、契約の当事者を特定でき、契約の法的効力が失われる心配がないためです。
また、新住所を記載した契約書を再度作り直す場合、その内容次第では印紙代もかかり余計な出費が発生することもあります。
\\ こちらの記事もおすすめ //
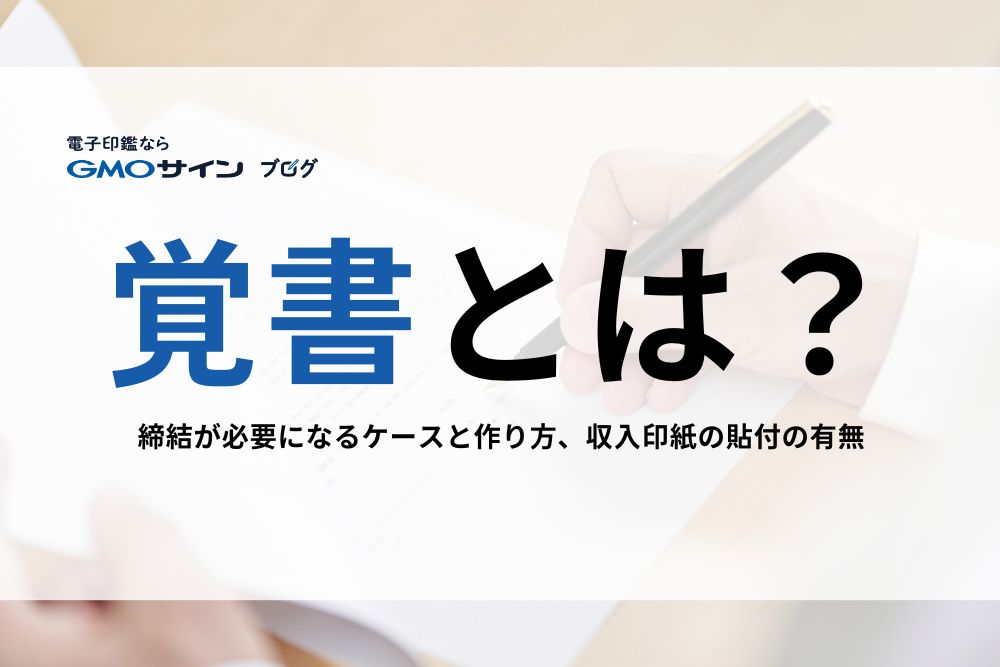
契約書の住所に関するよくある質問
契約書に住所を書きたくないのですが、省略できますか?
当事者の合意があれば住所がなくとも契約自体は成立しますが、当事者特定の観点から省略は推奨されません。後々のトラブルを避けるため、正確な住所を記載することが原則です。どうしても開示したくない特別な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
契約書の住所は住民票や登記簿謄本と完全に一致させる必要がありますか?
はい、完全に一致させるのが最も望ましいです。「丁目」をハイフンで省略するなどの表記揺れが即座に契約を無効にすることはありませんが、公的書類と寸分違わず記載することで、当事者の特定に関するあらゆる疑義を排除できます。
契約書に名前だけ書いて住所が書いていなかったら有効?
契約書に住所の記載がなくても、必ずしも無効になるわけではありません。民法上、契約は当事者の合意によって成立するという原則があるからです。
ただし、住所がないことで当事者が特定できない場合や、法令で住所記載が義務付けられている特定の契約では問題が生じる可能性があります。たとえば不動産取引や金銭貸借など重要な契約では、後々のトラブル防止のために住所記載が強く推奨されています。
名前だけでも有効な場合もありますが、リスク回避の観点からは詳細な住所情報を含めることが望ましいといえるでしょう。
契約書に住所を書くときの番地の書き方は?
契約書における住所の番地表記は、公的書類と一致させることが基本です。住民票や免許証に記載されている表記にあわせておきましょう。
一般的には「東京都千代田区丸の内1-2-3」のように、数字をハイフンでつなぐ表記が多く用いられています。不動産登記簿上の表記では「一丁目二番三号」のように漢数字が使われることもありますが、契約書では算用数字が読みやすいとされています。
また、マンションやビルの場合は「〇〇マンション101号」のように部屋番号まで記載する必要があります。
契約書の住所を間違えたら効力はない?
契約書の住所記載に誤りがあっても、それだけで契約が無効になるわけではありません。重要なのは、その誤りが契約当事者の特定に影響するかどうかです。
番地の一部が間違っていても本人が特定できる程度の軽微なミスであれば、契約の効力には影響しないことが多いでしょう。ただし、完全に異なる住所が記載されていた場合は、当事者の同一性に疑義が生じる可能性があります。
\\ こちらの記事もおすすめ //

まとめ
本記事では、契約書における住所の重要性と正しい書き方について解説しました。最後に、本記事の要点を振り返ります。
- 住所の役割:契約当事者を法的に特定し、訴訟時の手続きを円滑にするために不可欠。
- 個人の書き方:原則として住民票通りの住所を、建物名・部屋番号まで省略せず記載する。
- 法人の書き方:必ず登記簿謄本(登記事項証明書)の本店所在地を記載する。
- 住所変更時:契約を再締結する必要はないが、重要な契約の場合は「覚書」を作成して変更の事実を書面に残すと安心。
契約は、当事者間の信頼関係の基礎となる重要な行為です。住所の記載をはじめ、正確な情報で契約書を作成することを心がけましょう。
なお、電子契約サービス「GMOサイン」をご利用いただくと、契約相手の情報管理や、住所変更に伴う覚書の締結もオンラインで完結でき、業務効率化とコンプライアンス強化を両立できます。GMOサインのことが3分でわかる無料ダウンロード資料もご用意していますので、以下のリンクからぜひダウンロードしてみてください。