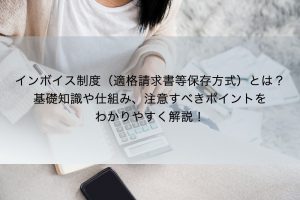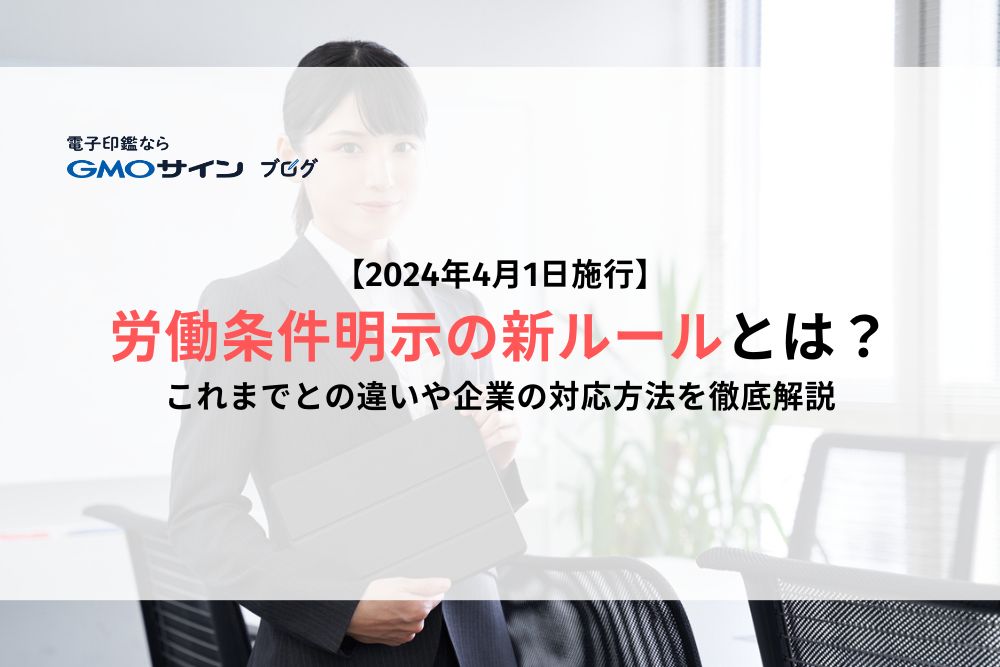刑事事件の判決では、懲役〇年・執行猶予〇年という結果が出ることも少なくありません。しかし、執行猶予とはどのようなものなのか、詳しく知らない人も多いでしょう。
執行猶予の概要や条件について、把握しておいて損はありません。本記事でわかりやすく解説します。
執行猶予とは
刑事事件の裁判において、執行猶予付きの判決が出る場合も決して少なくありません。執行猶予とは、有罪判決が下されても、刑の執行を一定期間猶予できる制度のことです。
執行猶予が付けば、有罪となり懲役刑が科されても即刑務所に収監されることはありません。
通常通りの生活が送れる
執行猶予が付くと、刑務所には収監されず、基本的に通常通りの生活が送れます。もし執行猶予の期間中問題を起こさずに期間が経過すれば、刑の言い渡しも無効になります。つまり、刑務所に収監されることがなくなるわけです。
執行猶予の目的
(刑の全部の執行猶予)
(参考:e-Gov法令検索)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
上で紹介したように、一定の条件を満たしていれば、執行猶予付きの判決となる場合もあります。
執行猶予は、比較的刑事責任が軽いものを対象にしています。執行猶予を付け、取り消しになった場合のデメリットを裁判官が伝えることによって、被告の自発的な更正を促せる可能性があります。
また刑務所に入ることが、逆効果になるリスクもあります。刑務所には何かしらの罪を犯した囚人が収監されているため、彼らから悪影響を受ける恐れがあります。比較的罪が軽ければ、執行猶予にしたほうが再犯を防止できる可能性が高くなります。
執行猶予付き判決の現状
刑事事件で起訴された場合、どの程度の割合で執行猶予が付くのでしょうか。第一審の割合で見てみると、60%程度で推移しています。執行猶予の期間は、1〜5年の間で裁判所がそれぞれの事例に鑑み決める形になります。
(参考:地方裁判所における民事訴訟事件(第一審)の審理の状況|裁判所)
執行猶予の条件
執行猶予付きとされるためには、一定の条件を満たさなくてはなりません。また、比較的軽い罪が対象になります。
刑法における条件
刑法の中では、執行猶予に関する条件も明記されています。基本的に3年以下の懲役・禁固もしくは50万円以下の罰金の場合に、執行猶予が付く可能性があります。このような量刑の犯罪には、重大犯罪は含まれません。
たとえば、重犯罪のひとつに殺人罪があります。殺人罪の量刑は最低でも5年以上の懲役となっています。つまり殺人罪で起訴されて有罪と認められれば、実刑判決となってしまうわけです。
情状酌量では、動機や被告の性格・年齢、犯行後の状況、社会的影響などが検討されます。もし情状酌量が認められれば、懲役刑でも1/2まで引き下げることが可能です。
殺人罪でも情状酌量が認められれば、懲役2年6カ月になる可能性があります。つまり、執行猶予が付く可能性が出てくるわけです。
情状とは
執行猶予が付くかどうかにおいては、情状が重視されます。情状は大きく分けて犯情と一般情状の2種類に分類されています。
犯情とは犯罪行為自体に関する事情を指します。被害の重大性や犯意の強弱、計画性の有無、犯行に至った動機や経緯などが考慮されます。一方の一般情状とは、被告の反省の度合いや再犯リスク、更生の可能性などを総合的に判断します。
たとえば示談成立の有無は、判決に大きな影響を与えます。もし、被害者側との示談が成立していれば、被害がある程度回復されている可能性があります。また被害者に対して真摯な対応をしていると評価され、きちんと反省しているとの心証を与えることが可能です。その結果、執行猶予が付く可能性も高まるわけです。
条件を満たしても執行猶予になるとは限らない
執行猶予になるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。しかし、すべての条件を満たしたからといって、確実に執行猶予にならないことも覚えておきましょう。
執行猶予が付くかどうかは、あくまでも裁判を担当する裁判官が判断します。その判断には、犯罪の重さや前科の有無、事件の内容、被害者との交渉、反省の態度が見られるかといった要素が総合的に考慮されるわけです。
執行猶予を付けるための対応策
執行猶予が付けば、刑務所に入らずに済みます。また、基本的に通常通り社会生活を送ることもできます。そのため、できれば執行猶予を付けてほしいと思う人が多いでしょう。
執行猶予を付けるためには、さまざまな対応策が存在します。被害者の有無などによって、対応策が異なるため、分けて紹介します。
被害者がいる場合
傷害など被害者が明確にいる場合であれば、示談交渉を進めることが大切です。示談が成立すれば、被害者の処罰感情がなくなったことの立証になるからです。
判決を下すにあたっては、被害者感情が重視されます。示談に応じることで、被害者の処罰感情がなくなれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
示談は、執行猶予が付く加害者のために行うと思われがちです。しかし、被害者への救済といった意味合いもあります。示談金を受け取ることで問題に一応の決着が付き、被害者側も前向きに今後の人生に取り組めるようになるからです。
示談交渉は加害者自身で行うのではなく、弁護士が代理人となって被害者側と交渉することが一般的です。刑事事件の担当が豊富で、示談交渉に長けた弁護士にお願いするとよいでしょう。
被害者の感情によっては、示談が成立しない場合もあります。その場合でも執行猶予が付く可能性はあります。そのためには、被害弁償を行うことが重要です。
被害弁償とは、弁護士が代理人となって、謝罪したり被害を弁償したりすることです。仮に被害者側が受け入れなかったとしても、加害者が今回の事件について深く反省していることが示せます。また、被害回復に努めている姿勢も強調できます。結果的に裁判官の被告への情状が良くなって、執行猶予付きの判決が出る可能性も高くなるわけです。
被害者がいない場合
事件の性格上、具体的な被害者がいない事案も出てくるでしょう。具体的には薬物事件などが挙げられます。このような被害者のいない事案でも、執行猶予が付く可能性は十分考えられます。被害者のいない事案では、執行猶予を付ける妥当性を裏付けられるような証拠を集めることが重要です。
情状には犯情と一般情状があるため、両面で被告にとって有利になる証拠集めを進めましょう。まず犯情ですが、犯行が決して悪質ではなく被害が軽微なものにとどまっていることを強調しましょう。また、計画性がないなど、動機が悪質ではないことを示せば、被告人の犯情で有利になる可能性があります。
一般情状の場合、社会の中でも更正が期待できる点を強調しましょう。たとえば執行猶予が付いた場合、被告を監視する人がいることを示せば、裁判官も安心して執行猶予を付けられます。そのためには監督者を誰にするか、よく検討しておきましょう。
就職することで社会復帰を進め、更生することも一つの方法です。就職先が決まっているのであれば、その会社の上申書を提出するとよいでしょう。これらの証拠は、弁護士が収集してくれます。裁判所への提出手続きの代行も可能です。
執行猶予の取り消し
せっかく判決で執行猶予が付いたとしても、取り消されてしまう可能性があります。取り消しには自動的に取り消される場合と、裁判官の判断で取り消される場合があります。以下のような行動を執行猶予の期間中に行わないように注意してください。
自動的な取り消し
自動的に取り消されてしまう事例は、刑法26条に規定されています。その条件をまとめると、以下のとおりです。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(参考:e-Gov法令検索)
まず猶予期間中に何か違法行為を犯し、禁錮刑以上の判決が下されると、自動的に執行猶予が取り消されてしまいます。執行猶予期間中に実刑判決が出た場合、前の判決の懲役刑も加算されるため、かなりの期間刑務所に入らないといけなくなります。
裁判官の判断で取り消される事例
裁判官の判断で取り消される事例に関しても、刑法第26条の2で規定されています。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(参考:e-Gov法令検索)
執行猶予期間中に軽微な罪を犯して、罰金刑になったとします。この場合、裁判官の判断次第では取り消される可能性があります。そのため、執行猶予期間中は、疑われるような行動をとらないように常日頃から気を付けなければなりません。
執行猶予に関するよくある質問
懲役3年執行猶予5年とはどういう意味?
「懲役3年執行猶予5年」とは、裁判で懲役3年の有罪判決を受けたものの、5年間は刑務所に入らず社会で生活できるという意味です。
この5年間の猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、懲役3年の刑は執行されず、刑務所に入る必要がなくなります。
執行猶予が終わったら前科はつく?
執行猶予が付いても、有罪判決を受けた事実は変わらないため、前科はつきます。執行猶予期間を無事に満了しても、前科が消えるわけではありません。
刑務所に入らなかったとしても、有罪判決を受けた記録は残り、再び事件を起こした場合などには前科が不利に働くことがあります。
執行猶予中に交通違反をしたらどうなる?
執行猶予中に交通違反をしても、軽微な違反(例:スピード違反や信号無視など)で反則金や罰金で済む場合は、原則として執行猶予が取り消されることはほとんどありません。
しかし、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど重大な違反で起訴され、禁錮刑や懲役刑の実刑判決を受けた場合は、執行猶予が取り消され、もともとの刑と新たな刑の両方を服役することになります。
誠実な対応で執行猶予が付く可能性を高める
執行猶予付きの判決が出れば、刑務所に収監されずに通常通りの生活ができます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ、刑の言い渡しは効力を失います。執行猶予が付くか否かについては、いくつか条件があるため、条件を満たす努力をすべきです。
被害者に対する謝罪や被害回復などを行い、真摯に自分の犯した罪と向き合っていると評価されれば、執行猶予が付く可能性も高まります。弁護士に相談して、最適な対応について専門的なアドバイスを受けてみるとよいでしょう。