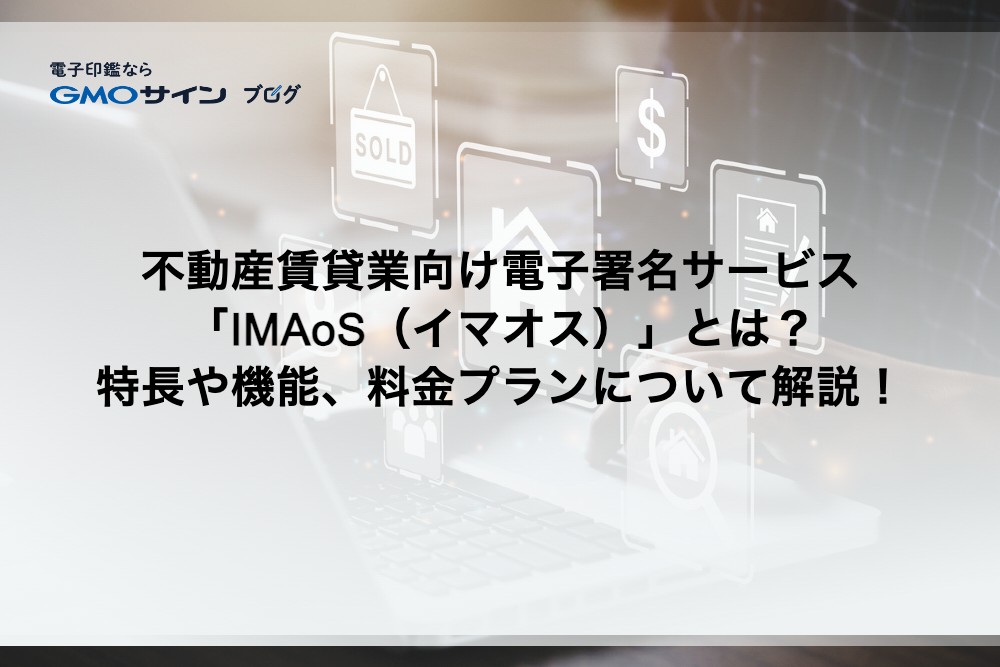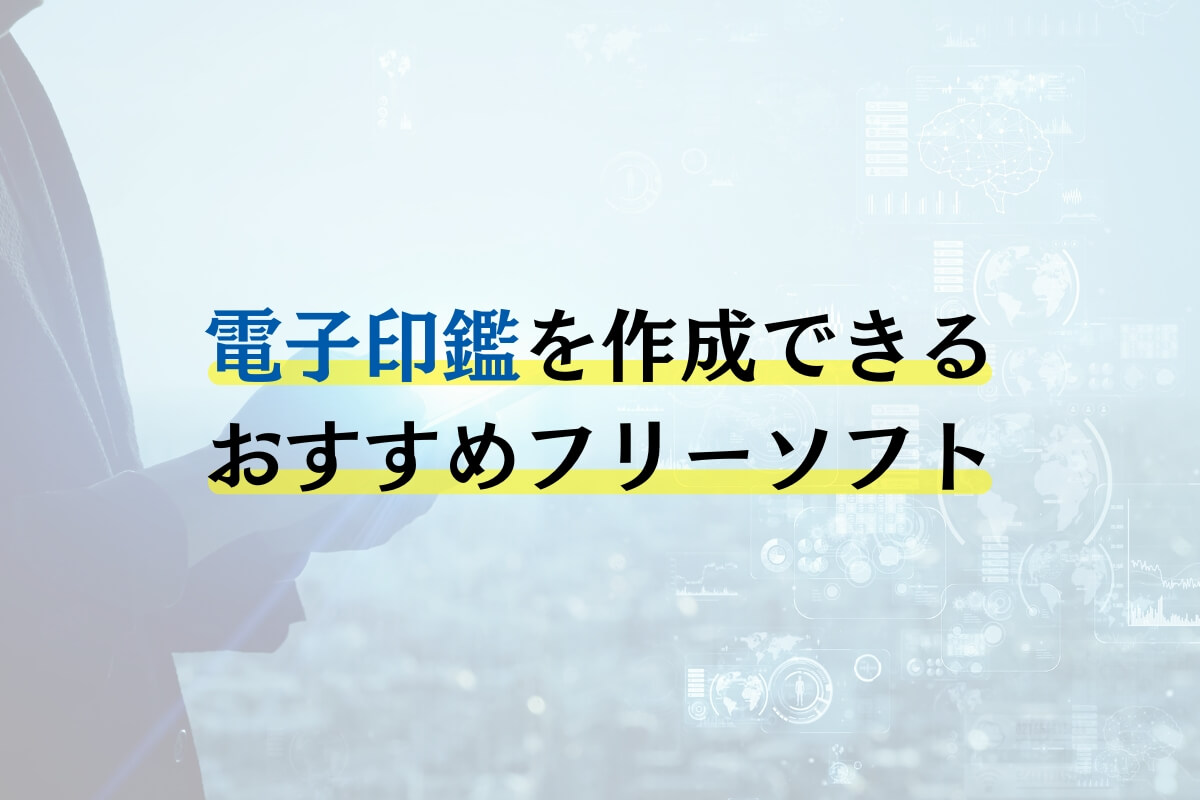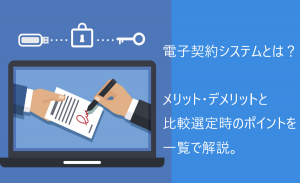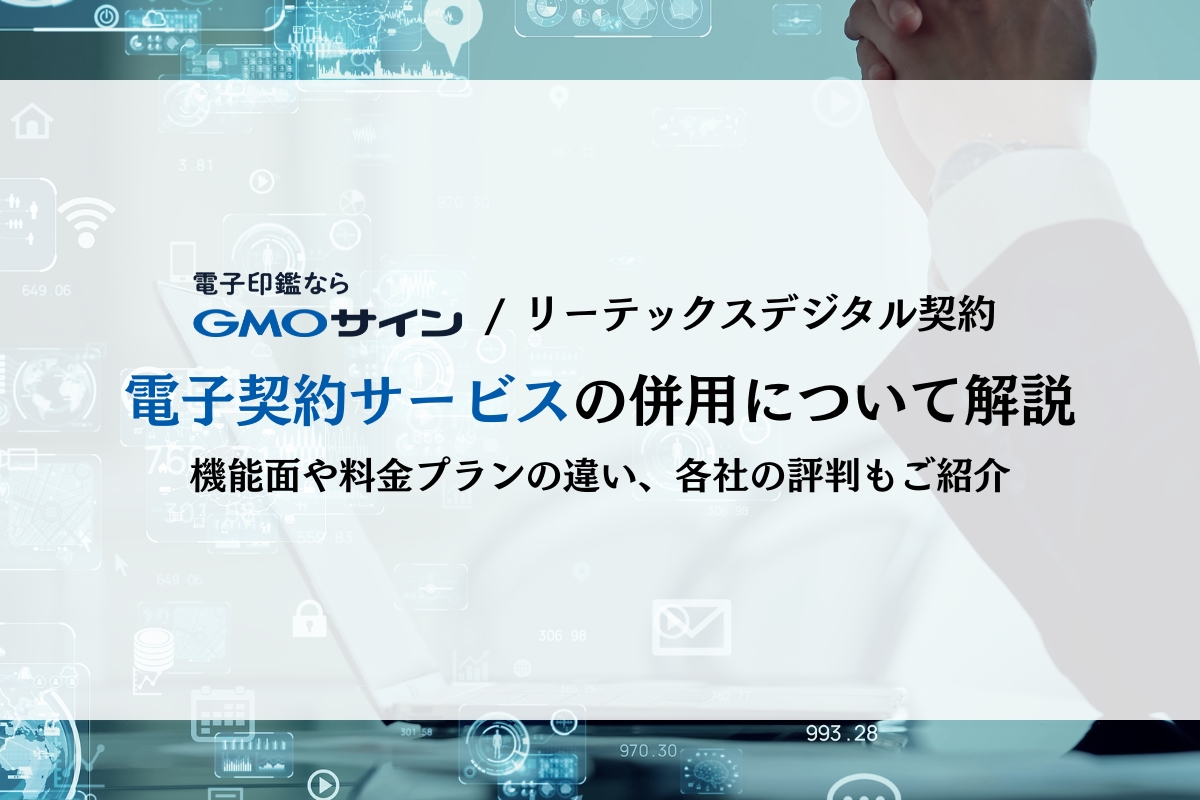契約期間の自動更新はどのように書けばよい?
自動更新条項の記載が適切でないと、予期しない契約継続や終了が起こるのでは?
契約終了後の存続条項の書き方を知りたい!
契約期間の記載が不適切だと、契約の開始・終了時期があいまいになり、双方の権利義務関係でトラブルが発生する可能性があります。この記事では、契約書における契約期間の正しい書き方とトラブルを避けるための重要なポイントを詳しく解説します。
- 契約期間について記載すべき3つの必須項目
- 自動更新の有無や条件設定の具体的な記載方法
- 契約終了後の存続条項の重要性と書き方
- 契約期間の変更・延長時の注意すべきポイント
- 契約期間を定めない場合のメリット・デメリット
- 契約期間管理で見落としがちな確認事項
契約書の期間については、記載方法のほかに「契約期間の管理漏れが心配」といった不安もお持ちではないでしょうか。
そのような方は、電子契約サービスの利用をおすすめします。電子印鑑GMOサインでは、契約期間の更新日(満了日)を自動で通知する機能があり、更新手続きの漏れを防止することが可能です。
- 電子署名により、契約書の改ざんリスクを排除して安全性を確保できる
- クラウド上での迅速な契約締結と管理が可能
- 電子署名法に準じた法的証拠力のある電子契約で、紙の契約書と同等の信頼性を実現
また、GMOサインのお試しフリープランなら、月5件まで電子契約を無料で利用できます。電子署名による締結や契約書テンプレートの登録、基本的な契約管理が可能なので、小規模な契約業務であれば十分に無料の範囲でも活用できるでしょう。安心・確実に契約管理を行いたい方は、GMOサインの導入をご検討ください。
契約書における契約期間の基本
契約書を作成する際は、いつまでその契約が有効なのか明記することが大切です。契約書における期間の概要や必要性など、基本を解説するのでそれぞれ確認していきましょう。
契約書の契約期間とは?
契約期間とは、契約を締結してからその効力が終了するまでの期間のことです。契約書の有効性や義務・権利などがいつまで継続するのか記載されているので、トラブルを防止する役割があります。
契約期間には、以下のような種類が存在します。
- 固定期間
- 自動更新
- 期間なし
固定期間にする場合は「2025年4月1日〜2026年3月31日」など、特定の間継続することを明記します。自動更新は、期間が満了したタイミングでお互いに終了の意思表示がない場合、そのまま契約を続行することが可能です。更新を毎回行う必要がないので、作業を効率化できることや更新のし忘れを防止できることがメリットとして挙げられます。
契約期間を定める必要性
契約期間を定めるのは、その契約がいつまで継続するのかを明確にして、当事者間のトラブルを避けるためです。口約束のみの場合、契約が終了するタイミングで「聞いていない」「更新すると思っていた」などの言い争いに発展する可能性があります。
契約書に具体的な期間を定めることで、解除や更新に関するトラブルを未然に回避することが可能です。また、通常の契約では期間が終了したタイミングで話し合いを行う必要がありますが、自動更新条項を設けることでその手間を回避できます。
契約書に記載すべき契約期間の3つの項目
契約書に記載すべき契約期間の項目は以下の3つです。
それぞれ重要な項目なので、どのような内容なのか理解を深めておきましょう。
契約期間
契約書では、いつまでその契約が続行するのかを基本的に定めておくことが大切です。契約が継続している間は、当事者間で債務を履行する義務や権利が発生します。
業務委託契約や賃貸借契約など、取引が特定の間継続される契約では具体的な期間を設けることが多いです。期間があいまいなままだと、想定していたスケジュールが終了していないのにもかかわらず、一方的に作業を停止させられてしまう可能性もあります。
自動更新の有無・条件に関する記載
自動更新は、契約期間が終了したタイミングで当事者のいずれかが解除の意思表示を行わなかった場合、そのまま契約を続行する条項のことです。契約の継続性を確保するために、業務委託契約やリース契約、サブスクリプション契約などで導入されています。
契約書に自動更新条項を記載することで、毎回の更新手続きを不要にして、失効によるトラブルやサービス停止を防げます。ただし、自動更新を設ける場合は、拒絶通知をいつまでにするべきなのか明確にすることが大切です。
自動更新を設けることで更新手続き漏れを防げますが、含められない場合には別の対策が必要です。
電子契約サービスのGMOサインでは、更新時期が近づくと通知が届くので漏れを防ぎやすくなります。オンライン上で文書を保存できることから紛失や改ざんのリスクも減らせるので、ぜひ電子契約の導入も検討してみてください。
契約終了後の存続条項の重要性
存続条項は、期間が満了したり解除されたりした場合でも、特定の効力が残ることを明示するためのものです。契約書に記載された義務や権利は契約終了と同時に消滅するのが原則ですが、性質上契約後も存続させたほうがよい条項があるため、契約書に定めておく必要があります。
具体的には、以下のような重要な条項は存続させるケースが多いです。
- 秘密保持義務
- 競業避止義務
- 損害賠償条項
- 知的財産権の帰属
- 準拠法や合意管轄
- 反社会的勢力の排除義務
たとえば、秘密保持義務が契約中のみ有効になっていると、元業務委託先が顧客情報を使って営業活動をしている場合に法的請求が困難になる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも、存続条項を設けることが大切です。
なお、秘密保持義務や競業避止義務は、無期限に課すと相手方の活動を不当に制限してしまうため、存続させる期間を定めるのが一般的です。例えば、秘密保持義務であれば契約終了後3〜5年、競業避止義務であれば1〜2年などが実務上の目安とされます。一方的に不利な内容は無効と判断される可能性もあるため、双方にとって合理的な期間を設定しましょう。
\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書における契約期間の記載例・ひな形
契約書における期間の記載方法は、自動更新の有無や存続条項の内容によっても異なります。ここからは、それぞれのタイプごとに記載例を紹介するので、契約書を作成する際の参考にしてみてください。
自動更新を含む場合の記載例
自動更新の内容を契約に含む場合は、以下のように記載します。
第○条(契約期間)
本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
ただし、契約期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者から書面により更新しない旨の意思表示がなされない限り、本契約は同一条件にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
条項を記載する際は、契約が継続する期間を明示できているのかチェックしましょう。また、自動更新をする際、いつまでにどのような拒絶通知をするべきなのかも明記しておくことが大切です。
自動更新なしの場合の記載例
自動更新なしで更新期間を設ける場合は、以下のような内容を契約書に記載しましょう。
第○条(契約期間および更新)
本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
契約期間満了後も本契約の継続を希望する場合は、契約満了日の30日前までに相手方に対し書面にて通知し、当事者間で協議のうえ、書面による合意により更新するものとする。
通知または合意がなされない場合、本契約は契約期間満了をもって終了する。
上記では、自動更新を行う場合と同様に、契約の有効期間を明確に定めています。また、協議を行なったうえで更新を行うことについても明記しています。協議の方法は契約によって異なりますが、書面や電子メールなどが一般的です。
契約終了後の存続条項を含めた場合の記載例
存続条項を含めた記載例は以下のとおりです。
第○条(契約期間)
本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
ただし、契約期間満了の30日前までに、いずれかの当事者から書面による更新拒絶の通知がない限り、本契約は同一条件にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
第○条(契約終了後の存続条項)
本契約が満了、解除、解約その他いかなる理由により終了した場合であっても、第○条(秘密保持)、第○条(損害賠償)、第○条(知的財産権)、第○条(準拠法および管轄)およびその性質上契約終了後も存続すべき条項については、契約終了後もなおその効力を有するものとする。
残存条項では、契約満了や解除、解約などが発生した場合、特定の条項の効力が残ることを明記しています。存続したい条項については、具体的に記載することが大切です。契約書内の「第○条」と記載することで、紛争時の解釈のあいまいさを排除できます。
\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書の契約期間を変更する方法と注意点
事前に契約期間を設定したものの、あとで変更をくわえなければいけない場合、トラブルを防ぐために正しい方法を理解しておくことが大切です。ここからは、変更する際の記載例や契約期間延長時の注意点について解説していきます。
契約期間の変更・訂正方法
契約後に期間の変更を行う場合は、当事者から合意を得て覚書を作成することが一般的です。以下は契約期間の変更に関する覚書の例です。
覚書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は、令和○年○月○日付で両者が締結した業務委託契約書(以下「原契約」という。)の契約期間について、下記のとおり変更することに合意し、本覚書を締結する。
記
1.契約期間の変更
原契約の第○条に定める契約期間を、以下のとおり変更する。【変更前】令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
【変更後】令和○年○月○日から令和○年○月○日まで2.その他条項
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。
本覚書は原契約の一部を変更するものであり、原契約の他の条項はすべて有効に存続する。令和○年○月○日
(甲)○○株式会社
住所:〒000-0000 東京都○○区○○町1-2-3
代表取締役 ○○ ○○ (署名・押印)(乙)△△株式会社
住所:〒111-1111 大阪府○○市○○町4-5-6
代表取締役 △△ △△ (署名・押印)
一方、契約前に内容を訂正する場合は、覚書の作成ではなく契約書の修正を行います。修正は以下の手順で進めます。
訂正したい期間に二重線を引いて消します。修正液やテープを使用すると改ざんのリスクが高まるため、ボールペンを使用して線を引きましょう。
二重線で消した期間の上部に訂正後の正しい期間を明記します。
どの部分を何文字訂正したのかわかりやすくするために「5行目、5字削除、5字加入」などの文章を記載します。
訂正印は、権限を有する者が押印したことを証明するために、契約書に使った印鑑と同一のものを使用してください。また、契約は当事者間の合意によって成立するため、訂正の有効性を確保するには、関係者全員から訂正印をもらうことも重要です。
契約書を複数部作成している場合は、すべての部に同一の訂正を施す必要があります。訂正が一部にしか反映されていないと当事者間で認識の違いが生じ、思わぬトラブルの原因となることがあるため注意してください。
契約期間延長時の注意点
民法第522条では、契約の成立について以下のように記載されているため、契約期間を延長する際は、必ず当事者の合意を得ることが大切です。
(契約の成立と方式)
引用:民法|e-Gov法令検索
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
契約期間の延長により、報酬や納期などの条項にも影響がある場合は、それらもあわせて見直しと修正を行いましょう。特に、報酬の支払いスケジュールや金額などが、以前の契約期間を前提として定められていた場合は注意が必要です。
\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書の契約期間を定めない場合の注意点
契約書で契約期間を定めない場合、そのメリット・デメリットを事前に把握しておくことが大切です。以下では、契約期間を記載しない場合のリスクやトラブル事例についてもあわせて解説していきます。
契約書で契約期間を定めない場合のメリット・デメリット
「期間を定めない契約を締結したいけど、メリット・デメリットはあるの?」と疑問を抱いている方に向けて、期間を設定しない場合の利点やリスクを解説していきます。
契約書で契約期間を定めない場合のメリット
契約書で契約期間を定めないメリットは以下のとおりです。
- 柔軟に契約を継続できる
- 都度の再契約が不要になる
- 柔軟な解約が可能になる
契約書に期間を定めない場合、当事者間で柔軟に契約を継続できます。当事者間の信頼関係が前提となりますが、長期的な業務提携や取引関係においてスムーズな関係維持が可能です。また、短期ごとの契約更新や覚書の作成といった事務手続きが不要になり、管理コストを削減できます。
(委任の解除)
引用:民法|e-Gov法令検索
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
契約書で契約期間を定めないデメリット
契約書で契約期間を定めないデメリットは以下のようなことが挙げられます。
- 契約の終了タイミングが不明確になる
- 更新条件や終了条件の明確化が困難になる
- 契約の有効性を巡って争いが起こるリスクがある
- 相互の信頼が前提となる
契約期間が明示されていない場合、いつ契約が終わるのか、判断基準が不明確になることがあるので注意が必要です。履行義務の有無や終了日をめぐって紛争になる可能性もあるので、契約期間の取り扱いは慎重に行いましょう。
契約書に契約期間を記載しない場合のリスクとトラブル事例
契約書に契約期間を記載しない場合、以下のようなリスクが考えられます。
- 契約終了の時期や方法が不明確になる
- 契約解除時の予告期間を巡って争いになる可能性がある
- 業務の継続や終了判断を巡って紛争になる可能性がある
契約期間について双方の認識に違いが生まれてしまうと、信頼関係が悪化する可能性があります。
また、口頭で契約解除を伝えたのにもかかわらず相手方が聞き逃していた場合、契約終了後に請求書が届くこともあるので注意が必要です。支払いを拒否した場合、訴訟を起こされるリスクもあるので、基本的には契約期間を文書に明示しておくことをおすすめします。
契約書作成時における契約期間の確認ポイント
契約書作成時は、期間について以下のポイントを確認しておきましょう。トラブルを未然に防ぐために重要な項目なので、それぞれの内容を参考にしてレビューを行うことをおすすめします。
契約期間は適切か?
契約期間は、業務の内容や目的に適しているか確認することが大切です。たとえば業務委託契約を締結する場合、期間が短すぎると委託した業務を完了できずトラブルにつながる可能性があります。
逆に契約期間を長く設定した場合、契約関係にメリハリをつけづらくなり、不要な拘束を生んでしまうこともあります。過去の取引や事例も参考にしながら、適切な契約期間を設定するように心がけましょう。
次の契約相手を選ぶ猶予や引き継ぎの有無なども考慮しながら期間を設定する必要があります。契約期間が定まらない場合は、相手方と相談しながら適切な内容を見極めることが大切です。
自動更新条項に条件を設けるか?
契約の更新を円滑にするために自動更新条項を設ける場合、どのような条件を設定するのかも重要です。更新の拒絶通知を期間終了間近に行えるようにすると、突然契約終了を告げられることがあります。
短い期間ですべての作業を滞りなく終わらせるのは困難であるため、バランスを考慮して条件を設定することがおすすめです。拒絶通知の期限は2週間〜1カ月前にすることが多いですが、2カ月前から通知を行えるように調整することもあります。
更新手続き漏れの対策も重要
契約を締結したあとは、更新手続きを忘れないように対策を行うことが大切です。
特に契約数が多い場合は、いつまでに更新の判断をするべきなのか把握しておくことが重要です。たとえば、契約ごとに開始日や満了日、更新通知期限などをGoogleスプレッドシートにまとめておくと効率的な管理ができるようになります。
また、電子契約サービスのGMOサインでは、更新時期が近づくと通知が届く機能があるので、漏れを防ぎやすいです。非改ざん性を証明するための電子署名やタイムスタンプの付与も行えるので、セキュリティ面での心配も減らせます。安全かつ効率的に契約を管理したい方は、電子契約の導入を検討してみてください。
契約書の契約期間に関するよくある質問
契約書の1年間はいつからいつまで?
契約期間の計算には、民法の「初日不算入の原則」が関係します。少し複雑ですが、トラブルを避けるために重要なので理解しておきましょう。
- 原則:期間の初日はカウントしない
-
民法では、期間の初日を計算に含めないのが原則です(140条)。例えば、契約書に「本契約は締結の日から1年間有効とする」とあり、締結日が2025年4月1日の場合、初日である4月1日は算入しません。
- 起算日(カウント開始日): 2025年4月2日
- 満了日: 起算日の1年後の応答日(2026年4月2日)の前日である、2026年4月1日となります。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
引用:民法|e-Gov法令検索 - 例外:「午前0時」から始まる場合や「〇〇から」と明記した場合
-
「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とあるように、「2025年4月1日から1年間」と始期を明確に記載した場合は、初日(4月1日)からカウントします。
- 起算日(カウント開始日): 2025年4月1日
- 満了日: 起算日の1年後の応答日(2026年4月1日)の前日である、2026年3月31日となります。
最も確実な記載方法このような計算の複雑さを避け、認識のズレを防ぐために、「本契約の有効期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとする」のように、始期と終期の日付を明確に記載する方法が最も安全で推奨されます。
契約期間の定め方は?
契約期間を定める際は、契約内容や目的にマッチしているのか確認しましょう。契約期間が短すぎる場合、委託した業務や遵守すべき作業が期日通りに完了しない可能性があります。民法上、契約は当事者間の合意のもと成立するため、契約者同士で相談しながら調整することも大切です。
契約書に効力のある期間は?
民法521条では、契約の締結について以下のように記されているため、当事者間の合意があれば自由に期間を調整できます。
(契約の締結及び内容の自由)
引用:民法|e-Gov法令検索
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
ただし、契約の種類によっては契約期間に制限が設けられているケースもあるので注意してください。たとえば借地借家法第3条では、借地権の存続期間が最低30年と定められています。
契約書に日付を空欄にしたら無効?
契約書の日付を空欄にしたとしても、契約自体が無効になることはありません。民法では、契約を申し入れる意思表示に対して、相手方が承諾した場合に契約が成立すると定められているためです。
民事訴訟法228条では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と記載されています。つまり、契約書の日付は成立における必須要件ではないということです。
ただし、法的なトラブルを防ぐためにも、契約期間や日付は明確に記載しておくことをおすすめします。
契約書の契約期間管理はGMOサインが便利
契約期間を記載する際は、その契約の内容や目的に合っているのか確認し、明確に記すことが大切です。契約期間が当事者同士であいまいになっていると、予期せぬ解除や紛争につながる可能性があります。
また、突然の契約解除を告げられてしまうと、業務整理や秘密情報の返却などの作業に追われることもあるので注意してください。
契約の締結が完了したあとも、それぞれの契約期間を適切に管理する必要があります。電子契約サービスのGMOサインでは、期間満了時にリマインド通知が届くため、契約の更新漏れをなくせます。自動更新に設定している場合でも拒絶通知の漏れを防げるので、契約書を安全に管理することが可能です。
GMOサインは、月に5件まで文書の送信ができるフリープランも用意しています。契約に関する業務の効率化を図りたい方は試しに利用してみてください。
免責事項(本記事のご利用にあたって)
本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。