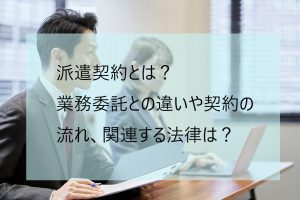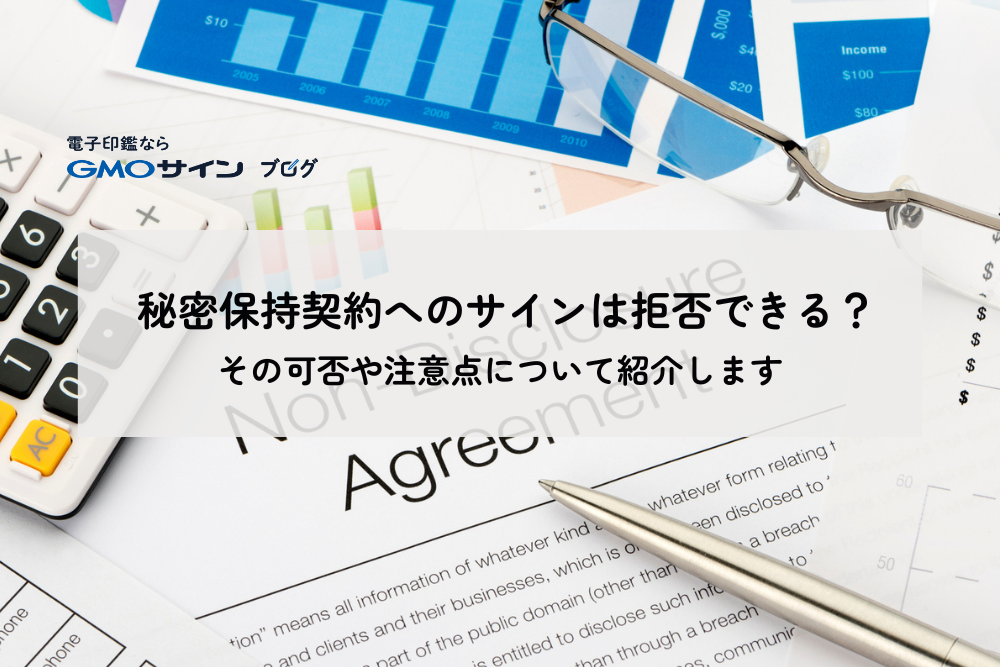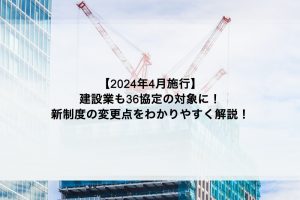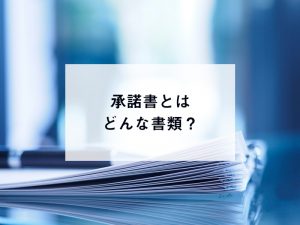毎年、数多くの火災が発生してます。
万が一の事態に備えて、火災保険に加入しておくことも検討するべきです。
この記事では、火災保険に加入する必要性や補償内容、加入率(未加入率)などに関して詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。.
火災の発生件数と被害状況
『令和5年版消防白書』によると、2013年には年間出火件数が48,095件でしたが、2022年には36,314件に減少しました。発生件数の減少に伴って死者数も減っていますが、損害額は増加傾向にあります。
また、過去に比べると出火件数が減少しているものの、2022年時点では依然として1日あたり99件の火災が発生していることも事実です。損害額が上昇していることを踏まえ、火災の発生防止に努めるとともに、万が一の事態に備えて火災保険への加入も検討するべきです。
火災保険とは?
火災保険とは、火災の発生などによって住宅(建物・家財)が損害を被る事態に備えるための保険です。火災だけではなく、落雷や雪などによる損害も補償されるケースがあります。
補償内容は保険商品・プランごとに異なるため、詳細を知りたい場合は各保険会社の公式サイトをご覧ください。
地震保険に加入する場合、火災保険を契約していることが前提とされる
上述したように、火災保険では、地震が原因で発生した火災による損害の補償に関してはカバーされません。
地震による損害の補償も受けたい場合は、別途、地震保険にも加入しておきましょう。地震保険は、火災保険の付帯保険という扱いです。そのため、地震保険単体では加入できず、火災保険とセットで加入する仕組みとされています。
火災保険の補償内容
火災保険は、さまざまな保険会社によって提供されていますが、保険商品やプランによって補償対象・補償範囲・保険金額が異なることにご留意ください。以下、それぞれに関して詳しく説明します。
補償対象
火災保険の補償対象は、以下の2つに区分されています。
・建物:被保険者が所有し、住居としてのみ使用している建物(持ち家)
・家財:建物内に収容される家財一式(動産)
建物には、門・塀・車庫などの付属物は含まれますが、土地は含まれません。なお、分譲マンションの場合は、専有部分が補償対象とされます(共有部分に関しては、マンション管理組合が火災保険の契約を締結ことが一般的)。また、補償対象とされる家財は、家具・家電・衣服など、日常生活で使う動産です。
保険商品やプランによって補償対象(建物のみ、家財のみ、建物と家財の両方)が異なり、自由に組み合わせることが可能な場合もあります。「高価な家財を保有している場合は家財も補償対象に含める」など、ご自身の状況を踏まえて補償対象を決めましょう。詳細は、各保険会社の公式サイトなどでご確認ください。
補償範囲
火災保険の補償範囲は、火災による損害だけではありません。保険商品・プランによっては、以下に示すように火災以外による損害も補償範囲に含まれ、補償範囲をご自身で選択できる場合もあります(地震による損害に関しては火災保険の補償範囲外)。
・偶然の事故(火災、破裂・爆発、水濡れ、物体の落下・衝突、騒擾、盗難など)による損害の補償
・自然災害(落雷、雪災、風災、水災など)による損害の補償
なお、デフォルトでは補償範囲に含まれておらず、特約・オプションとしてセットできるものもあります。また、補償範囲が広くなるほど、保険料も高くなることにご留意ください。詳細に関しては、各保険会社の公式サイトなどで確認しましょう。
保険金額
火災保険に加入しておけば、火災などで建物・家財が損害を被った場合に、実際の損害額が保険金として支払われます。その際、契約時に決めた保険金額が上限とされることにご留意ください。
建物の保険金額は、再調達価額(同等のものを建て直せる、または、再購入できる金額)を基準として決めるケースが主流です。建物の評価額は、新築時の建築費を元に算出する方法と、面積を元に算出する方法があります。
家財の保険金額に関しては、保険会社が定める範囲内で自由に設定が可能です。建物と異なり、再調達価額(新品で同等の家財を手に入れるために必要な金額)に設定する必要はありません。
保険金額が大きくなると、支払う保険料も増えます。「最低限の家具・家電を購入できる金額」に設定し、保険料を抑えることも検討しましょう。
火災と法律・公的支援
火災は、人為的に発生する場合と、自然災害の結果として発生する場合があります。
人為的な原因で火災が発生し、建物・家財の損害を被った場合、賠償を請求できるのだろうか
自然災害が原因で損害を受けた場合に、公的支援を受けられるのだろうか
と気になる方もいるでしょう。
以下、火災と法律の関係、および、公的支援に関して詳しく説明します。
重大な過失がない場合、火元は法律上の賠償責任を負わない
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)において、「重大な過失による火災でなければ、火元は賠償する責任を負わない」という主旨の規定があります。
最高裁判所の判例によると、重大な過失とは、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」とされています。
ご自身が火災を引き起こさないように注意していても、近隣住民が原因で火災に巻き込まれる可能性があり、重大な過失がない限りは火災を引き起こした人物に対して賠償を請求できないため、万が一の事態に備えて火災保険に加入しておくべきです。
故意による火災(放火)で損害を被った場合は、犯人に損害賠償を請求できる
第三者が故意で火災を引き起こしたこと(放火)で建物・家財の損害を被った場合は、犯人に損害賠償を請求できます。ただし、民事訴訟の結果、勝訴したとしても、犯人が資産を保有していなければ、賠償金を受け取れない可能性があることにご留意ください。
火災保険に加入しておけば、第三者による放火で損害を被った場合に補償を受けることが可能です。
住宅を失っても、公的支援だけでは資金が不足する
洪水による床上浸水や土砂崩れなど、自然災害によって被害を被った場合、国や自治体による支援を受けられることもあります。ただし、たとえば、被災者生活再建支援制度では、1世帯あたり最大300万円までしか支援金を受け取れません。300万円では、住宅の建て替えなどが困難なケースも多いでしょう。
上述したように、火災保険の内容によっては、火災だけではなく、各種自然災害’(地震を除く)による損害に関しても補償を受けられるケースがあります。住宅が全壊したり、大規模半壊の状態になったりした場合、公的支援だけでは生活再建に必要な資金が不足する可能性があるため、火災保険に加入しておくこともご検討ください。
火災保険の加入率(未加入率)
内閣府が損害保険料率算出機構の2015年度末データに基づいて試算した結果によると、持ち家世帯の火災保険加入件数は2,880万件、加入率は82%(未加入率は18%)でです(建物が補償対象とされている火災保険に関して集計)。
住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、金融機関から火災保険への加入を求められることもあり、持ち家世帯の多くは火災保険に加入しています。
上述した内閣府の試算結果によると、水災補償がセットされた保険への加入件数は2,307万件(加入率66%)です。水災補償に関しては、ハザードマップなどを確認したうえで、必要であれば(洪水などが起こる可能性が高いエリアであれば)セットしましょう。
火災保険への加入は必要か?
上述したように、ご自身が注意していても、近隣の住人が原因で火災が発生するケースがあります。重大な過失がない限り、火元の住人に対して損害賠償を請求できないため、生活再建が困難な状況に陥るかもしれません。
2022年の年間出火件数は36,314件(1日あたりの件数は99件)です。毎日、どこかで火災が発生しているため、万が一の事態に備えて火災保険に加入しておきましょう。なお、住宅ローンを組んで住宅を購入する場合は、金融機関から火災保険への加入を求められます。
賃貸住宅に住む場合も火災保険への加入は必要か?
持ち家ではなく賃貸住宅に住む場合でも、火災保険への加入は必要です。なお、家主と賃貸借契約を締結する際に、以下の3つに加入することを求められるケースが多く見受けられます。
・家財を補償対象とする火災保険
・借家人賠償責任保険
・個人賠償責任保険
借家人賠償責任保険とは、入居者が火災・爆発・漏水などを引き起こして貸主に対する損害賠償責任を負った場合に、建物を原状回復するための費用が補償される保険です。火災保険の特約としてセットするもので、単体では加入できません。
個人賠償責任保険とは、日常生活で過失により他者を死傷させたり、他者の所有物を破損してしまったりして(たとえば、水漏れを引き起こして階下の住人に被害を与えて)、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険です。借家人賠償責任保険と同様に、火災保険の特約として加入します。
火災保険の保険料を抑える方法
火災保険の補償範囲を広く設定すると、保険料が割高になることにご留意ください。保険料を抑えたいのであれば、補償範囲を絞り込みましょう。たとえば、ハザードマップをチェックして、水災リスクが小さいことが判明した場合は、水災に関する補償を外すこともご検討ください。
高価な家財を保有していない場合は、家財に関する保険金額を小さくすることも保険料の抑制につながります。また、複数の保険会社のから資料を取り寄せたり、公式サイトを閲覧したりして、保険料を比較することも大切です。補償範囲や保険金額が同じであっても、保険会社ごとに保険料が異なります。
さらに、保険会社によっては保険料を一括で支払うと割引を受けられるケースもあるので、資金に余裕がある方は一括で支払ってはいかがでしょうか。
火災保険の保険料を支払った場合、控除を受けられる?
そのため、
火災保険の保険料を支払った場合も、控除を受けられるのではないか
とお考えの方がいるかもしれませんが、火災保険の保険料を支払っても、原則として控除を受けられないことにご留意ください。
火災保険とセットで加入する場合がある地震保険の保険料に関しては、地震保険控除の対象とされます。
日本では定期的に巨大地震が発生するため、地震保険にも加入しておくことを検討しましょう。
なお、経過措置として、満期返戻金などがある10年以上の長期火災保険(旧長期損害保険)に2006年末までに加入した方は、地震による損害部分の保険料に関して、地震保険料控除を受けられる可能性があります。
火災などの被害に備えて火災保険への加入を検討しよう
ご自身が注意していても、近隣住民の不注意・過失によって火災が発生する場合があります。その結果、ご自身の建物・家財が損害を受ける可能性があるため、万が一の事態に備えて火災保険に加入しておきましょう。
火災保険に加入しておけば、火災だけではなく、落雷・雪災・風災・水災などによる損害の補償も受けられる場合があります。
なお、同じ補償内容であっても、保険会社によって保険料が異なるケースがあることにご留意ください。各社の公式サイトを閲覧したり、資料を取り寄せたりして、保険料などを比較したうえで契約することをおすすめします。