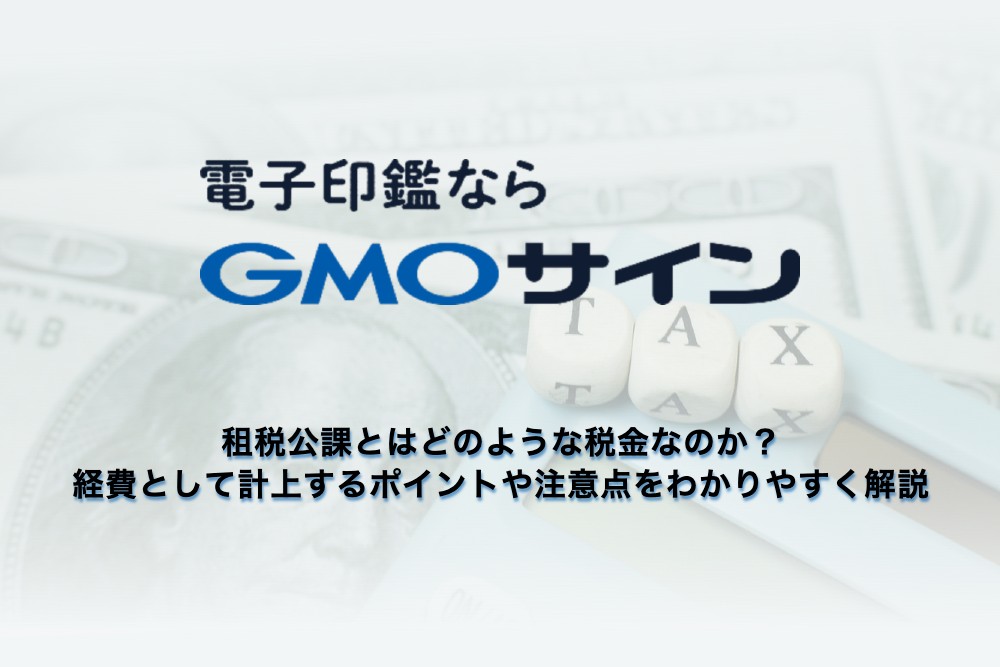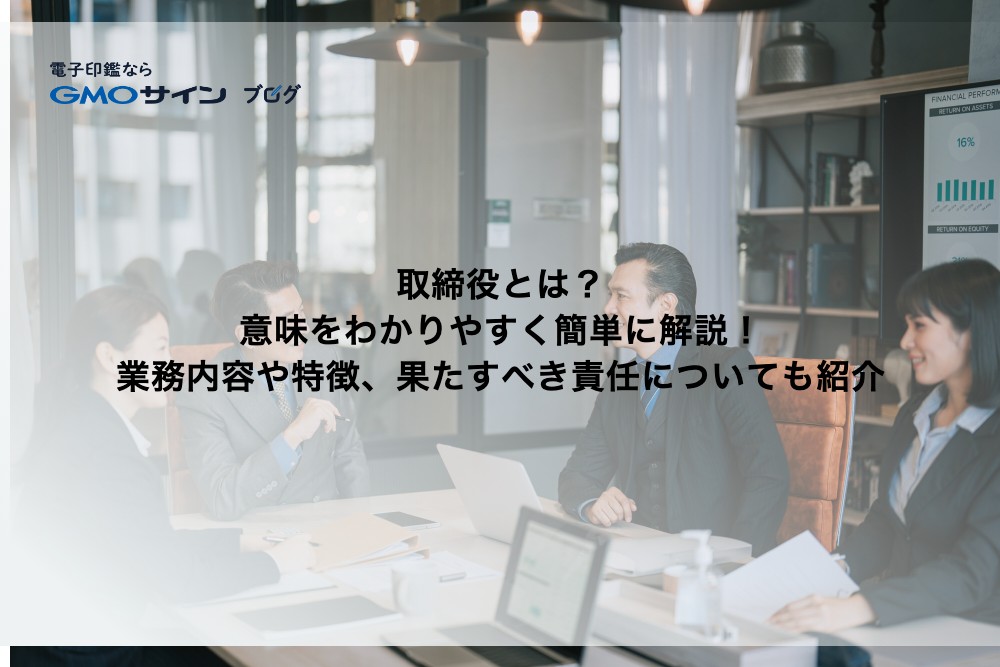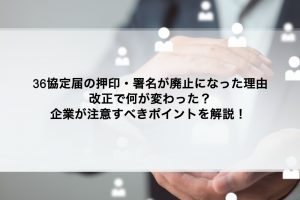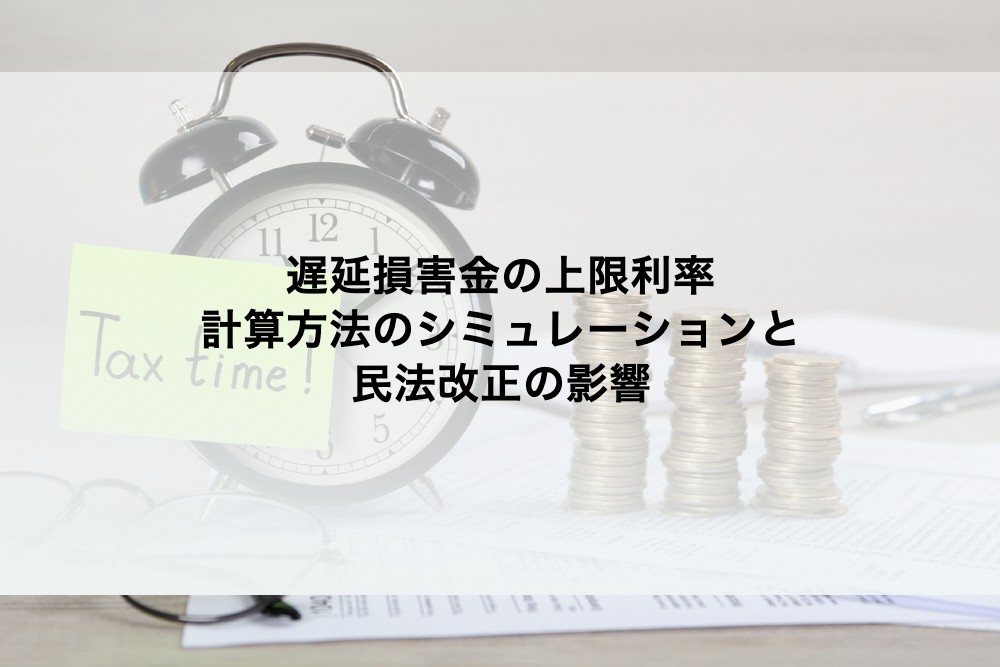法人や個人事業主には、租税公課という税金が課せられます。租税公課は税金として経理処理するときには経費として計上できる場合がありますが、経費として認められないケースもあります。
そこで本記事では、租税公課の概要や経費計上できる項目、申告するタイミングなどについて詳しく解説します。租税公課や税金の処理について気になる方は、ぜひご覧ください。
租税公課とは
租税公課とは、「公租公課」とも呼ばれる勘定項目の1つです。租税公課という1つの勘定項目に計上するわけではなく「租税」と「公課」に分けて計上します。
租税とは
租税とは、国や地方自治体へ納める税金の総称です。法人に対してかかる各種税金は、どれもこの租税項目で仕訳します。
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 自動車税
- 登録免許税
- 事業所得税
- 都市計画税
- 地価税
- 印紙税など
こうした税金はすべて租税に該当します。
公課とは
公課は税金という位置づけではなく、手数料や会費といった位置づけの費用が該当します。たとえば、国や地方自治体から各種証明書を発行してもらう際に発行にかかる費用は、公課に仕訳されます。また行政サービスを受けるときには手数料が発生しますが、その手数料も公課へ仕訳されます。
税金を納付する場合には租税という取り扱いとなりますが、税金の遅延などで罰金が発生した場合には、その罰金は公課に分類しなければいけません。具体的には、延滞税や過怠税、不納加算税などが該当します。
経費計上できる租税公課の項目
租税公課は、項目によって経費として計上できるかどうか区分されます。経費計上できる項目には、おもに事業を運営するうえで必要と見なされるものが対象となりますが、判断基準が複雑なので詳しく解説します。
また法人と個人事業主では扱いが異なるケースが多いので、その点もご紹介します。
法人事業税
法人事業税とは、法人が拠点としている自治体に支払う地方税です。事業の所得に対してかかる税金ではなく、事業そのものに対して発生する税金となっています。
法人の場合、法人事業税は租税公課として経費計上できます。しかし、公益性が高い公共法人では法人事業税は課税対象とならず、経費として計上されません。
また、個人事業主の場合に課される法人事業税は「個人事業税」とも呼ばれており、課税対象となる業種が法律によって定められています。地域によって対象となる業種は若干異なりますが、おもに70程度の業種が対象となっています。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業 |
| 運送取扱業 | ||
| 料理店業 | ||
| 遊覧所業 | ||
| 保険業 | ||
| 船舶定係場業 | ||
| 飲食店業 | ||
| 商品取引業 | ||
| 金銭貸付業 | ||
| 倉庫業 | ||
| 周旋業 | ||
| 不動産売買業 | ||
| 物品貸付業 | ||
| 駐車場業 | ||
| 代理業 | ||
| 広告業 | ||
| 不動産貸付業 | ||
| 請負業 | ||
| 仲立業 | ||
| 興信所業 | ||
| 製造業 | ||
| 印刷業 | ||
| 問屋業 | ||
| 案内業 | ||
| 電気供給業 | ||
| 出版業 | ||
| 両替業 | ||
| 冠婚葬祭業 | ||
| 土石採取業 | ||
| 写真業 | ||
| 公衆浴場業(むし風呂等) | ||
| 電気通信事業 | ||
| 席貸業 | ||
| 演劇興行業 | ||
| 運送業 | ||
| 旅館業 | ||
| 遊技場業 | ||
| 第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業 |
| 水産業 | ||
| 薪炭製造業 | ||
| 第3種事業 (30業種) | 5% | 医業 |
| 歯科医業 | ||
| 薬剤師業 | ||
| 獣医業 | ||
| 弁護士業 | ||
| 司法書士業 | ||
| 行政書士業 | ||
| 公証人業 | ||
| 弁理士業 | ||
| 税理士業 | ||
| 公認会計士業 | ||
| 計理士業 | ||
| 社会保険労務士業 | ||
| コンサルタント業 | ||
| 設計監督者業 | ||
| 不動産鑑定業 | ||
| デザイン業 | ||
| 諸芸師匠業 | ||
| 理容業 | ||
| 美容業 | ||
| クリーニング業 | ||
| 印刷製版業 | ||
| 歯科衛生士業 | ||
| 歯科技工士業 | ||
| 測量士業 | ||
| 土地家屋調査士業 | ||
| 海事代理士業 | ||
| 公衆浴場業(銭湯) | ||
| その他の医業に類する事業 | ||
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 | |
| 装蹄師業 |
固定資産税
固定資産税とは、土地や家屋などの不動産、そして建物などの償却資産に対して発生する税金です。法人の拠点となる建物は事業の運営にとって必須なので、経費として計上が可能です。
ただし、個人事業主では自宅の一部を事務所として兼用しているケースも見られます。そのような場合には床面積を計算して、ビジネスのために使用している割合を出したうえで、固定資産税を部分的に経費として計上します。
自動車に関する税金
自動車を所有している場合には、購入時に発生する自動車取得税をはじめ、車検で必要な自動車重量税や毎年発生する自動車税など様々な税金がかかります。これらの税金は事業の運営に対して必須として考えられるため、経費計上が可能です。
しかし、個人事業主では自動車の使用はどこまでが事業運営に必要なのか見なされる基準が異なる傾向がありますので、注意が必要です。
経費計上するタイミングについて
租税公課には多種多様な項目が含まれており、それぞれ経費として計上するタイミングが異なります。計上するタイミングは、以下の3つの申告方法で決まります。
- 申告納税方式
- 賦課決定方式
- 特別徴収方式
それぞれの方法について詳しく解説します。
申告納税方式
申告納税方式とは、法人などの納税義務者が自ら税金を計算した上で納付すべき金額が申告で確定する方法です。この方法で納税する租税公課には、事業税や事業所税、消費税などが挙げられます。
この方式で納税する場合には、経費を計上するタイミングは申告した事業年度となります。
賦課決定方式
賦課決定方式とは、国や地方自治体が税額を決定した上で通知された税額を納める方法です。この方法で納税する租税公課には、自動車税や固定資産税、不動産取得税などが挙げられます。
この方式で納税する場合には、経費を計上するタイミングは賦課決定が行われた日の事業年度となります。
特別徴収方式
特別徴収方式とは、納税義務者が事業者経由で間接的に税金を徴収する方法です。この方法で納税する租税公課には、軽油引取税や入湯税、ゴルフ場の利用税などが挙げられます。
この方式で納税する場合には、経費を計上するタイミングは納入申告書を提出した事業年度となります。
税金納付が翌年度になった場合の未払い租税公課は、未払金として処理できる
税金の納付は必ずしもその事業年度に行うとは限らず、場合によっては税金の納付が翌年度になってしまうケースもあるでしょう。特に賦課決定方式で納税する租税公課は、納付の期日が分割される場合があります。この場合には未払いの租税公課という位置づけとなってしまいます。
また租税公課として損金算入ができない税金の未払いに関しては、借方に法人税といった科目を計上したうえで、貸方には現金未払金という科目を計上しましょう。
租税公課に該当しても、経費計上できない項目
租税公課の中には、経費計上が認められていない項目もあり、おもに以下の項目が挙げられます。
- 所得に対して発生する税金
- 罰則的な税金
それぞれ詳しく解説します。
所得に対して発生する税金
法人や個人事業主などが稼いだ所得に対する税金は、経費として計上できません。具体的には、法人税や地方法人税、法人都道府県民税などが挙げられます。
これらの税金は所得に対して発生しますので、事業の運営に必要な税金ではないことから対象にならないと考えられています。
罰則的な税金
納付が遅れたことによって発生する罰則的な税金も、経費となりません。具体的には、延滞税や過怠税、不納付加算税などが挙げられます。
これらの税金は経費として計上できてしまうと、懲罰としての目的が薄れてしまうから対象外になるとされています。
消費税の扱いには要注意
法人が納付するおもな税金の一つとして、消費税が挙げられます。しかし、消費税はあらゆる品目に課せられる税金であるため、自社でどのように扱うかで大きく経理処理が異なります。
そこで、消費税を税込または税抜で計算した場合の経理処理についてご紹介します。
消費税分の費用を負担している場合には経費になる
消費税込みの値段で処理している場合には、経費として計上できます。このように消費税を負担している場合には、仕訳で消費税の取り扱いを分ける必要がないため、処理が簡素化できるメリットがあります。
しかし、消費税の額を把握できないうえに、収益や費用などにもすべて消費税が含まれているため、必ずしも正確な損益が示されるわけではない点がデメリットといえます。
税抜処理は経費にならない
一方、税抜で経費処理している場合には、消費税を経費として計上することはできません。この場合、消費税の区分には「借受消費税」や「仮払消費税」といった勘定項目を使うケースが多いです。
この方法では損益の正確性が担保しやすいメリットがありますが、仕訳を「税抜金額」と「消費税額」に分けなければならないため計算に手間がかかるデメリットがあります。
租税公課に関するよくある質問
租税公課とは具体的に何ですか?
租税公課とは、法人や個人事業主が国や地方公共団体に納める税金や公的な負担金の総称です。具体的には、固定資産税、自動車税、印紙税、事業所税などが含まれます。これらは事業活動を行う上で避けられない費用であり、会計上は「租税公課」という科目で処理されます。
ただし、所得税や法人税は利益に対してかかる税金なので租税公課には含まれず、別途「法人税等」という科目で処理します。また、消費税も原則として租税公課には含まれません。
租税公課に気をつけて、きちんと経理処理しましょう
租税公課は経費計上するタイミングが異なったり、消費税の扱いが難しかったりするなど扱いに困るケースが多いです。
しかし、適切に処理しなければ税務署から調査が入る可能性がありますので、厳密な処理が求められます。本記事では租税公課の処理で困りがちなケースについてご紹介しましたので、お困りの際はぜひお役立てください。