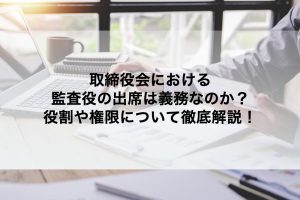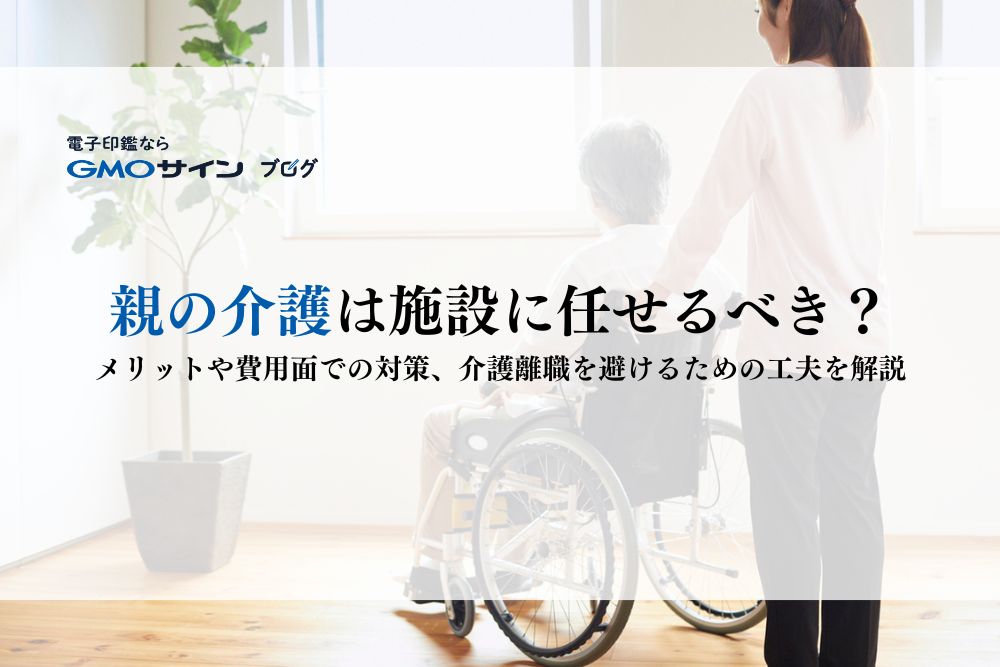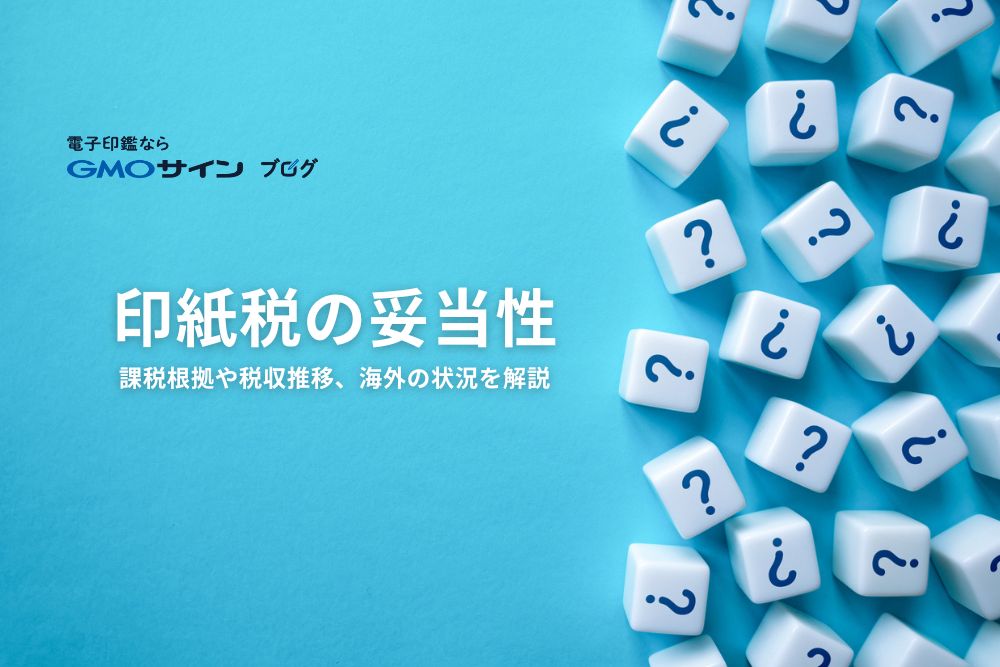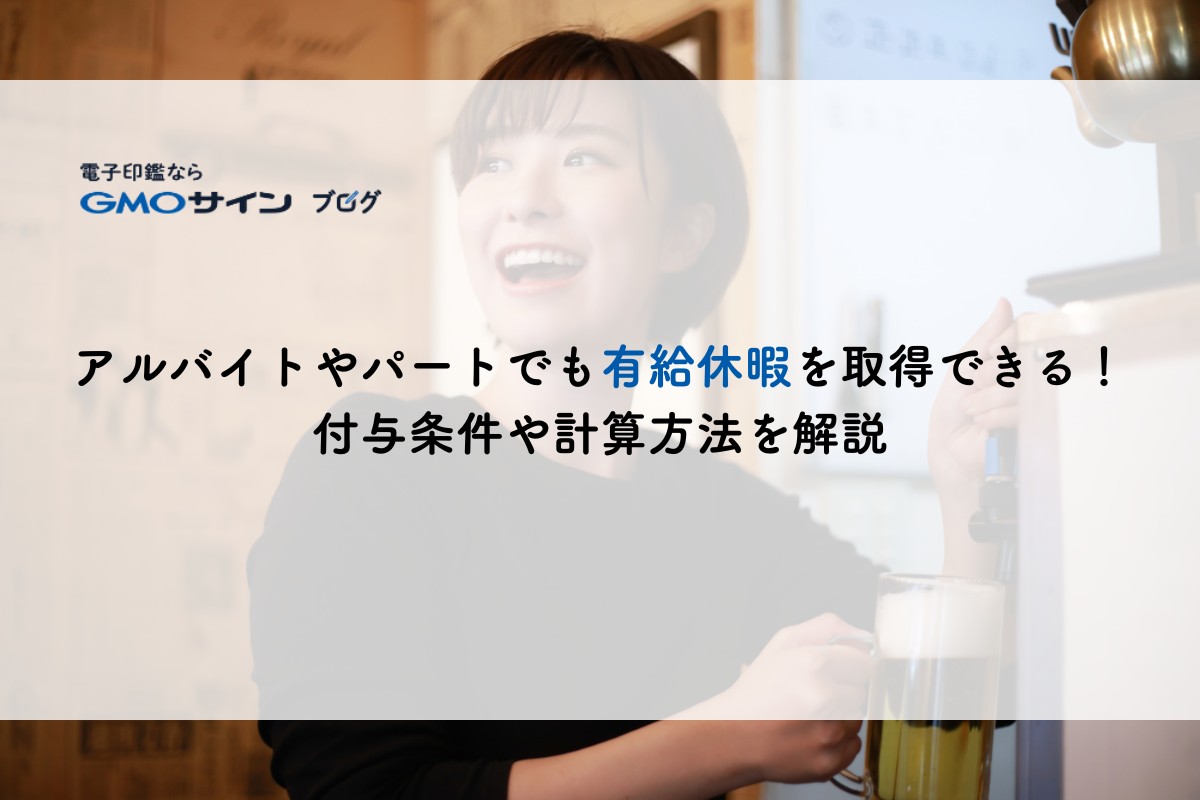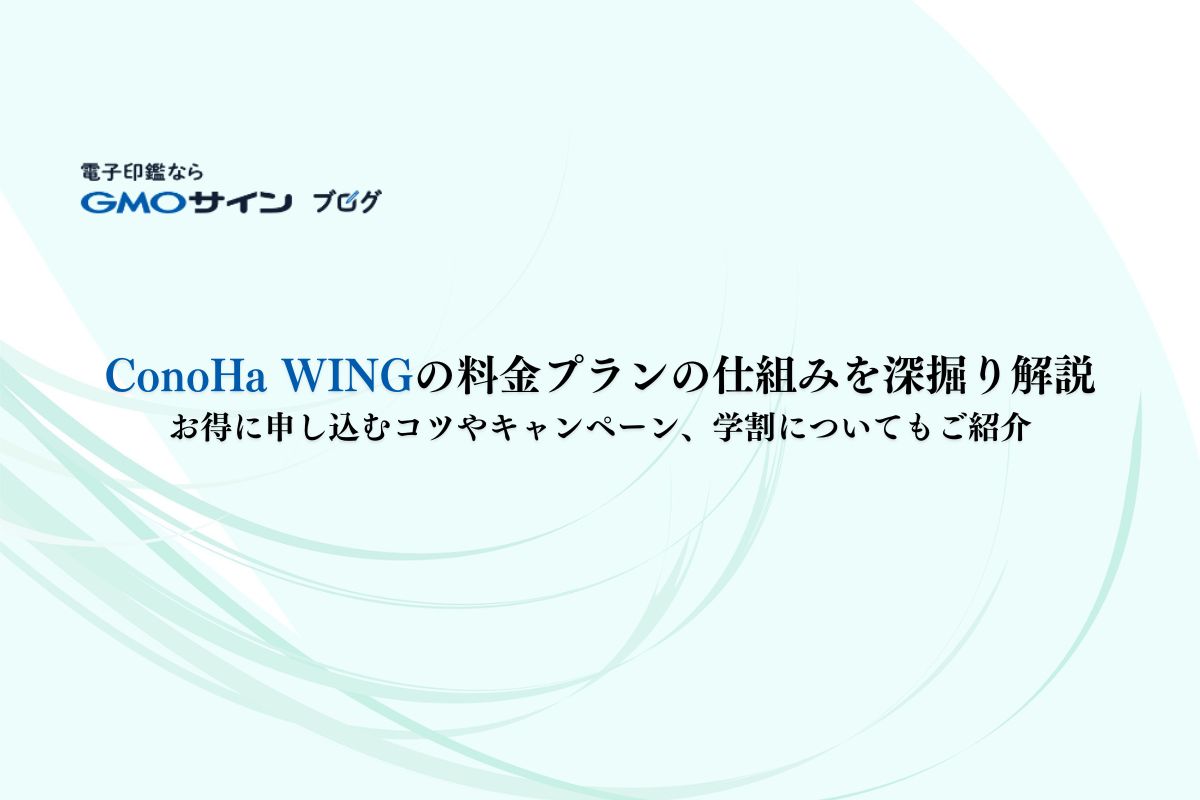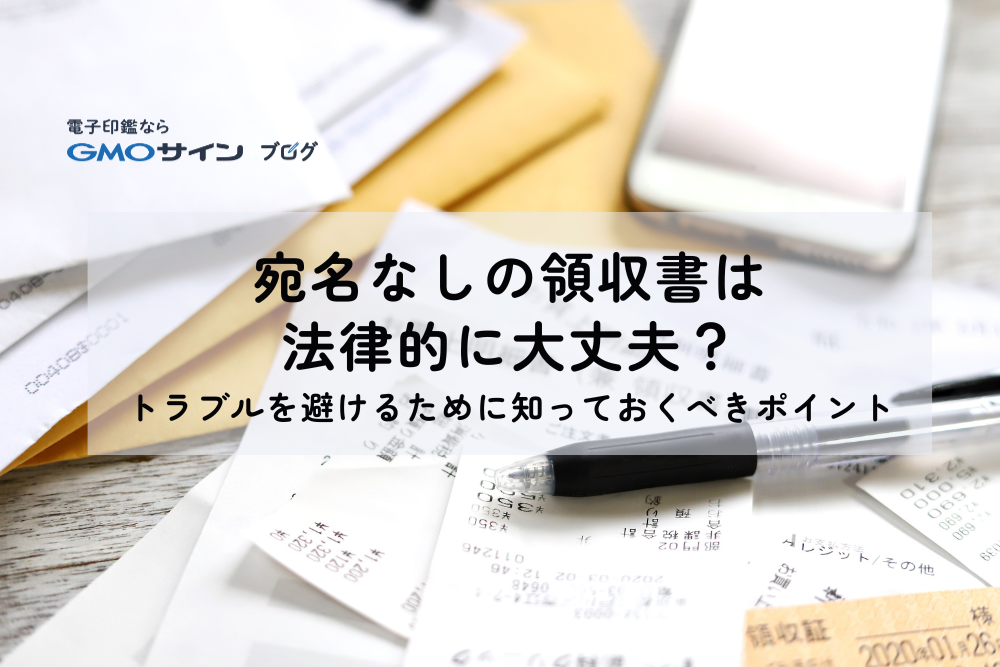企業を経営するには、利益を出さなければ活動を続けることはできません。また利益を出すためには売上を伸ばせばよいなど大まかな見当をつけられても、具体的な数値目標を示せなければモチベーションにつながりません。
そこで役立つのが、損益分岐点による合理的なビジネスプランの作成です。本記事では損益分岐点やその計算方法、具体的な使い方について詳しく解説します。
「損益分岐点」とは
損益分岐点とは、売上や費用を計算した上で損益が利益にも損失にもならないゼロになる分岐点を指します。そのため損益分岐点を知っておけば、どのぐらいの売上を出せば収益がプラスになるかマイナスになるのか把握できます。
また企業の売上は、売上高のすべてが利益となるわけではありません。そこからさまざまな費用を差し引いた額が利益となりますので、具体的にどんな費用が売上から差し引かれるのか解説します。
固定費
固定費とは、売上に関係なく毎月必ず発生する費用を指します。具体的には、オフィスの家賃や設備のリ-ス料金、人件費や広告宣伝費などが含まれます。
変動費
変動費とは、売上が多くなることでかかるコストが増え、売上が減ればコストも下がるといった特性を持つ費用です。具体的には、仕入れの原価や原材料費、販売手数料や外注費などが挙げられます。
損益分岐点の計算方法
損益分岐点は、以下の式で計算します。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益 × 売上高
限界利益とは、売上高から変動費を差し引いた指標です。おもに1個の商品を販売することでどのぐらいの固定費を回収できるかという指標として利用されています。
たとえば、オレンジを1個60円で仕入れて100円で販売するとしましょう。このオレンジの限界利益は、販売価格100円から仕入れ価格の変動費60円を差し引いた40円となります。
また同じ企業において、毎月の固定費が30万円かかるとします。この固定費30万円を回収するためには、限界利益40円のオレンジを何個販売しなければいけないのでしょうか?
計算は「30万円 ÷ 40円 = 7,500個」となりますので、この場合に利益を出すなら、オレンジは毎月7,500個以上売ればよいということになります。また毎月7,500個のオレンジを販売するためには売上の話となり、販売価格が100円なので7,500個×100円=75万円となることから、損益分岐点売上高は75万円とわかります。
「損益分岐点比率」とは
損益分岐点比率とは、一定期間内における企業の売上高と損益分岐点売上高、つまり利益がゼロになる売上高の比率を数値化したものです。算出された比率によって、その企業が持つ体力的要素を客観的に把握できます。
また損益分岐点比率は、以下の式で算出されます。
損益分岐点比率 = 損益分岐点売上高 ÷ 実際の売上高 × 100
損益分岐点比率が高い企業は、売上高とコストの差がそれほどなく、赤字に転落しやすい企業だと考えられます。一方損益分岐点比率が低い企業は安定した売上高であり、コストも低く抑えられているため、優良企業といえるでしょう。
損益分岐点比率の目安
優良企業に分類できる損益分岐点比率の目安は「60%」です。また60~80%でもかなり経営が安定している企業といえます。80%を超えている場合は注意が必要です。
ほとんどの企業における損益分岐点比率は、80~90%程度です。90%を超えると損益分岐点付近をさまよっている状況であることから、赤字転落のリスクが高いといえます。
損益分岐点比率の算出例
上記のオレンジ販売会社を例にして、損益分岐点比率を計算してみましょう。この企業の損益分岐点売上高、つまり利益を出すために必要な売上高は75万円でした。もしこの企業の実際の売上高が150万円あるならば、この企業の損益分岐点比率は、「75万円 ÷ 150万円 × 100 = 50%」となり、体力面ではかなり優秀な優良企業に分類できます。
しかし、この企業の実際の売上高が90万円の場合には、損益分岐点比率は「75万円 ÷ 90万円 × 100 = 83%」となり、一般的な企業と判断されます。このように、損益分岐点比率は自社の売上状況の把握に役立つのです。
経営状況の把握で使われる「安全余裕率」とは
安全余裕率という指標も、経営状況の把握で使われます。安全余裕率とは、実際の現在の売上高を100%という基準にして、売上高と損益分岐点の差がどのぐらいあるのかというギャップを示した指標です。
安全余裕率の算出方法
安全余裕率は、以下の式で算出されます。
安全余裕率 =(実際の売上高 - 限界売上高)÷ 実際の売上高 × 100
安全余裕率の算出例
上記の例で限界売上高が75万円、実際の売上高が90万円のオレンジ販売会社から、安全余裕率を計算してみましょう。この場合には、安全余裕率は以下のようになります。
安全余裕率 =(90万円-75万円)÷ 90万円 × 100 = 16%
つまり、このオレンジ販売会社では、売上が現在よりも16%落ちると赤字に転落してしまうことを表しています。安全余裕率を使えば、売上がどれくらい落ちると赤字になるのか具体化できるのです。
損益分岐点を分析するメリット
損益分岐点は、事業を運営して利益を出す場合には絶対に知っておかなければいけないマストな数値といっても過言ではありません。具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 利益を出すために必要な売上高が分かる
- 利益率をあげるためにいくらの売上アップが必要なのか分かる
それぞれ詳しく解説します。
利益を出すために必要な売上高が分かる
損益分岐点を算出しておけば、かかる費用を差し引いても利益を残すためには、どのぐらいの売上が必要なのか明確な数値として把握できます。大まかな計算でビジネスを経営するのではなく、具体的な数値にもとづいた合理的な計算を行えば、リスク管理や売上アップなども根拠がある明確な内容に設定しやすくなるでしょう。
利益率をあがるためにいくらの売上アップが必要なのか分かる
企業では「利益率を〇%アップしよう」といった目標を掲げることはよく見られます。そのような場合には、損益分岐点を把握することで「利益率をこのぐらいアップするなら売上はこのぐらいアップしなければいけない」というように売上などの項目に具体化して紐づけられます。
また売上目標に対して損益分岐点を使う分析方法は、おもに製造業で採用されています。なぜなら損益分岐点の計算には変動費と固定費が必要で、製造業ではこの二つの費用を把握しやすいことが理由と考えられます。
ほかの業種でも、変動費と固定費を把握できる企業ならば、損益分岐点を使った目標設定や目標売上高の分析を行いやすいでしょう。
損益分岐点を下げることは利益アップにつながる
損益分岐点は、毎月かかる固定費と変動費によって決定されます。損益分岐点を下げることはコストを低く抑えるということなので、企業の利益率アップにつながることが期待できます。そこで、損益分岐点を下げるための方法をお伝えします。
変動費を下げる
売上によってかかるコストが変わる変動費を下げるためには、材料費や外注費などを見直すとよいでしょう。たとえば発注先を見直したり、発注している数量に無駄がないかどうかをチェックしたりする方法がおすすめです。
必要ないものを買い控えて、より高品質の材料を低価格で仕入れられないかと常に模索することは、変動費を下げる対策としては効果的です。
また多くの企業が効果的だと実感している方法は、仕入れ単価を下げることです。具体的にはまとめ買いによって単価を下げてもらったり、数回取引した後に単価交渉したりする方法などが挙げられます。
固定費を下げる
固定費は、売上に関係なく毎月必ず発生する費用です。そのため固定費は下げられないと考えている企業は少なくありません。しかし、固定費でも工夫次第で下げることが十分に可能です。
まず広告宣伝費に関しては、広告をより効率的かつ効果的に打ち出すための方法を常に検証しましょう。
広告宣伝には多種多様な方法がありますが、タ-ゲット層を想定した上で、そのタ-ゲット層に対して最も強く訴求できる方法を時間帯や広告媒体なども含めて検証することが重要です。また、効率的かつ効果的な広告宣伝を実施すれば、費用を抑えつつ売上アップに貢献できるでしょう。
下げにくいイメージがある光熱費も、省エネ器具を採用したり電球をLEDに変えたりするだけで、長期的には大きな効果が期待できます。
人件費の削減について
人件費の削減も固定費を下げることにつながりますが、内容は慎重に検討することが重要です。人件費の削減には給与カットや労働時間の短縮などが考えられますが、社員のモチベ-ションが著しく下がるリスクがあります。
そのため、他の方法から検討することをおすすめします。たとえば外注先の見直しや設備投資による機械化やデジタル化を採用すれば、工数を減らして業務の効率化や人件費の削減につながります。
新しい経営スタイルに合った具体的な方法
昨今では新しい経営スタイルが多くなっていますので、そちらの方法に合わせたコスト削減方法をご紹介します。
基本的には固定費の節約が大事
売上に関係なく発生してしまう固定費は、できるだけ低く抑えるように工夫する必要があります。たとえばオフィス賃貸料などは、一人で起業する場合には自宅をオフィスとして使えばゼロにできます。
また昨今よく見られるテレワ-ク中心の企業でも、バ-チャルオフィスを活用する方法もあります。バ-チャルオフィスなら、住所や電話番号をレンタルできるだけでなく、郵便物の転送や企業登記などにも対応しているという利便性があります。
契約書の作成や管理もポイント
企業を経営する上では、契約書の作成や管理は必須です。従来よく使われていた紙ベースの契約書では、用紙代や切手代、郵送にかかる手間などでコストや時間がかかってしまいます。
そのため、契約書を管理するには電子契約サービスがおすすめです。特に『電子印鑑GMOサイン』では、低価格で便利なサービスを多く実装していますので、あらゆる規模の企業に対応できます。電子上で作成や管理をかんたんに済ませられますので、時間や手間を削減できます。
また本来必要な収入印紙を貼る必要もないので、印紙代の節約や貼り間違えによる過怠税リスクを避けられるメリットもあります。まだ使っていない事業者は、ぜひ導入を検討してください。
損益分岐点を使って経営の合理化を目指しましょう
「売上をこれくらいアップさせよう」と社員に提示しても、根拠がなければモチベーションにつながりません。しかし、損益分岐点などを用いた合理的な説明を行えば、社員にも納得してもらいやすくなります。
ぜひ本記事でお伝えした内容を使って、経営改善にお役立てください。