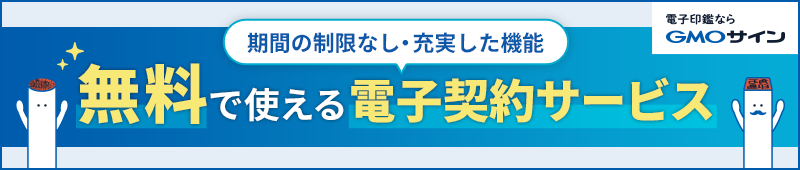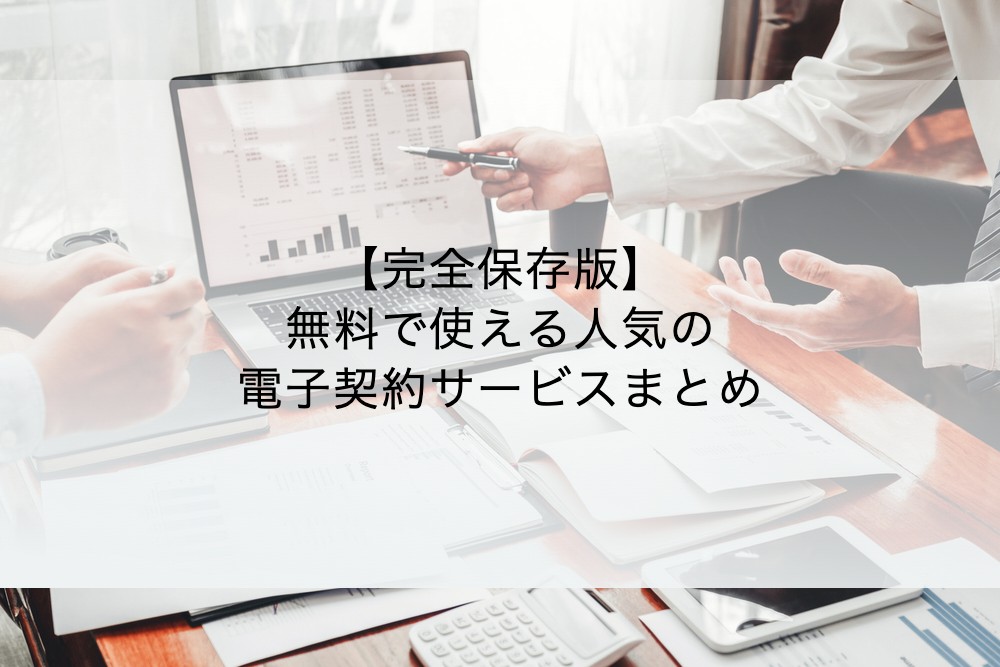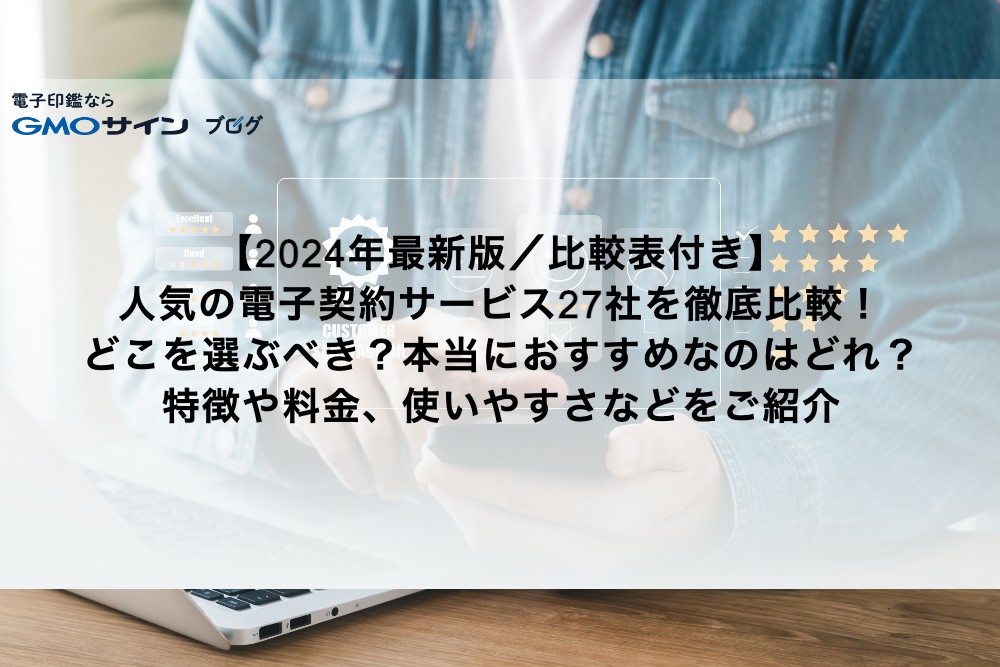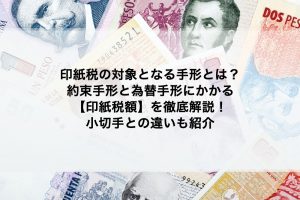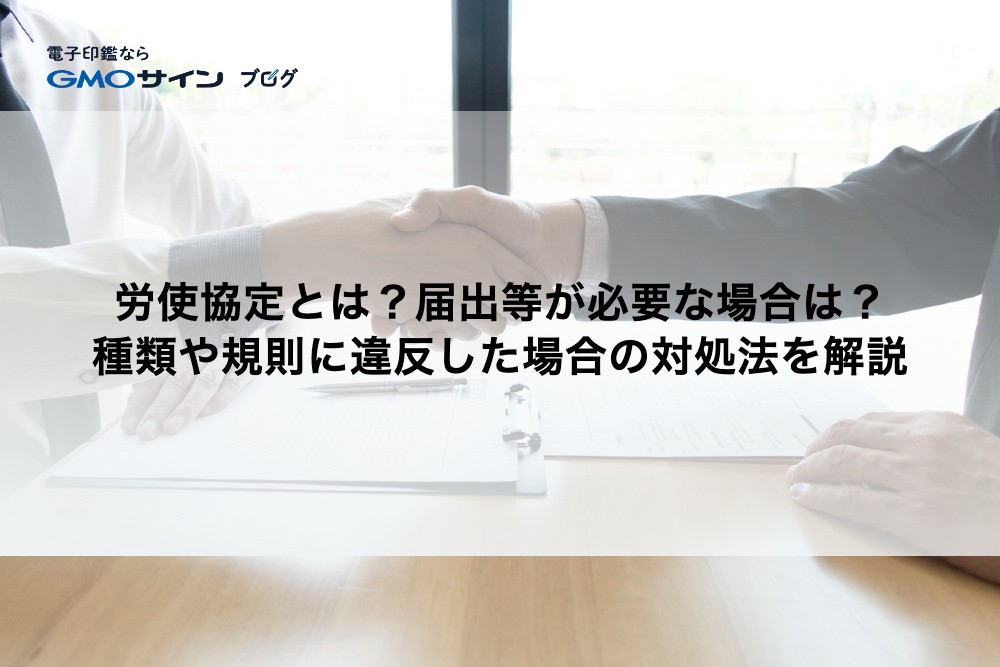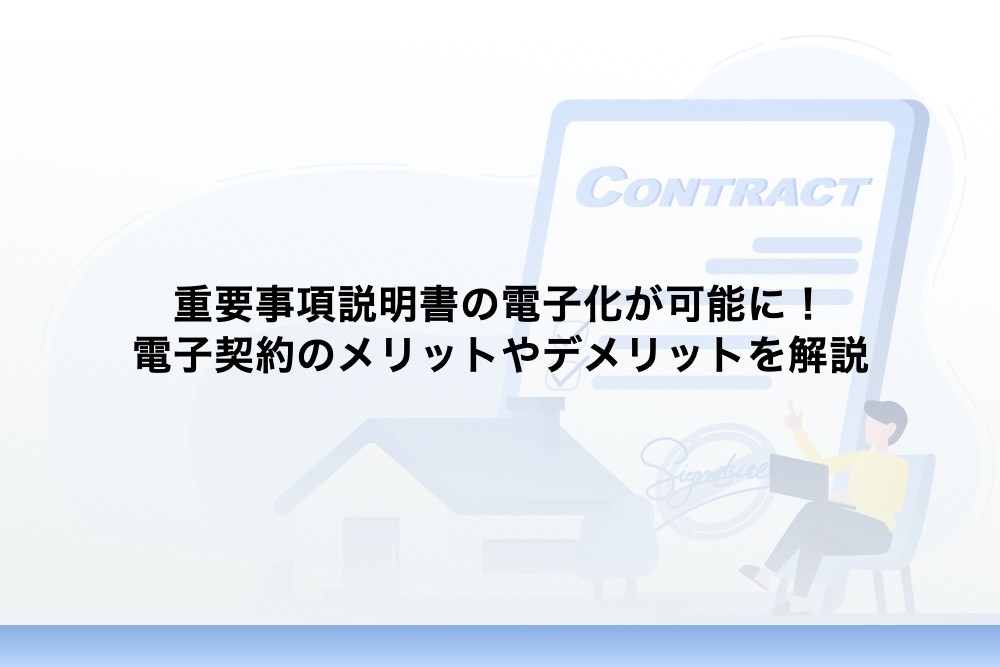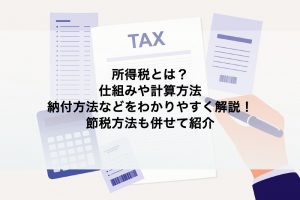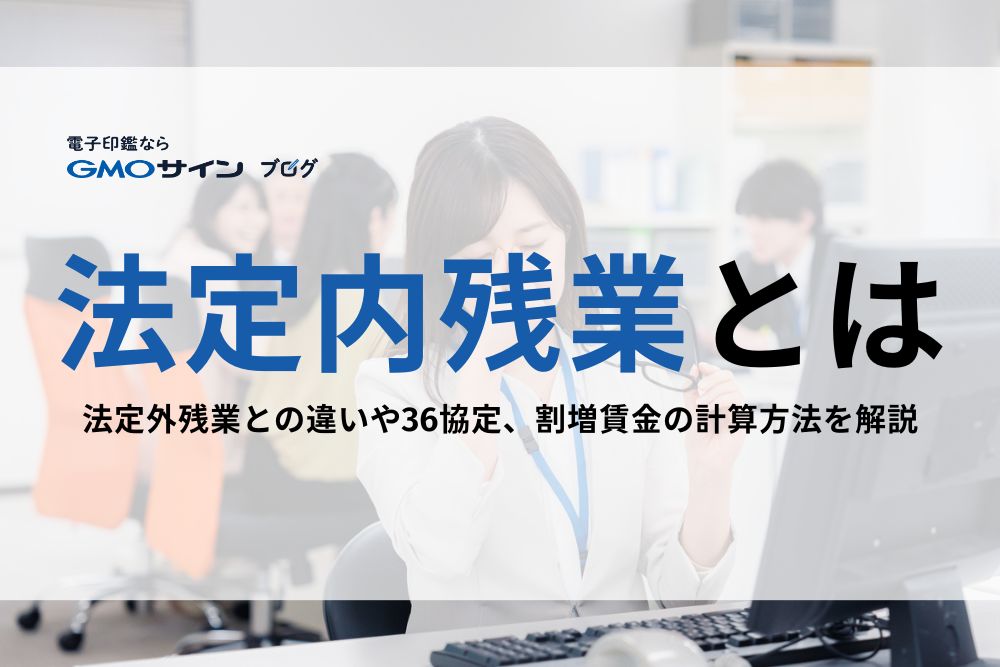企業会計原則とは?財務諸表の作成時に守るべき会計処理のルール
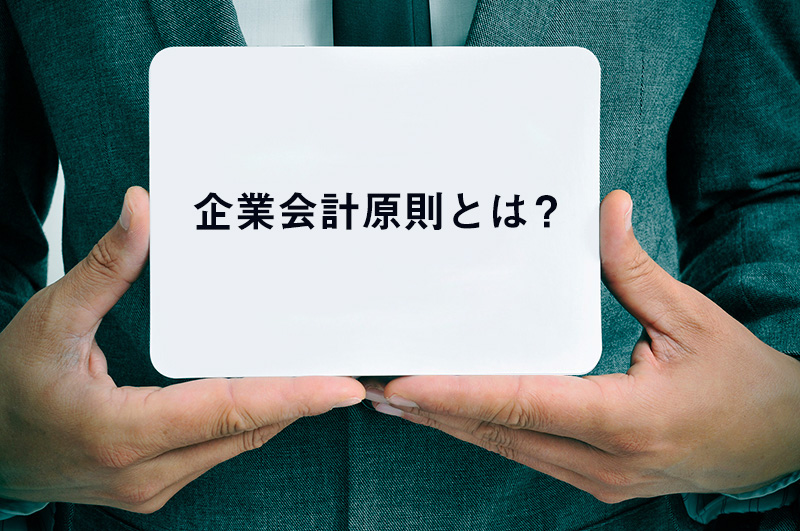
「決算書は、会社にとっての“健康診断書”である」といわれるように、決算書に記載されている内容からは、さまざまな情報を収集することができます。もし、会社によって決算書に書かれている項目や内容が異なると、他社と比較できず、適切な意思決定ができません。そこで、日本会計基準における普遍的なルールとして設けられたのが、「企業会計原則」です。この記事では財務諸表の作成時に欠かせない、企業会計原則について解説していきます。正しく財務諸表の作成ルールを理解して、原則に沿って経理を進めていきましょう。
企業会計原則の概要
企業会計原則は「財務諸表が適切に作成されたものかどうか」を判断する基準となるものです。株主や融資を行う金融機関、投資家などの利害関係者がその会社の実績を正しく評価するためには、欠かせないルールといえるでしょう。

財務諸表は、日本の会計制度の根幹となる企業会計原則に基づき、普遍的・統一的に作成されています。これによって、私たちは対象となる会社の財務諸表を適切に評価したり、複数の企業間での比較を正しく行ったりすることができるのです。
企業会計原則の構成
企業会計原則は「一般原則」、「貸借対照表原則」、「損益計算書原則」の3つから構成されています。ここでは、それぞれの原則について解説していきましょう。
一般原則とは?
一般原則は「包括的原則」とも呼ばれ、企業会計全般における理念や指針を定めるものです。財務諸表を作成する際に共通する「基本的な考え方」を示すものとして、貸借対照表原則や損益計算書原則よりも上位に位置付けられ、一般原則は後述する7つの原則によって構成されています。
貸借対照表原則とは?
次に貸借対照表原則は、貸借対照表を構成する資産や負債、純資産についての会計処理や表示方法に関する基準となるものです。貸借対照表はその企業の「財政状態」を表す重要な役割を持っています。
この原則は、資産と負債を相殺し、貸借対照表の表示から除外してしまうと利害関係者が正しい判断を行えないため、相殺せずに総額で表示しなければならないという「総額主義の原則」などによって構成されています。
損益計算書原則とは?
最後に損益計算書原則は、損益計算書を構成する費用や収益の計上基準や表示方法を、基準として定めています。損益計算書は、その企業の一事業年度における「経営成績」を表しているため、収益や費用を計上するタイミングをそろえなければ、正しい経営成績を把握することができません。そのため損益計算書原則では、費用・収益について発生した時点で計上する「発生主義」を原則としています。
その中でも売上高については出荷基準や検収基準など、販売が実現した段階で収益計上する「実現主義」を基準とすることによって、損益計算書における正しい期間損益の表示を義務付けています。
企業会計原則を理解する上で重要な7つの原則
先述のとおり、企業会計原則の最上位に位置する一般原則は、7つの原則で構成されています。「真実性の原則」、「正規の簿記の原則」、「資本取引・損益取引区分の原則」、「明瞭性の原則」、「継続性の原則」、「保守主義の原則」、「単一性の原則」の7つで、財務諸表を作成する上では、どれも重要な基準となります。では早速、これら7つの原則について、順番に解説していきましょう。

1.真実性の原則
7つある一般原則の中でももっとも重要であり、基本となるものが真実性の原則です。そのほか6つの原則が守られていたとしても、作成される財務諸表がそもそも虚偽の内容であれば意味がありません。真実性の原則では、「貸借対照表や損益計算書が真実に基づいて作成されなければならないこと」を示しています。
2.正規の簿記の原則
正規の簿記の原則では、「網羅性」、「立証性」、「秩序性」の3つを兼ね備えた方法で会計処理を行うことが求められています。「網羅性」はすべての取引が漏れなく記録されていること、「立証性」はすべての取引が客観的な根拠や会計記録に基づいていること、「秩序性」はすべての取引が継続的かつ体系的に記録されていることを、それぞれ要求しています。そして、これら3つの要件を満たすものの代表として、一般的には複式簿記が採用されています。
3.資本取引・損益取引区分の原則
資本取引・損益取引区分の原則では、企業の資本取引と損益取引を混同せず、明確に区分して処理を行うことを規定しています。
特に、資本取引と損益取引はまったく性質の異なるものであり、これを混同してしまうと貸借対照表や損益計算書の内容がゆがめられ、財務諸表の健全性が大きく損なわれる原因となるため、適切な区別が求められています。
4.明瞭性の原則
財務諸表を通じて利害関係者へ適切な企業情報を提供するため、会計事実について誤解を招くことなく、明瞭に表現することを規定するのが明瞭性の原則です。相殺後の金額ではなく総額で表示する総額主義や、財務諸表上、費用と収益の対応関係が明瞭になるように区分や配列を行うことが求められています。
また、貸借対照表や損益計算書に表示されないような事項や後発事象などがあった場合には、個別注記表へ注記し、適切な情報開示を行います。
5.継続性の原則
会計上、複数の会計処理や手続き方法が認められる場合がありますが、継続性の原則では一度採用した処理方法についてみだりに変更せず、継続して適用し続けなければならないと定めています。
例えば、売上の計上基準を毎期変更してしまうと、利害関係者は正しい期間損益を把握することができず、また企業としての利益操作にも悪用されかねません。そのような危険性を排除するために、企業会計処理の一貫性を求める継続性の原則が存在しています。
6.保守主義の原則
保守主義の原則は、将来的に企業へ不利益をもたらす可能性のあるものについて、明確に記録を行わなければならないことを規定しています。企業の抱えているリスクを決算書に表示することで、企業会計としての健全性を担保し、利害関係者にも適切な判断を促すことが可能となります。
保守主義の原則の代表例としては、売掛金などの債権に対する貸し倒れリスクを反映した貸倒引当金の計上が挙げられます。しかし一方で、過度に保守的な会計処理を行うと、企業実体と会計処理に乖離が生じてしまうため、注意が必要です。
7.単一性の原則
単一性の原則は、複数の帳簿を作成することを禁じる規定です。一般的に財務諸表は、株主や金融機関、投資家、税務署などへ提出されますが、提出先によって計算方法や表示方法を変えてはいけません。この原則によって、俗に言う二重帳簿や裏帳簿のような存在を明確に禁止しています。
企業会計原則に照らし合わせ、正しい財務諸表の作成を
企業会計原則は、企業会計において欠かせない原則です。企業会計に携わる方は、企業会計原則の趣旨や目的を理解し、各原則に照らし合わせながら公正妥当な会計帳簿の作成を行うことを心掛けてください。特に、7つの原則から構成される一般原則の重要性は、極めて高いとされています。これらに沿った財務諸表を作成することにより、企業活動の「合理性」や「比較可能性」が担保され、利害関係者からの正当な評価につながっていくでしょう。
<プロフィール>

服部 大(はっとり だい)
税理士
2020年2月30歳のときに名古屋市内で税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界では数少ない若手税理士。単発の税務相談や執筆活動なども行い「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘中。
服部大税理士事務所