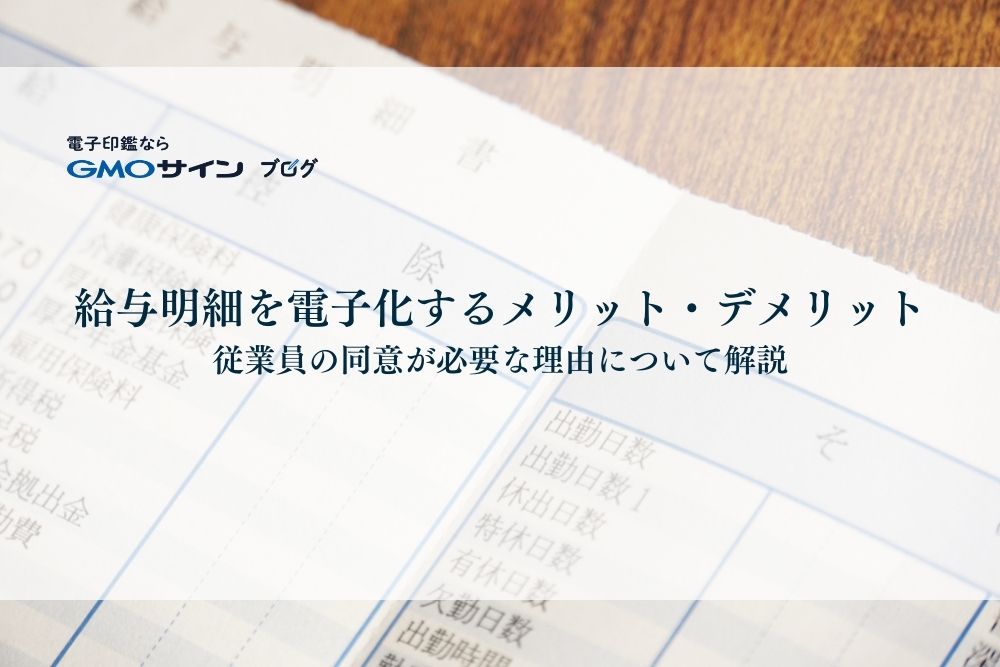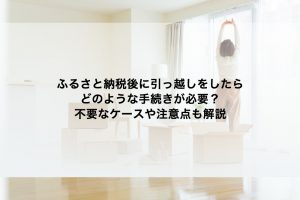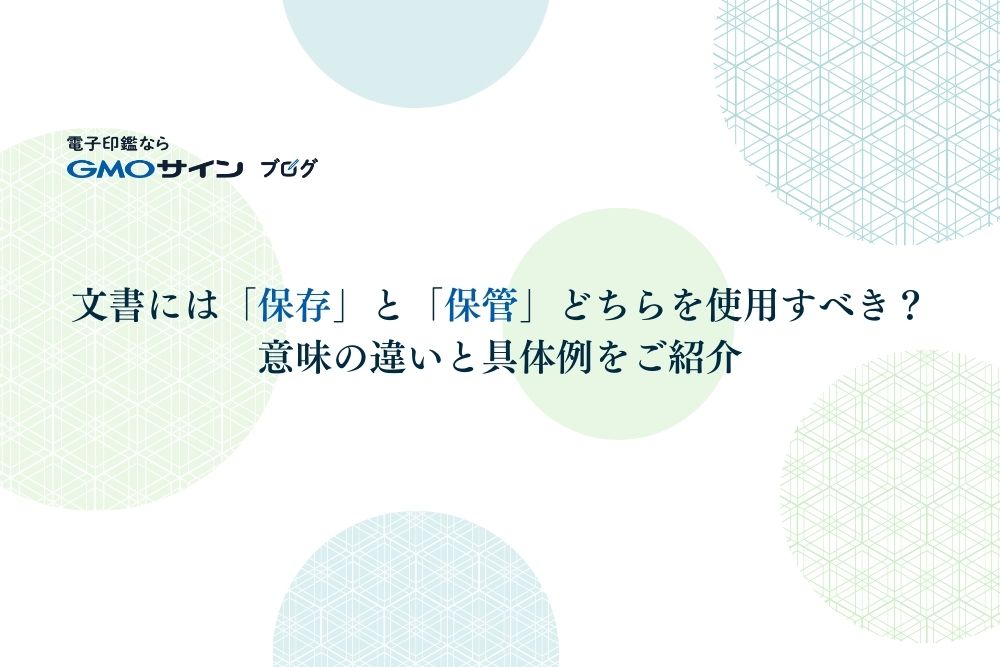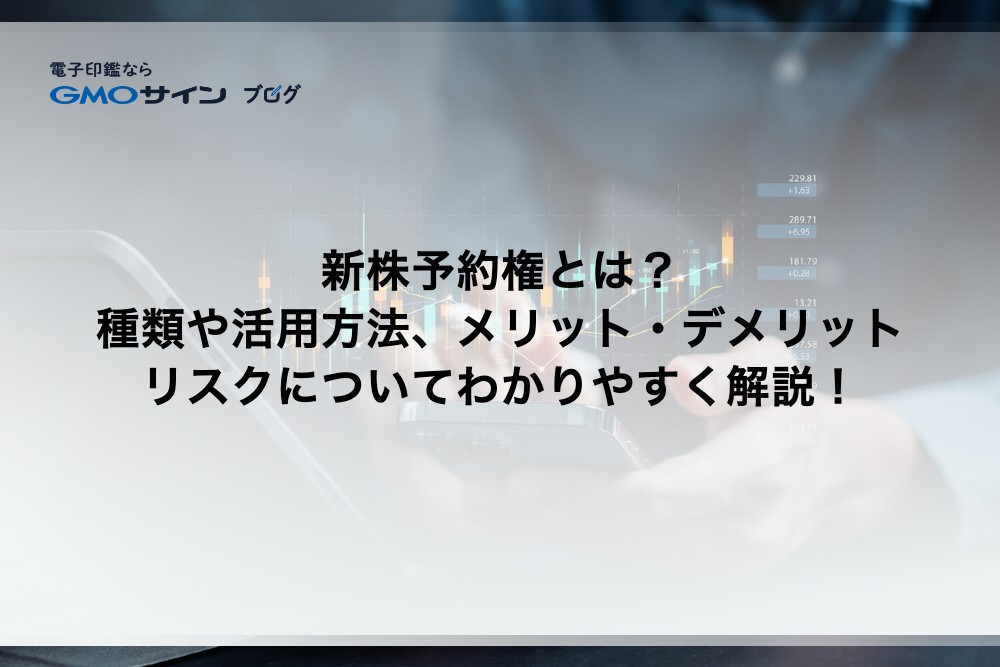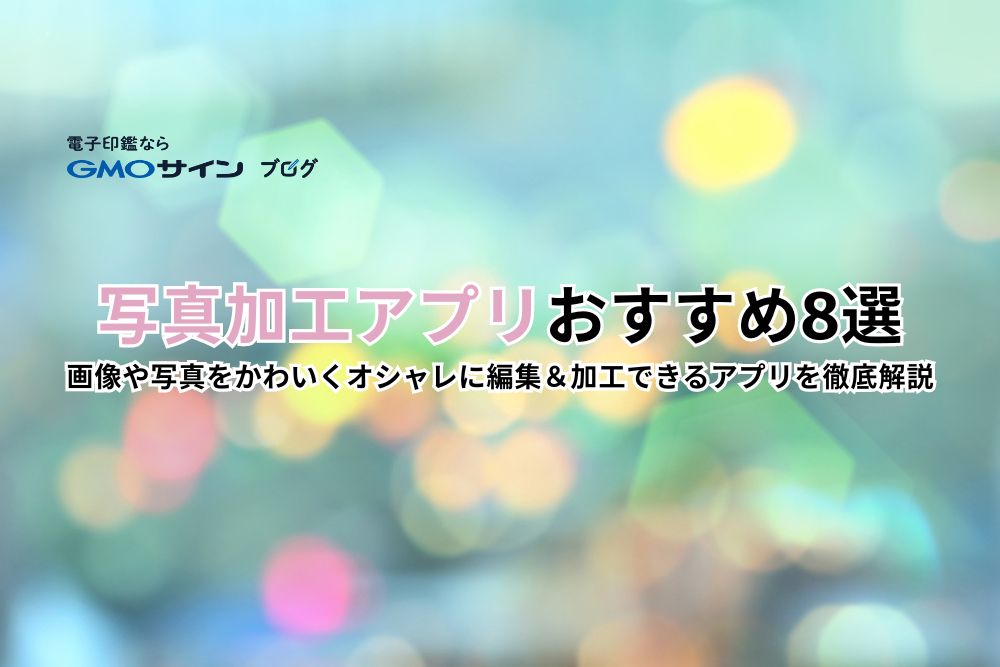\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

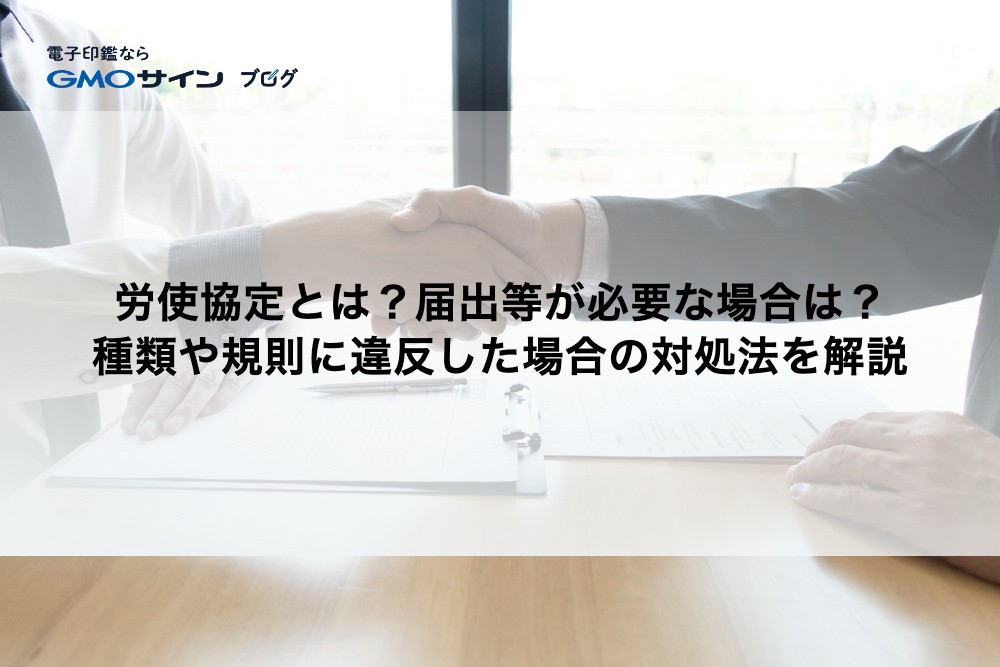
企業や職場では様々なルールが存在しますが、その中でも重要なものの一つに労使協定が挙げられます。労使協定は使用者と労働者ともに欠かせない重要な決め事なので、知らないと日々の働く環境に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
そこで本記事では、労使協定の概要や類似している職場のルール、届出義務、違反した場合の罰則などについて詳しく解説します。
労使協定とは、労働者と使用者との間で決められた約束を書面にして契約した協定を指します。交渉相手の労働者とは労働組合もしくは従業員の過半数の代表者であり、使用者と話し合って協定を締結します。
労使協定の代表的存在が、36協定です。36協定とは、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」であり、労働基準法第36条を根拠にしていることから36協定と呼ばれています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
通常法定労働時間は、1日8時間・週40時間を上限としています。しかし、企業によっては残業や休日出勤が必要なところも多く存在します。
このような場合に備えて、使用者と労働組合または労働者の代表者と書面で36協定を交わします。労使間で締結された36協定行政官庁に届け出れば、労働時間の上限を超えて勤務できます。なお、労働者の代表者とは全労働者のうち過半数の代表ならば問題ありません。
労使協定は、労働協約と混同されがちですので解説します。労働協約とは、労働組合と使用者との間で取り交わされた約束を指します。その内容には、賃金や労働条件、団体交渉、組合活動など様々なルールが盛り込まれています。
労使協定との違いは、締結する当事者です。労使協定は使用者と労働組合もしくは労働者の代表者で締結するのに対し、労働協約は労働組合の組合員が当事者になります。
労働協約は、全体的な職場環境を安定化させるために必要なルールと言えるでしょう。
就業規則とは、労働者が勤務中に守るべきルールを指します。また給与に関する取り決めや労働時間などの条件も盛り込まれています。
就業規則は、常に10人以上の従業員を雇用している企業などに義務付けられています。作成するだけではなく、労働基準監督署に届け出る必要もあります。
労使協定は使用者・労働者側の合意に基づき締結される契約ですが、就業規則は使用者が一方的に定める社内規程です。
労使協定との大きな違いは、その内容です。労使協定は労使間が話し合って労働環境を整えるために決めるルールですが、就業規則は使用者だけで定めた働き方や社内の風紀に関する内容をまとめた規定です。
労使協定は、労働組合もしくは労働者の過半数を代表するものと締結する必要があります。労使協定は使用者と労働者の代表とで交わさないといけないので、労働者の代表者が使用者と懇意であるような場合には不適切と考えられます。
そこで、労働者の代表者には以下のような条件が求められています。
・労働者の過半数を代表している
・管理監督者以外の人物である
・使用者の意向で選出されていない
労使協定にはいろいろな種類がありますが、その中には協定締結が義務付けられたものもあります。その上で届出しなければならないようなものも見られるのです。また、36協定と呼ばれるものは労使協定を締結した上で、労働基準監督署への提出が義務付けられています。一方で特別関係官庁に届け出の必要のないものもあります。
労使協定には36協定など様々な種類があり、中には届出が義務付けられているものもあります。具体的には、以下のものが挙げられます。
・36協定
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
・1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
・事業所外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定
届出を失念しているとトラブルを引き起こす可能性がありますので、それぞれ詳しく解説します。
36協定は、時間外労働や休日労働など法定労働時間を超えて従業員に労働させる場合に必要な労使協定です。労使間で締結した上で、労働基準監督署に届出を行いましょう。ただし、36協定を結べば何時間でも労働させてもいいわけではありません。
時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の方(※)が36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
出典:中小企業主・小規模事業者の皆さまへ サブロク協定をご存知ですか?|厚生労働省(※)具体的には、
①従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は、その労働組合、
②過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表する方【参考】
◆時間外労働の上限は、厚生労働大臣告示において、1か月45時間、1年360時間等とされています。
(これを「限度時間」と言います。)
*ただし、特別条項を締結すれば、年間6か月まで、限度時間を超えて労働させることができます。◆ただし、労働時間を延長する場合には、その時間をできる限り短くするよう努めなければなりません。

上図のように、基本的に1ヶ月45時間・1年間360時間を上限としています。そのため、法律にのっとった勤務時間に収まるように36協定を締結しましょう。
1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に決められる労使協定があり、主に小売業や旅館、飲食店のような業種で締結されます。届出の対象になるのは、30人未満の労働者規模の事業者です。
1ヶ月以内の一定の期間を平均した場合、1日もしくは1週間当たりの法定労働時間を超える働き方が求められる場合に必要な労使協定です。法定労働時間を超えた場合でも、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内になるようにしなければなりません。
ただし、1ヶ月単位の変形労働に関するルールが就業規則に盛り込まれているのであれば、労使協定を届け出なくても問題ありません。
業務の全部もしくは一部を事業場外で行う業務を対象にした労使協定です。使用者の該当する労働時間の算定義務が免除され、事業場外労働については特定の時間労働したとみなせるようになります。
事業場外で労働する場合には当然指揮監督権が及びませので、労働時間の算定が困難になる事態を防ぐために締結されます。
厚生労働省によると専門業務型裁量労働制に該当するのは、以下の19種類の業務です。
出典:専門業務型裁量労働制|厚生労働省労働基準局監督課
仕事の進め方や勤務時間のマネジメントなど労働者の裁量が大きい業務に関して、設定されていた時間を働いたとみなす協定です。
従業員の貯蓄金の管理に関する労使協定です。社内貯金制度などを運用する場合には、労働者と協定を結んで労働基準監督署に届出を行わなければなりません。
使用者と労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものが書面にて労使協定を締結したら、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。届出の方法ですが、窓口に提出、郵送、電子申請の3種類の中から選択してください。
36協定に関しては「36協定届」と呼ばれる用紙がありますので、こちらに必要事項を記入して提出しなければなりません。また2021年4月からは新様式が適用されています。代表者が適任であるかどうかのチェックボックスが新設されました。もし届に不備があった場合にはその労使協定は無効になってしまうので、間違いのないように慎重に手続きを進めていきましょう。
労使協定には、必ずしも届出する必要のないものもあります。届出の必要のない主要な労使協定は、以下の通りです。
・フレックスタイム制に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与
・年次有給休暇の時間単位での付与
・標準報酬日額による支払いの場合
・育児・介護休業等に関する労使協定
・休憩の一斉付与の例外
・法定控除を除く控除を行う場合
それぞれの労使協定について詳しく解説します。
フレックスタイム制を導入する場合には、労使協定を交わしても届出する必要がないケースもあります。フレックスタイム制とは、最大3ヶ月間を清算期間として、平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、その間特定の1日が8時間、1週間で40時間を超えて労働してもよい制度です。清算期間が1ヶ月以内であれば、労使協定の届出が不要になります。
年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇の日数の中で5日超の部分は特定の時季に与えられる制度です。特定の時季は、労使間の話し合いによって決定します。
年次有給休暇の付与する単位は、原則1日です。しかし、労使協定を締結すれば、年5日を上限として時間単位での有給休暇の付与も可能です。
年次有給休暇中の賃金を支払うにあたって、標準報酬日額をベースにする場合には労使協定を交わす必要があります。実際の賃金との間でズレが生じるので、労使協定が必要になるのです。
育児休業や看護休暇、介護休業ができない労働者の範囲に関する規定が盛り込まれた労使協定も届出が不要です。しかし、労使協定を締結すれば範囲を自由に設定できるわけではなく、育児・介護休業法第6条によって以下のように定められています。
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov法令検索
原則休憩を与える際には、全労働者一斉に付与しなければなりません。もし一斉付与できない事情があれば、労使協定を締結して一斉付与の特定の条件における適用除外ができるようにしておかなければなりません。
法定控除以外の控除を賃金から実施する場合には、労使協定の締結を交わさなければなりません。具体的には、社宅費や食費、親睦会費などを賃金から差し引く場合などが該当します。
労使協定に違反した場合には、どのように対処すればいいのでしょうか?労使協定違反と周知義務違反のケースがありますので、それぞれ詳しく解説します。
締結した労使協定に違反した場合には、罰則が課せられます。罰則の内容は、該当する労使協定によって異なります。例えば36協定で決められた時間外労働の上限を超えて従業員を働かせた場合にはと、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられます。
そのため、労使間ともに協定に基づく労働指導を徹底させましょう。
労使協定を締結するにあたっては、周知義務が発生します。周知義務は労働基準法106条から、すべての労使協定が対象になっています。
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
もし周知義務に違反した場合には、労働基準法120条から30万円以下の罰金が課せられます。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
労使協定は、労働者の権利や職場環境を守るために締結される必要性の高い決め事です。時間外労働や休日出勤を求める際には36協定が欠かせないように、必要に応じて労使協定を結んで、労働者の権利を守ることが求められています。
また労使協定には様々な種類がありますので、企業ごとに適切な労使協定を締結しておけば働きやすい環境づくりに役立つでしょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。