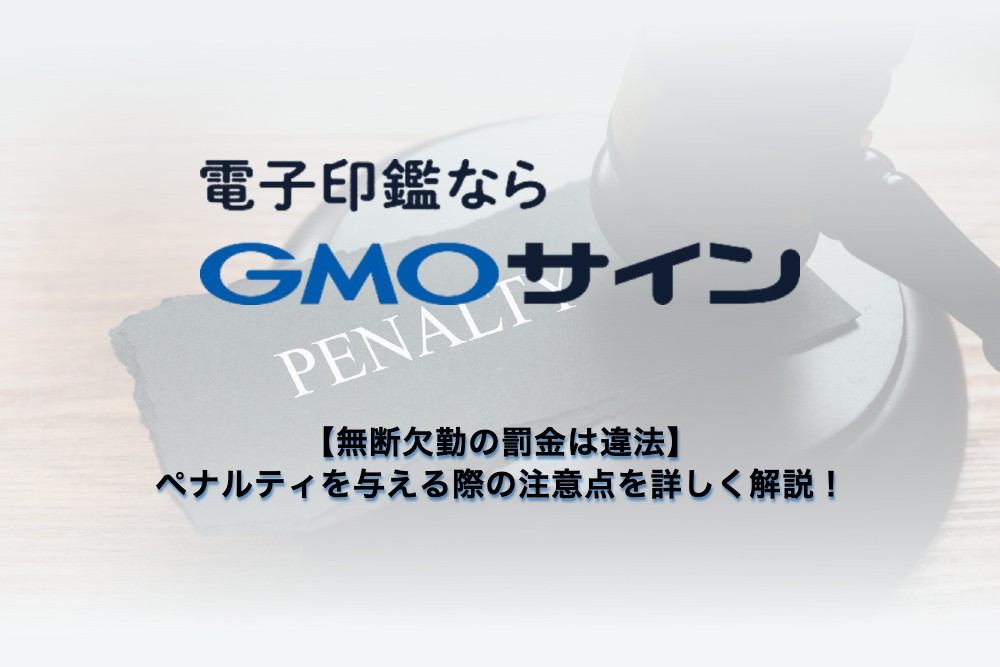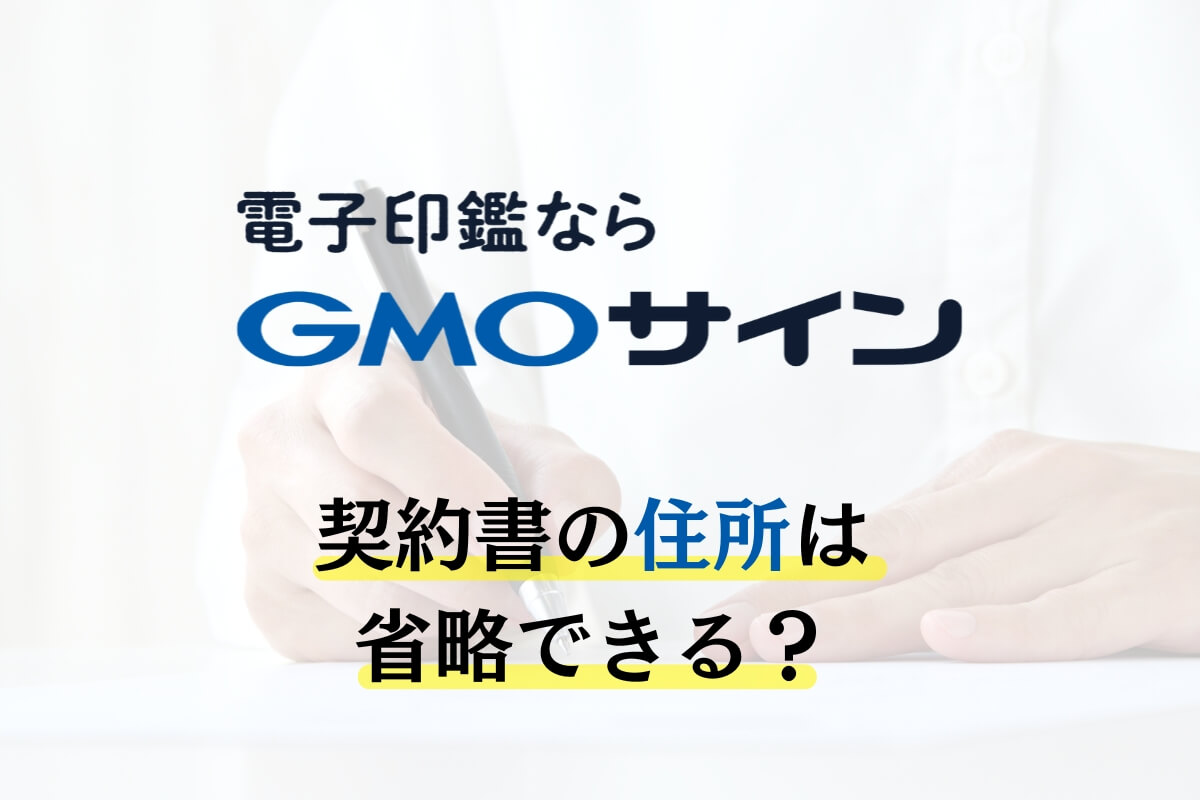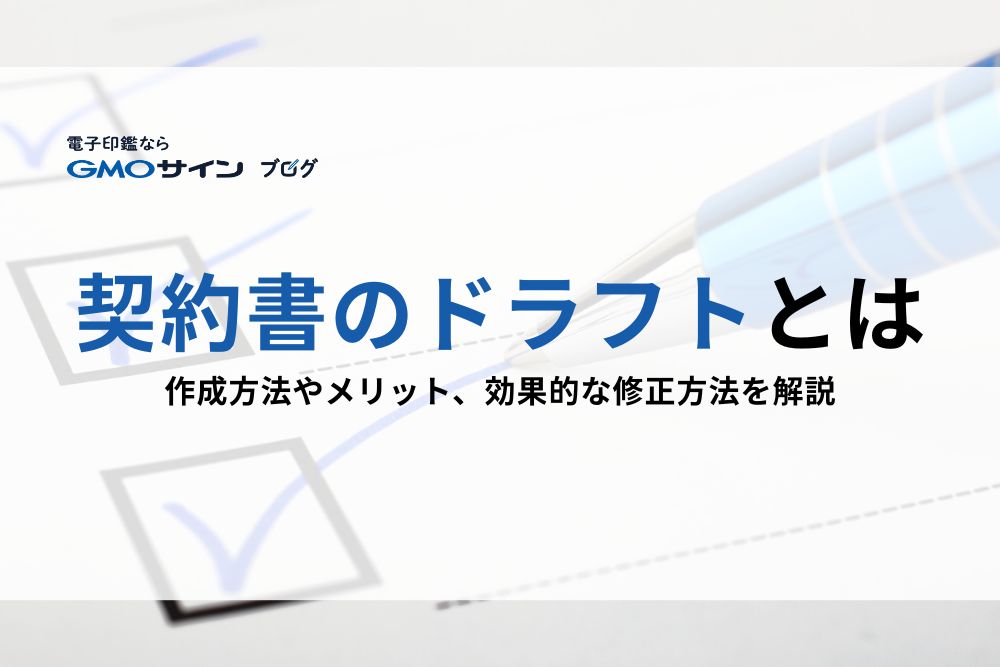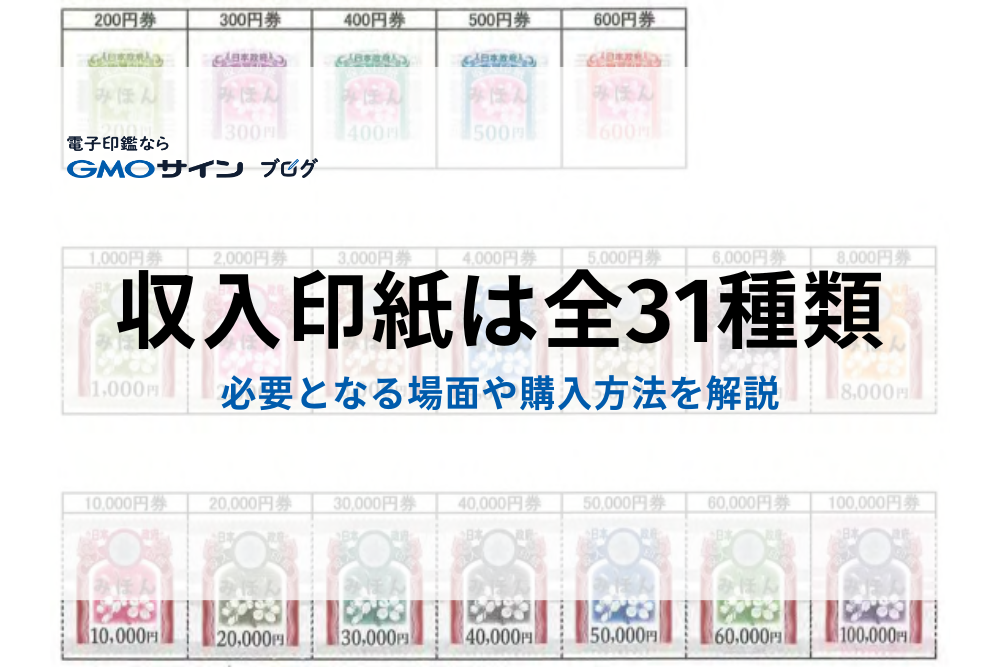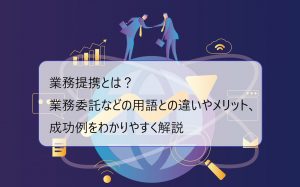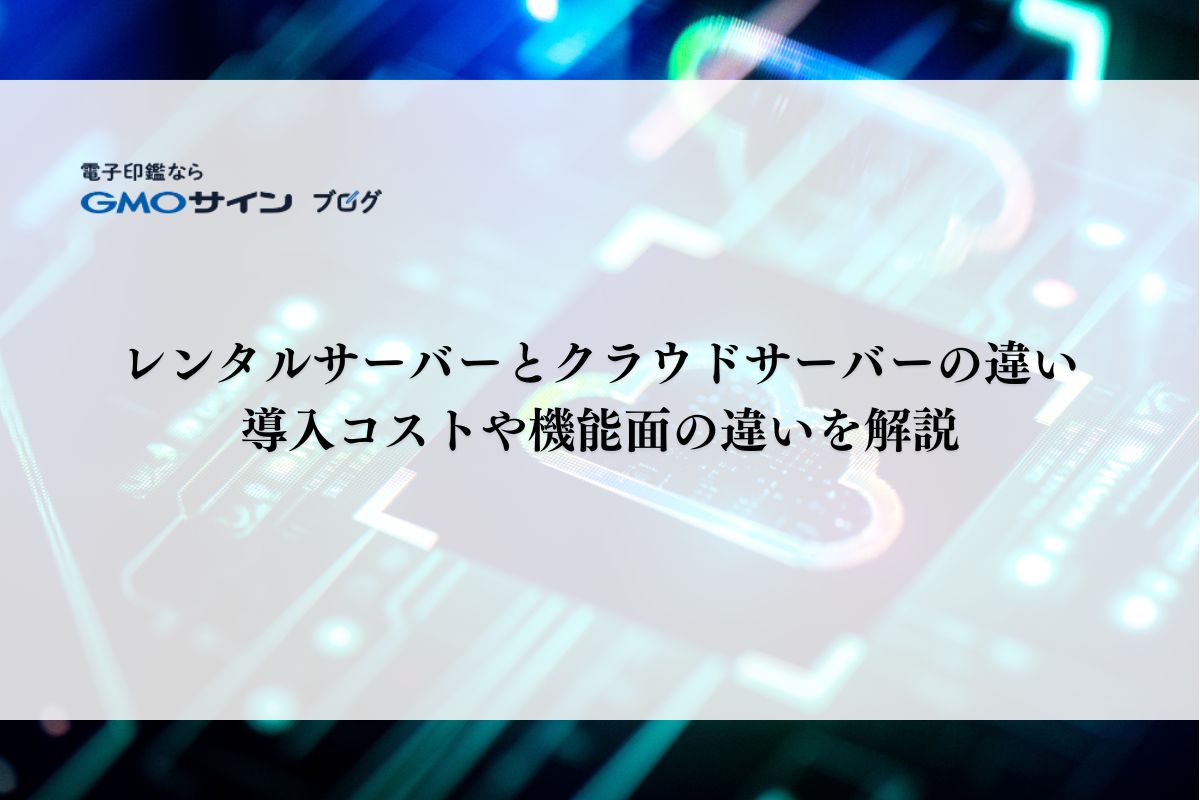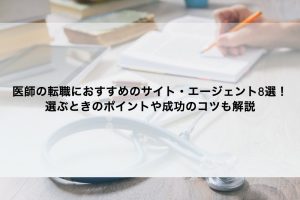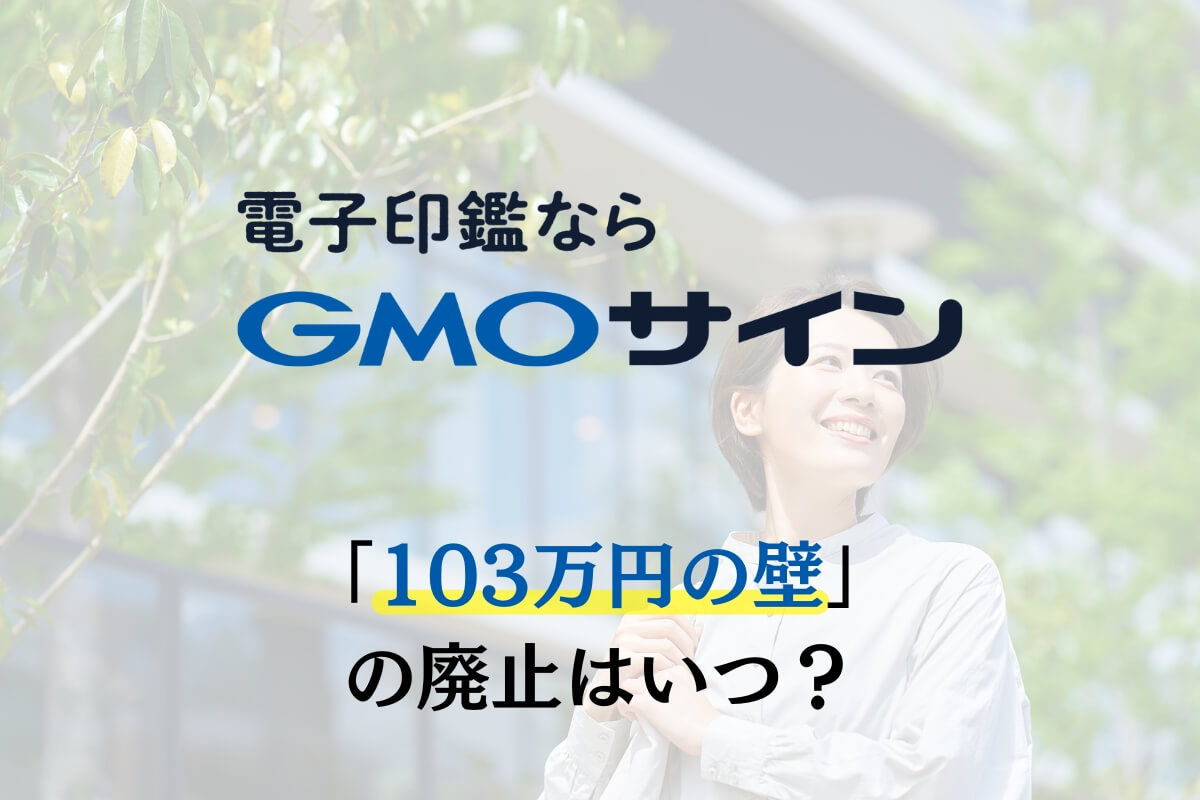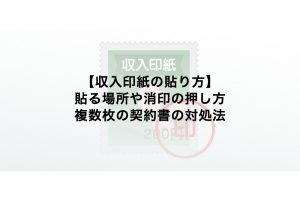ただし、状況によってはペナルティを科すことは可能です。ただ、ペナルティを科す際も法律を把握した上で適切に対応する必要があります。
本記事では、無断欠勤した場合の罰金やペナルティについて、法律に沿って解説します。また、社員とアルバイトでの違いについても解説しますので、企業の担当者様はぜひ、参考にしてください。
無断欠勤の定義
無断欠勤とは、会社に何の連絡もなく欠勤することを指すものです。しかし、これ以外にも会社と労働者間での取り決めによっては無断欠勤と判断される場合があります。
具体的には次のとおりです。
会社側が正当な理由と認めなかった場合
労働者が会社に欠勤の連絡をしたとしても、会社側が欠勤理由を正当と認めなければ、無断欠勤と同じ扱いになる場合があります。
病気や怪我、家庭の事情以外での欠勤は、正当な欠勤理由とみなされないケースが一般的です。
また、上述した理由以外でも、就業規則で上司の許可が必要な場合、許可が下りていないにも関わらず欠勤すると無断欠勤となるケースもあります。
欠勤理由が虚偽と判明した場合
欠勤の連絡をして承認を得た場合でも、後で欠勤理由が虚偽であったと判明すれば無断欠勤です。例えば、病気や怪我を理由に欠勤したが、実際には旅行に出かけていたことが判明すれば、欠勤した日はすべて無断欠勤となります。
社員やアルバイトが無断欠勤した場合に罰金を科すのは違法
社員やアルバイトが無断欠勤をした場合、会社として罰金を科すことは労働基準法第16条により禁止されています。
(賠償予定の禁止)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この法律は、立場上弱い労働者を守るためのもので、事前に労働者に対し会社が金銭を払わせるルールを制定することを禁じています。
罰金もこの法律に含まれるため、無断欠勤をした場合でも、会社側は労働者に対し罰金を科すことはできません。
これは社員でもアルバイトでも同様です。
上述の無断欠勤の定義において、単純に連絡をせずに欠勤する以外にも会社と労働者間での取り決めがあれば、連絡をしても無断欠勤になる場合があると解説しました。しかし、罰金に関しては労働基準法第16条により、罰金を科すことを決めておくのも違法です。仮に就業規則で「無断欠勤をした場合は罰金を科す」と記載したとしても、労働者は罰金を払う必要はありません。
また、無断欠勤をした労働者に対し、罰金と称して給与から天引きをするのも違法です。労働基準法第24条「賃金の支払い」において、賃金は全額を支払わなければならないと決められているため、無断欠勤をしたとしても給与から天引きはできません。
(賃金の支払)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
無断欠勤をした労働者にペナルティを与えることは可能
無断欠勤をした労働者に対し罰金を科すことはできないものの、ペナルティを与えることは可能です。
労働基準法第16条は、会社側が労働者の意思や権利を不当に拘束し、労使関係の継続を強要を禁じる法律です。
例えば、労働者が退職をしたいといった際、研修にかかった費用を返済すること、雇用契約期間を定め、その前に退職する場合は違約金を払うなどは違法となります。しかし、無断欠勤をした際にペナルティを与えることは違法ではありません。
無断欠勤した労働者に与えるペナルティの種類
無断欠勤をした労働者に対するペナルティには段階があります。
ここでは、一般的なペナルティの段階について解説します。
なお、ここで挙げるペナルティの段階は、あらゆる就業規則違反や職場規律違反などに対するものであり、必ずしも無断欠勤だけのペナルティではありません。
けん責・戒告
けん責とは、始末書を提出させ、書面において警告を行うペナルティです。また、始末書を提出させず口頭だけで注意を促す戒告処分といったペナルティもあります。
通常、けん責や戒告も1回の無断欠勤で行われることはなく、数回の無断欠勤を繰り返した際のペナルティです。
ただ、回数に関しては、会社によって異なり、1回で戒告、2回でけん責になるケースもありえます。
減給
けん責や戒告を科しても無断欠勤が続いた場合のペナルティが減給です。前述したように罰金という形のペナルティは労働基準法違反となるものの、減給という形でペナルティを科すことは可能です。
ただし詳しくは後述しますが、減給できる額は労働基準法第91条で規定されているため、会社側の裁量で額を自由に決めることはできません。
出勤停止
減給を科しても無断欠勤が続く場合のペナルティは出勤停止です。労働契約は変えることなく、通常、1週間から10日間の出勤を禁止します。
なお、この間の賃金は支払われることはありません。そして、勤続年数からも除外されます。
降格
出勤停止の次の段階が降格です。役職や職位、職能資格や等級などを引き下げます。なお、降格処分を科した場合、賃金の減額も可能ではあるものの、必ず労働者側の同意が必要です。
例えば、就業規則に降格となった場合、賃金の減額も同時に科すと明記・周知することは最低限必要といえます。
ただ、就業規則に明記している場合でも、容易に賃金の減額を行うことは、人事権の濫用と見なされる場合もあります。そのため、無断欠勤のみで降格や賃金の減額を行う場合は労働者が納得できる根拠を示した上で同意を得ることが欠かせません。
論旨解雇・論旨退職
ペナルティの最終段階で、労働者に対し一定期間内に退職届の提出を勧告します。提出があった場合は、そのまま退職扱いとしますが、提出がない場合は、懲戒解雇処分となります。
ペナルティの段階を経ずに懲戒解雇を行えるケース
ここまで、ペナルティの段階について解説してきました。ただ、無断欠勤が連続して続いた場合、減給や降格を経ることなく、懲戒解雇処分を科せる場合があります。
通常、労働者を解雇する場合、労働基準法第20条により、特別な事情がある場合を除き30日前までに解雇予告しなければなりません。
ただし、労働基準法第20条には、「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」という但し書きがあります。
そして、労働者の責に帰すべき事由の一つとして、「昭和 23 年 11 月 11 日基発第 1637 号、昭和 31 年 3 月 1 日基発第 111 号」の行政通達において次のように記載されています。
原則として2週間以上の正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
引用元:解雇予告除外認定申請について|厚生労働省
このことから、14日以上連続して無断欠勤した場合は、減給や降格といった段階を経ることなく、懲戒解雇を科すことも可能です。
(解雇の予告)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
(3)認定基準について
・ 次の基準に照らし、使用者・労働者の双方から直接事情を聞いて、判断します。(昭和 23 年 11 月 11 日基発第 1637 号、昭和 31 年 3 月 1 日基発第 111 号)
引用元:就業規則(変更)届|厚生労働省
「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、
判定に当つては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべき
であり、「労働者の責めに帰すべき事由」が法第 20 条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質
なものであり、従つて又使用者をしてかかる労働者に 30 日前に解雇の予告をなさしめることが当該
事由と比較して均衡を失するようなものに限つて認定すべきである。
「労働者の責めに帰すべき事由」として認定すべき事例を挙げれば、
(1) 原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に当たる
行為のあった場合、また一般的にみて、「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ
不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者
が継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯又はこれに類する行為を行った場合、事
業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事
業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関
係を喪失せしめるものと認められる場合
(2) 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また、これら
の行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を
失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認
められる場合。
(3) 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行
う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
(4) 他の事業場へ転職した場合。
(5) 原則として2週間以上の正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
(6) 出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意をうけても改めない場合。
無断欠勤した場合、アルバイトと正社員での違い
前項でペナルティの段階を解説しましたが、これはあくまでも正社員に対するペナルティの段階です。会社にもよるものの、アルバイトの場合、一般的には「けん責・戒告」「減給」までが社員と同じで、その後は「契約解除」となります。
上述したように連続して2週間以上無断欠勤をするのではなく、無断欠勤が多いというだけでいきなり契約解除することはできない点については注意が必要です。
また、会社によってはアルバイトであってもランクがあり、懲戒解雇の前に降格処分を科すケースもありえます。
この点については法律で決められているわけではなく、会社の裁量により変わるものの、アルバイトの同意が必要になる可能性もあるため、就業規則に明示しておくことが重要です。
無断欠勤をした際に与えられるペナルティとして減給する場合
無断欠勤を含む服務規律違反に対し、ペナルティとして減給を科す場合、減給額は労働基準法第91条で一回に減給額が平均賃金の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えない額とされています。
(制裁規定の制限)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
なお、ここで示される平均賃金とは、過去3か月間に支払われた総額を総日数(休日を含む)で割った金額です。例えば1か月の給与が30万円の場合、3か月で90万円で、これを90日で割った10,000円が平均賃金となります。
この結果から、一回の無断欠勤によるペナルティとして減給できるのは10,000円の半額、5,000円までです。
そして、1か月の間に2回以上の無断欠勤をした場合、賃金支払期における賃金総額の1/10を超えない額と定められています。そのため、30万円の1/10である3万円が限度額です。つまり6回以上無断欠勤があったとしても、3万円以上の減給をすることはできません。
ペナルティを科す際の注意点
無断欠勤を続ける労働者に対し、ペナルティを与える場合、いくつかの注意点があります。ここではそのなかでも特に重要なポイントについて見ていきましょう。
就業規則に明示した上で労働者への周知を徹底する
減給のように法律で定められているものでも、就業規則に記載がなく、労働者に伝わっていなければ、逆に労働者に訴えられてしまう可能性も考えられます。
そうなれば、会社側が不利になってしまうため、ペナルティの内容や科す際の根拠は必ず就業規則に明示した上で労働者への周知を徹底しましょう。
無断欠勤と認められないケースを理解する
会社に無断で欠勤していても無断欠勤と認められずペナルティを科せない場合もあります。
例えば、無断欠勤している労働者が社内でパワハラやセクハラの被害に遭っていた場合や精神疾患で欠勤の連絡ができない場合などです。
これらの社員に対し、無断欠勤によるペナルティを科した場合、後に裁判を起こされれば会社側が敗訴する可能性が高くなります。そのため、無断欠勤をする労働者がいる際は、ペナルティを科す前にまずは現状の把握を心がけましょう。
また、そもそも職場内でパワハラやセクハラが常態化しないよう、常日頃から環境整備を徹底することも重要です。
万が一に備えた管理体制を整備する
特に多くのアルバイトを雇用している場合、無断欠勤をするアルバイトが出ることは想定した上での人材管理が欠かせません。当然ながら無断欠勤するアルバイトに対し代理の人材を求めることはできないため、万が一のことが起きても業務が滞ってしまわないよう、会社側で人材を確保しておきます。
その上で誰であっても業務を回して行けるよう、マニュアルの作成をしておくことが必要です。
無断欠勤をした労働者にペナルティを与える場合は労働基準法の把握が重要
無断欠勤をする労働者がいれば、会社にとっては大きな損失につながる可能性があります。労働者数が少ない小規模企業の場合は、1人が無断欠勤しただけで業務が滞ってしまうケースもあるでしょう。
しかし業務に大きな支障が生じたとしても、当該労働者に対し罰金を科すことは労働基準法違反です。就業規則に記載してあっても、裁判になれば会社側の敗訴になる可能性は高くなります。
だからといって、無断欠勤を見過ごしていれば、会社にとっては不利益しかありません。そのため、ペナルティという形で減給を科すことは可能です。
また、減給をしても無断欠勤を繰り返す場合、正社員であれば出勤停止、降格、懲戒解雇といったペナルティを科すこともできます。アルバイトの場合は、減給しても状況が変わらなければ契約解除も可能です。
ただ、これも就業規則に明記し、周知を徹底すること、減給額は労働基準法第91条に準じるなどの対応が欠かせません。そのため、企業の人事担当者は必ず労働基準法を把握した上で、適切な対応を心がけましょう。