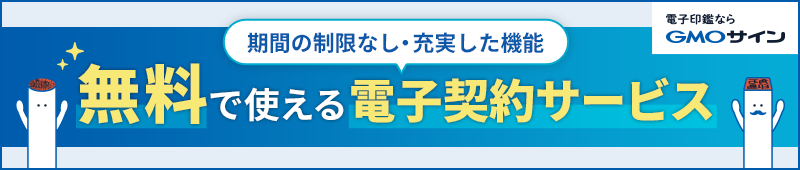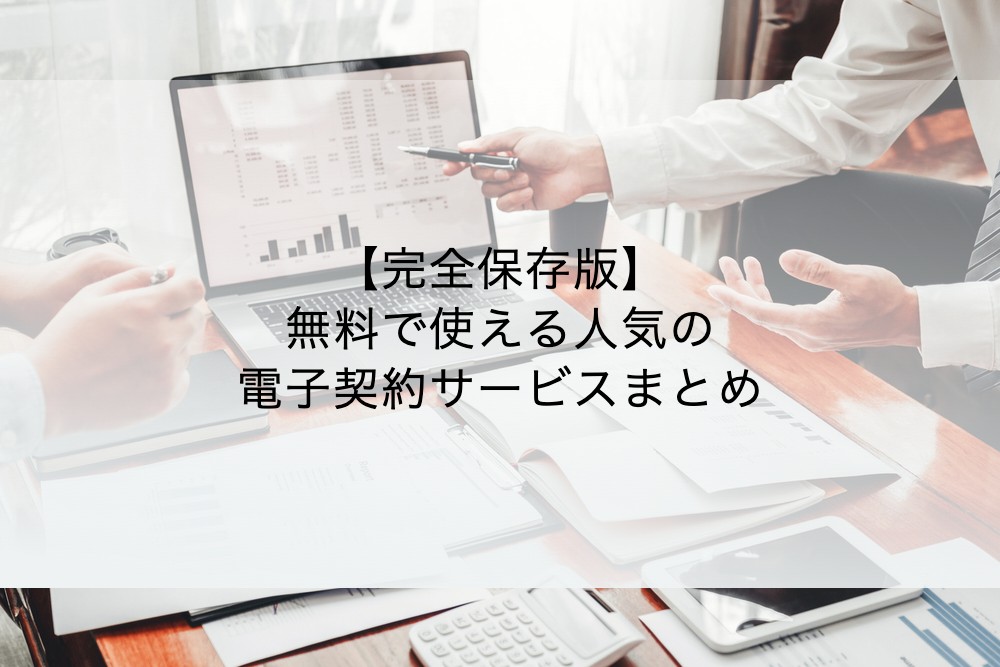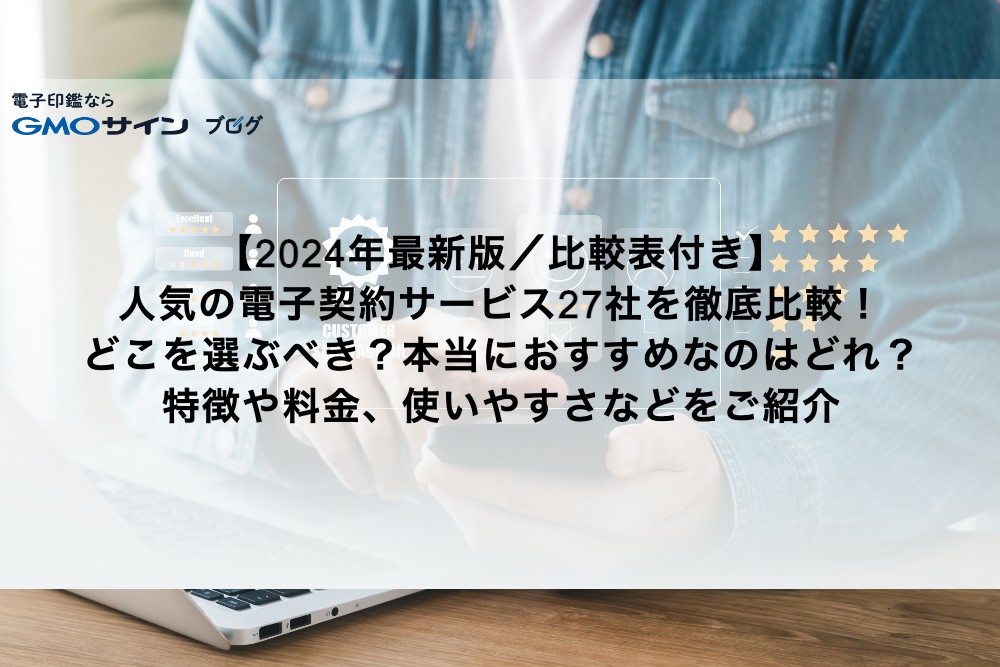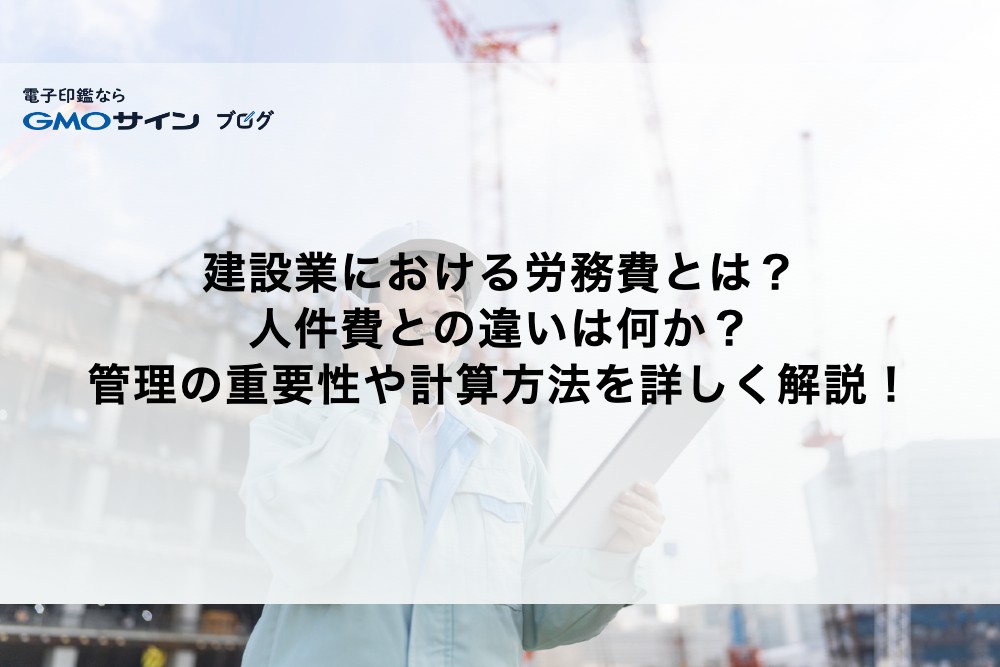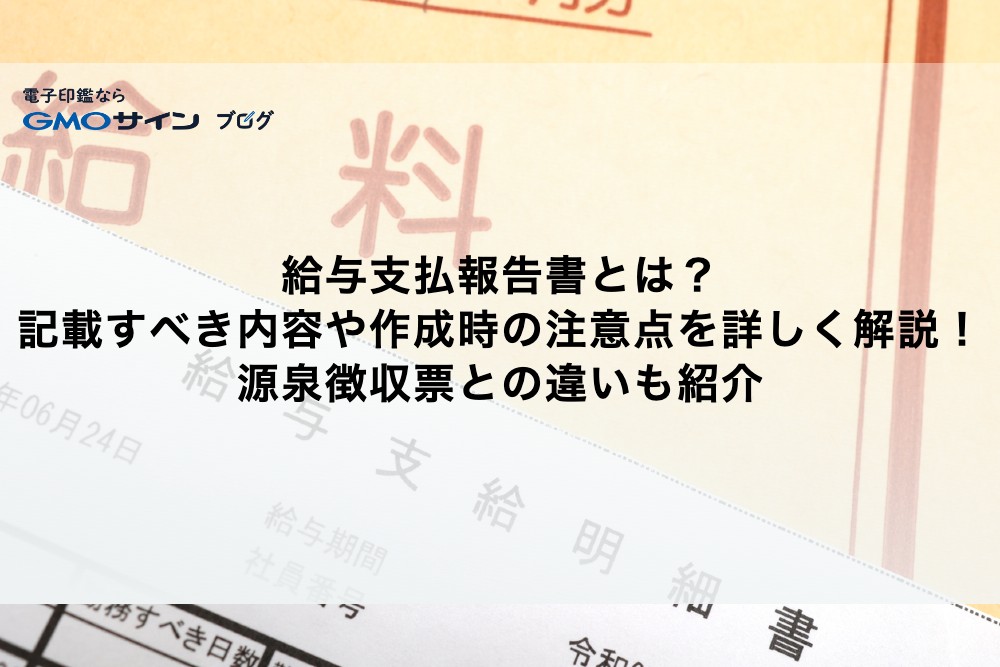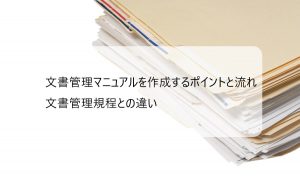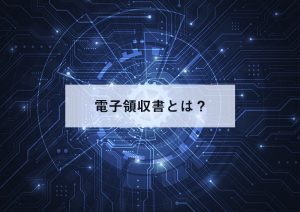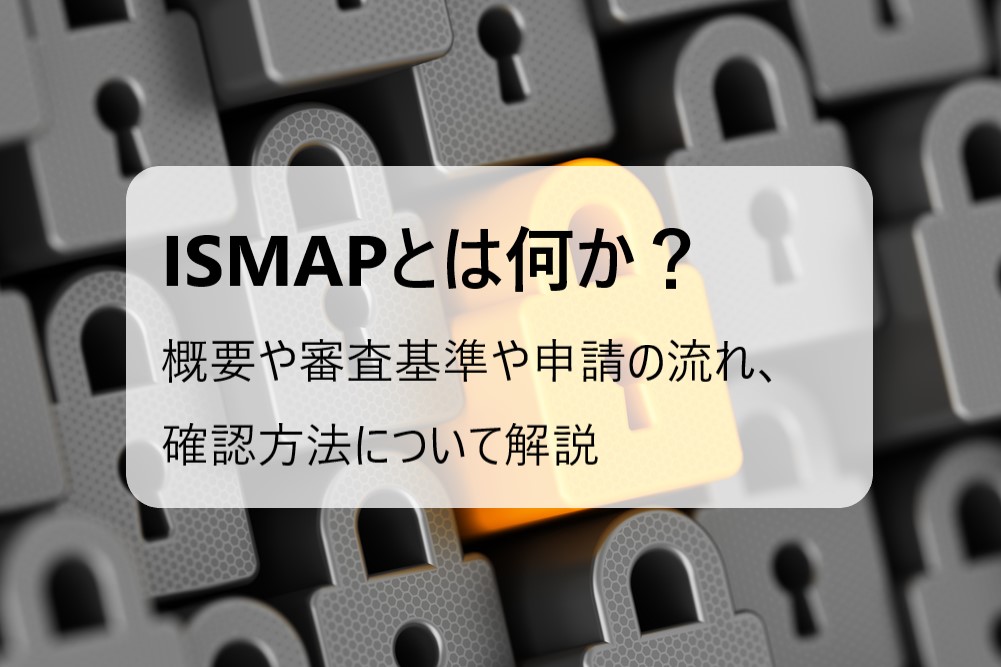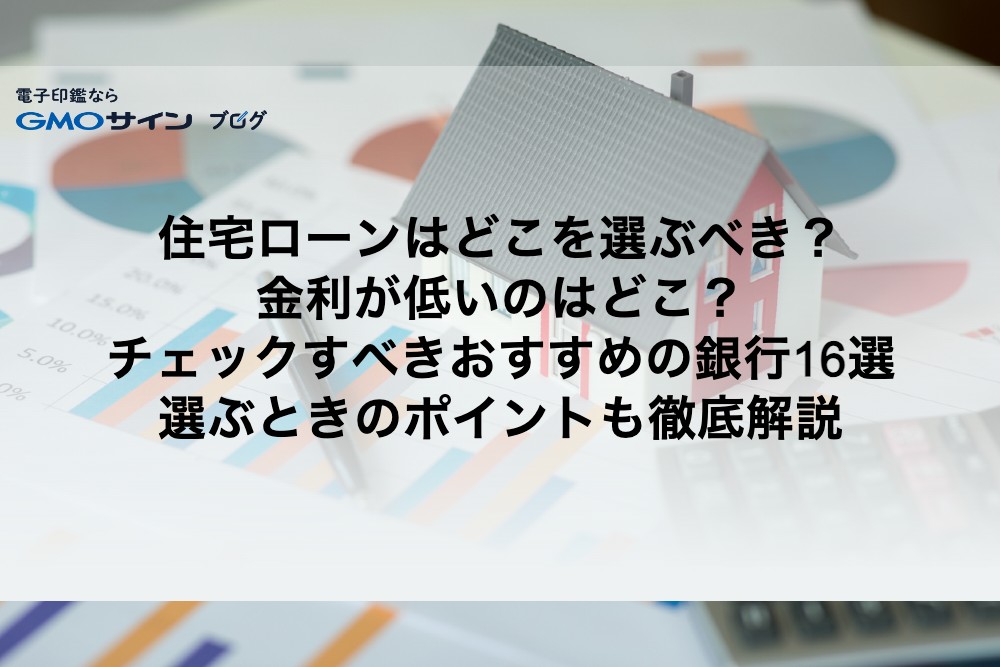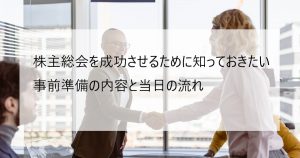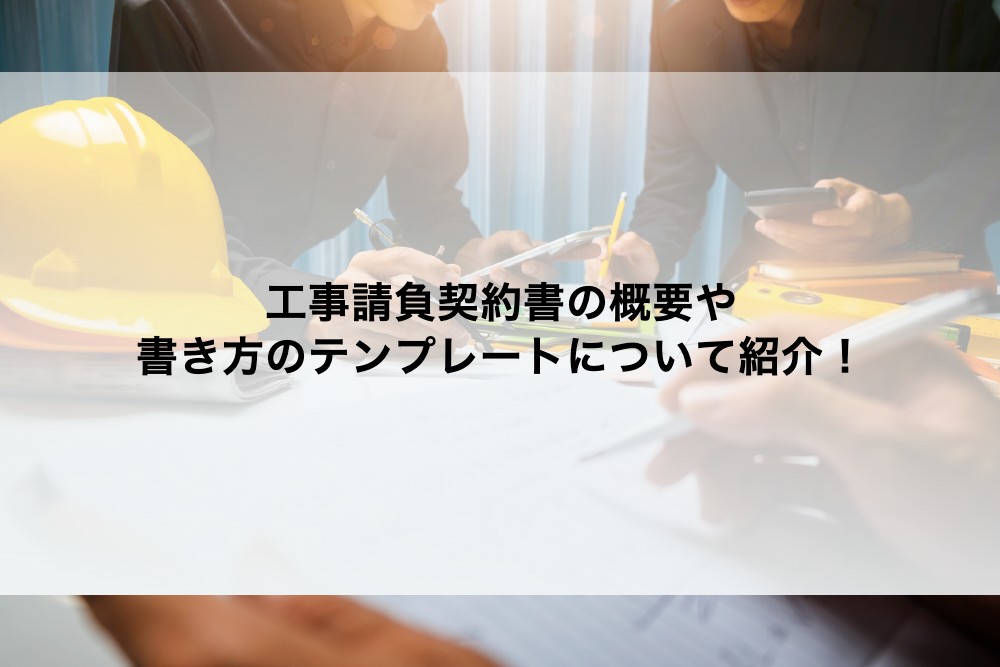会計監査とは?目的や種類、実施するタイミングを解説!会計監査で行う具体的な内容と注意点も紹介
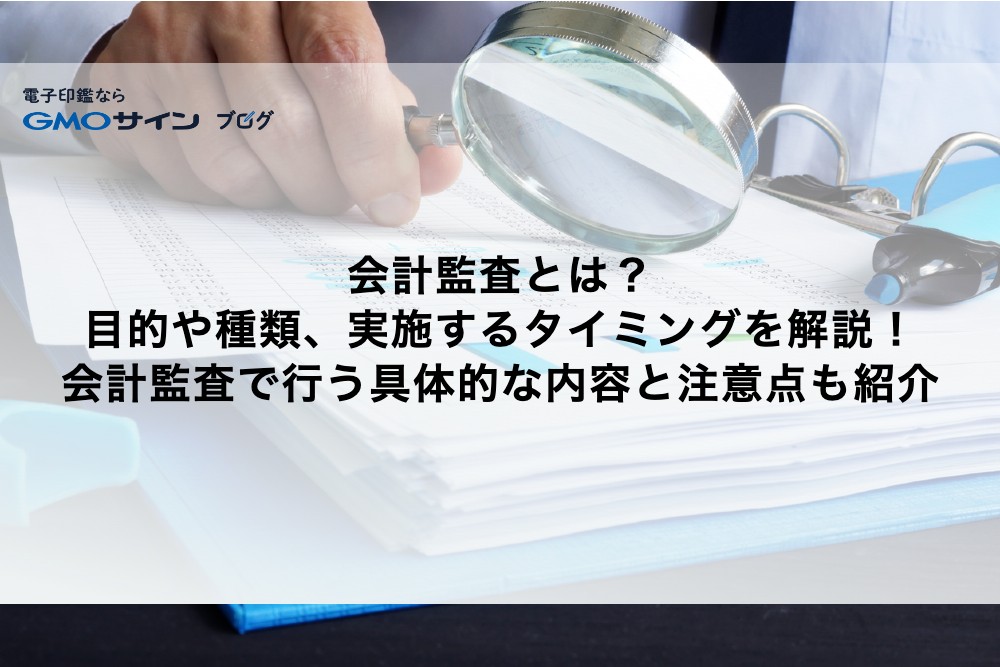
具体的には、会計監査人(通常は公認会計士、または、監査法人)が、会社の会計帳簿、財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)、そのほかの関連資料を詳細に検証し、その結果を報告するものです。
当記事では、会計監査の基本から、具体的な内容、受ける際の注意点などについて詳しく見ていきます。
会計監査の目的
会計監査は、企業の適切な財務報告を確保し、健全な経営を支えます。また、経済社会全体の信頼を維持する重要な役割も果たしています。
会計監査の主な目的は次のとおりです。
信頼性の確保
会計監査は、企業の財務諸表が、一般に受け入れられた会計原則(Generally Accepted Accounting Principles、略してGAAP)や、日本の会計基準(J-GAAP)などに従って正確に作成されているかを確認します。また、重要な事項がすべて適切に開示されているか、適切な形で表示されているかも確認する項目です。
これにより、企業の実際の財務状況や業績が、外部の利害関係者(ステークホルダー)に対して正確、かつ、公平に伝えられます。
内部統制の検証
企業の資産を保護し、不正行為を防ぐためのシステムです。これには、財務報告の正確さを保証するための手続きや、不正行為を防止、または検出するための措置、法令遵守を確保するための指導体制などが含まれます。
会計監査人はこれらの内部統制が適切に設計され、効果的に機能しているかを評価します。また、内部統制に関する問題点や改善点を報告するとともに、その改善を促します。企業の健全な運営にとって、適切な内部統制が確保されていることは非常に重要です。
問題点の発見と改善
会計監査を通じて、会計上の誤りや不適切な手続き、不正行為などが発見されると、これらの問題点は監査報告書に明記され、企業側に対して是正措置を講じるように求められます。また、企業の経営陣に対して、管理体制や業務プロセスの改善提案を行うことも会計監査人の役割です。これらは企業の長期的な成功に寄与するとともに、ステークホルダーへの信頼性を向上させます。
会計監査の種類
会計監査には内部監査と外部監査という2つの種類が存在します。それぞれ異なる目的と役割を持っていますので、確認しておきましょう。
内部監査
内部監査では、経営者自身が自社の管理体制や業務遂行状況、内部統制の適切性をチェックし、問題点があればそれを改善するための情報を提供します。内部監査部門など特設の部署によって行われるのが通常です。
外部監査
外部監査の主な目的は、企業の財務諸表が公正、かつ、適正に作成されているかを評価し、その結果を外部ステークホルダーに対して報告することです。
日本では会社法にもとづき、一定規模以上の株式会社(上場会社を含む)に対しては、外部監査が法定監査として義務付けられています。この法定監査は、公認会計士や監査法人によって行われ、その結果は監査報告書として公表されます。
外部監査の目的は、企業の財務諸表が法令や一般に認められた会計原則に従って適切に作成されているかを確認し、その情報が企業の実際の経済状況を正確に反映しているかを評価することです。
投資家などの外部ステークホルダーが、企業の財務状況について信頼性のある情報を得られるようにすることが目的とされます。なお、日本の外部監査には、会社法に基づく監査(会社法監査)と金融商品取引法に基づく監査(金融商品取引法監査)の2種類があります。
会社法監査とは下記のとおりです。
会社法では、一定規模以上の会社に対して監査役を設置することを求めており、監査役(または、監査役会)がその監査を担当します。また、大企業では会計監査人による監査が求められます。会社法監査では、企業の財務諸表だけでなく法令遵守や内部統制など、企業活動全体が対象となります。
会社法第436条に、監査を受けるべき計算書類が詳細に説明されています。
(計算書類等の監査等)
第四百三十六条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
公認会計士、または監査法人が財務諸表の信頼性を評価し、その結果を監査報告書として提出します。金融商品取引法監査の主な目的は、投資家や市場関係者が企業の財務諸表にもとづいて意思決定を行う際に、その情報が信頼できるものであることを保証することです。金融証券取引法第193条には、以下のように規定されています。
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
引用元:金融商品取引法 | e-Gov法令検索
これら2つの監査はそれぞれ異なる目的を持っていますが、両者とも企業の透明性と信頼性を確保するための重要な監査です。また、これらの監査が適切に行われることで、企業の健全な経営と市場の公正性が維持されるとともに、経済活動全体の信頼性が確保されます。
いつ誰が会計監査を行うのか
会計監査のタイミング、期間、誰が監査を行うかは、監査の種類や企業の事業年度、さらには、企業の特性などによって異なります。一般的な傾向は以下のとおりです。
会計監査のタイミングと期間
会計監査は通常、企業の事業年度終了後に行われます。これは、財務諸表が事業年度終了後に作成され、その財務諸表が監査の対象となるためです。監査作業は数週間から数カ月に及ぶこともあります。
ただし、監査のすべてが事業年度終了後に行われるわけではありません。事業年度途中に中間監査が行われることもあります。中間監査とは、監査作業の効率性を高め、事業年度終了後の監査の負荷を軽減するためのものです。中間監査では、内部統制の評価や一部の会計取引の検証などが行われます。
会計監査を行う者
会社法にもとづく会社法監査の場合、監査役や監査役会が監査を行います。大企業では公認会計士や監査法人が監査役の役割を果たすこともあります。
一方、金融商品取引法にもとづく監査の場合、公認会計士、または、監査法人が監査を行います。これらの専門家は、独立性を保つために監査対象企業の経営陣や従業員とは異なる立場で監査を行うのが特徴です。
なお、会社の内部で行われる内部監査は、企業の内部監査部門や内部監査担当者が行います。彼らは経営陣の指示の下で監査を行い、その結果を経営陣に報告します。
以上のように、監査の実施者は監査の種類や企業の規模、特性などにより異なりますが、どの種類の監査でも、監査の独立性と公正性が最も重要な要素です。
会計監査の内容
会計監査(外部監査)は多岐にわたる項目を対象として、それぞれの正確性と適切性を評価します。その内容は主に以下に示す項目です。
| 経理処理状態や帳簿組織等 | 監査人は、企業の経理処理や帳簿組織、会計システムを詳細に評価します。具体的には、内部統制システムの有効性、会計処理の適切性、経理処理の記録の正確性などの確認です。 |
|---|---|
| 伝票 | 伝票の発行、保管、承認プロセスなどの確認です。伝票は各取引の根拠となるため、監査人は伝票が適切に管理され、その内容が正確に記録されているかを確認します。 |
| 勘定科目 | 監査人は各勘定科目の内容を詳細に検証します。各取引の適切性、取引の記録、精算の正確性などです。 |
| 預金残高や借入金 | 銀行預金の残高は、銀行からの確認(銀行照会)や現金の点検を通じて検証します。また、借入金については、借入先からの確認や借入契約の内容を確認します。 |
| 売掛金・買掛金の残高 | 監査人は、これらの残高が正確に計上されているか、および、収集可能性が適切に評価されているかを確認します。疑わしい債権や収集困難な債権については、慎重な評価が行われるでしょう。 |
| 引当金 | 引当金の計上は、未来の損失や費用を予測するためのものです。その評価は主観的な判断を含むことが多いため、監査人は企業が引当金を計上するための基準や方法が適切であるかを評価します。 |
| 固定資産 | 固定資産の存在、評価、減価償却、除却などについて監査します。固定資産の取得、評価、管理に関する内部統制も対象です。 |
| 実地棚卸 | 企業の在庫や資産の存在と量を確認するために、監査人は場合により実地での棚卸を行います。物理的な資産の存在確認、数量確認、評価方法の確認などです。 |
| 財務諸表 | 最後に、監査人はこれらの財務諸表が一般的に認められた会計原則に従って適切に作成され、企業の実際の状況を適切に反映しているかを確認します。この段階ですべての監査結果が総合され、財務諸表全体の信頼性が評価されるという流れです。 |
会計監査の注意点
会計監査を受ける際には、事前に下記の点に注意しておきましょう。
準備の徹底
監査は企業の会計状況を詳細に調査するものです。したがって、企業側としては、関連するすべての資料を事前に整理し、監査人が迅速に情報にアクセスできるようにしておきます。たとえば、資金の出入りに関する記録、買掛金や売掛金の明細、資産の詳細などを明確にしておくとよいでしょう。
情報開示の透明性
情報を隠したり、誤解を招くような情報提供をしたりすると、監査人の信頼を失うだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性もあります。たとえば、損失を隠すために財務諸表を操作したり、内部統制の欠陥を隠したりすることは絶対に避けるべきです。
速やかな回答
監査人からの問い合わせや依頼に対しては、可能な限り迅速に対応することが重要です。情報の提供が遅いと監査の進行が遅れ、企業全体の業務に影響を及ぼすことがあります。
内部統制の強化
企業の内部統制は、会計情報の信頼性を保証するための重要な要素です。したがって、監査を通じて内部統制の弱点や問題点が明らかになった場合、これを改善するための具体的な措置を講じることが求められます。
円滑な会計監査で企業の信頼性を確保
会計監査は、企業の財務諸表の正確性と公正性を評価する重要なプロセスです。財務諸表の詳細な分析から資金の流れの検証、内部統制システムの評価まで多岐に渡ります。また、法的要求事項への適合性も評価対象です。監査を受ける企業は、適切な資料の準備と情報の透明性を心掛けましょう。