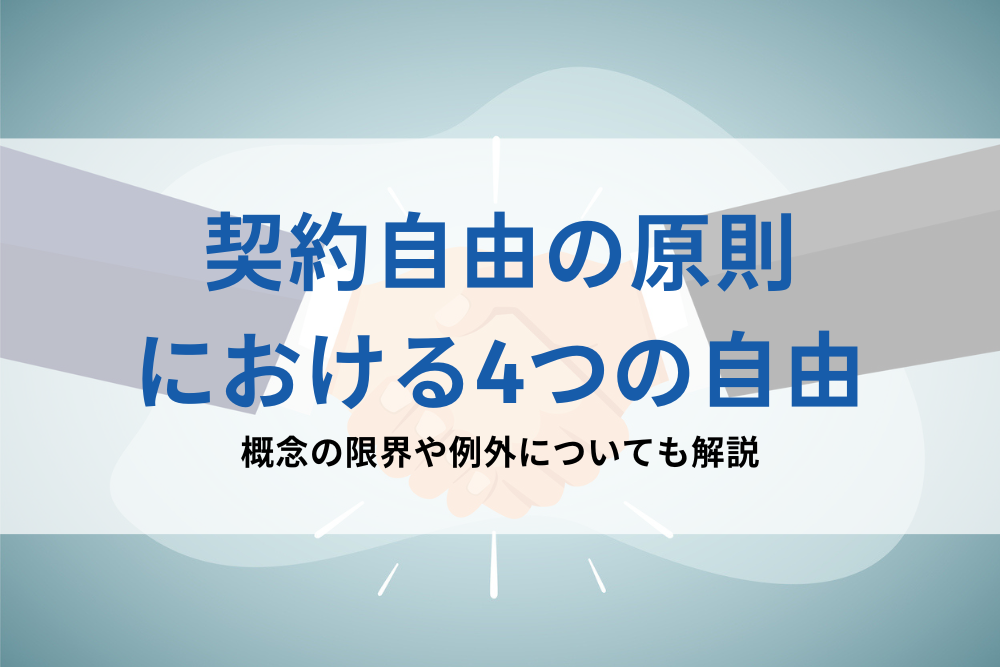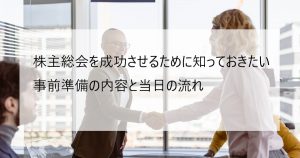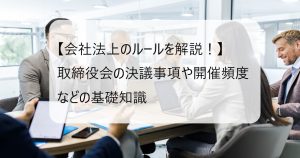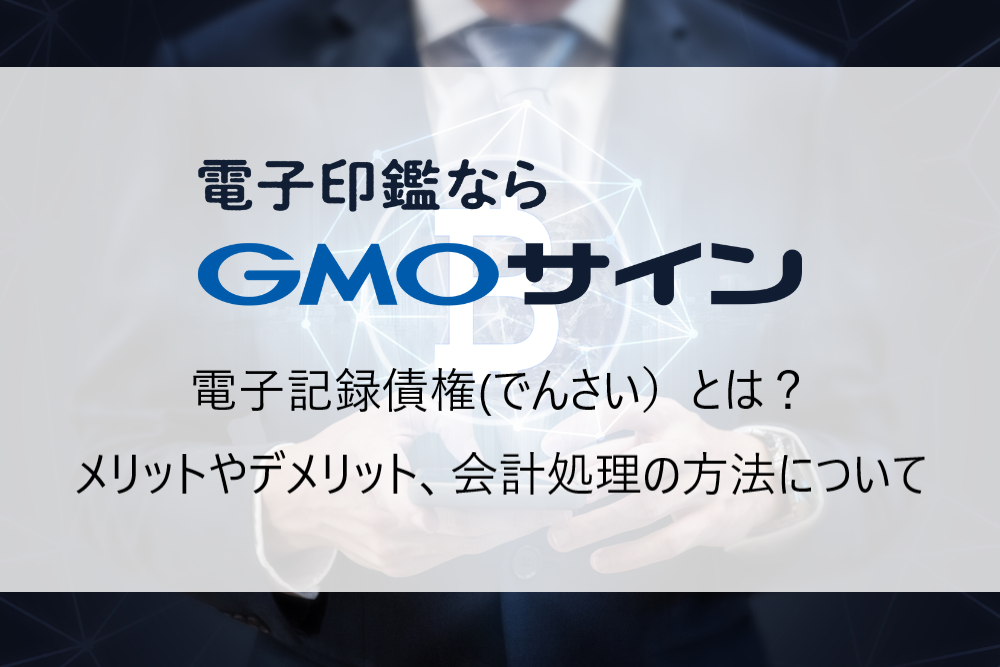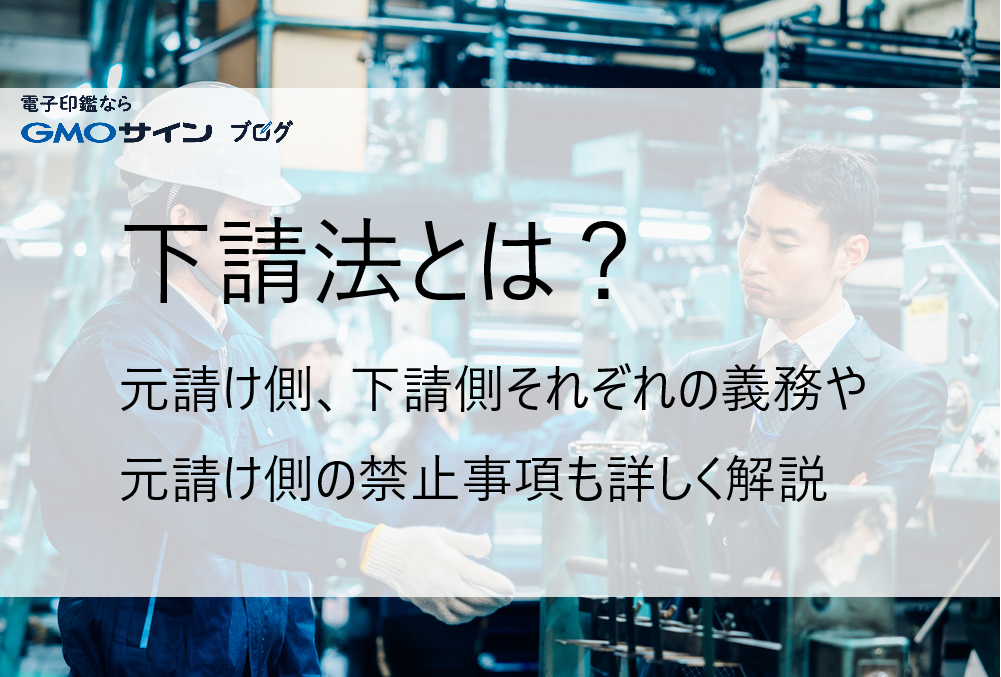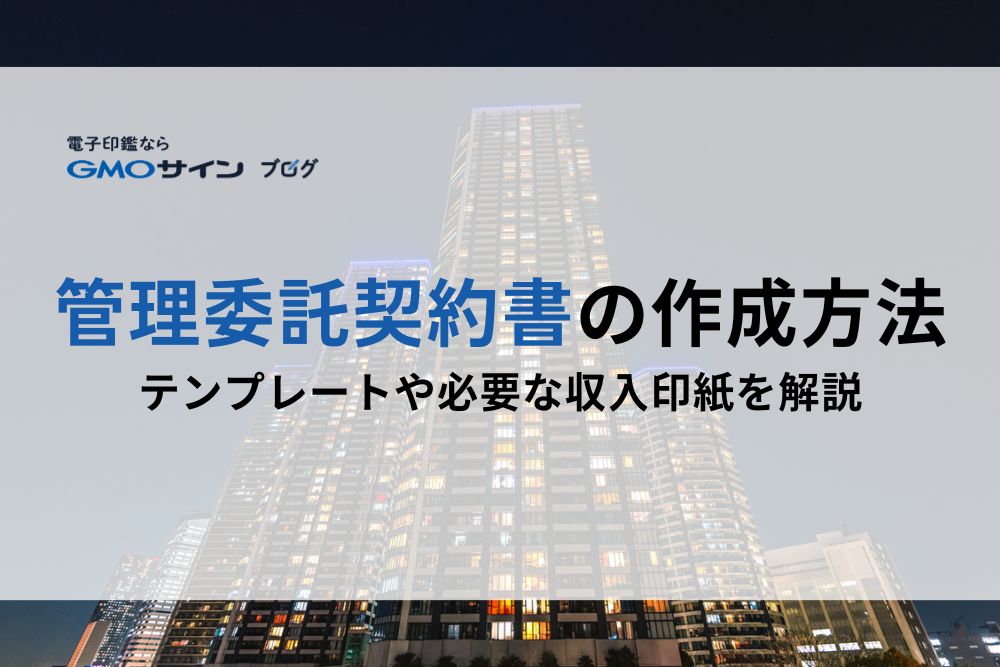\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

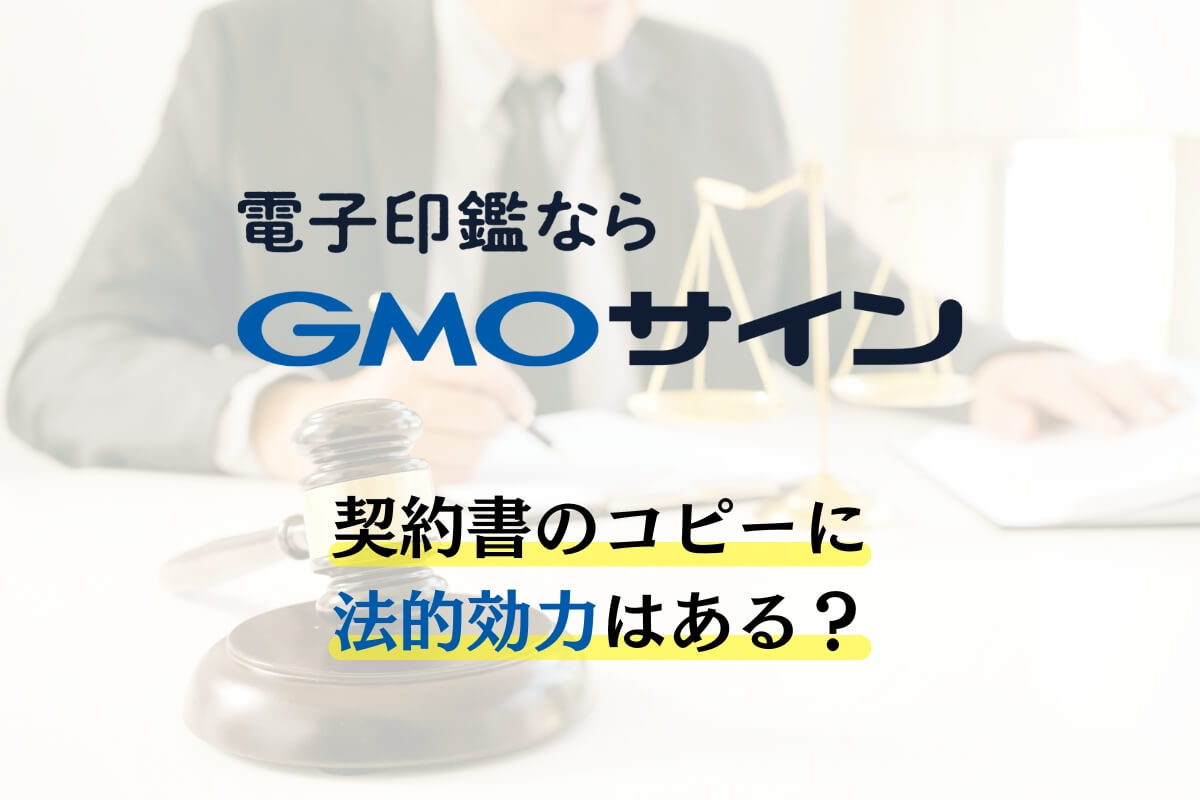
契約書は、当事者の人数分の原本を作成し、それぞれが一部ずつ保管するのが一般的です。しかし、当事者が多い場合や印紙税を節約する目的で、原本を「1部」のみ作成し、ほかの当事者へはコピーを交付するケースもあります。その際、「契約書のコピーに効力はあるのか」「証拠として活用できるのか」などと疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では、契約書のコピーにおける法的効力の有無や原本との違いを詳しく解説します。また、契約書をコピーして交付する際の注意点や印紙税を節約する具体的な方法も紹介します。契約書の作成・管理方法を見直し、コスト削減に役立ててください。
契約書は、原本のほかに写し・謄本・抄本・正本・副本に分類されます。それぞれ法的効力や印紙税法上の課税対象であるか否かが異なるため、違いを理解して適切に取り扱いましょう。
| 分類 | 定義 | 法的効力 | 印紙税の対象 |
|---|---|---|---|
| 原本 | 最初に作成した正式な文書 | ||
| 写し | 原本の記載内容をコピーした文書全般 | ※原本よりも弱い | ※内容による |
| 謄本 | 原本の記載内容を丸ごと複写した文書 | ※公的機関の認証があれば有効 | ※内容による |
| 抄本 | 原本の一部を抜粋して写し取った文書 | ||
| 正本 | 公証権限のある者が作成した正式な文書 | ||
| 副本 | 正本の控えや予備のために作成された文書 |
各文書の特徴や法的効力の有無を詳しく解説します。
契約書の原本は、名義人が最初に作成し、署名や押印が施された正式な契約書を指します。取引においてトラブルが発生したときに、合意内容を確認するために用いられる、重要な書類です。
原本は必ずしも一部のみとは限らず、関係者の人数分を用意する場合もあります。契約書が課税対象である場合は、すべての原本に収入印紙を貼付する必要があるため、適切に対応してください。
なお、法律上、関係者の人数分の原本を作成しなければならない義務はありません。原本をコピーして交付すること自体は違法ではないため、原本を一部のみ作成し、他の関係者にはコピーを控えとして渡す運用も一般的に行われています。
写しとは、原本に記載された内容をコピーした控えの文書全般のことです。具体的には、コピー機で複写したもの、署名や押印のないもの、原本と同一であることが明記されていないものなどが該当し、控えとしてコピーされたものはすべて写しと分類されます。
写しには原本と同じ内容が記載されていますが、法的効力は原本に比べて弱くなります。また、偽造のリスクがあるため、契約の成立が裁判で争われた際に、証拠としての信用性が低いと判断される可能性があります。ただし、原本やほかの証拠が存在しない場合には、写しが証拠として認められるケースもあります。
なお、基本的に写しは収入印紙を貼付する必要がありません。しかし、記載内容によっては貼付が必要な場合もあるため、作成時には十分に注意してください。
謄本は、原本に記載された内容を、一字一句変えることなく忠実に写した文書を指します。代表的な例として、戸籍謄本や不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などが挙げられます。これらの原本は市役所や法務局などの公的機関で厳重に保管されているため、必要に応じて原本の内容を写した謄本が交付される仕組みです。
法令上の権限を持つ者が職務上の権限に基づいて作成し、原本の記載内容と同一であると認めたものは認証のある謄本と呼ばれます。この場合に限り、原本と同等の法的効力を持ちます。
なお、謄本に署名や押印がある場合や正本と相違ない旨の記載がある場合は、印紙税の課税対象です。
抄本は、原本の一部の内容を抜き出して写した文書を指します。原本の内容をすべて写し取ったものを謄本、一部を抜き出したものは抄本と区別されます。
抄本の「抄」は、多くのなかから必要な部分のみを抜き書きする意味です。たとえば、家族全員の情報ではなく、一人分の情報のみを取り寄せたい場合は戸籍抄本を請求します。
謄本との違いを正しく理解し、必要な文書を適切に取得できるようにしましょう。
正本とは、公証権限を持つ者が作成した文書を指します。契約書のほかにも、判決の執行文の付与や判決書の送達などに用いられます。
正本とは、原本の内容がすべて写し取られた謄本の一種であり、原本と同様に法的な効力を有する重要な文書です。ただし、権限を持たない者が作成した場合は、正本とは認められません。なお、印紙税の課税対象と必要となる点にも気をつけて取り扱いましょう。
副本とは、正本の控えや予備のために作られる文書を指します。正本と同じ記載内容のものを複数作成する場合に用いられます。手元に保管するものを正本、公的機関に提出するものを副本とし、用途に応じて区別して使うケースが一般的です。
正本と記載内容は同じですが、副本に法的な効力はありません。正式な申請手続きには正本を求められる場合があるため、状況に応じて使い分けてください。
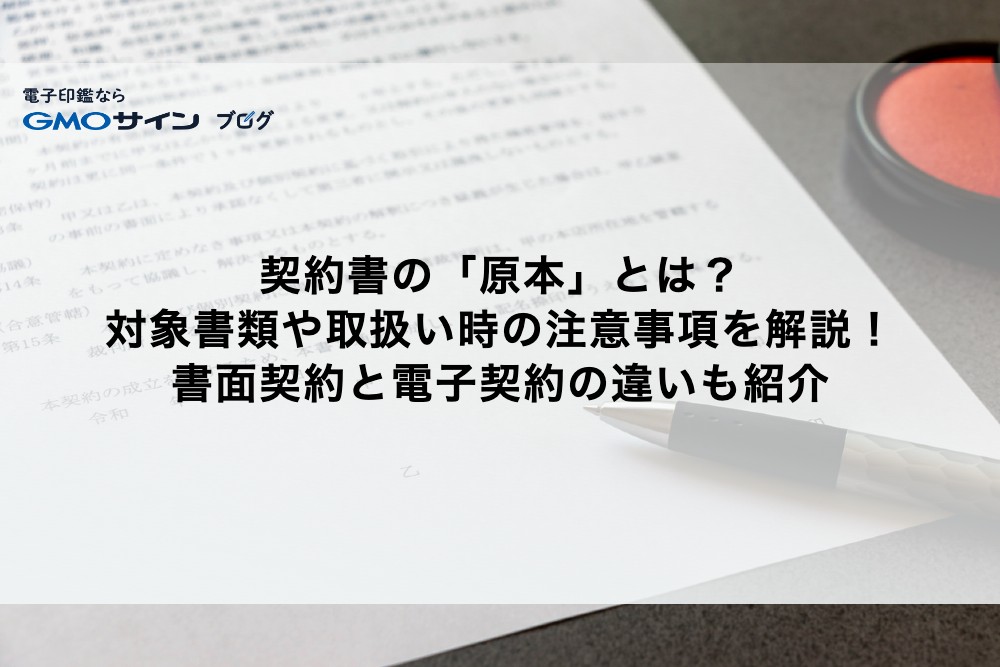
契約書の原本は、取引条件や契約内容を証明する重要な文書であり、特定の状況では提出を求められるケースがあります。ここからは、どのような場面で原本を求められるのか、また原本を用意できないときの対処法を解説します。
一般的に、契約書の原本は手元で保管し、各種申請の際はコピー(写し)を提出します。しかし、以下の場面では原本の提出を求められる場合があります。
訴訟においては、契約の事実を確認するための証拠として、裁判所から原本の提出を命じられる場合があります。税務調査では、取引を証明するために、契約書の原本や領収書などの資料の提出が必要です。また融資の申請では、金融機関が企業の財務状況や返済能力を審査するために、契約書の原本や事業計画書などが求められるケースがあります。
原本の提出が求められる場面を把握し、適切に保管・管理しましょう。
契約書の原本を提出できない場合でも、原本証明を付けることで、写しでも正式な書類として認められる場合があります。原本証明とは、提出する文書が原本の写しであり、原本と同じ内容が記載されていると証明する書面のことです。
基本的に原本は手元に一部しかないため、手続きや申請で提出できない場合があります。また、コピーしか手元にないケースもあるでしょう。このような場合に、原本証明を添えてコピーを提出すると、正式な書類として認められる場合があります。
原本証明の書き方に決まった形式はありません。「この写しは、原本と相違ないことを証明します。」など、原本の記載内容と同一である旨が記載されており、署名または記名押印があれば、原本証明として扱われます。
紙の契約と異なり、電子契約では原本・写し・謄本などの文書の区別は基本的にありません。
厳密には、電子契約の原本にあたるのは、最初に作成して保存された電子データです。しかし、電子データはコピーやダウンロードによって容易に複製できるため、どのデータが原本かを厳密に区別するのは難しいのが実情です。
そのため、電子署名やタイムスタンプを利用し、オリジナルのデータが改ざんされていないことを証明する仕組みが導入されています。この仕組みにより、電子契約では特定のデータを原本とする必要はなく、どのデータを使用しても問題はありません。
契約金額が高額な場合や契約書を複数の当事者へ交付する際は、印紙税の負担が大きくなります。本記事のテーマである「契約書の写し」を利用することは印紙税の負担を軽くする一つの方法ではありますが、その他にも「消費税額の明記」や「電子契約の利用」など、印紙税を節約する方法は複数存在します。
本項では、上記3つの代表的な方法について、それぞれ詳しく解説します。
契約書は、原本を一部のみ作成し、ほかの当事者にはコピーを控えとして渡すことで印紙税を節約できます。
印紙税は、契約の成立を証明するために作成された文書に対して課せられます。原本は印紙税の対象ですが、コピーは控えとして扱われるため、印紙税はかかりません。
ただし、以下の場合はコピーであっても契約の成立を証明する目的で作成された文書とみなされ、印紙税がかかります。
また、契約書のコピーは、原本に比べて法的効力や証拠能力が低いと判断される場合があります。さらに、原本ではなくコピーで契約を交わすことに対し、相手が不信感を抱く可能性もあります。契約の信頼性を損なわないためにも、取引先との合意のもとで適切な契約書を用意しましょう。
契約書に記載する契約金額は、消費税額を区分記載するか、税込み価格と税抜価格を記載することで印紙税を節約できる場合があります。
たとえば、契約金額1,000万円の工事請負契約書を作成する際に「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合、契約金額は1,100万円であると判断され、2万円の印紙税がかかります。一方で、以下のように契約金額と消費税額を分けて記載すると、契約金額は1,000万円であるとして印紙税を1万円に節約できます。
なお、この取り扱いの対象となるのは、第1号(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号(請負に関する契約書)、第17号(金銭又は有価証券の受取書)のみです。対象となる文書を作成する際は、ぜひ活用してください。
契約にかかる印紙税を節約するためには、電子契約を導入するのが効果的です。紙の契約では契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要となり、1件あたり200円から、場合によっては数十万円かかるケースもあります。一方で、電子契約は課税文書の対象外であるため、収入印紙の貼付が不要となり、契約ごとにかかる印紙税を削減できます。
また、電子契約は印紙税のほかにも、印刷や製本、郵送にかかる費用も節約できます。契約書を締結する頻度が高い企業ほど、電子契約を導入することで契約書の作成にかかる費用を大幅に節約できるでしょう。
紙の契約書だと収入印紙を貼り忘れた場合、印紙税の納付漏れと判断されて本来の3倍の税額を請求される可能性がありますが、電子契約であればそのリスクを回避できます。
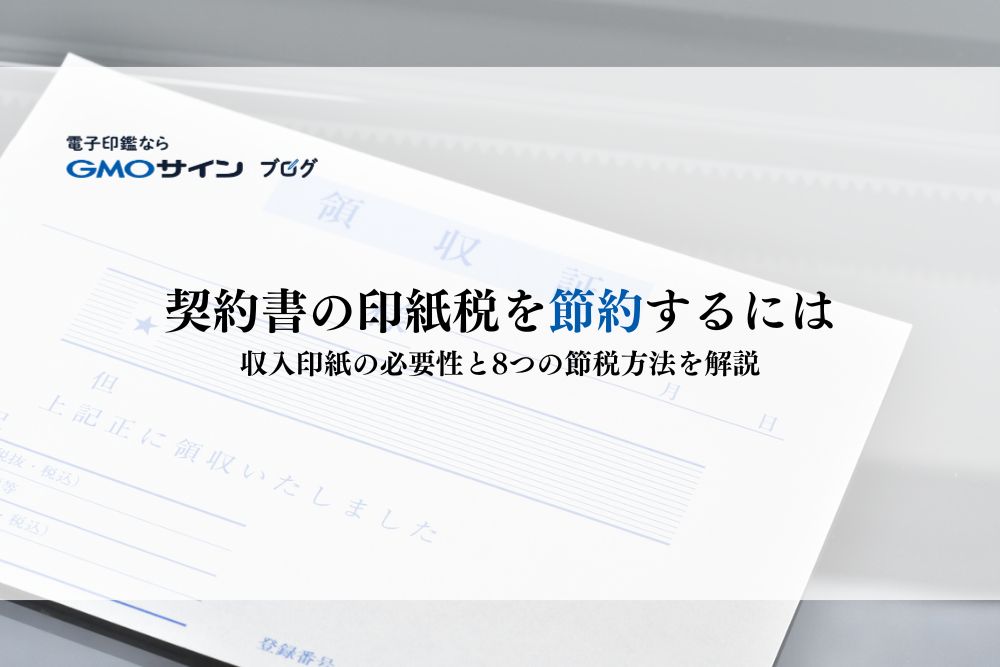
紙の契約書から電子契約に変えると、印紙税の削減のほかにも複数のメリットが得られます。一方で、導入や運用時に注意しておきたい点もあるため、電子契約サービスのメリットとデメリットの両方を理解しておきましょう。以下は、電子契約サービスの主なメリット・デメリットです。
電子契約は一定条件を満たしていれば、紙の契約書と同等の法的効力が認められています。コスト削減や業務の効率化に有効なサービスのため、自社に適しているかしっかりと確認したうえで導入を進めましょう。

契約書の原本をコピーして交付することで印紙税を節約できますが、原本に比べると法的効力や証拠能力が低くなる場合があります。また、原本ではなくコピーで契約を交わすことに対して取引先が不信感を抱くおそれもある点を理解しておきましょう。法的効力を担保しつつ、印紙税の負担を軽減したい方は電子契約サービスの導入を検討してみましょう。
電子印鑑GMOサインは、印紙税が節約できるだけでなく、契約書の作成・管理にかかるコスト削減や業務の効率化が図れる電子契約サービスです。月額8,800円(税込9,680円)で法的効力を担保する機能を標準搭載しており、強固なセキュリティを備えています。無料で使えるお試しフリープランも用意しているため、契約書の作成・管理にかかる負担を軽減したい方は、ぜひ一度お試しください。
\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。