\ 新プランリリース記念 /

\ 新プランリリース記念 /


住民税を毎年どのくらい支払っているのか、今年はいくら支払わなければならないのか気になる人は多いでしょう。大半の人にとっては、住民税の税額を自分で計算する機会はありません。
そのうえ、会社勤めの人なら給与から自動的に天引きされているため、改めて意識するタイミングはあまりないかもしれません。自営業者やフリーランスの人なら所得税の確定申告は行いますが、住民税は自治体が計算して納付書を送付しているでしょう。
しかし、納税している以上、税額がどのようにして計算されているのか把握しておくことも大切です。本記事では住民税について計算方法や減額方法などを中心に全般的に解説していきます。
所得のある人は、納税義務があるため住民税を支払っています。しかし、そもそも住民税は、どのような趣旨の税金なのか疑問に感じている人もいるのではないしょうか。所得税との違いがよく分からない人も多いかもしれません。最初に住民税の概要について確認していきましょう。
住民税とは、一定以上の所得のある人に課税される地方税のことです。法人に対して課せられる法人住民税と個人に対して課せられる個人住民税があります。
単に住民税といった場合には、個人住民税の方を指すことが多いです。
本記事においても、個人住民税に関する内容を解説しています。
また、住民税は単一の税金ではありません。都道府県民税と区市町村民税、森林環境税をあわせて住民税と呼びます。森林環境税は2024年から導入されました。税額の計算や納税は両方あわせて区市町村に対して支払う仕組みです。引っ越しをした場合には、1月1日時点での住民票が基準にされます。
(参考:東京都主税局「個人住民税|暮らしと税金」)
地方自治体が住民税を課税する目的は、行政サービスを行うための財源確保が目的です。公立学校の運営やインフラ整備、ゴミの処理、防災対策などに住民税が使われています。
住民税は地方自治体に納めますが、計算方法は全国で統一されています。では、住民税の計算方法について見ていきましょう。
住民税は基本的に、所得割を計算して均等割と森林環境税と合算して計算します。均等割は一律課税されるもので4,000~5,000円、森林環境税とあわせて5,000~6,000円ですが、自治体によりやや差があります。所得割は所得金額に応じて課税されるものです。所得に比例して負担も大きくなります。
所得割の計算方法は、所得金額から所得控除を差し引いた金額に対して税率をかけるものです。住民税の税率は一律10%で、所得金額で変わることはありません。10%の内訳は4%分が都道府県民税で残りの6%分が区市町村民税です。
また、所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。会社勤めの人の場合は、給与所得控除が必要経費として扱われます。
自営業者やフリーランスの人の場合には、実際にかかった経費や青色申告特別控除が必要経費です。
経費とは別に税額の計算上、所得から差し引かれる「所得控除」というものもあります。所得金額が高くても所得控除が多いと住民税が安いケースもあるため、重要な項目です。
また、所得控除の他に税額控除というものもあります。税額控除は所得控除よりもさらに有利で、住民税の計算をして算出された税額から差し引かれるものです。
所得控除には次のような項目があります。
医療費控除は年間の医療費が10万円を超えている場合、または総所得金額の5%を超えている場合に対象です。
本人の分だけでなく生計を一にする親族の分も含められます。ただし、重複してはいけません。控除金額は総所得金額が200万円以上なら年間の医療費から10万円を差し引いた金額となり、200万円未満なら総所得金額の5%を差し引きます。所得税でも医療費控除があり同じ金額です。
配偶者控除は被扶養配偶者がいる人に適用されます。金額は配偶者の所得額に応じて決まります。
ほかの所得控除項目も所得税より少ない金額に設定されているものがいくつかあります。社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除は所得税と変わりません。実際に支払った金額が全額控除対象です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合には、年齢と年金額に応じて公的年金等控除額を差し引いた金額が所得として扱われます。65歳未満と65歳以上で異なる設定がなされており、いずれも年金額が高くなれば公的年金控除も上がる仕組みです。
公的年金控除の最低金額は65歳未満で60万円、65歳以上で110万円です。年金額がそれ以下で他の収入がなければ、住民税はかかりません。
税額控除には次のような項目があります。
配当控除は、株式投資の利益を総合課税として申告する際に受けられる税額控除です。株式の配当金は受け取り時に源泉徴収されますが、配当控除を受けることでその分が相殺されます。株式投資の利益は分離課税と総合課税を選択可能です。必ずしも総合課税が得というわけではありません。
所得の高い人は、総合課税にすると控除は増えますが、トータルで負担する税金は大きくなってしまう可能性があります。
また、住宅借入金特別控除は住宅ローンを利用している場合に適用される税額控除です。住宅ローン減税と呼ばれており、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から税額控除されます。そして、所得税だけで控除しきれなかった分が住民税から税額控除される仕組みです。
寄附金控除は、国や地方自治体、公益法人、政党などに寄附をした場合に適用されます。所得控除になるものと税額控除になる物があり、寄附先によって扱いが異なります。ふるさと納税も寄附金控除の一種です。
均等割を5,000円と仮定し、住民税の計算式の具体例を紹介していきます。
会社勤めの人で給与所得控除後の金額が400万円の人の場合で住民税の計算式の具体例を見ていきましょう。各種控除は、医療費控除が10万円、配偶者控除が33万円、社会保険料控除が100万円と仮定します。
そうすると各種控除の合計が143万円です。また、税額控除として寄附金控除10万円と仮定します。計算式は次の順に進み、住民税の税額は162,000円です。
(給与所得控除後の金額400万円 ー 控除合計143万円)× 住民税税率10% = 257,000円
257,000円 ー 税額控除(寄付金控除) 10万円= 157,000円
157,000 + 均等割り5,000円 = 162,000円
フリーランスの人で青色申告特別控除後の所得金額が300万円の場合について見ていきましょう。年間の国民年金保険料が20万円、国民健康保険料が30万円、小規模企業共済が36万円と医療費控除が10万円と仮定します。
そうすると所得控除の合計金額は96万円です。税額控除として寄附金控除が10万円と仮定します。計算式は次のとおりで、住民税の税額は109,000円です。
(所得金額300万円 ー 控除合計96万円)× 住民税税率10% = 204,000円
204,000円 ー 税額控除(寄附金控除)10万円 = 104,000円
104,000円 + 均等割り5,000円=109,000円
70歳の定年退職済みの年金受給者で年金額が200万円で、ほかの収入がない場合について見ていきましょう。年間の国民年金保険料が20万円、医療費控除が10万円、税額控除は寄附金控除5万円と仮定します。計算式は次のとおりで、住民税の税額は15,000円です。
年金額200万円 ー 65歳以上の年金受給者で年金収入が330万円未満の方に適用される控除110万円 = 90万円
(90万円 ー 控除合計30万円)× 住民税税率10%=6万円
6万円 - 寄付金控除5万円 = 1万円
1万円 + 均等割り5,000円=15,000円
63歳で定年退職済みの年金受給者で年金額が120万円で、ほかの収入がない場合について見ていきましょう。年間の国民年金保険料が10万円、医療費控除が10万円、税額控除はなしと仮定すると、住民税は45,000円です。
年金額120万円 - 公的年金等控除額60万円 = 60万円
(60万円-控除合計20万円)× 住民税税率10%=4万円
4万円 + 均等割り5,000円=45,000円
住民税が高いと感じる場合には、利用可能な控除を使えていない可能性があります。住民税を安くするためには、所得控除や税額控除を上手く利用することが大切です。では、住民税をできるだけ減額する方法について見ていきましょう。
iDeCoというのは、国民年金と厚生年金へさらに上乗せする年金のことです。iDeCoの掛け金は所得税と住民税の計算において小規模企業共済等掛金控除に該当し、全額所得控除として扱われます。住民税が高いと感じていて、まだiDeCoに加入していない場合には、加入を検討してみるとよいでしょう。
住民税の税率は一律10%ですから、掛け金の10%分の金額だけ住民税が安くなります。所得税もあわせると、所得の高い人ほど減税額が大きくなる仕組みです。
ただし、毎月の掛け金には上限が設定されています。厚生年金のない自営業者やフリーランスは上限が最も高く、月額68,000円まで可能です。この場合、年間の合計で816,000円の所得控除が得られます。
会社員は企業年金の有無によって上限金額に差があり、月額20,000~23,000円程度、公務員は20,000円と低めの設定です。それでも上限いっぱいまで利用すれば年間合計で24万円の所得控除が得られます。
また、いずれの場合も下限金額は月額5,000円です。所得控除が増えるとはいっても、必ずしも上限いっぱいまで利用する必要はありません。あくまで無理のない範囲内で行いましょう。
小規模企業共済というのは、自営業者やフリーランス、零細企業の経営者が自分で退職金を作る趣旨の制度です。毎月一定額の掛金を拠出しますが、その掛金が全額所得控除として扱われます。
小規模企業共済の掛金は月額70,000円が上限で下限は1,000円です。上限いっぱいまで利用すれば、年間で84万円の所得控除が得られます。iDeCoとの併用も可能です。自営業者やフリーランスなら、iDeCoと小規模企業共済をあわせて最大1,656,000円の控除が得られます。
ただし、iDeCoと同様に、必ずしも上限まで利用する必要はなく、無理のない範囲で利用しましょう。
小規模企業共済に加入できるのは、税務署に開業届を提出済みの個人事業主と、一定規模以下の企業の経営者のみです。会社勤めの人は加入できないため注意しましょう。
自営業者やフリーランスの人は国民年金保険料を支払っており、その金額分は全額所得控除として扱われます。そして、実際に支払った日を基準にする仕組みです。そのため、過年度の未納や免除を後納・追納することで、所得控除を増やせます。
後納は未納分を後から納付することで過去5年分まで可能です。追納は免除分を後から納付することで、過去10年分まで対応できます。
ただし、後納や追納をするには手続きが必要です。手続きが完了するまで日数を要するため、年末が近くなってからだと間に合わない可能性があります。国民年金保険料の後納や追納をするなら、早めに手続きを済ませておきましょう。
また、会社勤めの人でも過去にフリーランスや自営業として働いていた人で、未納や免除があった人もいるでしょう。その場合には、現在は会社勤めをしていても、後納や追納をすれば、所得控除が適用されます。
国民年金保険料は、最大2年分まで前納することが可能です。前納した金額は、その年の所得控除として扱えるため、2年分の所得控除を1年で得られます。
ただし、控除を得る時期を前倒しにするだけという点に注意が必要です。翌年は国民年金保険料の控除が得られません。また、2年分前納した場合でも、来年の分は来年に控除を受けられるようにすることも可能です。
(参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」)
ふるさと納税というのは、特定の自治体に対して寄附を行い、見返りに特産品などの返礼品を受け取れる制度のことです。寄附をした分は寄附金控除としての扱いを受けるため、節税効果が得られます。
ふるさとという言葉が用いられていますが、自分の出身地や子ども時代を過ごした地域でなくても問題ありません。どの自治体に対してもふるさと納税ができます。
ふるさと納税の控除額は、寄附額から2,000円を差し引かれる金額を基準として計算される仕組みです。所得税に関しては総所得金額の40%を上限として所得控除として扱われ、住民税に関しては基本分と特例分に分かれています。
基本分は10%が税額控除になるというものです。所得税と住民税の基本分で控除しきれない場合には、特例分で所得割の金額の20%を上限にさらに控除されます。
寄附額から2,000円を差し引いた分をすべて控除に使えていれば、自己負担額は2,000円です。しかし、住民税の特例分を控除しても控除しきれない分がある場合には、実質負担額が2,000円を超えてしまうため注意しましょう。
毎年の住民税の税額を把握した上で、はみ出さないくらいの金額にしておくことが大切です。
また、ふるさと納税は寄附金控除という扱いのため、確定申告をすることで適用されます。しかし、ワンストップ特例制度が設けられており、事前に申請することで確定申告なしでもふるさと納税を適用可能です。紙の書類を送付して行う方法とオンラインで行う方法がありますが、オンラインの方ではマイナンバーカードを使用します。
紙の書類を送付する方法だと本人確認書類のコピーが必要です。オンラインならマイナンバーカードの読み取りとパスワードの入力で済むため手間があまりかかりません。
ただし、対象の自治体が6以上ある場合には、ワンストップ特例制度での対応はできないため確定申告が必要となります。
ふるさと納税を行う際にはふるさと納税ポータルサイトを利用するのが一般的で手続きもかんたんに行えます。ポータルサイトごとに掲載されている自治体の数や対応している決済方法などが異なります。寄附金受領証明書のダウンロードの可否などもポータルサイトによって異なるため、よく比較した上で利用するようにしましょう。たとえば、次のようなふるさと納税ポータルサイトがあります。
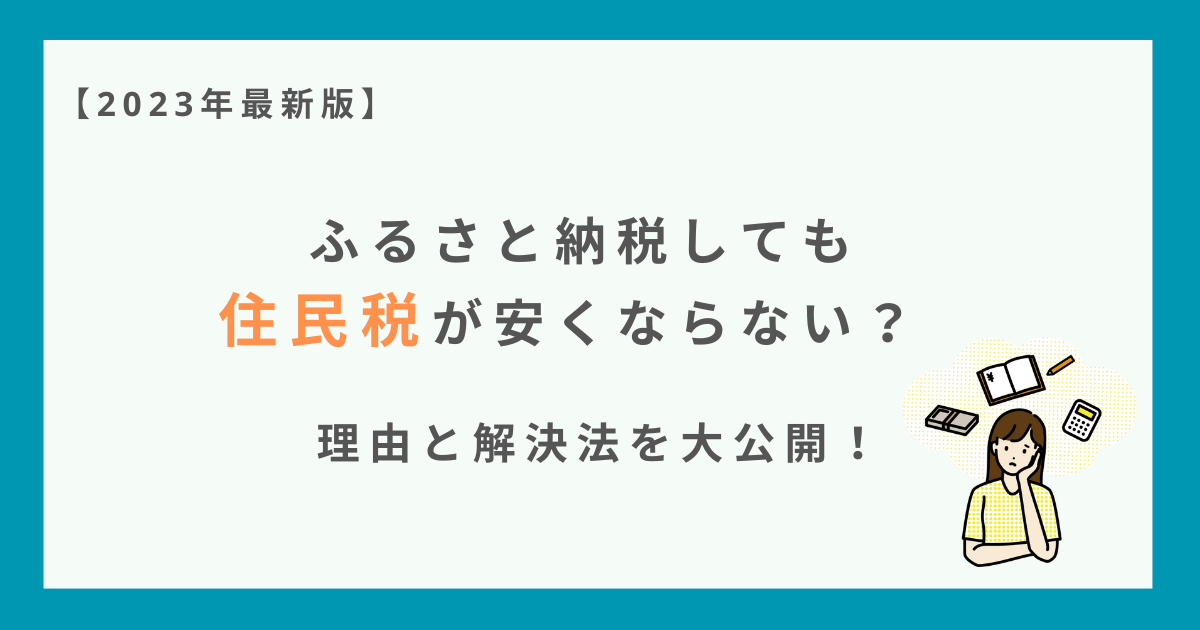
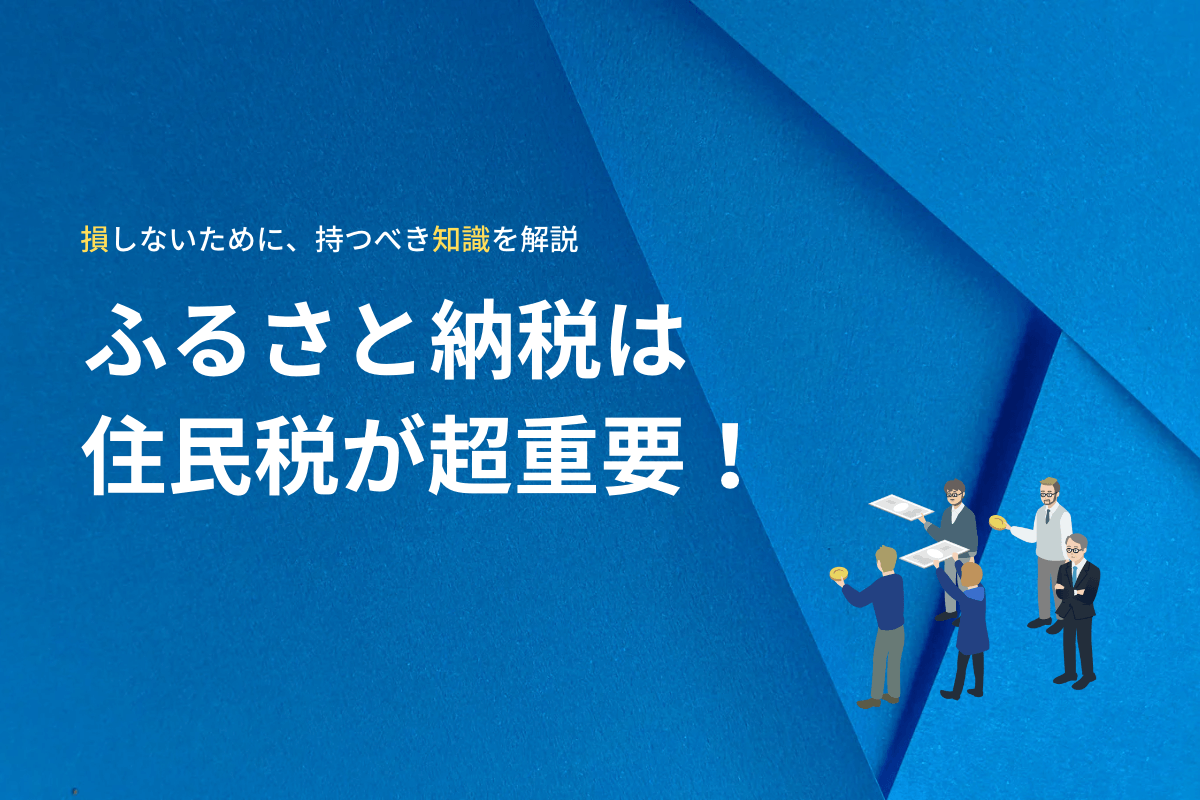
住民税の税額を計算する上で必要なデータは、基本的に所得税の確定申告書や年末調整のデータにほぼ含まれています。所得税のデータをもとにして自治体の方で計算するため、住民税の申告というのは、通常であれば必要ありません。
しかし、次のような状況の人は、住民税申告書を市役所や区役所、町村役場に提出する必要があります。
年末調整を行う前の時期に勤務先を退職し、年末まで再就職していなかった場合には、年末調整をしていない状態です。通常なら確定申告が必要ですが、所得税がかからない所得金額の場合もあるでしょう。たとえば、年のはじめの時期に退職して年末まで再就職していなかったような場合です。
所得税がゼロなら確定申告をしなくても所得税に関しては問題ありません。しかし、所得のデータが自治体で把握できない状態になってしまいます。そのため、住民税の申告が必要です。おもに国民健康保険料の計算に使用されます。
また、所得税がゼロの場合でも確定申告は可能です。確定申告をした場合には、住民税の申告は必要ありません。
国や各自治体では、低所得者向けの住民税の減免制度や住民税非課税者向けの支援制度などを実施しています。そのような支援制度の対象になるかどうかは、所得のデータを基準にしていることが多いです。
そのため、自治体の方で所得を把握していないと、支援制度を利用できません。減免制度や非課税者向けの制度を利用する際には、住民税の申告が必要です。
住民税の徴収方法は普通徴収と特別徴収の2種類があり、働き方に応じていずれかの方法によって行われます。それぞれの徴収方法について見ていきましょう。
普通徴収は自営業者やフリーランスの人に対して行われる住民税の徴収方法です。毎年6月前後の時期に市役所や区役所、町村役場から納税通知書と納付書が送付されてきます。
納付書は4期に分かれており、1年分の税額を4分割で納付する仕組みです。それぞれ納期限が設定されているため、その納期限に間に合うように納める必要があります。納期限より早く納付する分には問題ないため、一度に全額納めることも可能です。
また、仕事を退職したてでまだ再就職先が決まっていない人や、再就職の予定がない人なども普通徴収が行われます。
特別徴収というのは、勤務先が毎月給与を支給する際に天引きして徴収する方法です。会社勤めの人の場合には基本的に特別徴収が適用されます。
特別徴収の場合には、住民税の納付に関して個人では特に何も行う必要はありません。すべて勤務先が手続きを行ってくれます。1回の給与の支給で天引きされる金額は、前年1年分の住民税を12等分した金額です。
所得税の源泉徴収票とよく似ていますが、やや仕組みが異なります。所得税の場合には、当年の分が天引きされているため税額は確定していない状態です。年末調整で所得税の税額が確定し、過不足分が調整されます。これに対して、住民税の特別徴収は前年の所得を基準にして決まる仕組みであるため、すでに決定している点が大きな違いです。
そのため、住民税は年末調整で還付されたり追加徴収されたりすることはありません。
また、年金受給者で年金額が一定額以上の場合にも特別徴収が行われ、年金から天引きされます。ほかの収入がある場合でも天引きされる金額は年金にかかる分のみです。
普通徴収の場合には、納付書を使用して自分で住民税を納付する必要があります。では、どのような納付方法があるのか見ていきましょう。
最もシンプルな納付方法は現金での納付です。納付を銀行や信用金庫などの金融機関の窓口に持参して、現金で支払います。支払いを済ませると、金融機関名と控えに日付の入ったハンコが押されて手渡される仕組みです。
また、金融機関ではありませんが、コンビニでの支払いにも対応しています。コンビニは24時間営業のため、土日祝日や深夜など金融機関の窓口が閉まっているときでも納付可能です。
ただし、現金での支払いは毎回金融機関の窓口やコンビニまで足を運ばなければなりません。手間がかかり、特にお得な面もないのがデメリットです。
口座振替で普通徴収の住民税を納付することもできます。この場合、あらかじめ口座振替依頼書を提出するなどの手続きを済ませておかなければならないため、最初はやや面倒です。
一度手続きを済ませてしまえば、あとは翌年以降も自動で引き落としが行われます。
ただし、口座残高が足りないと引き落としできないため注意しましょう。その場合には、後日納付書が送付され、その納付書を使用して納付しなければなりません。
大半の自治体では、クレジットカードでの住民税の支払いにも対応しています。口座振替と同様に、あらかじめ手続きが必要ですが、一度手続きを済ませてしまえば自動的に支払いができるため便利です。
クレジットカードの場合には、残高不足で引き落としできない心配もありません。また、クレジットカードの種類によっては、住民税の支払いでもポイントが付く場合もあります。ただし、通常のショッピングなどとは異なり、手数料も発生するため注意が必要です。
住民税の税額とクレジットカードのポイント還元率によっては、必ずしもお得になるとは限りません。
Pay-easy(ペイジー)というサービスを利用して、インターネットやATMで住民税の支払いが可能です。住民税の納付書にPay-easyのロゴと番号が記載されているのを確認しましょう。
具体的な操作方法はインターネットバンキングによって異なりますが、Pay-easyの番号を入力して支払いができます。ATMを使用する場合も同様です。インターネットバンキングの場合には、自宅にいながら曜日や時間帯などと問わずいつでも住民税の納付ができます。
住民税の納付書には「eL-QR」という地方税統一QRコードが付いています。このQRコードをスマホ決済アプリで読み取ることで、住民税を納付できます。クレジットカード払いとは異なり、手数料の負担もありません。スマホ決済アプリの種類によってはポイントが付く場合もありお得な支払い方法です。
また、自治体によってはeL-QRだけでなく通常のバーコードを読み取って納付できるところもあります。
特別徴収の場合には、住民税は給与から天引きされるため、滞納してしまうということは通常ありません。しかし、普通徴収の場合には払い忘れなどにより、納期限が過ぎていても納付されないという事態がありえます。その場合には注意が必要です。
納期限が過ぎて数日経過すると督促状が送付されてきます。この段階ですぐに納付すれば特に大きな問題はありません。督促手数料が100円程度上乗せされるだけです。
しかし、督促状が送付された後も、納付しないままだと延滞金が課せられます。滞納は極力避けるようにしましょう。
年間の所得から各種控除を引いた課税所得に対して約10%が住民税として課税される仕組みになっています。
月収20万円の場合、住民税はおおよそ月々8,000円〜10,000円程度となります。具体的な金額は、扶養家族の有無や各種控除の適用状況、お住まいの地域によって金額が変わる可能性があることをご考慮ください。
また、住民税は前年の所得に対して課税されるため、昨年と今年で収入が大きく変わる場合は注意が必要です。
年間の所得から各種控除を引いた課税所得に対して約10%が住民税として課税される仕組みになっているため、月収30万円の方の住民税額は、一般的に月額12,000円〜15,000円ほどになります。
ただし、扶養家族の有無や各種控除の適用状況、お住まいの地域によって金額が変わる可能性があるため、目安として捉えてください。
住民税が課税されないおもなケースとしては、年収が一定額以下の方が挙げられます。
具体的には、給与所得のみの単身者で年収100万円以下、または控除後の課税所得が45万円以下の場合は非課税となることが多いです。
また、生活保護を受給している方や障害者手帳をお持ちの方で一定の条件を満たす場合も非課税措置があります。
住民税の額は、前年の1月から12月までの所得を基に計算されます。
計算方法としては、総所得金額から各種控除を差し引いた課税所得に対して、一律10%程度の税率が適用されるのが基本です。この10%は都道府県民税4%と市区町村民税6%に分かれています。
さらに、均等割という定額部分が加わり、都道府県民税と市区町村民税合わせて年間約5,000円が上乗せされます。
自治体によって細かい税率や控除の扱いが異なる場合もあるため、詳しくは居住地の市区町村に確認するとよいでしょう。
住民税が課税されるのは、基本的に年収100万円前後からと考えられます。ただし、これは単身者で給与所得のみの場合の目安であり、扶養家族の有無や控除の状況によって大きく変わります。
正確には、所得控除額の合計が課税所得を下回った場合に課税対象となります。
たとえば、給与所得控除や基礎控除などを適用した後の課税所得が45万円を超えると、住民税が課税される仕組みです。パートやアルバイトの方も、年収が103万円を超えると住民税がかかり始めるケースが多いので気をつけましょう。
住民税は所得割と均等割に分かれており、このうち均等割は5,000~6,000円程度で一定額です。
所得割は所得金額から各種控除を差し引いた金額に税率の10%をかけて計算されます。所得税とは異なり、累進課税ではありません。税額控除がある場合には、税率をかけて算出された金額からさらに差し引かれます。控除項目は所得税とほとんど同じですが、金額が異なる項目もいくつかあり、全体的に住民税の方が控除が少なめです。
住民税の負担を軽減するためには、控除を最大化することが効果的です。比較的所得が高めの人でも、iDeCoやふるさと納税を活用することで住民税を安くできる可能性があります。住民税が高いと感じる場合には利用できる控除がないかどうかを確認してみましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
