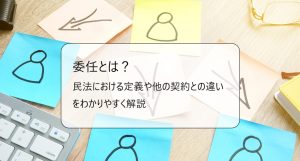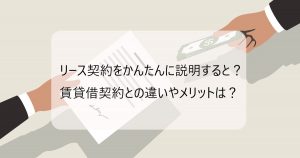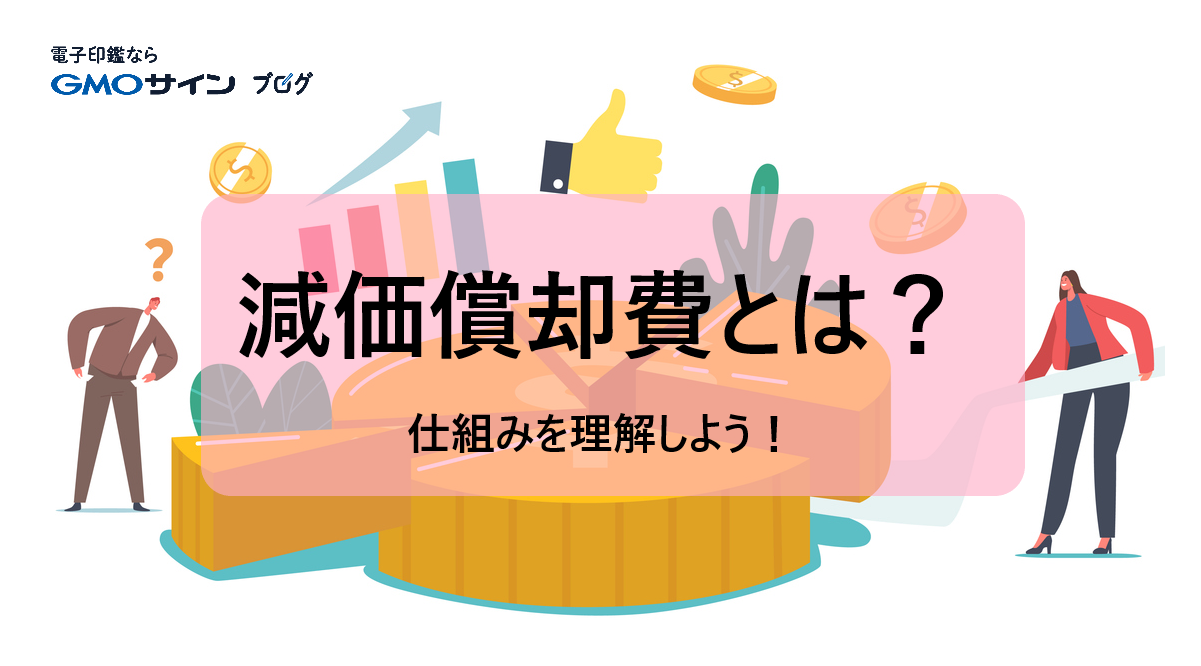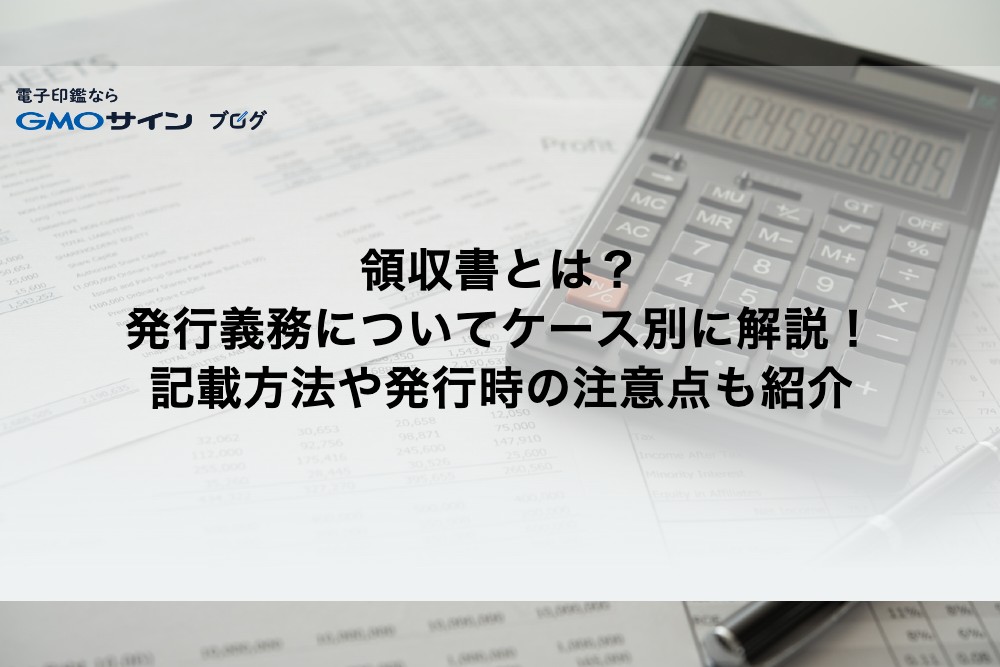地震保険に加入していれば、大きな地震が発生して自宅が被害に遭った場合でも一定の補償を受けられます。万が一に備えて地震保険に加入しようかどうか迷っている人も多いでしょう。ただ「地震保険はいらない」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
住んでいる地域や環境は、人によって異なります。実際に、地震保険の必要性があまり高くない人もいるでしょう。医療保険や死亡保険などにも加入している場合、これ以上保険料の負担を増やしたくないと考えるケースもあるかもしれません。
本記事では、地震保険の内容をかんたんに解説し、必要かどうか考察していきます。
地震保険とは
地震や噴火などが原因で火災が発生したり自宅が損壊、埋没、流失した場合などに補償を受けることができます。
通常の保険商品とは異なり、地震保険に関する法律に基づいて政府が再保険する仕組みが採られているのが特徴です。
再保険というのは、万が一の際に責任の一部をほかの保険会社に転嫁する保険契約であり、地震保険に関しては政府が責任の一部を引き取り、補償するものです。
そのため、具体的な補償内容や保険料に関しては、どの保険会社でも違いはありません。
また、地震保険は火災保険の付帯保険という扱いです。そのため、地震保険を単体で契約することはできません。火災保険を契約していることが前提とされています。
地震保険の補償対象となる財産の種類
大きな地震が発生すると自宅の建物だけでなく、自宅の中に置いている家財道具なども倒れて破損することがあるでしょう。地震が原因で火事になってしまうと、さまざまなものが燃えてしまいます。
地震保険では補償対象を
・建物と家財
・建物のみ
・家財のみ
の3パターンから選択可能です。
また、家財に関しては無制限に対象になるわけではありません。家財が補償対象になっている場合でも、補償対象外になるものがいくつかあります。
たとえば、小切手や商品券などの有価証券や印紙、切手、預貯金証書は対象外です。宝石や貴金属類、骨董品などは価額が30万円までのものしか対象になりません。自動車も対象外です。
建物に関しては地震保険は住宅を対象としているものであるため、工場や事務所などとして使われている部分は除外されます。
地震保険の補償金額
また、損壊の程度は
・全損
・大半損
・小半損
・一部損
の4段階で判定され区分される仕組みです。
全損なら保険金額の100%、大半損なら60%、小半損なら30%、一部損なら5%補償されます。ただし、時価額による制限が設けられており、いずれの区分も時価額に対する同じパーセンテージを超えて補償を受けることはできません。たとえば大半損なら時価額の60%が限度です。
地震保険の保険料
地震保険の保険料は保険金額に保険料率をかけた金額です。保険料率というのは基本料率に割引率と長期係数をかけて算出されます。では、基本料率と割引率、長期係数について、それぞれどのようなものなのか見ていきましょう。
基本料率
基本料率は建物の構造区分と地域で決まる数字です。建物の構造区分はイ構造とロ構造の2種類に分類されます。耐火性の高い建物はイ構造に分類されており保険料が安くなる仕組みです。
地域は地震の発生頻度などを考慮して分類されています。主に太平洋側など地震が発生しやすい地域は高めで、日本海側など地震の少ない地域は安いという設定です。
割引率
4種類の割引制度が設けられており、該当する場合には保険料が割引になります。
・免震建築物割引
・耐震等級割引
・建築年割引
・耐震診断割引
もっとも割引率が高いのは免震建築物割引で50%の割引を受けられます。また、耐震等級割引は耐震等級に該当する場合に割引を受けることができられて、割引率は耐震等級によって異なります。耐震等級1の建物なら10%、2の建物なら30%、3の建物なら50%です。
建築年割引は新耐震基準が施行された1981年6月1日以降に新築された建物の場合に適用されて割引率は10%です。耐震診断割引も10%の割引が適用されます。
長期係数
長期係数は保険期間によって決まる数字で、長期契約ほど割引率が高くなります。5年が最大です。
地震保険への加入が必要な理由
地震保険は必要ないと考える人もいるかもしれませんが、地震保険への加入を迷っているなら加入しておくのが無難です。では、なぜ地震保険への加入が必要なのか、主な理由について見ていきましょう。
日本は地震大国
日本は世界的に見ても地震が多い国です。
東日本大震災や能登半島地震などをはじめとして、大きな地震がたびたび発生しています。これまで地震の被害が少なかった地域でも大地震が発生することがあり、日本国内であればどの地域に油断はできません。
また、近い将来に南海トラフ大地震が発生する可能性があるといわれています。もし本当に南海トラフ大地震が発生してしまうと、西日本の太平洋側の地域では甚大な被害が出てしまうでしょう。西日本の日本海側や首都圏の地域も震度5弱程度の揺れになるものと予想されています。
こうしたリスクに備えたいのであれば、地震保険への加入は必要です。
政府の支援だけでは不十分
大きな自然災害が発生すると、政府が一定の支援を行ってくれる可能性が高いです。東日本大震災や能登半島地震においても、政府による支援が行われました。
政府が行う支援は、あくまで被災直後の生活を一時的に支援する程度にとどまります。仮設住宅なども提供されますが、数年しか住むことはできません。仮設住宅に住んでいる間に、自宅を修復して住めるようにするためには、地震保険が必要です。
二重ローンになるリスクを回避するため
家の住宅ローンを現在返済中だという人もいるでしょう。もし、ローン返済中に大地震で住宅が損壊してしまうと、住宅ローンを返済しながら修繕や再建をすることになります。かんたんな修繕であれば、それほど負担は大きくないかもしれません。しかし、被害状況によっては大がかりな工事が必要になることもあります。修繕が難しく建て替えざるをえないこともあるでしょう。
大がかりな修繕や建て替えには多額の費用が必要で、キャッシュでの支払いが難しくローンを組むケースも多いです。そうなると、もとの住宅ローンの返済もあるため、二重ローンになってしまいます。
地震保険に加入していれば、修繕や建て替えの費用の一部が補償されるため、二重ローンを回避できることも多いです。二重ローンになってしまったとしても、金額は抑えられるでしょう。
地震保険がいらないという意見が見られる理由
地震保険はいらないという意見では、主に次のようなことを理由としています。
保険料の負担が大きい
地震保険の保険料が高いことで、地震保険はいらないと考える人は多いです。保険料は条件によって差があり、一概に高いわけではありません。しかし、鉄骨・コンクリート造の建物でも保険金額1,000万円の場合で年間27,500円の都道府県もあります。木造の場合にはさらに高く41,100円です。
経済的な余裕がない場合には、保険料の負担が大きく感じられるでしょう。そうなると、どうしても優先度は低くなってしまいます。そもそも現在火災保険に入っていない人だと、火災保険に入った上で地震保険に入る必要があるため、さらに負担が大きく感じられます。
保険金だけでは修繕や再建をするのに足りない
地震保険に加入していて、実際に地震の被害を受けて保険金が降りる場合でも、安心できるわけではありません。保険金だけで修繕や再建できるケースは希で、被災した大半の人は保険金に自己資金を加えて修繕や再建をしています。
また、損壊の程度を判定する基準は厳しいのが実情です。全損であれば延べ床面積の70%以上を焼失または流失していなければ判定されません。大半損でも50〜70%という基準です。そのため、小半損や一部損と判定されてしまうケースも多いです。
一部損だと保険金額の5%が限度となりますから、全然足りないでしょう。一部損でも修繕工事をするとなれば、それなりに大きな金額になります。保険料が高い割に受け取れる保険金が少ないということで、地震保険はいらないと考える人もいるでしょう。
地震保険の必要性が特に高い人
次のような状況の人は地震保険の必要性が特に高く、加入しておくのがおすすめです。
地震のリスクが高い地域に住んでいる人
たとえば東日本大震災の被害が大きかった東北地方の太平洋側などが挙げられます。南海トラフ大地震で大きな被害が予想される西日本の太平洋側に住んでいる人も加入しておくのが無難でしょう。
また、住んでいる場所が海沿いや山沿いかどうかなども重要です。
海沿いの地域は大きな地震が発生した際に、津波による被害が懸念されます。山沿いの地域だと土砂崩れによる被害を受ける可能性があるでしょう。地震の他に噴火による被害を受けることもあります。そのため、山から遠い内陸の地域よりは地震保険の必要性が高めです。
住宅ローンを返済中の人
住宅ローンを返済中の人も、地震保険に加入しておくのが無難です。保険料の負担は大きいかもしれませんが、万が一被災した場合に二重ローンのリスクを回避できます。
地震の被害による収入への影響が大きい人
地元の中小企業に勤務している人や自営業で店舗を構えている人などは、大地震で被害を受けると仕事への影響も大きいです。収入が大きく減ってしまう可能性があります。地震保険に加入して備えておく必要があります。地震保険への加入の必要性が高いといえるでしょう。
地震保険の必要性があまり高くない人
地震保険は基本的には加入しておくのが無難ですが、次のような状況の人はそれほど必要性が高くありません。
耐震性の高い家に住んでいる人
耐震性の高い家なら大きな地震が発生しても、損壊せずに済む可能性があります。損壊していなければ、保険金が降りることもありません。そのため、地震保険に加入しないという選択肢もありでしょう。
住宅ローンを完済している人
住宅ローンを完済しているのであれば、建物が損壊し、立て直しとなっても二重ローンになってしまうことはありません。また、住宅ローンを完済しているくらいだと、建物の築年数が長いことが多いででしょう。割引制度にも該当しづらく、保険料も高くなりがちです。そのため、地震保険の必要性はあまり高くないといえます。
まとめ:万が一の事態に備えて地震保険への加入を検討しておこう
地震保険に加入していれば大きな地震が発生したときの被害に備えておくことができます。しかし、地域や建物の構造によっては保険料が高くなりがちです。保険金が降りても、修繕や再建をするのに足りない可能性があります。そのため、地震保険は必要かどうか疑問に思ってしまう人もいるかもしれません。
少しでも負担を軽くするため、地震保険に加入しておくのがおすすめです。特に地震の多い地域や海沿い、山沿いなどに住んでいる人で、現在地震保険に加入していない人は加入を検討してみましょう。