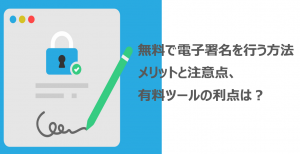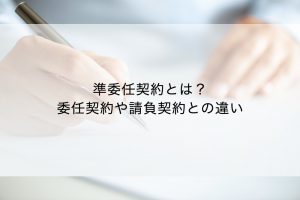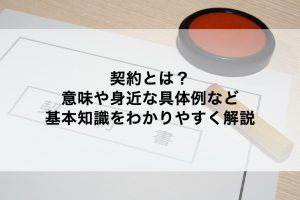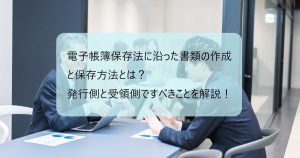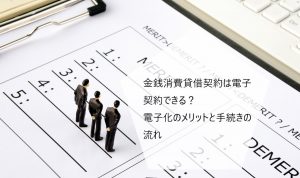\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /
\\ 期間限定キャンペーン実施中 //
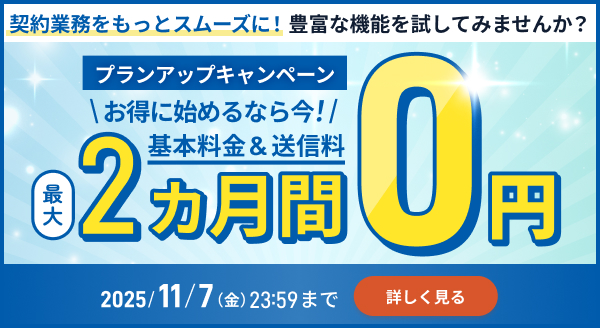
【予告】GMOサイン10周年特別セミナー


形式的証拠力と実質的証拠力の違いは?
文書の成立の真正という概念と証拠力にはどのような関係性がある?
裁判で文書が証拠として認められるための具体的な要件を知りたい!
文書の証拠力を正しく理解せずに契約を進めてしまうと、いざというときに法的効力が認められず、大きな損失を被るリスクがあります。この記事では、形式的証拠力と実質的証拠力の基本概念から、文書の成立の真正との関係性まで、法的根拠とともに詳しく解説します。
万一の紛争時にも確実な証拠力を確保するためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。
電子契約は従来の紙の契約書と比べて、タイムスタンプや電子署名により文書の改ざんが困難になるため、形式的証拠力を確保できます。また、作成者の特定や作成日時の記録が自動化されるため、実質的証拠力の根拠となる事実関係もより明確にすることが可能です。
法的リスクを最小限に抑え、確実な証拠力を持つ契約書を作成するために、ぜひGMOサインの導入をご検討ください。
裁判では「証拠」が事実認定の基礎となりますが、その証拠には「形式的証拠力」と「実質的証拠力」という2つの異なる概念があります。
民事訴訟や刑事訴訟において、証拠の価値は単純に「あるかないか」だけで決まるものではありません。証拠として法廷に提出されるまでの過程と、その証拠が事実を証明する力の強さという、2つの側面から評価される必要があるのです。
この2つの違いと役割を理解することで、いざというときに法的証拠力が認められる契約書を作成できるようになります。まずはそれぞれの違いを理解しましょう。
形式的証拠力とは、その文書が本当に作成者本人によって作成されたものであると法的に認められる力を指します。たとえば、「この契約書は確かにA社とB社が正式に作成したものだ」と認定される根拠となります。
民事訴訟法228条では「文書が真正かどうかを証明する必要がある」と決められており、作成者本人によるものではないとみなされた場合、その文書は証拠としての効力を失います。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
引用:e-Gov法令検索
具体的には、文書であれば作成者の署名や印鑑の確認、電子データであれば改ざんされていないことの立証などが求められます。これらの要件を満たさない証拠は、内容がどれほど重要であっても、裁判所は証拠として認めません。
実質的証拠力とは、証拠の内容がどの程度信用できるか、つまり事実認定にどれだけ役立つかを示す力のことです。形式的証拠力が「誰が作ったか」を問題にするのに対し、実質的証拠力は「何が書かれているか」「それがどの程度信頼できるか」を重視します。
裁判官は実質的証拠力を判断する際、証拠の内容とほかの証拠との整合性、証拠が作成された状況や作成者の信頼性などを総合的に考慮します。判断は裁判官の自由心証に委ねられており、同じ証拠でも裁判官によって評価が変わる場合があります。そのため、法的紛争では実質的証拠力を高めるための立証活動が重要になるのです。
(自由心証主義)
引用:e-Gov法令検索
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
たとえば、日記の記述であっても、ほかの客観的証拠と一致していれば実質的証拠力は高くなるでしょう。逆に、公的文書であっても記載内容に矛盾があれば、実質的証拠力は低く評価される可能性があります。
電子契約を利用すると、署名プロセスやタイムスタンプ、アクセス履歴などが自動的に記録されるため、契約がどのような経緯で成立したかを客観的に示しやすいという特徴があります。実質的証拠力を高めたい場合は利用を検討することをおすすめします。
前の章で、形式的証拠力と実質的証拠力について解説しました。実際の現場では「文書の成立の真正」という考え方も加わり、これらが連動して文書の証拠価値が決まります。
文書の成立の真正が認められることで形式的証拠力が生まれ、そのうえで実質的証拠力が判断されるという流れを理解することが大切です。
この章では3つの役割の違いと、証拠として認められる「二段の推定」の仕組みについて解説します。
形式的証拠力と実質的証拠力、文書の成立の真正の定義と役割は以下のように異なります。
| 概念 | 判断内容 | 役割 |
|---|---|---|
| 文書の成立の真正 | 文書が本人によって作成されたか | 証拠認定の前提 |
| 形式的証拠力 | 文書の成立が法的に推定されるか | 証拠能力の判断 |
| 実質的証拠力 | 文書内容の事実としての信用性 | 証拠価値の判断 |
文書の成立の真正は、「この文書は確実にその人が作ったもの」という事実を認めることです。これが認められると形式的証拠力が生まれ、文書が証拠として法廷で認められることになります。
実質的証拠力は、文書の内容が本当に事実なのかを判断するものです。以下のようにさまざまな事情が総合的に考慮されます。
たとえば、契約書に「100万円を支払う」と書かれていても、実際にその支払いがあったかどうかは銀行の振込記録や領収書などの裏付けが必要です。
つまり、裁判における証拠評価は、以下のようなステップで進みます。
このように、文書が裁判で有効に機能するためには、段階的なハードルを越える必要があるのです。
民事訴訟法第228条第4項に規定される「二段の推定」は、押印のある私文書の成立の真正を証明しやすくするための重要な法的仕組みです。具体的には、以下の2つのステップで推定が働きます。
この二段の推定によって、文書の成立を主張する側は、原則として印影が本人の印鑑のものであることを証明すればよくなり、証明の負担が大幅に軽減されます。この推定は、文書の形式的証拠力を確保する上で極めて重要な役割を果たします。
ただし、成立の真正が認められた後の実質的証拠力の評価は、裁判官の自由心証に委ねられているため、二段の推定とは別の問題として扱われます。
\\ こちらの記事もおすすめ //

これまで紙契約における証拠力について説明しました。ところで、近年注目されている電子契約では、どのような仕組みになっているのでしょうか。
電子契約では、電子署名とタイムスタンプが紙契約の押印・署名の役割となります。つまり、適切な電子署名があれば文書の成立の真正が認められます。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:e-Gov法令検索
法的証拠力の高い電子契約を結びたいとお考えの方は、GMOサインのような電子署名法や電子帳簿保存法に準拠した電子契約サービスの利用をおすすめします。
電子契約サービスを利用することで、電子契約は紙契約と同じかそれ以上の証拠力を持たせることが可能です。
証拠力の仕組みを理解したら、次は実際の業務でどう活かすかが大切です。形式的証拠力と実質的証拠力の両方を高めるためには、署名権限の管理から契約内容の書き方、文書の保管方法まで、実務での対策が必要になります。
ここでは法務部や事業者が日常業務で実践すべき4つのポイントを解説します。
契約書の形式的証拠力を確保するためには、署名や押印を行う人の権限が明確でなければなりません。代表取締役や部門長など、契約締結の権限を持つ人が署名することで、「この契約は会社として正式に結んだもの」という推定が働きます。
実務では、社内で誰がどの契約に署名できるかを明確にルール化することが大切です。
このように金額別に権限を定めます。また、署名者の印鑑証明書や委任状を管理し、必要に応じて相手方に提示できるよう準備しておきましょう。
権限のない人が署名した契約書は、あとで「その人に契約権限はなかった」と争われるリスクがあるため、ご注意ください。
実質的証拠力を高めるためには、契約内容を具体的に記載することが大切です。「何を」「いつまでに」「どのように」「いくらで」行うのかを明確に書くことで、当事者間の権利義務関係がはっきりし、後のトラブルを防げます。
たとえば、業務委託契約では次のように書きます。
悪い例: 「A社はB社に対し、システム開発業務を委託する。」
良い例: 「A社(委託者)はB社(受託者)に対し、別紙仕様書記載の顧客管理システムの設計、プログラミング、及びテストを含む開発業務を、契約金300万円(税別)で委託する。B社は本システムを2025年12月31日までにA社に納品し、A社は納品後10営業日以内に検収を行う。」
このような具体的な記載により、契約書の内容が事実として信用されやすくなります。
\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書は作るだけでは不十分です。きちんと保管しないと意味がありません。紛失や改ざんを防ぐため、管理の仕組みを作ることが大切です。
契約書の保存期間を法的要件に基づいて設定し、期限管理も行いましょう。仕組み化された管理により、必要なときに確実に契約書を提示でき、改ざんされていないことを証明できます。
電子契約を導入することで、紙の契約書以上の証拠力を確保できます。電子署名法に準拠したサービスを利用し、タイムスタンプを付与することで、文書の真正性と完全性を技術的に保証できるためです。
電子契約サービスを選ぶときは、次の3つを確認しましょう。
これらの機能により、「誰が」「いつ」署名したかが確実に記録され、改ざんが技術的に不可能になります。署名プロセスがシステム上で自動記録されるため、署名の経緯も証拠として残すことが可能です。
電子契約は業務効率化だけでなく、証拠力の向上という法的メリットも大きいため、ぜひ導入を検討してみてください。
形式的証拠力は「文書が真正かどうか」、実質的証拠力は「文書の内容が事実かどうか」を判断する基準です。どちらの基準も契約書を作るうえで欠かせないものです。企業の実務においては次のことが重要になります。
しかし、これらすべてを手作業で管理するのは手間でしょう。
そこでおすすめなのが電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの導入です。電子署名法に準拠した電子署名やタイムスタンプにより、形式的証拠力と実質的証拠力の両方を確保できます。
GMOサインのお試しフリープランなら月5件までの電子契約が無料でご利用いただけます。確実な証拠力を持つ契約書を作成したい方は、無料プランからぜひ試してみてください。
免責事項(本記事のご利用にあたって)
本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。