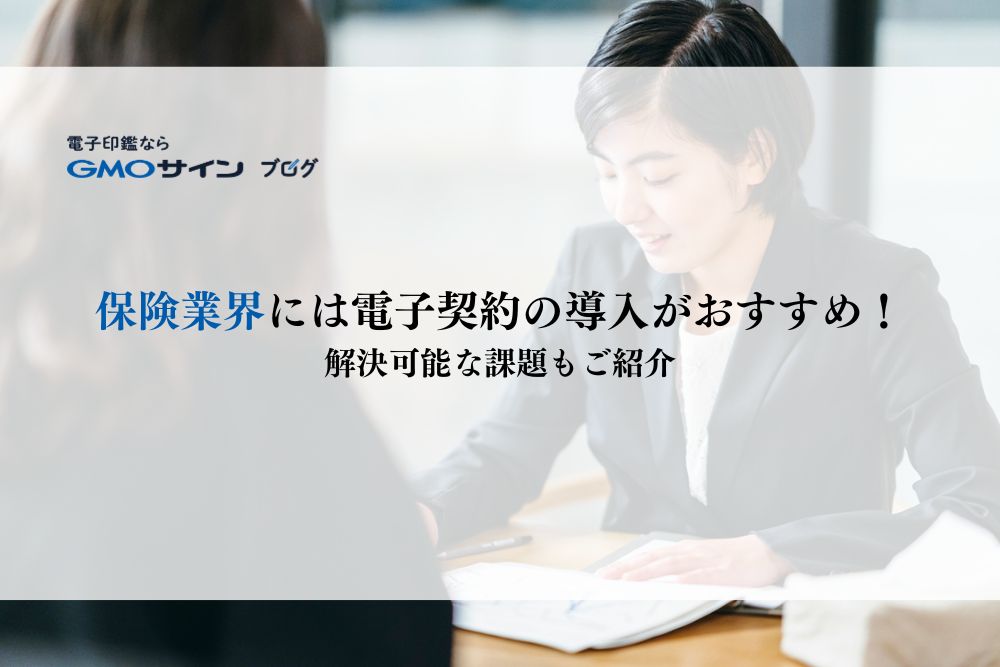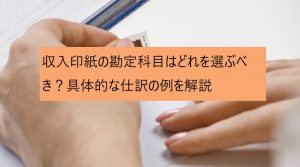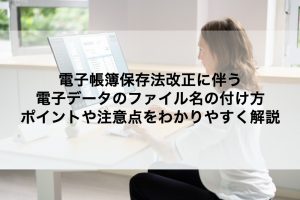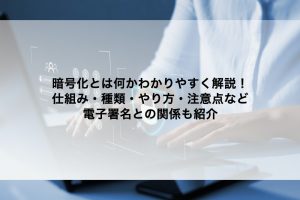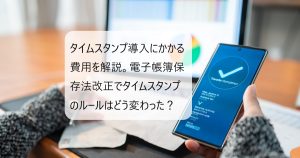業務システムとの連携を検討しているけど、
どの電子契約サービスのAPIが自社にあっているかわからない…
セキュリティ面や法的有効性についてはどのような問題がある?
実装や運用にどれくらいのコストと工数がかかる?
要件整理が不十分なままAPI連携を進めると、期待した業務効率化が実現できず、システム改修の二度手間やコスト増につながるおそれがあります。この記事では、電子契約サービスのAPI連携について、具体的な活用事例や導入手順、注意点まで詳しく解説します。
- 電子契約のAPI連携を導入することで得られるメリット
- ほかの業務システムと連携した活用事例
- 具体的な導入事例で見る実現できる業務改善
- API連携を導入する際に注意すべきポイント
電子印鑑GMOサインでは、BOXやkintone、Salesforceなど、さまざまなSaaSとの連携が可能です。

SFAやCRMと連携することで契約書作成から送信、ステータス管理までを自動化でき、営業部門の生産性を大幅に向上できます。また、ERPや会計システムと連携することで、部門間の契約関連フローをシームレスに接続し、経理・総務業務の負担軽減にもつながります。
- さまざまなサービスとのAPI連携により柔軟なシステム連携が可能
- 電子帳簿保存法や電子署名法に対応した高い法的証拠力
- IPアドレス制限やOAuth対応など堅牢なセキュリティ機能
- ワークフロー構築や自動化も視野に入れた豊富なオプション機能
業務システムとの連携を成功させるためには、APIの仕様だけでなく、サポート体制や導入後の運用まで視野に入れた選定が重要です。GMOサインでは、API仕様書の提供はもちろん、導入支援サービスも充実しています。資料請求や導入サポートを活用し、自社に最適な連携方法を検討してみてはいかがでしょうか。
電子契約サービスのAPI連携とは?
業務を効率化するうえでAPI連携はとても重要ですが、「どんな機能があり、なぜ必要なのかよく分からない」という方も多いかもしれません。ここでは、電子契約サービスのAPI連携がなぜ大切なのか、また連携で実現できる主な機能について、わかりやすく解説します。
APIとは?電子契約サービスと連携することの重要性
API(Application Programming Interface)とは、複数のプログラムをつなぐ機能のことです。かんたんに言えば、異なるシステムやサービス間で情報のやり取りを可能にする仕組みを指します。
たとえば、営業支援ツール(CRM)と連携すれば、営業担当者が顧客情報を入力するだけで、その内容をもとに契約書が自動で作られます。さらに、その契約書をワンクリックで送信したり、署名の進捗状況をシステム上でリアルタイムに確認したりすることも可能です。
これにより、手作業による入力ミスや書類のやりとりの手間が大幅に減り、スムーズに契約業務を進められます。API連携は多くの企業にとって役立つ技術といえるでしょう。
電子契約サービスのAPI連携で実現できる代表的な機能
電子契約サービスのAPI連携で実現できる機能としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自動化機能
営業担当者が顧客情報を入力するだけで、契約書の作成から送信までを自動で行えます。 - リアルタイム監視
契約書の進捗状況や署名の有無を、すぐに確認でき、必要な通知を受け取れます。 - 法的証拠管理
契約書のデータを長期間安全に保存し、証明書も発行できるので安心です。 - 外部システム連携
ほかの業務システムとつなげることで、社内の業務フローをひとつにまとめて効率化できます。
従来の手作業による契約書作成から締結・保管まで一連のプロセスを、既存の業務システムと統合して効率化できます。これにより、契約業務の完全自動化を果たせるでしょう。
\\ こちらの記事もおすすめ //
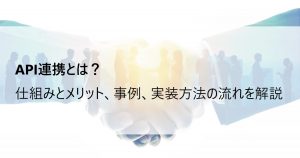
電子契約サービスのAPI連携のおもな活用シーンとメリット
電子契約サービスのAPI連携には、さまざまな使い方があります。ここでは、具体的にどんな場面で役立つのか、またそれぞれのメリットについてわかりやすく説明します。
CRM・SFA連携による契約業務の効率化
CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)と連携することで、顧客情報や商談情報を自動的に契約書に反映させられます。自動化によって手作業でのデータ入力を省けるので、業務効率がアップし、ミスが生じにくい仕組みも作れます。
さらに、契約ステータスがリアルタイムでCRMに反映されることで、営業マネージャーは案件の進捗を即座に把握できるようになります。従来は契約書の作成から送付、署名状況の確認まで複数のシステムを行き来する必要がありましたが、API連携により一つの画面で全てを管理できるのです。
文書管理システム連携による契約文書の一元管理
電子契約サービスとBoxやGoogle Driveなどの文書管理システムをAPI連携することで、契約文書の保管・検索・共有が格段に効率化されます。
締結済みの契約書が自動的に指定のフォルダに格納され、契約種別や取引先、契約期間などのメタデータも同時に付与されるため、必要な契約書を瞬時に検索することが可能です。手作業による手間やミスが大幅に減り、業務のスピードと正確さが大きく向上します。
また、アクセス権限の設定を自動化でき、部門ごとに閲覧可能な契約書を制御することも可能になります。監査対応時には、特定期間の契約書を一括でエクスポートでき、コンプライアンス体制の強化も図れるでしょう。
ERP・会計システム連携による契約管理と部門間連携の最適化
ERPや会計システムとの連携により、契約情報と財務情報を紐づけた管理が実現できます。契約締結と同時に売上計上や請求処理のプロセスが自動的に開始され、経理部門の作業負担は大幅に軽減されるでしょう。
特に複数年契約や分割払いの案件では、この連携の効果が顕著です。契約内容に合わせて自動的に請求スケジュールが作られ、契約の変更や解約があった場合も、その情報がすぐに会計システムに反映されます。これにより、作業負担の軽減はもちろんのこと、請求漏れや金額の間違いといったミスを防げる効果もあります。
営業部門が締結した契約の内容を経理部門がリアルタイムで確認できるなど、部門間の情報共有も円滑になるでしょう。
ワークフローシステムとの連携による業務スピード向上
契約締結には多くの場合、社内承認プロセスが必要です。承認ワークフローシステムと電子契約サービスをAPI連携させることで、契約書の作成から承認、締結までの一連のプロセスが大幅に短縮されます。承認者が出張中でも、スマホから契約内容を確認して承認できるため、意思決定の遅延を防げます。
承認履歴も全て記録されるため、誰がいつ承認したかが明確になり、監査対応時の証跡としても活用できます。内部統制の観点からもメリットは大きいといえるでしょう。
HR・人事システム連携による担当者の負担軽減
人事システムと連携すれば、雇用契約書や労働条件通知書などを自動で作成・管理できるので、作業がとても効率的になります。たとえば、従業員の情報をもとに必要な書類が自動で作られるため、入社手続きにかかる時間や手間を大幅に減らせます。
新入社員の情報は人事システムから自動的に取得されるため、氏名や住所、雇用条件などの基本情報を何度も入力する必要がありません。雇用形態に応じた適切な契約書テンプレートが自動選択され、法令に準拠した正確な書類作成が可能となります。
また、契約更新時期の管理も自動化され、有期雇用契約の更新漏れの防止にも役立ちます。人事担当者は事務作業から解放され、より重要な仕事に集中できるようになるでしょう。
電子契約サービスと他社システムの連携事例
電子契約サービスとAPI連携を導入するにあたって、実際の事例を参考にしたい方も多いでしょう。ここからは、GMOサインと他社システムを連携した事例について紹介します。
事例をもとに、どのような課題を解決できるのか確認してみてください。
沖縄綜合警備保障株式会社:ミスなくスピーディーな契約の締結が可能に
沖縄綜合警備保障株式会社では、長年使っていたシステムで警備請負契約書と工事発注書を別々に手作業で作成していたため、作業の手間がかかったり、ミスが起きたりする問題がありました。そこで、クラウド型の販売管理システム「楽楽販売」とGMOサインのAPIを連携させて、業務の効率化を図りました。
楽楽販売とGMOサインとのAPI連携により実現したことは、契約情報を登録すると自動的に契約書や発注書がGMOサイン経由で送信され、締結まで完結できるようになったことです。月150件の書類のうち約7割が電子化される見込みで、「ミスなくスピーディーに処理できるようになった」と効果を実感されています。
このように、沖縄綜合警備保障株式会社では「楽楽販売」とGMOサインのAPIを連携させたことで、手作業やミスの多かった契約業務が大きく改善されました。
>「楽楽販売」と電子印鑑GMOサインのAPI連携で実現したミスなくスピーディな契約の締結
株式会社マクアケ:契約締結プロセスの可視化と契約締結のスピードアップを実現
株式会社マクアケでは、紙契約に伴う封入・郵送といった手間や印紙代が重くのしかかっており、業務負荷とコスト負担が問題視されていました。そこでGMOサインを活用し、業務委託契約書やNDA、取締役会議事録などで電子契約を導入しています。
さらに、以前からファイル共有に利用していたBoxとのAPI連携も行い、さらなる業務効率化を模索されています。
- 契約締結後の指定フォルダへの契約書格納
- 契約種別や取引先名、契約期間などの情報で必要な書類をすぐに検索
- 部門ごとやプロジェクトごとの閲覧制限(アクセス権限)
- 過去の契約書の一括エクスポート
こうした作業を効率化できるため、株式会社マクアケのように契約書の数が多い大企業や、複数の部署や拠点で契約管理が必要な企業、監査やコンプライアンス対応が求められる業種に特に役立つでしょう。
>わずか1日での契約締結を実現。圧倒的にスピーディーかつ効率的に締結業務を完了
ランサーズ株式会社:セールスフォースとの連携で業務フローをスリム化
日本最大級のクラウドソーシングを提供するランサーズ株式会社では、煩雑なPDFのダウンロードやメール送付、保管といった手作業が多く、遅延や改ざんリスクも懸念されていました。そこで、Salesforce上で帳票を作成し、API連携によって電子署名依頼から送付、管理までシームレスに処理できるようにしました。
結果として紙ベースで発生していた作業が削減され、業務効率の改善を実現しています。また、電子署名による証跡管理と作業に関わる人員の削減から、改ざんのリスクも減らせました。
担当者からは「ストレスを感じることがありません」「スピード感の違いに怖さを感じるくらい」といった声が挙がっています。業務効率に課題を感じている方は、ぜひGMOサインをお試しください。
>セールスフォース×電子印鑑GMOサインで帳票作成から送信、電子署名。そして文書管理までをシームレスに
主要な電子契約サービスのAPI対応状況を比較
国内では以下のような電子契約サービスが代表的です。自社にあったサービスを選べるよう、それぞれのAPI対応状況について解説します。
| サービス名 | API利用可能プラン | API利用料金 (月額/税抜) | 連携サービス例 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 電子印鑑GMOサイン | お試しフリープラン以外 | 10,000円 ※別途初期費用 | Salesforce, kintone, Box, Power Automate, LegalForceなど多数 | ・豊富なAPI機能と多様なサービス連携 ・堅牢なセキュリティと高い法的証拠力 ・手厚い導入サポート |
| クラウドサイン | Corporateプラン以上 | 28,000円~(プラン料金) | kintone, Salesforce, Hubble, バクラク申請など100以上 | ・弁護士ドットコムが提供 ・連携サービス数が豊富 ・充実したチャットサポート |
| マネーフォワードクラウド契約 | フル機能版プラン | 要問い合わせ | Salesforce, Slackなど | ・マネーフォワードの他サービスと親和性が高い ・申込書作成から保管までを効率化 |
| WAN-Sign | 要問い合わせ | 要問い合わせ | intra-mart, kintone, OPTiM Contractなど | ・情報資産管理のプロであるワンビシアーカイブズが提供 ・一括署名機能に強み |
※2025年8月時点の情報です。最新の料金やプラン詳細は各公式サイトをご確認ください。
電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサインでは、外部のCRMや基幹システム、帳票システムなどさまざまなサービスをAPI連携できます。GMOサインの各機能を連携することで、契約書の作成や稟議承認、締結、書類保管までをシームレスに実行可能です。利用できるおもなAPIについては、以下のようなものが挙げられます。
| おもなAPI | 詳細 |
| 認証 | ・アクセストークン生成 ・トランザクションID取得 |
| 登録・削除 | ・文書アップロード ・文書情報登録 ・文書取得・削除 ・ユーザー登録・更新・削除 |
| 署名 | ・署名位置設定 ・署名処理実行 |
| 情報取得 | ・文書詳細情報 ・管理番号取得 ・追加フィールド情報取得 ・操作ログ取得 |
また、連携できるサービスの一例は以下のとおりです。
- Salesforce
- kintone
- Box
- Power Automate
- LegalForce
- AgileWorks
- X-point
- ActRecipe
- ダンドリワーク
(引用:外部サービス連携|電子印鑑GMOサイン)
クラウドサイン

弁護士ドットコム株式会社によって提供されるクラウドサインでは、Salesforceやサイボウズなど100以上のシステムと連携が可能で、契約書の作成から締結、管理までを自動化できます。
たとえば、CRMやERPと連携することで、顧客情報や契約者情報の入力を省けます。システム間でデータが自動的に共有されるので、入力ミスの防止と作業時間の短縮を実現できるでしょう。また、契約データに関連した業務情報をまとめて管理できるので、業務プロセスの把握がかんたんになります。
連携できるサービスの例は以下のとおりです。
- kintone
- Salesforce
- BizteX
- Hubble
- lawgue
- バクラク申請
- DONUTS(ジョブカンワークフロー)
- collaboflow
- X-point
- eValue
- MAJOR FLOW
(引用:外部サービス連携|クラウドサイン)
マネーフォワードクラウド契約
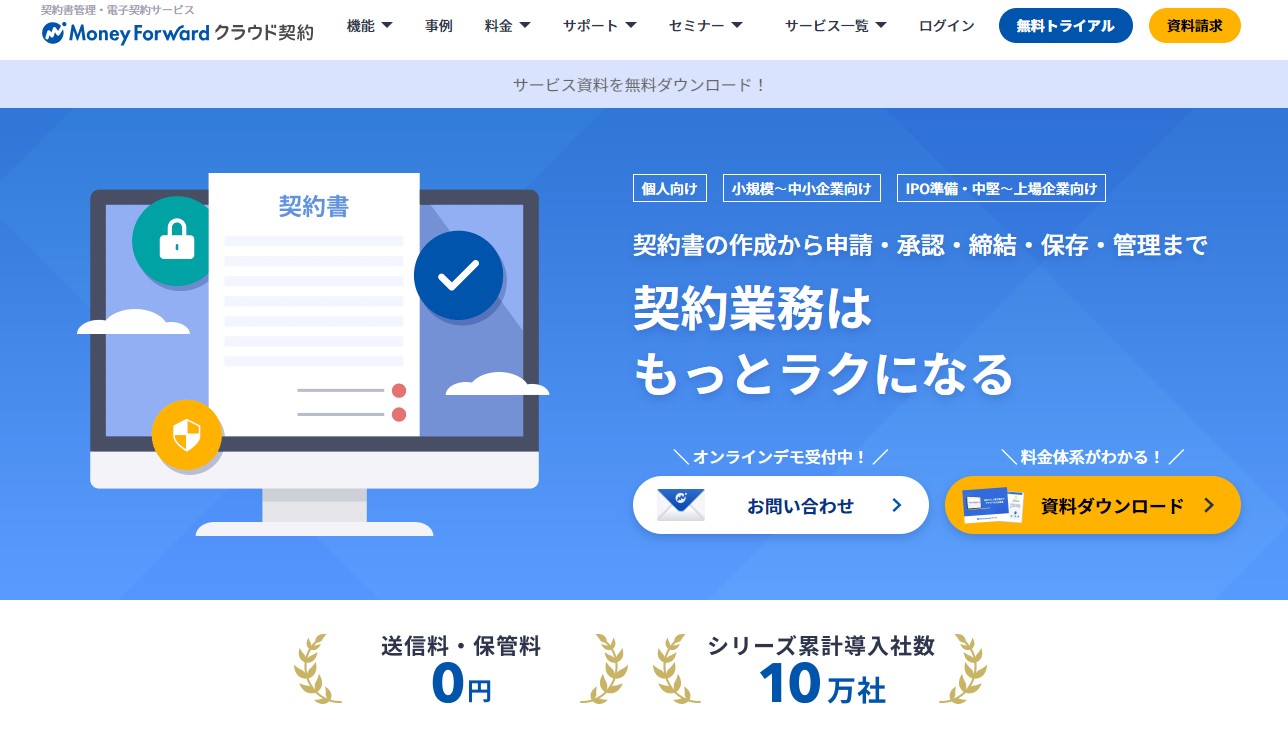
マネーフォワードクラウドの電子契約サービスであるマネーフォワードクラウド契約では、CRMやワークフローシステムなど、さまざまなサービスと連携が可能です。たとえば、Salesforceとの連携では、商談データをもとに申し込みの作成・送信ができます。
電子契約の締結が完了すると、クラウド契約に自動的にデータが保存されるため、申込書の作成から保管までの手間を削減できます。また、Slackと連携することで、締結が完了した際やワークフローが承認された際に通知を受け取ることも可能です。
WAN-Sign

WAN-Signでは、Salesforceなどの顧客管理システムやワークフローシステムなどと連携して業務の効率化を図れます。API連携によって一括署名もかんたんに実行できるようになるので、毎月1,000件以上の署名が必要な企業にもおすすめです。WAN-SignでAPI連携を利用できるサービス例は以下のとおりです。
- Tradeshift
- POファイナンスR
- Magic xpi
- intra-mart
- kinterpR
- kintone
- 環境将軍R
- OPTiM Contract
(引用:サービス連携・API連携|WAN-Sign)
電子契約サービスAPI連携の導入手順
目的・要件の整理
API連携を検討する際は、目的を明確にすることが大切です。たとえば「契約書の送信を自動化したい」「契約状況を自社システムで管理したい」など、自社の課題から目的を定め、業務プロセスのどこを自動化・効率化したいのかを洗い出します。
そのうえで、連携対象のSFAやERPなどの自社システムと連携するデータ項目(契約書のテンプレートや取引先情報、契約日など)を整理します。法務部や情報システム部、経理部などの関係部署とも事前に連携し、法的要件やセキュリティポリシーも踏まえた要件定義を行うことが重要です。
対応しているAPIの確認
使っているサービスと連携できるAPIのリストを確認します。多くのサービスでは、公式サイトやドキュメントにAPIマニュアルが掲載されており、どのような機能が利用できるのか記載されています。
もし分からない場合は、サービスの問い合わせ窓口を利用するのもおすすめです。自社のやりたいことや困っていることを伝えれば、どのAPIやどういった機能が適切かをアドバイスしてもらえます。
開発環境の構築・実装
API連携させるサービスが決まったら、電子契約サービスの公式サイトでユーザー登録をします。登録後、審査が必要な場合は数日〜数週間かかることもあるので、余裕を持って進めましょう。
ユーザー登録が完了すると、APIキーやシークレットキーが発行されます。これらの情報は、Salesforceなどの外部サービスと電子契約サービスをつなぐために必要です。
次に、電子契約サービスが提供しているAPI仕様書を確認し、連携させるサービスの管理画面や開発環境で設定を進めます。
連携設定が終わったら、テスト環境で実際にデータのやり取りや動作確認を行い、問題がなければ本番環境で運用を開始します。APIの仕様や設定方法は公式マニュアルやサポート窓口で詳しく案内されていますので、分からない場合は問い合わせてみましょう。
テスト
電子契約サービスのAPI連携を実装したあとは、問題が発生しないことを確認するために、テストを行います。まずは、APIが設計どおりに機能するかどうかを確認しましょう。たとえば、データの送信や受信が正しく行われているか、問題なく契約書の作成や署名ができるかなどをチェックします。
また、APIの応答時間やデータ処理の速度を測定し、期待されるパフォーマンス基準を満たしているのか確認することも大切です。テスト結果を分析し、問題が発見された場合には修正作業を行います。その後、再度テストを実施して修正が正しく行われたかチェックしてください。
本番運用
テスト環境での運用が成功したら、次に本番環境に移行します。
本番環境においても、初期の数日間はテストを行い、エラーや不具合の発生を確認しましょう。また、社内の利用者に対して新システムの操作方法を教育し、スムーズな運用ができるようにすることも大切です。
本番運用開始後も、システムのパフォーマンスは監視する必要があります。たとえば、APIのログをチェックしてエラーの頻発度を分析したり、ユーザーからのフィードバックを収集して使い勝手や機能に関する改良点を見つけたりするとよいでしょう。
電子契約サービスのAPI導入時の注意点
電子契約サービスのAPI導入時の注意点は以下の4つです。連携後にトラブルが起こらないように、それぞれの注意点を把握して、適切な導入を進められるようにしましょう。
プランによるAPI制限
選択するプランによって、APIの利用可能範囲やリクエストの制限が異なるので、事前に確認しておいてください。
たとえば、基本プランでは契約書の作成や署名機能のみが利用可能で、通知機能などの高度な機能は上位プランでしか利用できない場合があります。自社の業務プロセスに必要なAPIの機能を事前に確認し、適切なプランを選定することが重要です。
また、連携したいCRMサービスやほかの業務システム側でも、API連携ができるプランとできないプランが分かれていることがあります。
法的有効性の担保
API連携を行う場合は、その法的有効性を確保することもきわめて重要です。電子契約の法的有効性は、電子署名法によって認められています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
当事者本人によって電子署名が付与された契約書は、法的証拠力が推定されると記載されています。そのため、APIを利用して契約を締結する場合も、電子署名を確実に付与できる機能が求められます。
また、電子契約書は電子帳簿保存法の要件にも従わなければいけません。APIによって生成・保存された電子契約データが、「真実性の確保(訂正削除の履歴が残るなど)」や「可視性の確保(日付・金額・取引先で検索できるなど)」といった法的要件を満たしているかが重要です。サービスを選定する際には、API連携で自動保存した場合でも、これらの電帳法要件に準拠できるか、事前に必ず確認しましょう。
セキュリティ・ガバナンス対策
セキュリティとガバナンスに関する対策を講じることで、データの安全性を確保し、企業の信頼性を高められます。
セキュリティ対策としては、たとえばデータを暗号化して外部から盗み見られないようにしたり、アクセスできる人を制限したり、操作履歴を記録して不正がないかチェックしたりする方法があります。特にデータ暗号化は、情報漏えいや不正アクセスを防ぐためにとても大切なので、API連携を導入する際には、そのサービスが対応しているか必ず確認しましょう。
ガバナンス対策としては、電子契約に関する法律やルールをきちんと守ることが大切です。データをどう使うかや、セキュリティ対策・管理の責任者を明確にしておく必要があります。従業員にもセキュリティ教育を行い、APIを使うときの注意点やリスクについてしっかり理解してもらいましょう。
サービスの仕様変更リスク
APIを介している外部サービスが仕様変更を行った場合、それに依存する自社のシステムも影響を受けます。特に、APIのエンドポイントやデータフォーマットが変更されると、既存の連携機能が動作しなくなる可能性があるため、注意が必要です。業務自体が一時的に停滞するリスクもあるでしょう。
仕様変更が行われた場合は、変更内容を自社のシステム担当者や開発パートナーにすぐ共有し、影響範囲を確認することが大切です。仕様変更のタイミングにあわせてマニュアルや社内手順書も更新し、テスト環境で新しいAPI仕様に合わせた動作確認や修正作業を行いましょう。
電子契約サービスのAPI連携を活用して業務改革を実現しよう
電子契約サービスは、CRMやERP、ワークフローシステムなどと連携することでより業務を効率化しやすくなります。契約書の作成から管理までを自動化できるので、ほかの重要な業務に時間を充てやすくなることがメリットです。自動化することで、人的なミスや人件費の削減にもつながるでしょう。
ただし、電子契約サービスのAPI連携はプランによって制限が課されていることもあるので注意が必要です。法的有効性の担保やセキュリティ・ガバナンス対策などに問題がないかもチェックしておきましょう。
電子署名法や電子帳簿保存法に準拠しているGMOサインなら、法的証拠力の担保やセキュリティ・ガバナンス対策なども問題なくクリアできます。使いやすい操作性や豊富な機能も評価されているポイントで、非常に多くの企業に導入いただいています。
外部サービスと電子契約サービスを連携したい方は、以下のAPIに関する資料をぜひ確認してみてください。