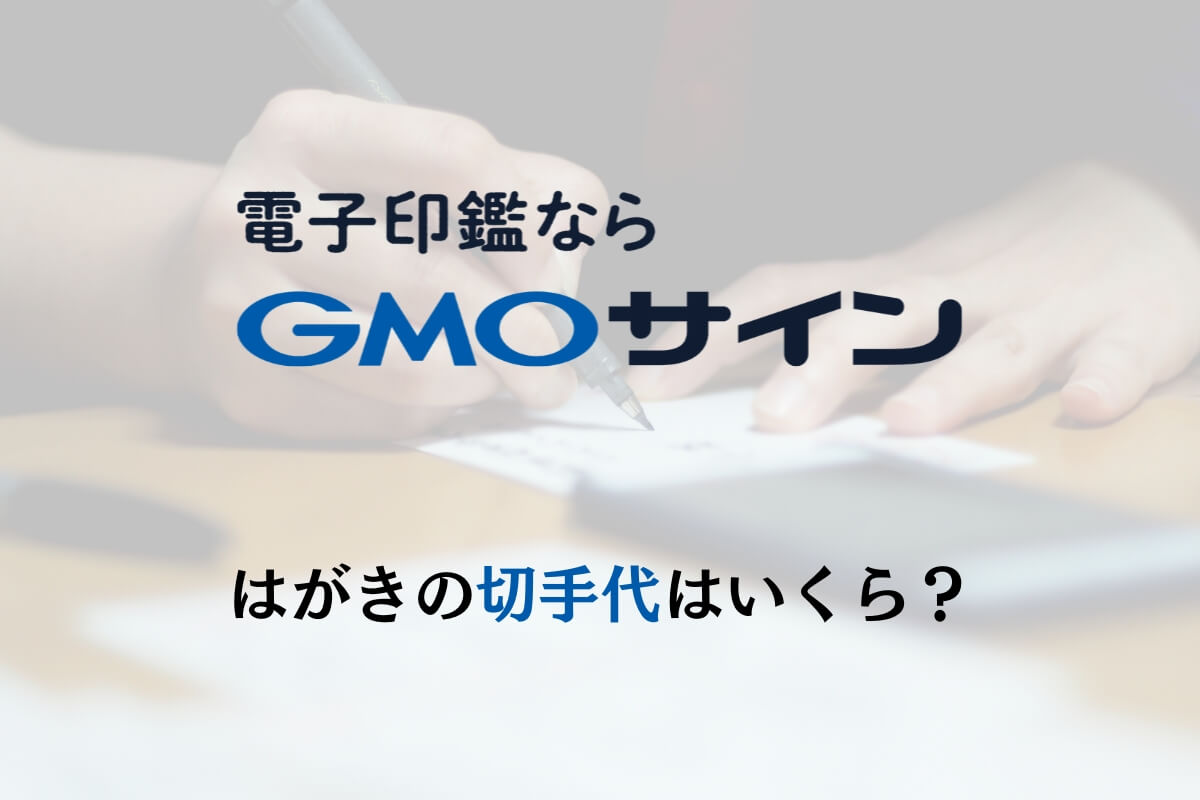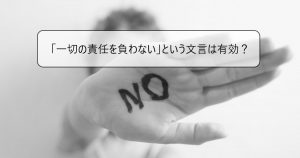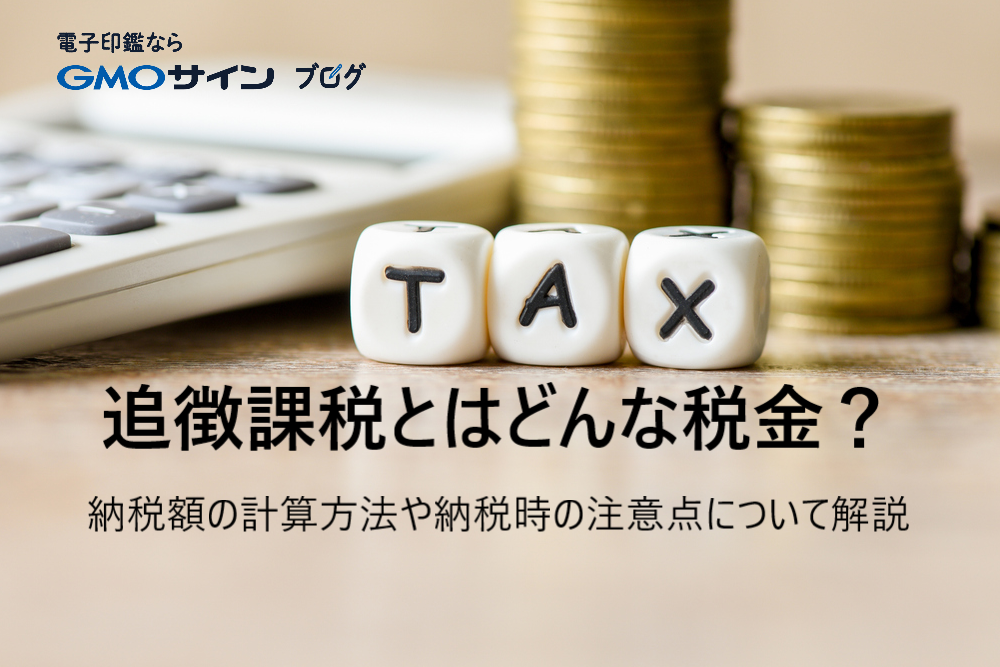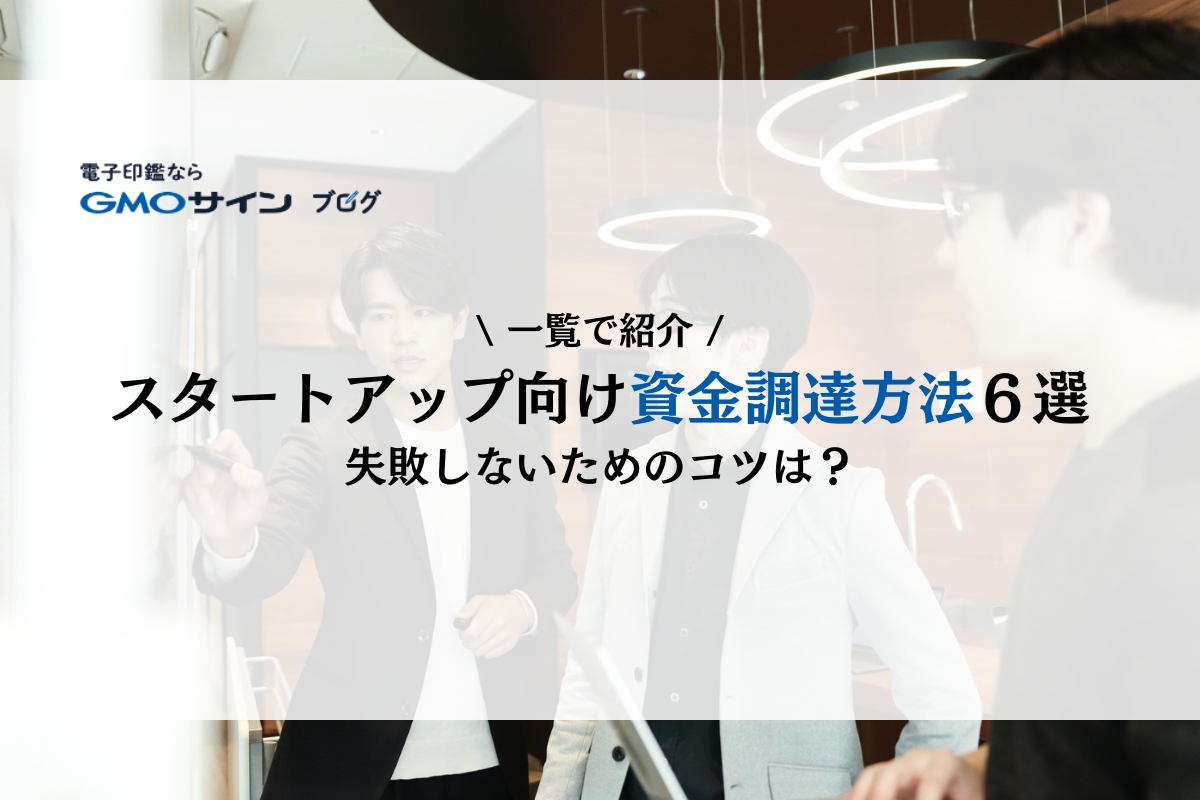\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /


消費貸借契約は口約束だけで法的に有効?
契約書に不備があって後々トラブルになったらどうしよう…
利息の設定や返済条件など、どこまで細かく決めておくべき?
消費貸借契約において最も注意すべきは、口約束やあいまいな条件設定が原因で、返済トラブルや法的紛争に発展するリスクがあることです。この記事では、消費貸借契約の基本から契約書作成の実務まで、トラブルを防ぐために必要な知識をわかりやすく解説します。
消費貸借契約を適切に締結するには、これらのポイントを正確に理解し、漏れなく契約書に反映させることが重要です。
ただし、いくら正確な契約書を作成できたとしても、紙の契約書では紛失リスクも存在します。そのため、より安心して契約を結ぶためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。特に消費貸借契約のような金銭が絡む重要な契約では、電子契約の改ざん防止機能や契約履歴の管理機能が、後々のトラブル防止に大きく役立つでしょう。
GMOサインは無料プランも用意されており、月5件までの契約であれば費用をかけずに電子契約を始められます。無料プランでも電子署名やタイムスタンプ、契約書の保管といった基本機能はすべて利用可能です。まずは無料プランから電子契約を始めてみてはいかがでしょうか。
まず、消費貸借契約がどのような契約なのかを理解しましょう。基本的な仕組みと種類をわかりやすく解説します。
使用貸借や賃貸借など、似ている契約との違いを理解し、必要な契約形態を正しく選んでください。
消費貸借契約とは、借りたものを自由に消費したうえで、後日、同じ種類・品質・数量のものを返す契約です。民法第587条でも以下のように定められています。
(消費貸借)
引用:e-GOV 法令検索
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借契約は、民法で定められた13種類の典型契約の1つとして位置づけられており、私たちの日常生活や事業活動で広く使われる基本的な契約形態です。
お金の貸し借りだけでなく、お米やガソリンなどの物品にも適用されます。たとえば友人に1万円を貸したり、隣の家の人からお米5キログラムを借りたりする場合がこれにあたります。
ポイントは「借りたものそのもの」ではなく「同じ種類・同じ品質・同じ量」を返すことです。借りたもの自体は自由に使えるため、消費してしまっても構いません。
消費貸借契約には大きく分けて3つの種類があります。
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りのことです。友人への1万円の貸し借りや住宅ローン、事業資金の融資などが当てはまります。
金銭消費貸借の場合に1万円を借りたとしましょう。その返還の際は、借りたお札そのものを返す必要はありません。別の1万円札や、千円札10枚でも返済できます。
借りたお金は自由に使え、同じ金額の日本円を返せば契約は成立します。
消費貸借契約では、お米や小麦粉、ガソリン、コピー用紙など、同じものを返還できる物品が対象になります。
身近な例をあげると、コワーキングスペースでコピー用紙500枚を借りて、後日同じ規格のコピー用紙500枚を返すようなケースです。また、カフェ経営者がコーヒー豆を同業者から借りたり、建設現場でほかの業者から資材を融通してもらったりすることなども、消費貸借契約に当てはまります。
準消費貸借契約とは、すでに発生している借金や未払いの債務を、改めて消費貸借契約として整理し直す契約です。たとえば、商品代金の未払いがある場合に、その支払義務を金銭消費貸借契約に切り替えることで、返済方法や期限などを明確に定められます。
こうすることで債務の内容がはっきりするため、支払いに関するトラブルを防ぐ手段として活用されます。
消費貸借契約と混同しやすい契約として、「使用貸借」と「賃貸借」があります。
最も大きな違いは返還する対象です。消費貸借は「同じ種類・同じ品質・同じ数量」のものを返しますが、使用貸借や賃貸借は「借りたものそのもの」を返す必要があります。
下の表でおもな違いを整理しました。
| 項目 | 消費貸借 | 使用貸借 | 賃貸借 |
|---|---|---|---|
| 返還するもの | 同じ種類・品質・数量のもの | 借りたものそのもの | 借りたものそのもの |
| 使い方 | 消費・使い切り可能 | ていねいに使用し、元の状態で返還する | ていねいに使用し、元の状態で返還する |
| 対価 | 原則無料(利息を付けることも可) | 無料 | 賃料あり |
| 典型例 | お金の貸し借り、物の貸し借り | 無料で車や部屋を貸す | 家賃を払って部屋を借りる |
| 法律上の根拠 | 民法587条 | 民法593条 | 民法601条 |
たとえば、友人から車を借りた場合、返すのは「借りた車そのもの」であり、「同じ車種の別の車」では代替できません。このケースは消費貸借ではなく使用貸借または賃貸借になります。
契約の形式を間違えると、返済義務や対価の支払い条件が変わってしまうおそれがあるため注意しましょう。契約書を作る前に、必ず契約の形式を確認しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
消費貸借契約の基本を理解したところで、次は「この契約がいつ成立するのか」という重要なポイントを確認しましょう。
2020年の民法改正により、消費貸借契約は書面による「諾成契約」としても結ぶことが可能になりました。この改正内容を押さえておくことで、契約成立のタイミングや必要書類を正しく理解でき、法的に有効な契約を進められます。
消費貸借契約の成立方法には2つのタイプがあります。
2020年4月の改正前は要物契約のみでした。たとえ「来月10万円貸します」と約束しても、実際にお金を渡すまでは契約が成立していなかったのです。しかし、改正後は以下の条文にあるとおり、書面による諾成契約も有効になりました。
(書面でする消費貸借等)
引用:e-GOV 法令検索
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、書面で合意さえすれば、実際にお金や物を渡す前でも契約は成立します。ただし、口約束だけでは成立せず、必ず書面で残すことが条件です。
現在は2つの方式が選べます。書面を作成すれば諾成契約として交付前に成立し、作成しない場合はこれまでどおり要物契約として交付時に成立します。事業資金の融資など事前に条件を確定させたい場合は諾成契約が向いており、友人との少額の貸し借りなどは要物契約でも問題ありません。
重要なのは、目的や金額に応じてリスクの少ない方式を選ぶことです。
契約を成立させるには、「何を」「いくら」「いつまでに返すか」について合意することが基本です。要物契約では実際の交付が成立要件となり、諾成契約は書面またはPDFファイルなどの電磁的記録の作成が必要になります。
契約書は法的に必須ではありませんが、実務上は必ず作成すべきです。口約束では「借りた覚えがない」「金額が違う」などのトラブルが起こりやすく、高額や長期の返済ではリスクが大きくなります。
契約書は裁判時の証拠となり、公正証書にすれば裁判なしで強制執行ができる場合があります。利息や遅延損害金、保証人などの条件も明確にできるため、トラブル防止には契約書の作成が不可欠です。
また、契約書のやり取りには電子契約の利用がおすすめです。電子契約は紙の契約書に比べて改ざん防止や保管の利便性が高く、消費貸借契約に伴うトラブルを未然に防ぐうえで、より安全な方法といえるでしょう。
契約を有効に成立させるためには「何を契約書に書くか」も大切です。必要な項目をきちんと入れておけば、あとから条件で揉めたり、トラブルになったりすることを防げます。ここでは、契約書に必ず入れてほしい内容と、その理由をわかりやすく解説します。
まずは、誰と誰の契約なのかをはっきりさせるため、氏名や住所を正確に書きます。個人なら名前と住所、法人なら会社名・本店所在地・代表者名を入れます。住所は住民票や登記簿にあるものと一致させておくと安心です。
貸付金額や貸付日など、具体的な条件は契約内容の中でも特に重要なポイントです。たとえば、金額は「50万円」、日付は「2025年8月10日」など、明確にしましょう。物を貸す場合も同じで、「新米コシヒカリ10キログラム」「ガソリン200リットル」といった具合に、品名や量まではっきりと記載します。
ここが曖昧だと、「そんな金額じゃなかった」「貸したのはもっと前だ」などと、あとで食い違いが出やすくなります。契約書には具体的な金額・日付・内容をしっかり書き、必ずお互いに確認しておくことが大切です。
返す日と返す方法についても、はっきり決めておきましょう。「◯年◯月◯日までに一括で返す」や「毎月末までに◯回に分けて返す」など、具体的な日付や回数を記載します。
どちらの方法を選ぶにしても、お互いが納得できる返済計画を立て、契約書にしっかり残しておくことが大切です。
利息を設定する場合は、必ず法律で決められた上限を守る必要があります。上限は元本の額によって異なりますので、以下の条文をご確認ください。
第一章 利息等の制限
引用:e-GOV 法令検索
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
つまり、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限となります。
これらの上限を超えて利息を設定した場合、超過部分は法律上「無効」となり、支払いを請求することはできません。違法な高利率を設定すると、契約自体の信用性が損なわれるだけでなく、貸主側が行政指導や罰則の対象となるリスクもあるため、必ず法定範囲内で利率を定めましょう。
なお、利息をつけない場合でも、「無利息」と明記しておくと安心です。
返済が遅れたときに発生する遅延損害金については、利息制限法第1条・第4条で上限が決められています。金額の目安は、以下のとおりです。
契約書には上限内で具体的な割合を明記しておくと安心です。ただしこちらも、上記の範囲を超えるとその超過部分は無効になるためご注意ください。
さらに、期限の利益喪失条項を入れておくと、一定期間の返済が遅れたときに、残りの金額をまとめて請求できるようになります。この条項は法律で明確に定められているものではありませんが、実務では広く利用されており、債権回収を円滑に進めるために契約書へ記載しておくことが望ましいとされています。
万が一、貸したお金を返してもらえないときに備えて、保証人や担保の設定も検討しておくとよいでしょう。保証人の場合は、普通保証なのか連帯保証なのかを明確にし、氏名・住所・押印も忘れずに記入してもらいます。担保については、物件や権利の内容を具体的に記載し、必要に応じて登記を行ってください。
これらの項目を契約書に記載しておくことで、万が一返済が滞った場合でも、回収の可能性を高められます。
契約を安全に進めるためには、必要な内容をしっかりと盛り込むことが欠かせません。では、それらの項目は実際の契約書ではどう書かれているのでしょうか。ここからは、これまでの内容を形にした具体例として、実務でよく使われる金銭貸借契約書のテンプレート(ひな形)をご紹介します。
ただし、テンプレートを使用する際は、金額や日付、返済方法など契約内容を適切に調整してください。
金銭消費貸借契約書
貸主と借主は、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結する。第1条(当事者)
貸主
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________借主
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________第2条(貸付金額および目的物)
貸主は、借主に対し、金____円を貸し渡し、借主はこれを受領した。第3条(貸付日)
貸付日は、令和__年__月__日とする。第4条(返済期限および方法)
返済期限は、令和__年__月__日とする。2. 返済方法は、以下のいずれかとする。
(1) 一括返済
(2) 分割返済(毎月__日限り金__円)3. 返済は、貸主指定の口座への振込により行う。振込手数料は借主の負担とする。
第5条(利息)
利息は、年__%とする(365日の日割計算)。第6条(遅延損害金)
返済期限を経過しても返済がない場合、借主は未払元金に対し年__%の割合による遅延損害金を支払う。第7条(期限の利益の喪失)
借主は、次の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を失い、直ちに残債務を支払わなければならない。(1) 元金または利息の支払を1回でも怠ったとき
(2) 差押え、仮差押え、競売、破産、民事再生の申立を受け、または自ら申し立てたとき
(3) 他の債務について期限の利益を喪失したとき
第8条(保証人)
保証人を立てる場合は、連帯保証人とする。連帯保証人
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________第9条(担保)
担保の有無は以下のとおりとする。
□ 有(内容:____________________)
□ 無第10条(準拠法および協議)
本契約の解釈について疑義が生じた場合は、貸主および借主は協議して解決する。本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、貸主および借主が署名または記名押印し、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
貸主
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________
印
借主
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________
印
連帯保証人(該当する場合)
住所:____________________
氏名/名称:____________________
(法人の場合)代表者職氏名:________________
印
実際の消費貸借契約では、ちょっとした書き漏れや思い違いによって、大きなトラブルや税金問題につながることがあります。ここでは、消費貸借契約を結ぶうえで注意すべきポイントを解説します。
口約束は証拠が残らないため、あとで「そんな約束はしていない」と言われても反論できません。たとえ親しい相手でも、必ず契約書を作りましょう。
書面を作成しておくことで、貸主と借主双方の合意内容が明確になり、万が一裁判になった場合でも有力な証拠として活用できます。
契約書は紙でも電子でも構いませんが、電子契約は日付や内容が改ざんされにくく、保管しやすいメリットもあるためおすすめです。
無利息でまとまった金額のお金を貸すと、税務署から「実質的に贈与ではないか」と見られることがあります。特に親族間の貸し借りでは注意が必要です。贈与と判断されれば、贈与税がかかる場合もあります。
無利息にする場合でも、契約書を作って返済計画を書いておきましょう。そうすることで「贈与ではなく貸付である」という証拠になり、後々の誤解や税務上のトラブルを未然に防げます。
貸主が利息を受け取った場合、その金額は雑所得として所得税の課税対象となることがあります。少額であっても申告が必要になる場合があり、申告を怠ると追加で税金が課される可能性があるため注意が必要です。
利息を設定して受け取ったら、毎年の確定申告で正しく申告しましょう。複数の貸し付けをしている場合は、受け取った利息の合計額をしっかりと記録しておくことが大切です。
税務や契約内容に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
(参考:No.1500 雑所得|国税庁)
返済期限や方法が曖昧だと、「まだ返さなくていいと思っていた」「分割払いだと思っていた」など、お互いの思い違いから返済が遅れたり、請求をめぐって言い争いになることがあります。最悪の場合、裁判などの大きなトラブルに発展するおそれもあります。
そのため契約書には、返済期限や方法を具体的に書きましょう。たとえば「2025年8月10日までに一括返済」や「毎月末日までに○円ずつ返済」など、日付や金額を明確に記載することが大切です。
保証人や担保については、事前に明確な取り決めをしておかないと、万が一の際に十分な対応ができない場合があります。取り決めが不十分だと、「そのような責任があるとは思わなかった」と主張され、支払いを求めることが難しくなることもあります。
また担保についても、対象物や権利内容が曖昧だと、差し押さえや売却をスムーズに行えません。権利関係のトラブルを未然に防ぐためには、必要に応じて登記まで行っておくことが推奨されます。
担保や保証の設定には専門的な知識が求められるため、不安がある場合は司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
実際にお金や物を渡せば、法律上は口頭の約束だけでも契約は成立します。しかし、口約束だけでは証拠が残りません。
後から「そんな約束はしていない」「金額が違う」と言われても、証明することが難しくなります。トラブルを防ぐためには、どんなに親しい間柄でも必ず書面や電子契約で記録を残しましょう。
借用書は「確かに10万円借りました」という事実を証明するシンプルな書面です。一方、消費貸借契約書は民法第587条に基づき、返済期限、利息、遅延損害金、保証人など、契約の詳しい内容をすべて記載します。
友人への少額の貸し借りなら借用書でも十分かもしれませんが、金額が大きい場合や、分割返済など条件が複雑な場合は、しっかりとした消費貸借契約書を作成することをおすすめします。
契約書で禁止していなければ、期限より早く返済することは可能です。ただし、利息を付けている場合は、返済額の計算方法を確認する必要があります。
契約解除については、お互いが合意すればいつでも可能です。一方的に解除するには、相手が契約違反をしているなど、正当な理由が必要になります。
消費貸借契約の原則は「借りたものを自由に消費してよく、同じ種類・品質・数量のものを返す」ことです(民法第587条)。
借りた1万円札そのものを返す必要はなく、別の1万円を返せばよいとされています。お米を借りた場合も、同じ銘柄で同じ量を返せば問題ありません。
片務契約とは一方だけが義務を負う契約のことで、消費貸借契約は基本的に片務契約に該当します。ものを受け取った借主だけが「返還する義務」を負い、貸主には義務がありません。
ただし、これは要物契約の場合であり、書面による諾成契約の場合は異なります。まだものを渡していない段階では、貸主に「約束した対象物を貸す義務」があり、借主にも「返還する義務」があるため、お互いが義務を負う契約(双務契約)となります。
ただし諾成契約においても、貸主がものを渡したあとは、借主だけが義務を負う片務契約に変わります。
利息をもらうことは可能です。ただし、契約書に利息について明記する必要があり、何も約束しなければ無利息となります。
利息を設定する場合は、利息制限法で上限が決まっているため注意が必要です。借りる金額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が上限となっています(利息制限法第1条)。
消費貸借契約の基本から成立条件、契約書に記載すべき項目、注意点まで解説しました。最も大切なことは、契約内容を明確に記載しておくことです。後になって「条件が違う」「そんな約束はしていない」といったトラブルを防ぐためにも、書面に残すことは欠かせません。
しかし、紙の契約書には紛失や改ざんのリスクが伴います。特に金銭が関係する契約の場合、契約書の改ざんによって双方の信頼関係が損なわれ、深刻なトラブルにつながる可能性があります。そのため、改ざん防止の仕組みを導入することが重要です。
契約書の改ざん防止には、電子契約の活用がおすすめです。電子印鑑GMOサインなどの電子契約サービスを利用すれば、電子署名やタイムスタンプ機能によって改ざんを検知でき、迅速に対応できます。さらに、契約書の作成から署名、保管までをすべてオンラインで行えるため、遠方の相手ともスムーズに契約を締結できるといったメリットもあります。
GMOサインでは、月に5通までの電子契約が無料で行えるお試しフリープランも用意しています。
改ざん防止に役立つタイムスタンプや法的証拠力を担保できる電子署名、その後の契約書の管理を無料で行えますので、ぜひお気軽にご利用ください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。