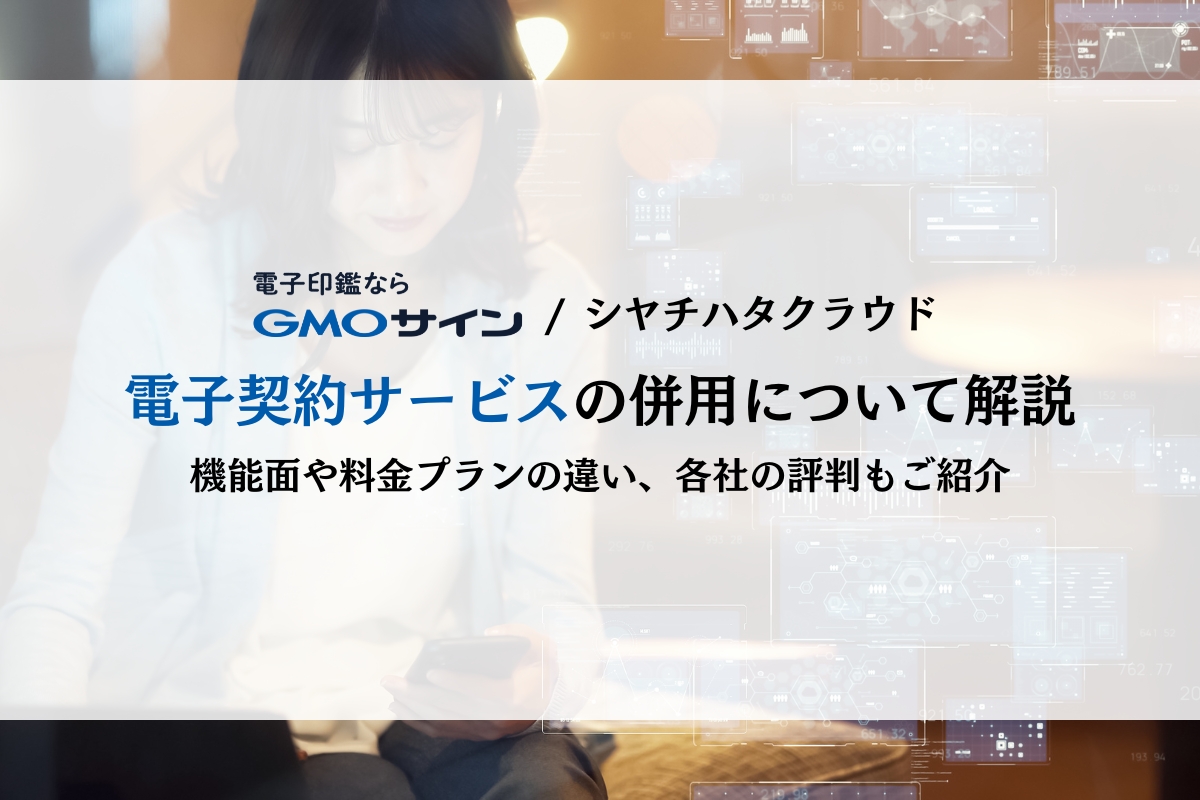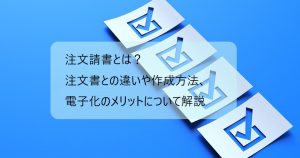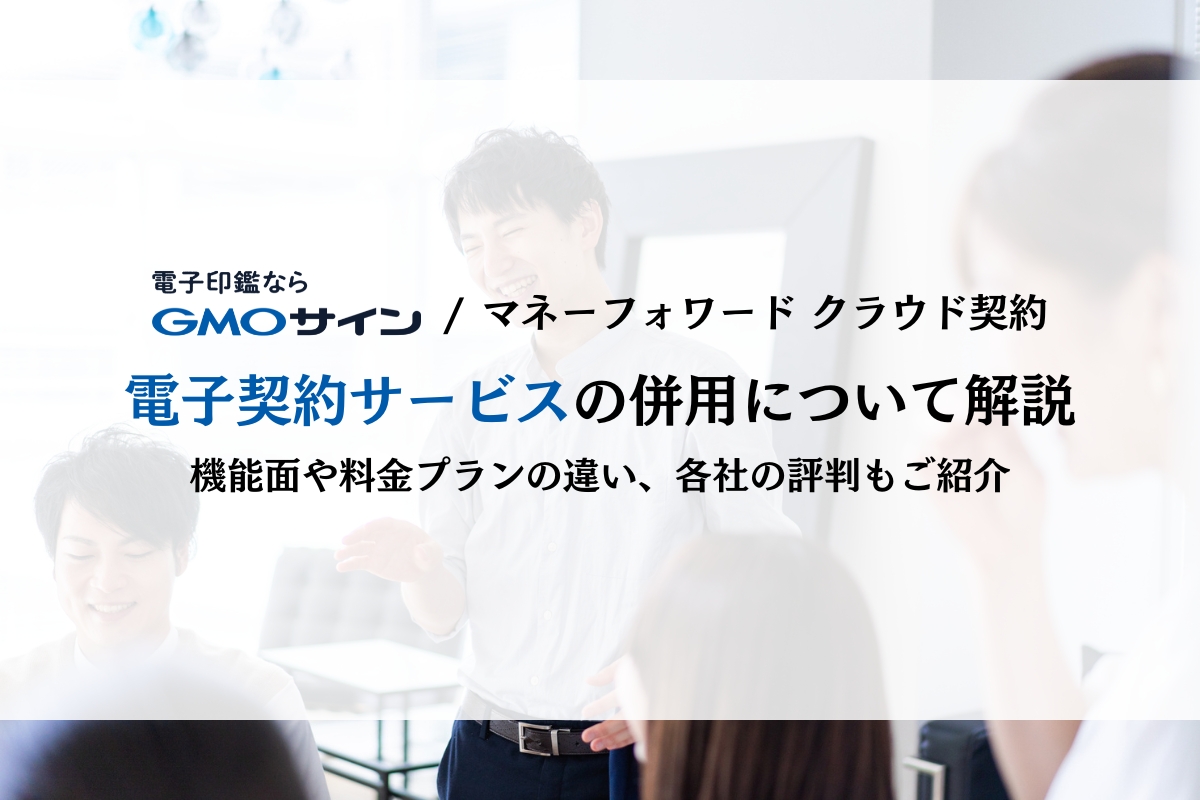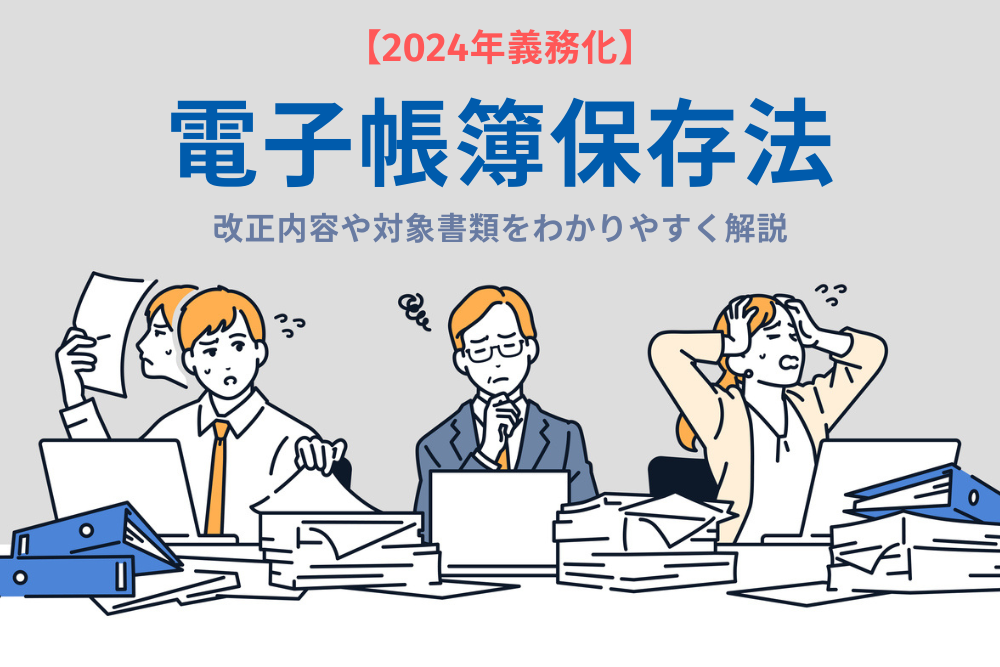金額の記載方法を間違えて、トラブルになったらどうしよう…
契約書の金額には、アラビア数字と漢数字のどちらを使えばよい?
消費税の表記や端数処理など、細かいルールが複雑で心配…
契約書の金額記載は一見シンプルに思えますが、実は多くの落とし穴が存在します。記載ミスがあると契約の有効性に疑問が生じたり、支払いトラブルに発展したりするリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、契約書における正しい金額の書き方について、基本ルールから特殊なケースまで解説します。記事のおもな内容は以下の通りです。
- 金額記載の基本ルール(アラビア数字・漢数字の使い分け、カンマの使用方法)
- 消費税や源泉徴収の正しい記載方法
- 金額訂正時の適切な手順と注意点
- 分割払いや変動金額など特殊ケースの対応方法
- 契約書作成における金額以外の重要ポイント
また、契約を結ぶ際には電子契約の導入がおすすめです。電子契約なら、タイムスタンプと電子署名が入ることで金額の改ざんを防ぎやすくなります。万が一、金額の修正が必要な場合も印刷・郵送などの手間がかからないのもメリットでしょう。
なかでも電子印鑑GMOサインは累計送信数国内No.1(※)の実績があり、使いやすい操作画面が特徴で、はじめての方でも安心して利用できます。
- テンプレート登録機能で契約書をかんたんに作成できる
- 電子署名法に準拠した電子署名およびタイムスタンプの付与ができる
- クラウド上で安全に文書を管理できる
- 契約書の修正や更新もかんたんな操作で行える
GMOサインのお試しフリープランでは、月5件まで無料で契約書を送信でき、基本的な電子契約機能をすべて利用できます。契約書に関する不安を解消し、効率的で確実な契約業務を実現するために、ぜひGMOサインをご活用ください。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)
契約書における金額記載の重要性とそのリスク
契約書に金額を記載する際は、適切な内容になっているか注意が必要です。以下では、金額を適切に記載するべき理由やトラブル事例などを解説するのでそれぞれ確認していきましょう。
金額の適切な記載が重要な理由
業務委託契約書や売買契約書などを締結する際、契約書に適切な金額が記載されていない場合、当事者間でトラブルにつながることがあります。たとえば、金額の記載ミスや税込み・税抜きの誤解などにより、契約が取り消しになるケースもあるので注意が必要です。
契約書では業務内容や目的物の詳細、秘密保持義務などさまざまな情報が記載されていますが、金額は特に重要な項目の一つです。記載ミスがあった場合は契約関係が悪化する可能性もあるので、正確な内容になっているか必ずチェックしましょう。
金額記載ミスが引き起こすトラブル事例
金額の記載ミスによって発生するトラブルの事例として以下のようなものが挙げられます。
- 100万円と記載すべき箇所が10万円になっており、契約書を作り直すことになった
- 100万円と記載されていたが、消費税の扱いが不明だったため当事者間で支払額の認識にずれが生じていた
- 追加作業分の報酬について契約書に記載されておらず、言い争いになった
契約書の金額は1桁でも誤りがあると、大きなトラブルに発展する可能性があります。また、税込み・税抜きの表記など細かい点にも注意が必要です。
デザインや動画制作などを依頼する場合には、一度納品したあとに修正をくわえることが多いので、追加作業分の報酬についても明記しておきましょう。業務を請け負う側や商品を販売する側にとって、契約書に記載された金額は売上につながる重要な項目です。間違いがないように、当事者双方で繰り返し確認してください。
金額を記載する際の注意点
契約書に記載される金額は、契約における重要な項目です。民法第522条第1項では、相手方からの承諾があった際に契約が成立すると記載されているため、当然金額についても合意を得る必要があります。合意を得ずに契約を行った場合は、契約が取り消しになることもあるので注意しましょう。
(契約の成立と方式)
(引用:民法|e-Gov法令検索)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
また、契約書に金額を明記する際は、記載方法にも注意が必要です。紙の契約書の場合は「一・二・三」などの漢数で記載すると付け足しや書き換えがしやすくなってしまいます。
契約書への金額の書き方|基本ルール
契約書に記載する際は、さまざまなルールを守らなければいけません。ここからは、アラビア数字と漢数字の使い分けや「円」と「¥」の使い分けなど、基本的な金額の書き方について解説していきます。
細かい記載方法を把握することで契約後のトラブルを防ぎやすくなるので、それぞれの内容を確認していきましょう。
アラビア数字と漢数字の使い分け方
契約書に金額を記載する際、アラビア数字と漢数字のどちらかを使用しますが、使い分けには注意が必要です。「一・二・三」などの漢数字を用いる場合、改ざんや付け足しによるトラブルが発生する可能性が高まります。
漢数字を記載したい場合は「壱・弐・参」などの大字を利用することがおすすめです。かんたんに調整を行えなくなるので、改ざんのリスクが低くなります。不安な場合はアラビア数字と大字を併用することで、より安全性を確保しやすくなるでしょう。
金1,100,000円(金壱百拾萬円也)
「円」と「¥」の使い分け方
契約書では「円」と「¥」の使い分け方にも注意してください。基本的に契約書に金額を記載する際は「円」を使用することが望ましいです。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律では「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」と明記されています。
(通貨の額面価格の単位等)
(引用:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律|e-Gov法令検索)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
「¥」はあくまでも通貨記号であり、法律上の通貨単位ではありません。また「¥」は中国人民元(CNY)の通貨記号としても使用されているため、取引先との認識に誤りが生じる可能性があります。
3桁ごとに「,(カンマ)」を用いる
契約書に金額を記載する際は、3桁ごとに「,(カンマ)」を使用しましょう。「1,000(千)」「1,000,000(百万)」などの大きい数字は、カンマを用いることで瞬時に値を判断できるようになります。
日本語では1万、1億、1兆というように、4桁ごとに単位を区切ることが一般的です。「,(カンマ)」は欧米式で3桁ごとに区切るため、慣れていないとすぐに数値を認識することが難しいこともあります。
しかし、多くの契約書や資料では「,(カンマ)」を使って数字を表記することが多いです。数字を記載する際に「,(カンマ)」を忘れると読みづらくなってしまうので、契約書を作成したあとは一つずつチェックすることをおすすめします。
「也」や「ー」の意味と必要なケース
契約書の金額には、数字のうしろに「也」や記号の「-」などが記載されているケースもあります。「也」は助動詞「なり」で、断定の意味を持っているため「金壱百萬円也」と記載されている場合は「きんいちひゃくまんえんなり」と読むことが可能です。
「也」や「-」がない場合、いつのまにか0を付け足されてしまい、トラブルにつながるケースもあるので注意しましょう。前述した「,(カンマ)」も改ざんのリスクを減らせるので、契約書では併用することがおすすめです。契約書に金額を記載する際は、前に「金」や「¥」を追加して「金壱百萬円也」「¥1,000,000-」などと表記します。
契約書の金額を訂正する場合の書き方・注意点
契約書の金額を訂正する際には、手順や方法に間違いがないように注意が必要です。以下では、署名・押印前や契約成立後など、シチュエーションごとに金額を修正する方法や注意点をそれぞれ解説していきます。
署名・押印前の契約書の金額の訂正手順と注意点
署名や押印をする前は、以下の手順で訂正を行いましょう。
まずは契約書に記載された誤った金額に二重線を引いて消します。修正液やテープを使用すると以前の内容がわからなくなってしまい、トラブルの元になってしまうので、油性のボールペンを使用して線を引くことが推奨されます。
二重線で消した金額の上部に正しい金額を記載します。たとえば、誤った金額「500,000円」を二重線で消し、その上に正しい金額「800,000円」とわかりやすく表記します。
たとえば「5行目、3字削除、3字加入」といった形で記載します。「一、二、三」などの漢数字はあとで改ざんされるリスクが高いので避けましょう。「壱、弐、参」などの多角数字であれば問題ありませんが、基本的には算用数字を使用することをおすすめします。
訂正印は、権限を持った人物によって押されたことを証明するために、契約書に使用したものと同じ印鑑を使いましょう。また、契約は当事者の合意によって成立するので、有効性を証明するために契約当事者双方(甲・乙)の訂正印が必要です。
契約書を複数作成している場合は、ほかの文書にも同様の訂正をしておきましょう。訂正を忘れると双方の認識に誤りが生じてしまい、トラブルにつながることがあるので注意が必要です。
契約成立後の金額の修正方法と注意点
契約成立後に金額を修正する際は、直接の訂正ではなく、覚書や変更合意書を作成することが一般的です。たとえば、以下のような手順で行います。
覚書を作成する際は、同意を得た変更内容を明記することが大切です。具体的には、以下のような内容を記載します。
覚書
〇〇株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)は、令和〇年〇月〇日に締結した「〇〇契約書」(以下「原契約」という)に関し、契約金額を以下のとおり変更することについて合意し、本覚書を締結する。
第1条
甲および乙は、原契約第〇条に定める契約金額について、次のとおり変更することに合意する。(変更前)契約金額:金〇〇〇円(税別/税込)
(変更後)契約金額:金△△△円(税別/税込)
第2条
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めが引き続き適用されるものとする。
本覚書の定めと原契約の内容に矛盾がある場合には、本覚書の定めが優先して適用される。第3条
本覚書は、甲および乙の記名押印または署名により、令和〇年〇月〇日より効力を生じるものとする。令和〇年〇月〇日
【甲】
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
会社名:〇〇株式会社
代表者:代表取締役 〇〇〇〇(署名または押印)【乙】
住所:△△県△△市△△区△△〇丁目〇番〇号
会社名:△△株式会社
代表者:代表取締役 △△△△(署名または押印)
覚書には、契約当事者全員が承諾したことを証明するために、署名や押印を行う必要があります。一部の当事者が署名や押印をしていない場合、有効性に問題が発生してしまうので注意してください。
金額変更に伴う印紙税が発生する場合は、必要に応じて収入印紙を貼り付けましょう。また、覚書が複数存在する場合は、最新のものを明確にするために日付や通し番号を付けることが重要です。
変更内容が追跡可能な状態を保つ必要があるので、元の契約書も破棄せずに保管しておきましょう。
\\ こちらの記事もおすすめ //
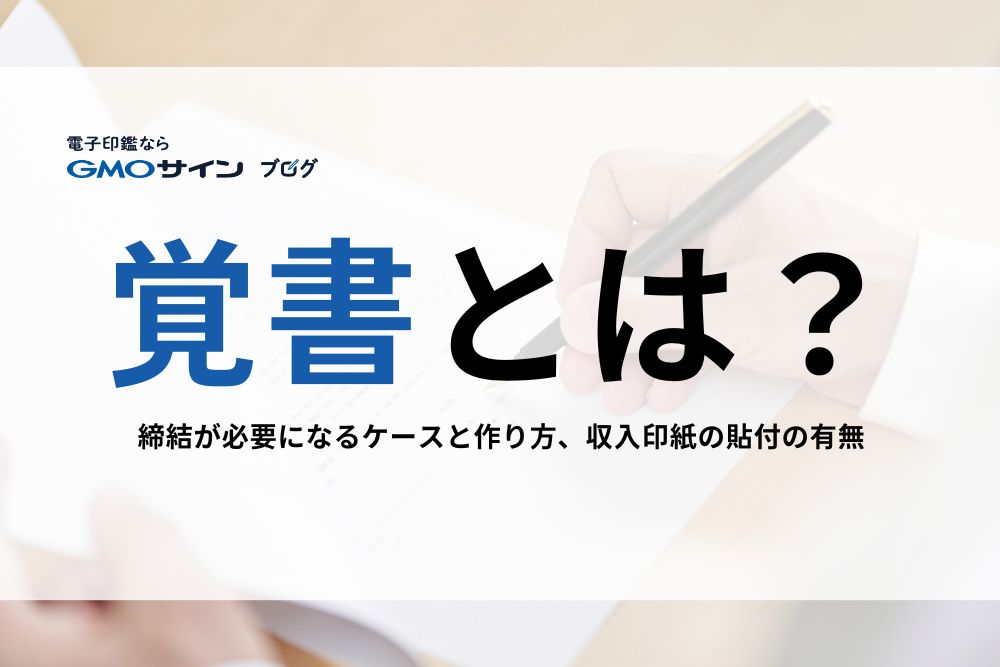
電子契約書の金額の修正方法
電子契約は、改ざんを防止するための電子署名やタイムスタンプを付与しているため、一度作成した契約書を訂正することが基本的にできません。金額訂正が必要な場合、電子契約では原本を書き換えず、改訂版を再送信して再署名する方法をとるのが一般的です。タイムスタンプが履歴を残すため、改ざん防止とバージョン管理を両立できます。
\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書への消費税・源泉徴収金額の正しい記載方法
消費税・源泉徴収金額についても正しい記載方法を把握しておくことが大切です。ここからは、内税や外税、源泉徴収が必要なケースなどに分けて契約書への記載例を解説するので、それぞれ確認しておきましょう。
契約書に書く金額は税抜き?税込み?
店舗やチラシなどでは価格の総額表示が義務付けられていますが、契約書では適用されていないため、対象にはなりません。したがって、当事者間の合意内容に従って表記を行う必要があります。契約書に消費税の扱いが記載されていない場合、当事者間でトラブルにつながる可能性があるので注意してください。
税抜きで契約を締結する場合は、報酬や代金とは別に消費税が加算されます。税率が変更されても柔軟に対応できるため、事業者間の契約で使用されることが多いです。一方、税込みの場合は、総額が契約書に記載されるので、支払い金額が明確になるメリットがあります。ただし、税率が変わると実質的な報酬額も変わってしまうので注意が必要です。
消費税込み(内税)の記載例
消費税込み(内税)で報酬を設定する際は、以下のように記載します。
第○条
甲は、乙に対し、本契約に基づく業務の対価として、報酬金額を金100,000円(税込)とし、契約締結日から30日以内に支払うものとする。
本報酬には、消費税および地方消費税相当額を含むものとし、甲および乙は、当該金額が消費税相当額を内包する金額であることを確認のうえ、別途これを請求または加算しないことに合意する。
上記のように「金100,000円(税込)」と報酬を明記することで、当事者間での認識の違いを防げます。ただし、税率が変更された場合は報酬金額も変わるので、長期契約や継続業務を前提としている契約では「税率変更時には金額を見直す」などと記載するとよいでしょう。
消費税抜き(外税)の記載例
消費税抜き(外税)の契約を締結する際は、以下のような内容を記載します。
第○条
甲は、乙に対し、本契約に基づく業務の対価として、報酬金額を金100,000円(消費税別)とし、これに対する消費税および地方消費税相当額を加算して支払うものとする。
消費税率が変更された場合には、当該変更後の税率に基づき算出された消費税額をもって調整するものとする。
報酬は、乙の請求に基づき、請求書発行日から30日以内に、乙の指定口座へ振込送金の方法により支払う(振込手数料は甲の負担とする)。
消費税込みのケースと同様に「金100,000円(消費税別)」と表記し、報酬に加算して支払うことを明記します。上記のように、消費税率が変更された場合の対応方法についても記載しておくと安心です。
源泉徴収が必要な場合の記載例
源泉徴収は、事業者が報酬にかかる所得税をあらかじめ差し引くことです。国税庁によると、以下のような報酬に該当する場合は源泉徴収を行う必要があります。
- 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい)
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(引用:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁)
源泉徴収が必要な場合は、以下のように記載します。
第○条
甲は、乙に対し、本業務の対価として、報酬金額100,000円(消費税別途)を支払うものとする。
ただし、乙が個人である場合において、当該報酬が所得税法第204条に基づき源泉徴収の対象となるときは、甲は、報酬額に対する法定の源泉所得税及び復興特別所得税相当額(現行法上、報酬額の10.21%)を控除したうえで、残額を乙の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとする。
なお、甲は、当該源泉徴収額を所轄税務署に対して法定期限内に適正に納付する責を負う。
報酬や料金に消費税および地方消費税が含まれている場合、原則として、その税込み金額全体が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書などにおいて報酬・料金と消費税などの額が明確に区分されて記載されている場合には、報酬・料金部分のみを源泉徴収の対象金額としても問題ありません。
契約金額が複数ある場合の書き方と記載例
契約金額が複数ある場合は、項目や業務ごとの報酬について明記する必要があります。記載が漏れているとトラブルにつながる恐れがあるので、注意点もあわせて確認していきましょう。
項目ごとに金額を記載する方法
一つの契約書に複数の項目を記載する場合は、内訳を明確にすることが大切です。たとえば、契約書には以下のように記載します。
第○条
1.甲は、乙に対し、本業務にかかる報酬として、下記の金額(いずれも消費税別)を支払うものとする。
(1)業務A:金 50,000円
(2)業務B:金 30,000円
(3)業務C:金 120,000円小計(税抜):200,000円
消費税(10%):20,000円
合計(税込):220,000円2.上記報酬は、乙による業務の完了および甲による検収確認の後、乙の提出する請求書に基づき、甲がその発行日から30日以内に乙指定口座へ振込送金により支払うものとする。
3.乙が個人であり、かつ当該報酬が所得税法第204条に基づく源泉徴収の対象となる場合には、甲は、所定の源泉所得税および復興特別所得税相当額を控除の上、前項の方法により支払う。
小計は各項目を足した金額のことで、合計は消費税もあわせた総額のことです。契約書にそれぞれの内訳や小計・合計などを細かく記載することで、当事者間での認識の違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
合計金額のみを記載する場合の注意点
合計金額のみを記載する際は、以下のような内容になります。
第○条
甲は、本契約に基づく本業務の報酬として、乙に対し、金220,000円(消費税および地方消費税を含む)を支払う。
2.前項の報酬は、乙による本業務の完了および甲による検収確認後、乙が提出する請求書に基づき、甲が請求書受領後30日以内に、乙の指定口座に振込送金する方法により支払う。
3.乙が個人であり、かつ当該報酬が所得税法第204条に基づく源泉徴収の対象となる場合には、甲は法定の源泉所得税および復興特別所得税相当額を控除のうえ支払うものとする。
契約金額が複数ある際、合計金額のみを記載すると何に対しての対価なのか不明瞭になってしまいます。事前に当事者間で話し合いを行い、業務範囲について明確にしておくことがおすすめです。追加業務の扱いについても定めておくと、安心して契約を締結できるでしょう。
別途資料を参照させる場合の記載方法
契約を締結する際、金額や業務内容の詳細を別途資料に記載する場合は、本文で別紙の存在を明示しておくことが大切です。報酬について記載する際は、以下の例を参考にしてください。
第○条
本契約に基づく業務の報酬は、別紙「報酬明細書」に記載されたとおりとする。
なお、報酬額には消費税および地方消費税を含まないものとし、別途加算して支払うものとする。
【別紙2:報酬明細書】
■ 報酬内訳(税抜)
・業務A 50,000円
・業務B 30,000円
・業務C 20,000円小計 100,000円
消費税(10%) 10,000円
合計(税込) 110,000円
特殊なケースにおける契約書の金額の書き方
分割払いや成功報酬などを設定する際は、金額に関する内容が正しい書き方になっているのかチェックすることが大切です。支払回数や遅延損害金などの条件を明確にし、法律的に有効な契約書を作成できるように記載方法を確認しましょう。
分割払い(割賦払い)の記載方法
契約の報酬を分割払い(割賦払い)とする場合は、以下の項目が正しく記載されているか注意しましょう。
- 支払額
- 支払回数
- 支払期日
- 遅延時の措置
たとえば、契約書には上記の内容を含めて以下のように記載します。
第○条
1.甲は、乙に対し、本業務の対価として、報酬金額330,000円(税込)を下記のとおり3回に分けて支払うものとする。
(1)第1回:契約締結日から10日以内に110,000円(税込)
(2)第2回:2025年7月末日までに110,000円(税込)
(3)第3回:2025年8月末日までに110,000円(税込)2.上記金額には、消費税および地方消費税が含まれている。
3.支払方法は、乙の指定する銀行口座への振込送金によるものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
4.甲が支払期日までに各分割金を支払わない場合、乙は催告のうえ、本契約を解除し、残額の一括支払を請求できるものとする。
5.前項により契約が解除された場合、甲は、乙に対し、未払金額のほか、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
※遅延損害金の利率は当事者間で自由に定められますが、
① 金銭消費貸借など“貸付け”に該当する場合は利息制限法の上限(元本に応じ年15〜20%)を超える部分は無効。
② 事業者と消費者の契約(貸付け以外)では消費者契約法により年14.6%を超える部分が無効。
したがって本記載例(年14.6%)は、消費者との取引であれば上限内、事業者間取引であれば法定上限はなく実務上も適切な範囲と言えます。
報酬を分割する場合は、それぞれの振込期日を正確に把握することが大切です。期日を過ぎても相手方の催告に応じない場合、債務不履行として契約を解除できることや残額の支払いについても義務付けます。
変動する金額(成功報酬、出来高払いなど)の記載方法
営業代行やコンサルタントの業務では、成果の納品ではなく実績に応じた報酬が支払われるケースもあります。成功報酬や出来高払いにおいては、以下の点を明確にすることが大切です。
- 成果の定義
- 報酬額の算出方法
- 報酬の上限額や下限額
- 成果の判定方法
- 支払い時期や方法
また、報酬額の算出方法や上限額・下限額の設定についても当事者間で認識を合わせておきましょう。営業代行を例にすると、契約書には以下のように記載します。
第○条
1.乙が本業務により紹介した顧客と甲が契約を締結し、かつ当該顧客が実際に代金の支払を完了した場合、甲は乙に対し、成果報酬として契約金額(税抜)の10%を支払うものとする。
2.報酬の支払時期は、甲が当該顧客からの全額入金を確認した日の翌月末日までとする。
3.報酬額には、消費税および地方消費税が別途加算されるものとする。
4.成果の有無および金額は、甲が保有する契約書・請求書・入金記録等の資料により証明されるものとし、乙はその閲覧を求めることができる。
5.成果が生じなかった場合、乙に報酬の支払義務は生じない。
成果の判定を行う際は、別途資料を参考にすることもあります。契約書には、どのような資料を参照するのか明記することも大切です。
端数処理が発生する場合の記載ルール
契約書において報酬や費用の計算に端数処理が生じる場合、トラブルや請求誤差を防ぐために、処理方法を明示的に記載することが重要です。たとえば、契約金額や報酬を割合(%)で算出する場合や消費税の計算によって1円未満の端数が発生することがあります。
端数処理をしない場合、契約当事者間で計算結果が食い違うおそれがあるので注意してください。たとえば、歩合報酬で端数処理が発生する可能性があるケースでは、以下のように記載します。
第○条
乙に支払う報酬額は、当月の売上金額(税抜)の5%とする。
報酬額の算出に際し、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
税と報酬で異なる処理をする場合は、それぞれ明確に記載することも大切です。
為替レートが変動する場合の記載方法(外貨建て契約)
為替レートの変動が関係する外貨建て契約では、為替変動による影響をどのように扱うかを明確に記載する必要があります。不確実性に関する紛争を避けるために重要なポイントなので、必ずチェックしておきましょう。
たとえば、外貨建て・円貨決済でレート変動が発生する場合は以下のように記載します。
第○条
- 甲は乙に対し、報酬としてUSD 10,000を日本円で支払う。
- 円換算に用いる為替レートは、支払日の株式会社○○銀行が公表する外国為替電信売相場(TTS)とする。
- 為替レートの変動による円換算額の増減について、甲乙は異議を述べないものとする。
なお、レートの変動が発生しない記載例は以下のとおりです。
第○条
- 報酬は、USD 10,000(米ドル1万ドル)とし、日本円での支払とする。
- 円換算額は、為替レート1USD=¥145として計算し、1,450,000円(消費税別)とする。
- 乙は、為替変動による差額調整を請求しないものとする。
契約書で条件やリスクの所在を明確にしないと、レートの変動で受け取り金額が目減りしたことで追加報酬の要求が発生することもあります。
契約書の金額に関するよくあるQ&A
契約書で金額の記載を間違えた場合、どうすればよい?
契約書で金額の記載方法を間違えた際は、誤った金額を二重線で消して、正しい金額を上部に記載します。また、どのような変更を行なったかを明確にするために「5行目、3字削除、3字加入」などの文章を欄外に明記しましょう。あわせて、当事者間で合意があったことを示すために、訂正印を押すことも大切です。
金額を修正テープで修正してもよい?
金額を訂正する際は、修正テープではなく二重線を使用することが大切です。修正テープを使用すると、以前の契約内容がわからなくなってしまい、書き換えのリスクも発生します。法的な有効性が認められない可能性もあるので、正しい訂正方法を把握しておきましょう。

口頭で金額を合意したが、契約書への記載は必要?
契約は口頭でも成立するため、金額について合意を得ることは可能ですが、契約書に明記しておくことがおすすめです。契約書に内容をまとめていない場合は、あとで「言った・言っていない」のトラブルにつながるおそれがあります。
消費税が今後上がる可能性がある場合の適切な記載方法は?
消費税が今後上がる可能性がある場合は、契約書に以下のような文言をくわえておきましょう。
第○条
甲は、本業務に対する報酬として、金○○円(税込)を乙に支払うものとする。ただし、将来、消費税等の税率が改定された場合には、改定後の税率に基づき、報酬額を見直すものとする。
特に、消費税込みの金額としている場合は、消費税の変更によって実質的な報酬額が変わることがあるので、上記のように規定を設けておくことが大切です。
契約書に100万円を記載するにはどうしたらよい?
契約書に100万円という金額を記載する際は「¥1,000,000-」「金壱百萬円也」などと記載します。前後に入れる金や也などの文字は付け足しを防止するためのものなので、金額とあわせて記載することがおすすめです。
契約書に金額の欄が空欄でもよいですか?
原則として空欄のまま契約を締結してはいけません。金額は契約の根幹をなす重要事項であり、空欄のままでは「契約内容について当事者間の合意がない」と判断され、契約自体が無効になる重大なリスクがあります。
どうしても金額を後日決定したい場合は、「甲乙協議の上、別途書面にて定める」といった条項を入れることも可能ですが、トラブル防止のため、金額を確定させてから契約を締結するのが鉄則です。
正しい金額表記で契約書を作成しよう
契約書に金額を記載する際は、正しい表記方法を理解したうえで内容を調整することが大切です。金額についての認識が当事者の間で異なる場合、紛争につながるリスクがあります。
なお、契約書を締結する際には、電子契約の利用をおすすめします。電子契約は、紙の契約書にかかっていたインク代・印紙代などのコストを抑えられることや業務効率化につながることがメリットです。
電子署名やタイムスタンプなどの技術によって非改ざん性や本人性を担保できるため、セキュリティ面でも安心です。電子契約サービスのGMOサインでは、作成した契約書にかんたんに電子署名を付与できます。オンライン上で文書が保管されるため、金額を操作される心配がなく、紛失のリスクもありません。
GMOサインは、操作性や豊富な機能などが評価されており、累計送信数が国内No.1(※)であることも特徴です。これから電子契約の導入を検討されている方は、まずGMOサインのフリープランで使用感を試してみてください。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)