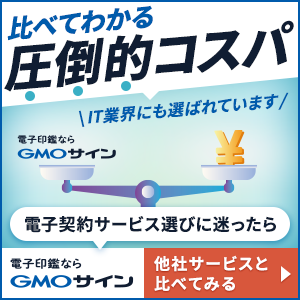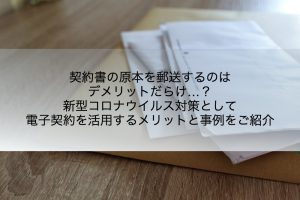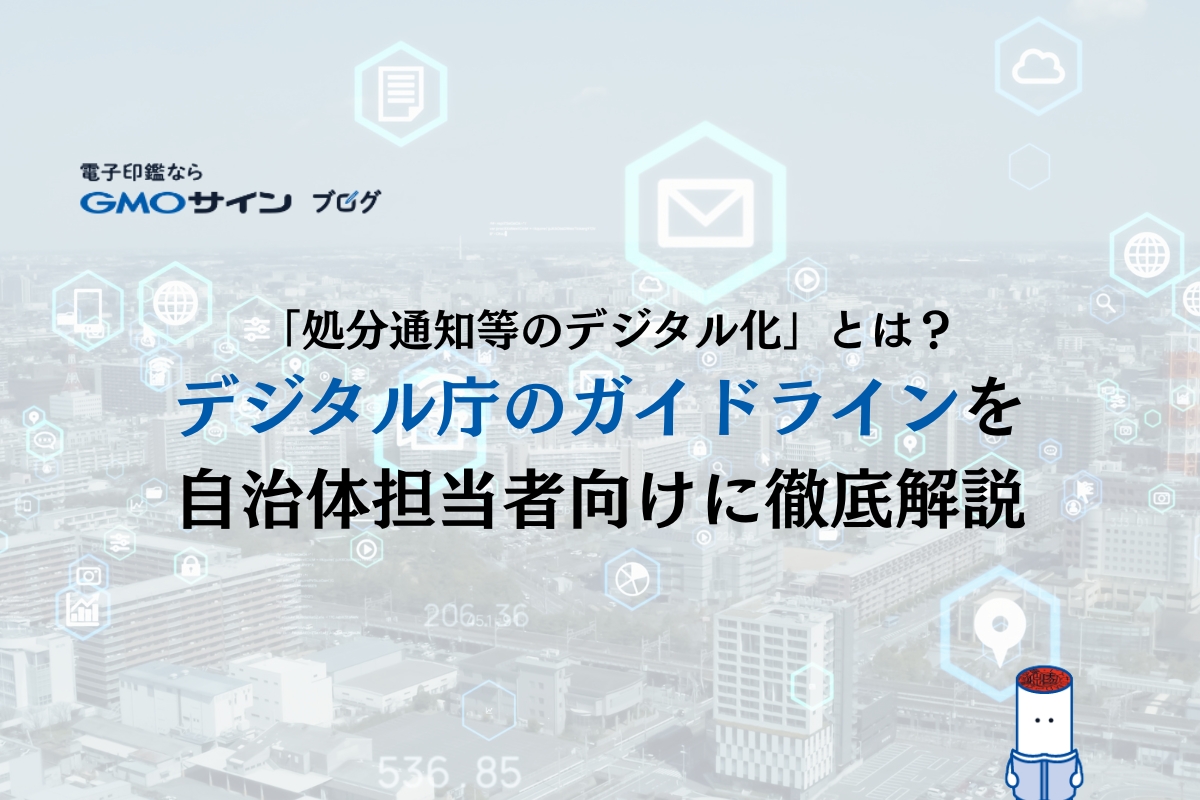ビジネスを進めていくうえで切っても切れないものが、契約です。ビジネスをしていると契約書を交わす場面にしばしば出くわすはずです。
ところでこの契約書は、その性質によっていくつかの種類に分類されるのをご存じでしょうか。その中の1つに、今回紹介する双務契約があります。ここでは、双務契約とは何か、またよく似た言葉である片務契約との違いについて解説します。
双務契約の概要
そもそも双務契約とはどのような形態の契約なのでしょうか。まずは双務契約とはどのような契約なのか、順に説明していきます。
双務契約とは
双務契約とは、契約する双方がお互いに債務を負う形態の契約を指します。双務契約の具体例として、売買契約や雇用契約、賃貸借契約、請負契約などが挙げられます。
たとえば売買契約の場合は、売主は商品もしくはサービスを提供する義務を負い、買主はその商品やサービスに見合った代金を支払う義務を負うことになります。
片務契約とは
よく双務契約とセットで紹介される契約形態として、片務契約があります。片務契約の場合は、契約当事者のどちらか一方だけが債務を負担することになります。
具体的には贈与契約や消費貸借契約(※無利息の場合)、使用貸借契約などが片務契約に該当します。
双務契約の同時履行の抗弁権
双務契約の特徴として、同時履行の抗弁権が認められる点が挙げられます。同時履行の抗弁権とは、相手が債務を履行するまで自分の債務の履行を拒むことを主張できる権利のことです。
双務契約における危険負担
危険負担とは、双務契約が成立したあと、目的物が債務者の責めに帰することができない事由で滅失・損傷したことで債務を履行することができなくなった場合に、そのリスクを契約当事者のどちらが負担するかという問題を指します。
契約書にこの点が盛り込まれていればその取り決めに従うことになりますが、特に盛り込まれていないようであれば、民法に定められた規定により処理されます。
債務者主義と債権者主義
危険負担には、債務者主義と債権者主義という考え方があります。債務者主義とは一方の債務が消滅すると反対債務も消滅するという考え方、債権者主義とは一方の債務が消滅しても反対債務は残り続けるという考え方を指します。
改正民法で変わった危険負担のルール
危険負担に関する民法のルールは、2020年4月1日に施行された民法改正によって大きく見直されました。
改正前の民法
改正前の民法では、危険負担について「債務者主義」を原則としていました。これは、売主(債務者)の責任ではない理由で商品が失われた場合、買主(債権者)は代金を支払う必要がない、という考え方です。ただし、特定のケースでは買主が代金支払義務を負う「債権者主義」が適用される例外もあり、複雑でした。
旧民法 第五百三十六条
① 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(出典:民法の一部を改正する法律案新旧対照条文)
改正後の民法
改正民法では、この考え方がよりシンプルになりました。当事者双方の責任ではない理由で契約の目的(商品の引き渡しなど)が達成できなくなった場合、買主(債権者)は代金の支払いを拒絶できます(民法536条1項)。
さらに重要な点として、買主(債権者)は契約そのものを解除することも可能になりました(民法542条)。これにより、買主は単に代金の支払いを拒むだけでなく、契約関係そのものから解放され、別の相手から商品を買い直すなど、より柔軟な対応が取れるようになったのです。
改正民法 第五百三十六条
① 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(出典:民法の一部を改正する法律案新旧対照条文)
危険負担についてはしっかりと取り決めを
双務契約を締結する際には、このような危険負担についても事前に当事者間で取り決めを交わしておくことが大切です。というのも、取り決めがないと、思わぬ損害を被る可能性があるためです。
トラブルを回避するという意味でも、しっかりとシミュレーションをして、契約内容に盛り込むようにしましょう。もちろん、契約当事者の一方のみが債務を負う片務契約についても、不利な内容となっていないかを検討・確認することは大切です。
いろいろな分類の契約理解しよう
双務契約と片務契約のほかにも、契約にはいろいろな分類のものがあります。なかには混同しやすいものもありますので、最後に契約の主要な分類について確認してみましょう。
典型契約と非典型契約
典型契約とは民法で規定された13の契約を指します。
13の契約とは、売買契約や雇用契約、請負契約、委任契約、消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約、贈与契約、交換契約、組合契約、寄託契約、終身定期金契約、和解契約が該当します。これ以外の契約は非典型契約といいます。
\\ こちらの記事もおすすめ //

諾成契約と要物契約
諾成契約と要物契約といった分類も存在します。両者の違いをかんたんに言えば、契約の成立に物品や金銭の受け渡しを必要とするかどうかです。諾成契約は、当事者が合意した段階で成立する契約を指し、物品や金銭の受け渡しの事実は契約の成立に影響しません。
一方、要物契約は、当事者の合意だけでなく、実際に物品や金銭の受け渡しがあって初めて成立する契約です。かつては消費貸借契約がその典型例でしたが、2020年4月の民法改正により、書面で契約する場合は当事者の合意のみで成立する諾成契約となりました。
\\ こちらの記事もおすすめ //

有償契約と無償契約
経済的な観点から、有償契約と無償契約という分類もあります。両者は、当事者同士が対価として見合う経済的支出を伴う契約かどうかで区別されます。
契約の当事者双方が、互いに対価といえる経済的な支出(法律用語で「出捐(しゅつえん)」といいます)をする契約が有償契約です。売買契約における代金の支払いはもちろん、互いの土地を交換するような交換契約も有償契約に含まれます。具体的には売買契約や賃貸借契約、雇用契約などが該当します(※)。
一方、金銭の受け渡しの伴わないものは原則として無償契約に該当します。たとえば贈与契約は一方が金銭を与えるだけの形になるため、無償契約の一種です。
※金銭の支払いだけでなく、物や権利を移転したり、使用させたりすることも「経済的支出」に含まれます。
双務契約に関するよくある質問
双務契約と片務契約の違いは?
双務契約と片務契約は、契約の当事者双方が互いに対価的な意味を持つ債務を負担するかどうかによって区別されます。
当事者が負う債務の性質によって区別され、それによって法的な取り扱いにも違いが生じます。
双務契約の事例は?
双務契約の具体的な事例をいくつか紹介します。
- コンビニエンスストアでの買い物(売買契約)
- 賃貸マンションを借りる(賃貸借契約)
- レストランで食事をする(飲食物供給契約・請負契約の一種とも解釈可能)
- アルバイトをする(雇用契約)
- クリーニング店に洋服の洗濯を依頼する(請負契約)
- スマートフォンを分割払いで購入、通信サービスを利用する(売買契約と電気通信サービス利用契約の組み合わせ)
双務契約の反対は何?
双務契約の反対は片務契約です。
契約によって当事者のうち何人が主要な義務を負うか、その義務が互いに対価関係にあるかどうかが、双務契約と片務契約を分けるポイントとなります。
まとめ
双務契約は、売買や雇用などビジネスの中心となる契約形態であり、当事者双方が債務を負うからこそ、同時履行の抗弁権や危険負担といった特有のルールが存在します。これらの知識は、取引上のトラブルを未然に防ぐために不可欠です。
そして、こうした重要な契約内容を正確に記録し、安全かつ迅速に締結するための最適なツールが「電子契約サービス」です。
電子契約サービス「GMOサイン」を活用すれば、契約書の作成から締結、保管までをクラウド上で一元管理できます。印紙代や郵送費などのコストを削減できるだけでなく、改ざん防止技術によって契約の証拠力を高め、コンプライアンスを強化します。
↓ 今すぐ無料ダウンロードできるおすすめ資料 ↓