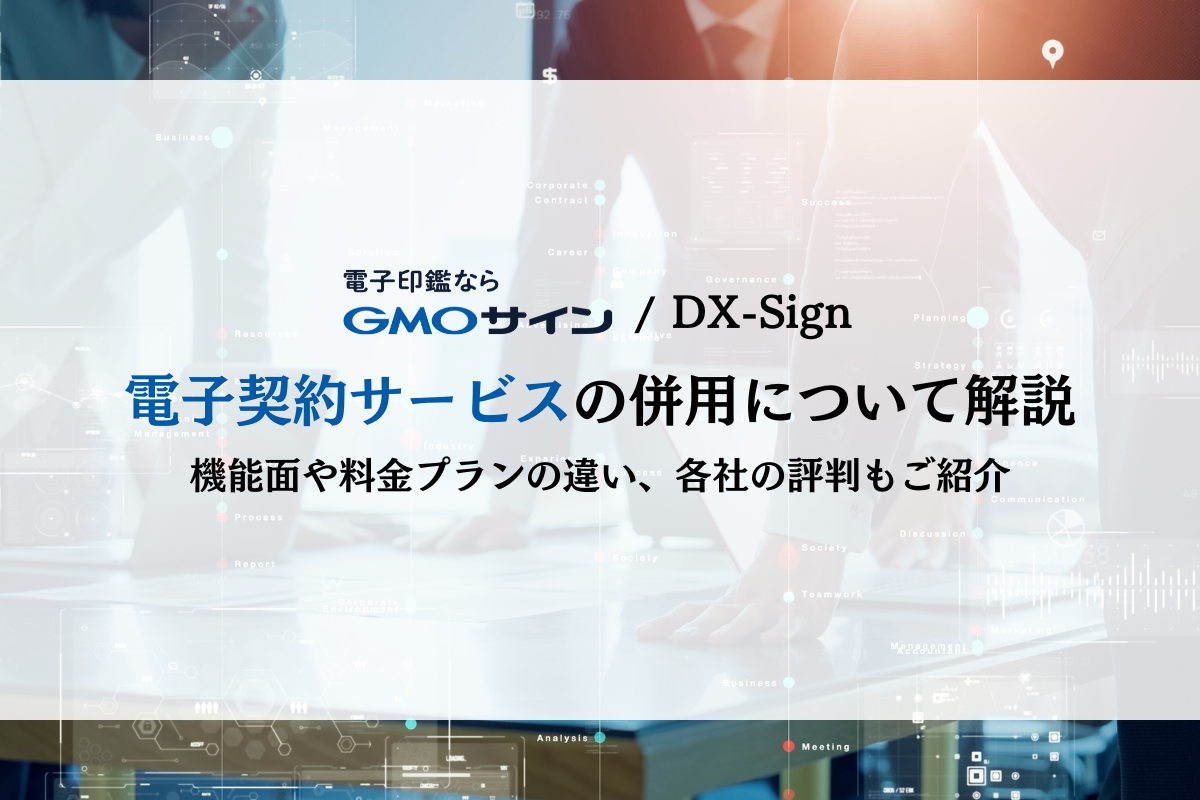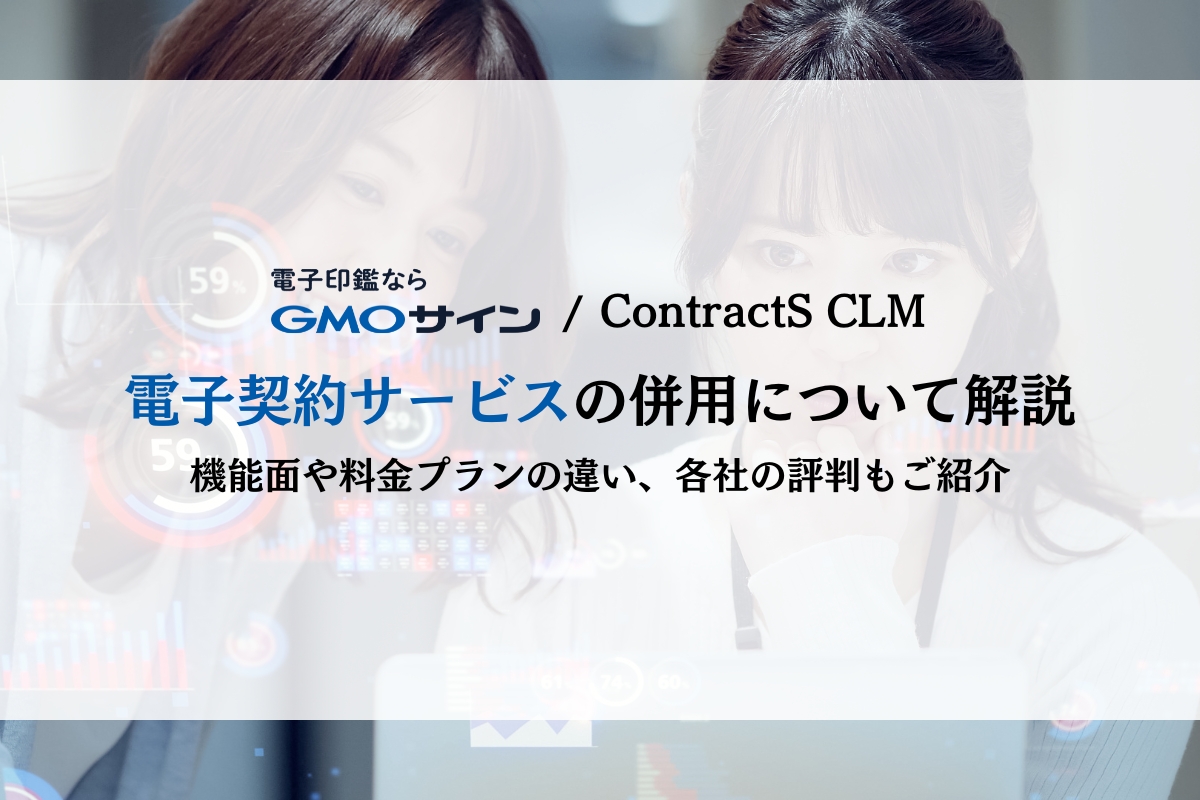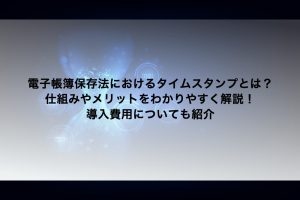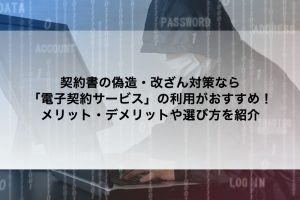押印のない契約書は法的に有効?
相手方との間でトラブルが発生した際、押印がないと契約の証明が難しくなる?
電子契約には従来の押印に代わる確実な証拠力がある?
結論からお伝えすると、押印のない契約書でも法的には有効です。しかし、証拠力の観点から注意が必要です。本人の意思表示を証明できないリスクや、契約の存在自体が争われる可能性があります。
この記事では、契約書における押印の法的意味と、押印なしでも安心して契約を結ぶための対策について詳しく解説します。
- 押印なしの契約書の法的効力と根拠
- 押印の本来の役割
- 押印がない場合に生じるリスクとトラブル事例
- 電子契約時の押印の代替
- 押印がない契約書を結ぶ際の対策方法
より安心して契約を結ぶためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。電子署名とタイムスタンプにより、従来の紙の契約書と同等の法的証拠力を持った契約が可能で、なおかつ改ざんを防ぎやすいといった特徴もあります。電子契約の場合は印紙も不要になるため、コスト削減にも役立つでしょう。
- 法的証拠力の高い電子署名機能を標準搭載
- タイムスタンプにより改ざん防止を実現
- 直感的な操作で誰でもかんたんに利用可能
- 高度なセキュリティで機密情報を保護
GMOサインのお試しフリープランでは、月に5件まで電子契約を無料で行えます。電子署名や契約書の管理、テンプレート登録といった基本的な電子契約の機能を利用できるので、この機会に体験してみてはいかがでしょうか。
押印なしの契約書に効力はある?
押印なしの契約書に効力はあるのか、以下のとおりに解説します。
順に見ていきましょう。
契約書に押印がない場合の法的効力
契約書に押印がなくても、法律上その契約が無効になるケースは基本的にありません。民法には「契約自由の原則」があります。当事者間の合意があれば、契約は成立するという考え方です。
たとえば、口頭での約束でも契約は成立し、内容について合意されていれば、メールやチャットでのやり取りも法的な効力を持つ場合があります。契約に必要なのは、あくまでお互いの合意です。
押印のない契約書が認められるケース
以下のような場合は、押印のない契約書でも一般的に認められます。
- メールやチャットなどの記録がある
契約内容について具体的なやり取りがされており、双方が合意に至ったことが明確に記録されている場合 - 録音データがある
口頭で契約した内容が録音され、当事者の双方が合意している旨を確認できる場合 - 契約内容が履行されている
実際に商品やサービスが提供され、対価が支払われている場合
いずれも、当事者間の合意が客観的な証拠として示せる場合です。ただし、メールを誤って削除したり、録音データに雑音が入っていたりすると、合意を示す証拠として使えないおそれがあるため注意しましょう。
契約の成立における押印の役割とは?
押印は契約の成立において必須ではないと説明しましたが、契約書では押印が求められるケースが多々あります。その背景として、押印にはおもに2つの役割があるからです。
1つ目は、証拠としての役割です。契約書に押印をすると「この契約書は本人が作成し、内容に同意している」という証拠になり得ます。万が一、契約内容について争いが生じた場合でも、押印があれば本人の同意があった旨の証明が可能です。
2つ目は、本人の意思を明らかにする役割です。押印という行為は「契約内容に同意し、これを遵守する」という意思を示します。押印によって、後から「知らなかった」「同意していない」などの主張をされるリスクを減らせます。
なぜ押印なしでも契約書は有効なの?法的根拠を徹底解説
押印なしでも契約書が有効である理由を、法的観点から解説します。
それぞれ見ていきましょう。
契約の成立要件
契約は、当事者双方の「申し込み」と「承諾」という意思表示が一致することで成立します。お互いが契約内容に合意したその瞬間に、契約は法的に効力を持つのです。
民法では、口頭の約束でも契約が成立すると定められています。そのため、押印がないからといって、契約が無効になるわけではありません。
民法上の「契約自由の原則」により契約方式は自由
民法第522条には、契約の形式や手続きよりも、当事者間の「申し込み」と「承諾」の有無を優先するという「契約自由の原則」が明記されています。
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:民法 第五百二十二条
押印は契約の成立で必須とされる要件ではなく、当事者間の合意が大切です。どのような形式で契約を結ぶかは、基本的に自由とされています。
ただし、この「契約方式の自由」には重要な例外があります。法律によって、書面で作成しなければ契約の効力が認められない「要式契約」が定められているためです。
- 保証契約(民法第446条2項)
- 事業用定期借地権設定契約(借地借家法第23条3項)
- 任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条)
これらの契約は、たとえ当事者間で口頭の合意があっても、法律で定められた形式(書面)で作成しない限り、法的に無効となります。すべての契約が押印不要・書面不要というわけではないため、重要な契約を結ぶ際は、書面作成義務の有無を事前に確認することが不可欠です。
書証においても押印の有無は関係ない
裁判では、押印がない契約書でも有効な証拠として扱われます。民事訴訟法で、契約書は「書証」として証拠能力を持つとされていますが、押印の有無は問われません。
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
引用:民事訴訟法 第二百二十八条
契約書の内容が真実であり、当事者間の合意を反映しているかどうかが大切です。契約が成立した証拠として、慣習的に契約書の作成や捺印が行われてきましたが、法的に必須ではありません。
契約書に押印は不要だが重要!押印が持つ3つの意味と役割
契約書において押印は必須ではありませんが、重要であることは確かです。
押印が持つ意味や役割について解説します。
証拠力の強化
押印された書面は高い証拠力を持つとされています。民事訴訟法第228条4項では「署名又は押印がある書面は、本人の意思に基づいて作成されたものと推定する」と定められているためです。
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
引用:民事訴訟法 第二百二十八条
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
押印がなくても契約が無効になるわけではありません。しかし、後々「この契約書は自分が作成したものではない」と主張された場合に、本人の意思である旨を証明する手間が増えるおそれがあります。押印は、そのような事態を避けるための手段の1つとして有効です。
意思表示の明確化
押印は、契約の内容に合意したという意思を明確に示す役割も担っています。契約は、当事者同士の意思の合致で成立します。
しかし、口頭の合意だけでは、後になって「言った」「言わない」の争いにつながりかねません。書面に署名と押印をすることで、契約内容に同意し、その内容に拘束されるという当事者の意思が示されます。
心理的効果
契約の当事者に対して、安心感など心理的な効果をもたらす場合もあります。また、印鑑を押すという行為は、契約の重みや責任を意識させ、軽々しい気持ちで契約を結ぶのを抑制する可能性があります。
電子契約で押印がない場合の法的効力は?
最近は紙の契約書に代わって電子契約で取り交わす機会も増えています。電子契約で押印がない場合の法的効力についても理解しておきましょう。
電子契約の法的有効性
電子契約で締結する際にも押印は不要です。電子署名法には以下の記載があります。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名法 第三条
特に重要なのは、本人による電子署名がされていること、タイムスタンプによりその署名や内容が改ざんされていないことが明らかであることです。電子契約においても押印や印影画像の挿入は必須ではありません。
電子契約における電子署名・タイムスタンプの役割
電子契約では、電子署名とタイムスタンプが、紙の契約書における押印や署名の代わりを担っています。
文書が作成されたことを証明し、改ざんされていないことを確認するための技術。契約の当事者が本人であること、契約の内容が途中で変更されていないことを証明できる。
電子署名がいつ行われたかを証明するもの。特定の時刻にその文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを示す。
電子署名とタイムスタンプを利用することで、電子契約でも紙の契約書に劣らない証拠力を持てます。
\\ こちらの記事もおすすめ //

電子契約書に押印が付与されている理由
電子契約書では、紙の契約書のように押印(印影風画像)が付与されている場合があります。押印が不要であるはずの電子契約書になぜ押印が入っているのでしょうか。
そのおもな理由は「契約書に押印するのは当たり前」と考えている人に安心して電子契約をしてもらうためです。日本では契約書に押印する慣習があり、押印がないことに不安を感じる人がいると考えられます。押印を付与することで、安心感を与え、電子契約をスムーズにする狙いがあります。
押印なしの契約書でトラブルになるケースとリスク
押印なしの契約書は法的に有効ですが、以下のようなリスクが発生する可能性があります。
本人の意思表示を証明できないリスク
契約書に押印がないと、本人の意思でその内容が合意・作成されたことを後から証明できない可能性があります。「本当に本人の意思で作成されたものなのか」と疑問が生じるおそれがあるのです。
もし、本人が「契約内容が私の意思とは違う」と主張した場合、押印がなければ、その反論を覆すための証拠が不足しかねません。その結果、契約の有効性が否定されたり、トラブルの解決に時間がかかったりするリスクがあります。
契約の存在自体が争われるリスク
契約が正式に締結されたことを示す押印がない場合、相手方が「そのような契約は存在しない」と主張する可能性もゼロではありません。
口頭での合意やメールのやり取りでも契約は成立しますが、それだけでは不安な場合、契約書があればその内容と契約の成立を明らかにできます。しかし、契約書を作成しても押印がないと、相手方が「これは単なる交渉段階の書類だ」といった主張をした際に、否定する証拠として使えない可能性があるのです。
改ざん・捏造のリスク
押印がない契約書には、改ざんや捏造のリスクも潜んでいます。押印がないと、契約書の書き換えや偽造が、押印ありの場合に比べて容易です。
万一、契約書が改ざん・捏造されてしまった場合、不正を立証するには、ほかの証拠を集める必要があり、手間と時間がかかります。予期せぬリスクを避けるためには、契約書に押印をしておいたほうがより安心でしょう。
押印なしの契約書によるトラブルを防ぐための対策
押印なしの契約書でトラブルを防ぐための対策を以下の2パターンに分けて解説します。
それぞれ見ていきましょう。
書面契約の場合の対策
書面契約においてトラブルを防ぐための対策は以下の4つが挙げられます。
- 当事者の署名・記名を必ず得る
- メールやメッセージで合意形成の証拠を残す
- 契約内容の具体的な記載
- 公正証書の活用(特に大切な契約の場合)
順に見ていきましょう。
当事者の署名・記名を必ず得る
押印がない書面契約では、必ず当事者に署名や記名をしてもらいましょう。なお、署名と記名の違いは以下のとおりです。
- 署名:手書きで氏名を書くこと
- 記名:手書き以外の方法で氏名を書くこと(例:印刷など)
法的な証拠としての証明力は、一般的に署名の方が強いとされています。なぜなら、手書きの署名は筆跡鑑定によって本人が書いたことを証明しやすく、契約書が本人の意思で作成されたことの強力な証拠となるためです。
メールやメッセージで合意形成の証拠を残す
契約の締結に至るまでの過程で、メールやチャットなどのツールを使い、合意形成の証拠を残すのも対策の一つです。たとえば、「この条件で契約を進めてよろしいでしょうか?」「はい、問題ありません」といったやり取りがあれば、契約内容に合意した証拠として使えます。
契約内容の具体的な記載
契約書の内容は、誰が読んでも誤解が生じないよう、具体的に記載します。あいまいな表現や抽象的な言葉づかいは避け、義務と権利・契約期間・金額などを詳しくすると、解釈のずれやトラブルを防げます。
たとえば、「適切な対価を支払う」ではなく「〇月〇日までに〇円を支払う」といった記載をしましょう。さまざま解釈ができる表現を使うとトラブルにつながりやすいので、数字や固有名詞を用いて記載するのがおすすめです。
公正証書の活用(特に重要な契約の場合)
特に重要度が高い契約では、公正証書の利用を検討しましょう。
金銭の支払いなどに関する契約で、「債務者が支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する」旨の文言(強制執行認諾文言)を記載しておけば、万が一契約内容が履行されない場合に、裁判を経ずに強制執行の手続きに移ることが可能です。
費用はかかりますが、多額の金銭が絡む契約や長期間にわたる契約では、公正証書を利用するのも一つの手です。
\\ こちらの記事もおすすめ //
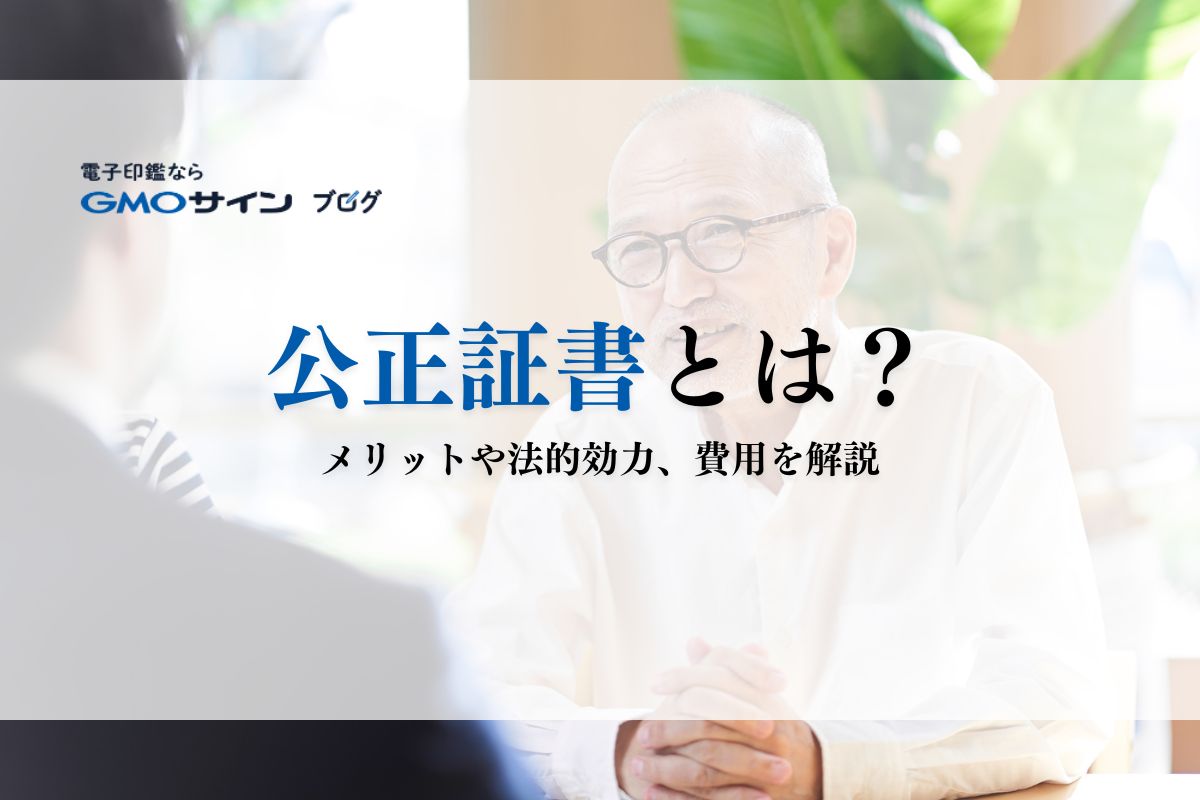
電子契約の場合の対策
電子契約の場合は、以下のような対策ができます。
- 法的効力のある電子署名サービスを利用する
- 契約締結プロセスの適切な記録・保存
順に見ていきましょう。
法的効力のある電子署名サービスを利用する
電子署名法により、要件を満たした電子署名には署名や押印と同等の法的効力が認められています。そのため、電子契約を行う際には電子署名法に準じた電子契約サービスを利用するのがおすすめです。
電子契約においては、信頼できる電子署名サービスを選んで利用することが大切です。
契約締結プロセスの適切な記録・保存
電子契約で押印がない場合にトラブルを防ぐには、契約を締結したプロセスの記録と保存が欠かせません。「いつ、誰が、どのような契約に合意したのか」といった情報をシステム上で管理すれば、双方が合意に至った過程がわかります。
なお、GMOサインなどの電子契約サービスでは、以下のタイムスタンプが自動的に記録されます。
- 契約書を作成した日時
- 送信履歴
- 閲覧履歴
- 署名した日時
争いに発展した場合でも、契約の有効性を主張するときの根拠となり得るため、電子契約サービスの導入をおすすめします。
押印のない契約書の有効性に関するよくある疑問
契約書に押印がなくても有効?
契約書に押印がなくても、法律上は有効です。契約の成立に押印は必須とされておらず、当事者同士が合意していれば契約は成立します。
書面に押印することは、あくまで合意があったことを証明する手段の1つです。
契約書に署名がなくても効力はある?
契約書に署名がない場合でも、契約の効力が認められるケースはあります。民法では、契約の成立要件として、押印と同様に署名も必須とはされていないためです。
鍵となるのは、契約を結ぶ双方の意思が合致していることです。口頭での合意や、メールのやり取りなどで契約の意思が明確に示されていれば、署名がなくても契約は有効と判断される可能性があります。
ただし、後のトラブルを避けるために、契約書には署名または押印を行っておくことが推奨されます。
契約書だけでなく、見積書や請求書にも押印は不要?
見積書や請求書についても、原則として押印は必須ではありません。契約書と同じく、法律で押印が義務付けられている書類ではないためです。
ただし、押印をすることで、その書類が正式に発行されたものであることを示し、信頼性を高められます。
なお、企業間の取引では慣習として押印を求められるケースがあるため、取引先の慣習にあわせて判断しましょう。
契約書への押印を廃止するメリットは?
契約書への押印を廃止すると、以下のメリットがあります。
- 業務の効率が上がる
書類の印刷・郵送・対面でのやり取りといった手間がなくなる - コストを削減できる
印紙代や郵送費などを抑えられる - 押印のために出社する必要がない
テレワークへ対応しやすい
押印の廃止に加え、電子契約を導入すると契約業務がスムーズに行えます。
FAXやメールで送られてきた契約書に押印がなくても有効?
FAXやメールで送られてきた契約書に押印がなくても、契約自体は有効になる可能性があります。契約の成立には、当事者間の合意があればよく、押印は必須ではないためです。
なお、FAXやメールでのやり取り自体が、契約への合意を示す証拠として認められる場合があります。
たとえば、メールで最終的な契約内容を確認し、「この内容で同意します」という明確な意思表示があれば、契約が成立した証拠となり得ます。
契約書に押印がなくても、契約の法的効力は認められる
押印がなくても契約の法的効力は認められます。契約は当事者の合意で成立するとされ、押印は必須の要件ではありません。
ただし、押印は契約が成立したことの証拠力を高め、当事者の意思表示があったことを明確にする役割があります。金額の大きな契約や重要な契約であれば、契約書を作成して押印すると安心です。
なお、書面での押印を廃止したいと考えているなら、電子契約サービスの導入がおすすめです。オンライン上で双方が電子署名とタイムスタンプの付与を行うことが可能で、紙の契約書と同等の法的証拠力を担保できます。
GMOサインの「お試しフリープラン」では、月間5件まで無料で電子契約が可能です。「押印を廃止したいが急に切り替えるのは不安」といった場合は、以下よりお気軽にお試しください。
\ \ クレジットカード登録不要 //