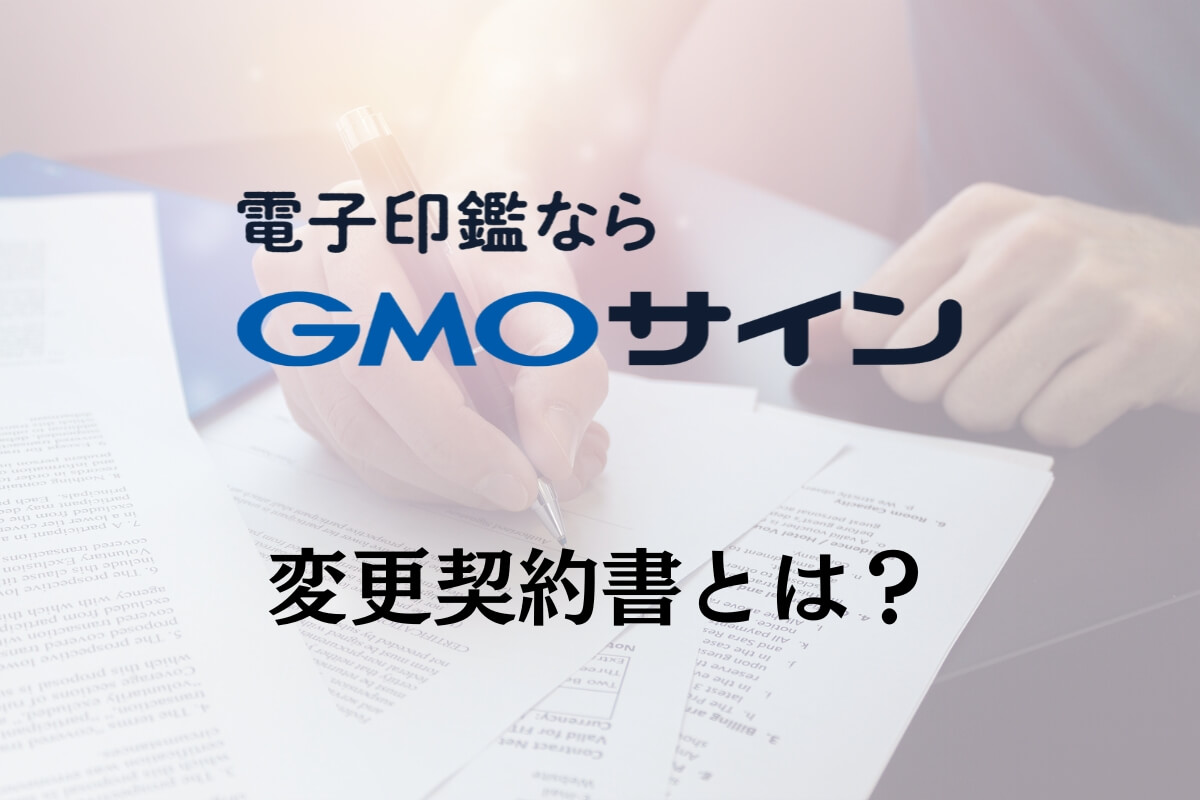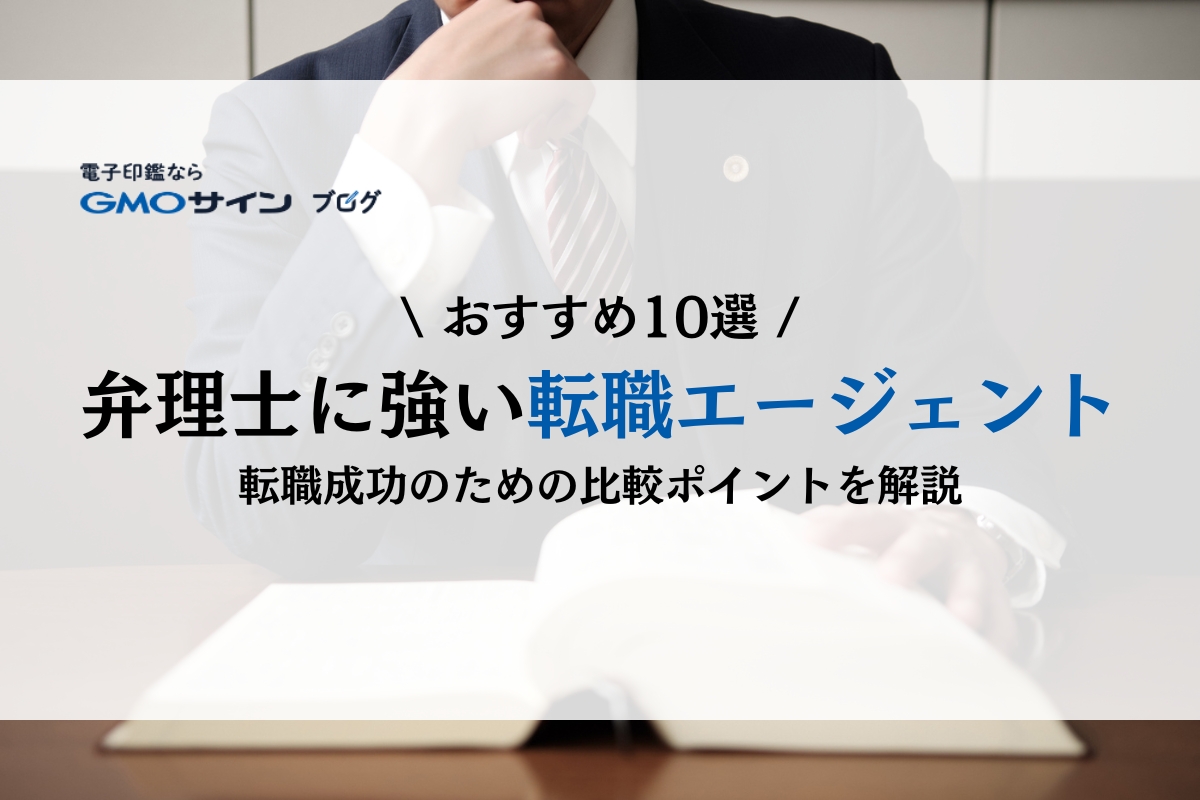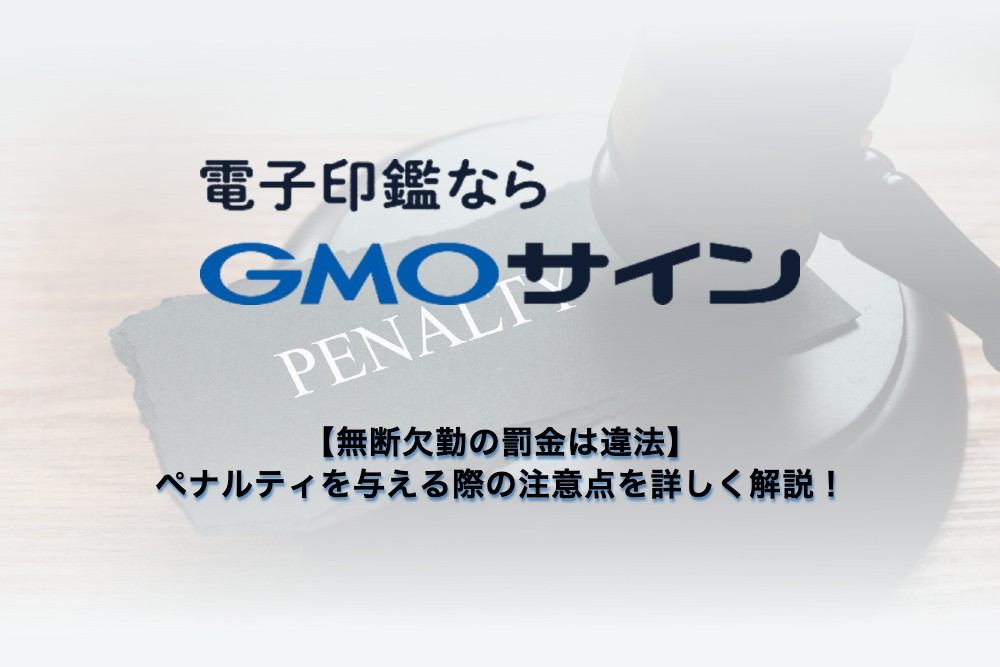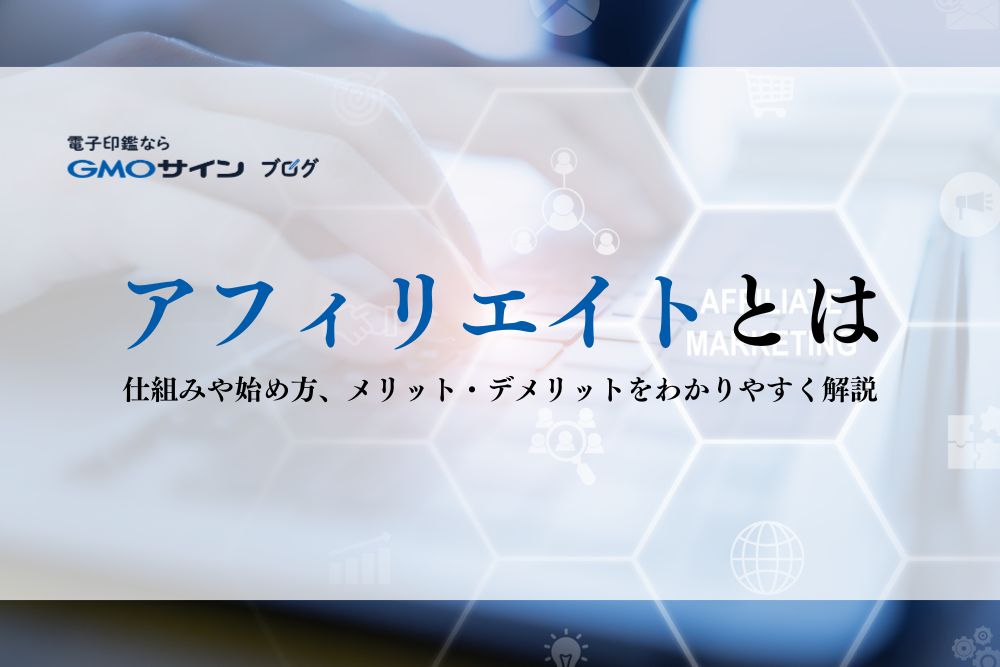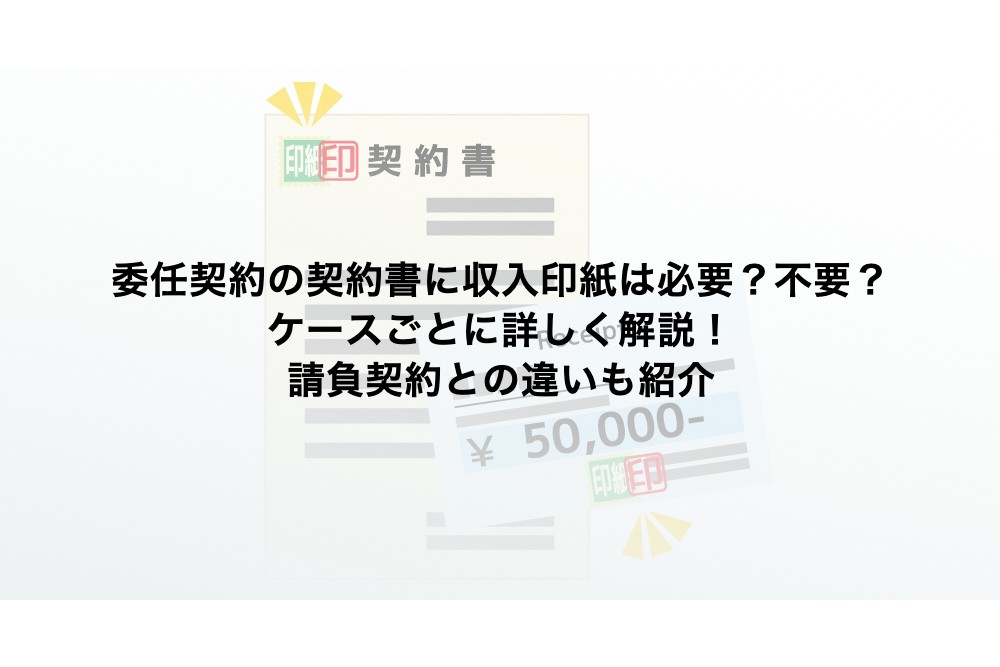従業員が無断欠勤をした場合に、上司や経営者は電話などで連絡をして理由を尋ねたり出社するように促したりするのが一般的な対応でしょう。無断欠勤をしていても、連絡さえ取れれば、従業員がどのような状況か把握できます。
しかし、無断欠勤している従業員と連絡が取れなくなることもあるでしょう。そのような状態が続くと、会社としては従業員の安否が気になり、業務を進める上でも支障が出てしまうため何とかしたいところです。
本記事では従業員が無断欠勤していて連絡が取れない場合にどう対処すべきか、注意点とあわせて解説します。
従業員が無断欠勤する主な理由・原因
従業員が無断欠勤してしまう理由はさまざまであり、意図的に無断欠勤しているのではなく連絡できない状態であることも考えられます。では、従業員が無断欠勤する理由や連絡できない原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
そのまま退職するつもりでいる
本来であれば、退職する際にはきちんと連絡して退職届を提出しなければなりません。しかし、責任感の弱い従業員だと、退職するつもりで無断欠勤をしてそのまま出社しなくなるケースもあります。
特に強く叱責したり激しい口論になったりしたような事情があれば、その可能性が疑われるでしょう。辞めるかどうかに関して口論になっていた場合には、本人は退職の意思を伝えたつもりになっているケースも考えられます。
アルバイトなど非正規の雇用形態の従業員の場合、きちんと手続きを踏まなくても辞められると誤認しているケースもあるようです。
ケガや病気で出勤できない状態
ケガをしてしまったり病気にかかってしまったりして出社できず連絡が取れない可能性もあります。
たとえば、交通事故に遭って救急搬送されてそのまま入院しているような場合です。軽傷であれば連絡できますが、重傷だと症状が回復するまで連絡するのは難しいでしょう。
また、精神疾患で出勤したり会社に連絡したりするのが難しい状態に陥っているケースもあります。
事件に巻き込まれている
何かしらの事件に巻き込まれている可能性もあります。
容疑者として警察に逮捕されていれば、出社することも、会社への連絡もできません。また、事件の被害者になっている可能性もあります。
どちらの場合も、家族や弁護士が会社に連絡して知らせることが多いです。
職場内でのハラスメントにより出勤を拒んでいる
パワハラやセクハラなどが職場内で行われている場合には、それを苦痛と感じて出勤できない可能性もあります。被害を訴えていた可能性がある場合は、事実関係を調査してみましょう。
人事異動に抵抗する意図で出勤を拒んでいる
人事異動に対して拒否する意思を表明するために無断欠勤するケースも希に見られます。人事異動の発表があったり、人事異動に関する話をしたりした直後なら、その可能性を疑ってみましょう。
無断欠勤で連絡の取れない従業員の安否確認をする方法
無断欠勤で従業員と連絡が取れない場合には、まずは安否確認が必要です。安否確認をする主な方法について見ていきましょう。
LINE・メール・ビジネスチャットツール
普段従業員と連絡に用いている方法の他にも、利用可能な連絡手段があれば、メッセージなどを送信してみましょう。
電話が通じない場合には、スマホが料金滞納などで止められてしまっている可能性もあります。メールの場合にはパスワードを紛失するなどして、ログインできなくなっていることも考えられるでしょう。
LINEやメール、ビジネスチャットツールなど複数の方法で連絡を入れてみると、応答してもらえることもあります。
自宅を直接訪ねる
どの通信手段でも連絡が取れない場合には、直接自宅を訪ねてみましょう。
ただし、ハラスメントが原因となっている可能性が高い場合には、直接自宅を訪問するのは避けた方がいいかもしれません。
自宅を訪ねた際、郵便受けに郵便物が大量に溜まっているようであれば、何日も帰宅していない可能性があります。
連絡が取れた後の対処法
無断欠勤している従業員と連絡が取れた場合には、まずは無断欠勤をしている理由を尋ねましょう。
ケガや病気、精神疾患などが原因で連絡できない状態だった場合には、休職の手続きが必要です。ハラスメントが原因だった場合には、事実関係を詳しく調査した上で、対策を講じる必要があります。
人事異動に応じないなどの理由で無断欠勤している場合には、一度話し合いの場を設けることも重要です。本人が考え直して応じてくれる可能性もあります。話し合いの結果、退職という運びになった場合には、退職の手続きを進めましょう。
まったく連絡が取れない場合の対処法
無断欠勤している従業員とまったく連絡が取れない場合には、次のように対応する必要があります。
身元保証人に連絡する
雇用契約を締結する際に、ほとんどの場合身元保証人を立てているでしょう。
主に親族が身元保証人になっているため、連絡してみることで、本人の状況がわかる場合もあります。また、本人と連絡が取れないことを身元保証人に知らせる意味でも、身元保証人への連絡は必要です。
管理会社に連絡する(賃貸やマンションの場合)
無断欠勤している従業員の自宅が賃貸住宅やマンションの場合には、管理会社に連絡してみましょう。事情を説明すれば、管理会社の方で鍵を開けて確認してくれる可能性が高いです。自宅内で倒れていないかどうかも確認できます。
警察に連絡する
身元保証人や管理会社に連絡しても、本人の所在かわからない場合には、行方不明になっている可能性があります。気になる場合は警察に連絡しておきましょう。
解雇を検討する
無断欠勤が続き連絡が取れない従業員でも雇用関係が続いていれば、会社は社会保険料を負担しなければなりません。コストだけが発生し続けることになるため、見つかって勤務が再開する見込みがなければ解雇を検討するのが妥当でしょう。
解雇する場合の注意点
無断欠勤で連絡の取れない従業員を解雇する際には、次のような点に注意が必要です。
就業規則の規定に沿って手続きを進める
無断欠勤が続いていて連絡が取れないことを理由に従業員を解雇する際には、就業規則の規定を適用して手続きを行うのが基本です。
就業規則の規定内容によっては、解雇ではなく退職扱いとする場合もあります。
また、行方不明により解雇または退職扱いする場合の無断欠勤日数の目安は2週間ほどです。就業規則の規定に沿って手続きを行った場合でも、無断欠勤日数がまだ少ないと、解雇できない場合もあります。
安否確認の証拠が必要
解雇または退職扱いにした後に、従業員が出社してきたり連絡を入れてきたりしてトラブルになるケースもあります。
ひどい場合には訴訟に発展するケースもあるため注意が必要です。
こうした場合、安否確認を行った上で、連絡がとれず行方不明と判断したことを証明しなければなりません。
メールやLINEなどでの連絡は証拠能力が弱いため、内容証明郵便を送付しておくことが望ましいでしょう。
内容証明郵便を送っておくことで、安否確認を行ったという事実と、郵送された日時が正式に記録されます。
解雇通知書の送付が必要
本人が出社していれば、対面で伝えた上で解雇通知書を手渡せますが、連絡が取れない場合には郵送による方法となります。この場合も、証拠として残せるように内容証明郵便を利用しましょう。
解雇通知書には、解雇日を明記する必要があります。また、労働基準法第20条において、解雇予告の規定が設けられている点に注意しましょう。30日間の猶予を設けるか30日分の給与に相当する解雇予告手当を支払うことが定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
30日間の猶予を設けると、会社は解雇日までの間は社会保険料を負担する必要があります。これに対して、解雇予告手当を支払って解雇通知を受け取った日に解雇するようにすれば、社会保険料の負担はありません。
多くの場合、解雇予告手当を支払う方法を選ぶ方が得策です。
また、両方の方法を組み合わせることもできます。たとえば、10日間の猶予を設けて20日間分の解雇予告手当を支払うような形です。
解雇できない場合もある
従業員が無断欠勤をしている理由がケガや病気、精神疾患、ハラスメントの場合には解雇することができません。
ケガや病気、精神疾患の場合には、医師の診断書を提出するように伝えた上で、休職扱いにする対応が一般的です。
診断書の提出を求めても提出しない場合には、解雇することもできます。
ハラスメントが原因の場合には、調査と職場環境の改善をしなければなりません。防止策を十分に講じた上で、従業員に対して出社を求めます。それでも出社しない場合には解雇も可能です。
解雇・退職扱い後に行うべきこと
無断欠勤が続いて連絡が取れなくなった従業員を解雇または退職扱いにした後に行うべきことを見ていきましょう。
未払い給与の支払い
当該従業員が無断欠勤をしている間の給与に関しては、会社に支払い義務はありません。しかし、先月分の締め日から無断欠勤をする直前まで間の給与は支払う必要があります。この場合、欠勤控除という形で欠勤日の日数分だけ日割りで差し引く形で精算します。
また、退職金制度のある会社なら、退職金に関しても精算が必要です。この場合、最後に出勤した日を退職日として扱います。
私物の返還・処分
突然無断欠勤が続いた場合には、デスクの引き出しやロッカーなどに私物を置いたままになっていることも多いでしょう。本人と連絡が取れた場合には、私物を取りに来るように伝えましょう。
本人と連絡が取れない場合には、処分することになりますが、トラブルを避けるため、内容証明郵便を利用するのが無難です。
期限を指定した上で取りに来るように催促し、期限を過ぎたら処分する旨の内容を記載します。解雇通知書と一緒に送付すればスムーズでしょう。
すぐに取りに行くのが難しい場合もあるため、私物を処分する期限は長めに設定しておきましょう。1カ月先くらいが望ましいとされています。
また、身元保証人が近くに住んでいる場合には、身元保証人に引き取ってもらう方法でも問題ありません。
従業員が休職する場合の手続き
従業員がケガや病気で連絡が取れない状況が続いていた場合なら、連絡が取れた後も出勤が難しいことが多いでしょう。休職することになった場合には手続きが必要です。
休職願を提出するように指示
休職する際には、就業規則の規定に則って休職の手続きをしなければなりません。ケガや病気で出社が難しい状況なら、休職届の用紙を郵送するなどしたうえで、提出するように本人に指示しましょう。
社会保険料と住民税の手続き
そのことを本人に対して説明しておく必要があります。また、給与からの天引きができないため、支払い方法についても決めておく必要があるでしょう。
傷病手当金の手続き
ケガや病気で休職する際には、4日目以降に関して健康保険から傷病手当金が支給されます。申請書を書くのは本人ですが、事業主の証明など会社の方で記載しなければならない部分も一部あります。
まとめ:解雇する場合でも休職させる場合でも必要な手続きは確実に済ませよう
従業員が無断欠勤を続けて連絡が取れなくなった場合には、さまざまな理由が考えられます。
まずはLINEやメール直接訪問などできる限りの方法でコンタクトを試みることが大切です。どうしても連絡がつかない場合には、身元保証人に連絡した上で解雇の手続きを行います。また、ケガや病気などが原因の場合には休職手続きが必要です。
いずれの場合も必要な手続きをせずに放置してしまうことだけは避けるようにしましょう。