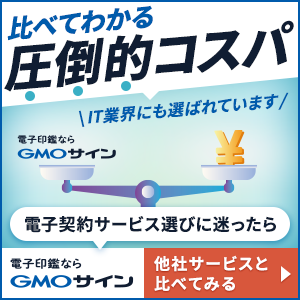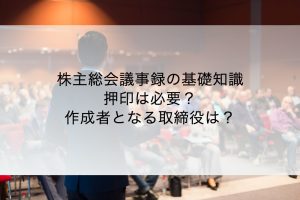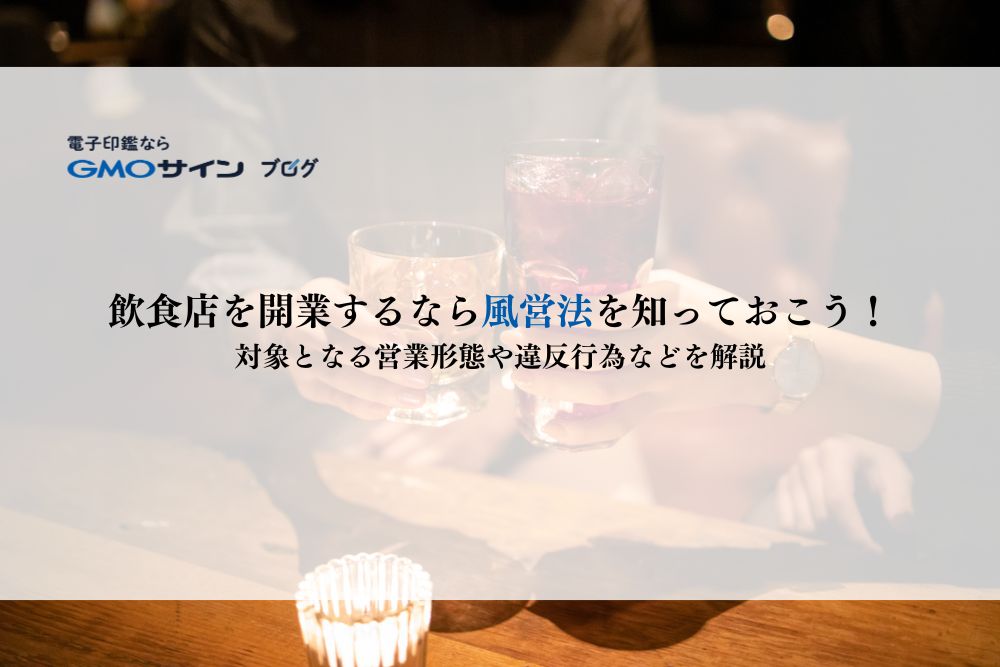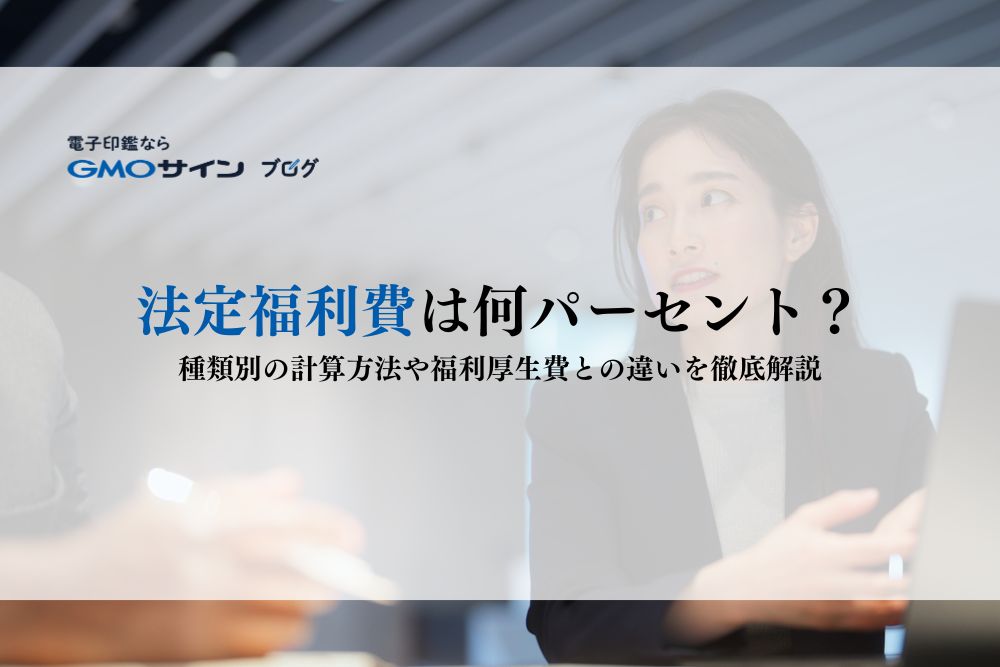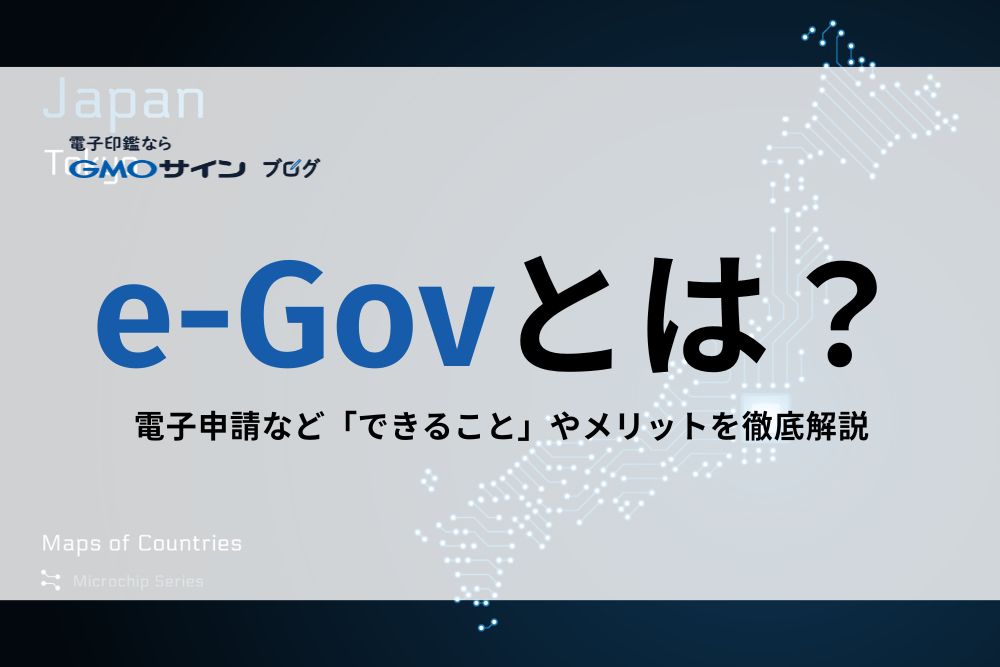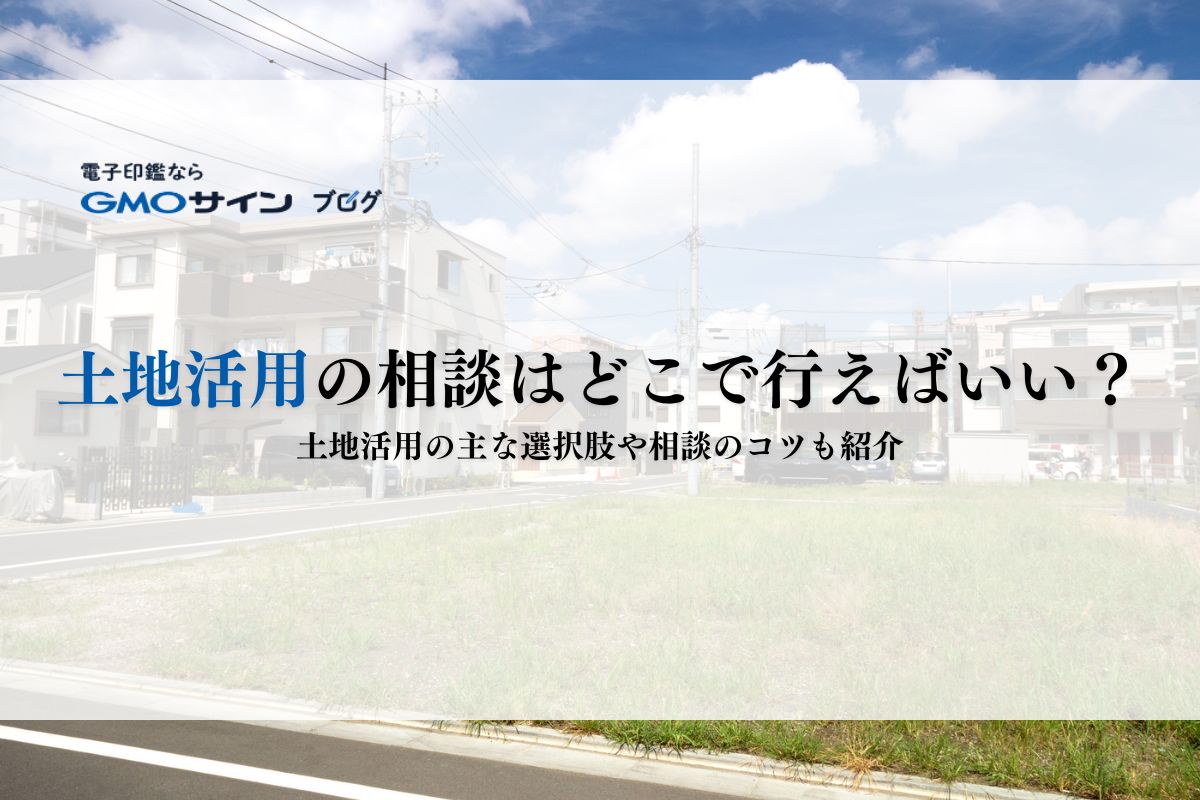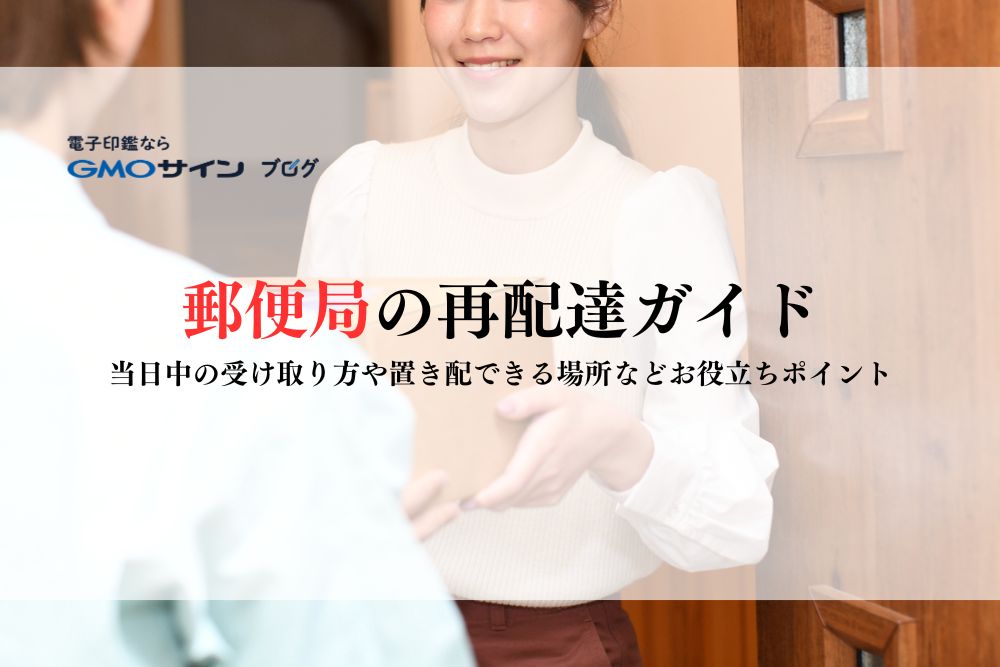転職は、キャリアの形成や所得の増加を図るうえで、よりよい環境を求める手段です。しかし、安易な転職は後悔のもとになる可能性があります。
収入は増えたけど、前より忙しくなってライフワークバランスが崩れた
前の職場のほうが雰囲気がよかった
このような後悔をしないためにも、転職で失敗しやすいポイントを知っておきましょう。
この記事では、転職を検討中または後悔している人に向けて、転職で後悔しないための知識や後悔後の対策を解説します。転職による後悔ゼロを目指すために、ぜひ参考にしてください。
転職者の背景:およそ2割が再転職を希望している
厚生労働省の統計によると、一般労働者に対する転職者の割合は7.2%と、およそ14人に一人が転職者です。転職者の満足度調査では「満足」と答えた人の割合が53.4%なのに対し「どちらでもない」が34.5%、「不満足」が11.4%でした。
また、「今の職場で今後も働きたい」と答えた人の割合が52.7%なのに対し「転職したい」と答えた人が21.0%と、転職者のおよそ2割が再転職を検討しています。
転職によって環境を変えても、思い描いた働き方ができず後悔する人は少なくありません。
転職失敗例と後悔する5つの原因
転職で後悔する5つの原因を、失敗例とともにみていきましょう。
想定していた仕事内容ではなかった
転職で後悔する原因の一つ目は、求人情報から想定していた仕事内容と、実際の仕事内容が異なる場合です。
- 面接での説明が曖昧または誇張されていた
- 雑用などでやりたい業務に携われない
- 業務の専門性のレベルが想定より高い(または低い)
- 興味のある業務が別部署に移動または撤退した
求人募集や面接の担当者が、仕事現場の状況や業務をすべて把握していないケースもあります。そのため、思っていた仕事ではなかったと後悔するケースは珍しくありません。
年収が下がるなど労働条件が悪化した
転職後に労働条件が悪化した場合も、転職後に後悔する原因です。
- 年収の低下で予想より生活が厳しくなった
- 年収は上がったが休日が減り自由な時間がない
- 残業代が支給されず労働時間と収入が見合っていない
- 会社の業績悪化により賞与が支給されなかった
- 福利厚生や手当が最低限で、前職のほうが条件面で優れていた
特に、転職して年収が下がると後悔しやすくなります。
人間関係や社風に馴染めなかった
転職先の人間関係や社風に馴染めないと、転職後の後悔につながります。
- 上下関係が厳しく、自由に発言できない
- 上司や同僚と相性が悪い
- 情報共有や連携が十分にされない
- 派閥争いが絶えず、職場の雰囲気が悪い
- 中途採用者へのサポートが薄い
社内の人間関係や社風は転職前に把握しにくいため、入社後に自分とは合わない社風だったと後悔するケースは少なくありません。
会社の将来性に不安を感じた
入社後に会社の将来性に不安を感じ、後悔するケースもあります。
- 経営状態が悪化している
- 給与の支払いが遅れる、あるいは滞る
- 事業に将来性が見えない
- 不正行為が常態化している
- 社員の退職が相次いでいる
経営状態の悪さや、給料の不払い、不正の横行などは、事前に掴みにくい内部情報です。 たとえ待遇がよくても「働き続けて大丈夫だろうか」と不安を感じると、後悔につながります。
転職が目的になっていた
「今の職場を辞めたい」という気持ちが先行し、転職すること自体が目的となると後悔につながります。
転職で自動的に状況がよくなると思い込むと、不十分な自己分析で転職を進めがちです。また、企業研究を怠り、実情を深く理解しないまま入社すると、理想とのギャップを感じます。
転職で後悔しやすい人の特徴
転職で後悔しやすい人の特徴を確認していきましょう。
他人の言動や感情に振り回されやすい
他人の言動に左右されやすい人や、自分の感情に振り回されやすい人は転職で後悔しやすい傾向があります。
- 周囲やネット上の転職成功例に流されやすい
- アドバイスを鵜呑みにしてしまう
- 一時的な不満や感情で行動し、冷静な判断ができない
こうした特徴がある人は、自分にとっての働きやすさや労働の価値観を見失いやすくなります。深く考えずに転職を決めてしまうと「思っていたのと違う」と感じやすくなります。
理想の水準が高い
職場に対する理想が高い人も、転職後のギャップに悩みやすくなります。
求人や採用面接において、会社側は自社の良い面を強調しますが、どの職場にも欠点や課題があるものです。転職条件へのこだわりは大切ですが、高すぎる理想は現実とのギャップが大きくなり、後悔しやすくなる原因です。
今の職場から逃げたい気持ちが強い
転職の理由が「今の職場から逃げたい」という気持ちが強い人は、転職後に後悔しやすくなります。
起こった問題に向き合わないまま転職すると、根本的な問題が解決していないため、再び不満を感じるようになります。また、「早く辞めたい」との思いから、転職条件を妥協してしまうのも後悔する原因です。
自己理解が不十分である
自己理解が不十分な状態で、自分のやりたいことを優先してしまう人は、転職後に後悔しやすくなります。
自分のやりたい仕事が、自分のスキルや経験に見合っているとは限りません。間違った自己認識のもとで転職すると、転職先と自分のスキルとの不一致が生じてしまい、「仕事がうまくいかない」と後悔する可能性があります。
情報収集が不足している
企業の情報収集が不十分なまま転職先を決めると、転職後に後悔しやすくなります。
良い面が強調されている求人情報だけを読み込んでも、実態を掴めません。転職先の評判や将来性などを調べず、求人情報や募集要項のみで判断して入社すると、実際の職場環境や業務が想像と異なる場合があります。
転職成功へ導く6つのポイント
転職を成功させるために押さえておきたい6つのポイントを紹介します。
①転職の目的を明確にする
転職を成功させる一つ目のポイントは、転職の目的や理由を明確にすることです。
転職を考える理由が、
- 人間関係なのか
- 給与面で不満があるのか
- もっとスキルを磨きたいからなのか
など、まず転職を考える理由を具体的に言語化しましょう。
そのうえで、転職して何を実現したいのかを考え、目的を明確にします。人間関係でストレスを感じずに働きたい・給与を高くしたい・スキルを向上したいなど、理想の働き方をイメージしましょう。
転職の目的を明確にすると、転職の希望条件に優先順位をつけやすくなります。収入を上げたいから職場までの距離が多少遠くても構わないなど、自分が最も重視したい条件を見極めるためにも、目的を明確にしておきましょう。
②自分のスキルや信念を理解する
自分のスキルや信念を整理し、自己理解を深めることも、転職を成功させるポイントです。
以下の情報を書き出してみましょう。
- 所持している資格
- 勤務歴と職務内容
- リーダー・主任・課長などマネジメントや役職経験
- 実績や専門性
これらの情報を言語化すると、自分のスキルや強みを整理ができます。可能であれば第三者から、自分では気づきにくい長所や課題について意見をもらうと、より客観的な自己理解につながります。
スキルや信念を整理すると、自分に合った会社を見つけられるため、後悔を防ぐためにもスキルや信念の見直しは必要です。
③自分に必要な収入を把握する
自分に必要な収入はどれくらいかを把握しましょう。
現在の収入より「大体このくらい増えるといいな」「このくらいなら減ってもいいかな」と曖昧に考えると給与面で不満が生じやすくなります。以下の情報を整理し、自分の人生設計や生活スタイルに合った収入を試算しましょう。
- 毎月の生活費
- 生活費のなかで増やしたいもの、減らせるもの
- 現時点での貯蓄額と毎月の貯蓄額
- 支出予定(車の費用やマイホーム購入、結婚出産など)
- 老後資金
これらを整理すると、転職先に求める年収の目安がはっきりします。
④求人情報の意図を読み取る
求人情報から意図を読み取ることも大切です。
求人には良い印象を与える情報が多く、会社の表面的な良さしか分かりません。しかし、どの会社も抱えている問題はあります。また、会社のアピールポイントによっては、働きにくさにつながる可能性があります。例えば、
- 急募・大量募集 → 離職率が高い可能性
- アットホームな職場 → 飲み会や社内イベントが頻繁にある場合も
- やりがいがある → 賃金と労働が見合っていない可能性
- 年収〇万円も可能 → 歩合制(成果報酬型)で収入が安定しにくいことも
- 若手が活躍中 → ベテランがいない、人材が定着していない懸念
といったように、求人情報を深く読み取ると、会社の内部事情や社風がみえてきます。
⑤実際に働いている・働いていた人の口コミを調べる
実際に働いている、あるいは過去に働いていた経験がある人の口コミを調べ、企業研究を深めることも転職成功のポイントです。
- 残業の量や休暇の取りやすさ
- 上司や同僚との関係性
- 社内の雰囲気
- 働いてみないと分からない問題点
こうした情報は、求人票や面接だけでは把握できません。
口コミを調べる場合は、一つの意見で判断しないように注意してください。また、古い口コミは現在の状況と異なる可能性もあります。信頼性を見極めつつ、実態を把握しましょう。
⑥面接で会社の実情を確認する
面接では、会社の雰囲気や内部の様子をしっかり確認しましょう。面接は会社に評価されるだけではなく、自分自身が会社を評価する場でもあります。実際に会社へ訪れたら、働いている人の言動・オフィスの清潔感・雰囲気や社風を観察しましょう。面接では、とくに以下のような点を確認します。
- 求人内容と実際の労働条件との相違
- 業務内容や期待されるスキルのレベル難易度
- 働き方や評価制度に関する質問への対応
面接官が、質問に対し率直に答える会社は、信頼性が高い傾向にあります。一方、回答を曖昧にしたりはぐらかしたりする場合は、実態を理解していない可能性があり、現場とのミスマッチが生じるリスクがあります。
\\ こちらの記事もおすすめ //

転職後の後悔を防ぐチェックリスト
転職後に後悔しないためには、事前に重要なポイントを押さえておく必要があります。チェックリストを参考に、冷静に情報を見極めましょう。
転職を検討しはじめた段階のチェックリスト
転職を検討しはじめた段階では、以下をもとに自分のスキルや転職の目的を整理しましょう。
- 転職したい理由が明確か
- 現職で解決できないか検討したか(異動や相談など)
- 転職によって何を実現したいか
- 自分のスキルや経験を整理・言語化したか
- 希望条件をリストアップしたか
- 条件に優先順位をつけたか(年収・勤務地・勤務時間・社風・業種など)
- 家族やパートナーと相談したか
これらを明文化すると、転職の軸がはっきりします。
転職先を決める段階のチェックリスト
転職先を決める段階では、以下のリストに沿ってチェックしましょう。
- 求人情報の良い面だけをみていないか
- 実際に働いた経験のある人の口コミを確認したか
- 勤務条件が希望と一致しているか
- 自分に必要な最低年収をクリアしているか
- 会社の将来性は確認したか
これらの項目を確認すると、自分に合った会社かどうかを冷静に判断しやすくなります。
確認すべき面接段階のチェックリスト
面接では、以下のチェックリストを活用して転職先を見極めましょう。
- 面接官が会社について誠実に説明しているか
- 業務内容は求人内容を相違ないか
- オフィスや社員の様子はどうか
- 面接の雰囲気が自分に合いそうか
- 不安点や引っかかった点が残っていないか
- 人事評価の方法など求人情報に記載されていない点はどうか
面接は緊張するため、質問の返答に精一杯になりがちです。あらかじめチェックリストを準備し、聞きたい内容を確認しておくと、見落としを防ぎ、入社後の後悔も回避しやすくなります。
転職でよくある後悔への対処法
冷静に転職先を決めても、やはり入社してから「こんなはずじゃなかった」と思う可能性はあります。ここでは、転職で後悔した場合の対処法を紹介します。
状況を整理する
転職で後悔したら、まずは状況を整理して冷静になりましょう。
- 後悔の原因は何か
- 入社前に想定していた状況とどう違うのか
- 慣れや努力で解決する問題か
自分のなかにあるモヤモヤした気持ちを言語化すると、一時的なストレスなのか根本的な問題なのかを判断しやすくなります。
時間が解決するのを待つ
後悔後にすぐ辞めようとせず、時間が解決するのを待つのも有効な対応です。
新しい職場では、環境・人間関係・業務内容などに慣れないため、最初は誰でも不安やストレスを抱えるものです。しかし、時間とともに職場や業務に慣れ、人間性やスキルを周囲に理解してもらえると、不安が解消される可能性があります。
また、転職直後は雑用や研修が多いため、自分のスキルを発揮できず「こんなはずではなかった」と思いがちです。本格的な実務を任されるようになると、やりがいや手応えを感じられる可能性もあります。最初の違和感や不安は一時的である可能性を考慮しましょう。
社内の調整で改善できないか模索する
転職後の後悔につながった原因が、社内の制度や調整で改善できないかを検討しましょう。
- 社内カウンセリングの利用
- 業務内容変更の相談
- 部署異動の相談
- 現在の役割や期待されている業務を確認
「転職に失敗した」とすぐに結論づけるのではなく、自分から働きかけて環境を良くしていく意識を持つことで、後悔は減らせるはずです。
再転職や出戻りを考える
問題が改善する見込みがない、あるいは時間の経過とともに悪化する場合は、再転職も視野に入れましょう。転職先は新たに探す方法のほか、以前の職場に戻る選択肢もあります。
会社によっては「アルムナイ採用」や「カムバック採用」などで出戻りを歓迎しているため、再雇用の制度を確認してみましょう。
転職で後悔した際によくある質問
転職後に後悔した人から寄せられる、代表的な質問を紹介します。
転職して後悔する人は何割くらいですか?
転職で後悔する人は全体のおよそ1〜2割と考えられます。厚生労働省の転職者への満足度調査と転職希望調査をみていきましょう。
- 満足:53.4%
- どちらでもない:34.5%
- 不満足:11.4%
参考:令和2年転職者実態調査の概況(個3.転職について)|厚生労働省
- 今の職場で今後も働きたい:52.7%
- 分からない:24.9%
- 機会があれば転職したい:21.0%
参考:令和2年転職者実態調査の概況(個4.今後の希望等について)|厚生労働省
調査によれば、およそ1割の転職者が不満足と回答し、2割が再転職を希望しています。これらの情報をまとめると、1〜2割が転職に後悔しているといえるでしょう。
転職後、一番つらい時期はいつですか?
転職後にもっともつらく感じやすいのは、入社から1〜3カ月の間とされています。
新しい人間関係や、仕事の全体像が見えないといった環境は多くの人が疲れを感じます。また、通勤手段の変化や勤務時間の変化によって、生活時間も調整しなくてはいけません。
職場に慣れるまで、仕事上でも生活上でもストレスが溜まるため、入社後の数カ月はつらいと感じる人が多くみられます。
転職を後悔する人の特徴は?
転職を後悔しやすい人の特徴は以下のとおりです。
- 他人の言動や感情に左右されやすい
- 理想が高く、現実とのギャップを受け入れにくい
- 今の職場から逃げたい気持ちが強い
- 自己理解が不十分である
- 情報収集が不足している
これらの特徴がある人は、自分のスキルや本当に求めている条件に合った会社を選べません。また、転職そのものが目的になっている場合は、冷静な判断ができず転職に失敗する可能性があります。
転職をやめたほうがいい人の特徴は?
転職をやめたほうがいい人の特徴は以下のとおりです。
- 職歴が極端に短い人
- 金銭面や健康面など生活が不安定な人
- 昇進や昇給の見込みがある人
- 職場への不満のみでその他の待遇に満足している人
金銭面や健康面で生活が不安定な人は、収入減や環境への適応がうまくいかない可能性があるため、転職には慎重さが求められます。
元の会社へ出戻りしてもいいですか?
元の会社への出戻りは、再転職の選択肢の一つです。
出戻りで復職した人は、会社の即戦力となるケースが多く、出戻り再転職を制度化している会社もあります。
元の職場で成果をあげ、周囲にも信頼がある人は出戻り再転職が向いている可能性があります。一方で、トラブルによって退職するなど円満に辞められなかった場合では、出戻りは難しいでしょう。
まとめ:転職は目的ではなく手段
厚生労働省の統計によると、一般労働者に対する転職者の割合は7.2%と、およそ14人に一人が転職者です。しかし同統計によれば、転職者の半数が満足しておらず、2割が再転職を希望するなど転職後に後悔する人は少なくありません。
転職後に違和感を覚えた場合は、すぐに結論を出さず、時間の経過や社内の調整で解決できるのかを見極めましょう。無理しすぎず再転職や出戻りを考えるのも一つの手段です。その場合は失敗した原因を分析し次につなげましょう。
転職は、求める働き方やキャリアを実現するための手段でそれ自体がゴールではありません。入社後に後悔しないためにも、自分なりの転職の目的や軸を明確に持っておきましょう。
「言った、言わない」の後悔を防ぐ最後の砦、雇用契約書
転職活動で後悔しないために、企業研究や自己分析は非常に重要です。しかし、最終的な意思決定を下す前にもう一つ、必ず確認すべきものがあります。それが「雇用契約書(または労働条件通知書)」です。
「面接では残業は少ないと聞いていたのに…」
「提示された年収に、みなし残業代が含まれているとは知らなかった…」
このような後悔は、雇用契約書の内容をしっかり確認することで防ぐことができます。給与、業務内容、勤務時間、休日といった大切な労働条件は、すべてここに明記されています。口頭での説明だけでなく、書面で最終確認することが、入社後の「言った、言わない」というトラブルを防ぐ最後の砦なのです。
電子契約は、PCやスマートフォン上で契約内容をじっくり確認でき、そのままオンラインで締結が完了します。データとして契約書が手元に残るため、「いつ、どのような条件で合意したのか」が明確になり、後からでも簡単に見返すことができます。紙の書類のように紛失する心配もありません。
契約プロセスを電子化し、透明性を確保している企業は、コンプライアンス意識が高く、従業員との約束を大切にする信頼できる企業である、と考えることもできるでしょう。