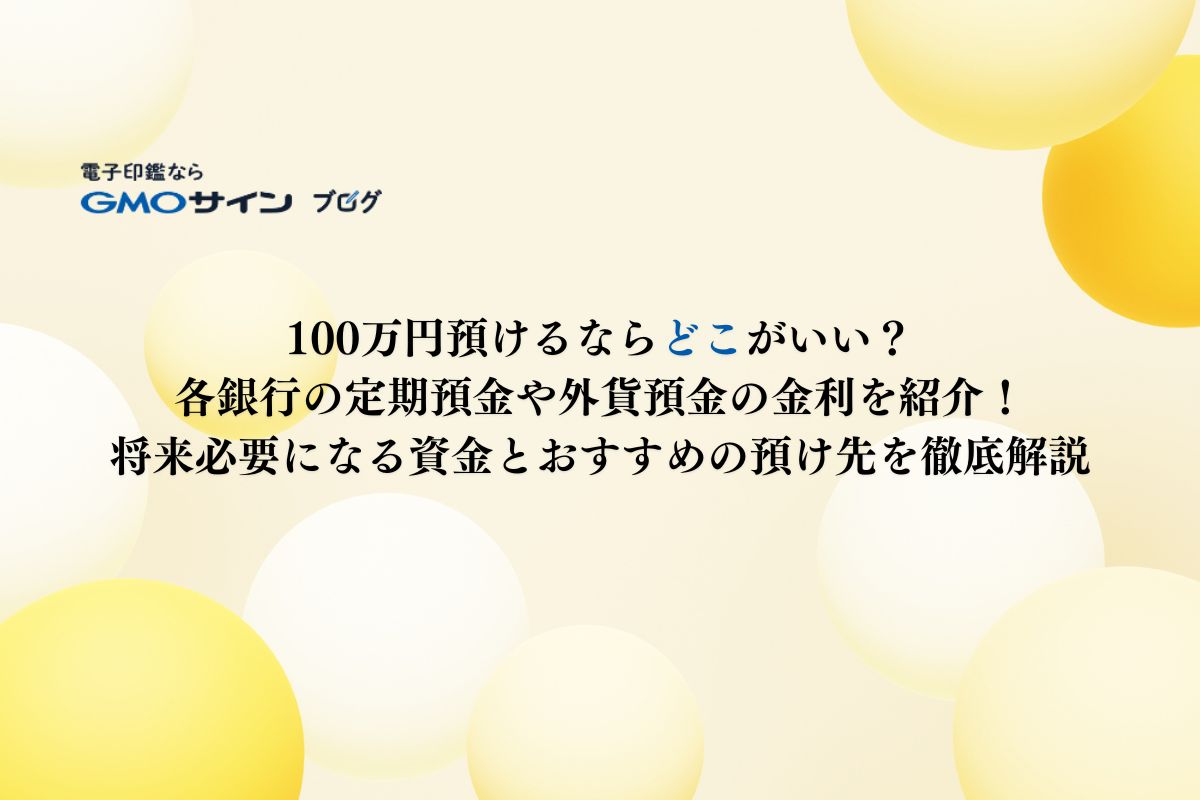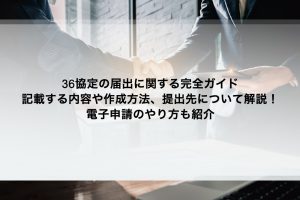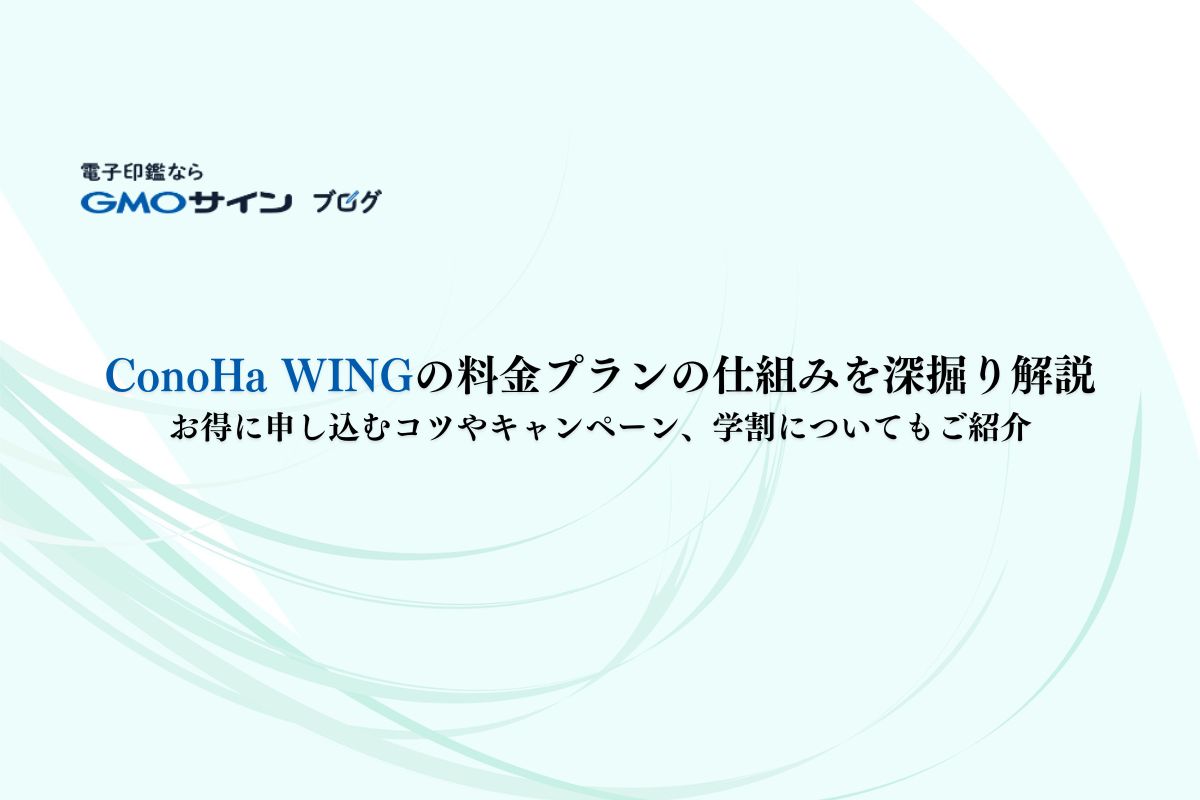不動産投資をする際には、物件選びが非常に重要です。優良物件を適正価格で購入することができれば、その後の運用は上手くいきやすいと言えるでしょう。逆に、収益性の低い物件を購入してしまうと、入居者募集や管理に注力してもなかなか上手くいきません。
そこで、不動産投資においては収益還元法という方法で、不動産の価値を判断することが多くあります。収益還元法を用いれば、優良物件なのか割高な物件なのかをおおよそ判断できるため、不動産投資をするなら、ぜひ理解しておきたい評価方法です。そして、収益還元法を上手く活用するには、計算方法はもちろんのこと、基本的な考え方についても理解しておくのがいいでしょう。
本記事では収益還元法について、基本的な考え方や計算方法をわかりやすく解説していきます。
収益還元法とは
収益還元法というのは、不動産がこれから将来にわたって生み出すと想定される利益を元にして価値を計算する方法です。では、どのような考え方を基本としているのか、利用されるシーンを併せて見ていきましょう。
収益還元法の基本となる不動産価値の考え方
不動産の価格は立地や面積、建物の構造、築年数など、さまざまな要因によって決定されます。そのため、同じ不動産でも着目する部分によって高く評価されることもあれば、低く評価されてしまうこともあるのです。
収益還元法では、不動産の稼ぐ収益に着目して価値を測るのが基本的な考え方です。収益還元法によって算出された不動産価格は、周辺の不動産と比べて高くなることもあれば安くなることもあります。
また、土地と建物は別の不動産として扱われていますが、収益還元法においては土地と建物を分けないで考えるのが特徴です。土地の上にある建物に関しては土地と一体のものとして捉え、価値を測る際にも土地と建物の合計で考えます。建物が家賃などの収益を生み出している場合には、土地もセットで活用されているためです。
収益還元法が利用されるシーン
収益還元法は、収益を得る目的で所有する不動産の価値を測る際に用いられます。賃貸住宅などは家賃収入を得られるため、収益還元法で価値を測られる不動産の代表的な例です。賃貸オフィスの価値を測る際にも収益還元法が用いられます。
また、不動産が生み出す収益というのは、家賃や賃料だけではありません。ホテルや店舗などの売上も、不動産が生み出す収益として捉えることができます。そのため、収益還元法でホテルや店舗の価値を測ることも多くあります。
還元利回りとは
収益還元法について理解するには、還元利回りという概念を理解しておかなければなりません。還元利回りというのは、不動産に対して投資をした際に得られる利回りのことです。投資額を基準にして1年間に得られる利益の割合を示しています。
例えば1,000万円の投資をして1年間に50万円の利益が得られると仮定すれば、還元利回りは5%です。
収益還元法には2種類の計算方法がある
収益還元法で不動産の価値を計算する際には、直接還元法とDCF(ディスカウントキャッシュフロー)法の2種類の方法があります。では、それぞれの計算方法について見ていきましょう。
直接還元法
直接還元法で不動産の価値を測る際には次の計算式に当てはめて算出します。
純利益というのは収益から経費を差し引いた金額のことです。賃貸物件であれば、家賃が収益に該当し、税金や管理費、広告費などが経費に該当します。
例えば、家賃が10万円の賃貸物件であれば、1年間の家賃の合計金額は120万円です。経費が20万円で還元利回りが5%と仮定すると、直接還元法による不動産の価値は次のように計算されます。
上記の条件に該当する不動産を収益目的で購入する場合には、2,000万円よりも安ければ割割安、高ければ割高ということになります。
直接還元法は計算式が簡単ですが、家賃の下落や空室リスクなどは考慮されていません。
DCF(ディスカウントキャッシュフロー)法
DCF法は家賃の下落や空室リスクなども考慮した上で、不動産の価値を測る方法です。次の計算式に当てはめて算出されます。
現在価値というのは金利を考慮した上で、将来得られる利益を現在の価値に換算したものです。例えば、インフレ率が3%なら(1+0.03)をかけて、1年後の103万円は現在の100万円と同じ価値になるものとして計算します。そのため、1年後の利益に関しては(1+0.03)で割ることで現在の価値に換算可能です。
2年後の利益は、現在の価値に換算するには(1+0.03)で2回割る必要があります。つまり、2乗で割るということです。3年目以降の分に関しても同様にして研計算します。現在価値に変換するためのこの3%という数値は割引率といって、金利やインフレ、不動産の利回りなどの状況によって変わるものです。
直接還元法の例と同様に家賃が10万円で年間の経費が20万円の場合、で割引率を3%、5年後に1,500万円で売却すると仮定しましょう。DCF法に当てはめると次のように不動産価値を算出できます。
- 1年目の純利益の現在価値
-
(120万円-20万円)÷(1+0.03)=970,873円
- 2年目の純利益の現在価値
-
(120万円-20万円)÷(1+0.03)^2=942,595円
- 3年目の純利益の現在価値
-
(120万円-20万円)÷(1+0.03)^3=915,141円
- 4年目の純利益の現在価値
-
(120万円-20万円)÷(1+0.03)^4=888,487円
- 5年目の純利益の現在価値
-
(120万円-20万円)÷(1+0.03)^5=862,608円
- 5年後の売却価格の現在価値
-
1,500万円÷(1+0.03)^5=12,939,131円
- 合計
-
970,873円+942,595円+915,141円+888,487円+862,608円+12,939,131円=17,518,835円
※^2や^3は2乗、3乗を表すものです。
※小数点以下の端数は切り捨てています。
DCF法での計算は直接還元法と比べるとやや複雑です。
収益還元法以外の不動産価格の評価方法
不動産の価値を評価する方法として、収益還元法以外にはどのような方法があるのか見ていきましょう。
積算法
積算法は不動産の基礎価格を元にして価値を評価する方法です。次の計算式に当てはめて算出されます。
基礎価格×期待利回り+必要諸経費
積算法においては、不動産の基礎価格が大きく影響し、収益力はあまり重視されていません。また、土地と建物を別々に扱う点でも、収益還元法とは異なります。
ただし、金融機関で融資の審査を行う際には、積算法を用いて物件の評価をすることが多いようです。
取引事例比較法
取引事例比較法は、対象の不動産と条件が似通っている不動産の取引事例と照らし合わせて評価する方法です。類似物件と同じくらいの評価額になるように評価を行います。主に中古物件の評価を行う際に用いられることが多い手法です。
また、取引事例比較法は、収益還元法や積算法のように計算式に当てはめて価値を算出するものではありません。そのため、評価を行う人の感覚が影響してしまう可能性もあります。
収益還元法を用いて不動産の価値を評価するメリット
不動産の価値を評価する際に収益還元法を用いるメリットについて見ていきましょう。
収益力を重視した不動産価値を測れる
収益還元法を用いた評価額は、不動産の収益力を重視して評価しています。これから不動産を購入して継続的に収益を得ていきたいと考えている人にとって、優良物件かどうかを判断する上で非常に有用です。
価格設定が妥当化どうか判断する上で役立てられる
売りに出されている不動産は、価格設定が高すぎると感じるものもあれば割安と感じるものもあるでしょう。しかし、収益性を考慮すると、高すぎるように感じられても、妥当な価格だということもよくあります。逆に割安に感じられる物件は、収益性が低いために安い価格で売られていることも多く見られます。
ですから、収益目的で不動産を購入する際に、収益還元法で不動産の価値を測ってみることが重要です。それにより、本当に高いのかそれとも割安なのかが分かります。価格交渉をする際にも、収益還元法で計算した金額を根拠に交渉するのが効果的です。
ローンの審査の際に収益性の高さを加味してもらえる
不動産は非常に高額なため、大半の人にとってキャッシュで購入するのは難しいものです。また、収益目的で購入するのであれば、居住用ではないため住宅ローンは利用できず、不動産投資向けの専用のローンを利用するのが一般的です。
不動産投資向けのローンでは、購入する不動産を担保にします。そのため、借入をする人の年収額や勤続年数など本人の属性の他に、購入する不動産が審査結果に影響します。そのため、収益性の高い物件なら、審査で有利に扱われる可能性が高く、収益還元法で価値を算定して資料として提出すれば、相応に評価してもらえます。
収益還元法における不動産の評価を高める方法
収益還元法で不動産を評価した場合の評価額を高めるためには、どのようなことを行えばいいのか見ていきましょう。
空室率を下げる
直接還元法を用いる場合もDCF法を用いる場合も、純利益が計算式の中に含まれています。純利益が高ければ、収益還元法で計算した場合の評価額も高くなる仕組みです。
そして、純利益を高くするには空室率を下げる必要があります。賃貸物件であれば空室から家賃収入は入ってきません。一方で経費は空室にかかる部分も発生するため、空室率を下げることが純利益を上げることにつながり、収益還元法での評価額を高めることにもつながります。
家賃をやや高めの設定にする
家賃が安めの設定になっていると、空室率が低くても純利益はあまり高くならないため、家賃は高めの設定にするのが望ましいでしょう。ただし、あまり家賃を高くしてしまうと、入居者がなかなか集まりません。空室率が上がってしまうことで、かえって純利益が下がってしまう可能性もあります。
そのため、周辺エリアの類似物件の家賃相場を確認し、やや高めくらいの家賃設定にしておくのがいいでしょう。
建物の外壁を綺麗に保つ
賃貸物件を探している人の中には、建物の外観を重視して選ぶ人も少なくありません。内装も大事ですが、外観が綺麗なら内見の申し込みも増えます。また、綺麗な外観の物件なら、多少家賃が高くても納得してくれる人も多くいます。
つまり、建物の外壁を綺麗に保てば、空室率が下がり家賃も上げやすくなるため、純利益が増えます。
また、DCF法で評価する場合においては、売却時の価値も重要です。外壁のメンテナンスをこまめに行っていれば、綺麗な状態で売却することができます。そのため、売却時の価格が高くなり、DCF法で計算した場合の評価額が高くなりやすいと言えます。
まとめ:不動産投資をするなら収益還元法で物件の評価額を確認しておこう
収益還元法は、不動産の価値を評価する方法の1つで、収益力を重視しているのが特徴です。また、収益還元法の中でも直接還元法とDCF法の2種類に分かれています。直接還元法の方が計算式が簡単ですが、家賃の下落や空室リスクなどは考慮されていません。より詳細に収益力を測りたいなら、DCF法を用いて計算するのがいいでしょう。
収益還元法で不動産の価値を評価することで、価格の妥当性も判断可能です。ローンの審査で収益還元法による評価額を資料として提出することで有利に働くこともあります。不動産投資をするなら、物件を購入する前に収益還元法による評価額を算出し確認しておきましょう。