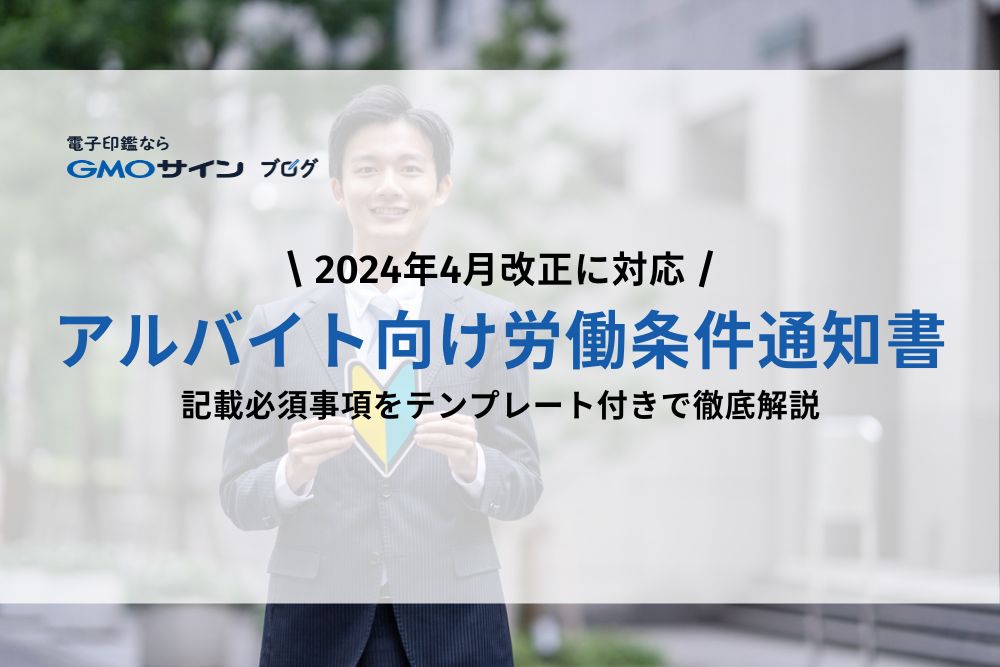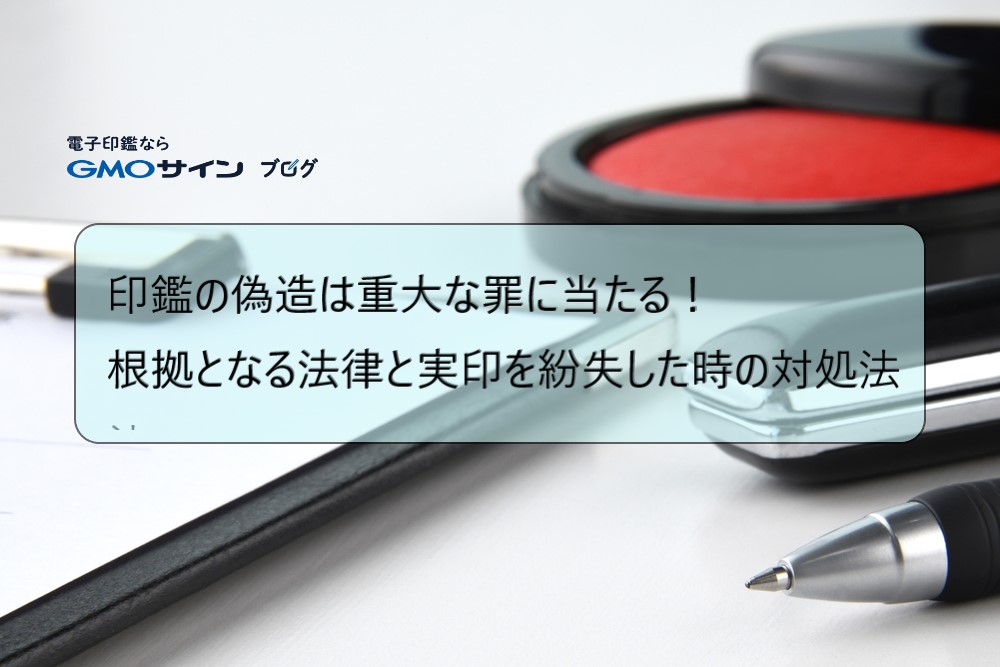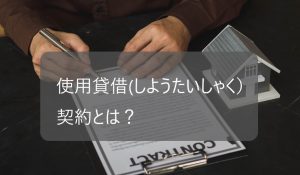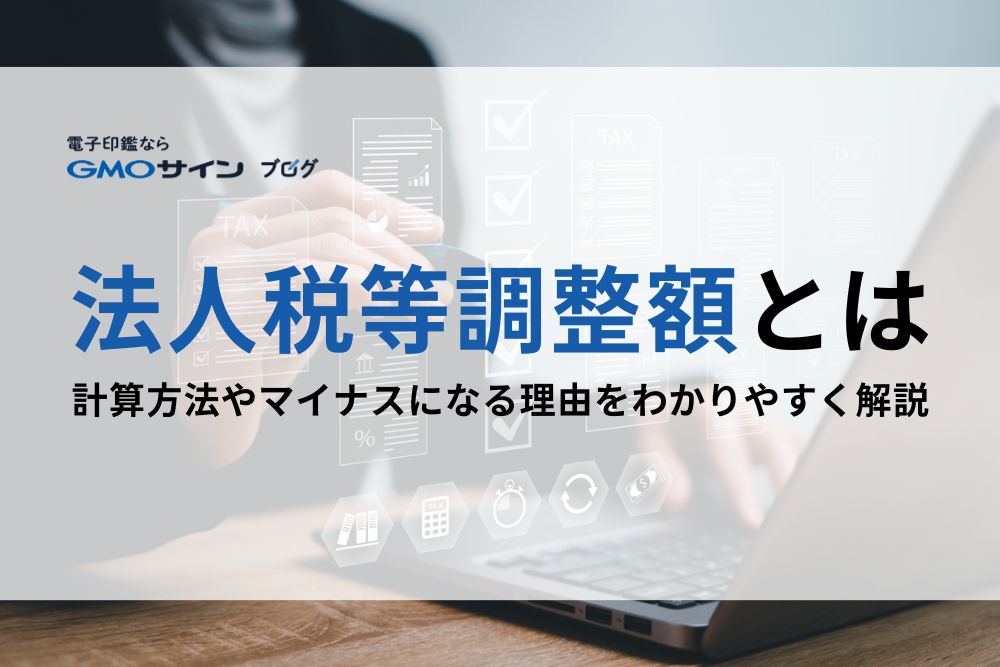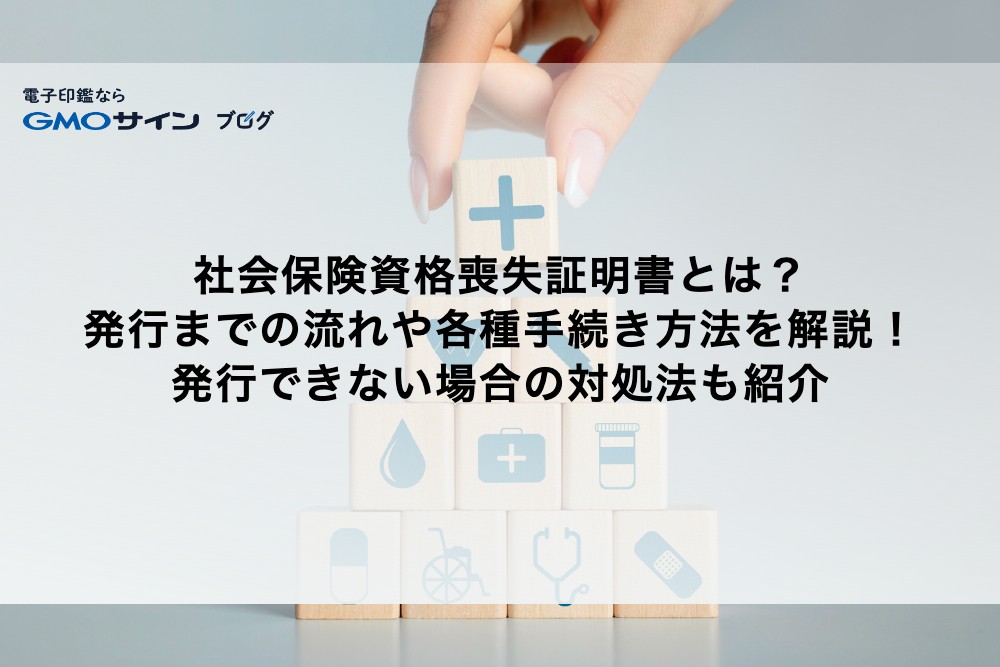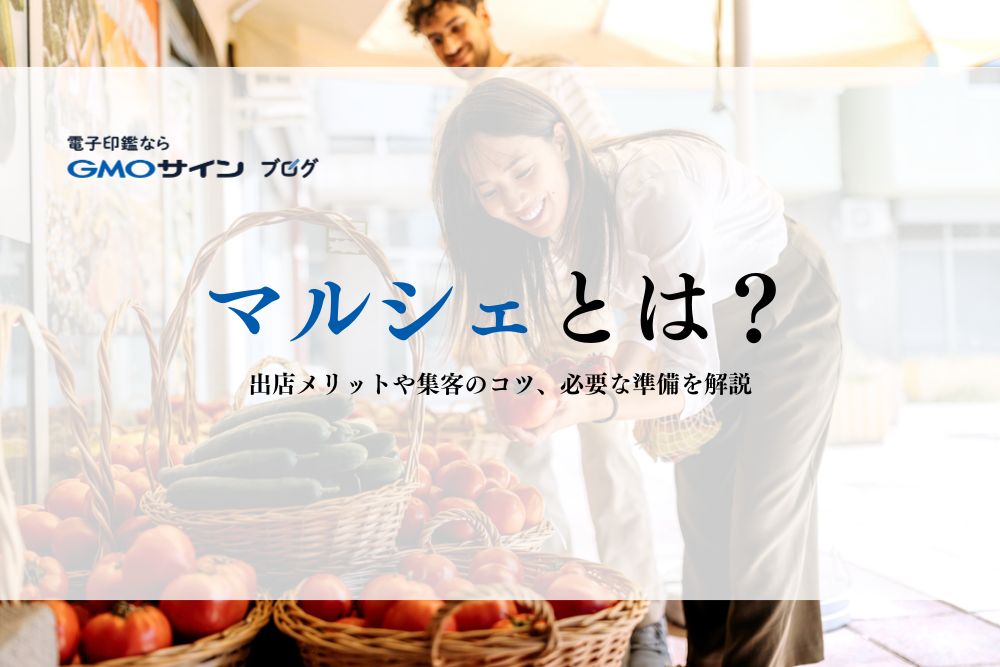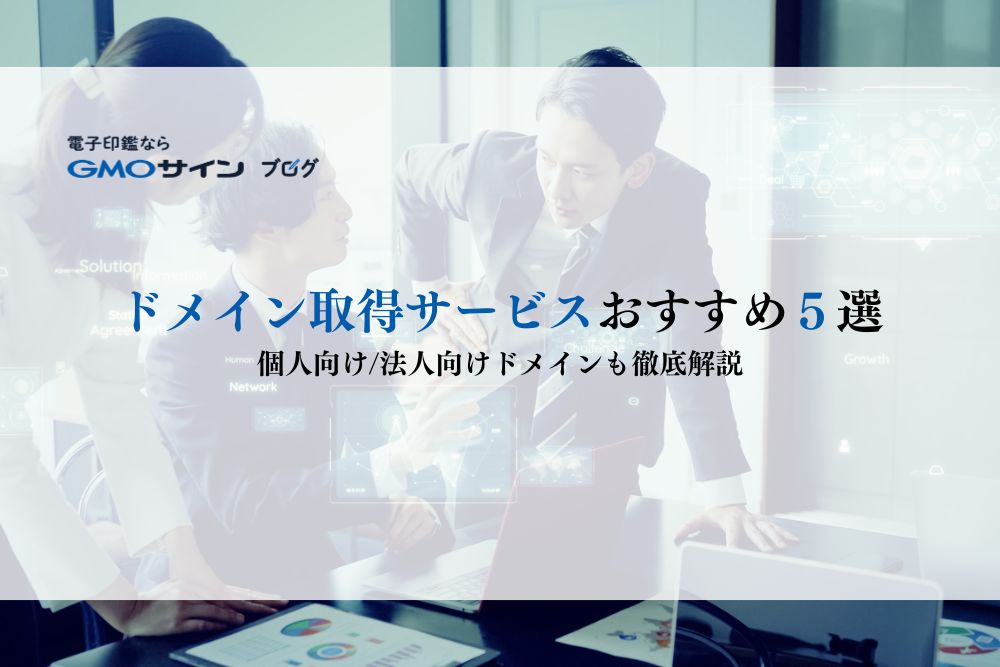\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //


浸透印は一般的なハンコのように朱肉やスタンプ台を用意する必要がなく、とても便利なハンコです。しかし書類によっては「浸透印は使えない」とされているものがあります。なぜ浸透印が使えないのでしょうか。
実は浸透印のメリットとデメリットにその理由が隠されています。ここでは浸透印とはどのようなものなのか解説するとともに、ビジネスで利用する時に注意したいポイントをご紹介します。
浸透印とはハンコの内部にインクが内蔵されたもので、印面にそのインクが浸透し連続して捺印できるものを言います。捺印するのに朱肉やスタンプ台が必要なく、浸透印をもっているだけで完結するため携帯するのにも便利です。
浸透印は印面が乾燥して劣化しないよう、キャップがついているものが一般的で、浸透印内のインクが無くなったときは、インクを補充すれば繰り返し使用できることも特徴です。補充用のインクは利用している浸透印のメーカーや種類によって専用のものが用意されています。

なお、浸透印は大きく分けて2種類が販売されていて、ひとつは凹凸タイプ、もう一方をフラットタイプと言います。凹凸タイプは文字通り印面がゴム印のように盛り上がっていて、耐久性に優れています。
フラットタイプは印面が平らで、凹凸タイプに比べて耐久性は劣ります。一方、凹凸が無い分イラストや写真、ロゴといった画像をきれいに押印できます。特に後者はオリジナルのデザインでハンコを作成できるサービスも多いため、会社名+ロゴといった浸透印も簡単に作成、購入できます。
浸透印のメリットはなんといっても使いやすさにあります。例えば荷物を受け取るときや訂正印を押すような「すぐに使いたい」場面では、朱肉やスタンプ台を用意しなくて済みますし、印鑑についた朱肉を拭き取る手間もありません。また、朱肉よりも浸透印に使われるインクの方が乾きやすく、押印したあと触って汚してしまう、といったことも防げます。さらに、浸透印の印影は内蔵されているインクの発色がよいため、美しい仕上がりとなります。
そんな便利な浸透印ですが、一方でデメリットもあります。浸透印のインクは朱肉に比べると耐久性に劣り、経年劣化で変色するほか、薄くなってしまうことがあります。
また、公的な書類や契約書など、書類によっては「浸透印は使えません」と明記されていて、通常の印鑑での押印が求められることもあります。そのような書類に浸透印が使えない理由のひとつは先述したインクの耐久性です。また、ゴムなどを素材にしているため、使い続けるうちに劣化して変形したり、力加減によって印影が変わったりするため同一性が保てないことも理由として挙げられます。
さらに、大量生産品であるため、誰でも同じものを購入でき、本当に本人が押したものかどうかの証拠になりにくいことも理由のひとつです。これらの理由から、浸透印は銀行印や実印として登録することができません。
現在では浸透印を認印(銀行印や実印として登録していない印鑑)として利用できることをうたうメーカーや商品もあり、インクの耐久性も長くなっています。しかし残念ながらこうした知識が世間一般に浸透しているとは言えず、場面によってはトラブルとなることもあります。
ビジネスで浸透印を使うときはいくつか注意すべきことがあります。まず「印鑑」を押すことを求められている場面です。こうした場合、浸透印では不可であるが多いです。また、先述のように契約書などに利用することはできませんので、こうした場合に備えて浸透印ではない認印などを用意しておくとよいでしょう。
職場で荷物を受け取ったり、社内書類を回覧したりする場合は浸透印でも問題ないことが多いのですが、一方で社外の書類に利用することは避けた方がいいかもしれません。もし利用する場合は、社外の方に前もって確認をしておくことでトラブルを避けられるでしょう。
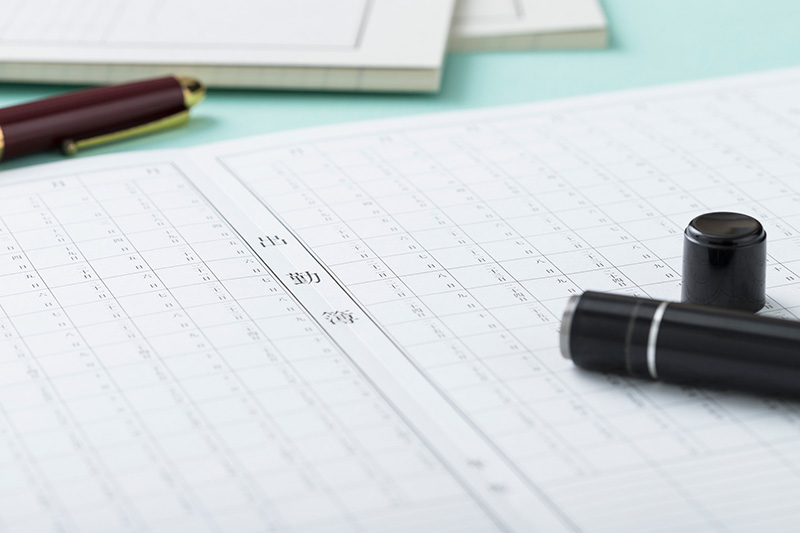
長く保管するような書類も浸透印での押印を避けた方が無難です。繰り返しになりますが、これも浸透印のインクの方が朱肉よりも耐久性が低いと言われているためです。
浸透印は便利かつ手軽に使える反面、実印や銀行印として登録できないことや、公的な書類や契約書などには使えないということをお伝えしました。以前に比べると耐久性の上がっている浸透印のインクですが、朱肉に比べるとまだまだ耐久性は低く、長期保管が必要な書類には不向きです。
認印として利用できることをうたうメーカーや製品もありますが、提出相手が「使えない」と思っている場合には、浸透印を使う必要はないでしょう。便利な浸透印ですが、ビジネスで使用するのであればトラブルを避けるために、浸透印ではない認印も用意しておき、用途に合わせて使い分けることが重要です。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。