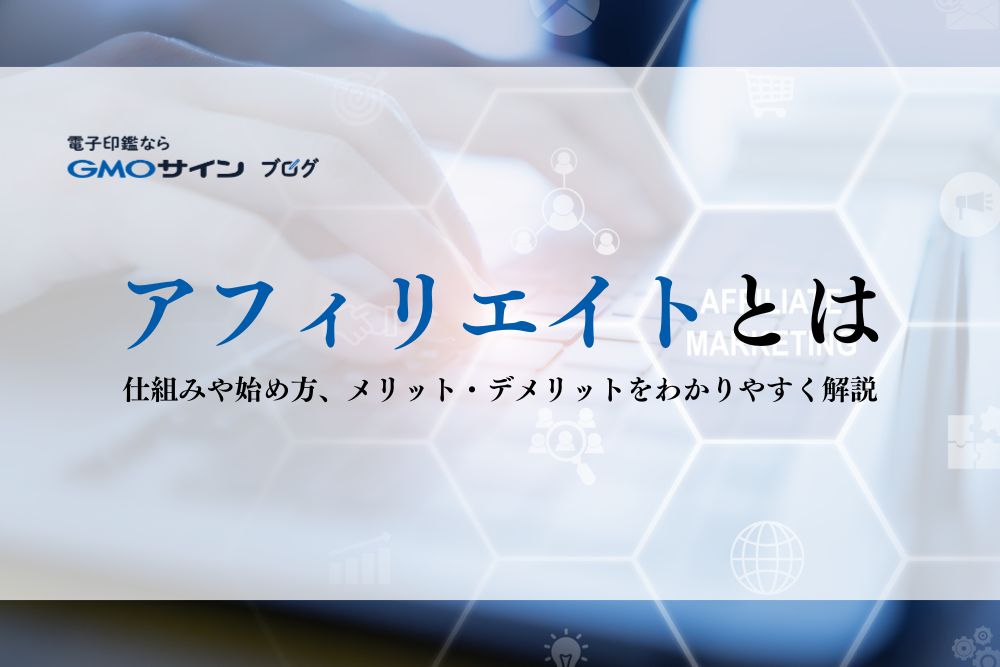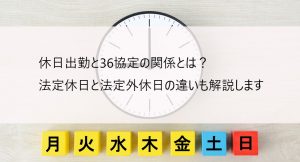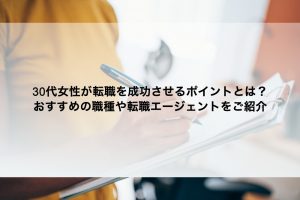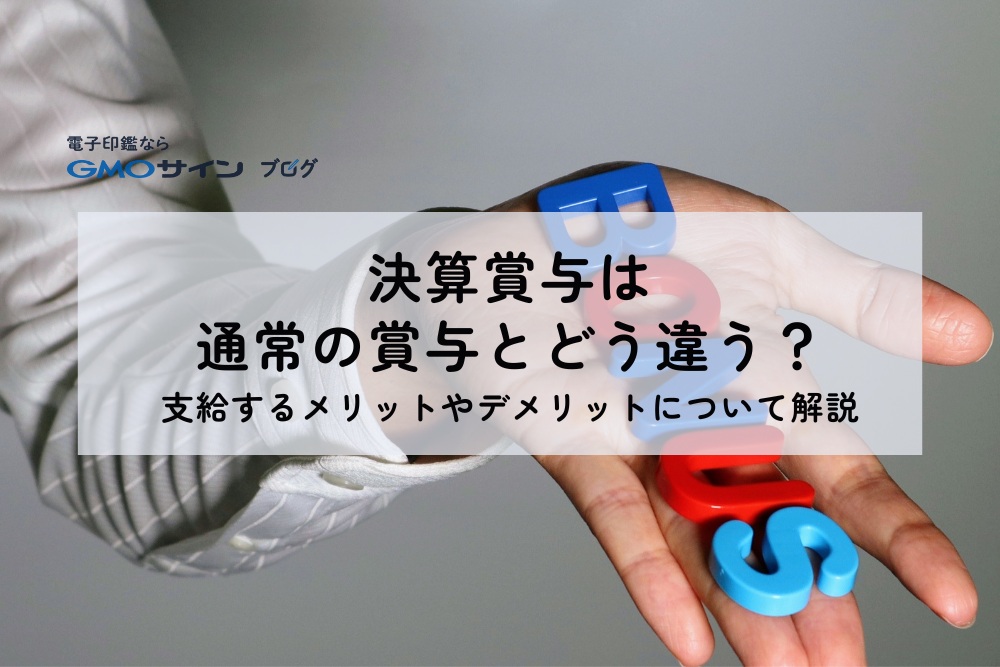よくニュースで耳にする横領はどういった犯罪なのでしょうか。漠然とイメージできるが、着服や窃盗との違いが分からないという人も少なくありません。
もし、自分の会社で横領が起きたらどうすべきなのか悩んでしまいます。また、魔が差して自分が横領をしてしまったらどうやって解決するのがベストなのでしょうか。
そこで、本記事では、横領の概要や対策などについて詳しく解説します。
横領とは何か?
横領とは、他人に頼まれて管理しているものを勝手に使用することです。
第三十八章 横領の罪
(参考:刑法|e-Gov法令検索)
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
かんたんな例をあげると、以下はすべて横領となります。
- 知人から借りていたDVDをリサイクルショップに売る
- 経理担当者が私的に経費を流用する
- 雇われ店長が店の売り上げを使ってしまう
また、横領には3つの種類がありますので、次の章で解説します。
横領の種類
横領の種類は以下の3つです。
- 横領罪(単純横領)
- 業務上横領罪
- 遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)
それぞれ罰則が異なります。横領罪は、単純横領罪とも呼ばれます。友人に借りているものを売るという行為などは単純横領罪の代表例です。業務上横領罪は、店長が店の売り上げを着服するなどの行為がこれに当たります。
遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。たとえば、落ちていた財布を拾って自分のものにしたといったケースにおける財布は、持ち主の手を離れた遺失物であり、占有を離脱したものです。しかし、持ち去る行為は横領に当たります。
占有と所有の違いは?
横領について理解するうえで、占有と所有の意味を把握しておくことは大切です。所有は、その人の持ち物であり、物理的に支配している物という意味です。占有は、その人が物理的に持っている物を指します。横領は占有の侵害がありません。
所有
特定の物について所有権を有すること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
(参考:図解六法)
占有
1.民法上は、自己のためにする意思で物を所持すること(一八〇)。「所持」とは、社会通念に照らして物を事実上支配すると認められる状態をいい、他人を通じて物を所持することも可能である。また、「自己のためにする意思」についても判例・学説は極めて緩やかに解している。
2.刑法上は、支配の意思で事実上物を支配すること(二四二、二五二等)。自己のためにする意思を要せず、他人のために財物を所持する場合も含むが、代理占有や占有の相続は認められない。また、常に物理的な握持を要するものでなく、財物を監視しなければならないものでもない。なお、各犯罪の罪質によって占有概念の内容に若干の差異はある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
(参考:図解六法)
金銭については、占有している人が所有していると判断されます。しかし、使途が明確な金銭は預けた人に所有権があるとみなされ、預けられた金銭を自分のものにすればそれは横領罪となります。
横領と着服や窃盗の違いは?
横領と着服そして窃盗は、かんたんにいえば自分の物ではない金銭や物品を手に入れることです。それぞれの言葉に違いはないように感じている人が多いでしょう。
しかし、横領とは、上記で説明したように刑法上の言葉です。自分の物ではないのに自分の物のように使ってしまう行為を指します。ここでは、着服・窃盗との違いについて解説します。
着服
着服は横領と同じ意味で、自分の物ではないにもかかわらず、不正な手段で自分の物にすることです。
横領との違いは法律用語であるかどうかです。着服は法律用語でなく、一般に使われる言葉です。「金品を着服した」「会社のお金を着服した」のように使います。
窃盗
窃盗とは、他人の物(占有物)を盗むことで、犯罪行為です。たとえば、家の中に入って盗む侵入盗や、職場のロッカーから人の物を盗んだり、机の上に置いてあった財布からお金を盗んだりする職場盗などがあります。店から商品を盗む万引きも窃盗の一種です。
たとえば、友人から預かっていた本を売ったという場合、その本を売った犯人が友人の本を占有していたことになります。自分が占有していた友人の本を売ったということで横領罪が成立します。
道で拾ったアクセサリーを自分のものにしたという場合は、そのアクセサリーは落とし物なので、すでに人の占有を離れています。そのため、横領罪に当たります。しかし、書店の棚にある本を持って帰ったという場合は、被害者(書店)が占有していた本を盗んだので窃盗に当たる行為です。
業務上横領をするとどうなるのか?
被害者が被疑者に対して横領を指摘し、相手が認めるのであれば、その段階で話し合いによる解決も可能です。しかし、被疑者に何も確認しなかった、あるいは話し合いで解決できなかった場合は、警察が介入します。
被害者が警察に被害を申告すると、警察から事実関係を聞かれるなどの責任追及がなされます。警察官が必要であると判断すれば、被疑者は逮捕されるでしょう。
もし、逮捕する必要がないと考えられる場合には、在宅の状態のままで呼び出しをし、取り調べが行われます。業務上横領が発生し、なおかつ紛争が解決していないのであれば、基本的に事件は起訴されます。
ただし例外があり、横領したのが配偶者、同居の親族もしくは親子や祖父母、孫など直系血族の場合、横領罪とはなっても刑法第244条に基づき刑が免除される場合があります。
(親族間の犯罪に関する特例)
(参考:刑法|e-Gov法令検索)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
たとえば、息子が父親の通帳からお金を着服したというケースは、横領罪が成立したとしても、刑法で裁くことはできない場合があるということです。
中小企業ができる横領予防対策
会社内で横領事件が起きると、金銭的被害により会社経営に重大な支障が出るだけでなく、会社の信用に傷がつきます。また、従業員同士にも不信感が生まれてしまうでしょう。
横領が発覚すれば多くの場合は解雇となり、その人が生み出す利益がなくなります。これは会社にとって大きなダメージです。また、金銭の問題だけでなく、会社の信頼を損なわないためにも、横領事件に対する予防策を講じなければなりません。
1人の担当者にお金を任せきりにしない
中小企業などで起きる横領事件の事例を見ると、長年にわたって1人の経理担当者に会社のお金のことをすべて任せきりにしていたというケースが多いです。以下のようなケースに当てはまる会社は要注意です。
- 会社のお金の流れは、社長よりも経理担当者が詳しい
- 会社のお金について経理担当者以外、誰も詳しく知らない
横領予防対策で大切なのは、1人の担当者にお金を任せきりにしないことです。経理担当者を複数おくことが予防策として有効となります。権限を1人に集中させず、チームとして活躍できる会社を作ることを意識しましょう。
横領に限らず、何事にもこの人にしかできないという文化が会社内にあるならば、横領事件が起きやすい土壌を作ることになります。中小企業には多い文化なため、注意が必要です。業務分担は横領を防ぐだけでなく、後進の育成にもつながり、会社にとっても大きなメリットとなります。
外部の専門家にも相談してチェック体制を整える
中小企業においては、人員確保が難しい場合もあるでしょう。複数の経理を置けない場合は、内部監査を定期的に行うことが必要です。日常の経理担当者以外が、通帳の履歴・支出を定期的にチェックするとよいでしょう。経理の仕事を見える化し、さらにチェック機能を整えることも大切です。
従業員が横領していたらどう対応するべきか?
従業員による業務上横領を発見した場合、すぐに従業員に対して問いただすのは良策ではありません。本人から事情聴取する前に、弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談する際には、事情聴取するに当たり、以下のポイントに気を付けましょう。
- 十分な証拠が確保されているか
- 他にも確保すべき証拠があるか
- 横領を認めさせるための事情聴取の方法
弁護士への相談と並行して事前調査を行います。横領が発覚した場合、初動段階で重要なのは、事前の証拠確保と本人に横領を認めさせることの2点です。
証拠がなく、会社が横領の事実を正しく把握できていなければ、事情聴取の際に認めさせることはできません。被疑者に横領の事実を認めさせ、横領の全貌を話させるためには、事前に会社がしっかり調査を行う必要があります。
証拠が確保でき、弁護士にも相談したのであれば本人への事情聴取を行い、返済請求をします。返済に応じないのであれば、刑事告訴そして懲戒解雇という流れで進めていきます。
また、返済請求をする前に、刑事告訴や解雇を行ってしまうと、被疑者と連絡が取れなくなり、返済請求に支障が生じます。そのため、順番通りに正しく対応する必要があるのです。
業務上横領をしたらどうすべきか?
当然のことですが、横領しないことがベストです。しかし万が一、業務上横領罪を犯してしまったら、警察沙汰になる前に示談を行いましょう。被害者に謝罪をし、被害を弁償するのが最も良い解決方法です。自ら横領を打ち明けることで、謝罪を受け入れてもらえる可能性が高まります。
もし「お金がなくて被害弁償できない」「被害者に謝罪を受け入れてもらえない」などで示談ができないなら、自首することも検討すべきです。また、たとえ警察沙汰になっても、引き続き示談交渉をして被害者に許してもらう努力を怠らないようにすべきです。
業務上横領罪の時効は?
刑事訴訟法250条2項4号により、業務上横領罪を犯した際の時効は7年です。7年を過ぎると時効が成立し、刑事事件として立件される可能性はなくなります。
第二百五十条
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
(参考:刑事訴訟法|e-Gov法令検索)
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
(参考:民法|e-Gov法令検索)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法第724条により、被害者が横領の事実を知ってから3年以内であれば、刑事事件としての時効が成立していても損害賠償請求される恐れがあります。もし、会社内で横領が発覚したならば、時効が成立しないうちに弁護士や警察に相談するなど具体策を取らなければなりません。
偽装請負に関するよくある質問
- 偽装請負はなぜ悪い?
-
偽装請負の問題の核心は、労働者保護の観点にあります。正規の雇用関係であれば、労働基準法や社会保険制度による保護を受けられるはずの労働者が、これらの保護から除外される事態を引き起こすのです。
また、直接雇用義務の回避や人件費削減を目的として行われることが多く、労働者は不安定な立場に置かれがちです。このような理由から、労働者派遣法や職業安定法によって厳しく規制されているのです。
- 偽装請負がバレたらどうなる?
-
偽装請負が発覚した場合、企業には厳しい制裁が待ち受けています。
まず行政処分として、労働局から是正勧告や行政指導を受けることになるでしょう。悪質なケースでは派遣法違反として罰金刑(最大300万円)が科される可能性もあります。
また民事上のリスクとして、偽装請負状態で働いていた労働者から直接雇用の申し込みを強制される「みなし雇用」の適用や、過去の未払い残業代などの請求を受ける可能性があります。
企業イメージの低下や取引先からの信頼喪失など、間接的な損害も看過できません。こうしたリスクを避けるためにも、請負と派遣の区分を正しく理解し、適法な労働者活用を心がけることが重要です。
横領の正しい理解と対策をしよう
横領とは、預かったものや管理を任されたものを、勝手に自分のものとして使ってしまう行為です。友人から借りたDVDを売ったり、会社のお金を私的に使ったりする行為が該当します。
会社での横領を防ぐには、お金の管理を一人に任せきりにせず、複数の人で経理を担当したり、定期的に監査する仕組みを作ることが大切です。