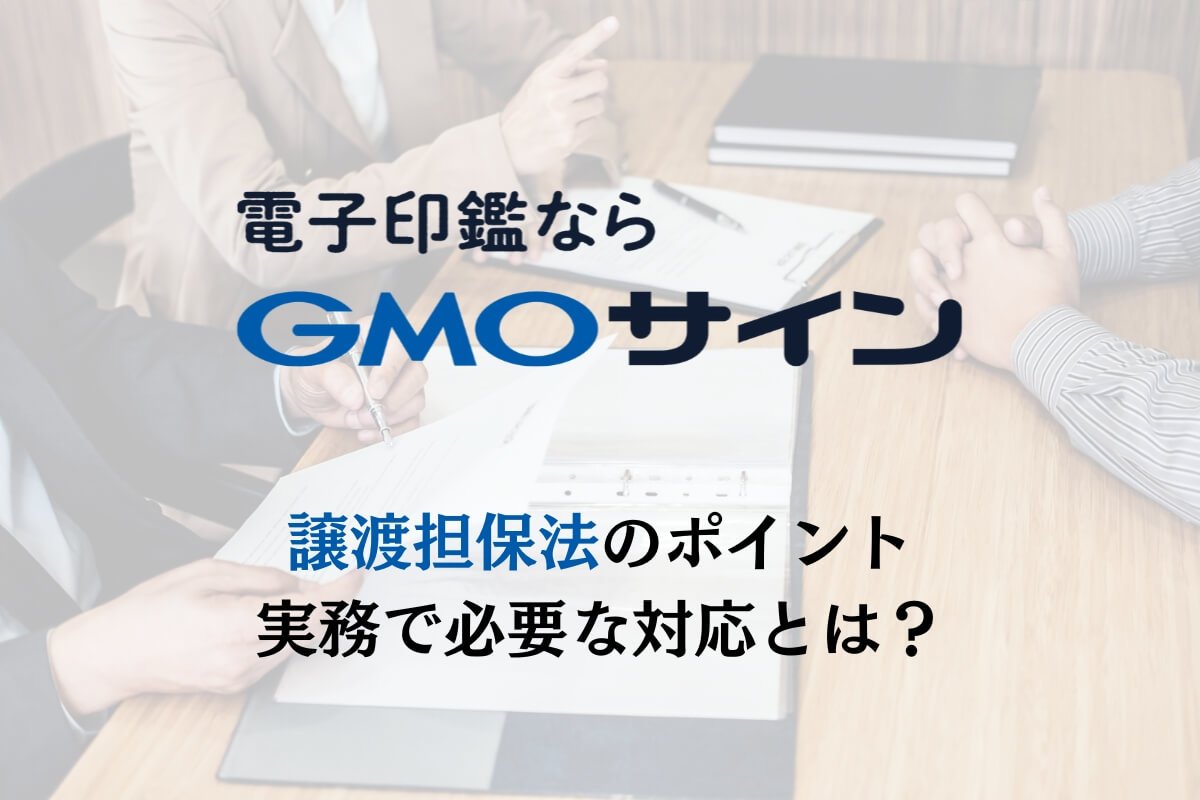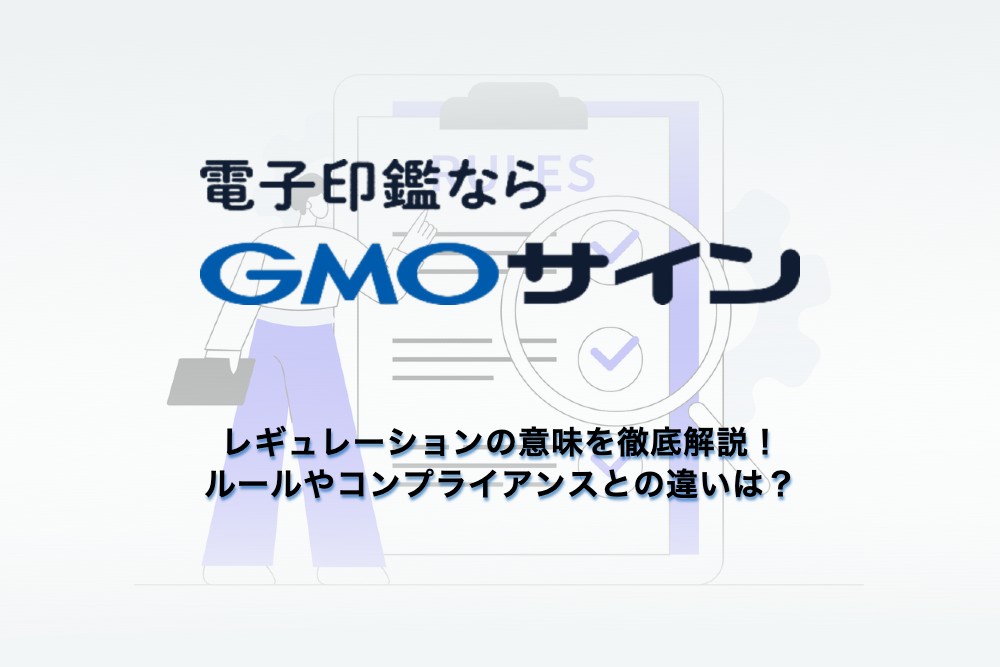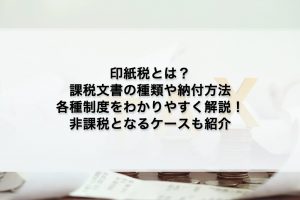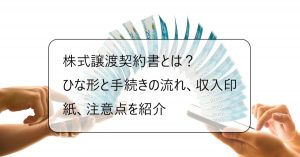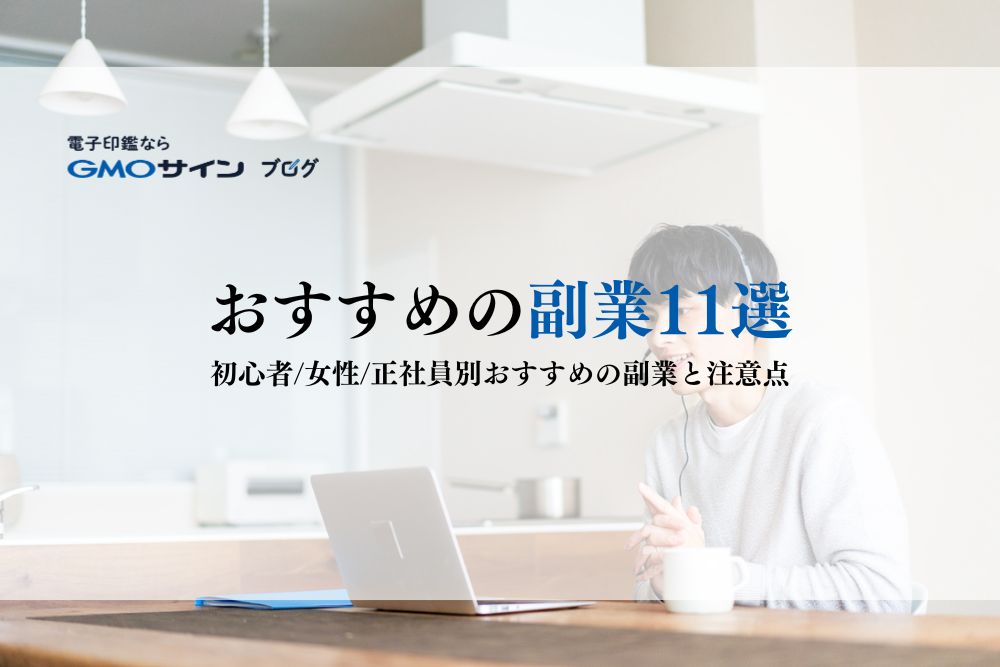譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の要点は?
譲渡担保法が自社の既存契約にどのように影響する?
法改正に向けて具体的に何を準備すべき?
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)の施行は、金融機関や事業会社、リース会社すべてに重大な影響を与える可能性があるため、準備不足は重大なリスクを招く可能性があります。この記事では、譲渡担保法の全体像から実務への具体的な影響までを詳しく解説します。
- 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)の基本知識
- 譲渡担保法で押さえておくべき5つの重要ポイント
- 金融機関・事業会社・リース会社それぞれが受ける具体的影響
- 登記手続きから社内体制整備まで、実務で必要な7つの対応策
譲渡担保契約及び所有権留保契約の法整備に伴い、登記や書面管理の厳格化が求められています。こうした状況では、証拠力の高い契約書の作成・管理が重要です。
また、オンラインで締結・保管ができるので、業務の効率化やリスク軽減といったメリットも受けられるでしょう。
契約書フォーマットの変更や登記手続きの電子化には、電子印鑑GMOサインの活用をおすすめします。安全で迅速な契約管理を行いたい方は、ぜひGMOサインの資料請求や無料のお試しフリープランをご利用ください。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)とは?
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(以下:譲渡担保法)は、2025年6月6日に公布されました。取引先との担保契約整備や社内規定の見直しを検討している企業担当者にとって、本法の理解は実務上不可欠です。この章では以下の内容を解説します。
まずは基本を押さえておきましょう。
譲渡担保法の目的と背景
譲渡担保法の目的は、譲渡担保および所有権留保といった非典型担保の法的地位を明確化し、契約の透明性と安定性を確保することにあります。
従来、これらの担保は民法上に明確な根拠がなく、個別の判例や慣習を頼りに判断されてきました。そのため、契約の有効性や担保権の帰属・効力に関する法的解釈が分かれ、債権者・債務者間のトラブルや倒産時の混乱が生じるケースも多かったのです。
たとえば集合動産や集合債権を担保とした場合、倒産手続開始後に新しく取得した財産に担保権の効力がおよぶか否かについては、実務上見解が分かれていました。担保権者が所有者として扱われるのか、質権者などの担保権者として扱われるのかも明確ではなく、債権者や一般債権者の利益調整も難しい状況でした。
新法では契約の成立要件や担保権の性質、第三者対抗要件や私的実行手続などの重要事項を体系的に整理しています。これによって契約当事者は、明確なルールに基づいて担保設定や執行が行えるようになりました。社内規定や契約フォーマットに反映しやすくなる点で、実務的なメリットが大きいといえるでしょう。
公布日・施行日・経過措置の有無
譲渡担保法は2025年5月30日に可決・成立し、同年6月6日に公布されました。施行日はまだ確定していませんが、附則で「公布の日から起算して2年6カ月以内に政令で定める日」と規定されています。
政令次第では、前倒しされる可能性もあるでしょう。準備期間が読めないため、実務に携わる人は早めに社内規程の見直しを進めておくと安心です。
また経過措置も設けられました。施行前に締結された既存の譲渡担保契約・所有権留保契約にも新法が適用されますが、占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権の順位計算など、一部では既存の権利関係を保護する特例が附則や整備法に盛り込まれています。
詳細な調整事項は政令に委ねられているため、今後示される省令・ガイドラインを継続的に確認し、社内オペレーションに落とし込みましょう。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)の5つのポイントを解説
ここでは、譲渡担保法の要点を5つに分けて解説します。
ポイントを押さえ、社内規定の策定や実務運用に落とし込んでください。
譲渡担保契約の範囲・権限の明確化
これまで譲渡担保契約は法律に明確な規定がなく、担保権者と設定者(担保を提供する側)の権限や、どのような財産に担保権を設定できるかが不明確で、トラブルの原因となっていました。
新法では動産や債権など譲渡可能な財産であれば、広く譲渡担保権の対象とできることが明文化されています。さらに担保権者は、担保物から優先的に弁済を受ける権利や、保険金や売却代金などの金銭にも権利をおよぼす物上代位権を持つことが明確になりました。
一方、設定者は担保物である動産を引き続き使用・収益する権利を持ち、必要に応じてその返還や妨害排除も請求できます。
集合動産譲渡担保・集合債権譲渡担保に関する規定の整備
これまでは、在庫商品や売掛金のように、数量や内容が日々変動する集合動産や集合債権を担保にする際、法律上のルールが明確ではなく、その担保の効力や対象範囲が不明確な場合がありました。
新しい法律では、「この倉庫にある在庫すべて」や「この期間に発生する売掛金すべて」といった形で、まとまりごとに財産を特定して一括で担保にできることが、明文化されています。
設定後、新たにその範囲に含まれる財産にも担保権が及ぶことが明確になったため、在庫や売掛金の増減にも柔軟に対応できるでしょう。
設定者は原則として、集合動産の処分や債権の取立てが可能です。集合全体の価値を維持する義務も負うため、資金調達の多様化や事業の流動性向上につながります。
譲渡担保権とほかの担保権との優劣関係の明文化
同じ財産に譲渡担保権、質権など複数の担保権が設定された場合、これまでどの担保権が優先されるか明確な法律がなく、実務で混乱が生じる原因となっていました。新法では、担保権の優先順位は対抗要件を備えた日付によって決まることが明記されました。
たとえば、動産であれば引渡しや登記、債権であれば通知や承諾が対抗要件となります。占有改定は外部から認識しにくいため、登記など公示性の高い方法で対抗要件を備えた担保権を優先するルールも導入されました。
私的実行手続の規定
これまで譲渡担保権の実行は、裁判所を通さずに行う私的実行が判例上認められてきましたが、具体的な手続きやルールが法律で定められていませんでした。
新法では私的実行として担保権者が担保物を取得し、その価値で債権を清算する帰属清算方式と、担保物を第三者に売却し、その代金で債権を清算処分清算方式の2種類を明記しています。
どちらの場合も、担保権者は実行前に設定者へ通知し、2週間の猶予期間を設けなければなりません。また動産譲渡担保については、裁判所を通じた実行手続(引渡命令や競売など)も新たに設けられ、迅速かつ公正な債権回収が可能となりました。
倒産手続における取扱いの明確化
これまで担保設定者(債務者)が倒産した場合、譲渡担保権がどこまで効力を持つかは判例や実務上の解釈に委ねられており、不透明な部分が多くありました。しかし今回の法律で、倒産手続開始後に新たに取得した動産や債権には原則として譲渡担保権がおよばないことが明確化されます。
譲渡担保権者は、倒産手続において質権者と同様に扱われることが明文化され、裁判所による実行手続の禁止命令や取消命令の制度も新設されました。倒産時の利害調整や事業再生の円滑化、一般債権者の保護が図られています。
また、集合動産・集合債権譲渡担保については、倒産後の新たな財産に担保権がおよばないことや、倒産財団への一定額の組み入れ義務なども定められました。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)が実務に与える影響と注意点
今回の法制定によって、実務にはどのような影響が考えられるのでしょうか。業種ごとに考えられる影響と注意点を解説します。
スムーズな移行のために、業務に与える影響を正確に把握しておきましょう。
金融機関への影響
譲渡担保法の制定により、金融機関における担保実務は大きく変わると予想されます。契約の有効性や担保権の優先順位が法律として明文化されたことで、リスク評価や債権保全の制度的裏付けが強化されました。私的実行手続の明確化により、担保権の執行における法的安定性も向上しています。おもなプラスの影響は以下のとおりです。
- 担保の法的性質が明確化され、契約スキームの信頼性が向上
- 対抗要件や優先順位が法定され、登記・引渡し管理が明確に
- 私的実行手続が整理され、債権回収の迅速化と透明性が向上
- 契約書式の標準化が可能となり、審査・管理コストが削減
- 与信判断の根拠が強化され、リスク分析が精緻化
一方で注意すべきは、制度が整備された分だけ実務面での形式不備が致命的になりうる点です。登記漏れや契約書に記載不備があれば、担保権の優先順位を他の債権者に主張できないおそれがあります。
また私的実行を行うには、法定の方式や要件を正確に満たす必要があり、従来の運用慣行のままではリスクを抱える可能性があるでしょう。契約審査・登記管理・社内教育を一体的に再設計する必要があります。
事業会社(担保提供者)への影響
事業会社にとっては、担保提供に関わる契約実務や社内手続きの見直しが求められる一方で、契約トラブルの未然防止や取引の透明性向上といったメリットがあります。おもなプラスの影響は、以下のとおりです。
- 集合動産・将来債権の担保設定が法的に認められ、資産活用の幅が広がる
- 契約構成要素が明文化され、社内テンプレート化がしやすくなる
- 倒産時の担保効力が明確になり、リスクコントロールが容易になる
- 契約・法務・財務部門の役割分担が明瞭化し、業務効率が向上
- 金融機関との折衝で、共通理解を持ちやすくなる
ただし、形式的な要件を欠いた契約は、法的効力を失うリスクがあります。たとえば、集合物担保を設定する際に種類や所在を曖昧に記載した場合、担保の特定性を欠くとして無効と判断される可能性があります。倒産時には否認権や差止請求の対象となる場合もあるため、契約の締結時点で倒産リスクを織り込んだ条項設計が求められるでしょう。
リース会社への影響
所有権留保契約の法的位置づけが明文化されたことにより、リース会社は契約の執行可能性や財産管理の確実性を高められるようになりました。特に、倒産手続との関係が整理されたことで回収リスクの予測が可能になり、顧客対応も標準化できます。考えられるおもなプラスの影響は、以下のとおりです。
- 所有権留保の法的構造が整理され、契約の安定性が向上
- 契約解除後の引渡しルールが法定され、トラブルが減少
- 倒産時の取扱いが明確になり、回収戦略が立てやすくなる
- 契約テンプレートの整備が進み、法務対応の標準化が可能に
- 財産保全に関する判断の一貫性が保たれ、社内統制が強化
しかし、条文に沿わない契約運用はリスクを増幅させます。契約条項において所有権の帰属や解除条件、回収方法などを明記していなければ、裁判上で無効と判断される可能性があるでしょう。また、実態と乖離した契約内容は否認権の対象とされやすく、回収が困難になるリスクがあります。
実務で必要な7つの対応を解説
譲渡担保法の施行に向けて、企業側では契約フォーマットの見直しや登記手続の整備、社内規定の改訂など、多岐にわたる実務対応が求められます。取り組むべき具体的な対応は、以下の7つです。
それぞれ解説します。
登記・書面管理・契約書フォーマットの変更
譲渡担保法では契約の成立要件や対抗要件が明文化されたため、これに準拠した契約書フォーマットの整備が急務です。
具体的には、担保の目的や対象物の特定方法(種類・数量・保管場所など)、担保権者の処分権限、担保の実行方式などを文面に明確に反映させる必要があります。動産譲渡登記や債権譲渡登記における登記事項の整合性を図るため、社内で管理する書面のひな形(申請書・覚書など)も再設計が必要です。
登記手続きの流れと必要書類の整理
譲渡担保を公示して第三者対抗要件を確保する登記は、担保とする財産の種類によって手続きの流れや必要な書類が異なります。まず、契約書の中で担保の対象が個別の財産なのか、複数の財産をまとめたものなのか、また将来発生する財産も含めるのかといった範囲をはっきりさせておくことが大切です。そのうえで、どの登記制度を利用するかを選びましょう。
不動産は物件所在地を管轄する法務局で、所有権移転担保や仮登記担保等、通常の不動産登記制度を用いて手続きします。動産・債権は東京法務局が受け付ける動産・債権譲渡登記ファイル制度を利用するのが実務上一般的で、申請情報を記録した電磁的媒体を添付する点が大きな違いです。おもな必要書類は、以下となります。
| 担保対象 | おもな必要書類 |
|---|---|
| 不動産 | 登記申請書 登記原因証明情報(譲渡担保契約等) 登記識別情報(旧権利証) 代理権限証書(委任状) 登録免許税 |
| 動産 | 登録申請書 申請情報データ 登録免許税 |
| 債権 | 登録申請書 申請情報データ 登録免許税 |
各種登記は契約内容や申請方式に応じて手順・書類が変わります。詳細要件や最新運用は、必ず所管法務局・司法書士・弁護士などに確認してください。
社内体制整備・業務フローの見直し
法施行後は、契約部門だけでなく財務・営業・登記実務を担う部門との連携が重要です。契約に関連する各過程の役割分担を整理し、契約の起案・審査・実行・管理に至るフローを明文化しましょう。
新法に対応した業務手順書やマニュアルの整備や、関係者への研修の実施も必要です。特に集合物や将来債権を担保とする場合は、在庫管理や売上計上といった実務情報の正確性が担保効力に直結するため、情報システム部門との連携も視野に入れる必要があります。
実行時の対応(引渡命令・競売手続など)
担保権の実行時には、私的実行(帰属清算方式・処分清算方式)や裁判所を通じた競売手続など、複数の選択肢があります。
新法では実行前に設定者へ通知し、2週間の猶予期間を設けることが義務付けられています。通知には担保物の見積価額や算定根拠を明記する必要があり、不合理な価格設定は無効とされる場合もあるので注意が必要です。競売や引渡命令を選択する際は裁判所の手続きに則り、必要書類や期日管理を徹底しましょう。
このような手続きは債権回収の最終手段になるため、社内での準備や弁護士・司法書士との連携も欠かせません。
既存契約の洗い出しと移行措置への対応
施行前に締結された既存の担保契約については、経過措置の内容を確認し、必要に応じて契約内容の見直しや再締結をしなければなりません。まず社内で既存契約の一覧を作成し、新法の適用範囲や移行措置の対象となる契約を特定しましょう。
移行措置期間内に契約書式や管理方法を新法基準にあわせて改訂することで、将来のトラブルや権利喪失を防げます。特に登記や通知が未了の契約については、早急に手続きを完了させることがポイントです。
利害関係者への通知・調整
担保権の設定や契約内容の変更にあたっては、取引先や金融機関などの利害関係者への通知と調整が不可欠です。新法では通知や承諾が対抗要件となるケースが増えているため、関係者への連絡漏れがあると権利主張できなくなるおそれがあります。通知方法や内容は書面で記録を残し、合意内容や承諾事項を明確にしておくことが大切です。
また利害関係者との調整をスムーズに進めるため、事前に説明会や個別面談を実施して理解と協力を得る努力も求められます。
電子登記・オンライン手続き環境の確認
紙の契約書管理は改ざんリスクや保管コストの面からも限界があるため、電子署名による契約締結への移行が加速しています。新法対応を機に、担保契約の電子化や登記のオンライン対応に取り組む企業は増えると予想されるでしょう。
たとえばGMOサインなどの電子契約サービスを導入すれば、改正電子帳簿保存法に対応しつつ、真正性・改ざん防止・タイムスタンプ管理が可能になります。登記申請もオンラインで進められるため、書類提出の手間やミスを削減できるのも大きなメリットです。
電子登記対応には法務・IT部門の連携が不可欠のため、社内規程や運用マニュアルを整備しつつ、社内教育や導入支援も計画的に進めていきましょう。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)に関するよくある質問
譲渡担保とは?
譲渡担保とは、債務者が債権者に対して、あらかじめ財産権(動産や債権など)を譲渡することで、債務の担保として機能させる仕組みです。質権や抵当権と異なり契約上の自由度が高く、物の占有を移さずに担保を設定できるため、在庫や売掛債権などを担保とする実務で重宝されています。
譲渡担保法では仕組みを明文化し、担保権の法的安定性を高めるために条文が整備されました。
担保に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
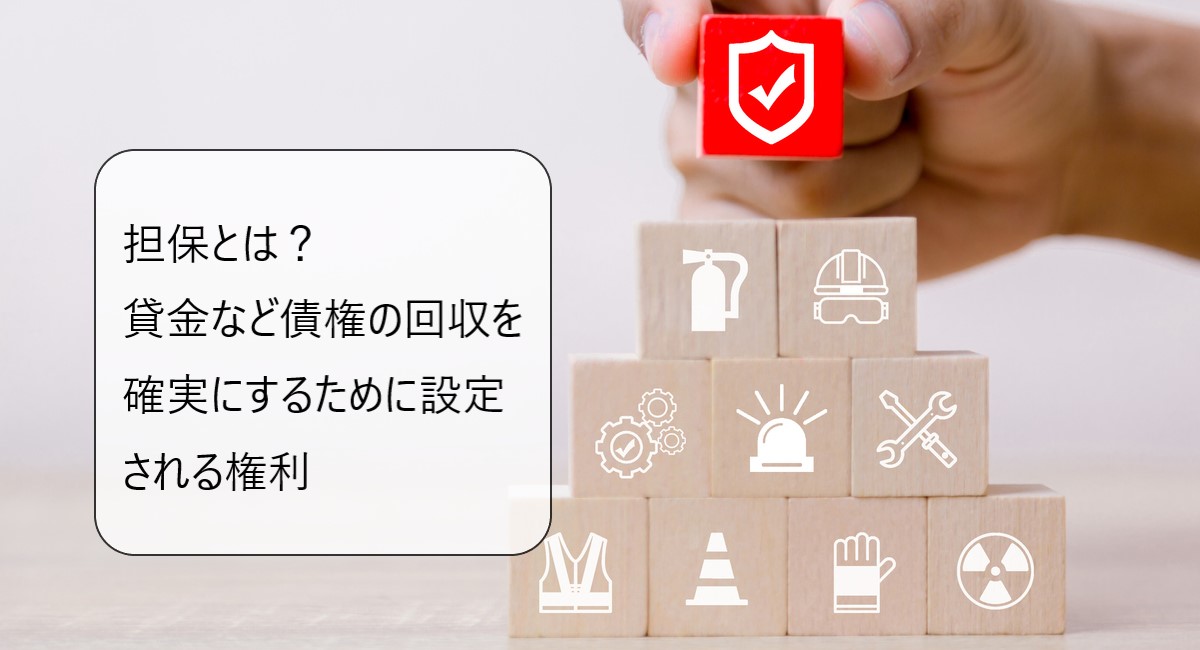
譲渡担保は民法に規定されている?
これまで譲渡担保は民法に明文の規定がなく、判例や実務慣行によって運用されてきました。そのため、契約内容や効力、第三者への対抗要件などが曖昧で、実務上トラブルの原因となることが多かったのです。
しかし、2025年に公布された譲渡担保法により、法律上の明確な根拠が与えられました。譲渡担保契約の効力や登記・通知などの対抗要件、倒産時の扱いなどが明文化され、今後はより安心して譲渡担保を活用できるようになります。
譲渡担保・抵当権・質権の違いは何?
いずれも担保の手段ですが、性質や取り扱いが異なります。
抵当権は不動産を対象とし、債務不履行時に競売を通じて優先弁済を受ける権利です。質権は動産や債権を対象とし、債権者が担保物を占有することで効力が生じます。
譲渡担保は、動産や債権の名義上の所有権を債権者に移転することで担保化する仕組みで、担保物の占有は移さずに使用継続が可能です。
譲渡担保は契約自由の原則に基づき、内容を柔軟に設計できるため、流動資産に対する実務的な対応力が高いという特徴があります。今回の法改正によって担保制度の違いが明文化され、実務においても選択肢の整理が容易になりました。
宅建業者は譲渡担保を禁止されている?
宅地建物取引業者(宅建業者)は、宅地建物取引業法により、消費者保護の観点から譲渡担保の利用に一定の制限があります。
たとえば一般消費者が不利益をかぶることを防ぐため、宅建業者が売買契約の際に買主から譲渡担保を受けることは、原則禁止です。(受領した額が代金額の10分の3以下である場合を除く)
宅建業者が譲渡担保を利用する際は法令やガイドラインを十分に確認し、正しい運用を心がける必要があるでしょう。
まとめ:譲渡担保法の施行に向けた準備を進めましょう
2027年12月6日までに施行される見込みの譲渡担保法は、曖昧だった譲渡担保契約や所有権留保契約のルールを明文化し、契約実務の透明性と安定性を大きく向上させる制度です。
施行に向けて、まず既存の契約書や社内規程を新しい法律の内容に合わせて見直すことが重要です。対象となる契約の洗い出しや、必要に応じた契約書式の改訂、登記手続きの整備、関係者への通知・調整など、準備すべき事項は多岐にわたります。特に、担保の対象や範囲、対抗要件の明確化など、法令遵守を徹底するための社内体制の整備が不可欠です。
たとえばGMOサインのような電子契約サービスを活用すれば、法的証拠力のある電子署名やタイムスタンプによる証跡管理、契約の進捗管理や検索性の向上など、法改正後の契約実務に最適な環境を整えることが可能です。
GMOサインでは無料のお試しフリープランや資料請求も利用できます。この機会に、電子契約への移行を検討し、法令対応と業務効率化の両立を図ってみてください。