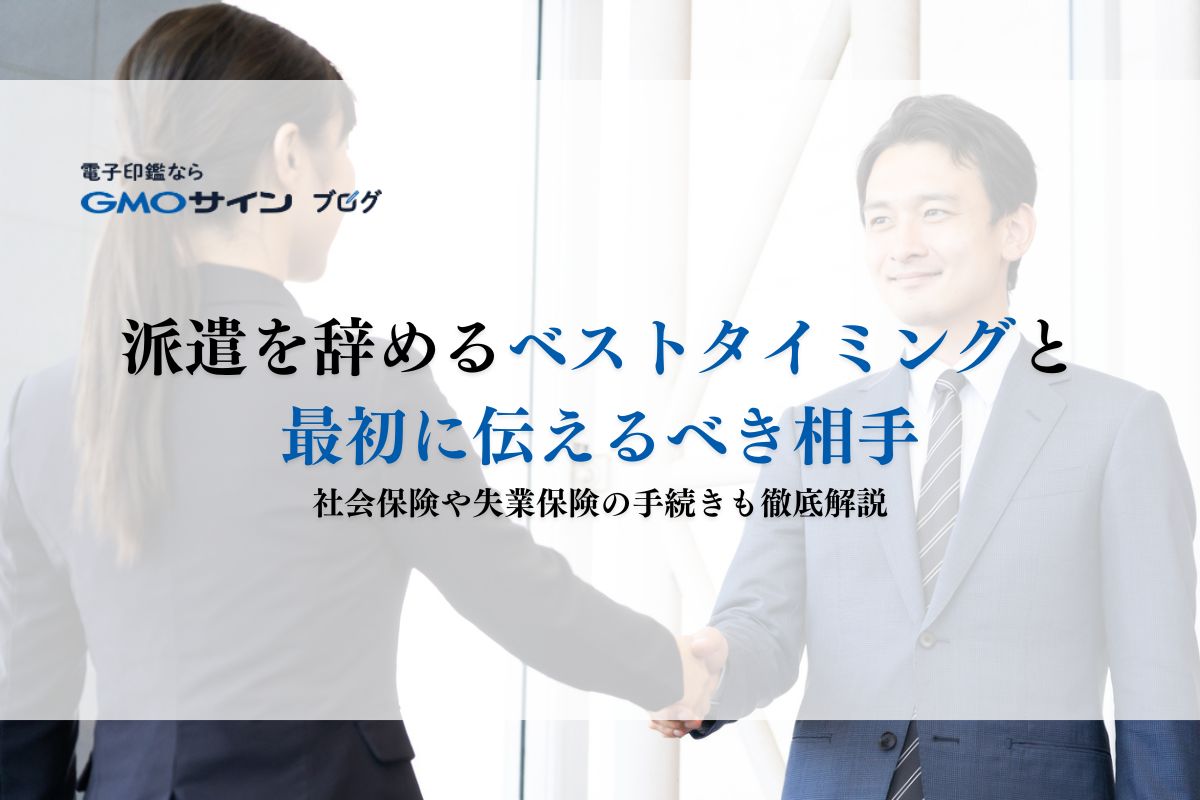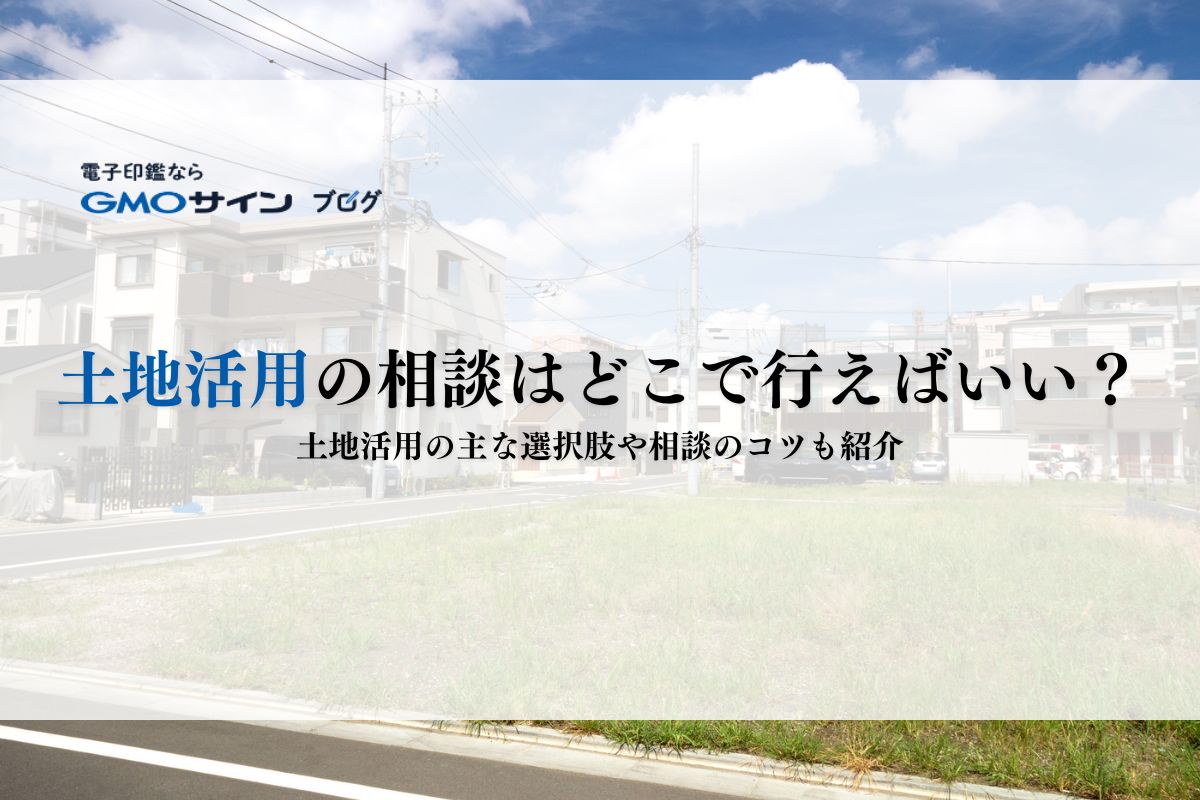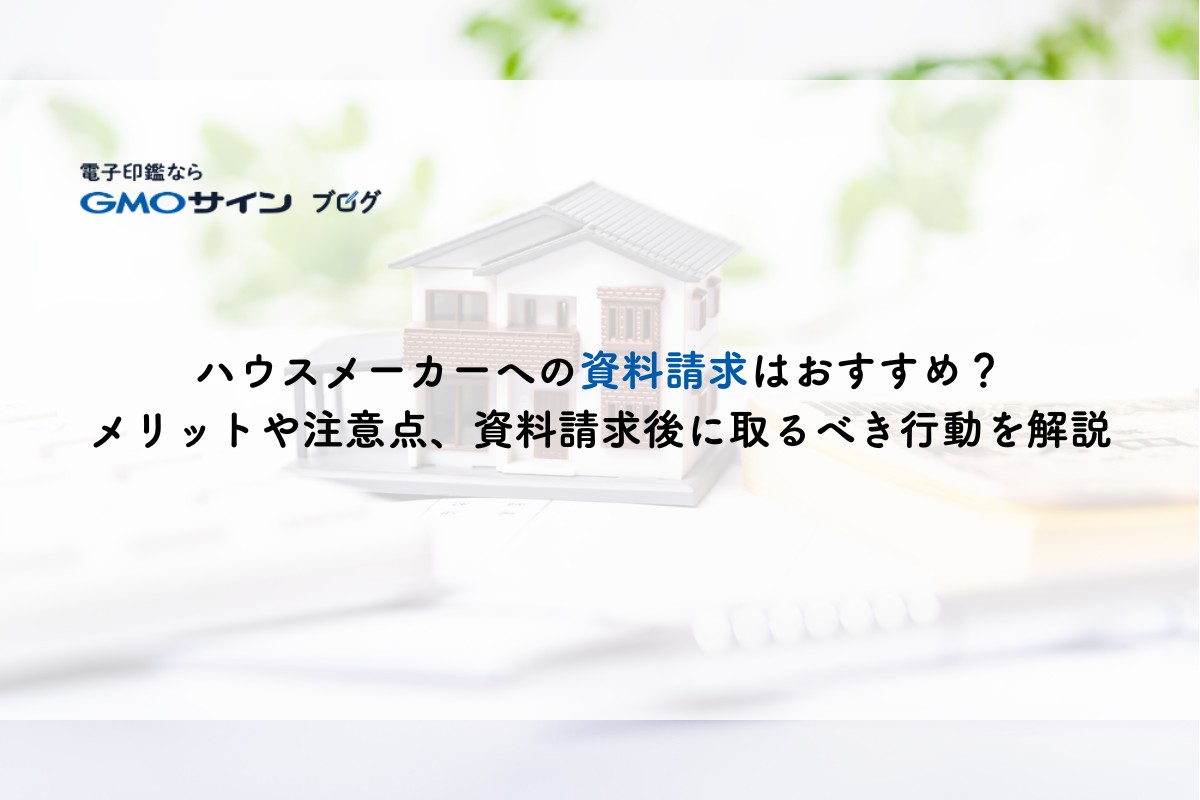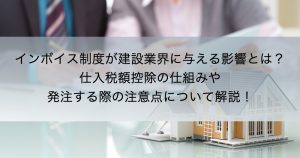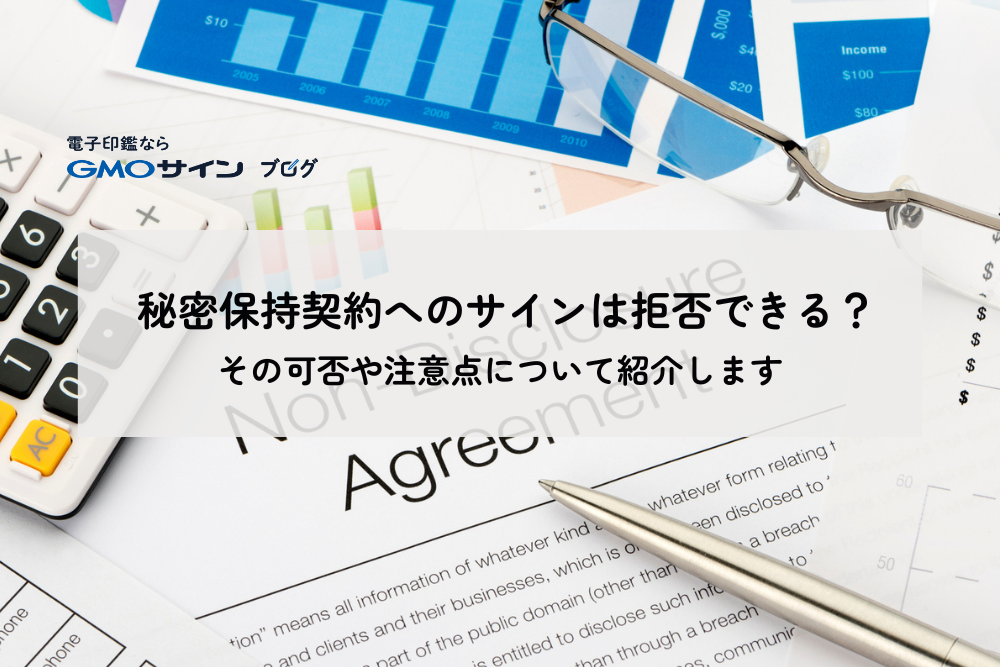公務員として働いているなかで懲戒免職という言葉を耳にしたら、どんな不安が頭をよぎるでしょうか。「自分には関係ない」と思っていても、予期せぬ事態で人生が大きく変わってしまう可能性があるかもしれません。
この記事では、懲戒免職について、その定義から具体的な事例、退職金や年金への影響、再就職の可能性まで徹底的に解説します。万が一、懲戒免職の危機に直面した時や懲戒免職について詳しく知りたいと思った時に、この記事が参考になるでしょう。ぜひ、最後まで読み進めてください。
懲戒免職とは?
まず、懲戒免職の法的根拠と懲戒処分の種類について解説していきます。これらを知ると、懲戒免職がどのような場合に、どのような根拠に基づいて行われるのかを把握できるでしょう。
懲戒免職の法的根拠(根拠法令)
懲戒免職は、公務員が重大な非違行為を行った場合に下される最も重い懲戒処分です。国家公務員の場合は国家公務員法第82条1項、地方公務員の場合は地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。
これらの法律は、公務員の仕事を問題なく維持して、国民からの信頼を損なわないように、懲戒免職の要件や手続きを定めています。具体的には、法令違反や職務怠慢、信用失墜行為などが該当し、これらの行為が公務員全体の信用を損なうと判断された場合です。
懲戒処分の種類
公務員に対する懲戒処分は、その重さに応じていくつかの種類があり、軽いものから重いものへと段階的に分けられています。
| 処分種類 | 内容 |
| 戒告 | 最も軽い処分。対象となる行為について厳重注意を行い、反省を促す。 |
| 減給 | 一定期間給与を減額で責任を取らせる。 |
| 停職 | 職務を一時的に停止するもので、その期間中は給与が支給されない。 |
| 懲戒免職 | 最も重い処分。公務員の身分を剥奪し、職を失わせる。 |
これらの懲戒処分は、公務員の非違行為に対して、組織の秩序を維持し、公務に対する信頼を回復するために行われます。
懲戒免職と懲戒解雇(クビ)の違い
懲戒免職という言葉を耳にする際、懲戒解雇やクビといった言葉も一緒に思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。これらの言葉はどれも、組織から職を失うという意味は同じですが、対象者や法的根拠において明確な違いがあります。ここでは、それぞれの言葉の意味や違いを解説していきます。
懲戒解雇とは?
懲戒解雇とは、民間企業における最も重い懲戒処分を指します。従業員が会社の規則に著しく違反した場合や重大な不正行為を行った場合に適用されるもので、解雇の中でも特に厳しい処分です。
懲戒解雇は、単なる解雇とは違い、従業員の責任を取らせる意味合いが強く、退職金の不支給や減額といった経済的な制裁を伴う場合もあります。企業は、就業規則に懲戒解雇の要件を明記し、労働基準法と労働契約法に則った手続きを行う必要があります。
懲戒解雇との違い
懲戒免職と懲戒解雇の違いは、処分の対象者です。懲戒免職は公務員に対して行われるものであり、国家公務員法や地方公務員法に基づいています。一方、懲戒解雇は民間企業の従業員に対して行われるものであり、労働基準法や労働契約法に基づいて行われます。
クビとの違い
クビという言葉は、一般的に解雇を意味する俗語として広く使われています。法的な用語ではなく、解雇や退職勧奨、雇止めなど幅広い意味を持ちます。企業が一方的に雇用契約を終了させるさまざまなケースを含んだ曖昧な表現です。
懲戒免職の具体的な例
懲戒免職は、その処分が下される行為によって、いくつかのカテゴリに分類できます。ここでは、4つのカテゴリに分けて、それぞれの具体的な例を以下で紹介します。
一般服務関係の懲戒免職例
一般服務関係とは、公務員が職務を遂行するうえで守るべき基本的なルールや倫理観を指します。おもに下記の例を紹介します。
職務上の秘密漏えい
自己の利益を図る目的で、職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせる行為
違法な職員団体活動
ストライキなどの争議行為を企て、またはその遂行を共謀し、公務の運営を妨げる行為
公文書の不適正な取り扱い
公文書の偽造・変造、虚偽の公文書作成、公文書の隠匿・毀棄(壊して捨てることまたは物の効用を害すること)など、公文書の信頼性を損なう行為
ハラスメント
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにより、相手に精神疾患を発症させるなど、職場環境を著しく悪化させる行為
公金・官物取り扱い関係の懲戒免職例
公金・官物とは、国や地方自治体が所有する財産や金銭です。ここでは、以下のようなものがあります。
公金または官物の横領
職務上管理している公金や官物を、自分のものとして不正に使用する行為。
公金または官物の窃取
公金や官物を盗み取る行為。
詐欺による公金または官物の取得
人を欺いて公金または官物を交付させる行為。
公務外非行関係の懲戒免職例
公務外非行とは、公務員が職務外で行った違法行為や倫理に反する行為です。具体的には、以下のような例が挙げられます。
重大な犯罪
放火、殺人、強盗など、社会的に非難されるべき重大な犯罪行為
財産犯罪
他人の物を横領、窃盗、詐欺、恐喝するなど、財産を侵害する行為
薬物犯罪
麻薬、大麻、覚せい剤などの違法薬物を所持、使用、譲渡する行為
青少年に対するわいせつ行為
18歳未満の者に対し、金品を渡して淫行を行うなど、青少年を被害者とする性的な行為
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係の懲戒免職例
飲酒運転や悪質な交通事故は、重大な結果を招く可能性があり、公務員の信用を大きく損なう行為です。このカテゴリには、以下のようなものがあります。
酒酔い運転による死亡・傷害事故
酒酔い運転によって他人を死亡させる、傷害を負わせる行為
酒気帯び運転による死亡・傷害事故と救護義務違反
酒気帯び運転によって他人を死亡させる、傷害を負わせたうえで、救護義務を怠る行為
飲酒運転幇助(ほうじょ)
飲酒運転をする職員に対し、車両や酒類を提供する、飲酒を勧める、飲酒運転を知りながら同乗する行為
重大な交通事故と救護義務違反
飲酒運転以外での交通事故で他人を死亡させる、重傷を負わせたいうえで、救護義務を怠る行為
おもな交通行為と処分内容
交通行為の中で、懲戒免職の対象になった状況下での処分内容は以下のとおりです。
| 行為 | 処分 |
| 酒酔い運転で死亡事故 | 懲戒免職 |
| 酒気帯び運転で傷害事故+救護義務違反 | 懲戒免職 |
| 飲酒運転の幇助(ほうじょ) | 関与の程度により懲戒免職、停職、減給 |
| 死亡または重傷事故+救護義務違反(飲酒運転以外) | 懲戒免職または停職 |
懲戒免職を行う判断基準
懲戒免職は、公務員の身分を剥奪する最も重い処分です。そのため、判断は慎重に行われなければなりません。客観的な事実に基づき、公正な手続きを経て決定される必要があります。
懲戒免職の判断においては、以下の要素を総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。
(参考:懲戒処分の指針について|人事院)
- 非違行為の重大性は行為の内容、動機、態様、結果などを総合的に考慮し、対象行為が公務員全体の信用を著しく損なうものであるかを判断します。
- 故意または過失の度合いで、行為が故意によるものか、過失によるものかによって、責任が異なります。故意による悪質な行為は、より重い処分につながる可能性があるでしょう。
- 行為を行った公務員の職責を考慮します。管理職など、より責任の重い立場にある者が行った行為は、より厳しく判断される傾向にあります。
- その行為が社会的影響があるのかを考慮します。社会的な関心が高い事件や国民の信頼を大きく損なう行為は、より重い処分につながる可能性があるでしょう。
- 過去に懲戒処分を受けた場合は、今回の行為と合わせて総合的に判断されます。過去の処分歴は、今回の処分を重くする要因となることがあります。
- 日頃の勤務態度や非違行為後の対応なども考慮されます。反省の態度が見られない場合や勤務態度が著しく悪い場合は、処分が重くなる可能性があります。
- 懲戒処分を行うにあたっては、弁明の機会を十分に与えるなど、適正な手続きを踏む必要があります。しかし、手続きに不備があった場合、処分の有効性が異なるでしょう。
これらの要素を総合的に判断し、懲戒免職が相当であると判断された場合にのみ、処分が下されます。
懲戒免職に不服がある場合は異議申し立てができる
懲戒免職は、その後の生活に大きな影響を与える重大な処分です。もし処分に納得がいかない場合は、不服を申し立てる権利が保障されています。ここでは、不服申し立ての手続きや注意点について解説します。
懲戒免職を受けた場合、その処分が妥当ではないと感じた時は、不服申し立てが可能です。不服申し立ては、法的に認められた権利であり、処分を受けた人が自己の権利を保護するために重要な手段となります。ただし、不服申し立てには期限や手続きが定められているため、注意が必要です。
国家公務員や地方公務員は、人事院または人事委員会に対して審査請求を行えます。審査請求には期限があり、処分があったと知った日(処分説明書を受領した日)の翌日から3カ月以内、または処分説明書を受領しなかった場合でも、処分があった日の翌日から1年以内に申し立てる必要があります。
(参考:不利益処分についての審査請求の手引|人事院公平審査局)
懲戒免職における退職金や年金、失業保険はどうなる?
懲戒免職という厳しい処分を受けた場合、気になるのはその後の経済的な影響です。退職金や年金、失業保険など、生活を支えるはずだったものがどうなるのか。ここでは、それぞれの項目について詳しく解説します。
退職金は支給されない可能性がある
懲戒免職となった場合、退職金が全額または一部支給されない可能性があります。退職金の支給は法律で一律に定められているわけではなく、各組織の規定によって異なります。
- 国家公務員の場合、国家公務員退職手当法に基づき、退職金の全部または一部を支給しない、あるいはすでに支払われた退職金の返納を命じる
- 地方公務員の場合は、各自治体の条例で定める
ただし、必ずしも全額が不支給となるわけではありません。個別の事情やこれまでの勤務状況などを考慮し、一部が支給されるケースもあります。しかし、重大な不正行為が認められた場合や組織に大きな損害を与えたと判断された場合は、全額不支給となる可能性が高くなります。
年金に影響はしない
懲戒免職を受けたとしても、国民年金や厚生年金といった公的な年金制度からの給付には、原則として影響はありません。年金は、加入期間や保険料の納付実績にもとづいて支給されるものであり、懲戒処分の有無によって左右されるものではないためです。
たとえば、禁錮以上の刑に処せられた場合や停職以上の処分を受けた場合には、共済年金の一部の減額や支給自体を停止することがあります。
失業保険は受けられない
懲戒免職によって職を失ったとしても、失業保険(雇用保険)は原則として受給できません。これは、公務員が雇用保険の適用対象外となっているためです。
(参考:国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律について|総務省人事・恩給局)
懲戒免職後の再就職と社会的影響
懲戒免職は職を失うだけでなく、その後の人生にも大きな影を落とす可能性があります。特に、再就職の難しさや社会的な偏見といった問題は、避けて通れない現実です。
懲戒免職後の再就職は、決して容易ではありません。公務員は、懲戒処分の事実が公表される場合もあり、履歴書に記載しなければ経歴詐称となってしまいます。また、国家公務員法や地方公務員法によって、一定期間(通常2年間)は再び公務員として職に就くことはできません。
民間企業への就職も、同様に困難となります。懲戒免職という事実は、多くが採用選考において不利に働き、企業によっては採用を見送られる可能性もあります。特に、公務員としての信用を重視する企業やコンプライアンスを厳格に守る企業では、その傾向が顕著です。
懲戒免職に関する正しい知識を持って、冷静な対処をしましょう
この記事では、懲戒免職に関するさまざまな側面を解説してきました。懲戒免職とは何か、懲戒解雇やクビとの違い、具体的な事例、そして退職金や年金などについても網羅的に紹介しています。
懲戒免職は、公務員にとって最も重い処分であり、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。正しい知識を持ち、万が一の事態に冷静に対処して、適切な行動を取りましょう。この記事が、懲戒免職について理解を深め、今後の人生設計の一助となれば幸いです。