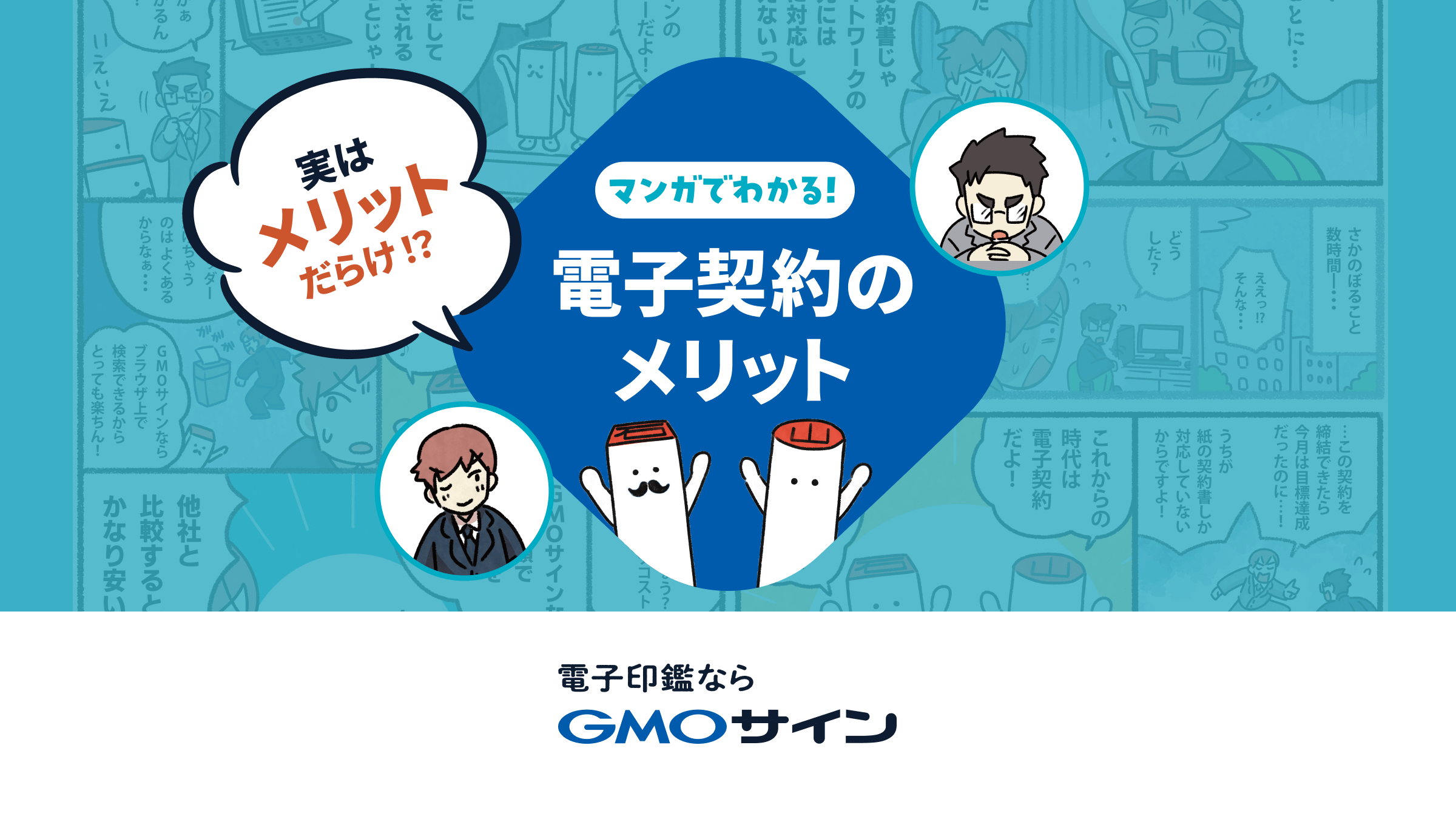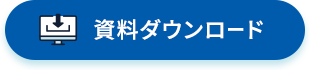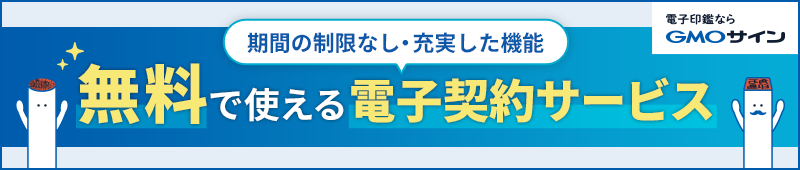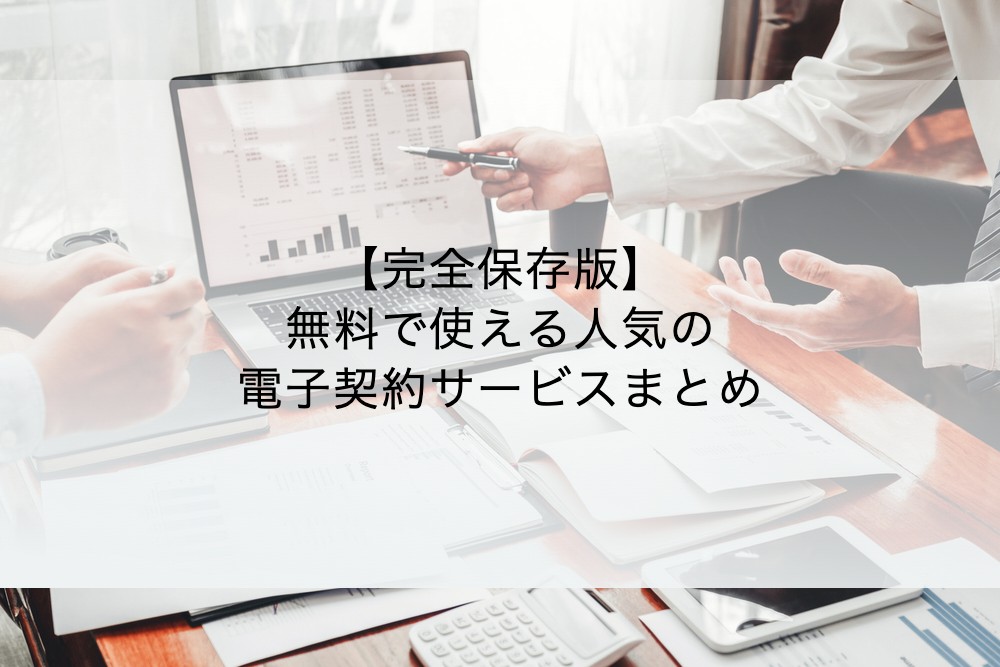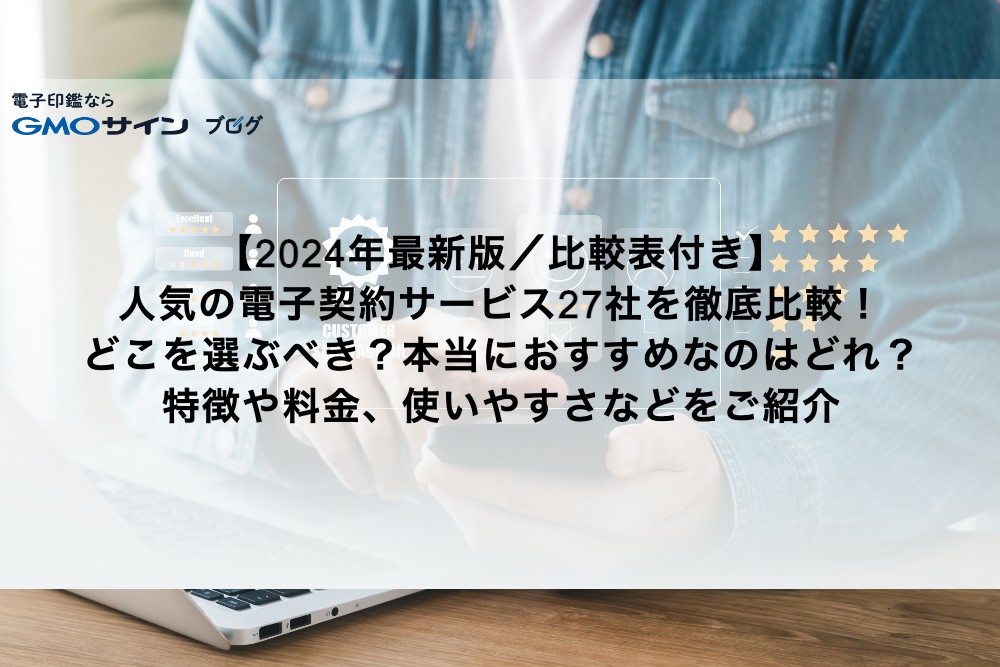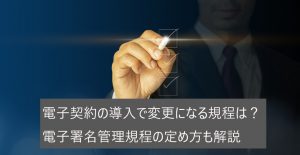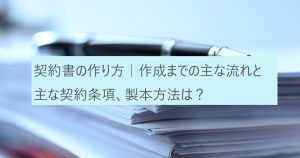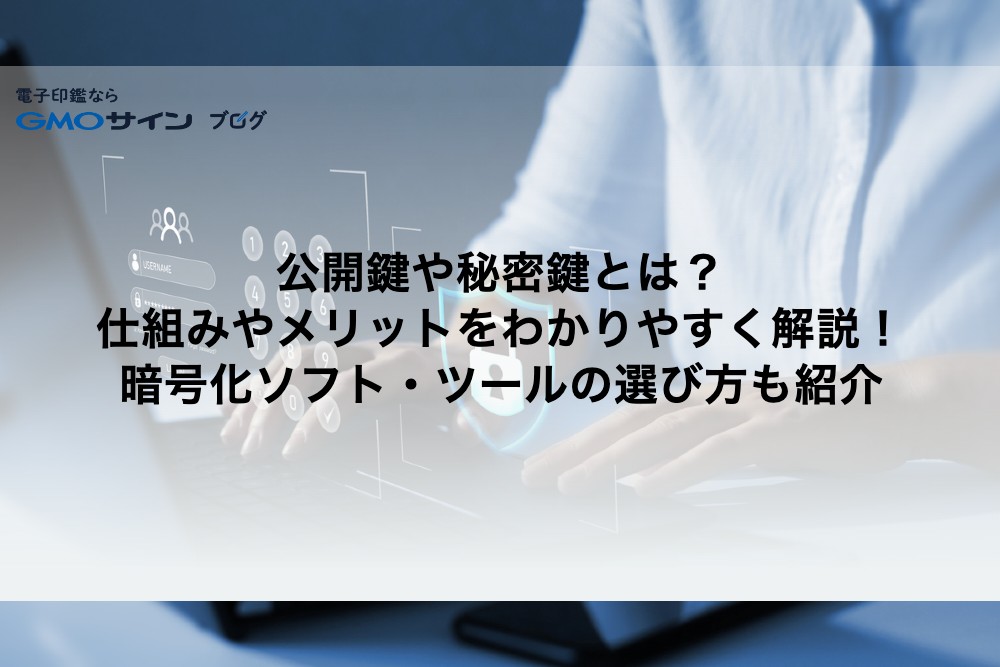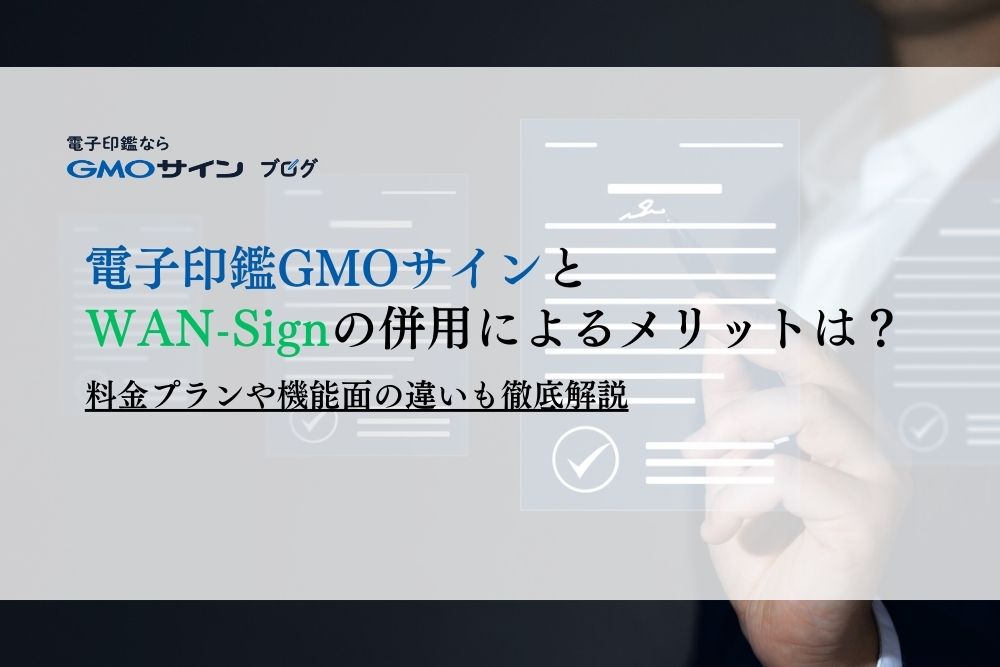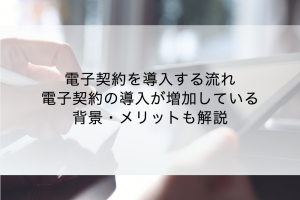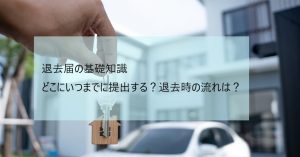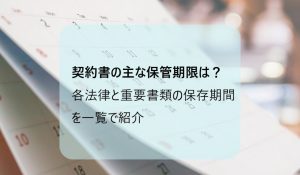バックデートの意味とは?問題となるケースやリスクを避けるための方法、契約書を結ぶ際に気を付けることは?
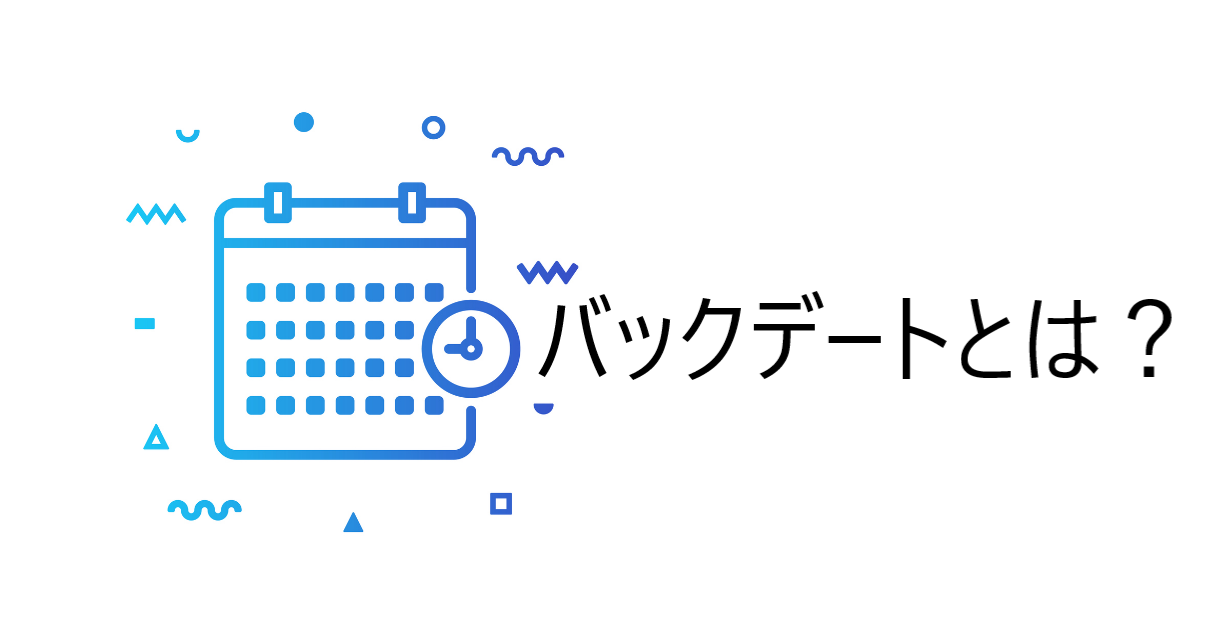
この記事ではバックデートの概要やバックデートに関係する契約締結日の種類、バックデートを行うリスクなどについて解説します。また、バックデートを回避するための具体的な方法についても取り上げているため、ぜひ参考にしてください。
バックデートとは?
バックデートとは、実際に契約を結んだ日よりも過去の日付を契約締結日として、契約書に記載することです。また、契約締結日は、契約当事者が締結日と定めた日となります。一般的には契約書に当事者の署名もしくは押印が完了した日のことです。
なお、契約書の署名欄には記入日や署名日などと記載されていることもありますが、こちらはあくまでも実際に署名や押印を行なった日付を記載するものであり、必ずしも記入日・署名日=契約締結日となるわけではありません。
契約締結日の主な種類
契約締結日にはいくつかの種類があります。どの種類を選ぶかによって契約の効力が発生するタイミングが異なるため、それぞれの違いを理解しておかなければなりません。
ここでは、主な契約締結日の種類を紹介します。
契約期間の開始日
契約書に記載されている契約期間の開始日を契約締結日とするケースがあります。
この方法を採用する企業は多く、一般的な契約締結日の1つといえるでしょう。
ただし、万が一8/20〜9/1までの間に契約違反が発生した場合、つまり契約書自体は作成しているものの、契約締結日を迎えていない場合、契約書の効力は発生しているのかどうかが問題となり、トラブルに発展する可能性があります。
最初に署名・押印のあった日
取引を行う企業間のうち、片方の企業が最初に契約書に署名・押印した日付を契約締結日とするケースもあります。
この場合、署名・押印のタイミングはA社の事情によって決まるため、後から署名・押印するB社にとっては納得しにくい部分もあるでしょう。
最後に署名・押印のあった日
先ほどの種類とは逆に、取引を行う企業間のうち、もう一方の企業が後から契約書に署名・押印した日付を契約締結日とするケースもあります。
この方法は、一般的な企業でも採用されている方法です。
ただしこの種類の場合、A社が契約締結日を空白にした状態でB社に送り、B社が契約締結日を記入する形となりますが、B社が自由に契約締結日を決めることができてしまいます。また、B社が契約締結日を入力し忘れる可能性もあるなど、トラブルにつながるケースもあるため注意してください。
合意形成があった時点の日付
契約に関するやり取りを行う中で、基本条件について実質的に合意形成があった日を契約締結日とすることもできます。
この場合、会議の場での口頭同意や交渉のやり取りを行うメールでの合意などに基づくこととなります。双方が合意したタイミングが契約締結日となるため、当事者同士でも納得しやすいというメリットがあります。
全当事者からの報告を受けた時点の日付
契約書の基本条件に合意し、その後社内ワークフローを経て決済されたタイミングを契約締結日とするケースもあります。
この場合、企業内の然るべき手順を経て手続きが行われていることもあり、透明性の高さを確保可能です。
バックデートが問題となるケース
バックデートは必ずしもトラブルにつながるわけではありませんが、基本的には避けるべきです。特に、以下のような場合は問題となる可能性があるため注意しなければなりません。
- 事実を捏造して虚偽の契約締結日を記載した
- 契約の締結までに時間がかかったため決算期をまたいでしまった
- 新社長が就任する前の期間であるにも関わらず新社長の名義で契約締結日を記載した
- 間違えて暦のうえで存在しない日付を締結日にしてしまった(11月31日など)
- 相手企業との合意がないにもかかわらず、さも合意があったかのように締結日を記載した
一方で、バックデートの発生がやむを得ない状況となるケースもあります。
バックデート自体に違法性はないため、このような実務上やむを得ないバックデートは一般的に問題視されることはありません。しかし、上記リスクが示すように不要なバックデートは、契約相手とトラブルになる可能性があります。やはり、バックデートはやむを得ない場合を除き基本的に避けるべきだといえるでしょう。
バックデートによる主なリスク
バックデートを行うと、第三者は本当の契約締結日がいつなのかわかりません。たとえ嘘の契約締結日を記載していたとしても、その嘘の日が本当の契約締結日と捉えてしまうでしょう。これは、虚偽の情報を契約書に記載していることになってしまい、企業のコンプライアンス面から考えると大きな問題となります。
もし虚偽情報の記載が発覚してしまうと、取引先や世間一般からの評価を大きく落とすことにもなりかねません。また、場合によっては私文書偽造罪に問われる可能性もあります。
バックデートを避ける方法
バックデートは、さまざまな方法を駆使することで回避可能です。ここでは、バックデートを避ける方法を2つ紹介します。
契約締結日とは別に効力発生日を定め、遡求適用する
バックデートを回避したい場合、契約書に効力発生日を記載することをおすすめします。
本契約は、契約締結日にかかわらず、○○年○○日に遡及して適用される、といった形で契約書に記載しておくことで、契約締結日よりも前の日付を設定することができます。これを遡求適用と言います。
ただし、効力発生日を設定する場合、取引を行う双方の合意が必要です。
電子契約サービスを利用し、契約にかかるタイムラグを縮める
電子契約サービスは、タイムスタンプを利用しますが、タイムスタンプは改ざんができないため、そもそもバックデートができません。そのため、電子契約サービスの利用はそのままバックデート回避となります。
電子契約サービスの場合、基本的に取引先の相手に契約書を送信したときの日付がそのまま契約締結日となりますが、任意の日付を設定することも可能です。
バックデートの回避には電子契約サービスを!
今回はバックデートの概要や契約締結日の種類、バックデートによるリスクなどについて解説しました。
バックデートは、契約を結んだ日よりも過去の日付を契約締結日として、契約書に記載することです。バックデートを行うと、虚偽の情報を契約書に記載することとなるため、コンプライアンス上の問題につながる可能性があります。そのため、やむを得ない状況を除き、基本的にはバックデートを行わないようにしましょう。
簡単にバックデートを回避したい場合は、電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」の利用がおすすめです。電子印鑑GMOサインは、クラウド型の電⼦契約サービスです。
紙の契約書のような製本、郵送作業を省けるため、契約締結までのスピードの劇的な向上が期待できます。もちろん、バックデートはできない仕組みとなっているため、安心して利用可能です。興味のある人は、ぜひ利用を検討してみてください。