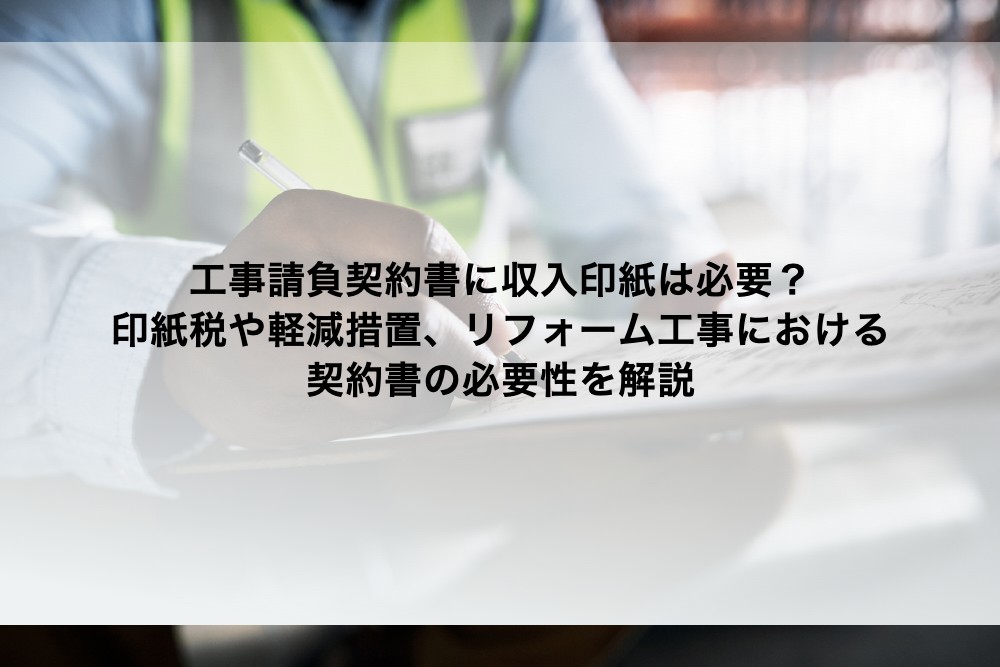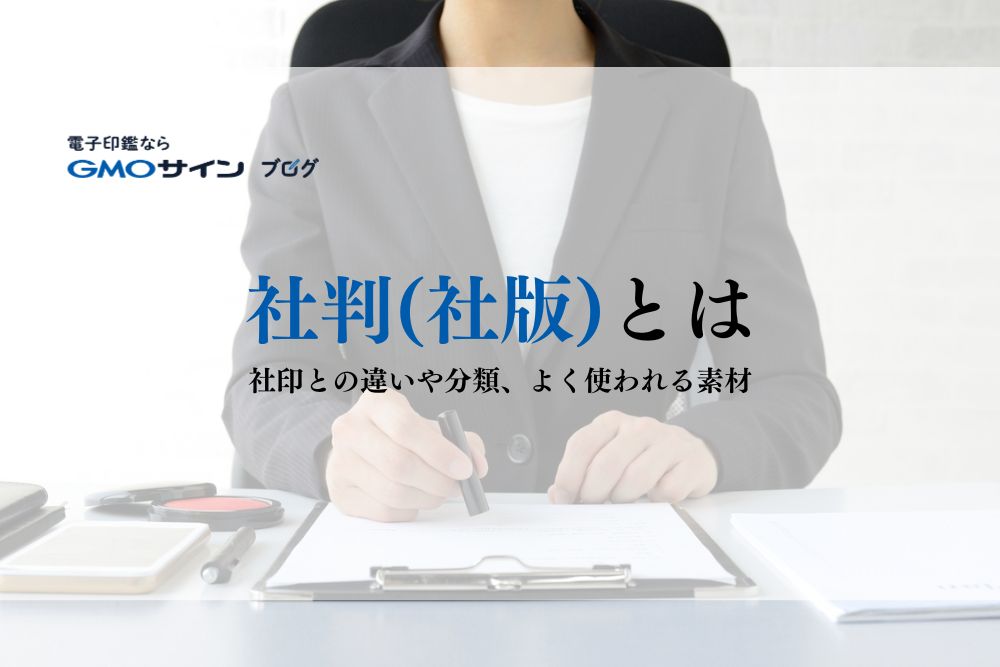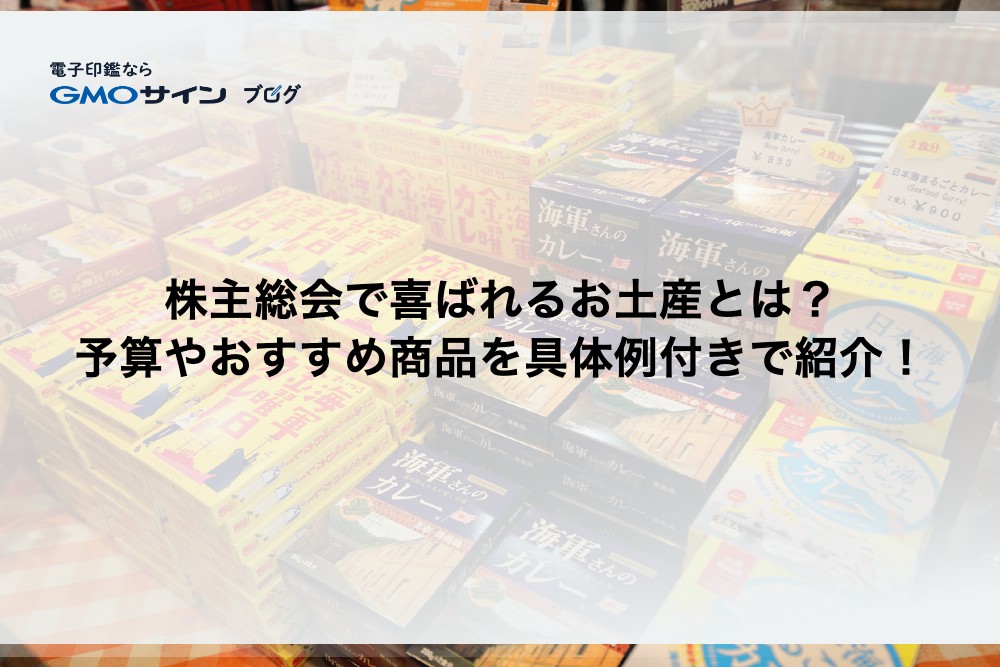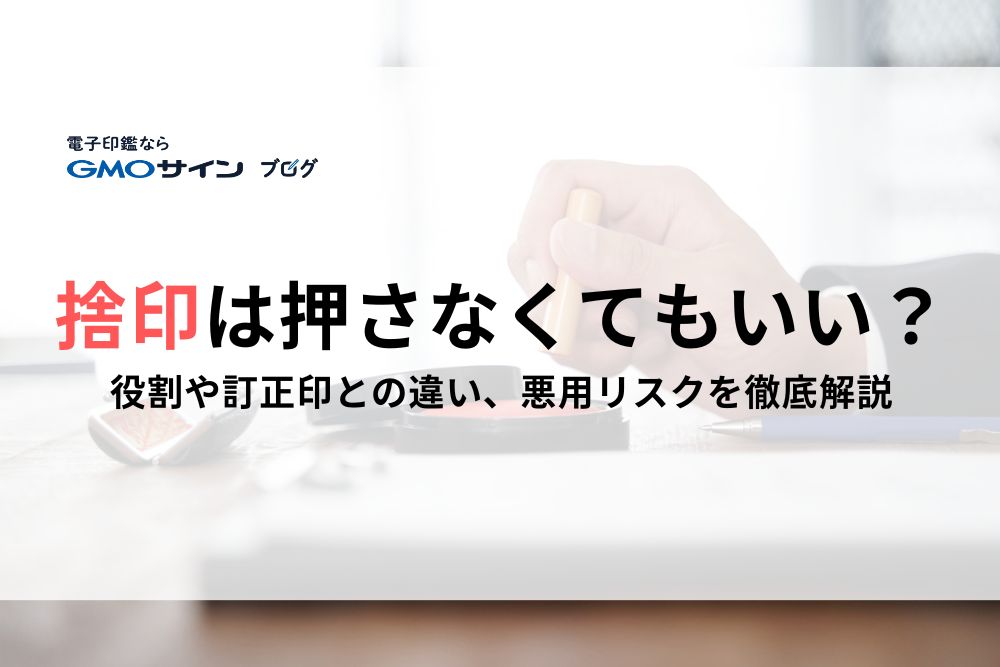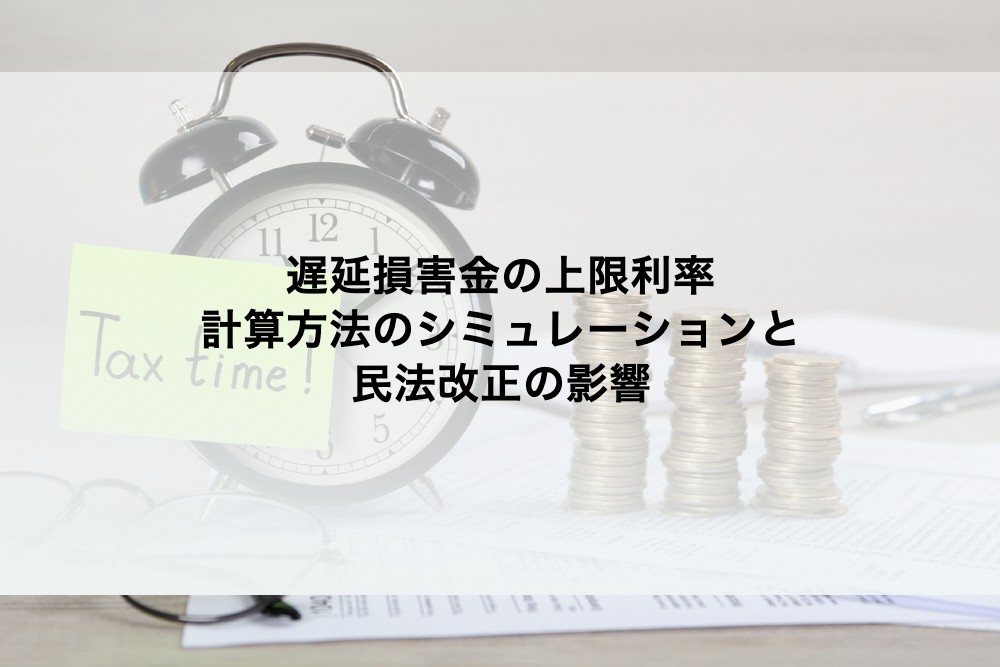企業が保有する特許を他社へ許諾したり、他社の特許技術を安心して利用したりする場合に必要となるのが特許実施許諾契約です。
この契約は、特許権を持つ企業にとっては収益化の手段となり、利用する企業にとっては事業を安定させるための重要な法的根拠となります。
本記事では、特許実施許諾契約の基本から、ライセンスの種類、契約書に定めるべき具体的な条件までをお伝えします。
特許とは?
特許実施許諾契約を理解するには、まず特許そのものへの理解が不可欠です。特許とは何か、企業にとってどのような価値を持つのかを解説します。
特許制度の目的と意義
特許制度は、新しい技術を開発した発明者に対し、その発明を独占的に使用できる権利を一定期間与える仕組みです。これにより、研究開発への意欲を高め、社会全体の技術革新を促進することを目指しています。
特許権を取得するメリット
特許権の取得は、企業にとって数多くのメリットがあります。その一つが、発明を独占的に実施できる独占排他権です。これにより、競合他社が同じ技術を使用して製品を製造・販売することを法的に阻止でき、市場での優位性を確保できます。
また、特許権を得ることで、企業の信用力向上とブランド力強化も可能です。特許の取得は、企業が高い技術力を持っていることの証明となり、顧客や取引先からの信頼を獲得しやすくなります。
さらに、特許権は収益化の機会を生み出します。自社で特許技術を使用するだけでなく、他社に特許実施許諾契約を結びライセンス供与することで、ロイヤリティ収入の獲得も可能です。また、特許権自体を売却する、特許譲渡という選択肢もあります。
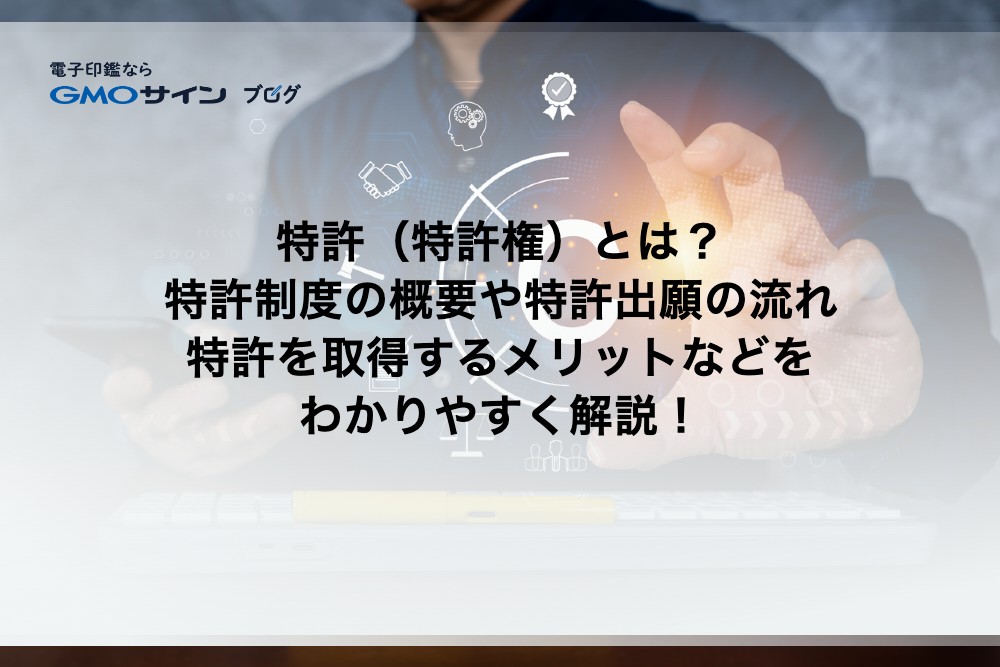
具体的な特許例
特許と言うと、何か特別なものと思われるかもしません。しかし、私たちの身近な製品や技術にも多く存在します。
これらはすべて特許によって保護されていて、それぞれの技術を開発した企業が市場での競争力を維持し、新たな技術開発を進めるための基盤となっています。特許実施許諾契約は、このような技術を他社が合法的に利用するための重要な手段です。
特許権を侵害されるリスク
特許権取得により、企業はさまざまなメリットを得られる一方、第三者による侵害リスクには十分な注意が必要です。
もし、他社が無断で特許技術を使用していることが判明した場合、特許権者は差止請求や損害賠償請求といった法的措置を取りましょう。ただし、法的措置には時間や費用がかかるため、事前契約によって権利関係を明確にしておくことが重要です。
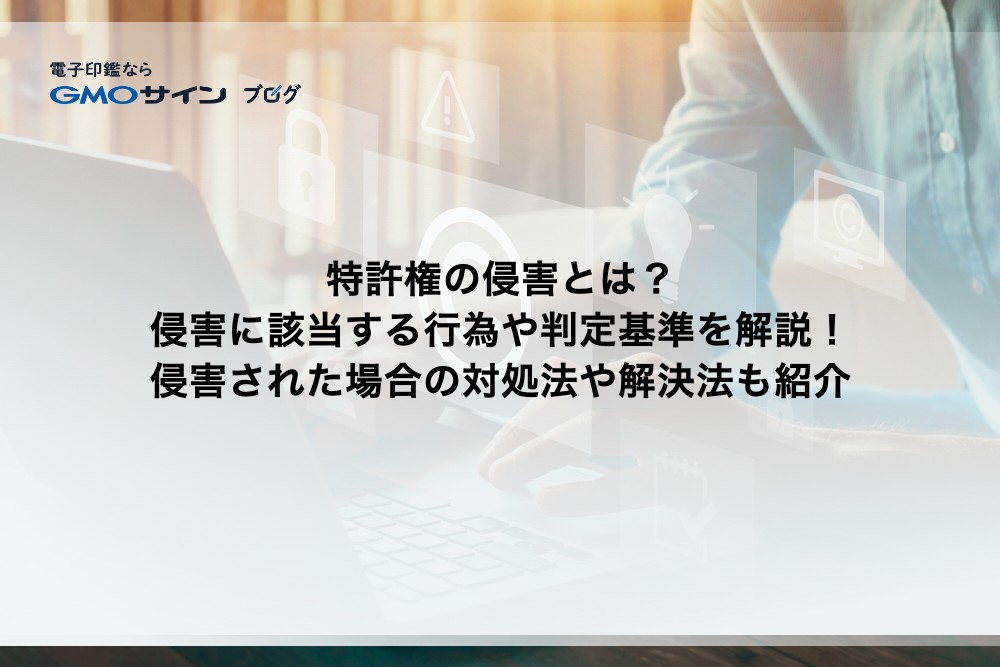
特許実施許諾契約の概要と特許法の実施権
特許の重要性を踏まえた上で、特許実施許諾契約の基本概念と、特許法における実施権について解説します。
特許実施許諾契約(ライセンス契約)とは
特許実施許諾契約は、特許権者が第三者であるライセンシーに対し、自社の特許技術を一定の範囲内で使用することを許可する契約です。
一般的に「ライセンス契約」とも呼ばれ、特許権を保有する企業が独占的に使用するだけでなく、他社にその使用を認めることで収益を得るという目的があります。ライセンシーは、その対価として特許権者にロイヤリティ(実施料)を支払うことで、安心して特許技術を活用した事業の展開が可能です。
特許権者にとって、この契約は、自社の特許を有効活用して新たな収益源を確保する手段となります。自社では事業化が難しい技術でも、他社にライセンス供与することで、特許の価値を最大限に引き出すことが可能となるのです。
一方、ライセンシーにとっては、多額の研究開発費をかけることなく、必要な特許技術を合法的に使用できるため、迅速な事業展開が実現します。
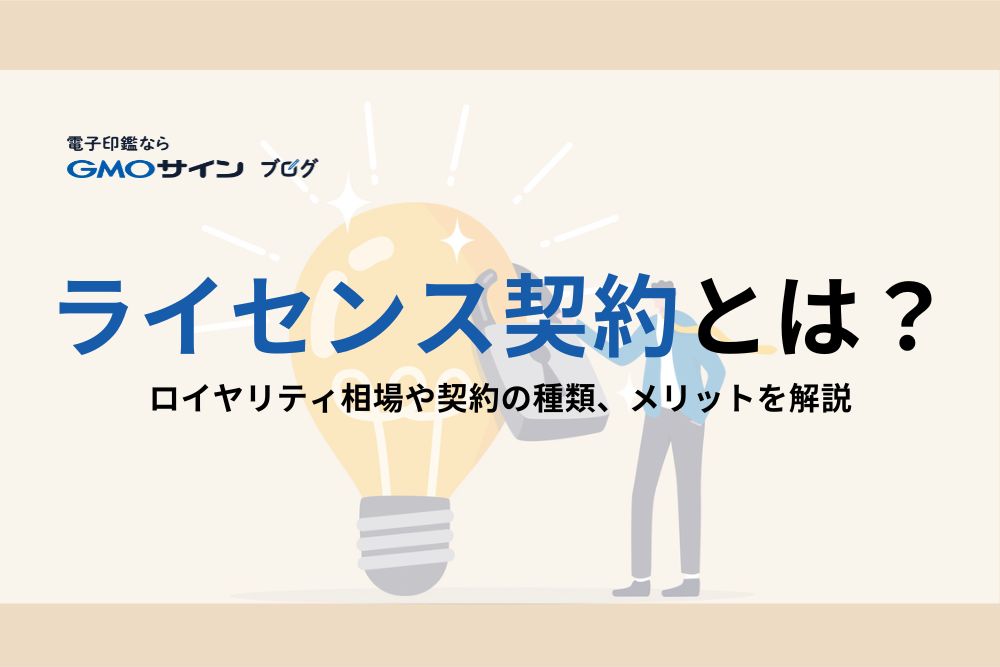
特許法における実施権の概念
実施権とは、特許法で、特許権者が特許発明を独占的に実施できる権利を指すものです。
どちらの実施権を設定するかは、企業にとって契約の根幹をなす重要な事柄です。当事者の事業戦略に大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。
通常実施権と専用実施権
特許実施許諾契約の根幹をなす「通常実施権」と「専用実施権」について、その性質と違いについて解説します。
通常実施権とは
通常実施権は、特許法第78条に規定されており、特許権者が第三者に対し、特許を一定の範囲内で使用させることを認める権利です。
特許権者は通常実施権を複数の企業に対して許諾できるため、多くのライセンシーから収益を得る機会があります。また、特許権者自身もその特許を自由に実施可能です。
通常実施権は、原則として特許庁に登録しなくても契約の効力は発生します。契約当事者間において、口頭での合意や書面による契約が成立した時点で有効となるため、手続きが簡便な点も通常実施権の大きな特長と言えるでしょう。
(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
参考:特許法七十八条|e-Gov法令検索
通常実施権のメリットとデメリット
特許庁への登録により、特許権が第三者に譲渡された場合や特許権者が破産した場合でも、その実施権を第三者に対抗できるというメリットもあります。第三者対抗力を持つことで、ライセンシーの事業安定が可能です。
さらに、通常実施権を設定するメリットとして挙げられるのが、特許権者がより多くの企業にライセンスを許諾し、収益機会を増やせる点です。これは、ライセンシー側から見ても大きなメリットで、専用実施権に比べて安価なロイヤリティで技術を利用できる可能性が高くなります。
一方、デメリットとしては、ライセンシーにとっては独占性がないため、市場で同じ技術を使用する競合他社が存在する可能性がある点が挙げられます。市場での優位性が限定的になる傾向があるのは、ライセンシーにとってデメリットとなり得るのです。
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
参考:特許法第九十九条|e-Gov法令検索
専用実施権とは
専用実施権は、特許法第77条に規定されており、設定された範囲内で特許を独占的に実施できる権利です。
専用実施権は、その内容を特許庁に登録することで初めて効力が発生します。登録には、設定登録申請書や契約書などの書類が必要です。登録をすることで、独占的に特許を実施できる権利を第三者に対し、主張できるようになります。
登録は効力発生要件であるため、実施権として成立させるためには、登録が必要不可欠と考えましょう。
専用実施権のメリットとデメリット
専用実施権を設定するメリットは、ライセンシーが市場で独占的に技術を使用できるため、大きな事業機会を得られる点です。独占販売権や独占製造権などを確保できますから、競合他社との差別化を図りやすくなるでしょう。
特許権者にとっても、専用実施権は独占性が高いため、通常実施権よりも高額なロイヤリティを設定できる可能性が高くなります。
デメリットとして挙げられるのは、特許権者が自ら特許を実施できなくなるため、その技術を活用した新たな事業展開が難しくなる点です。また、ライセンシーにとっても、専用実施権は通常実施権よりもロイヤリティが高くなる傾向にあります。
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
参考:特許法第七十七条|e-Gov法令検索
通常実施権と専用実施権の比較
通常実施権と専用実施権の主な違いを表にまとめ、それぞれの項目について解説します。
| 項目 | 通常実施権 | 専用実施権 |
| 独占性 | なし(非独占的) | あり(独占的) |
| 登録の要件 | 不要(ただし登録可能) | 必要(登録により効力発生) |
| 許諾数 | 複数企業に許諾可能 | 設定された範囲では1社のみに許諾可能 |
| 特許権者の実施 | 実施可能 | 実施不可(設定範囲内) |
| 主なメリット | 特許権者:収益機会の増加 ライセンシー:安価な利用 | 特許権者:高額なロイヤリティ ライセンシー:市場での独占 |
| 主なデメリット | 特許権者:収益が分散 ライセンシー:独占性がない | 特許権者:自社で実施不可 ライセンシー:ロイヤリティが高価 |
独占性
通常実施権には独占性がなく、特許権者は複数の企業と契約を結ぶことが可能です。一方、専用実施権は独占的であり、設定された範囲内ではライセンシーのみが特許を実施できます。
登録の要件
通常実施権は契約当事者間では登録不要ですが、第三者対抗力を持つためには登録が必要です。専用実施権は、特許庁への登録が効力発生の要件となります。
許諾数
通常実施権は、特許権者が望む限り、複数の企業に許諾が可能です。しかし、専用実施権は、一つの設定範囲につき一社にしか許諾できません。
特許権者の実施
常実施権の場合、特許権者も自由にその特許を実施できます。しかし、専用実施権の場合は、設定された範囲内では特許権者も特許の実施ができなくなります。
主なメリットとデメリット
独占性の有無が、双方のメリットとデメリットに直結します。特許権者は独占性のない通常実施権で多くの収益機会を得るか、独占性の高い専用実施権で高額なロイヤリティを狙うか、という選択が可能です。
契約書に定めるべき主要な条件と条項
特許実施許諾契約におけるトラブルを防ぐには、契約書にどのような項目を記載する必要があるのでしょうか。ここでは、契約書に記載する項目について、なぜ重要なのか、どのような内容を記載すべきか、注意すべき点は何かについて解説します。
許諾の範囲に関する条項
契約書には、許諾する特許の範囲を明確に記載します。範囲が不明瞭だと、無用なトラブルにつながる可能性が高くなります。
対象特許の特定と定義
許諾する特許を正確に特定するため、特許番号、発明の名称、出願日、特許登録日などを記載します。
実施行為の範囲
特許の「実施」には、発明の製造、使用、販売、輸入などさまざまな行為が含まれます。許諾する範囲を明確に限定し、どの行為をどこまで認めるかを定めます。
実施地域の限定
特許を使用できる地理的範囲や契約が有効な期間を明確に定めるものです。たとえば、日本国内のみか、特定の国や地域を含めるか、期間はいつからいつまでかなどを記載します。
ロイヤリティ(実施料)に関する条項
ロイヤリティとは、特許の実施に対して支払われる対価で、ライセンス料とも言われます。その算定方法には、売上高や生産数に応じた歩合方式、特定の金額を支払う定額方式、両者を組み合わせたハイブリッド方式など、さまざまな方法があります。
歩合方式
製品の売上高や生産個数に応じてロイヤリティの額を決定する方法です。たとえば、「ライセンス製品の売上高の3%」といった形で定めます。技術の貢献度や製品の市場性に応じて、料率を調整することが重要です。
定額方式
契約期間中、月々や年々、決まった金額を支払う方法です。たとえば、「月額10万円」といった形で定めます。製品の売上や生産数に影響されないため、ライセンシーにとってはコストの予測がしやすいというメリットがあります。
ハイブリッド方式
歩合方式と定額方式を組み合わせた方法です。たとえば、最低保証額として定額を支払い、売上が一定額を超えた場合は歩合制に移行する、といった形が考えられます。
契約書を作成する際には、どの方式で算定するか、料率は何パーセントか、そしていつ、どのような方法で支払うかを明確に定めましょう。また、ロイヤリティ算定の根拠となる売上高や生産数など、それぞれの情報をライセンシーが開示する義務についても規定することが大切です。
独占性に関する条項
契約の種類が「専用実施権」か「通常実施権」かを明確にします。前述の通り、これによってライセンスの独占性が決まるため、契約の根幹となる重要な条項です。
サブライセンス(再許諾)に関する条項
サブライセンスとは、ライセンシーがさらに第三者に対し、特許の使用を許諾することです。これを認めるか否か、また、特許権者の事前の書面による承諾を必要とするといった許可をする場合の条件を契約書に定めます。
改良技術の取り扱いに関する条項
特許技術の実施を通じ、ライセンシーが改良技術を発明するケースも少なくありません。その場合、改良技術の所有権をどちらが持つのか、特許権者も改良技術を使用できるのかなどを定めておくことが、将来の紛争を防ぐ上で重要です。
保証と責任に関する条項
権利侵害の保証、契約不適合責任などを契約書に盛り込むことも大切です。これにより、万が一の事態が発生した場合の責任の所在を明確にできます。
契約解除に関する条項
ロイヤリティの支払いが滞った場合や契約に違反した場合などに、契約を解除できる条件を定めます。
また、差押え、仮差押えなど公権力による処分を受けたとき、会社の解散、合併、分割など重要な一部の譲渡の決議をしたときなども契約違反と判断する場合があります。
後々のトラブルを避けるためにも違反については十分に検討の上、内容を決めるようにしましょう。
紛争解決に関する条項
契約に関して紛争が発生した場合に、どの裁判所で解決するかなどを定めます。なお、管轄裁判所の決め方としては、当事者であるどちらか一方の所在地を管轄裁判所とするのが一般的です。基本は特許を取得している側の管轄裁判所とするケースが多くなっています。
クロス式とは、特許権者側から訴訟を起こす場合はライセンシーの所在地を管轄する裁判所に、ライセンシー側から訴訟を起こす場合は特許権者の所在地を管轄する裁判所にする決め方です。
契約交渉から締結後の運用までの注意点
特許実施許諾契約は、交渉から締結後まで複数のステップを踏みます。それぞれの段階で注意すべき点を理解することで、円滑に手続きを進めることが可能です。
交渉フェーズ
交渉に入る前に、自社の契約目的を明確にしておきましょう。実際の交渉については、相手企業の事業内容や経営状況を事前に調査することで、交渉を有利に進められる可能性が高くなります。交渉では、自社にとって不利益な条件を受け入れないよう、慎重な対応が必要です。
契約書作成・レビューフェーズ
交渉で合意した内容をもとに、契約書を作成します。契約書は、前述した重要な事項を漏れなく記載することが重要です。
また、トラブルを防ぐには、曖昧な表現を排除し、誰もが同じ解釈ができるように記述する必要があります。そのためには、作成した契約書は、弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼し、法的に問題がないか確認してもらいましょう。
契約締結後の管理と運用
契約締結後も、契約内容を定期的に見直し、遵守されているかを確認することが重要です。特に、ロイヤリティの支払いが滞りなく行われているか、許諾範囲外での使用がないかなどについての監視はしっかりと行いましょう。
特許を適切に管理するには特許実施許諾契約の理解が重要
特許実施許諾契約は、企業の事業戦略において非常に重要な役割を果たします。特許権者にとっては収益の機会を創出し、ライセンシーにとっては円滑な事業展開を可能にするための法的な基盤となります。
特許権者が第三者に特許の使用を認めるライセンス契約は、特許権を独占的に使用するのではなく、他社に許諾することで収益を得るという目的があります。まずはこの基本をしっかりと理解しましょう。
また、特許実施許諾契約の根幹をなす通常実施権と専用実施権の違いについての理解も必須です。非独占的で複数の企業に許諾可能な通常実施権と、特定の範囲で独占的な権利を与える専用実施権は、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。契約の目的や事業戦略にあわせて、適切なライセンス形態を選択することが重要です。
さらに、契約書に定めるべき具体的な条項についても把握しておかなくてはなりません。許諾の範囲、ロイヤリティの算定方法、サブライセンスの可否、改良技術の取り扱いなど、将来的なトラブルを未然に防ぐために詳細に定めておくべき項目は多岐にわたります。
円滑な事業運営のためには、これらの知識を理解し、適切な契約を締結することが不可欠です。特許を活用した事業展開を検討されている方はぜひ、参考にしてください。