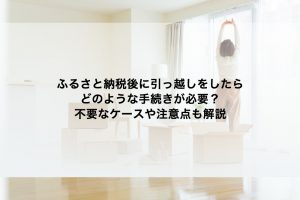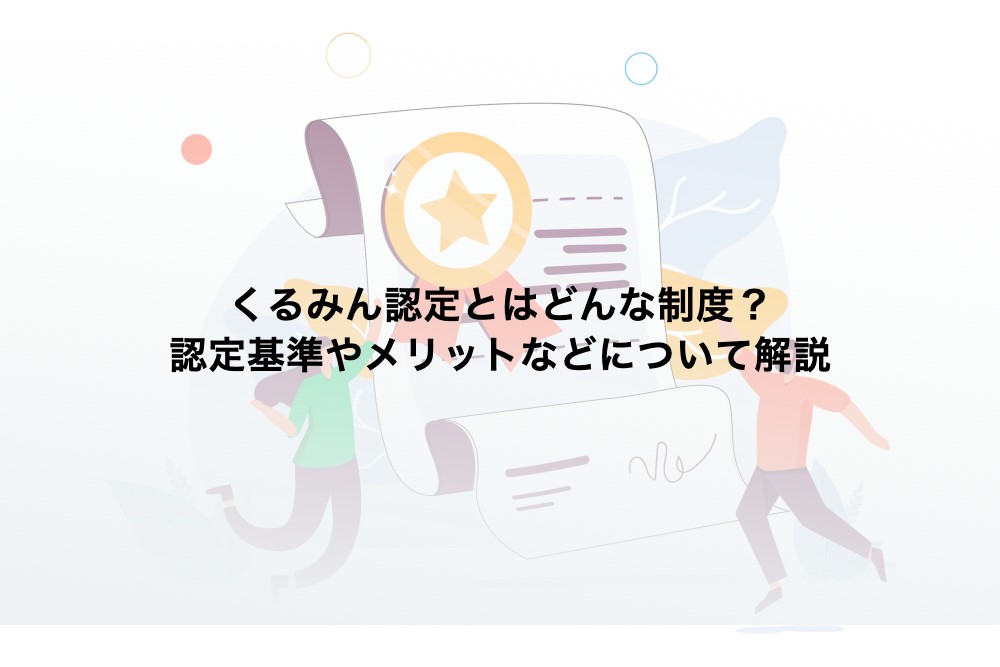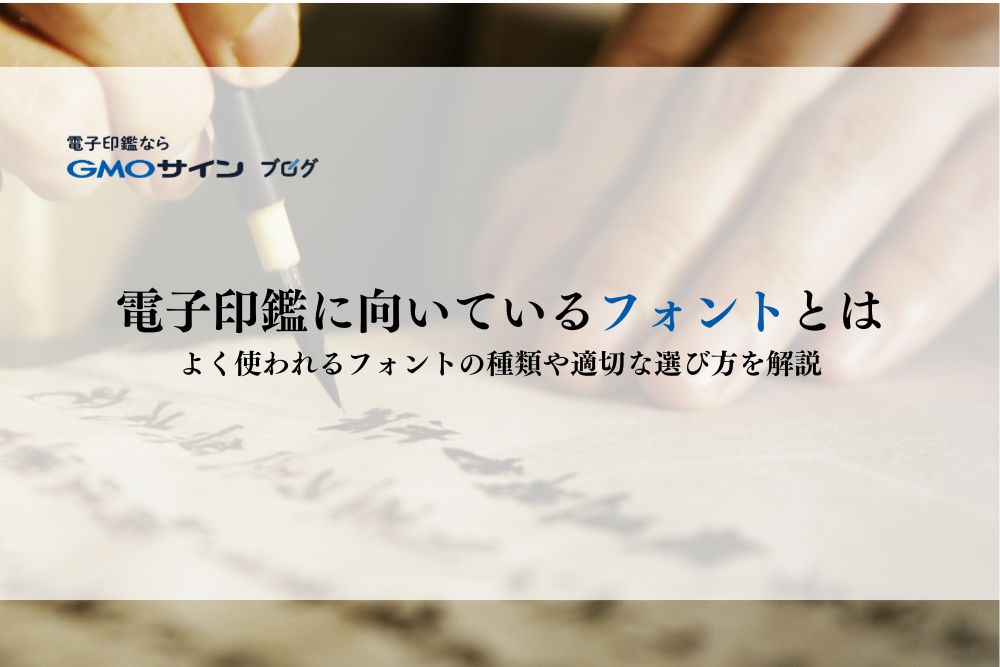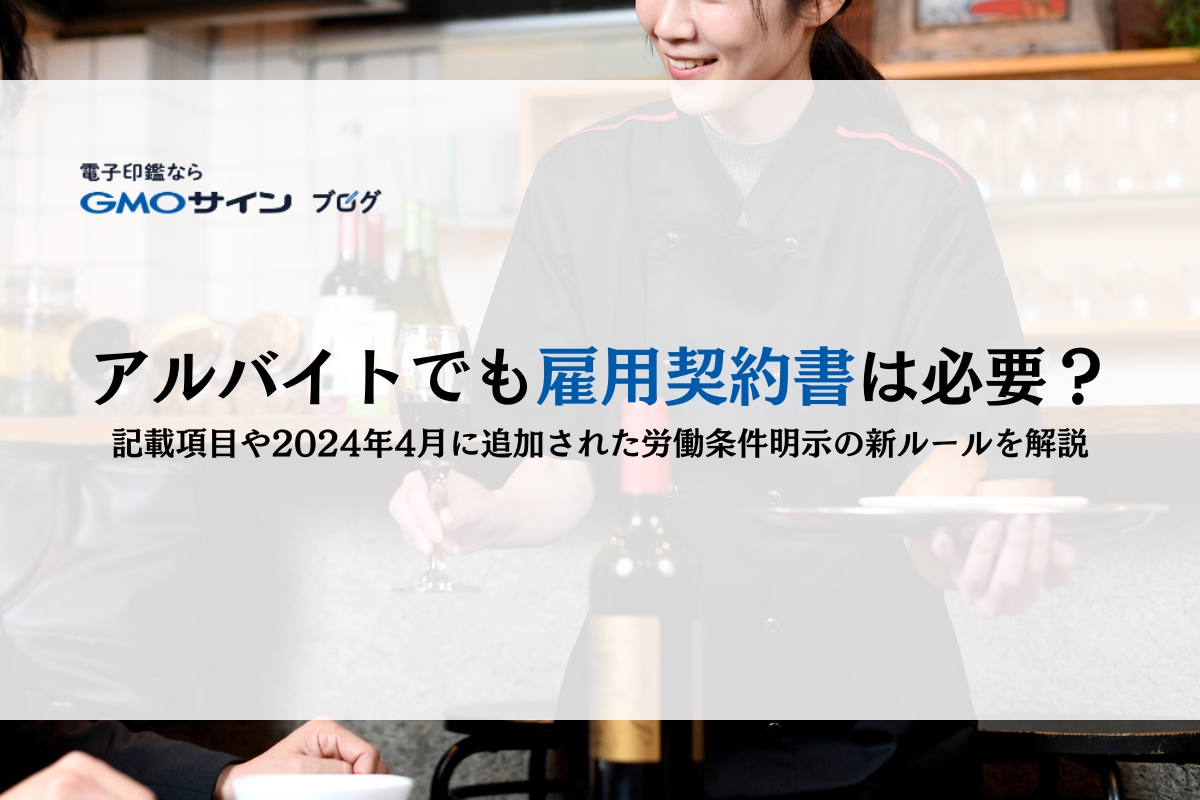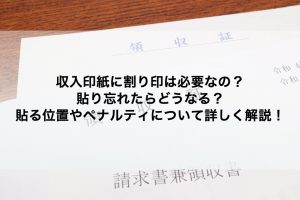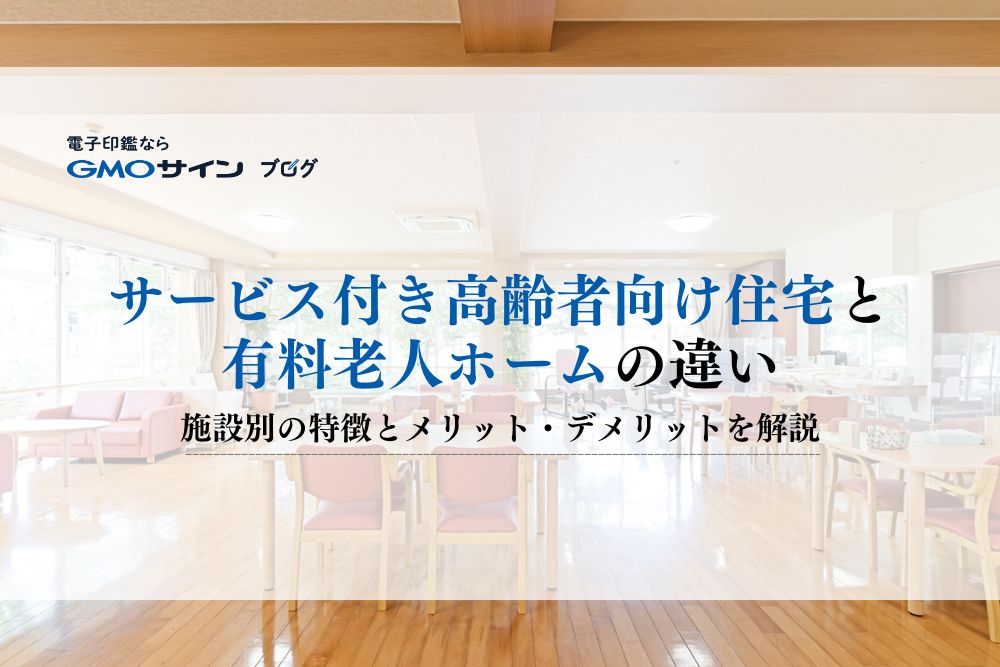ダンピング(不当廉売)という言葉を耳にしたことはないでしょうか。ダンピングとは正当な理由なく原価よりも大幅に下回る価格で商品やサービスを提供する行為です。ダンピングは、不公正な取引方法に当たります。
そこで本記事では、ダンピングの定義や問題点、罰則について解説します。
ダンピング(不当廉売)の基礎知識
ダンピング(不当廉売)とは、原価よりも大きく下回る価格で商品やサービスを販売する行為です。ダンピングを行うと、ほかの事業者の活動に深刻な影響をもたらす危険性があるため、好ましくないとされています。ダンピングは以下の3種類に分類できます。
散発的ダンピング
散発的ダンピングとは、過剰生産の結果売れ残った在庫を国外で投げ売りする行為です。
海外で売却する関係上、日本国内での経済活動とはなりません。そのため、日本の公正取引委員会も処分を行いにくくなっています。グレーゾーンのダンピングともいえるでしょう。
規制を回避しやすいことから、しばしば行われるダンピングの類型です。
略奪的ダンピング
略奪的ダンピングとは、ライバル企業を排除する目的で不当に安い価格で販売する行為です。
原価を大幅に下回る価格に設定してしまうことで、市場シェアを奪ってしまうのです。そして、ある程度のシェアを確保できて安定したところで妥当な価格に戻して、そこから収益を確保するわけです。
独占市場になってしまうため、間接的に消費者に影響が出かねない行為といえます。
継続的ダンピング
継続的ダンピングとは、相場価格よりも安い価格で長期にわたって継続的に販売する行為を指します。
この場合、正常な企業努力によって低価格で販売できている場合もあり、一概にダンピングと断ずることもできません。区別が難しいため、慎重に判断すべきといえます。
ダンピングは独占禁止法違反
ダンピングは、独占禁止法の不公正な取引方法に該当する違法行為です。
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
(参考:e-Gov法令検索)
どのような取引が不公正な取引方法に該当するのか、要件とあわせて頭に入れておきましょう。
不公正な取引方法
不公正な取引方法とは、市場においての公正な競争を妨げる恐れのある行為を指します。以下で紹介するように、独占禁止法第2条9項で定められています。
⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(参考:e-Gov法令検索)
一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
ダンピングの条件
独占禁止法の定義するダンピングに該当するには、いくつかの条件が存在します。
供給に要する費用を著しく下回る
先ほど紹介した独占禁止法第2条9項の中には、供給に要する費用を著しく下回る対価という文言があります。供給に要する費用とは、総販売原価のことだと考えてください。製造原価もしくは仕入原価に販売費と一般管理費を加えた金額のことです。
著しく下回る対価とは、廉売対象商品を供給しなかった場合に発生しないコストを下回るという意味合いです。製造原価もしくは仕入原価も回収できないような価格設定にすると、この条件に抵触する危険性が出てくるということです。
継続的な供給
独占禁止法の第2条9項に、継続して供給するという項目があります。文字通り継続的に供給するという意味ですが、相当期間において廉売を繰り返し行った、もしくは事業者の営業方針などをベースに客観的に継続性がうかがえることが必要です。
毎日その価格で販売していなくても、購買状況で継続して廉売していると判断されれば、条件を満たすわけです。
不当廉売に該当する
第2条9項の条件を満たしていなくても、以下の一般指定の6項に該当してしまうとダンピングに認定されてしまう危険性があるため注意してください。
(不当廉売)
(参考:不公正な取引方法|公正取引委員会)
6 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
具体的には総販売原価は下回っているが、廉売対象商品を供給しないと発生しない費用以上の価格で販売した場合が想定されます。
廉売対象商品を供給しないと発生しない費用を下回っている価格で単発的に販売した場合
そのほかにも廉売対象商品を供給しないと発生しない費用を下回っている価格で単発的に販売した場合などもダンピングに該当する可能性があります。つまり、公正な競争原理にマイナスの影響をもたらす場合には、不公正な取引方法に当てはまってしまう可能性があるということです。
独占禁止法を見てみると、ほかの事業者の活動を困難にさせる恐れのある場合も不公正な取引方法に該当しうるとあるため、注意しなければなりません。困難にさせる恐れに該当するかどうかは、事業の規模や商品の数量、廉売期間など総合的に判断して判定されます。
また、ほかの事業者とは同業他社に限らない点も理解しておきましょう。廉売によって競争関係に何らかの影響を及ぼす可能性がある場合には、ほかの事業者に該当します。具体的には卸売りや小売り業者の廉売によって、メーカー間の競争に影響をもたらす場合、業界が違っても当該メーカーがほかの事業者に当たる可能性があります。
正当性があればダンピングにはならない
上の条件に当てはまったとしても、廉売するにあたって何らかの正当性があると判断されれば、不公正な取引方法には当たりません。では正当な理由として、どのような事情が当てはまるのでしょうか。
具体的には需給関係によって販売価格が低落したり、原材料の再調達にあたって、当初の取得原価よりも低くなったりしている場合などです。そのほかにも想定外の原材料価格の高騰で、商品価格が供給に要する費用よりも大きく下回ってしまった場合もダンピングに当たらない可能性があります。
ダンピングへの罰則
ダンピングと認定された場合、独占禁止法違反となる可能性があります。つまり、罰則の対象になる可能性があるわけです。科される罰則には、いくつかの候補が考えられます。
排除措置命令
排除措置命令とは、当該行為の差止や契約条項の削除など違法行為を排除するために必要な措置を講じるように公正取引委員会が出す命令のことです。もし排除措置命令が出されれば、対象事業者は速やかに是正措置を講じることが義務付けられます。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、一種の罰金のようなものです。課徴金は違反行為を行った期間中に取得した売上額の3%が徴収されます。
差止請求
こちらは公正取引委員会による罰則ではありません。ダンピングによって被害を受けた、または被害を受ける可能性のあるものからの請求です。
ダンピングの停止もしくは予防を求める請求で、差し止め請求が認められれば、迅速にダンピング行為を停止しなければなりません。くわえて、再発防止処置を提示する必要もあります。
損害賠償請求
こちらもダンピング被害者による請求手続です。もしダンピングで他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する必要があります。
ダンピングの損害賠償責任は、無過失責任になります。故意ではなく過失で結果的にダンピングにより被害を生じさせた場合でも、その責任を負わなければならないわけです。
主要なダンピング事例
ダンピングに当たるかどうか、微妙な事例も多く存在します。場合によっては複数国にまたがるダンピング事例も存在し、時として貿易問題に発展する場合もあります。
日本製ステンレス棒鋼問題
2004年から韓国では日本製ステンレス棒鋼に対して、アンチダンピング関税をかけるようになりました。関税の期間は過去何度か延長されていて、日本も韓国に対して協議を求めています。
実際に完全廃止に向けた交渉も進められているようですが、まだ解決していない問題です。
アメリカのダンピング防止関税問題
日本製の熱延鋼板が廉価でアメリカに輸出されたことをきっかけに、起きた問題です。熱延鋼板の廉価輸出がダンピングに当たるのではないかということで、日本に関税を求める動きが起こりました。
日本は、アメリカがWTOの定めた協定と異なる方法でダンピングを主張していると反論しました。協議の結果、日本の主張が認められ関税を回避できました。
日本の海苔輸入割当制度問題
日本では毎年海苔の輸入数量の上限を決めています。もし海苔を輸入する場合、事前許可が必要です。
韓国は、この日本のやり方がWTO協定に違反しているとの申立てを行いました。一方の日本は、WTO協定の中の例外規定を活用していると反論しましたが、両者は合意に至りませんでした。
ダンピングに関するよくある質問
不当廉売とダンピングの違いは?
「不当廉売」と「ダンピング」は同じ意味です。原価を下回る価格で商品を継続的に販売する行為を指し、国内取引では「不当廉売」、国際取引では「ダンピング」と呼ばれます。どちらも独占禁止法で禁止されています。
不当廉売はなぜダメなの?
一時的に消費者は安く買えますが、長期的には問題があります。資金力のある企業が安売りを続けると、小さな競合他社は撤退せざるを得なくなります。
競争相手がいなくなれば、価格を上げたりサービスを低下させたりできるため、最終的に消費者も不利益を被ります。公正な競争を守るため規制されているのです。
ダンピング(不当廉売)を理解し、公正な取引をしよう
ダンピングとは、商品を不当に安く販売することで公正な市場競争を妨げる行為です。ダンピングは一見すると安く購入できるため、消費者からすれば好ましいことに思えるかもしれません。
ダンピングはグローバル社会の中では、国際問題に発展する恐れもあります。ダンピングに関する正しい知識を身に着け、問題の発生を未然に防止してください。