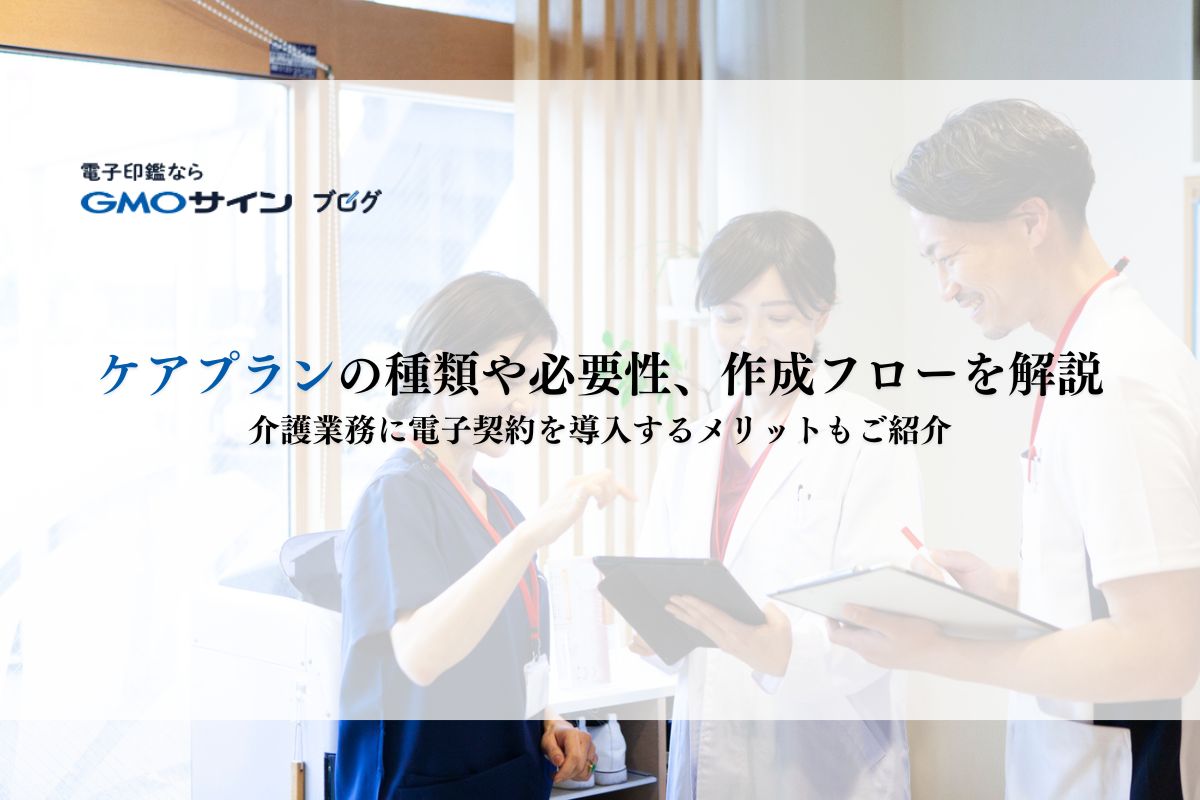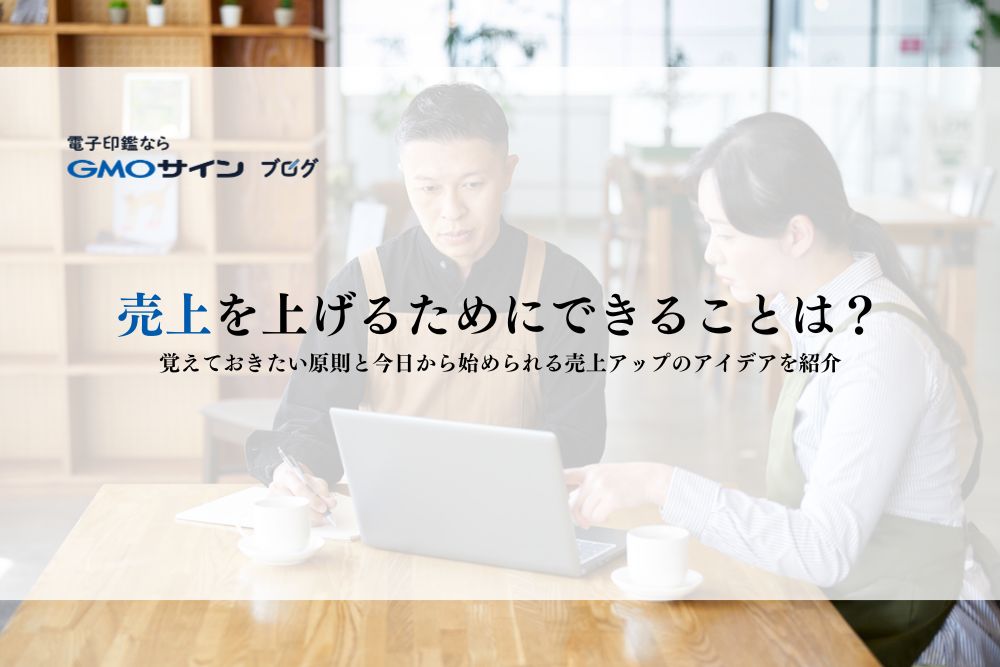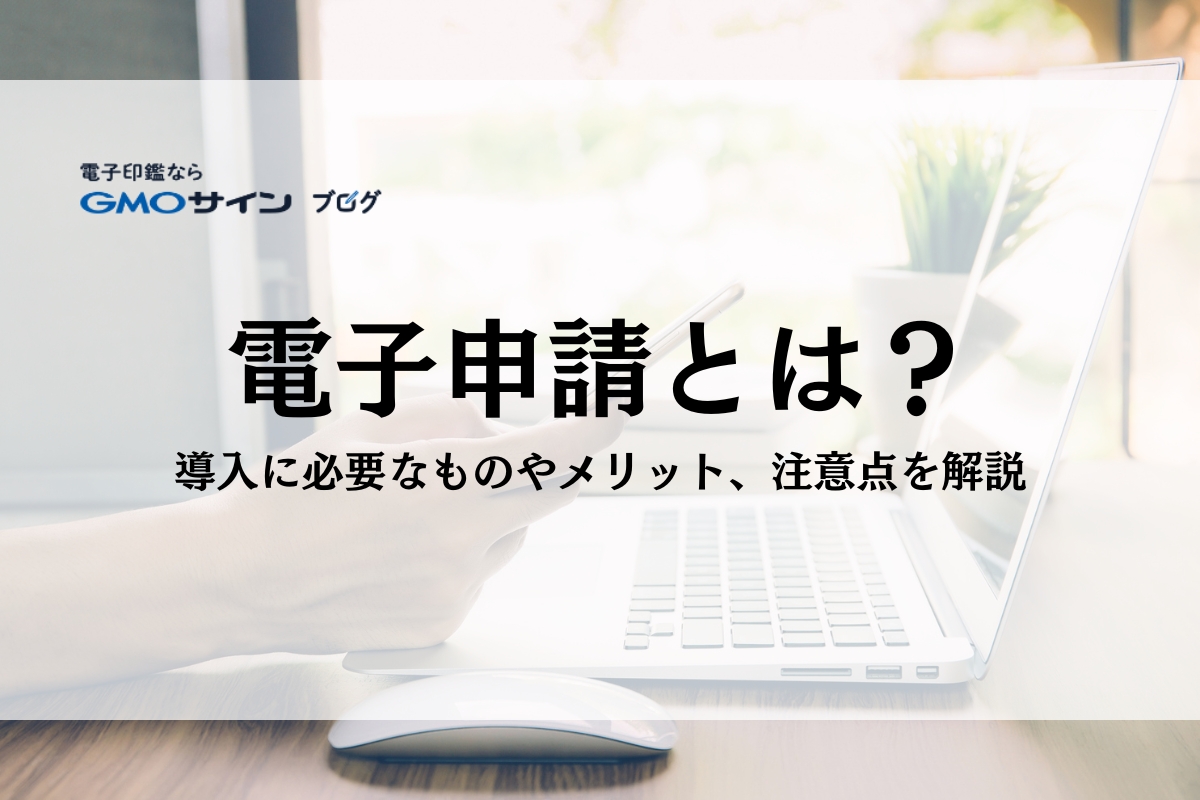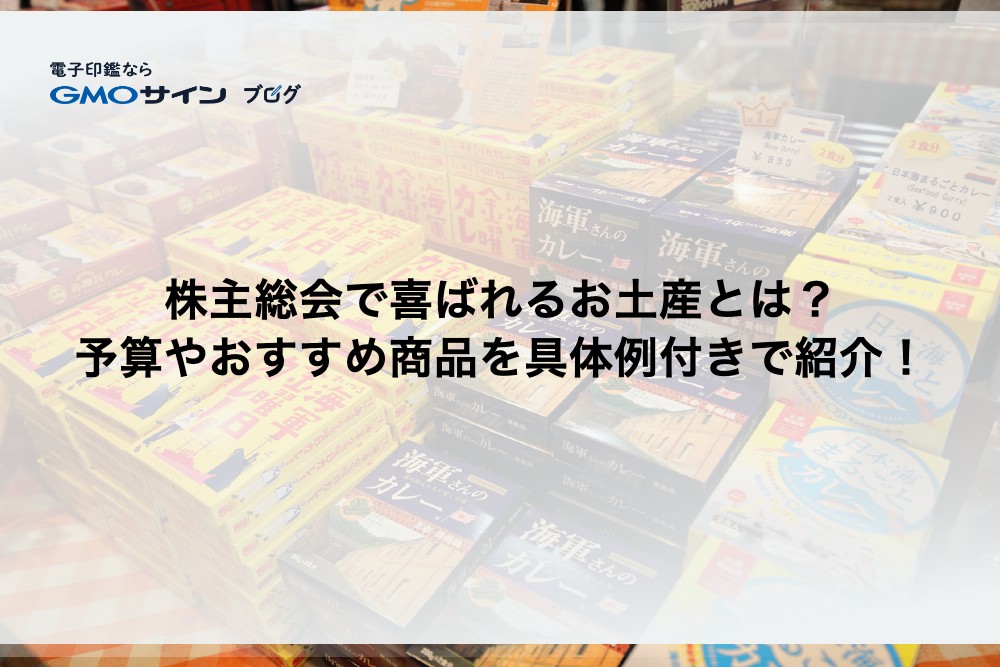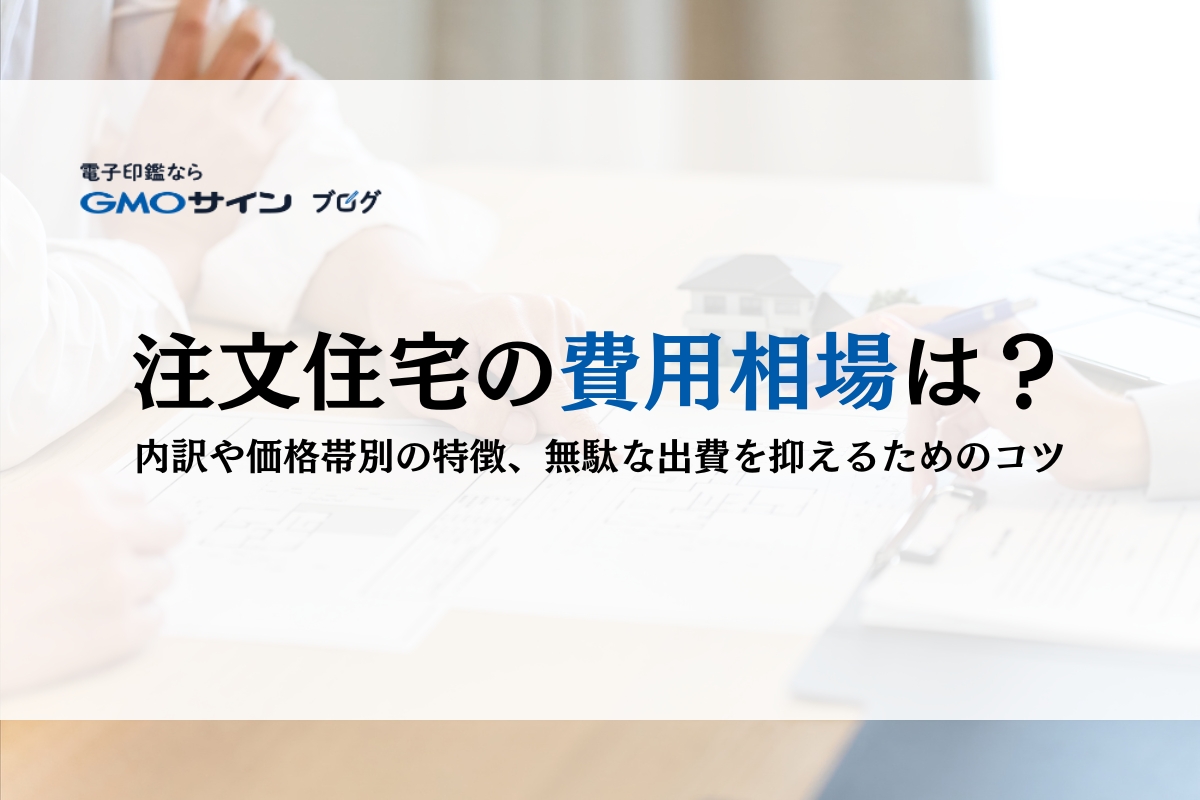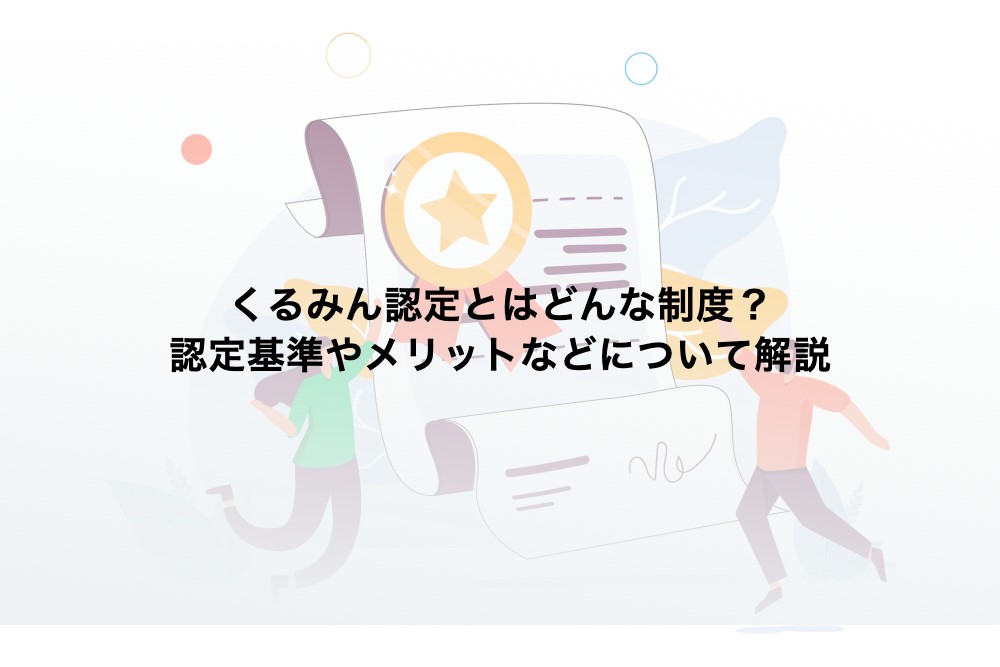下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、企業間取引において力関係の不均衡によって生じる問題を防ぐために制定された法律です。この法律は多くの事業者に関わるものでありながら、詳細を把握していない方も少なくありません。
本記事では下請法の対象となる取引や支払期日に関するルールを中心に、わかりやすく解説していきます。適切な取引関係を構築するための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。
下請け法(下請代金支払遅延等防止法)とは?
資本力が大きな企業が小さな企業に対して、商品およびサービスの発注を行うことは珍しくありません。これを、下請け取引と呼びます。
下請け取引を受注する業者は下請け業者と呼ばれており、中小企業などの法人が該当することもあれば、個人事業主が下請け業者になることもあります。
この下請け取引に関しては、下請法が適用されます。この法律は、下請け業者を守るために制定されているもので、正式には下請代金支払遅延等防止法といった名称です。
下請法の目的
資本力が大きな企業が資本力の小さい企業と取引を行う際には、とかく資本力が大きな企業にとって有利な取引となりやすいものです。
下請法は、こうした下請け業者の利益を守ると同時に、下請け業者が不当な扱いを受けないようにするといった保護の目的も有しています。
下請法ではおもに、取引における運用基準が規定されています。もし自社が下請け業者と取引をしている場合、気づかぬうちに下請法違反となってしまわないよう注意が必要です。
下請法が適用される取引
具体的にどのような取引に下請法が適用されるのでしょうか。実際は、自社よりも資本力が小さな企業へ発注した場合すべてに下請法が適用となるわけではなく、実質的な点も考慮されることになります。
下請法が適用される取引は、大きく4つに分類されています。他社と行っている取引において下請法が適用される場合、発注する側が親事業者、受注する側が下請け業者と位置付けられます。
製造委託
製造委託とは、製造業やメーカーに多い委託取引形態です。多くの場合、発注者が企画や品質、デザインを指定した上で取引先へ発注し、受注する企業はその仕様にあわせて製造して納品するという流れとなっています。
修理委託
製品や商品の全体修理および部分的な修理を別の企業へ委託する取引です。この場合も、下請法が適用される下請け取引に該当します。
情報成果物作成委託
近年増えているのは、この情報成果物作成委託取引です。これには、画像や映像のコンテンツ作成をはじめ、ソフトやアプリの開発委託、その他デザイン系の委託業務が含まれます。
下請けというと継続的に一定量の製品製造を依頼するというイメージを持つ方もいると思いますが、単発的な取引においても下請法は適用されます。
役務提供委託
役務提供委託とは、自社が顧客に対して提供している商品やサービスの提供業務を、他社に再委託するという取引です。この取引も下請けとなるため下請法が適用されます。
下請法適用の基準
続いて、下請法が適用されるかどうかの基準をみてみましょう。基本的には、発注する側と受注する側の資本関係に基づいて決まりますが、例外もありますので、順番に解説します。
下請法の適用は資本金の額で判断される
下請法が適用されるかどうかは、おもに資本金の額により判断されます。
| 親会社の資本金 | 受注する側の資本金 | 下請法の適用 |
|---|---|---|
| 1,000万円超~3億円以下 | 1,000万円以下 | 下請法が適用 |
| 3億円超 | 3億円以下 | 下請法が適用 |
| 1,000万円以下 | 1,000万円以下 | 下請法の適用対象外 |
| 3億円超 | 3億円超 | 下請法の適用対象外 |
ただし、委託業務の内容によっては、上記の資本金の額ではないケースがありますので、注意しましょう。
トンネル会社を作っても下請法は適用される
親事業者の中には、下請法が適用されることを免れるために資本力が小さな子会社を使用し、そこから下請け業者へ発注するという策を講じるケースがあります。
これはトンネル会社と呼ばれるものですが、下請法に関してはトンネル会社規制がかけられているため、規制に触れた場合は仮にトンネル会社を使っても意味はないといえるでしょう。
たとえば、親事業者がトンネル会社の役員の任免や業務執行などで実質的な支配をする場合、親事業者がトンネル会社へ委託した業務の50%以上を下請け業者へ再委託する場合などが挙げられます。
下請法で知っておきたい発注者の義務とは
下請法が適用されると、発注者にいくつかの義務が発生します。
発注した取引内容を書面化することは発注者の義務
どのような取引を発注したのかは、発注者が責任をもって書面化しなければいけません。これは下請法第3条で規定されています。
第三条
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
出典:下請代金支払遅延等防止法|e-Gov法令検索
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
口頭だけでの発注では、後からトラブルになるリスクが少なからずあります。その際、資本力の小さな下請け業者が不利益をかぶることを防ぐために、下請法では発注者にこの書面化義務を課しています。
支払期日は法律で決められている
下請法が適用される取引においては、納品物を受け取った日から60日以内に下請け業者へ代金を支払う必要があります。
下請法が適用されない取引だと、納品物の検査を行った上で支払うため、実際の支払いが60日を過ぎてしまうことも珍しくありません。この場合、支払期日が長くなってしまうと、資本力の小さい下請け業者にとっては資金繰りが難しくなってしまうことが考えられます。
そのため、下請法が適用される取引には60日ルールが設けられていて、納品物を受領した日から数えて60日が経過する前日が支払期日となっています。
ちなみに、役務提供の下請け取引においては、成果物を納品することはありません。この場合、役務を提供した日から数えて60日となります。役務提供が複数の日に渡っている場合は、役務提供の最終日からカウントして60日を迎える前日が支払期日となります。
取引記録を2年間保存することも発注者の義務
下請法第5条は、発注者が書面化された契約書や取引記録を保管することを義務付けています。保管しなければいけない期間は2年間で、紙面による保管でも、デジタル保管でも問題はありません。
(書類等の作成及び保存)
出典:下請代金支払遅延等防止法|e-Gov法令検索
第五条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
取引記録の保管を義務付けることには、発注者による違反行為を抑止するという目的があります。また公正取引委員会からの調査や検査が入った際には、提出の義務が生じます。
支払期日までに支払わなければ延滞利息がかかる
上記のとおり、下請法が適用される取引では、発注者は通常の取引よりも比較的短期間で下請け業者へ代金の支払いを行わなければいけません。
この義務を怠った場合には、延滞利息の支払い義務が発生します。この延滞利息の利率は14.6%と規定されています。
支払期日の正確な数え方
下請法では、製品の納品から60日を迎える前日が支払期日となるというルールがあります。
1日でも過ぎてしまうと延滞利息が発生するため、日数の数え間違いがないように、正確に数え方を把握しておかなければいけません。
納品日・役務提供日が1日目
支払期日を間違えないためには、下請け業者から成果物を納品された日、または役務提供の最終日を1日目として60日のカウントをスタートするのがポイントです。
あくまで日数が基準となりますので、カレンダーを見て2カ月後というわけではないため注意しましょう。
支払いサイトに注意
取引企業への代金支払いの際、支払いサイトに基づいて手続きを進めている企業は多いですが、うっかり支払期日を過ぎてしまう可能性があるため注意が必要です。
たとえば、締め日が毎月10日で、支払日は翌月最終日と設定されていたとしましょう。もし4月11日に下請け業者から成果物の納品を受けた場合、この支払サイトでは締め日は5月10日、支払日は6月末日となります。しかし、これでは下請法で設定されている60日ルールの支払期日を過ぎてしまうことになります。
支払いサイトに沿っていたため問題ないと思っていても、実は60日ルールに違反しているという可能性はあり、その場合は支払期日に遅れた日数に相当する延滞利息が発生します。
下請法で禁止されていること
下請法は、下請け業者の利益を守ることを目的として規定されています。その中には、発注者に対して禁止している事項もあります。
受領拒否
下請け業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒むことはできません。特に発注者の一方的な都合で受領拒否することは認められないこととなります。
代金の支払い遅延
下請法では支払期日について60日ルールが規定されています。意図的であっても、意図的でなくても、期日を過ぎることは禁止されています。
代金の減額や買いたたき
書面化した契約書に記載されている代金よりも安く買いたたく、減額した料金しか支払わないといったことも、下請法は禁止しています。受注者が了承していてもNGです。
返品
返品も基本的には認められていません。やり直しに関しては、契約の内容または社会通念上正当だと認められる範囲においては問題ありませんが、不当なやり直しに関しては下請法違反となります。
報復措置
下請け業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由として、下請け業者に報復的な経済措置を行うことも違法行為となります。
そのほかにも、親事業者が下請け業者に対して利益の提供を不当に要請することも禁止されています。
下請法に関するよくある質問
下請法とは簡単にいうと何?
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、大企業と中小企業の取引において、力関係の格差から生じる不公平な取引を防止する目的で制定された法律です。
具体的には、資本金の区分によって親事業者と下請事業者の関係を定義し、親事業者に対して様々な義務や禁止事項を課しています。製造委託や修理委託、情報成果物の作成委託など、幅広い取引が対象となるのが特徴です。
下請法に違反すると、公正取引委員会からの勧告や社名公表などの措置が取られることもあり、企業の評判に大きな影響を与える可能性があります。
下請法の支払い期日は?
下請法における支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から60日以内と定められています。この期間は業界慣行に関わらず守らなければなりません。
たとえば建設業界で90日サイトが一般的だとしても、下請法上は60日を超えることはできないのです。また、支払期日を定めていない場合は、物品等を受領した日が支払期日となります。
支払遅延が発生すると、親事業者は遅延利息(年率14.6%)を支払わなければならないほか、行政処分の対象となる可能性もあるためご注意ください。
下請法でやってはいけないことは?
下請法では親事業者に対して11の禁止行為が明確に定められています。
| 禁止事項 | 概要 |
|---|---|
| 受領拒否 | 注文した物品等の受領を拒むこと。 |
| 下請代金の支払遅延 | 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。 |
| 下請代金の減額 | あらかじめ定めた下請代金を減額すること。 |
| 返品 | 受け取った物を返品すること。 |
| 買いたたき | 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。 |
| 購入・利用強制 | 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。 |
| 報復措置 | 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。 |
| 有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。 |
| 割引困難な手形の交付 | 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。 |
| 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し | 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。 |
これらの禁止行為は取引の適正化を図るための重要なルールであり、知らなかったでは済まされない内容ばかりです。
下請法は1,000万円以下の取引でも適用される?
下請法の適用は取引金額ではなく、取引当事者の資本金規模によって決まります。つまり、取引金額が1,000万円以下であっても、資本金の規模関係が法律の定める条件を満たしていれば下請法は適用されます。
たとえば、資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者に製造委託する場合、取引金額が数万円であっても下請法の対象となるのです。
法律の適用範囲を正確に理解していないと、知らぬ間に違反行為を行ってしまうリスクがあります。取引開始前に必ず相手企業の資本金を確認し、下請法の適用有無を判断しましょう。
下請取引の4つの義務とは?
下請法は親事業者に対して4つの重要な義務を課しています。
- 発注書面の交付義務
- 支払期日を定める義務
- 取引記録の作成・保存義務
- 遅延利息の支払義務
これらの義務を怠ると、直接的なペナルティだけでなく、取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼします。
下請法のルールを理解して適切な契約を行いましょう
下請法では、親事業者が守るべき様々なルールが定められています。
特に重要なのが支払期日に関する規定で、下請代金は原則として物品等を受領した日から60日以内に定められた支払期日までに支払わなければなりません。また、発注時には発注内容や支払条件などを明記した書面を交付する義務があります。
適切な契約を行うためには、これらの規定を十分に理解し、法令遵守の姿勢で取引に臨むことが大切です。この記事を参考にして、下請法の基本的な知識を持っておいてください。